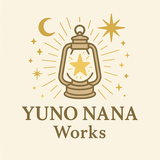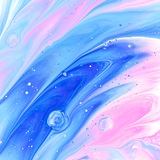ルノワールのレビュー・感想・評価
全210件中、1~20件目を表示
淡々とした日常の光と影を一枚の絵画のように切り取った作品
本作品は、前作「PLAN 75」で第75回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門で高い評価を得た早川千絵監督の長編監督第2作目になります。また本作品も2025年第78回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品されおり注目度が高い作品です。
1980年代後半の夏を舞台に、闘病中の父(リリー・フランキー)と、仕事に追われる母(石田ひかり)と暮らす11歳の少女フキ(鈴木唯)が、大人の世界を覗きながら、人々の心の痛みに触れていく中で、少しずつ大人になっていくひと夏の成長物語。
さて、
観終わった感想は🤫
起承転結のない物語、ごくありふれた誰かの日常をまるで絵日記のように、ごく淡々と静かにみせてもらったという印象です。11歳の少女フキ役の唯ちゃん、なかなかユニークな女の子でしたね。あの頃の子どもはみんなユリ・ゲラーとMr.マリックに夢中でしたからね😎自分の少女時代を見ているかのようなノスタルジーを覚えました。少しばかり無愛想、無感情にみえたのは、監督の演出だったのかしらね🤫しかしこれだけの注目作品に、あの年齢で堂々と主演を演じ切った度胸に拍手👏今後も期待したいですね。
この映画に何か特別なことは何ひとつない。それがいいと思うか、それが物足りないと感じるかで評価も分かれそうではあります🙄
身近な人の死も、大切な人との別れも、思春期ならではの少し危険な好奇心も、程度の違いはあるにせよ子どもから大人になる過程でみんなが体験する少し痛みをともなった記憶です。とくにこの年ごろの子どもにとって身近な人の死は、大きな心理的影響を与えます。人の命は永遠ではないこと、大切な人がある日突然いなくなってしまうこともあること。それを取り巻く大人たちの対応は、時に滑稽で痛ましく、あらゆる感情と対峙しなければならないことを知ります。
それが
「大人になる」ということならば
少女にとって、このひと夏は
少しだけ大人になることを
急かされた夏
ということでしょう🤫
タイトル「ルノワール」
解釈が間違ってなければ、フランスの印象派の画家ですね。
私はおしゃれなタイトルだなと思いましたよ🧐
世界は不思議にあふれている
子どもの無軌道さ、世界の不思議に触れた時の興奮や感動が静かに描かれていて、「子供ってこうだよね」と思った。理路整然としていない主人公の行動はむしろとてもリアル。危険なものも美しいものも、うさんくさん超能力も、初めて経験する時は、等しく世界の不思議だ。断片的なエピソードの積み重ねで一直線に進まない物語が、モザイクガラスのように個々の鑑賞者の思い出を刺激する。
面白いのは、この女の子にとって両親の不和や父親の死さえも初めての体験として、他の経験と等しく受け止められているようなところがある点。
主演の鈴木唯の不思議な存在感はこれから大物になる予感を感じさせた。リリー・フランキーとの父娘の関係に説得力がある。どっちも何を考えているのか、腹の底がわからない不思議な空気が似ている。河合優実は1シーンの出演で、強烈なインパクトを残していた。ルックも音もキレイで素晴らしかった。
幅広い世代に共感と、中高年にはノスタルジーも
本作については当サイトの新作評論枠に寄稿したので、ここでは補足的な事柄をいくつか書いてみたい。
評で紹介したように、早川千絵監督は「ルノワール」を作るうえで影響を受けた映画として、ビクトル・エリセ監督作「ミツバチのささやき」、相米慎二監督作「お引越し」、エドワード・ヤン監督作「ヤンヤン 夏の想い出」の3本を挙げた。プロットを引用したり演出を参考にしたりした、いわゆる元ネタを明かすのは作り手としての誠実さが表れているように思う。
と同時に、2014年の短編「ナイアガラ」がカンヌのシネフォンダシオン部門(次世代の国際的な映画制作者を支援する目的で、各国の映画学校から出品された短編・中編を毎年15~20本選出)に入選、長編初監督作「PLAN 75」がカンヌ「ある視点」部門でカメラドール(新人監督賞)の次点と、すでにカンヌからの覚えめでたい早川監督が国際映画祭の“傾向と対策”をしっかり実践していることを示唆してもいる。「ヤンヤン~」はカンヌで監督賞、「お引越し」もカンヌの「ある視点」部門招待、「ミツバチのささやき」はシカゴやサン・セバスティアンなど複数の国際映画祭で入賞。つまり、「幼い子供が大人の世界を垣間見て、少し成長する」筋の映画は、世界の映画人から愛され、評価されやすい傾向があると言える。そうした過去作の引用を散りばめることは、それら名作のシーンを思い出す点でノスタルジーを補強する効果も見込める。
もちろん1980年代を知る日本の観客なら、当時の出来事や流行を単純に懐かしく感じると同時に、その後に起こるバブル崩壊、オウム真理教が起こした一連の事件、1995年の阪神淡路大震災などを連想して、複雑な思いを募らせるかもしれない。ただしそうした時代背景を知らずとも、誰しも通ってきた幼い頃を思い出させてくれる普遍的な情感に満ちており、共感を呼ぶポイントがいくつもあるはず。
評の最後では鈴木唯について、「願わくばその野生馬のようにしなやかな個性と魅力を保ちつつ、女優として大成することを心から期待する」と書いた。早川監督にもぜひ、鈴木唯の成長の折にふれ、たとえば5年後とか、10年後とかにまたタッグを組んでほしい。フキのその後を描く続編の企画なら最高と個人的には夢想するが、まったく別のキャラクターで作るとしてもそれはそれで可能性が広がって面白い映画が期待できそうだ。
少女と大人の間
ストーリーがあるようでない、箇条書きのような映画。
小学五年生のふきは、超能力やオカルト的な呪い、伝言ダイヤルなど少し危険なものへの興味が強すぎる不思議な女の子。
ふきは同世代の子供と遊ぶよりも大人の世界に興味がありそう。
そんなフキの周りには汚れてしまった大人が沢山。
一番印象に残っているのは、末期癌の父親が家で襖を開けると妻の用意した喪服が堂々とかかっているのを見てしまった時。
そっとフキが襖を閉めるのに父を思う優しさを感じた。
会場でもその場面では「フッ」と笑いが漏れていた。
大人の世界って嫌だな…。
奥深い映画だったので、もう一度くらい見てみたい。
我家にも同じ絵(印刷)が飾ってありました。
映画.COMの高評判を経て、鑑賞しました。
宣伝スチルの「船上で踊るフキ」もいい感じ!
予備知識なしに観ました。
青春ものを想像していましたが、冒頭から驚き連続の"昔アルアル映画"
しかし映画を観終わったあと、この映画は何であったのか?
「少女 イレーヌ(ルノワール作)」には、深い意味があるのか? と数々の疑問が生まれ、思考が停止し。。。レビューが描けずに放置
誠に遺憾で、今まで、映画の2度観はした事がなかったのですが。。。
本作の配信を待って、2度目の鑑賞を数日前に行いました。
僕の年代では、誠に珍しい名前の"ふき"ですから、両親の"変わりもの度"を連想するのですが、
映画の中では、それに反して、4を目の前にした 活力のない父親 と、打算的でリアリティのある おばさん浮気母
そしてひとりっ子のふき
団塊の世代と団地住まいを連想する構図だが、住んでいるのは岐阜県の住宅地
"フキ"は、僕・弟の世代では、珍しい名前
雨の橋の上から、どうなったのか?
この映画は、生と死の間に揺れ動く"中2病の小学5年生"の不思議ちゃんを絵にしただけの
「映画賞狙いのワザとい映画」としか,僕には解釈できなかった。
この映画を2度も観たら、「怪物(2023年)」を観たくなりました。
ある種の問題をはらみながら、当時の時代を映した現在にも通じる秀作!
(完全ネタバレですので必ず鑑賞後にお読み下さい!)
結論から言うと、今作の映画『ルノワール』を大変面白く観て、秀作だと思われました。
今作の時代は1980年代後半であって、映画を観るにつれてその時代性は明らかになって行きます。
そして今作の特徴は、1980年代後半の時代背景もあり、エロスと死をオカルトで繋ぐ構成になっていたと思われます。
映画の中盤で、11歳の主人公・沖田フキ(鈴木唯さん)が知り合った、北久理子(河合優実さん)の夫が、幼児性愛にも通じるビデオ編集テープを持っていて、それを北久理子が追求したすぐ後に、鍵がかかったアパートの自宅へ、ベランダから入ろうとして誤って転落死したというエピソードが語られます。
また、映画の終盤では、伝言ダイヤルで知り合った明らかに少女性愛者と伝わる大学生・濱野薫(坂東龍汰さん)に危うい目に遭いかけます。
この、主人公・沖田フキが知り合った北久理子の夫が幼児性愛に通じるビデオテープを持っていてその後に転落死するエピソードも、主人公・沖田フキが伝言ダイアルで知り合った少女性愛者に危うい目に遭うシーンも、相当リスキーなエロス描写に思われながら、エロスと死にまつわる話がここで語られていたと思われます。
そして、このリスキーなエロス描写は、一方で、少女や女性が、男性からの病的で危険な性被害に常に晒されているとの、率直でリアルな表現だったとも言えます。
主人公・沖田フキの父・沖田圭司(リリー・フランキーさん)は、末期ガンで死に直面しています。
しかし主人公・沖田フキの母・沖田詩子(石田ひかりさん)は、夫の沖田圭司に対して殺伐とした対応しかしていません。
極めつけが、母・沖田詩子が、夫の死のために用意して掛けられていた喪服を、父・沖田圭司が見つけてしまう場面です。
ここでも終始、死にまつわる(ドライな)描写が続いています。
そして、これらのエロスと死を、オカルトで今作は繋いでいたと思われるのです。
夫の幼児性愛にも通じるビデオ編集テープを責め立て、夫を転落死で失った北久理子に対しても、主人公・沖田フキはオカルト儀式的な催眠術をしたりしています。
また主人公・沖田フキは、末期ガンで入院している父・沖田圭司の病床で、エスパーカード当てを楽しんでいました。
今作の映画『ルノワール』は、リスキーなエロス描写もありながら、死に対するドライな眼差しがあったと思われます。
だからこそ、心は満たされず、深淵に落ちる心情を、オカルト的な空気が救っていたとも思われるのです。
この1980年代後半の後に現実の日本では、バブルが崩壊し、オカルトブームはその後、オウム真理教によるサリンテロ事件によって事実上の終焉を迎えたと思われます。
その意味で今作は、その後の未来を暗示させる、不穏な(リスキーなエロス描写など)問題ある、しかしエロスと死をリアルに描いた秀作になっていたと、僭越思われました。
しかし一方で、現在でも心は満たされず、深淵に落ちる人々の心情は溢れていて、リスキーなエロスや、捨て置かれるドライな死に関する問題は、そこかしこに噴出しています。
そのリスキーなエロスとドライな死の、間を繋ぎ救う、当時のオカルトに変わる現在への解答が示された、(今作の早川千絵 監督・脚本の映画『PLAN 75』のように)現在の物語として描かれた作品であれば、傑作になったのに、との無い物ねだりも鑑賞後に個人的にはありました。
しかしながら、(こちらは両親の離婚という別の内容ですが)傑作・相米信二監督の映画『お引越し』とのオマージュも感じさせながら、問題内容もまとった秀作として、個人的にも面白く深く今作を鑑賞しました。
嫌いな映画でした。監督の少女時代のスケッチ⁉️
不快なスケッチ&ぶつ切りの断片→それをまとめるラストの人生讃歌⁉️で、誤魔化す。
冒頭から不快な映画だった。
♥︎
11歳の沖田フキちゃんが何者かに殺された。
そして葬式のシーンが描かれる。
しかし、これは沖田フキの夢を、本人が作文で発表しているのだ。
不謹慎で不快な映画でした。
続いて、お父さん(リリー・フランキー)が嘔吐するシーン。
お父さんは癌の末期です。
この映画は、映画の終わりでお父さんが亡くなって
そうして何事も無かったように終わるのです。
◆
フキは特に父親の死に怯える感情も持たない。
「死」はむしろ好奇心の対象です。
私が11歳の頃、「死」は今の何百倍も怖いものでした。
私の勝手な解釈ですが、早川千絵監督は、「PLAN 75」でも分かるように、
かなり人間的に特殊な歪んだ性格を持つけれど、一方では
社会的に適応力が高く、仕事の出来る才能のある方なのでしょう。
◆
このフキちゃんの役が、スラリとした美少女で利発な鈴木唯ちゃんという
フィルターを通すから、ちょっとエキセントリックだけど、
魅力的な少女として周囲は受け入れてしまいます。
◆
時代設定は1986年頃。フキは11歳。
超能力に好奇心を持ち、透視してトランプの札を見ようとしたり、
友達に催眠術を掛けようとしたり、子供らしい好奇心旺盛である・・・
その友達に原爆で焼けて死んだドキュメンタリーフィルムを見せて
失神させたりする。
◆
ボーダーラインの子供です。
優秀で知能は高いけれど発達障害があるようです。
「こちらあみ子」のあみ子より、カムフラージュする能力に
長けているから目立たないのです。
♥︎
お父さんの生きるための民間療法への100万円。
お母さんは、「どうせ死ぬのに・・・」と言い放つし、
外泊した部屋にはお母さんの喪服が広げられていたりするのです。
似たもの母・娘です。
◆
1980年代バブル時代。
ニュースや服装や食べ物なども細かく再現されて、
時代背景はたしかに
美しい風景やモチーフで誤魔化されたけれど、
後半を観ないで前半のサキの言動だけ見てれば、
あみ子よりずっとヤバくて可愛げのない優しさのない子供。
私は「あみ子」はすごい好きでしたし不憫でした。
この映画は美しい少女の主役(鈴木唯ちゃん)が可愛くて利発だから、
人生からハブられないけれど、相当にヤバくて不謹慎で醜悪な面を
最後で辻褄合わせをしたとしか思えません。
多分、早川千絵監督は、子供の頃、かなり特殊で歪な少女だったのではないだろうか?
昭和の終わり頃の風物は懐かしいし、
ロケ地の岐阜県は緑も多い田園地帯で、撮影はとても美しい。
◆
この不快感が、強い印象として刻まれないのも不思議だけど、
◆
ラストの歌の歌詞を聞くと、内容は「人間賛歌」
内容と整合性があまりにとれずに、かけ離れていて、
正直言って恥ずかしくなりました。
◆
なにかとても私には受け入れがたくて
ラストのヨットに乗って幸せそうなフキの映像とか唐突で、
フキが成長して、普通の心を持ったのなら、
少しは言葉で説明する必要があるだろうと思いました。
◆
極端に言葉で説明しないのが大きな欠点でした。
11歳の少女の瞳に映る哲学
行き詰まる大人たちと、知恵にあふれた少女の物語ーー今後に大期待の監督誕生!
早川千絵監督の2作目となる最新作だ。公開から少し遅れて名画座での鑑賞となった。
75歳以上の国民に死を推奨する、というSF的な設定の前作「PLAN 75」は国際映画祭で高く評価されたそうだ。僕は未見だ。前作もできれば映画館で必ず観るつもりである。
最初の感想は「すごい映画作家が誕生した!」ということである。これから、続けて次の作品をとって欲しいと切望している。
原作ではなく監督自身によるオリジナル脚本とのことだから、早川監督の作家性が全面的に反映された作品なのだろう。
ネットで読める監督インタビューによると「今回は出来るだけ意味づけや説明から離れたところから映画を作ってみたいと思っていた」とのこと。本作の死の床にある父親という設定も、ご自身の体験でもあるとのことでもあるし、また80年代という設定も現在49歳の早川監督の少女時代である。
自身の体験を元に、自分でも言語化できないそこにあったものを、探求しながら描く純文学的な作品なのだと思う。
すぐにパッと手に取れる、わかりやすいメッセージがあるわけではなく感想も書きにくいのだけれど、じわじわと心の奥底を動かされる力のある映画だった。個人的な感想として、何がこの映画のパワーになっているのかを考えてみたい。
「うれしい、 楽しい、 寂しい、 怖い そして“哀しい”を知り、 少女は大人になる」ーーこれが、公式サイトでの本作の紹介である。「不完全な子供」から「より完成された大人」への〝成長物語〟という意味だと思う。
しかし、本作を見ていると、むしろ11歳の少女フキの方が、より統合されていて、大人達の方が、欠損を抱えて生きていることが見えてくる感じがした。
本作の大人たちは、この社会に適応し、自分の役割をこなして生活していくだけで精一杯である。役割に過剰適応して、自分を見失っている感じだ。
石田ひかり演じる母は、昇進したばかりのワーキングマザーだ。8男女雇用機会均等法以前に入社した世代だろう。当時は、総合職で就職する女性は相当少なかった。また結婚・出産後に働き続けるというのはさらに少なかった。
働き続けるだけでも大変なのに、彼女は昇進している。相当な努力が必要だったはずだ。フキが11歳になって子育て負担が軽くなってようやく実現した昇進で、遅れた昇進だという焦りもあったかもしれない。せっかく仕事に集中できると思ったら、夫が病気になってしまった。
彼女は〝優秀な社員〟という役割に相当な労力を払い、その人格が強くなっている。だから〝パートナー〟として夫への愛情や友情、〝母〟としてのフキへの愛情や家庭生活は、空虚になってしまっている。
〝優秀な社員〟である誇りが、部下への厳しい指導になって、受け入れられない降格につながってしまい、また、1人の女性として自己実現できていない感覚が、優しいだけの凡庸な男との不倫につながってしまう。
ギリギリ80年代の89年入社の僕の経験では、当時はこうした管理職女性は本当に少なかった。会社もまだ家族的で、鷹揚で面倒見のいい兄貴的な上司が多かった。むしろ雇用機会均等法組が、中間管理職になり始めた90年代後半以降に増えてきたタイプとして描かれているように感じた。成果主義や株式重視の経営が広がった時期で、現場に厳しく成果を求めるカルチャーが一気に広がった時代だった。
ただ、この映画のように、厳しい指導が問題とされるようになったのは、本当に最近、2010年以降ではないだろうか。80年代後半という設定だが、そこから現在に続く、働く女性の普遍的な課題を象徴させた人物なのだと思う。
リリー・フランキー演じる父も、母と同じく、会社人格に乗っ取られているようだった。彼は末期ガンであることをうまく受け入れられないようだ。だから、死の恐怖に対しても、調査して対策を考えるという〝業務上のトラブル〟のような対処をする。さらに空き時間には、ベッドで会社の書類を読み込んだりしている。死を受け入れられたら、妻やフキとの愛情を深めたり、川沿いの散歩で平凡だけど美しい自然に目を向けられたかもしれない。
そして、主人公のフキ。
11歳だから、彼女はまだ未熟である。世間的な知恵は、これから学んでいかねばならない。しかし、この映画の大人たちが、これまで学んできた〝世間的な人生への対処〟のせいで、かえって行き詰まっているのに比較して、フキの対処は知恵ある賢者のように見えた。
一見、フキは父の死を受け止めきれていないようにも見える。悲しいという感情も、自分では気づいておらず、英語教室のお姉さん教師が泣くから「ああ、こういう時は悲しいと思って泣くんだ」と教えられたような感じである。
しかし、身近な人が死ぬから悲しいというのは、世間的な型通りの対処でもある。親の死は悲劇で、それは悲しく辛いことーーこうして感情を、言葉と思考で整理することもできる。しかし、言葉にして整理することで、抜け落ちるものもたくさんある。フキは全身で全てを受け止めているようだ。
フキの対処は怪しくも思えるスピリチュアル的な方法だ。
父ではなく自分の死を夢で見て、それを作文にする。
占いか呪術のようなことをしたり、テレパシーで言葉にせず伝えることを試みる。
遠くのベランダでたたずむ女性の危うさを直感し、家に上がり込んで催眠術もどきで抑圧を解除してしまう。
川の堤防で夕陽を眺める場面は、宇宙の知恵と交信しているようでもある。
フキがやっていることは、偉大な心理学者ユングが個性化といった大きな知恵との接続を試みる方法(夢分析、曼荼羅、自由連想法)のようでもある。この映画の中でただ1人、落ち着いた成熟した対処ができているように見えたのは、世間的な役割や「こうするべき」という世間的な知恵に縛られていないからこそ、できることなのかもしれないとも感じさせられた。ベランダの女性も、そして父と母も、フキの知恵によって、かなり救われたのではないだろうか。
ただ一つの失敗は、伝言ダイヤルで信頼できる大人を探そうとしたことだった。大人なんか頼りにせず、自分の感覚を信じて進めば大丈夫ーーそう応援したくなった。
しかし、彼女も世間的な知恵を身につけた大人に、一度はならないといけないのが辛いところだ。そうした人生の課題をこなした後に、もう一度、11歳のときの感覚を思い出してほしい。
早川監督自身が、一度、就職や家庭生活や子育てといった世間的課題をこなしてから、再び知恵ある子供の世界を探求している、そんな映画なのかもしれないと思う。
色々な見方をして考えさせられる映画だ。この映画の前では、僕の見方も、個人的な一つの感想に過ぎないと思う。
エンターテイメントとしての映画では、登場人物の明確なキャラクター設定と動機が必要とされるけれど、揺れ動くし、自分で自分がわからないのがまた人間というものだ。
早川千絵さんは、人間のわからなさや、言葉にすると抜け落ちてしまう〝人の全体性みたいなもの〟を描くことができる稀有な映画作家だと、本作を見て感じた。
早川監督は、会社勤務を経て、大学で学び、子育てもされて、映画監督としては遅いスタートをされた方のようだ。これからたくさん作品を作って欲しいし、50代を人生の収穫の時代として謳歌してほしいと思った。
今後を応援したい注目の映画監督。日本を代表する映画作家として、さらに大きく飛躍することを期待している。
謎のペド演出
11歳の少女フキ(鈴木唯)が経験した一夏の思い出を描いた本作は、監督早川千絵自身の自伝的作品なのだろうか。単なる断片的なエピソードの羅列と受け取られても致し方ない繋がりのなさが特徴だ。一見少女の支離滅裂な妄想をツギハギしたような本作だが、冒頭からタイトルクレジットまでのシークエンスが夏休み後の出来事だとしたら辻褄が合う。何せ、主人公のフキ自らが“(これで)おしまい”と言っているのだから、ほぼそれで間違いないだろう。
つまり、自宅介護中のリリー父さんが血を吐いてぶっ倒れるシーンが最初で、後に石田ひかり母さんが担任に呼び出されたのは別の作文が原因だろう。文才はあるもののフキは普段から“死”に関するヤバい作文ばかり書いていたのではないだろうか。なぜかって?父さんの死をどうやって受け入れれば良いのか、11歳の少女が予め自分なりに心の準備をしていたように思えるからだ。
あの超能力ごっこもその一つで。あの世に旅立った父さんの霊と“離れたところでも”テレパシーで交信できるように鍛錬を繰り返していたのではないか。仕事と介護で忙しくコミュニケーションが途絶えがちだった母さんと通じ合いたいと願う気持ちもあったのだろう。フキが自転車の助手席で母の背中に触れようとして手を引っ込めるシーンや、移動列車のラストシーンにフキの気持ちがよく反映されているに思える。
本作ではまた“眠り”が重要な意味を持っている。河合優実がフキのなんちゃって催眠術で真実を吐露し精神的に楽になったように、ペドフィリア未遂事件や父親との死別というショッキングな出来事を乗り越えるために、少女は“眠り”につくのである。永遠の“眠り”についた父親に会うために“眠り”を貪る少女。寝る子は(精神的に)育つのである。
問題は、少女のビルディングスロマンには相応しくないペドフィリアに本作があえて触れている点である。幼児性愛者と思われる河合優実の事故死した旦那と伝言ダイヤルで知り合った大学生は、冒頭紹介される作文のおそらく元ネタだ。当然父さんが家からいなくなった寂しさをして、少女にあんなヤバい行動をとらせたに違いないのだろうが、別に無くてもいいだろうというのが正直な感想だ。泣いている赤ん坊の動画や栄養失調で腹が膨らんだ子供の写真と、抗がん剤の影響で腹が膨れ上がった父親そして親の愛情不足に哀しむフキの境遇を重ねた(わかりにくい)演出で誤魔化していたが...
さらにピンと来ないのが、映画タイトルの『ルノワール』である。オーギュスト・ルノワール作“イレーヌ”を背景に、フキが家で飼っていた🦜を籠から出してあげるシーンがある。籠の中で大切に育てられたであろう貴族娘イレーヌとフキをダブらせて少女の精神的自立を描いた、ということなのだろうか。個人的には、評論家荻野洋一が本作の評論で語っていた、オーギュストの次男で映画監督のジャンにまつわる“触ってはいけない神経過敏な箇所”に関係しているような気がしてならないのである。
本作の時代設定であるバブル時代、ルノワールの贋作が良く出回ったことに早川監督がインタヴュー内で触れてはいたが、『PLAN75』で老人の自殺幇助というタブーをテーマにした早川監督だけに、本作でも知っている人は知っている“映画業界のタブー”に切り込もうとしていたのではあるまいか。ガンに罹患している事実を自ら探り出したリリー父さんのように。確信犯かと問われると、もう完全にル・ノワール(黒)なのである。
もしかしたら本作は、バブル時代にピークを迎えた西洋文化への盲目的信仰からの“お引越し”を日本人に促そうとした壮大な映画だったのかもしれない。
子役の鈴木唯の演技は見事だが、カンヌ映画祭を意識しすぎた感じが強い
配信(dmmtv)で視聴。
早川千絵監督作品はPLAN75以来だが、今回、子供の視点で描くとは思わなかった。しかし、この作品で何を伝えたいかははっきり伝わったし、子役の鈴木唯の演技は見事だった。ただ、気になったのはあまりにもカンヌを意識しすぎてまず日本の観客に評価してもらうことを考えていたのかどうかは疑問に感じた。PLAN75は見事だっただけにちょっと残念。石田ひかりや河合優実らが目立たなくなるぐらい鈴木唯の演技は見事で、これから期待。
そして少女は大人になっていく。
嫌いじゃないんだけど
ふわっとした作品は嫌いではないので観に行ってみたいなと思いふらっと拝見。
淡々としているのにどこかずっと不穏で、個人的には不安な時間が長くてしんどかった。
共感できる、あの年代ならではの残酷さと無鉄砲さ……なんだけど、いつか痛い目を見てしまうかもしれない、どうか立ち直れないほど悲しいことが起こりませんようにとずっと祈っていた。
人のものを勝手に触ったり、引き出しを開けたり、話を聞かなかったり、そんな電話しちゃダメだよとか、そんな形で知り合った人に会っちゃダメだよとか、そんな時間にひとりで外出ないで、なんて……心配性が発動しまくり。
平成一桁ガチクソババァ(ネットミーム)なので、色々と信じられなかった。
見た当初は、うん、悪くなかったと思ったはずなのに、見てから2ヶ月経ってレビューを書こうと思ったらそんなことしか浮かびませんでした。
でも、ゆるやかに成長はしていて、色んな人の色んな境遇や気持ちを実際に見て、知って、この子はどんどん大人になるんだろうなと、そういう救いで終わった気がして、絶望の話というわけではなかったかな。
わたしの修行が足りてないだけなんでしょうね(笑)
ひたすら暗い
相米慎二の『お引越し』みたいな映画かな?と思って見始めたら、ずっと宮台真司的な世界が描かれていて辛かった。子供の目線で大人の世界を描く映画はいくつもあるが、子供の無邪気さやその眼差しを通したありのままの世界のキラキラした様子と、大人の社会の苦悩や現実の対比が描かれているのが面白いところだけれど、これは子供のふりをした大人の眼差しといった様子で90年代のバブル崩壊後的な社会の歪みと陰が永遠と描かれている(設定的には80年代後半だが)
出てくる大人も基本的には皆んな嫌なやつで、主人公のフキもいい奴かと言うと微妙だし友達もほぼ出てこない。家でひとりぼっちで伝言ダイヤルに電話したりしている。これはきっと狙い通りで冒頭から自分のお葬式の空想から始まる所から、家庭の不安定さから離人症的になっていると推察される。
何処かで子供目線のユーモラスさなどを期待したが、ほぼそんな様子はなく本当にずっと暗い。基本的にフキが大人に出会い、その人たちの暗闇を見つめる構造になっているので会話のシーンばかりで映像に動きが無いのもシンドイ。舞台も田舎という訳ではなく、地方都市ぐらいの感じなので会話するシーンも狭く奥行きがない所がほとんどで画的にも面白くない。
唯一動きがあって面白い映像だと思ったシーンが伝言ダイヤルでロリコンぽい大学生に会いに行くシーンで狙ってやってるとしたら観客に何を思わせたいのか、感じさせたいのか甚だ疑問だった。
なので120分以上の上映時間も比較的苦痛で、いつ面白くなるのか、いつ終わるのかということばかりが頭にチラついてわざわざ劇場に観に来たことを後悔した。
角度によって別人のような
不確かなものを信じ、頼りにして生きる人たち
この映画ではさまざまなことを考えさせられました。そのうち「不確かなものを信じ、頼りにして生きる人たち」について、書いてみたいと思います。
超常現象、テレパシー、催眠術、祈り、手相占い、イミテーション、欺瞞などの不確かなものを信じる人たち。科学的に根拠が乏しいもの、まやかし、偽物、嘘、偽りなどをを信じ、あるいは、それを頼りに生きている人たち。その人たちにも、やがて、たしかな現実が現れます。その現実は、不確かなものを信じる人たちにとっては、必ずしも優しい現実ではなく、時として、厳しい現実となることもあります。それでも、人はその不確かなものを信じ、頼りにして生きています。
伝言ダイヤルで知り合った自称大学生、浮気相手の優しい表情と言葉、浮気の贖罪としての手相占い、家柄の良さそうな親友の家庭、健康食品、がんに効くという神の手道場、そして、バブルという時代背景そのもの。これらが、不確かなものとして挙げることができると思います。こういった不確かなものを頼りにして、人々は生きています。しかし、その後に現れる現実は、厳しいものであり、その現実には失望させられます。
この映画のタイトルである『ルノワール』についても、映画では不確かなものとして描かれていると思います。
映画では、主人公のフキはルノワールの『イレーヌ嬢』という肖像画に興味を示します。美少女『イレーヌ嬢』に、フキは少女としての理想像を見出したのかもしれません。ですが、フキが見た『イレーヌ嬢』は、芸術性がないレプリカ、不確かなイミテーション。
フキは、そのレプリカの絵画を父親に買ってもらいます。フキは、父親の生前はその絵画を病室に飾り、父親の死後は勉強机の横に飾ります。病室の『イレーヌ嬢』は、父親の回復を願うフキのささやかな思いの象徴のようです。勉強机の横に飾られた『イレーヌ嬢』は、フキにとって、亡くなった父親との絆と思い出を示す、シンボリックなものに感じます。言い換えれば、絵画はイミテーションであっても、フキにとっては、大切な父の闘病の証であり、父の愛情が詰まった大切な思い出の品ではないかと思います。
映画では、不確かなものを信じ、それを頼りにする人たちを、中立的に描いています。不確かなものを信じる人たちを、批判的ではなく、嘲笑的でもなく、憐憫的でもなく、「人はそういう不確かなものを信じながら、生きていくものです」と淡々と描いています。そして、このような描き方ができる早川監督に、「人間の尊さや人の営みの尊さ」と謙虚に向き合う姿勢を感じ取ることができると思います。
全210件中、1~20件目を表示