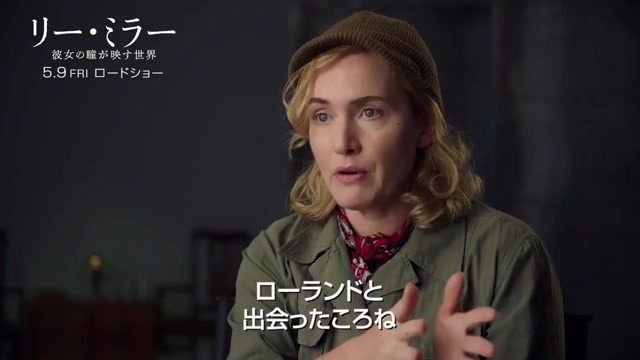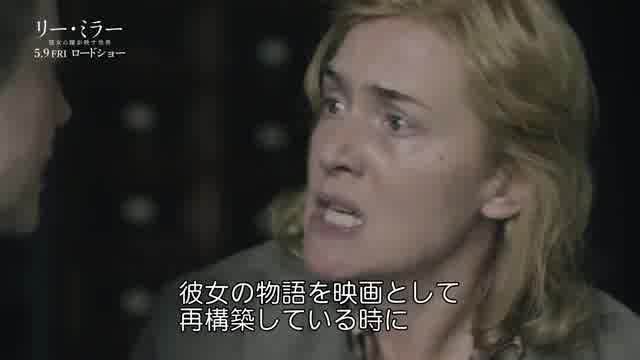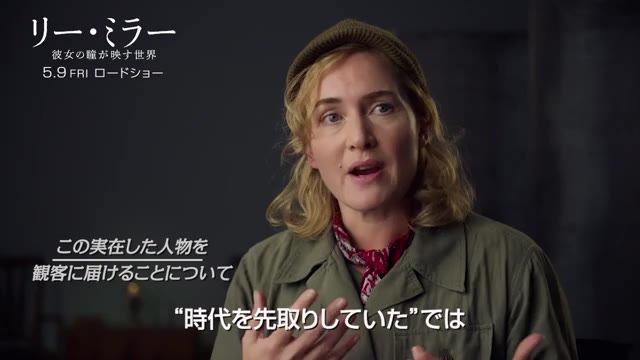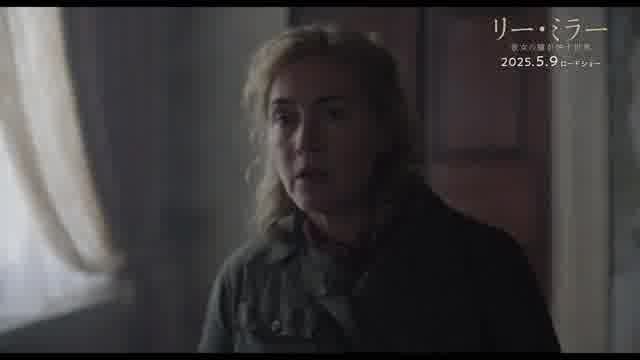リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界のレビュー・感想・評価
全126件中、41~60件目を表示
第二次大戦中に前線の写真を続けた、米国人女性写真家の記録。 有名な...
第二次大戦中に前線の写真を続けた、米国人女性写真家の記録。
有名なのは、ヒトラー邸宅の自殺現場や浴室の写真でしょうか。
戦地に女性が赴くことは、とても制限されていたとか。
英国だと絶対厳禁。
米国人だと、そういう"伝統"がなく、許可が出たと。
すさまじい機動力。向こう見ずが過ぎる。
そして記録力。真摯で強靭。
雑誌VOGUEの当時の内容にも驚きます。
掲載された写真、不採用の写真、さまざまですが。
映画内で紹介された写真の数々は、
とても表現できない、言葉を選ぼうにも難儀する、惨たらしい数々…
映画館なので遺体の腐乱臭を感じずに済むことが、せめてもの救いでした。
とても辛口な、諸々の映像が記憶にとどまってしまう映像体験でした。
最前線の写真が、英国では掲載されず、本人が口外もせず。
数十年も経てから、ご本人の没後に、息子さんが自宅の屋根裏で見つけたというのがまた驚きです。
語り継ぐべき時代に抗い信念を貫き通した女性の姿
20世紀初頭にVOGUE誌などでモデルをしていたリー・ミラーが第二次世界大戦中に初の女性従軍記者として欧州戦線の最前線に出向き、戦場カメラマンとして人々の姿を写し出した実話に基づく物語。
当時のイギリスでは、まだまだ女性蔑視が激しく、「銃後の守り」の役割しか与えられなかった。また、勇ましい兵士の姿は報道しても、負傷兵やナチスドイツに粛清された多くの人々(ユダヤ人に限らず、自由主義者や共産主義者、同性愛者など、お上の意にそぐわない者たちも含む)の姿、そして戦闘状態が終わった場所で繰り返される戦勝国兵士による女性たちへの乱暴などの姿は報じられない。「大本営発表」はどこかの国だけの話ではなかったことがよく分かる。
戦場での体験で心に深く傷を負ったリーは自分の仕事を封印し、子どもにすら話すことをしなかった。まだPTSDなどという言葉がなかった時代に、時代に抗い、信念を貫き通した女性の姿はきちんと後世に伝えていかなくてはならないであろう。
自分たちに都合の悪い歴史の事実を捻じ曲げ、なかったことにしようとする権力者が散見されるような時代にこそ、このような作品から大切なことを学び取るべきである。
ケイト・ウィンスレットが美しい
リー・ミラーをネットで検索し、モデル時代、芸術家からミューズと称えらた時代、戦時中の軍服姿、そしてヒトラーの浴室などの写真を見た。どれもとにかく美しい。
そして、ケイト・ウィンスレットはこの映画を作ることを熱望し制作総指揮をし主演もした。戦時中30代前半だったリー・ミラーを40代後半になるケイトが演ずるのはややふくよかな体型からして無理があるとの向きもあるが、私は全く気にならない。リーの70歳をメイクで演じたビジュアルを含め、美しい人はちょと体型が崩れようが、老いたとしても美しいのである。
「撮られるよりも、撮る方が好き」と言っていたリーは、戦火が激しくなった頃から従軍カメラマンとなりノルマンディー上陸作戦のフランスへ行った。解放されたパリだったが、占領下にドイツ人に協力した女性は髪を丸刈りにされ迫害されたり、いい気になった米兵は弱い女性を食い物にしようしていた。更に「行方不明になった人々が何万人もいる」と知ったリーは、帰ってこいよと訪ねてきたローランド(リーを理解した実に良い夫である)を振り切り、盟友となった「LIFE」のカメラマンのシャーマンと共にドイツ国境を越える。ダッハウ強制収容所では恐ろし光景が目に飛び込んできたがそれを撮り続けたし、過酷な環境で生き残った少女に優しい目線を送った。写真で告発しようと「VOGUE」に送ったが掲載されることはなかった、。
フランスにおけるホロコーストの犠牲者は8万3千人だったようだ。
欧州各国地域で行われたホロコーストはユダヤ人だけで600万人もの人々を殺害した。
リー・ミラーの死後、息子のアントニーが家の中を探したら屋根裏からミラーが戦場で撮った4万枚もの写真が出てきた。母の物語を後世に伝えようと著者を出した。そのアンソニーは「タイタニック」を見た時「ケイト・ウィンスレットならきっと素晴らしいリー・ミラーを演じるだろう」と思ったとのことである。
そして、それは長い時を経て実現した。素晴らしい映画になったと思います、。
全ての思いを込めたワン・ショット
ファッション・モデルからカメラマンに転身し、第二次世界大戦開戦後はカメラを持ってヨーロッパ戦線に向かった女性カメラマン、リー・ミラーの半生を辿る物語です。
あの戦時下に銃弾をかいくぐっていた女性カメラマンが居たなんて全く知りませんでした。そして、独軍敗戦直後のヒトラー宅のバスタブでこっそりとこんな自画像を撮っていたなんて。女性を軽んじる報道界への苛立ち・目の前の戦争への絶望・撮影への渇望、そして恐らくかなり強かったであろう売れる写真への意識、全てがこの1枚に凝縮されています。(添付の写真は実物画像)
恐らくエネルギーに溢れ、友達付き合いするにはかなり疲れる人物だったのでしょうが、それをケイト・ウィンスレットが本人が憑依したかの様な熱演でした。近年の彼女は、自身が出演する作品の社会性を明確に意識している様に思えますが、本作はその狙いが観る者の目玉を射抜く強さでした。
快楽主義の冒険家
様々な肩書を持つ彼女の一つである従軍記者という肩書。従軍記者と聞くと何を思い浮かべるだろうか。普通は戦争の悲惨さを伝える崇高な使命感を持った仕事と思いうかべるだろう。
確かに彼女にはそういう意識もあったのだろうが、それ以前に彼女はこの仕事を彼女の複数の仕事の一つとしてストイックに取り組んでいただけのように思える。従軍記者には崇高な使命感や特別な理由が必ずしもなくてはならないわけではない。たまたま彼女が生きた時代に大戦が勃発した。彼女にとって戦争は被写体の一つだった。戦場へ向かうのは彼女の人生における冒険の一つだった。
シュルレアリストの彼女は戦争を被写体にして自分の写真を撮り続けた。彼女が言うように写真はその一枚で一万文字の意味が込められるほどのもの。彼女は常に写真に様々な意味を込めて撮影した。それはシュルレアリストの彼女の作品作りに他ならなかった。
彼女は冒険家でもあった。けしてとびぬけて裕福な家庭に生まれたわけではない彼女はこの時代の女性が自分の欲望をかなえるには男性の財力に頼らねばならないことを知っており、富豪のエジプト人男性と結婚して彼の財力を利用し多くの冒険旅行を楽しんだ。
時には砂漠や遺跡を求めて冒険の限りを尽くし、また時には再びパリの社交界へ戻り有閑マダムのような暮らしを満喫し、そこで人脈を広げてはまたその人脈を頼りに冒険を繰り返す日々を送った。彼女の手にはいつも複数の紹介状がありそれは未知の土地では常に役に立った。彼女は世界中のどこにでも行ける翼を手に入れたのだ。それは彼女が人をひきつけてやまないほど魅力を持ち合わせていたからに他ならない。そんな中で起きた戦争。彼女にとって戦争も冒険の一つだった。
パリが解放されても彼女はいまだナチスの残党が戦闘を続ける場所を求めて戦場を渡り歩いた。それは砂漠や遺跡を求めての冒険旅行と変わらなかった。
戦争に対して冒険などと書くと不謹慎な印象を抱くかもしれないが、冒険の意味を人生の苦難を乗り越えて自己を磨き高める行動だと解釈すれば妥当とも思える。
彼女はその人生において常に冒険を求めた。自分がその時その時に興味を抱き、自分の好きなことをすることを何よりも大切にした。自分の思いのままに生きることを何よりも優先した。
彼女は快楽主義者である。自分の欲望のままに男性との逢瀬にふけった。彼女には貞操観念などなかった。でもふしだらとは違う。やはり彼女にとっては自分に正直に生きることが何よりも最優先されたのだ。妻の身でありながらフランスへ向かう船では愛人と楽しみパリで恋人のローランドとも逢瀬を重ねた。そんな彼女を富豪の夫はただ優しく見守り続けた。
彼女を快楽主義者にならしめた根源はその幼少期にさかのぼる。本作でも言及された性被害だ。彼女を不憫に思った両親は彼女を溺愛し思う存分甘やかして育てた。家庭では彼女の望みがかなわないことはなかった。しかし学校ではそうはいかず彼女はたちまち問題児となった。
頭を悩ませた両親は恩師とのパリ行きを許可せざるを得なかった。自由奔放な彼女にとってパリでの暮らしは水を得た魚のような暮らし。時はロストジェネレーションの時代、名だたる芸術家が活躍し、人々が享楽に明け暮れた自由な時代だった。
そこですでにファッションモデルとして活躍していた彼女はたちまち社交界の華となり、ジャン・コクトーやピカソなどの芸術家と交流を重ねた。コクトーはリーに彼の映画出演をオファーしたし、ピカソは彼女の自画像を描いた。映画冒頭のムジャンでのバカンスではピカソも訪れていてそこで描かれた肖像画をローランドが買い取りリーにプレゼントしたのだという。
そしてマン・レイも彼女に魅了された人間の一人だ。彼のモデル兼弟子となった彼女はたちまちその才能を開花させ彼とその評価を二分した。マンはリーが撮影した写真に自分の名を冠することを許すほど才能を認めていた。そしてリーの奔放すぎる性生活に嫉妬して彼女との心中を思わせるほどリーはマンを苦しめた。
カメラマンとして才能を開花させたリーはニューヨークで弟と共に写真スタジオを開設、世界恐慌の荒波にも負けず彼女はその人脈もありスタジオは軌道に乗る。その矢先に彼女はエジプトの富豪と結婚して弟は婚約者がいるにもかかわらず無職となりその後かなり苦境に立たされることとなる。
これらエピソードを並べるだけでも彼女の奔放さ、自分の好きなように生きるという姿勢はまさに快楽主義者にふさわしいと思える。
ファッションモデル、カメラマン、シュルレアリスト、従軍記者、料理研究家、旅行家、様々な肩書を持つ彼女を一言で言い表すのならやはり快楽主義の冒険家という言葉が最もふさわしいと思える。
本作は彼女の従軍記者時代のみを切り抜いてそこだけに焦点を絞っており、よくある従軍記者の物語に彼女の物語を矮小化してしまった。彼女の従軍記者としての行動原理も彼女の性被害の事実と絡めて、従軍記者としての原動力がさもそこにあるかのように描き観客を安易に納得させようとした。
確かに二時間の商業映画で彼女の人生を網羅的に描くことは困難だが、しかしそのように彼女の人生を分かったように描くのは彼女が一番我慢ならないのではないだろうか。
彼女は自分の写真には一万字もの意味が込められているという。そんな彼女の写真が雑誌に掲載される際には解説文が添えられた。その解説文に時として彼女は憤慨したという。自分の写真を理解せず貧相な想像力で解説した気になっているとして。
シュルレアリストの彼女の写真が高く評価されたのはその写真が表面的ではなく多くの意味が込められていると解釈できるからだ。彼女の作品の持つ多面的な魅力はまさにシュルレアリストの彼女のなせる芸術作品だったからに他ならない。その彼女の作品を理解できてない解説文に彼女は常に憤った。
それと同様に自分を分かったように描いた本作を彼女が見てどう思うのだろうか。少なくとも彼女はその幼少期の体験で他者を虐げることへの憤りからそれを従軍記者としての原動力にしたという観客が求めたものに対する安易な答えを押し付けるこの本作には憤ったのではないだろうか。
ただ本作は息子との語り合いという形で描かれた点は映画として高く評価されると思う。現実にはあり得なかった母と息子との心の交流を描いた点においては。
リー・ミラー、その自由奔放な生きざま。けして女性にとって自由に生きられない時代で自分の思う限りの自由を謳歌した彼女を演じたのがケイト・ウィンスレット。奇しくも彼女をスターダムに押し上げたタイタニックで演じたローズは沈没事故の後、亡き恋人ジャックのぶんまで人生を謳歌した。かの作品最後で彼女の枕元には様々な冒険の日々を体験した彼女の人生を思わせる写真が並べられていた。それはまさにリー・ミラーの人生を彷彿とさせるものだった。
ファッション誌の記者を戦場に?
丁寧につくられた上品な伝記映画でした。
期待していたドラマチック展開はなく、淡々としてたので、個人的には史実の一場面の空気を学ぶ感じにならざるを。
1番の違和感はヴォーグの記者が戦場にいることかも。
さすが欧米はファッション誌であろうとジャーナリズムなのか⁉️ と
…日本も戦争になったら文春記者が戦場に赴くのだろうか
ともあれ、映画としては息子だったりも分かりにくく過去のトラウマがジャーナリズムに傾倒したロジックも???
ただ女優魂は眩しく素晴らしかったです
彼女の瞳に映っていたもの
作品自体はやや平板だが、制作・主演のケイト•ウィンスレットの熱意を強く実感
ヴォーグ誌に戦争被害者や収容所の写真が載らなかった時、リーは激しく怒ります。「これは現実に起こっていることなのよ」
80年前の遠い出来事だけの話ではありません。今も戦争は起こり、多くの人々が犠牲になっています。不安になるから、可哀想だからと目を逸らしがちですが、ガザやウクライナの惨状は「現実に起こっていること」なのです。リーの言葉で目が覚めた思いです。
ケイト・ウィンスレットが自ら制作し並々ならぬ熱意で作り上げた、その心意気がとてもよく伝わってきます。
彼女は子供時代肥満体型でいじめにあい、「タ
イタニック」のヒット以降も度々体型批判を受けてきました。今回リー・ミラーを演じるにあたり「リーはありのままの自分で生きていました。私も自分自身の見た目を隠すのはもうやめたんです」とコメントしています。反ルッキズムを意図して実践し、彼女ぐらいのスターになれば、多少のリアリティを犠牲にしてもそれがやれてしまうのです。
まさに、アル中気味で後にいい母親にはなれなかったけれど、従軍を強行し弱き者たちに目を向け続けたリーに通じる部分ではないでしょうか。
そんな彼女たちに敬意を表したいと私は思います。
蛇足ですが、ヴォーグ誌のアシスタント役のカミラ・アイコが少し気になります。今回はごく小さな役でしたが、次回広瀬すず主演の「遠い山なみの光」(カズオ・イシグロ原作)に出演するようで、個人的には注目していきたいです。
彼女が見てきたものを再現するなら、ラストのネタバレはない方が良かったかも
2025.5.15 字幕 イオンシネマ京都桂川
2023年のイギリス映画(116分、G)
原作はアントニー・ペンローズの伝記『The Lives of Lee Miller』
実在の写真家、リー・ミラーの半生を描いた伝記映画
監督はエレン・クラス
脚本はリズ・ハンナ&マリオン・ヒューム&ジョン・コリー
物語の舞台は、1977年のイギリス、ファーリー・ファーム
モデル、写真家としての生涯を送ってきたリー・ミラー(ケイト・ウィンスレット)は、ある若いジャーナリスト(ジョシュ・オコナー)の取材を受けていた
ジャーナリストは彼女が撮った写真を見ながら、そこに込められた「物語」に傾聴していく
舞台は変わり、1938年のフランス・ムージャン
リーは友人たちと共に避暑地を訪れ、ジプシーのような生活を送っていた
モデル仲間のヌーシュ(ノエミ・メルラン)とその夫ポール(ヴァンサン・コロンプ)、編集者のソランジュ(マリオン・コティヤール)とその夫ジャン(パトリック・ミル)たちと過ごしていたリーだったが、そこにイギリス人の芸術家ローランド(アレクサンダー・スカルスガルド)が招かれてやってきた
リーは「どうしてこれまで出会わなかったのかしら?」と言い、ローランドの人となりを推理し始める
友人たちは「また、始まった」と言い、「今度は僕の番だ」とローランドもリーの人柄を語り始めた
その後、第二次世界大戦が本格化し、リーはローランドと共にロンドンに逃げることになった
パリは陥落し、ロンドンにも空爆が起こるようになり、そこでリーは爆破された街の写真(家の防空壕)を撮り始める
そして、現地にアメリカから派遣されていた従軍写真家のデイヴィッド・シャーマン(アンディ・サムバーグ)と出会い、行動を共にすることになった
イギリス政府は女性を戦地に派遣することを認めていなかったが、アメリカ人のリーは母国で申請をし、ようやくノルマンディーに行けるようになる
だが、最前線は想像以上に酷いもので、リーはそこで補給機のパイロットをしているアン・ダグラス(Harriet Leitch)と出会い、彼女を写真に収めた
映画は、1945年のドイツ・ベルリンにて「ヒトラーの家のバスタブで写真を撮る」というところまでを描き、ダッハウ、ブーヘンヴァルトの二つの収容所の現実を写真に収めていく様子が描かれていく
構成としては、ジャーナリストがリーの回想録を聞くというテイストだが、実際には「リーの死後に遺品を見つけた息子の想像」というものになっていた
リーは息子に戦争写真家であったことを死ぬまで隠していて、息子は第一子が生まれた際に「自分の幼少期の写真」を探すことになった
その際に母親が何をしていたかを知り、それを後世に残すための活動を始めている
原作にあたる伝記小説、ロケ地として使われたファーリー・ハウスなどがその活動の一環であり、それによって、第二次世界大戦の知られざる物語というものが世に出るようになったと言われている
映画は、女性が見た戦争という視点で語られ、戦争の影に隠れて蔑ろにされた女性の悲哀を切り取っていく
それと同時に、女性が踏み込めなかった世界を切り開いていく様子が描かれ、その集大成がバスタブの写真であると言える
この写真を撮る時にヒトラーの家で多くのアメリカ兵などがヒトラーが好んだウイスキーなどを飲んではしゃいでいたが、それらの道徳的とは言えない行為のさらに上をいくのがリーの写真であると思う
これまではどうして撮ったのかは謎だとされていたが、彼女の物語を女性目線で再構築すると、あのような理由になるのだろう
収容所での汚れをあの場所で洗い流すことに意味はあるし、騒いでいるアメリカ兵の倫理観を超えた、というところに彼女らしさというものが凝縮されているのかな、と感じた
いずれにせよ、女性が戦地に入ることで救われる女性もいれば、そこで尽くしている女性たちの励みにもなるので必要だと思う
イギリスとアメリカで扱いが違うところは国柄だが、彼女がアメリカ人でなければ成し得なかったというのは事実だろう
その後、戦争をどう裁くかという部分でもイギリスとアメリカの姿勢は違うし、アメリカでもダメなもの(ナパーム弾使用)はダメだったりする
そう言ったものが時代を超えて蘇ったのが戦後30年後であり、そこから多くの人が戦争がどんなものだったのかを知ることになった
そう言った効果を前面に押し出すというのも方向性の一つだと思うが、映画は「実は息子だった」というものをミステリーにしているので、それがうまくハマっているのかは何とも言えない感じがした
キャスティングの妙なのか、息子はどっちかというとデイヴィ寄りに見えるので、そのあたりに意図があったのかはわからない
それは重要なことではないと思うのだが、見えない痛みを描く映画ということを考えれば、見えないものを映している部分もあるのかな、と感じた
彼女らの行動があって、今、我々は事実を認識できている。
ドキュメンタリー作品として観るほうがしっくり行くかもしれない。報道写真家・リーミラーの半生を描いているが、点描的な流れで構成されているため、時系列に沿って淡々と綴られていく。
女性でありながら従軍記者になってまで戦線に赴き、その悲惨な実態を写真に収めていく彼女。その動機の根底にあるのが、幼少時代の不幸な出来事であることが終盤示唆されるものの、ホロコーストに纏わるの凄惨すぎる写真や、ヒトラーの浴室での半裸の自撮りなど、今ひとつその行動原理は読み取れずでした。
ただ恣意的な脚色を行わず、リーミラーが撮影した写真を元に純粋に構成されており、非常に真摯で良心的な作品と感じられました。どういう動機が彼女にあったにせよ、報道写真の存在があることで、我々は何が起きたのかを知ることができていることを至く実感した次第。
しかしなんだ。冒頭の上半身裸で屋外ランチしている文化はマジでわからんわ。
あれが実話とは…
戦争を体験していない私にとっては、簡単にあーだこーだ言える立場ではないが、命の危険もありながら悲惨な現場の写真を撮り続けるってのはよっぽどの使命感がないと出来ないことだと思う。その使命感は、撮れば撮るほど、戦地で亡くなった方々の無念を後世に残したいと思うのだろう。そんな写真が掲載されなかった時の怒りと悲しみは相当であっただろう。
と同時に、苦しんでいる人々を助けるより、ひたすら写真を撮るというのはどんな気持ちだったのだろうか… とも思う。私なら出来ない。
映画の構成はリーがインタビューされている程で始まるが、実は息子が遺品を見ながら彼女の過去を想像し、母親に対する蟠りと向き合うというものだった。素晴らしい。その終わりに感動し、リーの残した写真も戦争の悲惨さにも更に深みを持たせる効果があったと思う。
素晴らしい女優さん。バッと大胆な脱ぎっぷりもリーの性格を上手く表現出来ていると感心した。ちょっと、なんだろ、この役柄としてふくよか過ぎるのがイマイチだったので3.5。
女性初の戦場カメラマン
制圧者との闘いと女性としての闘いと。ズシリと重い良作。 リーの生き...
ついに映画化
リー・ミラーについての映画化はいつか現実になってほしいと、随分と前から思っていた。
映画化が決まって喜んだが、日本での公開は2025年と少し遅れたが鑑賞して良かった。
リー・ミラーを参考にした現代版の戦場カメラマンが出た『シビル・ウォー』も日本での公開が遅れた。
今作『LEE』は素晴らしい完成度ではないだろうか。でも正直もう少し長く見たかった。
もう一度映画館で観たいくらいだ。
しかし、今日観た後は暗い気持ちでの帰路となった。ダッハウ強制収容所の残虐行為が生々しく描かれていたせいもある。彼女の人生を考えながら帰った。
「傷にはいろいろある。見える傷だけじゃない。」ケイト・ウィンスレットが主演・製作を務め、モデルから20世紀を代表する報道写真家へと転身した実在の女性の数奇な人生の一部を映画化した作品。そう、一部だけ。
リー・ミラー(Elizabeth Miller:1907年4月23日アメリカ生まれ 〜 1977年7月21日)
今回映画で描かれるリーとパートナーのデイヴィッド・シャーマンは、ダッハウ強制収容所の残虐行為を目撃した最初の従軍記者で、彼らは1945年4月30日に到着し、ミラーは飢えた囚人たちの恐怖とSS警備員の死体を記録。
ローランドとの息子アントニーが、リー・ミラーが1977年に亡くなってからずっと後に、イースト・サセックスの自宅の屋根裏で6万枚のネガとプリントを偶然見つけたて発表し、再び世界が彼女の作品に注目する事となる。
連合国はすごいな
リー・ミラー、知らなかったな。
奔放というか退廃的なというかな生活を送ってるよね。
オープニングで上半身裸でピクニック風なのをやってるのは《草上の昼食》オマージュなのかな。
この辺みてるとね、インテリ層みたいな奴らがふざけたことをやれるのが社会の余裕だとは思うけど、あんまりにもふざけてると反インテリ主義に走るのも分かるなと思った。
この人たちはレジスタンスになったりで、芯は強いんだけど、そこがなかなか見えないもんね。
リー・ミラーは当たり前だけど写真うまいね。
モデルをやってたから、その辺で美しさに対する感覚が磨かれたのかなと思ったんだけど、Wikipediaみたらマン・レイの弟子で愛人だったんだね。「マン・レイは駄目よ」みたいな台詞もあったけど、そういう理由なのか。
それで従軍記者になって、色んな写真を撮ってくよね。
それを載せるのが VOGUE だっていうのがすごい。単なるファッション誌じゃないんだ。
戦場でも女性に読まれてて「あなたたちの仕事は世界を教えてくれる」って言われて、泣いちゃうね、こんなこと言われたら。
だんだんとナチスの行ないを撮るようになって、エグいね。
ヒトラー宅の浴槽で写真撮って、これで有名になったのかな。
すごいなとも思うけど、あんまり意味はないよね。
パリが解放されて、みんな手放しで喜んでるんだけど「そんな簡単な話じゃねえだろ」とリー・ミラーは怒ってるのがいい。
イギリス版VOGUEに写真が掲載されないと乗り込んでフィルムを切り裂くのいいね。そりゃ、そうだよ。
編集長で友人のオードリー・ウィザーズが「私も努力しているの」というと「そうね。でも十分じゃない」と飽くまでも怒る。
エンドロールでみんなのその後がでたときオードリー・ウィザーズはイギリス版VOGUEに写真掲載しなかったことを死ぬまで後悔したと出てて、なんか、すごいね。
観ててずっと思ったんだけど、そりゃ日本、戦争に負けるよね。
連合国側は従軍記者に女性を入れて、そりゃ命がけだけど、その人たちがなんとか戦場で生活できるだけの備えがある。
旗色が悪くなってからの日本軍にそれができたかというと、無理だよね。その辺も含めて、彼我の差は大きいなと思いました。
ラストはインタビュアーが実は息子で、遺品を前に独り問い掛けていたっていうギミックで終わるけど、これはまあ、なくても大丈夫だね。
全126件中、41~60件目を表示