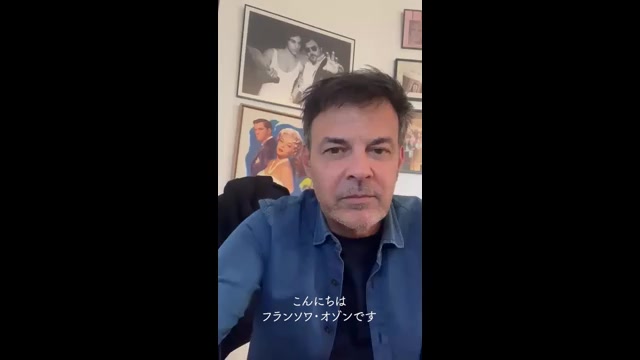秋が来るときのレビュー・感想・評価
全27件中、21~27件目を表示
チラシや予告からは想像できない
家族、友人、職業、嘘、罪、幽霊、様々なテーマがなんとも切なく連鎖する。
なかなか観たことがない感覚。
ブルゴーニュの秋の山の色が目に焼き付く。
遠くの親族より、身近な他人
ベルリン、カンヌの常連、フランソワ・オゾンです。余裕があります。力みも無駄な贅肉もありません。物語は小ぶりです。日常からの些細な脱線が、サスペンスとは呼べないほどの緊張を生み出しますが、最後は穏やかに静かに幕を閉じます。
母親を憎む娘と孫。過去を共有する親友。母親の友人を慕う男。娘婿。パリ市警の警部。登場人物は、それだけです。舞台となるのはオセール郊外の田舎町とパリ。ですが、ほとんどは田舎町で物語は展開して行きます。
ひなびた田舎町の風景。虚飾の無い街並み。小ぶりな物語。少ない登場人物。独居老人の日常。交錯することの無い時系列。と言う構成で、映画そのものが堅く引き締まった感じがするところが、とにかく好き。
愛する者と平穏な生活を守るために吐いた嘘。
母親を喪った孫息子も、同じ判断をする。
物語の核心にあるイベントは、シンプルです。
この緊張感を際立たせるための、一見だらだらした描写の連続は、オゾンらしい技巧を感じずにはおれませんでした。
やっぱりフランス映画が好きみたいですw
良かった。
結構。
静かなお話しでありながら見応えあります
かなり素晴らしい映画でした。
静かなお話しでありながら、最初から最後まで見応えがあります。
それぞれが各々に止むを得ない大きなものを抱え、それをもて余しながら生きていく。
色々と考えさせられました。
主役のエレーヌ・バンサンの演技は、流石に秀逸。
脇を固める俳優も良かったです。
フランス語の映画は耳に心地好く、朝に観る映画に相応しい。
良かれと思うことが大事
主人公の老婦人の過去が、物語の大きな鍵となるに違いないと思って観ていたら、中盤で、それがあっさりと明かされてしまい、少し拍子抜けしてしまった。しかも、それは、「墓場まで持っていく」といった類の秘密ではなく、村人の誰もが知っているような公然の秘密なのである。
この秘密によって、それまでの娘の態度にも合点がいくのだが、幼い娘を養うための苦渋の選択だったのに、そのことで娘に毛嫌いされるようになってしまった主人公の身の上には同情せざるを得なかった。
その一方で、主人公の過去を知った孫の男の子が、初めは嫌悪感を示したものの、事情をしっかりと理解して、主人公を許容するところでは、思わず「なんて良い子なんだ」と感激してしまった。
主人公の娘が、自宅のベランダから転落死してからは、主人公の親友の息子が彼女を殺したのではないかという疑念が高まってくる。
この息子が、親友が「子育てを失敗した」と言っている割にはイイ奴で、主人公の家の庭を丁寧に掃除したり、孫の男の子をいじめる上級生を懲らしめたり、主人公の娘に母親を嫌うなと言いに行ったりと、非の打ち所がないような活躍ぶりで、一体どんな罪状で服役していたのだろうかと不思議になる。
サスペンスとしての緊張感は、女性警察官が、彼のアリバイ等について、主人公と孫の男の子を尋問する場面で最高潮に達するのだが、2人の回答が「優しい嘘」であったことには納得できるし、ホッとさせられた。
何よりも、「良かれと思ってしたことが裏目に出る」と言う主人公に、「良かれと思うことが大事なのよ」と応える主人公の親友の一言が思い起こされて、胸が熱くなってしまった。
淡々と進んできた物語だっただけに、最後の最後に、何か「衝撃的な事実」でも明らかになるのだろうかと期待したのだが、そうした展開がないままで終わってしまったところには、物足りなさを感じざるを得ない。
その一方で、最後まで娘との和解を願っていた主人公が、たとえ脳内現象であったとしても、それを果たせたということは、ハッピーエンドであったに違いないと思えて、少し幸せな気持ちになることができた。
人生の終盤において、自分の幸せを選び取ること
さまざまなことを考えた映画でしたが、一晩寝ると、身体の中に染み込んで消えていくような感覚がありました。
主人公ミシェルの秘密が守られ、人生が穏やかに閉じられたせいかもしれません。
今作は、親子や近しい間柄での葛藤や理解、そして人間の多面性を描いたものだと思いました。
真実はわからないし、それぞれに言えないこともあるわけですが、登場人物ひとりひとりが矛盾や後悔を抱えながら生きている姿には、ブルゴーニュの豊かな実りに例えられるような、人の営みのたくましさを感じました。
誰もが多様な面を持ち合わせていること、ひとりの中でもさまざまに気持ちが揺れ動く様子など、繊細に丁寧に描かれていて素敵でした。
この映画は、真実とは何か? 正しさとは何か?と深く追求しませんし(警察でさえ!)、答えも提示しません。
真実がすべてを解決するわけではなく、むしろ真実は大切な誰かを傷つたり、自分自身の豊かな生活を損なう可能性もあるのだ、と表しています。
これは、人生の終盤においても「自分の幸せは自分で収穫するのだ」という能動的なメッセージなのではないでしょうか。
私の心に残ったのは、死んだはずのヴァレリーが幻のように母ミシェルの前に現れる場面。
生前、二人の間で語られた言葉よりも、語られなかった感情…愛、赦し、理解の断片のようなものが、浮き上がってくるのを感じました。
これを和解と受け取れるかどうかはもう少し考えを深めたいところですが、少なくともヴァレリーの中では娘との対話がなされ、穏やかな結末を迎えました。これは幸せなことだと思うのです。
死者との和解というのは私にとっても非常に興味のあることで、そのヒントが得られたような気がしました。
登場人物すべての人生をすくい上げる優しさに満ちていて、悲しみ、後悔、言葉にならなかった感情も、否定されることなくありのままに表現された、素晴らしい作品だったと思います。
激しすぎる親子の物語
舞台はフランスの田舎町、ブルゴーニュ地方。主人公は一人暮らしの高齢女性・ミシェル(エレーヌ・バンサン)。そしてチラシに映る美しい紅葉の中を歩く二人の高齢女性の姿から、のんびりとした人間ドラマを想像していたのですが、実際はまったく異なる内容でした。
物語の具体的な展開は驚くほどハードでした。ミシェルは娘・ヴァレリー(リュディビーヌ・サニエ)から蛇蝎のごとく嫌われており、そのヴァレリーは、服役を終えた親友の息子・ヴァンサン(ピエール・ロタン)ともみ合いになり、転落死してしまいます。さらに、ヴァンサンの母であり、ミシェルの無二の親友であるマリー=クロード(ジョジアーヌ・バラスコ)は末期がんで亡くなり、ミシェルがかつて売春婦だった過去も明かされます。そのことで、ミシェルの孫・ルカ(ガーラン・エルロス)は学校でいじめを受け、それをヴァンサンが助けるなど、次々に衝撃的な出来事が巻き起こり、ヒリヒリし通しでした。テンポも非常に早く、観る者を一瞬たりとも飽きさせません。さらにはヴァレリーの死をめぐるミステリー的な要素も加わり、全方位的に見応えのある、予想を裏切る作品でした。
しかし、冷静に物語を振り返ってみると、この作品の本質は「親子関係」にあるのだと感じます。ミシェルとヴァレリー、ヴァレリーとルカ、マリー=クロードとヴァンサン、さらには娘の死を追う女性刑事とその出産――それぞれの親子のあり方が描かれています。親子関係という人類普遍のテーマがあるからこそ、最後まで興味を惹かれ続けたのだと思います。
それぞれの親子関係には深い問題があり、観ているうちに、自分自身の親との関係にも重ねずにはいられませんでした。特に、ヴァレリーが母・ミシェルに向ける激しい憎悪には、客観的には嫌悪感を抱いたものの、ふと「自分も同じような感情を抱いていたのではないか」と気づかされ、大いに反省させられました。
いずれにしても、事前の予想を全く覆される内容でしたが、表層的なストーリーも面白い上に、底流にある親子関係の描写も興味深い作品であり、非常に印象的でした。
そんな訳で、本作の評価は★4.4とします。
分かりあえたなら。
パリ生活を終え自然に囲まれた田舎のブルゴーニュで暮らす80歳ミシェルの話。
パリ時代からの友人マリー・クロードと森の中でキノコ取りを楽しみ、そのキノコを持ち帰り調理と、…1本の電話から休暇で遊びに来た娘ヴァレリーと孫のルカだったが振る舞ったキノコ料理を食べた娘ヴァレリーがキノコ毒に当たり緊急搬送されることに。
自分から電話して遊びに来た娘ヴァレリー、自ら来といて母ミシェルへの態度はなぜ?があり。振る舞った食事を機にさらに拗れた母と娘の関係性、…の間に入った出所したばかりのマリー・クロードの息子ヴァンサンの優しさ、またその優しさで何か裏目な展開になりながらも。
「立派なキノコね」とカリっいやっキノコを取るシーンは少し下描写が一瞬よぎりながらも(恐らく私だけ)、ヴァンサンのイケメンさ、ルカの美少年にはT2時代のエドワード・ファーロングを思い出させで!ラストの展開ミシェルは何か急だしちょっと残念な終わりだったかな。
小川、川に掛かる橋を歩くシーンが違う場所で2回あったけど橋の手すりがオシャレでそこに目がいってしまった。
全27件中、21~27件目を表示