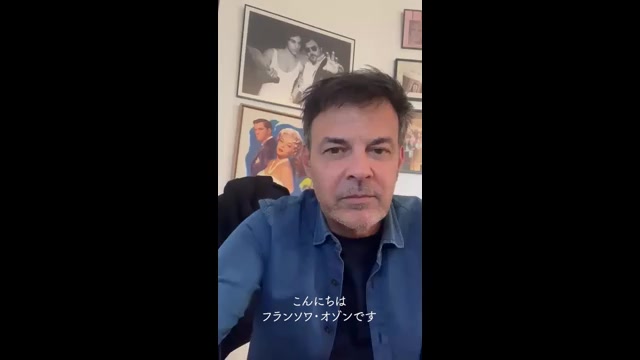秋が来るときのレビュー・感想・評価
全27件中、1~20件目を表示
【”良かれと思う事が大切、と老婦人は優しく言った。”今作はミステリー風味を漂わせつつ、人生の終盤を生きる女性の姿をフランソワ・オゾン監督が積み重ねた人生経験を表敬する姿勢で描いた逸品である。】
ー フランソワ・オゾン監督作品を映画館で観たのは「二重螺旋の恋人」が初めてであったが、エロティック且つミステリアスな内容に引き込まれ、パンフを即購入し、その後今作の前作までは全て映画館で観て来た。だが、この作品は私の居住区では公開館が少なく見逃していたのだが、鑑賞すると、フランソワ・オゾン監督のハイレベルなオリジナル脚本作りを含めたその才能に改めて驚くのである。-
■舞台は秋の自然豊かなブルゴーニュ。ミシェル(エレーヌ・ヴァンサン)は高齢だが、田舎での一人暮らしを楽しんでいる。
近くに住むマリー=クロード(ジョジアーヌ・バラスコ)とは、仲が良い。昔同じ”仕事”を巴里でしていたらしい。序盤は穏やかなトーンで物語は進む。
そこに、離婚調停中の娘のヴァレリー(リュディヴィーヌ・サニエ)が息子ルカを連れて休暇に来ると穏やかならぬ雰囲気が流れ始める。娘の母に対する口の利き方が、一々棘があるのである。
娘と孫に食べさせるためにマリー=クロードと、セップ茸などを取って来て振舞うが、只一人その料理を食べたヴァレリーは食中毒で病院に運ばれてしまう。
彼女は退院するが怒りは激しく、”息子も殺される!”とミシェルに言い放ち巴里へ戻ってしまうのである。落ち込むミシェルだが、マリー=クロードの息子で麻薬密売の罪で刑務所に入っていたヴァンサン(ピエール・ロタン:「ファンファーレ!ふたつの音」で、弟君を演じた人である。今作でも存在感が抜群である。)が出所してくる。
彼は、ミシェルの家の庭を整備し薪を割る仕事をしてあげる。そして、ションボリしている彼女の話を聞き、巴里のヴァレリーに会いに行くのである。
”スマホをミシェルの庭のテーブルに忘れたまま・・。”
◆感想<Caution!内容に触れています。>
・粗筋を細かく書いたが、フランソワーズ・オゾン監督のオリジナル脚本が、今作品も冴えわたっているのである。オゾン監督は多作の監督であるが、ほぼオリジナル脚本であるところが凄いのである。
・演出としては、ヴァンサンがヴァレリーに会いに行くところまで映されて、その後ヴァレリーが、アパルトメントから落ちて死んだという事実が描かれずに、電話で告げられる展開も絶妙に上手いのである。
・異国の地で働く夫ロランの下に行くことを拒んだヴァレリーの息子ルカは、ミシェルと暮らし始める。嬉しそうなミシェル。だが、ルカはミシェルがルカが生まれるまで、ヴァレリーを女手一つで育てる為に巴里で行っていた娼婦の仕事の為に、上級生に苛められるのである。そして、その仕事がきっかけでヴァレリーとの間に軋轢が出来ていた事も明らかになるのである。
ー 私は思うのだが、人類最古の商売と言われる娼婦の仕事は、ミシェルの様に夫が出て行き金だけ偶に送って来る境遇の女性が仕方なく付いた仕事であり、何で娘のヴァレリーは分かって上げれなかったのかな、と思うのである。ヤッパリ無理なのかな。
けれども育児放棄やヴァレリーを施設に入れずに育て上げた事は立派だと思うのだけど。それは、マリー=クロードも同じだと思う。故に二人は親友になったのだとも思うのである。-
■ヴァンサンがヴァレリーに会いに行った事を隠し通そうとするミシェルに、女警部がイロイロと調査してくるシーン。ミシェルが再出発の為に食事の店を開けた時の開業資金を”出世払い”として貸した事などから。けれども、ミシェルはキッパリと”あの子は私の庭仕事をしていました。”と答えるのである。
更にはルカが自分を苛めていた上級生に、ヴァンサンがムショ帰りと告げた、と彼が学校に迎えに行った帰りにバスの中で告げ、上着の胸ポケットから水鉄砲を出して水を掛けるシーンも良いのだな。故に彼も、非常カメラに映っていた”母に会いに行った自分がアパートの入り口の扉を明けた瞬間に擦れ違いで入って行ったフードを被った男の顔を見たか?”と、女警部に問われた時に、”知らないオジサンだった。”と答えるのである。
・後半の演出としては、死んだヴァレリーが、最初は青白い顔でミシェルに対し恨み言を告げる姿から、この世に現れる度に徐々に表情が和らいで来るのも上手いと思ったのである。
末期癌で死んだマリー=クロードの葬式の時に入って来た、老いた多くの女性達(且つての娼婦仲間であろう。)の姿をさり気無く映しつつ、葬儀場の外で一人涙するヴァンサンの姿と、彼のその姿を探しに行ったルカが見るシーンも良いし、ミシェルがマリー=クロードの墓に花を供えた後に、ヴァレリーの墓の前に行き綺麗に掃除をし花を供える彼女の後ろに、やや複雑な表情で立つ、死んだヴァレリーの姿・・。
■年は流れルイは巴里で美術学校に通っている。久しぶりにブルゴーニュに戻って来た彼を車で出迎えるのは、ヴァンサンである。
そして、且つてミシェルがマリー=クロードと茸を取りに行った森に行く道で、三人は車を降りる。そこで、ミシェルが森の中で見た鹿たちの群れ。誘われるように森に入って行った彼女の前に現れたのは穏やかな微笑みを浮かべるヴァレリーであり、彼女はミシェルに手を差し出すのである・・。
<今作はミステリー風味を漂わせつつ、人生の終盤を生きる女性の姿をフランソワ・オゾン監督が積み重ねた人生経験を表敬する姿勢で描いた逸品であり、最後の最後に母娘の確執が解けたシーンが沁みるヒューマンファンタジーでもあるのである。>
本当に脚本がうまい。
ミシェルとヴァレリーの間の「許せない」ほどの確執があり、悲しいかな、どうにもならない。
ヴァンサン(親友の息子)は、ミシェルの絶望を救うため(=ルカを取り戻すため)に行動を起こした。
ルカ(孫)は、祖母のついた「嘘」が、自分たち(ミシェルとルカ)が共に生きるために必要なものであることを受け入れる。
ミシェル、ヴァレリー、ルカの共犯関係がなんとも切ない。
けれど、最終的に「罪(嘘)」のすべてを受け入れ、心の平安(あるいは娘との和解)を得て安らかに、人生の「秋」を終える。
ブルゴーニュの美しい秋が彼らを包み込み、印象深い作品でした。
悪しきことも、良かれと思う。
老境に差し掛かった老婦人2人の穏やかな余生・・・
そんなストーリーを想像しました。
しかし予想とは大きく違っていました。
80歳のミシェルはブルターニュ地方の美しい森のそばに暮らしています。
パリに住む娘のヴァレリーが孫のルカを連れて休暇に来たのです。
ところが昼食に料理したキノコに娘が当たり、救急車で病院に搬送されて、
死にかけてしまいます。
娘は「お母さんに殺されかけた」と怒って帰り、そのままミシェルは
可愛がっていた孫のルカと会えたい境遇になり、
鬱病的になってしまいます。
一方、親友のマリー=クロードには受刑中の息子・ヴァンサンがいます。
ヴァンサンはやがて刑期を終えて母の元へ帰ってきます。
なにかと援助していたミシェルは菜園の片付けを頼み、
孫の遊び道具を捨てて・・・などと頼み、
ミシェルの寂しさを察したヴァンサンは
ある行動に出るのです。
【良かれと思ったことが裏目に出る】
マリー=クロードの座右の銘、です。
しかしミシェルは、
【良かれと思うことが大事なのよ】と正反対な言葉で返します。
ミシェルの【良かれ・・・】は、
ミシェルの見た目の可愛いおばあちゃんからは
かけ離れているのかもしれません。
ヴァンサンがヴァレリーを訪ねたことで、
煙草を吸いにベランダに出たヴァレリーは、
墜落して死んでしまうのです。
この事件=娘の死は、ミシェルにとっては
【良かれ、な出来事】
孫のルカとの同居生活が手に入ったのです。
又、もう一つ面白い趣向があります。
娘の亡霊が現れてミシェルと対話するのです。
「お母さんは思い通りにルカを手に入れたわね」
と、毒づかれたりします。
ほんとに怖いですねー。
事実ミシェルはヴァンサンにバーの開店資金を援助して、
こうマリーに言うのです。
「ヴァンサンは手伝ってくれたし・・・」
キノコも毒と知っててわざと食べさせたのか?
とか疑いたくなります。
やがてミシェルの過去が明かされます。
ミシェルもマリー=クロードも昔パリで娼婦として働いて、
ヴァレリーとヴァンサンを育てたと言う過去。
2人の外見からは想像も付かず驚きました。
そのことは近所でも知られていて、やがてルカはそのことで
学校で虐めにあうのです。
その解決法もまた
ミシェルがただのお婆さんではない事を、私は知るのです。
ヴァンサンにルカを迎えにやります。
「どいつが、いじめっ子だ!!」
木の下にたむろしている上級生をルカが指さします。
一言、二言言うヴァンサン。
「なんて言ったの?」と聞くルカに、
「務所帰り・・・と言った、意外と効き目がある」とヴァンサン。
やがてマリー=クロードが癌で亡くなります。
教会の葬儀には、ミシェルとマリーの昔の仕事仲間が10人も
参列します。
彼女たちとミシェルの繋がりは切れてなかったのですね。
その後、婦人警官がブルターニュの家を訪れます。
「内部告発があった」
「ヴァンサンがあの日、ヴァレリーを尋ねていたと、」
警官はルカに聞きます。
「マンションの出入り口ですれ違った男はヴァンサンか?」と。
ルカは「違う」と答えます。
しかしは内部告発・・・って一体だれが!!
マリー=クロード意外に知らないのでは?
題名が平凡でミステリーを窺わせるものがありませんね。
もう少し“意味深“な題名が良かったですね。
なかなかフランソワ・オゾン監督らしく、辛辣だけど優しく温かい。
娘のヴァレリー役のリュデイヴィーヌ・サニエは、
20年前のオゾン監督の出世作「スイミングプール」のミューズ、
だそうです。
こういう映画の作り方もあるんだねぇ・・・
猛暑の中、映画館へ涼みに行きました。
きれいな映像と音楽と速い展開で、意外におもしろかったです。
たぶん、
・ミシェルは、ヴァレリーを毒キノコで殺そうとしたが、失敗した。
・ヴァンサンは、ヴァレリーを説得に行っただけだが、事故で死んだ。
・ヴァンサンとルカは、ミシェルを殺そうとしたが、急病で死んだ。
と言う風に観客に思わせるつくりかな?
確かなことは、
・ミシェルとルカは、ヴァンサンが疑われないようにウソをついたことだけ。
監督の本意は?
普通に観れば内容は人の一生で別にインパクトは無いのだが、この主人公
元娼婦で男の扱いには慣れていたはず、友人の前科有り息子を動かし
保険金目当ての犯行を監督は全く美的に終わらせたんではないか?
娘のアパートへ行った男が顔を隠す必要はなく、見られた息子とは
仲良くして口封じ、他の人も言っているが、娘以外毒キノコを食べていない
孫はキノコが嫌いなのにキノコケーキを作った等 監督やりますな~
罪の意識
真実が明らかにならないことで、不思議な余韻が残る。もやもやして、だけど世の中の多くが、そのように曖昧なまま過ぎていくような気がする。
それでも私見としては、警察に頑張って欲しかった。そうでなければ、法が守られないことになってしまう。たとえひどい娘でも、命を奪われる理由などない。
なぜ祖母はキノコを食べなかったのか。なぜ残ったキノコだけをすぐに捨てたのか。なぜ親友の息子に、娘の愚痴を聞かせ、孫のおもちゃの処分をさせたのか。弱々しい外面を利用して、初めから強かに計画をしていたのではないか、とも思う。
警察が、もっとキノコの件や防犯カメラを精査していれば、少なくとも偽証は明らかになったのではないか。
そうやって見過ごされている事件は、実際にもあるのだろう。
罪を抱えたままの人間は、たとえ暴かれなかったとしても、罪悪感や後ろめたさから、心の安らぎや満足が得られなくなるのではないか。
事件後、祖母は娘の幻を見続け、親友の息子は金策に苦労し続けている。孫は学生生活を楽しんでいないように見える。
美しい自然の中にあっても、秘密を抱える三人が幸せには思えず、彼らの未来が明るいようには思えなかった。
秋の味覚はキノコだよね〜
「職業に貴賎はない」との考えは日本だけらしいが、その日本でも「娼婦をしてました」と言われたら後ずさりをするだろう。ましてや自国の伝統文化に強い誇りを持っているフランスだったらより賤しい存在として差別されるのだと思う。ミッシェル自身はその過去を恥じてはいないが娘のヴァレリーは(パリのアパートを譲ってもらったりお金の無心をするくせに)決して許すことはできない。そんな娘はさておき孫のルカは可愛くてしょうがない。親しい人は昔からの仲間のマリー=クロードとその息子のヴァンサンくらいしかいないけどそれで充分である。そんな背景のなか、2つの大きな出来事がミッシェルに起きる。毒キノコの件はルカがキノコ嫌いを知ってたのでミッシェルが故意に毒キノコを混入したのか?単なる事故なのか?ヴァレリーのベランダからの落下の件もヴァンサンが関わっているが、殺害なのか不慮の事故なのかはわからない。映画ではどちらにもとれるようにしてる。そのこと自体はミステリーだが主題は別のところにあるようだ。人の感情は様々で人生は複雑だけど、家族を思う気持ちに嘘はない。森の中で安らかに眠るミッシェルがそれを証明しているようだ、。
非常に複雑に絡んだ人間関係と感情がもたらす余韻
フランソワ・オゾン監督、すごい。よくこんな作品がつくれるなと思う。
主人公ミシェルと親友マリー=クロード、娘ヴァレリーとその息子ルカ。
そしてマリー=クロードの息子ヴァンサンが主要な登場人物だ。
ミシェルと娘の仲は悪く、それはミシェルの過去の仕事(娼婦)を娘が軽蔑しているかららしいが、
冒頭、ミシェルのつくったきのこ料理を食べて食中毒になり、死にそうな思いをしたことから不仲が決定的になる。
そんなミシェルに親切にされたヴァレリーは、ミシェル母娘が不仲だと聞き、
ヴァレリーのいるパリへ行き、ヴァレリーを説得しようとするのだが、、、。
この直後にヴァレリーが亡くなってしまう。詳しいことは一切描かれないし真相もわからない。
ヴァンサンが殺したかもしれないし事故かもしれない。
この謎の残し方が実に巧妙だ。
次にマリー=クロードが亡くなる。末期ガンらしい。
マリー=クロードは、ミシェルがヴァンサンのBARの開業資金を援助したことにショックを受け
倒れてしまい、その後急速に体調が悪化して亡くなってしまうのだが、
ここにもミシェルとヴァンサンの影が・・・。。なんて、不純なことを想像してしまうくらい
家族が亡くなっていく。
ルカが成長して(たぶん大学生)戻ってきたときに、ミシェル・ヴァンサン・ルカの3人で食事を囲むのだが
その時にルカが嫌いで食べれなかったきのこを、大好きだと言って食べるシーンに違和感あり。
あれ!?と思った。最初のヴァレリーが食べたきのこをルカが食べなかったのは、ルカが嫌いだと知っていて
敢えて出したのかなとか、図鑑できのこを調べていたけど、敢えて毒きのこを入れたのかな?など
ミシェルを疑う自分がいた。
そう捉えられてもおかしくない描き方が、やはり実に巧妙だと思う。
全然事件性はないかもしれない。でも、そう言いきれないかもしれない。全ては謎のまま。
ミシェルの最期も、たびたび現れるヴァレリーの霊が引導を渡したのか。それとも偶然か。
これまた謎のままである。
人生を描いた作品であると同時にミステリーでもある。
フランソワ・オゾン監督の巧妙な手練手管に感服した。
次回作も楽しみだ。
すべてが良いです。
秋の美しい森のほっこり映画と思ったら全くの勘違い。
ミステリー!
キノコ嫌いじゃなかったの!?
どういう事!?
どうしてみんな庇ってる!?
色々考えるのが面白かった。
映像、脚本、キャスト世界観に浸りました。
ブルゴーニュの黄金の秋
教会の神父の説教に「マグダラのマリア」が出てきたので、映画の背景は知れた。
一番素晴らしかったのは、かけがえのないブルゴーニュ、場所はオーセールの近くか。ブルゴーニュの秋は短く、午後4時には暗くなる、雨も多い。それでも、紅葉は美しかった。ただ、てだれのオゾン監督が、それだけで済ませる訳がない。
気になったところ、映像にはクロサワの影響があったのでは。庭の景色、ブランコが出てくるところ、葬列も。第一、カゲロウ(妖精)は雪の女を思わせた。TERブルゴーニュ・フランシュ・コンテ地域圏内の電車も、車内が広くて、きれい。
庭の畑で採れた材料を使った質素な食事も美味しそうだった。キッシュ、実だくさんのスープ、それからケーキ。森に親友と出かけて取ってきたキノコで娘が食中毒というけれど、軽いアナフィラキシーのようにも見えた。やはり素人のキノコ料理は怖い。昼からワインとはうらやましいが、彼らは少しの酒で、顔が赤くなることもない。それから、パンも。
ブルゴーニュは、もしかすると、オゾン監督がやがて帰ってゆく、終の住処なのかも知れない。私たちとの1番の違いは、彼らには教会があるから、基本的に一人であることか。
「良かれと思うことが大事」というミシェル(エレーヌ・ヴァンサン-80歳を超えたという-好演)の言葉が心に残り、我が「山本周五郎」を思わせた。
タイトルなし(ネタバレ)
パリでの生活を終えて、ブルゴーニュの森でひとり暮らす80歳のミシェル(エレーヌ・ヴァンサン)。
娘のヴァレリー(リュディヴィーヌ・サニエ)とは確執がある。
原因は、ミシェルの過去にあるようだ。
秋の休暇、ヴァレリーは息子を伴ってミシェルのもとを訪れる。
ミシェルは、森で友人と採取したキノコを料理して振る舞ったが、そのキノコ料理をひとりだけ食べたヴァレリーは食中毒を起こしてしまう。
母不信のヴァレリーは、ミシェルが自分を殺そうとしたと騒ぎ立てるが・・・
といったところからはじまる物語。
母娘ものなのかなぁと思っていたら、展開は意外な方へ。
ミシェルは、友人の息子ヴァンサン(ピエール・ロタン)を可愛がっており、ヴァンサンもミシェルを母のように慕う。
母娘関係を修復したいと思ったヴァンサンは、ヴァレリーが暮らすパリのアパルトマンを訪れるが・・・
と。
いやぁ、この展開には驚きましたわぁ。
「良かれと思ってやったこと。良かれと思って生きていればのよ」というのがテーマ。
達観した人生観。
事件の真相は観客に任せられている。
物語的にはそれほど面白いわけではないが、随所にオゾンらしさもあり、感心しました。
まぁ顕著なのは、オゾンの婆さん好きの側面。
登場する老女たちに親しみをおぼえます。
演出的は、省略・反復が上手い。
反復は、列車での移動。
物語をくだくだしく描かず、登場人物が列車に乗ることで、描写を省略し、反復でリズムを出す。
尖ったイメージのフランソワ・オゾン監督だが、歳を経て、円熟味が出てきましたね。
嘘と疑惑と優しさ
登場人物の台詞の中に嘘や曖昧さが多々あり、真実は分からないまま、観る側に委ねられます。
ミシェルは実の娘の死に関係しているかのような疑惑は満載で、でも友人や友人の息子や孫に対する優しさもあります。
そんな人間の複雑さを繊細に描くオゾンはやっぱりスゴイ!
ポスターだけで。
ポスター見ただけで鑑賞
あれ?
なんか、ほのぼのムードじゃない?
ボンジュール!
て、キノコ狩りして、
料理にふるまったら(ちゃんと図鑑で調べてるし)
なんとおばあちゃんミシェルが
ムスメに毒キノコ食べさせちゃった!
!!
えー!
このあたりで、やっと気づくわたし。
この映画、ホンワカじゃない!
ミシェルの過去話もおどろき、
え?ルカが生まれる前?
え?ちょっと待て待て
ルカ10歳いや、12歳くらいだとすると
計算ができないー
そんなことばかりが気になり
しかし、物語はどんどん進んでいく
死んでしまった一人娘の幻影?幽霊を
常にそばに感じながら
ヒトにはだれにも打ち明けられないことがある
死んで土にかえってしまえばおしまい
て、ことかな?
わたしがミシェルのココロのスキマの悪意
と、捉えてしまったから
そんな感想になりました
いや、おもしろかったです。
ゾワゾワ、ざわざわが止まらない
おばあちゃんに限らず、女性はキノコ好き。
まあ立派なんて言いながら、ペティナイフでシュパシュパ切って調理していきます。
もちろん、リュディヴィーヌ・サニエお目当てで観ました😎
ミッチェル役のエレーヌ・ヴァンサン(80)の方がかわいくてチャーミングなおばあちゃん。娘は終始イライラして、親に対して邪険な対応で、リュディヴィーヌ・サニエ(45)の笑顔はほとんどみられません😰
胸が痛みます。自分にも思い当たるフシや記憶がいろいろあるからです。
孫がもう来ないと思った時、これまでに買っておいたオモチャが目に入るとイライラするので、いろいろ手伝ってくれる親友の息子のヴィンセントに廃棄してくれと頼みます。
ヴィンセントはそのおもちゃをひとつひとつ大事に手に取り、壊れてないかチェックします。それをそっとのぞきみているミッチェル。ヴィンセントにバーの出店資金を彼の母親には内緒で出してあげます。
出店初日のパーティーでミッチェルとうんと親しげに踊るヴィンセント。店は順調なのにヴィンセントはずっと独身です。たぶん、ヴィンセントは超熟◯マニアか、服役前からミッチェルに仕込まれていたんでしょうね。
成長し、大学生になった孫のルカが「昔からキノコだいすきだもんね」って言った途端に、
一気にゾワゾワ、胸がざわざわ。
エンドロールの音楽もザ~ワ、ザ~ワと追い打ちをかけてくるようでした。
···········································
··········································
いくら歳をとっても女はオンナ
彼女や彼女の親友の マリー=クロード があの稼業繋がりであったにせよ、なかったにせよ、
親と言えども女を舐めたらいかんぜよ!っていうことですな😎
わたしはもうおじいちゃんなんで、生涯ずっと無害デス😅
人生の冬が来る前に
6月4日(水)
「M:I,ファイナルレコニング」の後、「サザンオールスターズ 東京ドームライブビューイング」以外映画館へ行って無かった。
半月ぶりに映画館へ。新宿ピカデリーで「秋が来るとき」を。
80歳のミシェルは、パリからブルゴーニュに移り、田舎生活をしている。パリの頃からの友人マリー・クロードがいて、刑務所に入っている息子ヴァンサンに面会に行く
マリーを送迎している。
休暇で離婚調停中の娘ヴァレリーが息子ルカを連れてやって来るのでマリー・クロードとキノコ採りをして二人にキノコ料理をふるまう。娘はキノコの毒に当たり緊急搬送され、怒ってルカを連れて帰ってしまう。母ミシェルと娘ヴァレリーのギクシャクした関係が謎だが、しかしそれには理由があった。
娘に電話しても出ない、孫のルカにも会わせてもらえないミシェルはうつ状態に。そんなミシェルの様子をみかねた出所したヴァンサンはパリのヴァレリーの所へ物申しに行くのだが…。
娘や孫への思い、友人への思い、祖母への思い。そして、嘘。嘘が本当?嘘も方弁。嘘と秘密が渦巻くオゾンの二重構造的世界(ゴーストも含めて)が展開されるが、終わり方がいまひとつスッキリしなかった。ストンと落としてくれたら、もう少し評価が上がったかも。
孫のルカ役の子はカワイかった。美男子だな。美男(ハンサム)になりそう。
言いたいことはわからなくもないが娘を思うと複雑
冒頭にマグダラのマリアの説教があることからも、過去に罪を犯していようとも愛があればやり直せる、ということなんだろうなとは思うものの。
自身も金に困りつつもなんとか真っ当に暮らそうとする娘からは軽蔑されて、いくら親子とは言っても、いなくなって正直ほっとした、というのは本当に素直な気持ちの吐露だろうなとは思う。
たとえ周りから非難をされようともなんとか娘を育てるために必死でしてきたことであって、一番そのことで否定してほしくなかったのは娘だったはずだ。
どうあがいても理解しあえない母娘の関係に疲れても仕方がないと同情する気持ちもわいてくる。
皆がうっすらと、ヴァンサンの罪を知っても、見ないふりをしたのは、そのほうが都合がいいしヴァンサンや友人への親愛の情があるからなのだろう。
が、それでも、では娘は非難するばかりでろくでもなかったのかというとそれもまた違うと思う。娘だって子供を離婚して奪われやしないかと不安で必死で娘なりに頑張って生きてきたのではないのか?
方法は違えどもなんとか必死で子供を育てようとした立場としての分かり合うことはできなかったの?同情はできなかったの?復讐とまでいかずとももう少しそこに思いをはせても良かったんではないの?
どうしてもそこがひっかかって、すんなりと人生賛歌だなとは受け取れなかった。前半は眠かったし。
言わなくてもいいものを
黙っていられないものだろうかと、考えてしまう。
どの人も、共通して秘密をかかえられない。
秘密なのに、なんだかオープン。
大事なとこだけは、秘密のまま。みんなで抱えていくわけで。
そのあたりの微妙なニュアンスの描写がうまい。
正直に生きたけど、その結果はどうだったのだろうかと考えさせられてしまう。
正直が正直を庇い、嘘が真実になる。そんなストーリーかもしれない。
フランス映画らしい
フランス映画を観ていつも思うのは、役者の皆さん演技がとても自然であること、ストーリーが淡々としていてメリハリが少ないこと、また終わらせ方もハッキリしないというか余韻を残す終わり方が多いことです。
本作もそれに漏れず、とても自然な感じで観ていて心地よいのですが、あまりにも淡々とし過ぎだと感じました。人が死んでいて、警察が事件性を疑っているにも関わらず、皆さんとても冷静で、なおかつ葛藤する様子があまり描かれていないのが不自然で残念でした(あえて描いていないのかも知れませんが…)。あと、ルカがヴァンサンを庇ったシーンも、子供にそれを背負わせるのはどうなのかと、ちょっとそのシーンの真意が分からなかったです。
という訳で、フランス映画らしく静かで穏やかな雰囲気だったのですが、それがかえって不自然に思われる作品でした。
真相はお話しできないが、ミシェルの顔が映ったときの神父の言葉は真実のように思える
2025.6.2 字幕 MOVIX京都
2024年のフランス映画(103分、G)
仲の悪い母娘の間で巻き起こる事故を描いたヒューマンミステリー
監督&脚本はフランソワ・オゾン
原題は『Quand vient l'automne』、英題は『When Fall Is Coming』で、「秋が来るとき」という意味
物語の舞台は、フランス・ブルゴーニュ地方の田舎町
元娼婦として娘・ヴァレリー(リュディビーヌ・サニエ)を育ててきたミシェル(エレーヌ・バンサン)は、人里離れた村で過ごしていた
家庭菜園で野菜を育て、親友のマリー=クロード(ジョシアーヌ・バラスコ)とともに森でキノコ狩りをする日々
ある日のこと、ヴァレリーが息子・ルカ(ガーラン・エルロス)を連れて休暇に来ることになった
ミシェルは孫と会えることを楽しみにしていたが、ヴァレリーは着くなり「実家の名義を自分にしてほしい」と言い出し、「公証人を選んでいるので会ってほしい」と続けた
その後、三人は山菜料理やキノコ料理を食べるものの、ヴァレリーの雑言に食欲が失せたミシェルは手を付けず、キノコ嫌いのルカはスープとパンだけを食べた
それから、ヴァレリーは仕事を始めたために、ミシェルはルカとともに森へと出かけることになった
そこで自然と戯れながら家に戻ると、たくさんの人だかりに加えて救急車まで出動していた
聞けば人が倒れていると言い、キノコの毒に当たったヴァレリーが気絶する前に救急車を呼んだとのことだった
治療を受けて事なきを得たヴァレリーだったが、「殺されるところだった」とまくしたてるのである
映画は、この毒キノコ事件でさらに険悪になった二人が描かれ、そんなところに服役中のマリー=クロードの息子・ヴァンサン(ピエール・ロタン)が出所してくる
ヴァンサンはお金を貯めてバーを開きたいと言い、ミシェルは15ユーロの時給で庭掃除の仕事を依頼する
そして彼は、ミシェルの家の手入れを始めるのだが、孫に会えないフラストレーションを抱えたミシェルに同情し、ヴァレリーに態度を改めるようにと、パリにまで出向いて文句を言うことになったのである
物語は、ヴァンサンがヴァレリーの部屋にいたときに事件が起こり、それは本当に事故だったのか、という謎を引きずったまま続いていく
ヴァンサンは母親に「事故」だと言い、警察もミシェルへの聞き込みから「自殺」であると断定する
だが、事件に疑問を持つ警部(ソフィー・ギルマン)は、ミシェルのもとに訪れ、それとない尋問を始めていく
そして、ルカに対して、防犯カメラの写真を見せて、「この男はヴァンサンではないか?」と聞く
映画は、マグダラのマリアの逸話を神父が語るシーンから始まり、「罪深き女」という言葉のところでミシェルの顔がクローズアップされたりする
その意味は「過去」を意味するものの、その後の未来において、彼女は罪深き女だったのか?という疑問が最後まで拭えない
穿った見方をすれば、ヴァンサンに依頼してその報酬を払ったみたいな感じになるが、そこまで計画的なものにも思えない
住人以外の人物が建物に侵入したということしかわかっておらず、部屋には争いの形跡もなく、状況的に「事件」と断定はできなかった
さらに、ミシェルが「不安定で」とヴァレリーの印象を操作し、「自殺」に対して反発しないという言動を見せる
だが、あの状況でヴァレリーが自殺をするとは思えない
彼女の前にヴァレリーの幻影が登場するのは、ミシェルに罪悪感があるからで、その罪悪感がどこから来ているのかは明白のように思える
それでも、ヴァレリーの死は彼女自身の現在が起こした延長線上にある偶然のようにも思えるし、ヴァンサンが彼女に近づいたことでパニックを起こしてバランスを崩したという線のほうがあり得そうに思えた
いずれにせよ、ヴァンサンにヴァレリーとの関係性を暴露したのはわざとなのかわからないが、ミシェルもマリー=クロードもヴァレリーの態度を良くは思っていない
ヴァンサンが無関係なヴァレリーのもとに行って態度を改めろというのも不自然な流れで、彼があの家の場所を知っていることの方が不思議であると思う
そう言った想像力が紡ぎだす仮定というものがどうとでも解釈できるのが面白いところで、はっきりとした答えが欲しい人向けには作られていない
ミシェルが人の愛し方を知っているかはわからないが、赦されないからこそ娘に連れて行かれたと思うので、そう言った意味も含めて、ミシェルは「罪深き女だった」のかな、と感じた
全27件中、1~20件目を表示