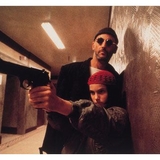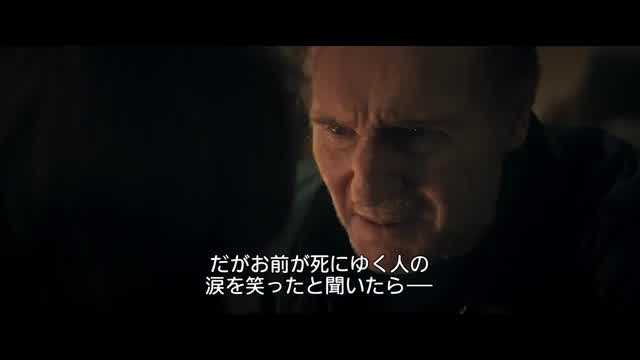プロフェッショナルのレビュー・感想・評価
全33件中、1~20件目を表示
タイトルなし(ネタバレ)
アイルランドの美しい自然とのどかでゆっくしりとした時間軸、そしてそこで暮らす感じのいい村人、町人たち。表向きはそんな風景なんだけど、少し重く湿った空気感が垣間見える。その小さな違和感がリーアムニーソンと逃亡者でありおたずね者になったアイルランドの過激派テロリストのデランたちが暗喩している様で演出的にハマってたと思う◎
銃撃戦などのアクション、殺しのシーンはしっかり殺すんだけど最初から最後までずっとキレイな印象を受けた◎。ほんとにデランが死ぬ最後までキレイだった。ビンセントに届いた賭けで勝ったお金と罪と罰の本、とりとめのない会話や描写も伏線になっておりやはりキレイに回収していて抜け目がない◎
リーアムニーソンや美しいデラン役の俳優(名前知らない)のムードが一役買っているとも思う、他の人なら完全にこけてると思う。いい映画でした。
殺し屋としては鈍ったかもしれないが、漢としてはプロ
1970年代の北アイルランド。殺し屋の過去を隠し、海辺の町で静かに暮らしていた。
爆破テロを起こした過激派グループが町に逃げ込んでくる。メンバーの一人が少女に虐待…。
少女を救い出し、過激派たちに制裁を下すは、勿論この男!
リーアム・ニーソン!
実際の内容とあらすじ/邦題にちょい相違がある。
あらすじからは少女を救う為に過激派どもを容赦なくバッタバッタ倒していくリーアム無双の痛快アクションと思うが、めぼしいアクションはクライマックスくらい。ほとんどヒューマンドラマってくらい地味。
それから、プロフェッショナル…? もっとキレッキレのスキルを見せてくれると思いきや、相手の不意の攻撃を受けるわ、鉄砲を撃とうとして弾を落とすわ、本当にプロの殺し屋…? 公開時、“プロフェッショナル”やら“アマチュア”やら“ベテラン”やらのタイトルが並び、ネタになってたね。
この派手さの無いアクション×ドラマ、西部劇タッチ。監督はやはり似た雰囲気の『マークスマン』のロバート・ローレンツ。当人同士はウマが合ったのかもしれないが、観客とのウマはあまり合わないようで…。(興行大不発&賛否両論…)
話的には悪くはない。
指示役から町の名士の暗殺を請け負い、殺す直前「最後に善い行いをしろ」と言われ、殺し屋としての人生に疑問を持つ。
これを最後に引退し、ガーデニング作りを始める。
そんな時、行き付けの酒場の娘に虐待の後が…。姉妹である酒場の女主人と過激派の女リーダー。その弟が女主人と娘の家に転がり込み、横暴を振る舞う。
クズ弟に制裁。当初殺すつもりは無かったかもしれないが、アクシデントで…。
弟を殺されたリーダーの姉は復讐を誓う。かなり激しい性格で、町中を聞き込み、殺し屋時の指示役を殺し、友人知人に暴行まで…。
見て見ぬフリなど出来ない。元々穏やかで情のある男なのだ。
殺しの仕事を楽しむ後継者の若い殺し屋を叱責。が、米カリフォルニアに行ってレコードを出すという夢を聞き、決着には同行させず、夢を追え。
友人警官や隣人女性など町の人々に好かれている。
が、友人隣人たちは知らなかったのだ。彼の本性を。
殺し屋…いや、町や友人の為に闘う漢。
渋くてカッコいい、やはりリーアムはリーアムだ。
静かなる暗殺者、がタイトルでいいのでは…?とは思ったw
※リーアム・ニーソン好き好きフィルターかかってます。
一番好きな海外俳優さんです。
アイルランドめっちゃ綺麗なとこですね。自然、建物風景の美しさなど好きな方は引き込まれてしまうとおもいます。私はこういうゆったりした中で起こる小規模なトラブルががんじがらめでめんどくさくなる展開嫌いではなく、90分映画なので抑えたいとこだけ抑えた映画で観やすいです。タイトル「プロフェッショナル」はみんな5分に一回作中爆発すると思っちゃうよ邦題!!リーアムの映画は今までそうだったんだから!!!!
リーアムはその田舎の静かでゆったりした土地の暗殺者で、お掃除人。川のそばで拉致した対象の人間自らに穴を掘らせて土の中で頭をショットガンで射抜いて埋め埋めして、最後にその上に木を植える、というオサレなことします。相棒の若い殺し屋もいて、2人でアイルランドの小さな街を掃除してます。
で、なんか色々あって外から来た4人のテロ組織?かな、を蹴散らします。町の住民も若干名犠牲になりますがお掃除完了します。そのシーンはゆったりした街並みの中の小さな酒場、爆発します。ここが一番の見せ場でしたかな。リアルを追求した感じの演出なので小規模でしたが中銃撃戦もなかなか良かったですよ💣
1970年代が舞台なのでスマホもないし、新聞と電話くらいしか通信手段がなくて、観ていて新鮮でした。ゆったりおつまみや ほろよい片手に見るのがベストな作品だと思います😊
リーアムはずっとカッコいいですね!96時間やアンノウンなどバリバリアクション、というわけにはいかないご老体だと思うので、これからも無理せず俳優業を期待してます☺️
おや、プロフェッショナルじゃないな、お前。
見逃していたリーアム・ニーソンの「プロフェッショナル」をアマゾンで。
1974年の北アイルランド。ベルファストでIRAによる爆破テロ事件が起きる。4人組のリーダーはデラン(ケリー・コンドン)。
おや、この間「F1」に出ていたな、お前。
北アイルランドの海辺の田舎町グレン・コルム・キルに住んでいる退役軍人のフィンバー・マーフィー(リーアム・ニーソン)は、表向きは本屋だが、実は殺し屋である。
殺しのターゲットを裏山?に連れて行き墓穴を掘らせて射殺し、そこに埋めると若樹を植える。付近には何本もの若樹があり、何人も殺しているのが判る。
元締めの男から報酬を受け取り来週の仕事を依頼されるが「もう引退する」と断る。「その仕事はケビンにやらせてくれ」
おや、こんな田舎町で毎週殺人の依頼がある?殺し屋が二人もいて、それで生計を立てている??
建前は本屋のフィンバーだが、警官のビンセント(キアラン・ハインズ)とは空缶を的にした射撃でいつも賭金をせしめている。「フィンバー、何の本を読んでるんだ」「ドストエフスキーだ」「アガサ・クリスティの方が良いな」
IRAの4人組は田舎町に潜伏する。フラフラ出歩いているデランの弟は、フィンバーが行くパブの給仕シニードの親族だが、食料をもらいに行き娘のニアを虐待している。
フィンバーが殺したのは男だけ。女、子供に手を出す奴は許さない。元締めに殺人を依頼するが断わられ自ら手を下すが、油断して失敗しそうになる所を殺し屋仲間ケビンに助けられる。
弟を殺されたデランは、怒りまくり元締めの男を射殺し、弟を殺したのはフィンバー
だと突き止める。
町のラグビー大会の会場でデランを見つけたフィンバーは後を追うが、後ろを取られる。
おや、フィンバー敵に後ろを見せるのか、プロじゃないな、お前。
ゴルゴ13なら絶対に冒さないヘマだ。
後ろを取ったら、後は引き金を引くだけなのに弟殺しの依頼者を連れて来ると言うフィンバーに引き金を引かないデラン。
おや、「F1」ではあんなに早くブラピの胸に飛び込んだのに、リーアムの背中には素早く銃弾を撃ち込まないのか、お前。
弟を射殺したのはケビン。カリフォルニアに行きたいと言うケビンに金を持たせ脚を洗って出直せと諭すフィンバー。
パブでデランと対峙するフィンバー。そこにケビンがやって来る。
おや、脚を洗わなかったのか、お前。
結局、爆弾持ってやって来たIRAの3人とパブで銃撃戦。爆弾は炸裂。ケビンはデランに撃たれて死ぬ。深手を負ったデランは隣の教会で息絶る。それを見守るフィンバー。
翌朝、ビンセントのパトカーには、フィンバーからの荷物が。紐解くと中には賭金の札が挟んである「罪と罰」。
ケビンの車で町を去るフィンバー。
おや、その行方は何処なんだ、お前。
北アイルランドの風景や隣人たちとの暮しは良かったが、何と言っても二人の殺し屋とIRAがスキだらけでお間抜け過ぎ。プロフェッショナルとは程遠かった。
原題は「聖人と罪人の地で」。
邦題が完全にミスリードだった。
次のリーアム・ニーソンは何をやるのかな。
罪と罰
時代は1974年アイルランド紛争の最中、足を洗おうとした元軍人の殺し屋フィンバー・マーフィー(リーアム・ニーソン)が住む北アイルランドの海辺の町に武装組織IRAのメンバーが逃げ込んでくる、メンバーの女ボス、デランが弟の仇フィンバーをつけ狙う・・。
どちらも人殺しなのだがIRAの方が市民迄巻き込むテロリストだからフィンバーの方が多少はましに思えます。独身の殺し屋のくせに猫を飼っている演出は、ハリウッドのシナリオの教科書にも載った「Save the Catの法則」にフィット、まさに善人ぽく思わせるためでしょう。物語は西部劇のようなアウトロー同士の抗争劇、悪をもって悪を倒すお話。
邦題のプロフェッショナルはプロの殺し屋フィンバーのことでしょう、原題のIn the Land of Saints and Sinners(聖人と罪人の国で)はまさに内戦で荒廃したアイルランドの惨状、おそらく聖人とはフィンバーの隣人たちのことで、フィンバーもデランも罪人の方でしょう。劇中でもドストエフスキーの小説「罪と罰」が出てきますが人間の内面的な葛藤や、罪と罰、救済といったテーマを探求し、人間の本質に迫るあたりは似たような感触の映画でした。
トレーラーとはちがう
96時間に代表されるスーパー暗殺者的なトレーラーだったがまったくちがう。アイルランドの田舎の人と自然の中で暗殺者として苦悩し引退する主人公。あくまでこれがテーマでありテロリストとの対決も地味。人の「罪と罰」とアクションが中途半端でした。
控え目なリーアム・ニーソン…
時代背景も去ることながら、一昔前の映画のようなスピード感。リーアム・ニーソンの年齢的な部分を加味したのか、単なるいつもの無双の殺し屋ではなく、殺し屋稼業に疲れ、平穏な生活で余生を過ごしたい男を描いている。IRAの姉も政治的テロであり、弟のために復讐する姿は単純な善悪では語れない。過去の所業が長くは居座れない運命、友との別れ、雄大な景色、音楽に寂しさを感じた
もっと最強の殺し屋かと思ったから物足りなく感じた
もっと早く敵を瞬殺してれば…
この街が大好きなんだなぁと思うと出ていかなくちゃいけなくなっちゃったのが切なかった
北欧が舞台で景色やお家やお部屋の中がめちゃくちゃオシャレだった
原題は「聖人と罪人たちの地で」
出演量産のリーアム・ニーソンの最近の作で、題名が「プロフェッショナル」‥
これは正直殆ど期待せずに見ました。
ですが、鑑賞したらとても良かったです。
荒涼だが美しい風景あり
日々の生活の穏やかさと楽しみ、老いの哀しみあり
日常の中での常軌を逸した内幕あり
人でなしにも、心あり、事情も言い訳もあり
友人あり
そして強く優しいが、強すぎず、また非情な冷酷さも日常なニーソン(ここ大切)
物語進行に緊張感があったので小さい画面にも関わらず、冗長さも感じず観られました。
まあ残念ながら、最近不可避的に観る側としての歳や心理環境も映画の批評に影響されてしまうので、評価に多少心情同調フィルタがかかっているかも知れません(勿論私は哀しい殺し屋でも強く優しい漢でもありませんが)。
頗る面白い、とまではいかないが、なかなか味わい深い映画でした。
これがちょっと面白い。
イーストウッドの映画の制作を長年やってきた人(ロバート・ロレンツ)が監督をしている。イーストウッドの映画の影響を感じる。「許されざる者」を彷彿とさせる。舞台は北アイルランドだけどまるでイーストウッドの西部劇だね。
時代はわざわさ74年に設定している(多分、IRAが過激だった頃)。
IRAの過激派が、ベルファストで爆弾テロを起こし、この静かな村に逃げ込んできた。主人公のリーアム・ニーソンはプロの殺し屋だったが足を洗ったばかり。だが過激派の一人が、村の少女に手を出したことを怒り、主人公は、今までのようにうに始末してしまう。殺された男の姉が過激派のリーダーで、弟が行方不明になったことを探ると、主人公にたどり着く。それで、村のみんなが集まるパブで落ち合うことに…。
主人公の隣に住む女性とは、お互い信頼し合っていて時々食事を共にする仲。パブの女主人とも仲が良く、その娘を主人公は暖かく見守っている。村の警察署長は主人公とは長年付き合っている親友。この村は、主人公にとっては居心地の良い場所だった。ここを終の棲家として落ち着こうと「殺し」をやめた矢先だった…。結局は、また殺しに手を染めてしまい、旅立ってゆく。
荒涼とした北アイルランドの風景がこの映画に合っている。
役者は、敵役の過激派の姉役のケリー・コンドンが素晴らしい。憎たらしいほどだが、筋が通っている。この敵役がしっかりしていないと作品が引き締まらない。
ほかに署長や、隣の女性、パブの女主人、それに彼を慕う若手の殺し屋(この設定も「許されざる者」を彷彿とさせる)、殺しの元締めとその母親など、脇を固める役者が生き生きとしていることで、この映画の厚みが出た。
その点もイースウッドの映画とよく似ている。
空撮を多用していて、その点もイーストウッドの「ミスティック・リバー」を思い出す。音楽はモロに西部劇。
頗る面白い、とまではいかないが、味わい深く、私好みの映画でした。
「プロフェッショナル」と「アマチュア」
狙ったのか偶然なのか同時期に「プロフェッショナル」と「アマチュア」という対抗したタイトルの作品の公開、さらに「ゴーストキラー」「サイレントナイト」を含めて“リベンジアクション”の作品の同時期公開で、全て面白そうで全部観ようと思っていました。
今日は第三弾です。
「サイレントナイト」や「アマチュア」は一般人が殺し屋に上がっていく過程や活躍が内容だと思いますが、これは殺し屋として活躍していた人間が下っていく過程が描かれていると思いました。
「プロフェッショナル」と付けた意味は何だろうと疑問を感じるところもありますが、プロの生き様や引き際がテーマということかなと思います。
「俺を怒らせるな。」というキャッチや「ハードボイルドアクション」という触れ込みでしたが、その水準の展開やアクションは少ないと思いました。
さらにアイルランドの田舎が舞台なので長閑で、他の作品とは画的にそこが違います。
リーアム・ニーソンの作品は面白いというのは裏切らないです。
以下少しネタバレ
↓
冒頭に巻き込まれて死んでしまった親子のことや、最後に助かった親子のその後が取り上げられると思ったのですが、そこは肩透かしでした。
明日は「アマチュア」を観ます。
誰一人プロらしいプロの登場しない、田舎のプロ気どりが織りなすほんわか老人アクション。
『アマチュア』に引き続いて、『プロフェッショナル』を視聴。
セット企画として、その「対比」を愉しむ予定だったのだが……
やべえ、こいつら、
全然「プロフェッショナル」
じゃねーじゃねーか(笑)。
むしろ、のんびりした田舎の村を舞台に、
田舎ののんびりした引退した殺し屋が、
のんびりした頭の弱い相棒と共闘しつつ、
のんびりした頭の弱いテロリストたちと
さんざんお互いにミスを犯しまくって、
お互いにスカタンをかまし合いながら、
なんとなく「老人ヒーロー属性」だけで、
リーアム・ニーソンがラスト・スタンディング!
そういった、田舎のラムネ水みたいな映画だ……。
まさに「タイトルに偽りあり」。
あと、ハードボイルド・アクションって宣伝に書いてあるけど、果たしてそうなのか??
どっちかというと、真顔でやってるドメスティック・アクション・コメディにしか思えないが……。
リーアム・ニーソンといえば、いまや「老人アクションの第一人者」(笑)であり、『96時間』以降、もはやどの映画がどれだったかすらよくわからなくなるほど、同工異曲の巻き込まれ型アクション・スリラーに主演し続けている。
そんな「市井の一般人に見えて実は凄腕のプロフェッショナル」というリーアム・ニーソンらしい役回りから、今回の主人公はかなり逸脱しているといってよい。
いや、「一見、いつものリーアム・ニーソンに見せかけておいて、実は普段の設定とは一味違う」という「ギャップ」自体を愉しむ映画といったほうがいいかもしれない。
いちいちこの映画の登場人物の行動に、整合性やリアリティを求めても仕方がない。
むしろ、やっていることのおおよそ全てが配慮を欠き、判断力を欠き、理に反している。
そういった類の、「あらかじめゆるく作られた」「ゆるいのが魅力の」映画。それが本作だ。
結論。
タイトルとして、邦題の「プロフェッショナル」ほどにふさわしくないものもない!
(原題の『In the Land of Saints and Sinners』(聖者と罪びとの地で)は、無駄にかっこいいだけだけど、少なくとも内容を外してはいない。)
あるいは……、これって配給会社の渾身のギャグなのか?
「なんだよ、出てくる連中、どいつもこいつもいったい何考えてるんだ?? よし、それならこっちは敢えて〈プロフェッショナル〉ってつけてやれ!!」みたいな。
強いて言えば、「プロフェッショナル(気どりw)」といったところか。
― ― ― ―
出だしから、いきなりテロリスト4人組が標的の爆殺に子供たちを巻き込み、しかも相手に警告を発したせいで、衆目に顔をさらしてお尋ね者になるという大きな不始末を犯す。彼らはテロリストとしては三流で、状況判断がとことん甘く、感情の制御もおぼつかない。
4人組のうちひとりは、逃亡中のテロリストなのに、毎日入り江での水泳にうつつを抜かし、親族の少女に無意味な暴行を加え、会ったばかりの男の車に乗せてやると言われてほいほい乗って、そのまま人生の最期を迎える。残された3バカトリオも、ラストに至るまでとことん無能で、とことん頭の悪そうな会話を繰り返す。
IRAの重信房子か永田洋子かといったコワモテの女性闘士は、最終的にアイルランド解放の大義とかそっちのけで、「私怨」の復讐戦へと猛進することに。残る2人は「やっておしまい!」と叫び続ける女性闘士にあごで使われて、さながらIRAのボヤッキーとトンズラーである(笑)。
対する主人公で老練な殺し屋のフィンバー・マーフィー(リーアム・ニーソン)も、冒頭の「殺し」こそルール通りに進めて卒なくこなしてみせるが、そのあとからは、やっていること全体がほぼめちゃくちゃだ。
●馴染みの女性の家で、子供があざだらけで叔父を嫌っているのを見ただけで、勝手に「チャイルド・アビューズ」(児童虐待)だと決めつける。
●被害者にも容疑者にもちゃんとした確認すらとらず、証拠調べもしないで、いきなり次の「殺し」のターゲットにするよう、元締めに要求する。(たとえば日本の『必殺』シリーズでは、殺し屋が依頼だけで動くことは絶対にないし、自分たちの目で悪の証拠を確認したうえで初めて仕置きする。逆にどれだけ義憤に駆られても、依頼者のいない(=金の発生しない)仕置きは「ただの人殺し」として徹底的に忌避される。これが正しい「殺し屋道」というものだ。)
●元締めに断られたら(そりゃ当然だ)、独断で相手を殺すことを宣言し、勝手に行動に移す(まさにルール無用のただの殺人鬼である)。
●叔父のテロリストが少女に渡していた銃弾を、元締めの家に置きっぱなしにして帰って、のちに元締めが姉のテロリストに射殺される、直接的な原因を生じさせる。
●どこに人の目があるかわからない海岸べりの道路で、顔出しのまま公然と相手を襲って、白昼堂々相手を昏倒させ、そのまま誘拐して連れ出す。
●トランクを開けた瞬間、閉じ込めていた若造の反撃を受け、ナイフで刺されて手負いになるばかりでなく、流血してあたりじゅうにDNAの痕跡を残すことに。その後もパニックに近い状況に陥り、相手には逃亡されるわ、弾を装填し損ねるわ、銃は空撃ちするわ、挙句に若い殺し屋仲間に相手を仕留めてもらって、助けられるはめに。
●若い殺し屋に助けてもらったくせに、偉そうにその若者に死体の穴を掘らせ、自分はふんぞり返って説教を垂れている。殺しに関する感傷的な思想の押しつけも、聞いているだけで痛々しいばかりだ。よほど、ドライな価値観で動いている若い殺し屋のほうが、殺し屋としてまともだと思う(こいつもバカはバカだけど)。
●テロリストたちに家を占拠されているのに気づき、そこに戻らないことにした選択自体は正しいにせよ、ヤサが割れているのに、テロリストが帰った瞬間に下まで降りて、隣人のおばちゃんを助けたり、爆弾が仕掛けられているかもしれない母屋に入って猫を連れ出したりしている。全編を通じて、行動に警戒心が毛ほども感じられない。
●家でテロリストに猫を見られているはずなのに、それをわざわざ少女のところに持っていって「飼ってくれ」と強要する。そもそも動物を譲り渡すのはよほど気ごころの知れた相手以外は迷惑な話だし、それが成獣だとなおさらだ。しかも、この猫を渡すことで、少女とフィンバーの強い関係性がテロリスト叔母さんにバレて、「依頼人が娘、もしくは母親と取られる」可能性を一切考慮していない。
●ノープランで、テロリストを観にグラウンドまで行って、その場でいきなり遭遇する(トイレでは容易に後ろを取られていて、ここで速攻で殺されててもちっともおかしくない)。さらには、どれだけ被害が広がるか全くわからないのに、安易にパブでの夜の打ち合わせに応じている。
●待ち合わせ場所のパブでは、女テロリストの義妹=少女の母親が勤めている。積極的にテロリストとの対決に親族(およびその娘)を巻き込んでいく理由が皆目わからない。だいたい、パブで女テロリストと待ち合わせた理由が「弟殺しの依頼人を教える」というものなのに、虐待された少女の母親がいる場所にわざわざ招き入れてどうしようというのか。「この女があたしの弟を売ったのね」って話になりかねないと思うのだが。
●若い殺し屋は、100%銃で武装していることがわかっている女テロリストに、イチャイチャしながら近づいていって、案の定いきなり撃たれて「ファッキン、いきなり撃ちやがった!!」とか騒いでる。およそ知恵の遅れ方が尋常ではない。
●わざわざ混雑しているパブで待ち合わせたうえ、そこで安易に銃撃戦を展開したせいで、結果的に、多数の村人の負傷者と室内の被害を生み出すことに。戦闘のプロフェッショナルといいながら、お互いいくらやってもとどめをさせず、弾はなかなか当たらず、お互い即死させられないまま、ラストシーンは教会まで持ち越される。
……とまあ、だらだらと気になった点を書き連ねてきたが、これだけ「すっとぼけた」部分が連鎖するのを見れば、賢明な皆さんならお分かりだろう。
要するに、これは「製作者が不用意で頭が弱くて注意力が散漫だから、こういう穴の多い展開になっている」という次元の話ではない。
明らかに、製作者は、主人公や、仲間や、テロリストや、街の住人も含めて、出てくる登場人物全員が「アホ」である、という大前提で、このドメスティックなドンパチものを作っている。そう、これらはすべて「わざと仕組まれているトンチキ」なのだ。
最近観た映画でいえば、去年K’sシネマの奇想天外映画祭で観た、オーストラリア産の珍作『デス・ゲーム/ジェシカの逆襲』に近いテイストかもしれない。
くっそド田舎で、掘っ立て小屋で暮らす頭の弱い美少女が、頭の弱い密猟者3人組にさんざん追い回されて、ついに逆襲に転じて3人を血祭にあげる。
お互い敵も味方も、やってることがゆるんゆるんで、攻めるも守るも「隙」しかないような妙ちきりんな映画。でもまあ、娯楽作品として割り切れば、頭を空っぽにしてのんびり愉しめる。
今回の『プロフェッショナル』も、まさにそういう映画である。
で、そういう映画だと納得して観るぶんには、それなりに楽しい。
僕は決して、この映画が嫌いではない(笑)。
― ― ― ―
なお、この映画における主人公フィンバーの立ち位置は、明らかに「西部劇における老ガンマン」を意識したものだ。
メインテーマの楽器がハーモニカというのがまず、いかにもマカロニ調だし、これから殺す相手に自分の墓穴を掘らせるという趣向は、そのまんま『続・夕陽のガンマン』他のマカロニ・ウエスタンからいただいたアイディアだ。
若造がつきまとってくる流れも、老×若のバディものとしてのテイストも、まさに西部劇の王道だし、「殺された無法者のきょうだいが復讐のために乗り込んでくる」というのもいかにも西部劇らしい展開だ。
老警官との空き缶の射撃競争とか、古いショットガンへのこだわりとか、酒場での派手な撃ちあいとか、すべては本作の根幹が「西部劇」であることを逆照射している。
― ― ― ―
その他、雑感を箇条書きにて。
●本作の設定年代は1974年。若い殺し屋は、しきりにカルフォルニアに行きたいと夢を語るが、同様に「フロリダ」への夢を語りながら犬死にしていくラッツォが出てくるジョン・シュレシンジャーの『真夜中のカーボーイ』の公開は1969年。
明るい都会の輝きに憧れる底辺の若者というアイコンは、アメリカン・ニューシネマの時代のひとつの象徴だった。
●リーアム・ニーソンはアイルランド出身で、2022年にはダブリンを拠点に撮られた『マーロウ』で、フィリップ・マーロウ役を演じていた(レイモンド・チャンドラーもアイルランドで若き日を過ごしている)。老齢に入って、ますますアイルランド系としての意識が高まっているようだ。
●「IRAの闘士が、テロ活動中に誤って子供を殺してしまったせいで身を持ち崩す」といえば、なんといっても『死にゆく者への祈り』(87、マイク・ホッジズ監督、ジャック・ヒギンズ原作、主演ミッキー・ローク)を思い出す。
この映画、実は若き日のリーアム・ニーソンもIRAの同僚役で出ているのだ。友人であるロークの処刑を命じられながら、優しすぎて殺せず、逆に同行の女闘士に射殺される役どころで、やけに本作と近接するところが多い。
明らかに『死にゆく者への祈り』のことを意識して作られた映画のように思える。
●作中には、ドストエフスキーの『罪と罰』をアガサ・クリスティーからの文脈で紹介するくだりがあり、ラストシーンでも本書が粋な形で登場する。『罪と罰』を「ファイダニットものの倒叙ミステリー」と認識する考え方はミステリー界隈では昔からあって、本作のテーマとも強く呼応している。
「人が人を殺すというのはどういうことか」
この根源的な問いに、国家や、宗教や、正義や、家族といったのっぴきならないファクターが絡み、それぞれがそれぞれの事情を抱えて、煩悶する。
ゆるいけど、一応は真面目な映画でもあるのだ。
暗殺者VSテロリスト
リーアム・ニーソン主演
1970年代
長年ロバートから依頼され、殺人業を営むフィンバー
かなりの人を殺してきたが、隣人や友人の優しさにふれ、殺人業を辞めるつもりだ
だけれども罪のない少女が、村に潜伏するテロリストの1人に虐待されてるのを知ってしまったら、そいつを放っておけるわけが無い
フィンバーにはその暗殺の仕事をするようになった背景があるものの、人間らしい心の持ち主
一方、まだ若いが同じ暗殺の仕事をするケビンは、フィンバーとは真逆で暗殺を楽しんでるかのような異常さがある
そんなケビンに、思わぬ展開でそのテロリストの暗殺を手助けされ、そこからそれまでなかった仲間意識が芽生えだす
ここからがフィンバーVSテロリストのせめぎ合いに緊張が走る
フィンバーたちに弟を殺されたことを知った姉デランは、テロリストのリーダー的存在だったが、弟の仇をとる為に我を忘れて、執拗に復讐心を燃やす姿がなんとも恐ろしい
最後フィンバーが自身の身をもって終わらすかと思えたが、また予想外な展開が繰り広げられ、手に汗を握るクライマックスだった
プロフェッショナルではない
アマチュアに対抗して付けたような邦題は、やや安易な気がする。アイルランドの事は知らないが、爆弾テロがよく起こった時代は日本にもあった。無差別に行うのがテロ。暗殺業で生活していた老人が、少女や友人のためにテロリスト達を葬っていくのが謎。これから殺す人に、自分を埋める穴を掘らせるような人に、心があるとは思えない。おじいちゃんは頑張ったが、私は頑張れずに時々、寝落ちする。
あ゛-面白かった。でもさぁー.....┐(´ー`)┌
お金は 迷惑かけた隣人にも 少しあげようよ。
多分 受け取らないかもだけど その時は 車の窓から
まき散らそう。(^_^)/~~~
そーそー 母子家庭の女性にも 分けようよ。
親切なオジサンなんだからさ。
植木は 肥料が良いから しっかり育つよね。
そして 数百年後には 良い泥炭になるかもね。
テロリストは 女性以外は「三バカ大将」かと思ったわ。
(⌒▽⌒)アハハ!
激渋骨太なおっさん向け活劇。
こういう映画が見たかったんだ、と興奮したぞ。
昔なら、新宿ローヤルで出会った拾い物、みたいな感じ。
IRAの過激派武装一味が田舎町に逃げ込むと、そこにはプロの殺し屋が住んでいて…って、ジャック・ヒギンズの小説みたい。
引退したい老殺し屋、次世代を担いそうな若造ヒットマン、地元の親友保安官、ほのかな隣人おばちゃんとの交流、そしていたいけな子供と猫。IRAのラスボスがかなり強烈で凶悪なこともあり、流石のリーアム・ニーソンもピンチになるんじゃないか、と心配になったよ。
終盤の「酒場の決闘」もかっちょ良くてしびれた。
原題と邦題の違いよ
邦題「プロフェッショナル」から想像すると、リーアム・ニーソンがテロリストを無慈悲に倒していくイメージだったけど、そんなのではなく引退して街の一部として穏やかに過ごしていこうとする一人の年老いた男の物語だった。
自分も邦題に惹かれて観に行った一人ではあるが、映画としては味わい深く面白かっただけに、タイトルで釣るのはどうかな。
邦題のせいで損してる。
最初は、リーアム・ニーソン主演で「プロフェッショナル」というタイトルだけ聞いて、「また同じようなアクションものかあ。もう本人もどれがどれやらわからんくらい出てるやん。」という印象で、全く観るつもりなかったのですが、よくよく解説や口コミに目を通すと、1970年代のアイルランドが舞台とのこと。大のアイルランド好きの私としては「これは観なければ」と一転。最近では「コット はじまりの夏」「イニシェリン島の精霊」等が良作でした。
こんなタイトルやからすぐ上映終わってしまうに違いないと思い、他にいろいろ観たいのを済ませて、なんとか上映2週目に間に合いました。たまたま、「アマチュア」「ベテラン」と同じタイミングの上映になって少し話題になったのがラッキーだったのかも。
観た感想としては、まずやはり荒涼とした海岸線やゴツゴツした大自然の風景が美しくて、それだけで評価2割増し。あと、本当にアイルランドらしいメンツの俳優さんばかりなのが良かった。中でもロバート役のコルム・ミーニーは、「アイルランドが舞台の映画と言えば」って感じで本当によく出てくる印象があるし、この人昔からおじさんで見た目がずっと変わらない。
お話としては、全体的にこじんまりしていて、めちゃ極悪なヤツは出てこない。敵味方とも使う武器はクラシカルなものばかりで、アクションやドンパチ(古!)がメインではなく、人情ものの色合いが濃い。イーストウッドの弟子みたいな監督ということで「許されざる者」を彷彿とさせるストーリーで、好きなタイプの作品でした。ただ、最終的にフィンバーは死んで、ケビンが仇撃ちするような展開のほうが良かったのではないかという気もしました。
とにかく原題の「聖者と罪人の地で」が深みのあるタイトルで内容を的確に表現しており、何も考えずにつけた(ような)邦題が腹立たしい。もったいない。
よかったが少し惜しい
まずはじめに書きます。批評家などの高評価に違わず、アイルランドの美しい風景、建造物に囲まれた景勝豊かな、しかしひどく寂しく荒涼とした土地の中で繰り広げられる、年老いた殺し屋の最後の仕事を堪能できます!その意味で北方謙三原作の角川映画「友よ、静かに眠れ」を彷彿とさせる、正統なハードボイルド映画だったし、リーアム・ニーソンの魅力も発揮されてた。
残念だったのは、リーダー格の女性ケリー・コンドンは好演してるものの、せっかくIRAテロリスト設定なのに、ニーソン演じる主人公への復讐動機が弟の殺害ということ。また部下2人のキャラも弱すぎていただけない。あんなリーダーには従いたくないのではないかと思う。またクライマックスを強調するためか、中盤の牧歌的展開にも、少々中だるみを感じた。警官役のキアラン・ハインズは結構よかったが、勘の良さを発揮するのが遅すぎる。
監督ロバート・ロレンツが目指したろう、イーストウッド版「許されざる者」と比較して、演出力の違いはいなめなかった。同様のハードボイルドとしては「友よ、静かに眠れ」のが優れている。
とはいえ、はじめに述べたように、美しいアイルランドの風景(「イニシェリン島の精霊」を思い出す)の中で描かれる最後の仕事に臨む殺し屋の哀愁は素晴らしく、久々に骨太のハードボイルドを観た気はした。最後、不覚にも目に涙が浮かんでしまった。
また、初めは人殺しを愉しむサイコな若者に見えたが次第に心を開き、ニーソンの良き相棒となる殺し屋仲間を演じたジャック・グリーソンはとても魅力的でした。
許されざる者
1972年の血の金曜日事件が起きた頃のアイルランド。そのドニゴール州グレンコルムキルを舞台にした、あたかもイーストウッド主演の西部劇「許されざる者」を彷彿させる内容。
かつての第二次大戦にアイルランド人ながらも従軍し、多くの敵兵の命を殺めてきたフィンバーは終戦後妻を失い、孤独な中なおも暗殺者として多くの人の命を殺めてきた。そんな彼も老齢の域に達し引退を決意する。
殺しから足を洗った彼だが、顔なじみの少女が男から虐待を受けていることを知り、彼は自分の「正義」のために男を抹殺する。しかしその男はベルファストで血の金曜日事件を起こしたIRA暫定派のリーダー、デランの弟だった。
弟を殺された彼女はフィンバーをつけ狙う。テロ行為を続ける彼らにとって市民をも巻き込むテロ行為はアイルランドの真の統一を目指すための戦いでありそれは彼らにとっての「正義」だった。そして愛する弟を殺されたデランにとって復讐のための戦いもまた彼女自身の「正義」であった。
殺しに慣れ切っていたフィンバーにとって邪魔な人間を葬り去るのはたやすかった。彼はそれだけ殺しに慣れていてその方法があらゆる難問を解決するのに手っ取り早い方法だった。
初めから法的手段に頼っていれば村を巻き込んでの危機を回避できたはずだが彼には安易な殺しという方法しか思いつかなかったのだ。それが結局は彼の愛する人々を危険にさらすこととなってしまう。自分が犯してきた罪、その罪に浸りきった故に繰り返された過ち。彼はそんな過ちに満ちた人生に終止符を打つために最後の戦いへと向かう。
共に自分が「正義」と信じて犯してきた「罪」。その罪をまるであがなうかのように対決の舞台に臨む両者。その約束の地であるバーで両者が相まみえた時戦いの火ぶたはきって落とされた。
まるでその様はかつて悪事の限りを尽くしてきたイーストウッド演じる無法者のガンマンとたとえ秩序を守るためとはいえ己の正義のために暴君のようなふるまいをするジーン・ハックマン演じる保安官との対決を思わせる。
村で唯一のバーにはフィンバーの顔なじみが揃っていた。そこには友人でもある警察官のビンセントの姿も。
戦いの中でフィンバーはビンセントにその正体を知られてしまう。しかしこの戦いはこのグレンコルムキルでの生活を捨て去る覚悟で臨んだ戦いでありもはや未練はなかった。
銃弾を受け手負いとなったデランがたどり着いたのは懺悔の地である聖コロンバ教会を思わせる建物。そこでフィンバーはまるで懺悔を受け入れるかのように先に逝く彼女を最後まで看取るのだった。
そして彼もまた贖罪のために安住の地であったグレンコラムキルの地を自ら去るのだった。まるで「罪と罰」の主人公ラスコーリニコフのように。
北アイルランド出身者であり、かつてIRA(アイルランド共和軍)のリーダであるマイケル・コリンズを演じたリーアム・ニーソンが今回はそのIRAから分派した過激派組織IRA暫定派を葬り去るという内容はまるで長く続いたアイルランド独立問題に自ら終止符を打つかのような内容でただの西部劇風エンタメ作品とは違う奥深さを感じさせた。
全33件中、1~20件目を表示