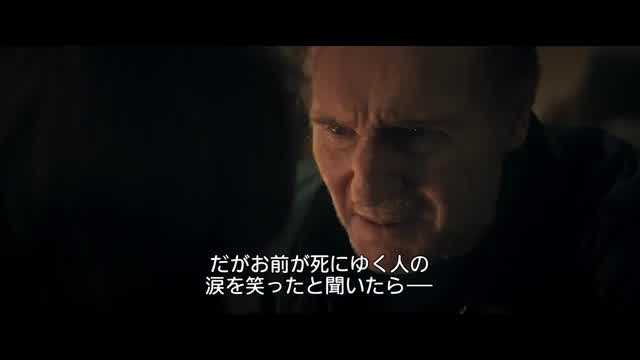「誰一人プロらしいプロの登場しない、田舎のプロ気どりが織りなすほんわか老人アクション。」プロフェッショナル じゃいさんの映画レビュー(感想・評価)
誰一人プロらしいプロの登場しない、田舎のプロ気どりが織りなすほんわか老人アクション。
『アマチュア』に引き続いて、『プロフェッショナル』を視聴。
セット企画として、その「対比」を愉しむ予定だったのだが……
やべえ、こいつら、
全然「プロフェッショナル」
じゃねーじゃねーか(笑)。
むしろ、のんびりした田舎の村を舞台に、
田舎ののんびりした引退した殺し屋が、
のんびりした頭の弱い相棒と共闘しつつ、
のんびりした頭の弱いテロリストたちと
さんざんお互いにミスを犯しまくって、
お互いにスカタンをかまし合いながら、
なんとなく「老人ヒーロー属性」だけで、
リーアム・ニーソンがラスト・スタンディング!
そういった、田舎のラムネ水みたいな映画だ……。
まさに「タイトルに偽りあり」。
あと、ハードボイルド・アクションって宣伝に書いてあるけど、果たしてそうなのか??
どっちかというと、真顔でやってるドメスティック・アクション・コメディにしか思えないが……。
リーアム・ニーソンといえば、いまや「老人アクションの第一人者」(笑)であり、『96時間』以降、もはやどの映画がどれだったかすらよくわからなくなるほど、同工異曲の巻き込まれ型アクション・スリラーに主演し続けている。
そんな「市井の一般人に見えて実は凄腕のプロフェッショナル」というリーアム・ニーソンらしい役回りから、今回の主人公はかなり逸脱しているといってよい。
いや、「一見、いつものリーアム・ニーソンに見せかけておいて、実は普段の設定とは一味違う」という「ギャップ」自体を愉しむ映画といったほうがいいかもしれない。
いちいちこの映画の登場人物の行動に、整合性やリアリティを求めても仕方がない。
むしろ、やっていることのおおよそ全てが配慮を欠き、判断力を欠き、理に反している。
そういった類の、「あらかじめゆるく作られた」「ゆるいのが魅力の」映画。それが本作だ。
結論。
タイトルとして、邦題の「プロフェッショナル」ほどにふさわしくないものもない!
(原題の『In the Land of Saints and Sinners』(聖者と罪びとの地で)は、無駄にかっこいいだけだけど、少なくとも内容を外してはいない。)
あるいは……、これって配給会社の渾身のギャグなのか?
「なんだよ、出てくる連中、どいつもこいつもいったい何考えてるんだ?? よし、それならこっちは敢えて〈プロフェッショナル〉ってつけてやれ!!」みたいな。
強いて言えば、「プロフェッショナル(気どりw)」といったところか。
― ― ― ―
出だしから、いきなりテロリスト4人組が標的の爆殺に子供たちを巻き込み、しかも相手に警告を発したせいで、衆目に顔をさらしてお尋ね者になるという大きな不始末を犯す。彼らはテロリストとしては三流で、状況判断がとことん甘く、感情の制御もおぼつかない。
4人組のうちひとりは、逃亡中のテロリストなのに、毎日入り江での水泳にうつつを抜かし、親族の少女に無意味な暴行を加え、会ったばかりの男の車に乗せてやると言われてほいほい乗って、そのまま人生の最期を迎える。残された3バカトリオも、ラストに至るまでとことん無能で、とことん頭の悪そうな会話を繰り返す。
IRAの重信房子か永田洋子かといったコワモテの女性闘士は、最終的にアイルランド解放の大義とかそっちのけで、「私怨」の復讐戦へと猛進することに。残る2人は「やっておしまい!」と叫び続ける女性闘士にあごで使われて、さながらIRAのボヤッキーとトンズラーである(笑)。
対する主人公で老練な殺し屋のフィンバー・マーフィー(リーアム・ニーソン)も、冒頭の「殺し」こそルール通りに進めて卒なくこなしてみせるが、そのあとからは、やっていること全体がほぼめちゃくちゃだ。
●馴染みの女性の家で、子供があざだらけで叔父を嫌っているのを見ただけで、勝手に「チャイルド・アビューズ」(児童虐待)だと決めつける。
●被害者にも容疑者にもちゃんとした確認すらとらず、証拠調べもしないで、いきなり次の「殺し」のターゲットにするよう、元締めに要求する。(たとえば日本の『必殺』シリーズでは、殺し屋が依頼だけで動くことは絶対にないし、自分たちの目で悪の証拠を確認したうえで初めて仕置きする。逆にどれだけ義憤に駆られても、依頼者のいない(=金の発生しない)仕置きは「ただの人殺し」として徹底的に忌避される。これが正しい「殺し屋道」というものだ。)
●元締めに断られたら(そりゃ当然だ)、独断で相手を殺すことを宣言し、勝手に行動に移す(まさにルール無用のただの殺人鬼である)。
●叔父のテロリストが少女に渡していた銃弾を、元締めの家に置きっぱなしにして帰って、のちに元締めが姉のテロリストに射殺される、直接的な原因を生じさせる。
●どこに人の目があるかわからない海岸べりの道路で、顔出しのまま公然と相手を襲って、白昼堂々相手を昏倒させ、そのまま誘拐して連れ出す。
●トランクを開けた瞬間、閉じ込めていた若造の反撃を受け、ナイフで刺されて手負いになるばかりでなく、流血してあたりじゅうにDNAの痕跡を残すことに。その後もパニックに近い状況に陥り、相手には逃亡されるわ、弾を装填し損ねるわ、銃は空撃ちするわ、挙句に若い殺し屋仲間に相手を仕留めてもらって、助けられるはめに。
●若い殺し屋に助けてもらったくせに、偉そうにその若者に死体の穴を掘らせ、自分はふんぞり返って説教を垂れている。殺しに関する感傷的な思想の押しつけも、聞いているだけで痛々しいばかりだ。よほど、ドライな価値観で動いている若い殺し屋のほうが、殺し屋としてまともだと思う(こいつもバカはバカだけど)。
●テロリストたちに家を占拠されているのに気づき、そこに戻らないことにした選択自体は正しいにせよ、ヤサが割れているのに、テロリストが帰った瞬間に下まで降りて、隣人のおばちゃんを助けたり、爆弾が仕掛けられているかもしれない母屋に入って猫を連れ出したりしている。全編を通じて、行動に警戒心が毛ほども感じられない。
●家でテロリストに猫を見られているはずなのに、それをわざわざ少女のところに持っていって「飼ってくれ」と強要する。そもそも動物を譲り渡すのはよほど気ごころの知れた相手以外は迷惑な話だし、それが成獣だとなおさらだ。しかも、この猫を渡すことで、少女とフィンバーの強い関係性がテロリスト叔母さんにバレて、「依頼人が娘、もしくは母親と取られる」可能性を一切考慮していない。
●ノープランで、テロリストを観にグラウンドまで行って、その場でいきなり遭遇する(トイレでは容易に後ろを取られていて、ここで速攻で殺されててもちっともおかしくない)。さらには、どれだけ被害が広がるか全くわからないのに、安易にパブでの夜の打ち合わせに応じている。
●待ち合わせ場所のパブでは、女テロリストの義妹=少女の母親が勤めている。積極的にテロリストとの対決に親族(およびその娘)を巻き込んでいく理由が皆目わからない。だいたい、パブで女テロリストと待ち合わせた理由が「弟殺しの依頼人を教える」というものなのに、虐待された少女の母親がいる場所にわざわざ招き入れてどうしようというのか。「この女があたしの弟を売ったのね」って話になりかねないと思うのだが。
●若い殺し屋は、100%銃で武装していることがわかっている女テロリストに、イチャイチャしながら近づいていって、案の定いきなり撃たれて「ファッキン、いきなり撃ちやがった!!」とか騒いでる。およそ知恵の遅れ方が尋常ではない。
●わざわざ混雑しているパブで待ち合わせたうえ、そこで安易に銃撃戦を展開したせいで、結果的に、多数の村人の負傷者と室内の被害を生み出すことに。戦闘のプロフェッショナルといいながら、お互いいくらやってもとどめをさせず、弾はなかなか当たらず、お互い即死させられないまま、ラストシーンは教会まで持ち越される。
……とまあ、だらだらと気になった点を書き連ねてきたが、これだけ「すっとぼけた」部分が連鎖するのを見れば、賢明な皆さんならお分かりだろう。
要するに、これは「製作者が不用意で頭が弱くて注意力が散漫だから、こういう穴の多い展開になっている」という次元の話ではない。
明らかに、製作者は、主人公や、仲間や、テロリストや、街の住人も含めて、出てくる登場人物全員が「アホ」である、という大前提で、このドメスティックなドンパチものを作っている。そう、これらはすべて「わざと仕組まれているトンチキ」なのだ。
最近観た映画でいえば、去年K’sシネマの奇想天外映画祭で観た、オーストラリア産の珍作『デス・ゲーム/ジェシカの逆襲』に近いテイストかもしれない。
くっそド田舎で、掘っ立て小屋で暮らす頭の弱い美少女が、頭の弱い密猟者3人組にさんざん追い回されて、ついに逆襲に転じて3人を血祭にあげる。
お互い敵も味方も、やってることがゆるんゆるんで、攻めるも守るも「隙」しかないような妙ちきりんな映画。でもまあ、娯楽作品として割り切れば、頭を空っぽにしてのんびり愉しめる。
今回の『プロフェッショナル』も、まさにそういう映画である。
で、そういう映画だと納得して観るぶんには、それなりに楽しい。
僕は決して、この映画が嫌いではない(笑)。
― ― ― ―
なお、この映画における主人公フィンバーの立ち位置は、明らかに「西部劇における老ガンマン」を意識したものだ。
メインテーマの楽器がハーモニカというのがまず、いかにもマカロニ調だし、これから殺す相手に自分の墓穴を掘らせるという趣向は、そのまんま『続・夕陽のガンマン』他のマカロニ・ウエスタンからいただいたアイディアだ。
若造がつきまとってくる流れも、老×若のバディものとしてのテイストも、まさに西部劇の王道だし、「殺された無法者のきょうだいが復讐のために乗り込んでくる」というのもいかにも西部劇らしい展開だ。
老警官との空き缶の射撃競争とか、古いショットガンへのこだわりとか、酒場での派手な撃ちあいとか、すべては本作の根幹が「西部劇」であることを逆照射している。
― ― ― ―
その他、雑感を箇条書きにて。
●本作の設定年代は1974年。若い殺し屋は、しきりにカルフォルニアに行きたいと夢を語るが、同様に「フロリダ」への夢を語りながら犬死にしていくラッツォが出てくるジョン・シュレシンジャーの『真夜中のカーボーイ』の公開は1969年。
明るい都会の輝きに憧れる底辺の若者というアイコンは、アメリカン・ニューシネマの時代のひとつの象徴だった。
●リーアム・ニーソンはアイルランド出身で、2022年にはダブリンを拠点に撮られた『マーロウ』で、フィリップ・マーロウ役を演じていた(レイモンド・チャンドラーもアイルランドで若き日を過ごしている)。老齢に入って、ますますアイルランド系としての意識が高まっているようだ。
●「IRAの闘士が、テロ活動中に誤って子供を殺してしまったせいで身を持ち崩す」といえば、なんといっても『死にゆく者への祈り』(87、マイク・ホッジズ監督、ジャック・ヒギンズ原作、主演ミッキー・ローク)を思い出す。
この映画、実は若き日のリーアム・ニーソンもIRAの同僚役で出ているのだ。友人であるロークの処刑を命じられながら、優しすぎて殺せず、逆に同行の女闘士に射殺される役どころで、やけに本作と近接するところが多い。
明らかに『死にゆく者への祈り』のことを意識して作られた映画のように思える。
●作中には、ドストエフスキーの『罪と罰』をアガサ・クリスティーからの文脈で紹介するくだりがあり、ラストシーンでも本書が粋な形で登場する。『罪と罰』を「ファイダニットものの倒叙ミステリー」と認識する考え方はミステリー界隈では昔からあって、本作のテーマとも強く呼応している。
「人が人を殺すというのはどういうことか」
この根源的な問いに、国家や、宗教や、正義や、家族といったのっぴきならないファクターが絡み、それぞれがそれぞれの事情を抱えて、煩悶する。
ゆるいけど、一応は真面目な映画でもあるのだ。