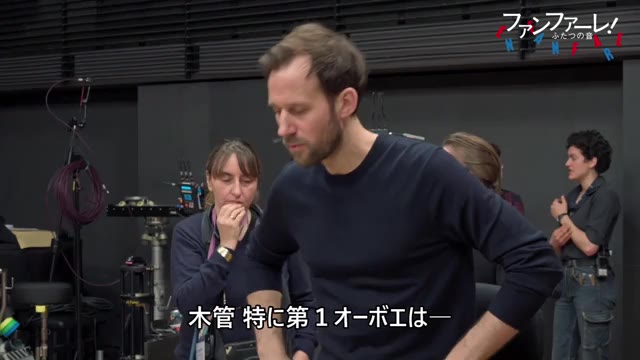ファンファーレ!ふたつの音のレビュー・感想・評価
全96件中、1~20件目を表示
音楽で語り合う兄弟の絆
こういう展開かな?と予想していた展開に全くならず、2回ぐらい予想外な展開になり、最後は思わず条件反射で「ブラボー!」って言って拍手したくなる衝動を必死に抑えた。
まさかこんなラストが待ち受けているなんて思いもせず、涙もろい私はあんなことされたら秒で泣いたよね。
生き別れになった兄弟が、兄の病気をきっかけに再会し、そこから始まる交流の描き方が本当に素晴らしい。
スマートな兄と無骨な弟。裕福な兄と貧しい弟。育った環境は真逆で、複雑な思いもあるけれど、そんなことを越えて音楽で絆を深めていく。
ぎこちない会話も、音楽になったら饒舌になり、硬い表情も柔らかくなる。音楽の力ってすごいなと思わせられる。
現実はうまくいかないことが多くて、急に不幸は降りてきたりもするけれど、それでも諦めずに助け合って、支え合って、何度だって立ち上がる。
芸術を愛するフランスだからこそ、芸術のもつ力を信じた作品のように感じた。
現在公開中の「8番出口」で不気味さの演出として使われている「ボレロ」が、作品違うだけでこうも違った曲に聞こえることにも驚き。
「ボレロ」は、孤独な踊り子が周囲を巻き込みながら舞い踊る様子を描いた曲。そんな「ボレロ」に合わせて、ひとりじゃないよと伝えるかのような圧巻のラストを是非映画館で体験してほしい。
ひとつ苦言を言うなら、エンドロールどうした?
こんなに素敵な音楽を聞かせてくれたのに、急にぶつ切り音楽で終わってしまって戸惑った。
幅広い観客を魅了する語り口と重厚さのバランスが秀逸
幼い頃に生き別れた兄と弟。そんな二人の思いがけない邂逅を描いたこの物語は、興味深いことにオーケストラとブラスバンド、クラシックとポピュラー音楽、さらには中央と地方、経済的格差など、様々な壁のようなものを融解させながら、誰しもを惹き込む語り口にて展開していく。私はクールコル監督がかつて脚本を務めた『君を想って海をゆく』(09)を愛してやまない一人だが、主人公の専門分野がこれまで向き合ってこなかった領域と重なり合い、そこで新たな自己発見が生じるという流れは本作にも通底しているように思えた。新旧様々な楽曲レパートリーが目と耳を充実した気持ちに浸らせる中、後半は地方経済や産業にもヒューマニズムあふれる視線が注がれる。そのタッチは懐かしき英国の名作『ブラス!』をも彷彿とさせるかのよう。音楽というものを一つの糸口として、やがて社会全般や労働者の尊厳をも包摂するドラマへ発展していく流れを大いに堪能した。
ラストで納得 邦題の意味
いや〜 久しぶりのフランス映画
実に良かった。
一年と短い時間だったけど、フランスにいたこともあり、やはり日常でもフランス語をたまに耳にすると懐かしく、嬉しくもなったりする。
そしてとても連休初日、旅行イベントのスタートととして、気持ち良いスタートが切れたのは、この映画がとても良かったからであるのは間違いない。
もちろんこのレビューの冒頭は、個人的な備忘録。
ボレロがボレロである所以。
映画「8番出口」でも使われていましたが、めっちゃ好きって曲ではないけど、やはり人を魅了しますね。
そう 世界的なヒット曲ですね〜。良い。
そしてマエストロって、カッコ良いですね〜。
プロが見たらわかりませんが、主人公の指揮するシーンは本当にカッコよかったなぁ。
心地良い余韻で終われる良作。
映画館で見ることが出来て良かったです。
今を愛し、誰かを愛するフランス節
兄の病気をきっかけに再会した、お互い存在すら知らなかった生き別れの兄弟のぎこちない関係を、共通の関心である音楽が埋めていく物語。
個人的にフランス映画という括りではミニシアター系の捻った作品を観る機会が続いていたせいで、最初はこの作品のノリに戸惑ってしまった。エピソードのデティールが疎かだったり、湿っぽい部類の感情に踏み込んだ次のシーンではわだかまりが解消していたり、物語の起伏を大きくするために描写が雑になる朝ドラ的なノリである。
フランスのヒューマンドラマ映画と言えばこうだったな、というのを思い出した作品だった。悲しみも怒りも尽きない生活ではあるけれど、隣人を大事にし、暮らしの中に楽しみを見出し、恋をして、人生を豊かにしようとするタフな明るさを持った普通の人たる登場人物たちが眩しい世界観である。ティボとジミーの物語であると同時に、普通の人であるジミーと仲間たちのささやかだが眩しい暮らしを、ティボの目で見守る物語でもあった。
ティボがジミーを見つめる眼差しの変化、ラストでジミーがティボを見つめる視線の力強さが印象的な作品だった。
身構えて観てしまった初見の記憶を消して観なおしたい。
難病物語もフランス映画になると・・
白血病を発症した高名な指揮者が骨髄移植のドナーを探していたところ、自分には生き別れになった弟が居た事を知るというお話です。
となると、迫り来る時間に追われながらその弟を懸命に探して、最後には移植が成功して感涙のラストになるのかと思いきや、物語は意外な展開を見せます。骨髄移植はあっさりと成功して、お話はそこから始まるのです。
この様に単なる感動の難病物語にはせず、現実の厳しさ酷薄さも描き切るのはフランス映画ならではの持ち味なのでしょうか。でも、その辛さを超える終盤の展開には、「そりゃあもう反則だろぉ、そんなの誰でもウルウル来てしまうよぉ」と結局、客席でハンカチを取り出してしまいました。やられたな。
フランスの音楽愛。兄弟が響かせる悲しきハーモニー。
世界的指揮者である兄。あるリハーサルで特定の楽器にアドバイスを送る。するとたちまちその奏者の音色が変わる。そんな瞬間を見事に映像化させたこの作品は、とても音楽を大切に扱っている。音も素晴らしい。
そんな兄が突然、白血病の宣告を受ける。必要なのは骨髄移植。妹は快諾してくれたが、思わぬ結果が・・・。実はほんとうの兄弟ではない、ことが判明する。ドナーを探すなか、遠く離れた地方に、実の弟がいることが分かった。彼は鉱山の音楽隊でトロンボーンを吹いていた。彼には絶対音感があることを、兄は発見する。
弟と楽団を取り巻く環境は厳しく。音楽を続けることが難しくなる。兄が手を差し伸べる。反発する弟。そんな中、一度は回復したかのように思えた兄の症状が悪化し始める。
フランス映画ですから、ハッピーエンドではありません。そして、B級作品のような雑なカット割りも気になるところです。しかし、楽器一つ一つの音が美しく、音楽愛にあふれた作品と思いました。感動のラストシーンでは誰もが知っているあの名曲が流れます。涙なしでは見れません。
音楽好きにはお薦めの感動作品です。
物語最後のボレロに向かって、地味にリズムを刻んでいく…
「ボレロ」は、2種類の旋律を繰り返すという斬新なバレエ曲。
この映画は、普通ならドラマにするエピソードを大胆に省いているところが斬新だ。
例えば、主人公が本当の家族を探す過程とか、突然現れた兄のドナーとなることを最初は拒絶した弟が思いなおす過程とか、ヘソを曲げて演奏会への参加を拒絶した弟が楽団に戻る過程などが省かれている。離ればなれの家族を見つけなければ物語にならないし、兄弟が仲違いしたままではいい話にならないのだから、わかりきった結果への過程で共感を得ようとはしていない感じだ。
絶対音感は幼少期に訓練を受けなければ、身につけることが難しいとされている。一流オーケストラの演奏家たちでさえ、演奏前の楽器のチューニングでは基準音をもらって合わせていく(相対音感)。訓練もなく生まれつき絶対音感をもつ人こそ、いわゆる天才と呼ばれる人たちで、10万人に1人とも20万人に1人とも言われている。
世界的な指揮者であり作曲家のティボ(バンジャマン・ラヴェルネ)が、生き別れだった弟ジミー(ピエール・ロダン)に絶対音感を見つけると、弟がもし自分と同じ境遇で育っていたら自分を凌ぐ音楽家になっていたかもしれないと思ったのは当然だ。
ジミーの音楽的才能を目覚めさせたいとティボは考えるのだが、『グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち』(’97)のように埋もれていた天才が指導者によって開花して巣立つ物語なのかと思えば、この映画はその期待も裏切ってくれる。
かつては炭鉱で栄えていたが、現在は地場産業も衰退した北フランスの貧しい町に暮らす人々。
別世界に生きてきたティボが思わぬ事で彼らと出会い、炭鉱町伝統のアマチュア吹奏楽団の団員のほとんどが努める工場の閉鎖と労働争議などの実情を知ることになる。
映画に登場する100年を超える伝統の楽団〝ワランクール炭鉱楽団〟のメンバーを演じているほとんどが実際の炭鉱労働者楽団の人々だというから驚く。演奏シーンに流れる音楽も彼らが演奏しているらしい。
かつての炭鉱町が、その栄華は今は昔となっているのは世界共通だろう。
産業が廃れても、伝統のコンテストが華々しく開催されていることに主催者たちの努力を感じる。
30数年経って始めて兄弟の存在を知った二人は、お互いのことをよく知らなくてもいつの間にか心が通い始める。これが血縁というものなのかは分からないが、この映画は兄弟の絆、その兄弟がいなかったら生まれるはずがなかった世界的指揮者と貧しい町の人々との絆を描いて、胸を打つ物語だ。
この、ユーモアと温かみのある物語は、しかしある面でシビアでもある。
絶対音感を持つジミーは、ティボによって夢を抱くようになるものの世の中は甘くない。
ティボは、弟がドナーになってくれたのに、白血病は完治していなかった。
恐らく、あの町の工場の再開も難しいだろう。
それぞれの現実は現実のままなのだが、それでも夢のようなボレロの大合唱・大合奏が、ひと時の幸せを登場人物たちに、我々観客に、もたらしてくれるのだった。
全ての音楽好きに、捧ぐ
最後絶望しかないけど
離れていても音楽がつないでいた心。終盤までの抑えた展開が丁寧でリアルでいい。それがラストでは率直に感動する。
兄貴に褒められ 自己評価の高い弟
フランスのオーケストラ映画は良いね
オーケストラものは登場人物も多いから、エピソードには事欠かない。本業が他にあるアマチュア楽団ならなおのこと。
しかも閉鎖危機にある工場の楽団で、生き別れの兄弟で骨髄移植とかてんこ盛り。
育った環境は違っても、揃って音楽の才能があるのは、少々出来すぎではあるのだけど、楽しそうな2人にほっこりする。
ちょっとした兄弟のすれ違いがあり、お決まりと言ってもいい、ライバルとのぶち壊しトラブルを経て、工場でのコンサートが企画されるワケだけど、去年『ボレロ 永遠の旋律』を観ていたから、工場の音から作曲されたことか予習できていて良かった。
工場がやんごとなき状況に陥って、どうなることかと思ったけど、まさかそんな展開とは。
やっぱりオーケストラものは、音楽で感動させる力があるから好きだ。
タイトルの『ふたつの音』がそういう意味だったのかと、胸が熱くなった。
9月19日初日だったから、上映終了にならないか不安だったけど、間に合ってよかった。
たしかにファンファーレ!
フィナーレでは?えっ!大粒の○○○が自然に!
100万分の一
全96件中、1~20件目を表示