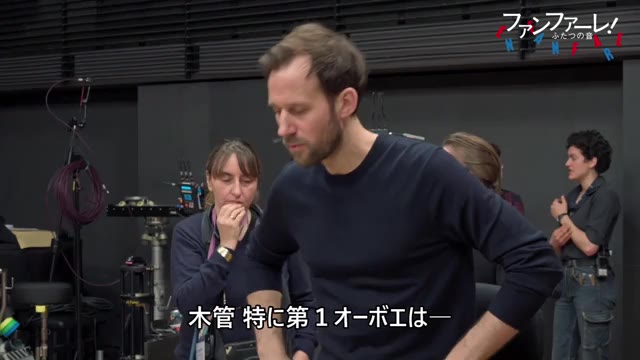「物語最後のボレロに向かって、地味にリズムを刻んでいく…」ファンファーレ!ふたつの音 kazzさんの映画レビュー(感想・評価)
物語最後のボレロに向かって、地味にリズムを刻んでいく…
「ボレロ」は、2種類の旋律を繰り返すという斬新なバレエ曲。
この映画は、普通ならドラマにするエピソードを大胆に省いているところが斬新だ。
例えば、主人公が本当の家族を探す過程とか、突然現れた兄のドナーとなることを最初は拒絶した弟が思いなおす過程とか、ヘソを曲げて演奏会への参加を拒絶した弟が楽団に戻る過程などが省かれている。離ればなれの家族を見つけなければ物語にならないし、兄弟が仲違いしたままではいい話にならないのだから、わかりきった結果への過程で共感を得ようとはしていない感じだ。
絶対音感は幼少期に訓練を受けなければ、身につけることが難しいとされている。一流オーケストラの演奏家たちでさえ、演奏前の楽器のチューニングでは基準音をもらって合わせていく(相対音感)。訓練もなく生まれつき絶対音感をもつ人こそ、いわゆる天才と呼ばれる人たちで、10万人に1人とも20万人に1人とも言われている。
世界的な指揮者であり作曲家のティボ(バンジャマン・ラヴェルネ)が、生き別れだった弟ジミー(ピエール・ロダン)に絶対音感を見つけると、弟がもし自分と同じ境遇で育っていたら自分を凌ぐ音楽家になっていたかもしれないと思ったのは当然だ。
ジミーの音楽的才能を目覚めさせたいとティボは考えるのだが、『グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち』(’97)のように埋もれていた天才が指導者によって開花して巣立つ物語なのかと思えば、この映画はその期待も裏切ってくれる。
かつては炭鉱で栄えていたが、現在は地場産業も衰退した北フランスの貧しい町に暮らす人々。
別世界に生きてきたティボが思わぬ事で彼らと出会い、炭鉱町伝統のアマチュア吹奏楽団の団員のほとんどが努める工場の閉鎖と労働争議などの実情を知ることになる。
映画に登場する100年を超える伝統の楽団〝ワランクール炭鉱楽団〟のメンバーを演じているほとんどが実際の炭鉱労働者楽団の人々だというから驚く。演奏シーンに流れる音楽も彼らが演奏しているらしい。
かつての炭鉱町が、その栄華は今は昔となっているのは世界共通だろう。
産業が廃れても、伝統のコンテストが華々しく開催されていることに主催者たちの努力を感じる。
30数年経って始めて兄弟の存在を知った二人は、お互いのことをよく知らなくてもいつの間にか心が通い始める。これが血縁というものなのかは分からないが、この映画は兄弟の絆、その兄弟がいなかったら生まれるはずがなかった世界的指揮者と貧しい町の人々との絆を描いて、胸を打つ物語だ。
この、ユーモアと温かみのある物語は、しかしある面でシビアでもある。
絶対音感を持つジミーは、ティボによって夢を抱くようになるものの世の中は甘くない。
ティボは、弟がドナーになってくれたのに、白血病は完治していなかった。
恐らく、あの町の工場の再開も難しいだろう。
それぞれの現実は現実のままなのだが、それでも夢のようなボレロの大合唱・大合奏が、ひと時の幸せを登場人物たちに、我々観客に、もたらしてくれるのだった。