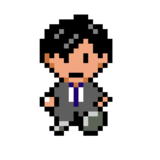ボサノヴァ 撃たれたピアニストのレビュー・感想・評価
全22件中、1~20件目を表示
🇧🇷ブラジル好き、ジャズ、ボサノヴァ好きには宝物のような映画
50年代のリオデジャネイロのカフェで突発的に発生し、世界のミュージックシーンに影響を与えたボサノヴァの創成期に活躍したジャズピアニスト、テノーリオがヴィニシウス(イパネマの娘の作詞家)のアルゼンチンツアーのピアニストとして帯同したある夜、行方不明になったという史実を、ニューヨーカーの音楽ライターが当時の関係者を取材して謎を追いかけるというお話。
音楽映画として完成度が高いため、歴史ミステリーとしては主題がもやもやしてもいいかなと思ってましたが、きっちり行方不明の原因や、なぜこのような悲劇が起こったかという背景まで描いています。(CIA=アメリカの通常営業。反共産のための軍事政権支援のため暗躍してた。ウクライナでマイダン革命起こしたのと同じことやってたということ)
実在したミュージシャンの話なので、当たり前ですがボサノヴァはもちろん、ジャズのレジェンドミュージシャンが関係者としてでまくります。
が!
これをアニメーションで見せてるところが、もう凄すぎてエンドロールで、え?って声がでるほど混乱し、思わずパンフレット購入。
なるほどガワはフィクション、中身はドキュメンタリー、そこをシームレスでみせるためのアニメなんですね。
よくある実写ドキュメンタリーだとインタビューの間の昔の映像とかは、あくまでイメージ的に挿入されたりしますが、ここを全てアニメでみせることで境界がなくなり話のリアリティが損なわれないという。こんな映像体験も初めてで驚愕、感動です。
ちょこっとだけ言うと、ジョビンがアニメでシェガジサウダージ(想いこがれて=ノーモアブルース)演奏したり、エラフィッツジェラルドがリオデジャネイロでボサノヴァと出会ってライブに飛び入りするシーンは最高でした。
ボサノバが好きな人で、歴史的背景も勉強しとかないと。。
ブラジルのボサノヴァにまつわる事件のドキュメンタリー映画です。
ボサノバというと出てくるのが小野リサぐらいの私。
今まで、まともにボサノバを聞いた事は無かった。
一人のピアニストが死んだ真相が取材形式で解き明かされる。
その過程でボサノバの歴史と、事件の原因となった当時の政治背景が語られていく。
そのドキュメンタリーをアニメ形式で描いている映画。
映像は、アニメというのか動きの少ない漫画というか、動きの少ないアニメ。。
この動きの感じは、絵のタッチは違うけど、昔見たハートカクテルみたいな動きでした。
まずは、まったく興味の無いボサノヴァの話が続くので、見ていてツラかった。
最初に思ったのは、なぜ実写じゃなく漫画にしたのだろういう点。
かなりの数の人のインタビューシーンが出てきていたので、全員の了承が得られなかったんだろうとは思うけど。。
次に、もっと演奏シーンを長尺で見たかった。
細切れの演奏シーンばかり。。
ボサノヴァを堪能できるようにして欲しかったかな。
後半にピアニストが殺された原因が究明されていくところは、少しだけ見応えがあった。
でも全体的に見ていてツラい作品でした。
後で知ったのだけど、主人公の音楽ジャーナリストの声がジェフ・ゴールドブラムだった。
事前に歴史的背景を勉強しておくか、ボサノバが好きな人が見るべき映画ですね。
ブラジルのサンバジャズと、アルゼンチン軍事政権について学べる、音楽あふれる恐怖の映画
色彩豊かな映像と音楽は楽しいのだが。。
彼の演奏が某有名通販サイトでダウンロードできるのが嬉しい
演奏シーンが多く、その殆どがオリジナル音源に動画を同期させているので、実写化するのは困難だろうし、エラ・フィッツジェラルドみたいに歌ったりジョアン・ジルベルトみたいに弾く演技はほば不可能じゃないだろうか。「ボヘミアン・ラプソディ」ではそういうところを巧く合わせていたように見えたけど、それでもイタいところはあったし。
なので、アニメ作品にしたのは賢明な選択だと思う。
強奏してもテンポが速まってもほんのり漂う哀愁はやはり独特で、もっと多くの録音を残して欲しかった。
それは兎も角、ラテンアメリカ諸国で一時期苛烈な独裁政治が罷り通っていたのはおぼろげながら知ってはいたが、これ程までだったとは。多くの人命だけでなく固有の文化すら奪って、一体何を目指していたのだろう?
非業の死をとげた伝説のジャズ•ピアニスト テノーリオ•ジュニオル その音楽、その人となり、その最期を関係者の証言によって綴る アニメーション•ドキュメンタリー
実はテノーリオ•ジュニオルて誰? の状態で本篇を見ました。見終わってすぐしたことは彼の唯一のリーダー•アルバム “Embalo”(1964年リリース)を音楽サイトで探し出して聴くことでした。本篇鑑賞中に感じていた既視感ならぬ「既聴感」はホンモノだったようで、これ絶対にどこかで聴いたことがある、となりました。昔よく聴いてたジャズのコンピレーション•アルバムからか、それともラジオからか、そんなところでしょう。
そして、Wiki を始めとするネット検索。どれどれ、テノーリオ•ジュニオル 1941年7月4日〜1976年3月27日 とな。ビートルズでいうとジョンが1940年生まれ、ポールが1942年生まれなので、彼の生年はふたりの生年の間の年になります。ジョンが暗殺されて大騒ぎになったのが1980年ですので、彼はジョンに先行すること4年、ひっそりとこの世を去っていたことになります。
ポップス寄りのボサノヴァをやってたセルジオ•メンデス(2024年83歳にて病没)は彼と同い年なんですね。本篇に出てきた名前をあげてゆくとーー エラ•フィッツジェラルドは彼より24歳年上で1996年に79歳没。チェット•ベイカーは12歳年上で1988年58歳でアムステルダムのホテルの窓から謎の転落死。彼のあこがれのピアニストだったビル•エヴァンスは12歳年上で1980年51歳没。ブラジルのボサノヴァ関係だと、ヴィニシウス•ヂ•モライスは彼より28歳年上で1980年66歳没。アントニオ•カルロス•ジョビンは14歳年上で1994年67歳没。ジョアン•ジルベルトは10歳年上で2019年88歳没…… と「夏草や兵どもが夢の跡」と芭蕉の句でも唱えながら合掌したくなります。1960-70年代のフィルム状況も考えると、チェット•ベイカーにウインクさせることに成功したアニメーションというのはかなりいいアイデアだったと思います。
それにしても、1976年34歳没とわずかな文字で片付けられかねない彼の死の裏にはこんな悲劇があったのですね。行方が分からなくなってから10年後に軍人の証言で真相らしきことがわかる、遺体は依然として行方不明というのは悲しすぎます。
さて、また “Embalo”を聴くとしますか。
合掌。
ラテン・アメリカの光と闇
ボサノヴァとジャズとの架け橋となったサンバジャズを支えたブラジルの天才ピアニスト、テノーリオ・ジュニオールを襲ったあまりにも酷い悲劇を関係者のインタヴューを中心に描いたアニメーション映画。
前半は、ボサノヴァの初期、彼が如何に有望な新星ピアニストであったのかが綴られる。ところが後半になると、かなり社会派的な要素が強くなる。サンバのようなブラジルの音楽と、ジャズがどのように結びついて、欧米や日本でも、人気を集めたボサノヴァが出てきたのか知りたかったのだが、後半は主題がテノーリオを襲った悲劇に移った印象。
テノーリオが拉致され、酷い目に遭ったのは、1976年3月、演奏旅行で訪れていた隣国アルゼンチンのブエノスアイレス、妊娠中の妻と4人の子どもたちを残して。当時は、軍事政権によるクーデターが起こる直前だった。彼がサンバジャズの分野で活躍し、有望株として注目されたのは、1962年から1966年だったから、少し間が空いているのかな。
誰に聞いても、テノーリオが政治的な活動をしていたとは思えない。いくら、口髭をたくわえ、長髪であったとはいえ、深夜、外出したくらいで、なぜ拉致され、釈放されることなく、悲劇につながってしまったのだろう。
彼が知的であったことは、皆口をそろえていた。ブラジルはポルトガル語、アルゼンチンはスペイン語だけど、何不自由なかったし、欧米のジャズ・ミュージシャンとは英語で会話できた。ただ、ラテン・アメリカの人たちは、ポジティブな誉め言葉しか言わないが、ちょっとだけ気になる点があった。彼は、途中で演奏をやめ、いなくなることがあった。しかも、皮肉屋。もしかすると、彼には、少しだけ精神の闇があり、それを反映して反社会的な、アナーキーなところがあることを見抜かれてしまったのでは。
それにしても、ラテン・アメリカの軍事政権には、ある種の連携があり、その背後には、米国のCIAがいたとか、自分のあまりの知識のなさに思いを致さざるを得なかった。
動くアートブックを観ているような
同じ映画館で観たかった作品に間に合わなくて、でもなんか観たいな〜という気分だったのでとっさに決めて座席へ。テノーリオ・ジュニオル、うーんわからん。ただ、アニメってところはいいなと本編を待ちました。
スタート直後、音楽に合わせてカラフルな文字が表示されると、めっちゃポップじゃんと。ああ、わたし好きなやつだなって。※チョロい笑
そして名前を知らなかっただけで、テノーリオの曲、ラジオで掛かっていたこともあり知っていたという…※ボサノヴァのよく掛かる番組がありまして
南北米大陸を舞台に主人公が取材を進めながらボサノヴァの歴史とテノーリオの真相に触れていくのだけど、ストーリ展開もよかったし、線の太くて色のハッキリしたアニメは観ていてとても楽しかったです。アートブックを眺めているかのようで、日本のアニメとは違う、センスの塊のようなアニメでした。
音楽もたくさん流れてくるので、音楽好きにもオススメです。繰り返し観たいなぁと思わせる映画でした。観終わってからずーっとSpotifyでセットリストを流してます。(そしてテノーリオをwikiる!笑)
軍事独裁政権時代の被害と音楽
ドキュメンタリー調アニメーション。
主人公は語り部のジャーナリストだが、事実上、取材対象となるフランシスコ・テノリオ・ジュニオールというヴォサノバのピアニスト・作曲家。
ジャーナリストがジュニオールの奥さんや愛人、ミュージシャン仲間へと訊きまわり。
アルゼンチンツアー中のジュニオールが、ブエノスアイレスでの公演後、アルゼンチンの海軍特殊治安部隊によって誘拐され、拷問ののち殺されたことに行き着く。
そこには南米各地で勃発していたクーデターによる軍事独裁政権の乱立、ホロコーストに近い外国人狩りという、歴史の闇が潜んでいた……
といった内容。
邦題に入ってるジャズ系ラテン音楽「ヴォサノバ」ってジャンル、あんまり関係なくない?
1957~1959年あたりのブラジル音楽の一大ジャンル&主人公のピアニストが築いたジャンルってことで、つけたのかしら?
原題は"Dispararon Al Pianista/They Shot the Piano Player"「ピアニストは撃たれた」 だけだし。
非常に興味深い内容ながら、色彩がゲリラ戦場のジャングルみたいで、崩れたわ〇せ●いぞうみたいな絵柄に、どんより倦怠感。
やや眠気を誘った(事実ところどころ記憶が欠落)。
アニメーションにしたのは、陰惨な事件をオブラートに包みたかったのかな、くらいな意味合いしか最初には感じられず。
ブラジルのメジャーな曲が多く流れるから、普通に実写ドキュメンタリーで観たかった。
いや、ひょっとしたらの推測ですが、この頃のミュージシャンって、音源は残っていても、演奏の映像(フィルム)があまり残ってないから、アニメーションを選んだのかもしれません。
時代が時代ですから、と思い至る。
もしそうなら、この手法を選んだ理由として納得はできます。
ボサノバの光と陰
ジャズボッサに始まり、ボサノバを通じてサンバ、ブラジリアンジャズ、MPBとブラジル音楽にのめり込んだこともあり、劇中でのレジェンド級の登場人物には興奮を覚え、訪れたリオの景色にもいたく懐かしさを感じた。
テノーリオ・ジュニオールの滑らかでかつ輝度の高いピアノの音色とリズム感は、一度聴けば深く刻まれること間違いなく、当時リイシューで偶然にも手に入れることができたアルバムは今でも、もちろん愛聴している。
共産主義勢力を押さえ込むための、汚い戦争に代表されるような中南米のクーデターによる軍事政権の粛清そして弾圧の犠牲者として描かれるが、当時のトロピカリア運動による抵抗、アーティストたちがヨーロッパへ亡命することを余儀なくされたことも併せて加えておきたい。
歴史を頭に入れてからの方が興味深い
とにかく不当に逮捕って、ある意味、見せしめみたいな感じなのかな。恐怖を植え付けると言うか…そんな中で捕まってしまったピアニストの彼は不運。
あと音楽が楽しめます、エンドロールが終わるまで聞き入ってまして。
ある程度の知識がないと理解に詰まるか
今年108本目(合計1,650本目/今月(2025年4月度)11本目)。
タイトルだけではいわゆる音楽映画かなという感じはありますが、実際にはアニメ作品で(一部、実写のように見えるシーンはあるが、全編どうもアニメ作品)、音楽映画の体裁を取りつつ、扱う範囲が1960年以降の南米の各国の独裁政権や反共産主義といった特殊な論点がメインなので、そこまでアンテナを張っていないとまぁ見るのが難しいのではないかなぁ、…といったところです。もっとも、メタ的にいえば、テアトル梅田さんで放映している以上、単純なアニメ作品であるはずがなく(アンパンマンなどは東京テアトル系列の扱いだが、テアトル梅田では放映していない)、まぁ何らか知識が求められるかなと思ったらそういった部分というのは、一部、「オオカミの家」や「ハイパーポリヤ人」(いわゆるピノチェト政権のお話を含む)と重なるとはいえ、その知識まで把握してみるのはきついかなという印象です。
この上で、さらに「ブラジルだけ言語が違う」というのは要はブラジルだけがポルトガル語(南米では他の国はスペイン語)といったやや高度なセリフが登場するのも全般的に知識の必要量をあげてしまっており、そこをどうとるのかな、といったところです。
ただ、同じ1950~60年代のいわゆるこうした混乱期といえば、身近なところでは朝鮮戦争やいわゆる冷戦くらい以外は常識の範囲外で、それらに触れられたという点においては良かったです。パンフがなかったのは残念ですが…。
採点上特に気になる点までないのでフルスコアにしています。
上記のように、現代(1950~60以降)の南米の政治史という特殊な知識を必要とする映画になりますので、そこを把握してからの視聴がおススメです。
ドキュメンタリーなのにアニメ
2025年劇場鑑賞114本目。
エンドロール後映像無。
消えた音楽家の足跡をたどるドキュメンタリーなのにアニメという変わった作品。最初えらい手間かけるな、と思いましたがもしかしたら内容が内容だけにそのまま出演するとまずい人もアニメなら顔を変えるのも可能なのでそういうことなのかもしれません。過去の映像も簡単に作れますし。そう考えると実写パートとアニメパートのドキュメンタリーもなんかあったような気がします。
内容はボサノヴァの歴史というよりは、ブエノスアイレスの軍事クーデターがいかに滅茶苦茶だったかを暴く話になってきていて、この作品の二本前にナチスの悪行を散々見せられた後でもひどいなと思ってしまう内容でした。少なくともナチスはあんなに殺したいターゲットを簡単に間違える事はなかったはずなので・・・。
正直アニメは・・・でも音楽絡みは最高
国家テロらしい
1950年代末、ブラジルのボサノバが注目され世界中のアーティストが取り込み大人気となった。2009年、アメリカの音楽ジャーナリスト・ジェフ・ハリスは本の出版会見を開いていた。元々、ボサノバの歴史について調べるためニューヨークからリオデジャネイロへやって来たジェフは、サンバジャズで名を馳せた天才ピアニスト、テノーリオ・ジュニオルのピアノの音色に魅せられた。彼に興味を持ち、その足跡をたどると、ブエノスアイレスでのツアー中に謎の失踪をしていて・・・という事実に基づく話。
原色の某有名イラストレーターの様な絵で、字幕も含め非常に見にくい。
作家の執筆発表、そして取材中に会った人達との話なんだが、有名な人なのかも知らず、それがアニメなので本人の顔を見れる訳でもなく、余計に興味を持てなかった。
1950年代から70年代まで、中南米でクーデターによる軍事政権が多くの国で発生していた。そして、テノーリオが失踪した1976年に、偶然にもアルゼンチンでクーデターが起きた。そんな南米の国の歴史を知る、という点では勉強になった。
失踪した時に一緒にいた愛人、妻などにもインタビューしてたが、当時は愛人が居るのも当たり前だったのだろうか?
元西武ライオンズのオーナーも愛人の子どもだったらしいから、昔の日本も妾とか2号さんとか、おおらかだったのだろうけど。
東Oや渡Oは不倫で相当叩かれたし、現在だったら大変だったろうな、とは思った。
タイトルなし
ピアニストのドキュメンタリー映画?
アニメーションだからどういうものかと思ったら、
当時の映像をアニメ化したものは少なく、インタビューや本人の行動のシーンが多かった。
サスペンスみたいで少し楽しかった。
アニメーションにしてる意味を感じない
中南米近代政治史を背景に、一人のピアニストの悲劇を描く。
テノーリオ・ジュリエールという音楽家の存在と彼を見舞った悲劇は全て事実である。
彼は、1976年にアルゼンチンへのツアー中、ブエノスアイレスで、アルゼンチン警察ないしは軍に拉致され拷問の上射殺された。ちょうどアルゼンチンではビデラ将軍が、ペロン派を放逐して軍事政権を打ち樹てた折であり、テノーリオの拉致はまさしくクーデターその日の早朝であったらしい。その行方は10年にわたって不明であったが、1986年になってアルゼンチンの元伍長クラウディオ・バジェホスがブラジルにやってきてサンパウロのTV局で、テノーリオを殺したことを告白したため明るみに出た。
テノーリオが優れたピアニストであったことは確かだが、この作品の作成意図はその音楽性を賛美することにはなく、むしろ彼が巻きこまれた悲劇と、突然彼を失った人々の悲しみ、故もなく人を攫い殺す権威主義的暴力の不道理を描くところにある。
この映画でフィクションであるのは、物語の語り手である作家と、彼がルポルタージュを書籍化しようとするところだけである。インタビューに登場する人物たちは全て実在しており、おそらくはインタビューも実際に行われてその内容も映画の通りであったのだろう。(インタビュー相手の安全のため一番改変されているかもしれないが)
登場人物はほんの一部しか知らないが、ジョアン・ジルベルトにしてもヴィニシウス・デ・モラリスにしてもソックリである。なぜ、アニメーションで、というところだが、おそらくはインタビュー相手を全て似顔絵で表現するというところから出発していて、さらに釣り合った表現をというところからあのスライドショー的な映像になったのであろう。
それともちろん、これは意図的なものだと思うが、映画の中では、最初はジャーナリストと編集者はボサノヴァ黎明期のブラジルのミュージックシーンを取材しようとしている。でもジャーナリストはテノーリオの謎について知ることによって作品の方向性を転換する。だから我々も、最初はボサノヴァや同じ頃に出発したヌーヴェルヴァーグの映画の清新さ、人間的な芸術性に触れているが、やがて非人間的体制による闇の深さにとらわれていく。
世界は変わる。それも信じられないような短い期間で。それはドミノ倒しのようにラテンアメリカが軍事体制になったこの映画の時代背景を見ていれば分かる。我々はまた、再び、同じ轍を踏もうとしているのかも知れない。ホワイトハウスの狂人が世界を振り回すこの数週間を経てつくづく思うのである。
全22件中、1~20件目を表示