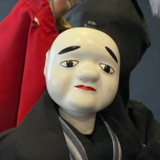長崎 閃光の影でのレビュー・感想・評価
全27件中、1~20件目を表示
一本の映画として本当にいい映画だった。
とても誠実な映画だった。
起こったこと、その中にいた人たちをそのまま、余さずに映画に刻みつけるのだという気概を感じた。
それだけに、見ている間は辛かったけど。
ああ、こんなことどうか起きませんように、と願うようなことが、次から次に起こる。
家族は真っ黒になって死に、恋人や同僚は正体不明の病に冒されて死ぬ。
あの爆弾のおぞましさをあらためて思った。
当たり前だがスクリーンに映されているような事態が、何万通りも起きていたのだ。実際に。
これは既に起こった事実なのだから。
年齢を重ねるにつれて、映画や資料映像とかで原爆の投下シーンを見ることが、本当に怖くなってきた。
その向こうで生きていた人々の営みが、日々本当にそれぞれ大変で、それぞれに意味のあるものであったということが、実感としてわかってきたからかと思う。
そしてそれを無惨に蹂躙する戦争行為が、何某かの理屈や事情を盾に、人間が意図してやるものなんだだということも。
この映画でも投下前のシーンがあったけど、ああ、止まってくれ、誰か止めて、と思ってしまう。
あと一週間で戦争は終わるのに。
人間がやってることなんだから、止まる道筋はあったはずなのだ。
「あと一週間早かったらみんな生きとったのに」ってセリフにもあったけど、終戦まで広島からは10日、長崎からは一週間もたっていなかったんだとあらためて思った。
何十万人が死に、突然戦争が終わり、一週間前に落ちた爆弾にやられて地獄のようになった街が残る。
一体何なのだろう、これは。
よく戦争を二度と繰り返さないように、とか、そのために記憶を語り継ぐ、とか言うけど、それはほんとに、お為ごかしや綺麗事ではなしに、ほんとに絶対的に必要なことなのだ。
それを確かな実感をもって、思い出させてくれる映画だった。
ただ、そういう、感じるメッセージとかではなしに、単純に映画としても掛け値なしに素晴らしい映画だったというのは、声を大にして言いたい。
臨場感のあるセット、美しい映像、俳優陣の誠実で確かな演技とそれを引き出す演出。
今年見るべき一本の映画があるとしたらこれだったんだと思った。
もう上映終わり間際だと思うけど、自分はこれ映画館で見れてにほんとに良かったです。
タイトルなし(ネタバレ)
昭和20年8月の長崎。
日本赤十字社の看護学校に通う女子学生3人は、故郷長崎に戻っていた。
3人とは、田中スミ(菊池日菜子)、大野アツ子(小野花梨)、岩永ミサヲ(川床明日香)。
スミには、造船所で働く勝(田中偉登)という幼馴染の恋人がいた。
そんな勝にも召集令状が届いた。
9日、長崎の空が閃光に包まれた。
原爆である。
スミ、アツ子、ミサヲの3人もそれぞれ看護婦として被爆者の看護にあたるが、現場は壮烈なものだった・・・
といったところからはじまる物語。
終戦80年ということで今年は戦争ものをよく観ている。
原爆投下直前から描かれる長崎。
3人の看護学生を通して描かれる戦争の悲惨さと不条理さ。
心が痛む描写も多々あり、不条理さに対する怒りも深く描かれている。
正直、観る前は「綺麗事として描かれているとイヤだなぁ」という危惧はあった。
が、そんなことはなかった。
「力作」かつ、既に「名作」の雰囲気すら感じました。
主役3人、いずれも好演。
ここで描かれる彼女たちは、犠牲者でありながらも献身する。
英雄といえる。
戦後のわが国の礎・・・
しかし、そんな英雄を生み出す必要など、戦争がなければ、生み出す必要などないのだ。
忌避すべきもの。
そんな戦争に対する怒りが本作には詰まっています。
80年前に終わった戦争のことを忘れないで。戦後を戦前にしないためにも覚えていて。当時を生きた人たちからの、そんなメッセージが込められた作品です。
毎年八月の風物詩。・_・
夏祭。七夕。打ち上げ花火。
お盆。日航機墜落。終戦の日。
原爆。ヒロシマ。そしてナガサキ。
この時期、戦争を描いた作品の上映が増えます。
今年も何本か、当時を振り返る作品がありました。
その中の一本としてこの作品を鑑賞することに。
重い内容なのかなぁ …と身構えながら
鑑賞開始。
実際に看護に従事した看護婦たちの声を集めた「閃光の影で」と
いう資料を元にしているそうです。
その混乱の中で、原爆が落ちた日に爆心地付近に居合わせた看護
学生の少女3人の行動を中心に、どんなことが起きていたのかを
描いた、ドキュメンタリーに基づいて後世されたとの事なのです
が、所々に創作を埋め込んだノン・フィクション風の作品なのか
な との印象を持ちました。
少女役3名の演技(セリフ・行動)を中心に捉えて観ていたので
すが(それはまあ、当然のことですが)、違和感を感じてしまった
箇所もそれなりにあった気が、しなくもないです… ・_・;
けれども
実際にその場で行動した方々の記憶と記録を元にしている という
その一点において、この作品が世に出た意味・意義は大きい。
そう思わずにはいられません。
80年前の戦争の記憶。戦争があったという事実。
それを風化させないためにも、後世に残すべき作品かと思います。
鑑賞して良かった。…とは思います。
見た方が良いか尋ねられたら、是非一度は、とお薦めします。
(二度観たいかと問われると、うーん …というのも本音)
※ 不意打ち気味に、グロい場面や血の気が引く場面が出てきます。
ガーゼ交換とか麻酔注射直後に足を●●…とか …@▲@~;;
その手のシーンの耐性が低い方はご注意くださいませ。(自分だ)
◇
■不自然に感じた場面
セリフによる会話に、真実味に欠けると感じる部分がありました。
瓦礫の下で父を見つけた少女が、やたら「大丈夫?」と声をかけて
助け出そうとする場面なのですが…
※どうにも 創作感を感じてしまいました。
そのセリフを含んだ箇所の演技も、ぎこちなく感じられ
不自然さが拭えない感じがしました。
記録されているセリフがそうなのか?と
最初は思っていたのですが、鑑賞後しばらくして思ったのは
# 当時の記録とはいえ、記録にそこまでのセリフまでは
残ってはいないのでは? #
ということ。
# そういった場面でのセリフはライターによる創作では? #
ということ。
そこに思い至り、なんとなく納得した次第です。
「人が 呆然とした」時、意味のある言葉は口をついて出ず
「 言葉を失う」状態になるような そんな気がしました。
■リアルに感じた場面
一方で、人力車を引く場面での3人娘の会話のシーン。
この部分にはリアルさを感じました。
それぞれが、相手の勝手な(と思える)行動を非難します。
ついにはこんなセリフまで。
「神はこの爆弾を落とした相手の事も許すの?」
信じていたことは、所詮は綺麗事なのだろうか。 と
理想と本音が混じり合った本心のぶつけ合いの場面。
だからこそリアルに感じられた場面です。
※ 今起きている戦争・紛争の当事者に対する問いかけ
にもなっているように感じます。
人類に与えられた永遠のテーマなのかもしれません
◇最後に
今年は戦後80年。
戦争を体験した世代もどんどん少なくなってます。
戦争がどれだけの物を破壊したのか
記憶の彼方に埋もれさせてしまわないように と
この時期に振り返ることには、意味があると改めて思います。
「戦後」が続きますように。
「戦前」になりませんように。
☆映画の感想は人さまざまかとは思いますが、このように感じた映画ファンもいるということで。
たった80年前の真実
たった80年前の事。自分は戦争を知らない。けど両親、祖父母、知人から生々しい体験は聞けた。
後何十年かすればこの戦争も、関ヶ原等の様に歴史の中に埋もれて、物語になるのだろうか?
観てる間、そんな事を考えていた。
きれいな映画館で、良い環境で。片手にドリンク、自由に飲める。
そんな自分に少し罪悪感を抱く。
原作は当時の看護師達の手記を纏めた本。その為、映画も散文的で、出来がいいとは言えない。
また、予算がなかったのだろう、CGやセットはショボい。
戦時中にしてはみな綺麗すぎるし、特に野戦病院での彼女らの日々、汚れていく感じは表現されていない。
悔しかったろうな。予算さえあれば…そう思っただろう。
そこは批判しても仕方ない。
そして戦後80年目の夏。
「鬼滅の刃」がスクリーンを席巻している為、この映画は朝7時台の、誰が見るんだという、ひじょうに鑑賞しにくい上映時間に追いやられている。それが現実。
しかし、それで良いのか!?
興行側には、今、見せなくてはいけない映画を観てもらうようにしなくてはいけないのではないのか!?
この夏に!
シネコンはすごく見易すく、綺麗で便利な環境を作った。しかし、大切な物を無くしてないか!?
そして、それは自分自身にも言えるのではないか⁉️
#長崎閃光の後で
それでも明日へ生きていく。
突然…空から地獄が降ってきた。
想像なんて容易に出来ない言葉を絶する現実。
それでも人々は、懸命に助け合いながら、懸命に足を引っ張り合いながら、
融和と差別の狭間で生き延びる。
美化だけではないトコロに感嘆。
楽しむことではない、感じることに意味がある。
まず、長崎・広島において原爆の被害に遭われ亡くなられた方々にお悔やみと追悼の意を。
そして、最悪の被害に遭われながら生きのび、戦時最悪の出来事を語り継いでくれた山下フジヱ様や皆様に、感謝の意をお伝えいたします。
本作は、看護婦(当時の呼称)を根幹とした「命を救う側」の視点であり、多くの戦争映画に表現されている激しい戦闘や激しい思想の表現はほとんど無く、「その視点」にふさわしい、粛々としたリアリティのある現場を鑑賞させていただきました。
エンターテインメント性が高く予算もつぎ込まれている戦争作品は、それはそれで良いですし好きですが、比例して確実な「脚色」「オーバーアクション」がつきものです。
本作は、楽しんだりする事、評価したりする事を基に鑑賞するよりも、戦時最悪の状況を、しっかりと感じることを伝えてくれた作品だと思いました。
本作は、原爆直後の現地の状況・その地の人々・戦争に対する妄信的な表現・戦争に対する倫理的な表現・絶望・怒り・許し・裏切り・悲しみ・ジレンマ・必死な思い・気分の悪い思いなど。
それらの表現を、非常に「現実的な人の反応」を映像化されていると思います。
それは同時に、「もし自分だったら」と主観的に考察したとき、同じように「曖昧な」態度だと思うからです。
封建的な帝国主義の確固たる「頑固意思」も多少表現されてはいますが、表現の多くは……
①アメリカと戦争してるがキリストを信仰する。
②恨みを持つが、許したくもある。
③逃げ出すが、つまずけば戻る。また、戻ってきた者に対して罰則だけは与えるが受け入れる。
④確固たる意志を全面に表明しながら、敗北すれば受け入れて染まる。
⑤裏切り行為に、呆れるだけで非難と攻撃をしない。
⑥普通に気持ちが悪いと思う。普通に逃げ出す。
……などなど。
これが人間なんですよね。
特に、主人公3人が荷車を引きながら思い思いをぶちまけて喧嘩する様子。
決着や結論は無い。
みな戦争に憤りと悲しみを持ちながら、ある者は怒り、ある者は謝り、ある者は許し前に進みたいと願う。
みんなの思いが正解で当たり前のジレンマ。
生きている人間の、自然的な感覚なんだと思います。
そして、現実に戻り荷車を引く……。
そうして前に進むしか無いから。
妄信的な強要や自殺行為、一貫した思念は人間の本質では無く、みんな怖いし疑問を持つし思想も揺らぐ。
それはカヨが恋人に対し、戦争に行かず助かったというその言動に一瞬は非難を浴びせるが、冷静になれば生きていることが嬉しいし、一緒に歩みたい気持ちになったこと。
婦長が逃げ出す看護婦に非国民呼ばわりしても、一時の感情なだけで戻ってきた人にまで継続して非難をしない様子に描かれている。
命を投げ出した人々も、時代と思想に翻弄されはしても、もし「必要」がなければ死にたくはなかったはず。
誇張表現のない、死を迎える人や火葬する人にも、何とも重苦しい現実感が胸を締め付けられました。
忌むべきは、戦争と暴力だという事。
憎むことや敵対意思ではなく、「戦争の悲惨さ愚かさを語り継ぐ事」を継承し、平和を継続させる事が重要であるという思いで最後まで鑑賞いたしました。
戦争は無くなりません。現実に。
だが、少なくとも最悪な被害を受けた日本は、悲惨な思いを平和の中で感じ取れる私たちは、反戦の思いを伝えていければと思います。
こんなもん
まあこんなもんかな、ただ終盤に原爆のキノコグモのシーンがありその時に急に、原爆の音、ドーーーーンてなるシーンがあるが、このドーーーーンめちゃくちゃビックリする。このドーン必要全くないじゃないか、内容も内容でうたたねしてるもんを起こすためなのか?心臓止まるがな。
一瞬で焦土に化しあまたの人間を殺戮した原爆の恐怖を見よ
今年は広島、長崎に原爆投下され80年。今も苦しむ人たちがいるという事実。映画「オッペンハイマー」を見たとき、実験で甚大な被害を与えることを目にしながら生活している人間に向かってこの爆弾を落としたことにずっと怒りを感じていました。だからこの長崎の惨劇を見て、悔しさと虚しさを感じ、忘れてはいけない、この状況を後世に伝えていくことが必要だと映画の力を示していた作品でした。
【映画感想文】
作り手たちの原子爆弾投下に対する強い怒りと憤りが強烈に伝わってきた。冒頭の当たり前のような日常生活や笑いあっていた家族が、原爆投下の一瞬で下敷きなったり、黒焦げになったり、街が焦土になってしまう、この非道さ理不尽さ。原爆は天変地異の災害ではなくまさしく人為的殺戮だ。
日本赤十字の看護学校に通う女学生三人が空襲による休校を機に帰郷し、家族と再会し楽しい時間を過ごしていた。そこに原爆投下だ、轟音と異常な光をともなって。そのとき、一人は祖母の家に行くため爆心地から離れていた、一人は父とミサに行っていた、もう一人は日本赤十字長崎支部で働いていた。
三人は生き残り、日本赤十字長崎支部で被爆者の看護にあたる。次々に運ばれてくる死傷者。被災者のうめき声、血、火傷、爛れた皮膚、足を切断する手術、傷口から蛆虫がわいてくるなまなましい描写の連続。彼女たちはそれを直視し看護する。原爆関連の映画は多数あるが、看護者の視点で見せる映画は初めての経験だった。必死に治療しても、看護しても被災者は次々に亡くなっていく。この無力感と虚無感がにじみでている。
彼女たちは看護者であるが被災者でもある。一人が実家を見に行ったとき、そこはすべて焼け野原になっていて、自分の家の側で家族が黒焦げになった姿を目にする。他の二人も家族の状況がわからないなかで被災者の看護をする。人が死んでいく姿を見なくてはならない過酷さと、自分のことは二の次にするに彼女たちの精神力、責任感に心を揺さぶられる。
原爆で焦土と化した街をCG化し緻密に描写する映像には目を覆いたくなる。たった一発の爆弾で街が、多数の人が死んだ。それだけではないこの悪魔の爆弾。被災者であまり傷を負っていない人が死んでいったのは、ほとんどが放射能における原爆病が引き起こしたものだ。この悪魔の爆弾は、何年も、何十年も、次の世代においても死をもたらすのだ。
そして一番の悲劇は、被災者が一生この体験を忘れられないことだ。心に負った深い傷は永遠になくならい。それが悪魔の爆弾だからだ。
観るまで躊躇しました。
小生が原爆について学んだのが1976年の小4で「実写版はだしのゲン」でした。
原作の中沢啓治先生の制作意図通りに、敢えて観る人のトラウマになる様に妥協せずリアルに表現され、それ以来二度とはだしのゲンは観ていませんが、自分の中の反戦と核兵器、放射能とは何なのか?の原点になる名作です。
その様な重い記憶もあり原爆を題材にした映画を観るには覚悟が必要でした。
本作品では直接の被爆は避けられたものの「被曝」によって時間差で原爆病に冒される描写も含まれ救護所を舞台に救護に従事した者の人間模様が描かれています。
エンディングロールも印象的で福山雅治さんのネムノキを主役の3人がカバーしていました。
そしてキャスティングでびっくりしたのが「赤い彗星」のあの人が…。
見てよかった
語弊のある言い方に聞こえるかもしれないけど、私は戦争の話が好きです。
忘れては行けない大切なことだから。
広島に比べて長崎の原爆の話は耳にする事が少なく、看護婦さんたちの目線での話はとても惹き込まれました。
朝鮮人に治療しない(迫害する)シーンは、私はあって良かったと思います。
ソレがその時の時代のリアルだったのだろうと思うから。
患者の対応に追われる看護婦、傷口に蛆が涌いて吐き気を催したり、逃げ出したり、直視出来ない状況を直視しないといけない看護婦たちの様子は、ココロをえぐられました。
『映画』というところだと、小野花梨の演技力がすごすぎた。
戦争は究極の理不尽
今年は戦後80年ということで、戦争の映画がたくさんですね。
手記…よくぞ書いてくれました。戦争を経験した人たちが、だんだん少なくなり語り継ぐ…語り継ぎ続けなければならない事実。
あと7日早く負けていたら…
戦争は究極の理不尽。
なのに、武器を山ほど買ったり意味の分からないことをする政治家。
戦争になった時、犠牲になるのはただの市民である私たち。
戦争を知らない世代の私ですが、せめて戦争反対という気持ちを発信し続けなければ、理不尽に亡くなった人たちに申し訳ない。
作中に「赦す」「許せない」と話すシーン
なぜ生かされているのかというシーン
いろいろ考えます。
私たちにできるのは、考え続けることなのかも知れませんね。
福山の主題歌、美輪明宏さんの語り、そして当事者の姿…たくさんの方の思いの籠った作品です。
テーマではなく、あくまで映画の出来としての評価です。
広島の平和祈念式典での石破総理の挨拶に引用された歌に触発されて、広島と長崎の違いはあるが観ておこうと思った。
映画やドラマ化も数え切れないほどされているが、戦争そして原爆の悲惨さはそれに触れる度に言葉を失ってしまう。
この映画も多分に漏れずそうであった。
トラックに掲げた赤十字の旗が翻るだけで胸に迫るものがあった。また、主人公たちがそれぞれのやり場のない思いや感情をぶつけ合う場面は心に染みた。
さて(ここからはマイナスに感じたことを書くので、ネタバレあり)、観ていて気になったのは脚本、演出、編集(あるいは監修、校閲)の甘さ。
カットのつながりが不自然な箇所が多々あった。例えばバスに間に合わないと先を急ぐカットの次のカットではまだバスに乗る前なのにのんびり歩いて登場し、先を急ぐ風がない。急いだから十分間に合う時間になった?ならその一言がほしい。軍医にコッヘルと言われたのに、看護婦はピンセットを渡し怒鳴られ、2、3カット後、鑷子(せっし)と言われちゃんとピンセットを渡す。それが鑷子とわかっているなら、なぜ先のカットで間違った?疲弊して判断力がなかった?なら軍医の怒り方や、看護婦の演技に疑問が残る。火葬場で我が子と見間違って錯乱する看護師が、いや見間違いだったと判断する契機が不明。例えば1秒でもその子の顔をまじまじと見るカットがあるとか、少年の訝しげな表情のカットがあれば納得できるのに。人物の描き方も雑。婦長だって葛藤があっただろうにただのヤリマンみたいな描き方。
また、スケール感が狭い。予算の都合もあるのだろうが、見えていない部分の広がりが感じられない。テレビドラマくらいのスケール感が残念。
当時の看護婦たちの手記をもとに書かれた脚本らしいが、盛り沢山にしすぎて一つ一つのエピソードが軽々になってしまったのだろうか。
テーマがテーマがだけにもっともっと丁寧に作ってほしかった。
被爆したクスノキは、、どんな想いで長崎の空を眺めて続けてきたのだろうか
2025.8.7 イオンシネマ京都桂川
2025年の日本映画(109分、G)
原作は日本赤十字社刊行の『閃光の影で 原爆被害者救護赤十字看護婦の手記』
原爆被害者の救護にあたった看護学生の目線で紐解く戦争映画
監督は松本准平
脚本は松本准平&保木本佳子
物語の舞台は、1945年8月の長崎
空襲によって看護学校が休校となったスミ(菊池日菜子)、アツ子(小野花梨)、ミサヲ(川床明日香)は、久しぶりに故郷に帰ることになった
スミは父(加藤雅也)、母(有森成実)と再会を果たし、恋人未満の友人・勝(田中偉登)と会うことになった
勝は「スミの写真」が欲しいと言い、その理由は「赤紙が来たから」だった
勝は日本の敗戦は濃厚と考えていて、それは誰にも聞かれてはいけない本音だった
スミはその後、忘れ物をした父を追って列車へと乗り込む
一方その頃、アツ子は日赤長崎支部にて見学を行い、ミサヲは父(萩原聖人)とともに教会を訪れていた
そして運命の11時、長崎上空にて原爆が爆発し、あたりは閃光に包まれてしまう
爆心地から離れていたスミは怪我をすることはなかったが、アツ子は爆風に巻き込まれて足を怪我し、ミサヲは父とともに瓦礫の下敷きになってしまう
アツ子は事務局長の小川(利重剛)の命によって、看護婦長の川西(水崎綾女)らと共に学校を救護所へと変えていく
まだ看護学校を卒業できていないのにも関わらず実地に放り込まれた彼女たちは、先輩たちに揉まれながら、できることを行なっていく
だが、新型爆弾の威力は想像以上で、何の治療もできないまま多くの人が亡くなっていく
そして、無力であることを感じながらも、前に進むしかなかったのである
今年は戦後80年ということで、談話にしがみついている一部の人を除けば、英霊に敬意を払う時期が近づいている
毎年、この時期の日本では厳かなる時間を過ごすのだが、もう戦争経験者は1割を切るほどになっていて、劇中の3人も生きていれば95歳とかになっている
記録は残るものの、記憶から薄れていくのも時間の問題であり、このような映画は定期的に作られる意味がある
そんな中で、本作がどのような特異点を描けるかと言えば、この土地独特の戦争に対する捉え方であると思う
舞台が長崎ということもあって、キリスト教の布教が進んでいる地域で、そんな土地にキリスト教国のアメリカが原爆を落としたという構図になっている
同じ神様を信仰している土地に落とす意味は語られないが、俯瞰的に見れば、神の試練というものが人の力で行われていることになる
また、本土の端の地域ということもあり、アメリカから見た時に一番遠い本土という位置付けになっている
それは政府から最も遠い場所という意味合いがあり、都会で決められた戦争に巻き込まれているという感覚が強いように思える
実際にどのように戦争の機運が高まっていったのかはわからないが、あの時期に全国統一的に一致団結に至っているとも考えづらい
それゆえに戦争を醒めた目で見ている勝もいるし、それぞれが思うところがあっただろう
また、看護婦の一人のセリフで「長崎は大変だ」という、他人事のような感覚を植え付けるものもあって、それは違和感なのか、実際の感覚なのかはわからない
戦争を知らない世代は、戦争経験者の言葉を聞いて育ち、学校教育の中でその悲惨さというものを学んでいく
それゆえに「我ごとに思える人もいれば他人事に感じる人もいる」のだが、戦時中でも「他人事に感じる人もいる」というのは、ある意味衝撃的な一幕だったように思えた
映画を通じて伝わるメッセージは他にもたくさんあるのだが、一番印象に残ったのは「無駄なことをしているという虚無感」であると思う
終戦間近の赤紙招集を受ける勝も、救護をしても次々と死んでいく人々を思うと、何のために一生懸命になっているのかわからなくなる
そんな中で、戦争というものをどのように受け止めるのか、という違いがあって、キリシタンのミサヲは「赦す」という考えに至っていた
これはキリスト教などをはじめとした考え方なのだが、キリシタンではない二人が「赦す」と「許す」を混同していないのかは気になってしまった
「赦す」という言葉は、言い換えれば「過去に囚われない生き方をする」というもので、相手の行為を受け入れるというものではない
あくまでも、過去の出来事に縛られずに前を向いて行こうという考え方であり、許せない気持ちと同時進行する感情であると思う
このあたりの微妙なニュアンスが出てくるのが長崎の戦争映画であると思うので、そこをもう少し掘り下げても良かったのかな、と感じた
いずれにせよ、本作が作られる意義はあると思うし、政治的な思惑に弄ばれるよりは意味が大きいだろう
そんな中で「長崎」を舞台にしつつ、未熟な看護学生の視点を取り入れると言うのは珍しいパターンのような気がする
ただし、それ以上にキリスト教が他の地域よりも布教されている土地というところに主眼を置いても良かったと思う
映画では、讃美歌を歌いながら壊れた教会を目指す信者の群れが描かれるものの、そう言った人々がどのように神の試練を理解しているのかは興味深いところだと思う
天災などの人智が及ばないことを神の試練だと捉えられても、人の意思によってもたらされた厄災を同等に扱うものなのか、というところは疑問が残る
なので、そこをクローズアップすることで、長崎ならではの戦争映画が描けたのではないか、と感じた
敢えて厳しく言うが、実体験者の方は見ないし、見ても「こんなものじゃない」と言うだろう
戦後世代だが長崎に生まれ育ち、その後教師になった者として手記や体験記、関連書籍は相当数読んできた。今もそう。一言で言うならば、きれいすぎる。ある知人の実被爆者の方は、一度だけ原爆資料館を訪れて、「こんなもんじゃない」と思い、二度と行っていないとのこと。例えば、救護所だが、実際は嘔吐物や排せつ物にまみれて、蠅や蚊、蛆が蔓延して、まず手当の前の段階に看護師だけでなく動員されてきた一般人もあたっていた。中には幼い子どもを背負った若い女性が寺に収容された重症者たちの世話をしていたのだが、水も包帯もなく、膿だらけのどろどろの布をバケツで洗うしかなく、そんなことをしている内に、幼子は亡くなってしまった。それはほんの一部のことで、映画の中で白い白衣を着た少女たちが折り重なって眠るシーンとは、いかに現実とかけ離れているかわかるだろう。
浦上のカトリック信者は「神の摂理」として受け入れたという事は、永井博士の言葉から有名になったが、小崎修道士は住吉のトンネル工場内で意地の悪い先輩が苦しんでいた時、「ざまあみろ!」と思って放っておいたと告白している。また爆心地付近ではピカッと光ってからドーンと爆風が来たのではなく、光と音がほぼタイムラグの無い「ピシャッ」というのが近いと聞いたことがある。というようなことはいくらでもあげられるがやめておく。意味も無いし、矛盾をつくことが目的では無いからだ。ただ、若い世代に、「こんなものなのか」と理解されるのはちょっと厳しいと感じる。見終わった後、自分で調べて見たくなるような映画であって欲しかった。
あと気になったのは、「結局、この映画は何をテーマにしたかったのか?」ということ。ただ悲惨さだけを描きたかったのならば、前述の理由で成功していないと思う。
ひとつ思うのは、朝鮮人の被爆者が救護を求めてきた際、看護婦長?の女性は「朝鮮人につける薬はなか!」と足蹴にする。それに対し、主人公らの少女たちの心情などには一切触れられず流されてしまった。しかし、原爆・戦争の矛盾こそがこのワン・シーンに象徴されていたのであり、このテーマを丁寧に追っていれば、若い世代にも一石を投じる作品になった可能性もあったと思うが、残念である。
最後にエンディングで流れた「クスノキ」だが、あまりにも山王神社の楠だけが商業的に大きく独り歩きしすぎており、どうにも違和感を拭えない。被爆木は他にも市中に無数にある。中には被爆木と認定されていない木もあるのだが、木にとってはそんなことはどうでもいいことだ。
個人的には楠よりも遥かに小さい、若草町にある5本のカキの木の方をもっと多くの人に知ってもらいたいし、見てもらいたい。ほっそりとした木肌は無惨なほど焼け焦がされていながらも、健気に若葉やカキの実をつけているのだが、その姿に私は励まされる。
異常な事に慣れていく異常さ
広島に比べて取り上げられることが少ない(ように感じる)長崎での原爆被害を、日本赤十字で看護に当たった3人の看護学生の視点で描きました。
戦争末期でもどこかのどかだった町が原爆で一変し、過酷な状況の中でも懸命に仕事をした看護婦たち。まだ15歳だった主人公は当初恐怖で動けなかったものの、次第に使命感をもって働くようになります。
しかし被爆者は毎日どんどん亡くなっていくし、薬も設備も限られていて、病院(救護所)では非情な決断も必要となります。こういう事実があったことを忘れてはならないです。
戦時中に「ちよこれいと」をやっても大丈夫なの?とか思いますが、地方だと結構のんびりしていたのかも、でも教会で礼拝をしていたのにはちょっと驚きました。
映画としての評価ですが、若い世代に伝えるという意味では十分だと思います。
女の子たちは自然な感じで良かったです。小野花梨さんは上手ですね。3人が歌うテーマ曲も美しいです。
ただ、脚本と演出は、大人がお金を払って観る程のものでは無かったです。観客に若い人がいなかったんですが、むしろ若い人に無料で広く観てもらいたいです。
洗濯や玉音放送のシーンが舞台の場面を見ているように不自然に感じました。玉音放送って、「この世界の片隅に」では正座して聞いていたと思いますが庭で立って聞いていて、戦時中の人にはとても見えない婦長さんがラジオを途中で消す、なんて有り得ない気がしました。
朝鮮人の治療を拒否したシーンですが、拒否したけれどそれがずっと心の中で引っ掛かっていた、というのでは駄目なんでしょうか。日赤の看護婦がそんな事をした事実は無いという断り書きをするくらいなら、不要なシーンです。当時の風潮を表現したというならその通りの描写にするべきです。
実際に手記を書いた方の一人が主人公の現在という設定で出演してくれましたが、ナレーションの美輪明宏さんは男性の声にしか聞こえないので主人公の80年後の語りとしては不自然でした。
クスノキ
戦後80年というのもあり、当時を綴った映画が多く公開されていますが、長崎の原爆にフォーカスを当てた作品は珍しいなと思い鑑賞。
「か「」く「」し「」ご「」と「」で一目惚れした菊池日菜子さんが出演していたのもきっかけになりました。
当時の状況を鮮明に描きつつ、とても残酷な描写をしっかりやっており、日常が非日常に変わる瞬間の恐ろしさがひしひしと伝わってきました。
被害者の怪我や病状はどストレートに映しており、欠損描写はもちろん、ガラスが目に入って目の見えない妊婦だったり、足を切らなきゃいけない患者は麻酔もそこそこにギザギザ刃でギコギコ切らないといけないというのは映ってないにしても看護婦たちの目線と唸り声だけでも肝が冷えました。
朝は元気だと思ったら、夜には一気に病状が進行して死んでしまったり、水を飲むと死んでしまったり、遺体は近くで直に焼くといった生々しい現状もしっかり映されます。
実際にこのような事が行われていたと思うとより生々しいです。
ストーリー的には看病がメインなので大きな動きは無いですが、少しメロなドラマを加えるためにテンポがぐねってしまっていたのはもったいなかったです。
そんな事する前に看病するべきでは…?と思ってしまいましたが、映画的には仕方ないかなと思ったり、当時あの場所にいたら大切な人との再会って感動的だよなとも思いました。
映像面はそこまでお金かかってないんだろうなって感じの映像で、灰なんかのモロ合成しました感はちょっと笑ってしまいましたし、基本的には建物内とその付近でのシーンが多いので背景の変わらなさは惜しいなと思いました。
7万人以上の死者が出ているというのがエンドロール後に出てきますが、今作は限定的な範囲のみの被害しか映されていないので深刻さが少し足りないかなと思いました。
NHKでの特集のようにも思えましたし、学校の授業で観るとなるととても良いものなんですが、あくまでも映画館というところでは映像面は満足できる出来ではなかったです。
一通り落ち着いて普段の生活に戻り、それでも戦争の残り香は消えない中で、小さな希望を紡いでいくラストはしみじみするものがありました。
節目の80年、戦争を実際に体験した人も少なくなってきてしまっている中で、この様に語り継いでいってくれる作品が多く生まれていって欲しいなと思いました。
10年前とはまた色々状況が変わってきたんだなと改めて感じました。
鑑賞日 8/2
鑑賞時間 15:50〜17:50
一週間早く負けていれば
導入でメイン3人がいいコだと伝わったこともあり、ひたすら辛い作品だった。
重さはしっかり伝わるが、“映画”としては…
原爆投下後から、ずっと悲惨な救護所の様子が続く。
救えた描写はほぼなく、零れ落ちる命を主人公たちと共に無力に眺めさせられる。
医者どころか、正式な看護婦ですらない彼女たちに出来ることは少ない。
いや、医者ですら出来ることなどほとんど無かった。
アツ子が黒焦げになった家族を見つけた時の心情はいかばかりか…
(鼻水や涎まで垂れ流す小野花梨の泣き顔が素晴らしい)
ただ、物語としての展開が皆無のため映画としては残念ながら退屈。
仕方ないとはいえ、看護師や市民がそれぞれ同じような格好をしているため区別がつけづらい。
メインどころは方言が微妙なところ以外はいい芝居をしていたが、モブがちょっとヒドかった。
“閃光”の直後に1人残らず大人しかったり、列車に乗ろうとする様子に必至さゼロだったり。
「お母ちゃん、水」botの子供は何故あそこまで執拗に繰り返させたのか理解に苦しむ。
メインが3人というのが多いとは思わないが、背景や心情が描ききれてるとも言えない。
他にも色々つまむなら、主役は看護学生ひとりにして、医者や看護婦長、妊婦など掘り下げてほしかった。
ミサヲの死がアッサリな割にエピローグも冗長かな。
唯一救えた空広くんのくだりはベタながら嫌いじゃない。
戦争の悲惨さを伝えるという意味ではしっかりとしたつくりになっていたとも思う。
母を探す兄弟の敬礼、特に最初の弟を背負った状態でのそれはなかなか見事。
でも映画としては(派手さやエンタメ性という意味でなく)もう一捻りほしかったです。
何より、不謹慎ながら看護婦長がちょっとエロ過ぎて集中できなかったので、そこもどうにかしてほしい。
重い主題にうちのめされますが、観てよかった作品
満席のシアターで鑑賞。
題材が題材なので、終始、観ているのがつらい場面が続きます。
健気で純真な白衣の天使たちの活躍を美化して描くような展開ではなくて、名ばかりの救護で満足な治療もできず、ひたすら死と向き合う、救いのない日々が描かれている中、時折、はっとするほどうつくしい画が映し出されるので、なおのことその痛ましさが増して感じられました。
3人の少女たちは、それぞれに惨いエピソードがありますが、ひとりひとりがその悲劇に襲われる場面よりも、後半、3人がリアカーを引きながら心情を吐露する場面や、終盤にうち2人が堤防に腰かけて語り合っている場面がことさら胸に迫りました。
過ぎた過去の悲惨な史実に留まらず、現代のわたしたちの身に惹きつけて感じられる場面だと思います。
エンドロールで流れる少女たちの歌声のあどけなさに、日々、惰性で生きている自身の来し方を顧みてひどくうちのめされました。
映画の善し悪しではない。
監督曰く、惨たらしい描写ではなく、広く知ってもらうことを優先したそうだ。
被爆者からすれば「こんなものではない」のだろう。
だが、自分が小学生の頃は「平和教育=怖い」という印象が非常に強かった。
これはもしかしたら平和や戦争の議論を避けることになるのかもしれない。
悲惨さを伝えつつも、議論を恐れないことこそが
この映画の目的だったのではないだろうか。
そして、私たちがこの映画を通してヒロシマ・ナガサキを議論し続けることが、
慈善団体の婦人が話していた「生きること、忘れないこと」になるのだろう。
さらに、それが核兵器使用の防止になることを願う。
何百回も繰り返された核実験も悲惨だが、
戦略核の使用の最後の地が長崎になることを心から願う。
全27件中、1~20件目を表示