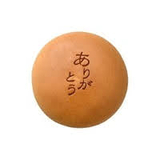長崎 閃光の影でのレビュー・感想・評価
全129件中、81~100件目を表示
少女たちの使命感
戦後80年に相応しい素晴らしい作品
長崎に原爆が落ちた後の物語という事は、情報として、知っていたものの、地獄絵図のような惨劇やはり観ていて、辛かった。あの原爆の凄まじさは、映画館の大きなスクリーンで、爆音を重低音で、感じて欲しい。主人公が10代の女性3人の看護師というのが、とても良く、効いている。若い3人があの惨劇を経験し、どう思うのか、何を感じるのか。この若い子たちの思いが、この物語全体を包みこみ、心の奥底に染みわたってくる。そして、ラストの若い3人が歌う鎮魂歌のような美しい歌声に、涙が止まらなかった。この映画は原爆を知らない、日本の若い人たちに、世界中の人々に、届いて欲しい。この重く苦しく難しいテーマに身を投じた、松本准平監督に、3人の若い女優に、そして、エンディング曲をプロデュースし製作に名を連ねた福山雅治に、盛大な拍手を送りたい。
この様な映画は絶対必要!!
特にエンターテイメントなんぞ全くありません。でもこの様な映画は絶対必要で今のご時世なら尚更。ホントならば青春を謳歌している世代が戦争によって全て失われながらも、泣きながらも自分の役割に従事する姿は私達がもしその境遇で出来るでしょうか?出来ないと思ったらせめて戦争の無い世界を真剣に考えなくてはなりません。殺し合い、悲しみ・憎しみ合う為に生まれてきたわけではありませんし。被爆された中には在日朝鮮人の人への塩対応が描かれびっくり。確かにその状況では・・差別的なところで描けないところでしょうがよく描いてくれました。戦争ってそういう事。【くすのき】の曲とエンドロールが終わっても殆どの観客は暫く席から立ち上がれませんでした。そう言う気持ちが私達には必要なのです!
長崎原爆の現実を…
アメリカが憎い
2025年劇場鑑賞218本目。
エンドロール後映像無し。
この世界の片隅にみたいに、前半長崎に暮らす人々の日常を描いて、情がわいた頃に原爆かなぁ、と思っていたのですが、割と早めに8月9日はやってきます。
なかなか被爆直後の病院をこれだけしっかり描いた作品はないと思います。本当コロナ禍の病院も真っ青の、地獄のような様相で、何もできず人が床で死んでいくのを見て普段忘れていたアメリカのしてしまった事に対しての怒りや憎しみが湧いてきます。劇中、それでも私は許す、というカトリック教徒の女学生のセリフが出てきますが、そんなカトリックもまとめて殺戮したのがアメリカなんだよなぁと思いました。この映画自体は全然アメリカは悪党だ、アメリカを絶対許すな、という作品ではないのですが、この現実を突きつけられると多少の悪感情は持たざるを得ないなぁと思いました。アメリカではこの映画観ないと鬼滅観たらダメとかにできませんかね?
がんばらんば
1945年夏の長崎で負傷者の救護に奔走する看護学生たちの話。
看護学生の3人の少女が、講義の無い夏の間長崎に帰郷して来て巻き起こっていく。
8月9日、婆ちゃんの家に届け物に出かけるスミ、赤十字病院で見学という名目で手伝いをするアツ子、父親と共に教会へ行くミサヲをみせて、そして11時2分…。
救護所や病院で奮闘する様子に加え、家族への想いややり場のない怒りや憎しみや様々な不安等々をみせていく流れだけれど、ムダに煽ったり溜めたりはなく突っ走る感じ。
それこそがむしゃら、無我夢中という感じが伝わってくるし、あまり重苦しくはないのは良かったけれど、ちょっとあっさりに感じてしまう部分も…。
とはいえ悲惨さややり切れなさと、歩き始める様子も伝わってきてとても良かった。
史実に基づく重み
分かりやすくということを優先するためか、凡庸なステレオタイプの描写が気になる部分もあるが、それを補って余りある、史実に基づく重みが心に響く作品。
小野花梨が出色。
「慟哭」としか言いようがない姿で悲しみを表現した彼女を見るだけで、世界に引きずり込まれて、その目線で物語に入ってしまった。
途中の、リアカーを引きながら、彼女たち3人が言い争うシーンは、今も各地で続く戦争を思いながら、これからもずっと自分の心に重く残り続けると思う。
原爆は、その瞬間を生き延びた者たちに対しても、被曝による後遺症で牙を剥き続ける。
「核兵器が最も安上がり」発言をした方は、そのことを知っているのか知らないのかわからないが、その方に賛同している人たちにも、この映画が届けばいいのだけれど。
8月1日からの公開で、初回の土日なのに、大手シネコンで、早朝と夕方の2回上映というのが切ない。
観客も自分も含めてシニア世代のみ10名程度。これが現実。
テーマの重要性は強く感じたが、作品としては物足りなさが残った。
看護学生の視点から戦争を描く試みは新鮮で意義深いと感じたものの、映画の表現力が題材の重みに追いついていない印象だった。
主役の3人は年齢設定(15歳・17歳)に見えず、演技にも説得力が欠けたため、未熟さや揺れ動く感情がリアルに伝わってこなかった。もっと若い俳優を起用していれば、看護学生としてのリアリティが増したのではないかと思う。
展開は淡々と進み、緊張感や山場が乏しく、体感時間は実際の上映時間以上に長く感じられた。多くのエピソードを散りばめているのにどれも掘り下げが浅く、感情移入しづらかったのも残念。
さらに気になったのが、朝鮮人への差別発言の描写。エンドロールには「実際の看護学生や赤十字の人々はそのような言葉を発していない」と明記されていたが、それならなぜわざわざ看護学生に言わせたのか。もし史実に基づいた人物がいたなら、その人の口から語らせるべきではなかったかと思う。こうした演出が、作品全体の説得力を損ねていた。
原爆の重みは、終盤の当事者の登場でようやく現実味を帯びたが、それまでの描写にはインパクトが足りず、心に迫るものが弱かった。
予告編通りの印象にとどまり、期待を超える驚きや感動がなかったのは惜しい。テーマの大切さを否定するつもりは全くないが、もっと心を揺さぶる作品に仕上げてほしかった。
静かに迫ってくるものA Quiet Force that Draws You In
原爆に関して、
深く関わったのは高校3年の時、
合唱コンクールの自由曲で、
それは広島だったので、本を読み、
広島にも行った。
そこから折を見て、
長崎のことも、
調べたり本を読む機会があった。
この映画の中で描かれるエピソードは
良くも悪くも知っていた。
ただ資料で当たるのとは全く違う、
映像が持つ静かに対象に迫っていく力に
思わず息を呑んだ。
爆裂のその瞬間の描き方は様々だけれど
個人的にはこの映画の描き方が
最もリアルで、最も悲惨に感じた。
助かった側で、助ける側の視点で
助ける場面が固定で描かれていたから、
原爆とその後のものを描く映画の中で
一番リアルに感じた。
実際の写真に残っていると思われる
エピソードも描かれていたけれど、
この映画の中では、
逆に、現実離れして見えてしまった。
しかし、教会の上に炸裂させるとは、
彼の国が宗教について語るのは
話半分に聞いておいた方がいいな、
と改めて思ってしまった。
My deep engagement with the atomic bomb began in my third year of high school. For our chorus competition, we chose a free piece related to Hiroshima, which led me to read books and visit the city.
Since then, I’ve taken opportunities to learn about Nagasaki as well—reading books and doing my own research.
The episodes portrayed in this film were ones I already knew, for better or worse.
But the quiet force of the visuals—how the film slowly and steadily approached its subject—took my breath away. It’s a power you simply can’t feel from written documents alone.
There are many ways to depict the moment of the explosion, but to me, the way this film handled it felt the most real—and the most harrowing.
Because the scenes focused on those who survived and tried to save others, in a fixed and grounded perspective, it felt more realistic than any other film depicting the atomic bomb and its aftermath.
Some of the episodes depicted seem to come from actual photographs, yet paradoxically, they appeared almost surreal within the film.
Still, the fact that they detonated it above a church made me think—when that country speaks about religion, perhaps it’s best to take it with a grain of salt.
使命を全うした少女たちの戦いの物語
日本赤十字社の看護師たちの手記をもとに脚色を加えながら映画化した作品。1945年8月の原爆投下直後の長崎を舞台に看護学生だった3人の少女たちの姿を描いた物語。救える命よりも多くの命を葬らなければならなかった悲惨な現実の中で命の尊さと生きる意味を考えさせられました。
映画初主演となる菊池日菜子も主演を見事に演じていました。彼女の今後の更なる活躍を期待しています。長崎出身の福山雅治がプロデュースした主題歌も心に染みました。
2025-114
全人類が共有し、後世に語り継ぐべきテーマ
基本的に映画の感想なんて、見た人のそれぞれの感じ方に委ねられていて、正解があるわけではないと思っているので、ここで自分の主観を披露するつもりはない。ただ、唯一の被爆国として、原爆被害の大きさ、残虐さ、永年に渡って人々に与える苦痛や影響などはこれからも発信し続ける義務があると思うし、日本人として絶対に忘れてはならない歴史的事実であって、被爆80年の節目にこの映画が作られることには大きな意味がある。
ただ1点だけ残念だったのは、朝鮮出身者に対する看護婦さんの対応シーン。あの大混乱の中でいちいち患者の出身地を確認できたのか(市内各所から運ばれてくる市民の出自を看護婦は覚えていた?、患者は身分証を持参していた?)と、若干の違和感を覚えていたところにエンドロールの「注意書き」。
何のために事実でない創作を、あの場面で差し込む必要があったのか?献身的に治療にあたられたであろう当時の医療関係者にも、大変失礼ではないだろうか。ここのコメント欄にも、史実に基づくシーンだと誤解している方が散見される。
もちろん当時の朝鮮半島出身者が様々な差別を受けていたことは理解しているが、実在の方の手記を原作としている以上、余計な創作を追加しないほうが、より原爆の悲惨さが伝わったのではないかと思う。
やや配慮・説明不足のきらいはあるが、良作。
今年176本目(合計1,717本目/今月(2025年8月度)4本目)。
私は長崎出身ではありませんが、同じ原爆投下の広島市出身です。
さて、こちらの映画です。典型的に、他国での上映が想定されている作りであり、その意味では(翻訳字幕を前提とするなら)長崎弁は他国では気にはならないでしょうが、日本で見る場合、「ある程度」理解が必要かな…といったところです(Youtube等での方言勉強みたいな動画を見ているだけで違う?)。
原爆投下の被害となった広島・長崎には共通点も多いものの、異なる点もあり、その異なる点として、長崎では江戸時代からの文化の関係でキリスト教の発達が他の地方と異なる点があります。それは広島とも当然違います。よって、映画の中でもある程度キリスト教のことを知らないと分からないところも多々出ます。もちろん、原爆投下後の救出等においても、本映画が描くように、教会などが果たした役割も当然違います(広島の原爆では、「表立って」カトリック教会等が出てくるようなことはない)。
採点にあたって、いわゆる差別的な発言については、エンディングロールで断り書きはでますが、これらも踏まえて以下のように採点しています。
--------------------------------------
(減点0.2/いわゆる強制連行と長崎のかかわり)
実際に程度の差はあれ、当事者に対する差別はあったし、映画にいう「差別的な内容は当時を配慮したものであり、当該団体または職員の発言という記録は存在しません」といった部分は理解はできます。ただ、当時の「当事者」はこの映画でいうところのだけではなく、数は少ないながら、台湾、中国からわたってきた方や、(圧倒的な兵力差はあったとはいえ)アメリカ等の交戦による捕虜者も少ないながらに被害者の一人です(人数は少ないが、一定程度の当事者はいるので、それらの団体が個別にそれぞれこの時期になると弔いの集まりを開いている)。また、当然の理として、(救助の意味の見込みが少ない)高齢者や身障者など、当時の治療などにおいて後回しにされたであろう人がいたことは容易に想定ができる部分があり、こうした人がいたことについても配慮もあってよかったのではないか、と思えます。
一方、映画でいう「当事者」は、特に長崎においては重労働に従事していたことはよく知られていますが、敗戦色が強くなるとどんどん男性は(年齢の下限など無茶苦茶だった)駆り出された事情があるため、それら重労働に従事していた当事者において、日本の敗戦色が強くなったこの当時(原爆投下の年、前年等)において、それでも労働に従事する当事者に対し、一定の理解、あるいは感謝を示していた人たちも一定数長崎にはいたことは知られており(このことは、広島とは若干事情が異なる)、このことにも触れても良かったかなと思います。
また、各国での放映が上映が想定できることは書いた通りですが、その「当時者」の当該国ではやはり支障をきたすので、「その部分」において(エンディングロールではなく、その描写の位置において)断り書きが必要な気がします。
(減点0.2/当時の火葬埋葬(土葬)と第二次世界大戦、原爆とのかかわりの説明不足)
日本で墓地埋葬法ができたのは、実は戦後です。帝国憲法において「ある程度の制限はついても」信教の自由はありました(旧帝国憲法)。ただ、ここから派生する、いわゆる「お葬式」については、人の重要な出来事にかかわることから、よほど過激な信教でもない限り当局は事実上介入しなかった事情はあります。このため、当時から今でいう火葬は既に定着していました。何より、当時は衛生事情がまだ発達していなかったので、当局もある程度火葬を推奨していた事情はあります。
ただ、ここから第二次世界大戦になると、木材等、戦争の道具に使われうるものはどんどん「徴収」されるようになったため、火葬が難しくなり、また、火葬を行うと空襲の標的になることは明らかなので、当局も当然推奨しなくなり、「一定の配慮は必要だが、まずは最低限の弔いを行い、その後、風葬、あるいは(海への)散骨等も…」といったように、火葬を極力避けるような雰囲気になっていきました。そして、木材等が実際に手に入りづらくなると(そして、男性はどんどん駆り出されますので、木材の運搬等を必要とする火葬は、実際にも難しくなっていた)、事実上それが制限されるようになっていきます。
ところが、原爆投下の直後の広島、長崎はその「現場」に当然、木材がゴロゴロと転がっている状況であり、原爆投下後ですのでさらなる空襲があることも誰も想定しなかったし(ただ、それは結果論で、第三の投下があってもおかしくななかった)、何より被害者が極端に多かったため、投下による着火でできた火も積極的に使われ、逆に今でいう火葬→土葬がどんどん行われるようになります。これは、そうした環境が「原爆投下により」結果的に可能になってしまったこと、また、公衆衛生等がさらに劣悪となってしまった2都市においてはそうしないとさらに被害が拡大するという実際的な問題であり、これは、火葬をできるだけ避けましょうという当時の風潮のさらなる例外にあたります。
このことは、実は墓地埋葬に関して当時の考えが二転三転した部分で、ある程度は説明があっても良かったのでは…と思います(ある程度このことは歴史を知らないと理解に詰まってしまう)。
(減点0.1/当事者は何歳だったのかが微妙(数え年・満年齢関係))
明治維新後、それまでの数え年を満年齢に改めることとなりましたが、明治維新のころといえば江戸時代後期~末期のいわゆる伝統的な数え年が当たり前で、国民の中でも数え年がまだまだ主流でした(数え年か、満年齢かというのは婚姻年齢等、年齢を参照する法以外などでは、そもそも本質論ではない)。これが満年齢を基本とし、定着するのは戦後のことになります(現在でも、冠婚葬祭等では伝統的に数え年を使うことはある)。
映画内で「何歳か」を自己紹介するパートは、このことについて説明があってもよかったかな、と思います(数え年・満年齢の概念がない国、まだそれが残る国等、バラバラです)。
--------------------------------------
生き方って難しい
80年の節目でもあるのでいろんな人に観てほしい
きっかけは忘れてしまいましたがぜひ観たいと思ってた映画だったので鑑賞しました!
一変した日常の中で看護学生として、人として、使命を全うしようとした少女たちの戦いが始まったー
1945年、長崎。看護学生の田中スミ、大野アツ子、岩永ミサヲの3人は、空襲による休校を機に帰郷し、家族や友人との平穏な時間を過ごしていた。しかし、8月9日午前11時2分、長崎市上空で原子爆弾がさく裂し、その日常は一瞬にして崩れ去る。街は廃墟と化し、彼女たちは未熟ながらも看護学生として負傷者の救護に走する。救える命よりも多くの命を葬らなければならないという非情な現実の中で、彼女たちは命の尊さ、そして生きる意味を問い続ける一
というのがあらすじ!
日本赤十字社の看護師たちによる手記を原案にして当時看護学生だった少女たちの視点から描かれています
原爆の話を観たのは久しぶりな気がします
テレビであるのは戦場の話が多いような…
投下後の話は記憶にある限りないと思います
長崎の資料館は昔見たことあってちょっと記憶があやふや…
でも広島の資料館は最近行ったので鮮明に覚えています
人が多すぎてかなり疲れましたが…笑
その資料館やテレビ、授業で観たドキュメンタリーなどで知っていたことが描かれていてそうだったなと改めて思い出しました
水をあげたらいけない、健康な人が放射線で容態が悪化したりなど…
物資は少ないし当時は放射線の影響とかわからずにどんどん亡くなっていくし命を助けられないのはつらいですよね
救う命より救えない命が多い
どんなに無念だったことか…
観ていたこちらもつらかったですね
赤ちゃんを産んだお母さんが亡くなった場面や背負っていた弟が亡くなってたところなどいろいろつらい
でも婦長に関してはおい!って思いました笑
実際にあったことなのかもなとは思いましたけど…
予算が少なかったのかわかりませんが思ったより悲惨な場面は描かれていなかったなと思いました
なのでいろんな人が観やすいと思うのでぜひ観てほしいと思います
そしてこんなにも悲惨なことがあった事実をこれからも伝えていかないといけないと思います
この映画を観ていろいろな想いが伝わりましたし改めて考えるきっかけになりました
この映画を制作していただきありがとうございました!
長崎も忘れない
もっとお金をかけて作ったらもっと良くなった気がする でも主人公の女...
もっとお金をかけて作ったらもっと良くなった気がする
でも主人公の女優さんはよかったです
あと、
終戦間際の日本でも、一般の人は、
チョコレートとかパイナップルとか言って遊んでたのかな?
そういう時代背景的なことが気になったけど、
手記がおおもとなんだからそうなのかな?
長崎を取り上げた映画作品は珍しいので、見ておくべきと思いました。 ...
全129件中、81~100件目を表示