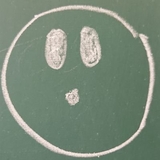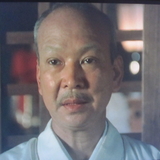8番出口のレビュー・感想・評価
全373件中、1~20件目を表示
相手は小松菜奈さんで間違いないですか?
日本ではトップクラスのヒットプロデューサーである川村元気氏と、これまた才能あふれる脚本家平瀬謙太朗氏が仕掛けた「ヒット」間違いなしの企画からの映画。初日から長蛇の列のがあったとの報告と受け、実際公開3日間で興収9.5億円を突破、2025年公開の実写映画で1位を獲得。
原作ゲームはやったことはなく、本作の「説明がしっかりされている」らしいノベライズも手にすることなく、「ヒット」しているということだけだと、全く興味のないタイプの作品だが、割とうるさ型の有名評論家、youtuberが絶賛している。
ゲームの世界観とそこに迷い込んだ男の人生の「選択と決意、父になる」の物語らしく、ノベライズもはっきり言語化しているらしい。
8番出口
・
・
・
主人公二宮はオープニングで、スマホで戦争か災害のニュースをザザっとスワイプし、ちゃんと読んでるのか、ふりをしているのか、よくある車両入り口に陣取る。
直接経験したことはないが、サラリーマン退勤時のラッシュアワーの地下鉄に、乳児を抱いた母親が乗っており、赤子がギャンギャン泣く。それをうるさいから何とかしろと母親にキレまくるサラリーマン。あるかもしれない、あった話も聞くこのシチュエーション。残念?ながらこのシチュエーションにオレ自身はあまりリアルを感じない。
想定通り何か行動を起こせるはずもなく、というか、起こす必要がない二宮は電車を降り、その後別れた彼女から「電話」がかかる。二宮は、(過去のことは分からないが、)電話の画面に見える(超美人の)小松菜奈と別れており、明らかにうだつが上がらない二宮にどうしようかと相談するのである。そうして彼は「8番出口」の世界に迷い込む流れ。
8番出口の異変については、彼の小松菜奈からの相談をどう受け止めるか、の選択および決意と全く関係のない異変ばかり。ゲームのことは知らないで話を進めるが、そこに登場するオジサンの一幕は全く二宮の脱出劇には関係がない。とこの辺はゲームファンへのサービスなのだろうということで納得はしている。
だが、彼が脱出し、「病院へすぐ行く」と言って乗った電車は、物語最初と同じ電車、シチュエーションなのである。そこで彼は、オレたち観客の方を見据え、その騒ぎの方へ顔を向けて閉幕する。「騒ぎの方へ顔を向けて」なので、二宮がその騒ぎに対して「父親になるには良しとする行動」に出た、という解釈が強いようだが、果たしてそんな行動は存在するだろうか。
この映画は、初めから二宮の妄想で、不快とされる「赤子のギャン泣き」と「他人の止まない咳」を浴びせて、やかましい音響とともに、こちらの神経を触って観客を試す。赤子と喘息といった当人にはどうしようもないことを、観客のオレたちにはことごとく不快に感じさせる確信犯。これはなかなかに上手いと思った。
また本当に小松菜奈(のような女性)に子供ができたのなら、こんな話にはならないだろ、という突っ込みも作り手側には十分承知の上だと思う。
となると、そもそも子供ができたというのが、妄想。あるいは、相手は「小松菜奈」であるはずがない。
そして同じ電車(シチュエーション)に戻った、ということは、彼は映画のはじめから勝手に妄想し、結局答えを出せずにループしている。つまり騒ぎのほうを向いたが、そのまま電車を降りた、というほうが正しく観える。初めから何も起こっていないということ。(消えたカバン、収まった咳、「ボレロ」で挟む)
つまり、登場人物はすべて主人公の持っている顔、一面。電車でキレる男ですら、主人公の顔と思ってもいいかもしれない。
今回の「不快」の演出および演技が確信犯であること。クリアしたかに見えてそうではない、という解釈も可能である点。ヒットメイカーだけど、浅い、と言われてきた川村氏の一撃。それがこの違和感、異変探しのゲームと「合っている」と思わせた点がとても素晴らしい。観客を試す、といった実験もそれなりに成果があったようだ。
そして、「意を決した」とも「また逃げた」「そもそも現実に向き合っていない」ともとれる、二宮氏の風貌(と役作り)が素晴らしい。
だけど、オレ個人はすっごい長い90分だったので、この評価。
追記
このポスター、実は二宮氏の鼻先口先のほんの少しだけ8の字から出ているんだよね。ちょっとだけ、ループから抜けている、すこしだけ「前に出る」ということなんだろうけど。
オジさんGJ!
いや、オジさんが素晴らしい。聴くところ、演じたのはベテランの舞台俳優さんみたい。私が言うことじゃないけど、よくぞご出演いただきました。不気味で鉄壁の演技力、ありがとうございます。
ゲームの映画化と云うことで、非常に限られた世界観ではあるものの、その再現度が素晴らしい。そもそも、元のゲームが素晴らしかった。実写にしか見えない映像感覚で(オジさんは流石にCG感は拭えない)続編の8番乗り場のリアリズムも、もはや異常。開発者さんはその手の専門家なんでしょうか。
映画化のテーマとしては「心の迷いが生んだ時空の歪み」→「迷いから決断する勇気」ということでしょうか。「満員電車で泣く子供」「キレた他人から怒鳴られる」「それを助ける勇気が無かった」「彼女から身ごもったとの電話」「迷ってる。どうしようか決められない(泣」、そして主人公は地下に迷う。この流れ、設定付けからゲームの舞台に突入するまで、淀みなく素晴らしい。
そして進むか戻るか、このシンプルで純粋にプレイヤーの判断力が試されるゲーム性、そして決断する力は「勇気」、見知らぬ人でも助ける「勇気」、ゲーム性と主人公の設定を重ね合わせた、「ゲームの映画化」としては予測を超えて「甘さ」「脳天気さ」もない渋くて好印象だと感じました。
細かいことを云えば、「観に来た人はみんなゲームをプレイ済みでしょう?」という感じが拭いされない。プレイヤーが間違い探しに入るのが早すぎる気がする。「異変の有無」と云われて、指さし確認で間違いを探すのは、ゲームプレイの再現に入るのがちょっと早い気がした。そして迷いだしたら、まずスマホを取り出すと思う。地下で何も判らなくとも、チラ見ぐらいするのが現代人。
また、オジさんに設定付けされたのには驚いた。成る程、元はオジさんもプレイヤーで闇堕ちしたという設定ですか。元のゲームでは8番じゃない出口から出ると単なるリスタートだけど、NPCに墜とされるのは映画ならではの面白いアイデア。あの女性が歩いてくるバージョンも遊んで見たいな。自分が一通りプレイしてからも、映画化を記念してでしょうか。いくつか異変が増えていたので、女性の方もお願いします。
あと、(説明はなかったけど、ミスリードではないと思いますが)自分の未来の子供の出現も面白い。異空間での現象なら有りかと思う。ただ、最後にあの子とはぐれて、なにか思ったりしなかったのでしょうか。何か一言あるべきだったでしょうか。それとも自分の未来の子供と判ったから、もう振り返る必要はなかったのか。
結論的に自分の迷いと迷宮のサスペンスを重ねた良作だと思います。「見つけてほしいから迷子になった」「道に迷う→心の迷い」「結論を出す勇気が出せず、自分から道に迷っている」等々、迷いに関する哲学めいたものがあるような気がして実に有意義だったかと。
あと、付け加えるなら、如何に映画の中の話といえど、あんなに可愛い彼女がいるんだから、二宮さんには頑張って欲しいものです。
(追記)
付け加えで、映画版固有の異変で興味深いものが幾つか。
「電話をかけてきた自分の彼女(同じ地下道にいた)」
「通路のど真ん中で待ち構えている少年の母親」
「開いた扉の向こうで見て見ぬふりをする自分自身」
これら自分自身や自分の味方のようで、「異変」という自分の「敵」なんですよね。自分の大切なものやトラウマが自分を惑わし襲ってくる自分自身にしか通用しない罠。
似たようなエピソードが他の映画にもあったのを思い出しました。うろ覚えですが、攻殻機動隊シリーズ劇場版「イノセンス」で、手榴弾に殺されかけたトグサが「自分の妻と娘の姿が脳裏に浮かんだ」というと、バドー「気を付けな、そいつらは死神だ」という――ちょっと理屈が掴みかねますが。その他、グインサーガという小説では主人公グインのトラウマとなる人物が自分を責め立てる、自分の心を鏡映しにした罠。
小説にして映画化もされている「1984」では、これは具体的な調査の上での拷問でしょう。どうやって調べたのか自分だけが苦手なネズミで根を上げさせたり。
「鬼滅の刃」などでも最終的には自分のトラウマと対峙することはよくありますが、故意に仕掛けられる場合もあれば、見るもの触れるもの全て自分のトラウマを連想し恐怖する場合も有り、前述3つの異変を説明するとしたら、そういうことかもしれません。よくある言い回し、「自分との戦い」と言ってしまうと、ちょっとチープになっちゃうんですけどね。
生きている空間
8番出口自体、ゲームが気になっているくらいで実況動画や実際にプレイなどはしていませんが、私の映画的価値観が合う方のレビュー動画を見て、公開から少し経った頃に見ることにしました
その方いわく、ファン映画的な部分があるため必ず実況動画や実際にプレイをしてから行くべき、実況動画やプレイが気にいればきっとハマるとのことで有名YouTuberの実況動画をみてなかなか面白そうなゲームだと思ったので少し期待値高めに設定して見ましたが、結果的にやはりプレイ映像を見ていてよかったと心の底から思います。
長尺で回す撮影手法で終わりないループを演出するのはなかなか考えられていて見ごたえがありました
二宮さんの実際に8番出口に迷い込んだときの緊迫感と喘息による閉塞感。喘息の友人がいるのですが発作がそのまま当事者のようでとてもドキドキしました
ビックリ要素はあるにはありますがわかりやすいですし、少ないです。少し身構えるくらいで十分です
人間的なストーリーは最低限。
でもそれが8番出口の異界感を生み出す絶妙な加減で素晴らしかった
ゲーム勢からするとびっくりなおじさんの正体と設定もあって原作知っている人でも8番出口を映画の1つの作品として記憶に残していくのは見事だと思いました
一番良かったのは、流行りの歌手や尖った新人を使わず、世界一有名なループ曲のボレロを使用したこと
最後の二宮さんの涙ぐみながら何かを決意した顔から一転、真っ黄色な8番出口のロゴが全面に出され、ボレロが大音量で流れる展開は、思わず「お見事!」と叫んでしまいそうでした
さて、この作品に向く人と向かない人ですが、私が考えるに向く人は
・情報量の少ないメタファーを感じ取れる人
・概念的な恐怖を感じ取れる人
・8番出口というゲーム性やゲーム空間が合う、好きな人
は特に刺さるのではないかと思います
逆に向かない人は
・恐怖対象が人や幽霊など具体的でないと怖く感じない人
・メタファーが苦手、感じにくい人
・映像的な部分でいろんな変化を楽しみたい人
・津波や濁流の映像を見ても平気な方
はあまり見ても刺さらないのではないかと思います。
他にも色々喋りたいですがひとまずこのあたりで気になった方は是非ゲームを見たりプレイしてから映画を見ることをおすすめします
20分で終わるジャンプスケア・ループ系ホラーゲーム、それを90分の映画に。
ゲーム内容、世界観、登場人物を脚本家なりに解釈し表現しているのでとても見ごたえがあるし、作者の思いも見て取れてよかった。
同じ場所をひたすらループする恐怖、焦燥をBGM、カメラワーク、人物で表現できている。見ているこちらも心臓が締め付けられるような気分、凄みがある。またゲームに負けず劣らずのジャンプスケア要素が多い、予備の心臓が必要かも。
不快なトラウマ表現もあり、お化け屋敷レベルでも本当に無理な人は映画館では視聴できないと思ったほうがいい。
♦良いと思ったところ①最初と最後
「走行する地下鉄車内、子供の泣き声にキレるサラリーマンとひたすら謝り、赤ん坊をあやす母親。周りの人は気が付かないフリをして誰も母親を助けない。」しかし主人公もその一人、結局大音量のボレロを流すイヤホンでサラリーマンの怒号に蓋をして気が付かないフリ。彼には母親を助ける勇気はなかった。
上記がプロローグの内容、これは後々地下通路をループする一因となった。
そしてラストシーン、主人公はプロローグと全く同じ状況に遭遇する。「地下鉄車内、サラリーマンに怒鳴られる赤ん坊の母親を誰も助けようとしない。」
徐々に音量が大きくなるBGMボレロ、主人公である迷う男の顔に真正面から徐々にズームが入る。迷っている様子。どうなるか。
迷う男、意を決して母親とサラリーマンがいる方向へ動き出す。タイトル「8番出口」が大きく出て終幕。ボレロに合わせて流れるエンドロール。
ループものの最後にふさわしい終わり方、最後の最後に主人公は迷いを振り払い、母親を助けた。人間としての成長と真のループからの脱出が同時に描かれていて圧巻。これが見たかった。
♦良いと思ったところ②キャスティング
本当にゲームから出てきたような風貌の河内大和、「歩く男」はこの人にしかできない。
物語の構成から必要な主人公「迷う男」、冴えないフリーター役は二宮和也ピッタリ。
ほかの出演者も全員実力派で演技も自然、映画の雰囲気に自然と引き込まれた。もう少し下手な人を出演させておけば心臓が擦り減らずに済んだかもしれない...
所感
なぜ地下鉄通路のループにハマってしまったのか、通路をNPCのように歩いているおじさんは何なのか、後々繋がってくるので納得。主人公はプロローグの出来事がずっと気がかりであることを、彼女との電話や、異変の描写でしっかり示されてるし。
ダメ出しするとすれば「よし怖がらせちゃうぞ~ホラホラホラ~」感が一部ある。ジャンプスケア・ホラーだから当たり前ではあるけどもう少し巧妙にできたところもある。ねずみのシーンとか。
地下鉄の出口が無限ループの迷路になって出られない。
主人公が地下鉄を降りて、地上へ上がろうとしたら出口に辿り着けずに無限ループを繰り返すようになった。
どうやら「8番出口」まで辿り着ければ脱出できるようなのだが、そこへ行くまではルールを守らなければならず、守らずに(注意書きの条件をクリアできなかったら)進めばまた元の場所に戻されてしまうのだった。
幾度もループを繰り返すうちに、主人公は不思議な面々との邂逅を重ねていく。
モブキャラと思われた主人公以外の登場人物も、同じ罠に嵌ったプレイヤーだったとは!彼等は彼等で脱出への道を同じように探し求めていて、ルールを逸脱できなかったのだ。
子どもを置き去りにして出口へ進んでしまった人は・・・脱出できたの?
やっぱりゲームかな?
しばらく映画館から離れていたら、観たかった作品も軒並み公開終了してしまいました。そんな中、本作品がまだ公開していたのは嬉しかったですね~。是非とも大画面で観たかった一本です。でも、期待が大きすぎたのかな?入場者も思ったより多くて驚いたのですが、ファンの人ごめんなさい。自分にはハマりませんでした。
元々、賛否両論分かれるクセのある作品だと思いますが、何か物足りなかったですね。エンドロールが人気歌手の歌でなく、クラシックを使ったのは好感が持てたのですが・・・
【ネタバレ】
別れたはずの彼女に妊娠が発覚して、思い悩んだニノが異世界に迷い込んだって感じですかね。地下道の迷路の中を、異変を見つけたら引き返し8番出口から外に出る話。
ニノ、おじさん、子供とそれぞれのパートで話が進んでいく。
子供と絡むことによって、ニノの心境に変化が生まれるんだけど、この辺がありがちのドラマと言いましょうか・・・良い話なんだけど、何か説教くさい?若干、興ざめした部分があります。
異変を探すところを見て、ストーリーが展開していくんだけど、やっぱり異変は自分で探したいかな?「8番出口」のゲームはやったこと無かったんですが、本作品を見たらちょっと興味が出てきました。映画としては、ちょっと面白みに欠けるけど、ゲームは楽しくプレイできそうです。
ものすごくストレスを感じた(褒めてます)
予備知識なし、あまり評価高くないらしい、という前提で、期待せず観に行きました。結果、面白かったです。
確かに「世にも奇妙な…」だと言われればその通りですが、ほぼ展開がないのに1時間半飽きなかったし、恐らく制作陣が狙った通り?のストレスを感じて、最後は納得できるエンディングでした。
終わった後から思ったのは、二宮さんと少年のストーリーは、少年だけのものだったのか?どこかで分岐したのか?
少年のラストはあれがトゥルーエンドなのか?
1つだけ分かっていることは、おじさんだけバッドエンド(お気の毒)。
〜実はゲーム、実際体験したら怖い〜
小説が原作の作品だそうですね。観てから知りました。劇場で何度も予告編見て気になったので鑑賞しました。
ある条件をクリアしないと脱出できない無限ループに迷い込んだ主人公。迷い込む前と後で、行動が変わる姿も描かれます。無限ループ脱出の条件としては映画で見せる作品としては分かりやすいもので、ゲームとしてプレイする分にはかなり初級のルールかな。
ただもう一つと見所として、主人公の身に起こるトラップがどんどん過激になっていくことや、同じ運命に巻き込まれた人達の恐ろし過ぎる運命も描かれます。(ゲームの一部になっちゃうみたいな?昔からよくある鉄板ホラー)
細かいこと考えないで、何かテーマを期待しないで観るのがオススメです。個人的には見て楽しめました。
日本のホラーは〇〇の表現を規制しろ!
日本のホラーは妊娠中絶流産の表現を規制しろ!
話もまとまっているし、ゲームの世界観やら異変やら引き継いでるけど、うっす!!!!
日本のホラーは妊婦と未来の自分の息子を出したらホラーになるの!?意外性も伏線もないから、あんなに広告費出して何度も見たいような爽快感がない!
登場人物の行動謎すぎて、キャラ萌えも共感もできなかった…
ずっと
8番出口
つまらない
でサジェストしてる
津波表現も、「安易な恐怖表現」のアレしかないから、他のホラー表現も物語全体な流れもアレ
多分津波の表現を気にする人は、他の部分が気にならなかったんだと思うんだけど、そもそもの問題で「こんなに絶賛される作品ではない」というのが結論というか、単調というか、予想通りというか、ポエムというか素人のつくるフリーホラーゲームを見てきた感じって表現が一番あうよ!
ポスターのアレコレとかも本当に気付くと面白いところがあるから、脚本があわなかった
でも多分10代とかはささるかも………いや、ニノ世代のサブカルに触れたことない男性?
いや、いやうーーん?????
誰が面白いと思うのかわかんない
体験
劇場で映画を観ることは、アトラクション等と同じ一種の体験型エンターテイメントであるという感覚を、この作品は分かりやすく伝えてくれる。メッセージやら伏線やら何なやら、そうしたものは物語の核として必須アイテムだが、そればかりに気を取られていては、恐らく”映画を楽しむ”という状態にまで心が持っていけない。この作品は、登場人物を名前から何まで結構ぼかして写し続けることで、観客がドラマに配るリソースを強制的にカットし、謎の通路とそこで起きる超常現象に翻弄される人々と出来るだけ同じリアクションを観客が取れるように、空間を組み立て続けた。あの通路と似た閉塞感を持つ、映画館でやるからこそ輝く演出方針だ。
最高の評価を付ける理由はただ一つ。私は、映画館で映画を観たあとの、まだ映画の世界に居るのではないかという感覚がどうしようもなく心地よく感じて好きなのだが、この作品を観たあと、今までに無いような強さと重さと深さで以て、私はその感覚に飲み込まれたのだ。閉ざされた空間で巻き起こる超常現象から逃れ、現実に帰っていく。主人公と同じ状況だからこそ起きた、鑑賞後も残留する没入感の飽和。あれを超える体験は、断言するが、この作品以外では絶対に味わえないだろう。
単純なゲームをうまく映画化したのには感心
周りを見ると人がごった返していて(年配の方がいたのにはびっくり)注目度は高いと思わされた。
最初、映画化を聞いた時には成立するのかと思ったが、迷い込む前後で話を膨らませて脱出したい目的を持たせ、帰りたいと思わせるのはうまいと思った。
肝心のお話だが、劇中のニノと異変を探していくのかなと思い、一緒になってじっくり看板やら見るも異変の殆どはこことは別の事象。異変がないと話が単調になってしまうので、 様々な異変のバリエーションで見せていったのとか、いつも歩いているおじさん、子供に焦点を当てて話を膨らませていた(おじさんが女子高生を化け物でカウントしていたのには笑ったw)。
ゲームをうまく映画化してるなぁと思ったものの、つまらなくはないが実写化するとこんな感じかな程度で可も不可もない感じ。エンディング、迷い込む前にループしますかw
明るいホラー
映画館で見なくてもいいかなぁー
ゲームじゃなくて 実際なったらそうなるよねって作品
世にも奇妙な物語に近い感じはします
実際に巻き込まれたら
何なんだよぉおぉ ふざけんじゃねぇぞ バカやろぉおぉぉ ってなりますよ
その点で歩くオジサンは 居た価値があったと思ってます
奇形ネズミは うえぇぇってなりました
洪水は ほっときゃ出口までいけんじゃねとか達観してたら
ニノがあの状況で子供助けたのは ビックリした
まるで舞台劇だね。
SAWとかよくある状況の作品だね。
何度も何度も繰り返す。それぞれも事情があるんだろう。
小松菜奈さんあまり出番なかったのが悔やまれます。
川村元気さんが監督なんだ。ニノも脚本に絡んでるだね。
招待券があったので観ました。
新感覚でした。
求めていた内容ではなかったが見所はあった
最初のBGMで「あれ、これデ●モンの映画だっけ?」と思ったのは私だけじゃないはず…冗談はさておき…。
原作ゲームの内容は既に知っていて、「アレをどうやって映画化するんだ?」と興味が湧いたので見に行きました。
原作ゲームは見慣れた地下鉄通路で行われる怪奇アドベンチャーで、妙にリアリティのある地下鉄通路の景色とそこで起きる異変の不気味さやシュールさが印象的で奇妙な面白さを感じる作品でした。
だから映画になる場合も不思議でシュールな異変の数々を割と軽いノリで淡々と進んでいき、最後に「やったー出れたー!」くらいの感じになるんかなー?って思っていたのですが、この予想は大きく外れました。
以下個人的に悪かった点と良かった点を挙げさせていただきます。
【■悪かった点】
・主人公の抱えてる問題やホラー要素が強調されすぎてて8番出口の魅力が薄れてる。これ8番出口でやる必要ある?
・要所である生理的不快要素(嘔吐や不快爆音)。
・主人公の葛藤とか家族とか赤ちゃんのこととかどうでもよくて「異変」をもっと出してほしかった。
・主人公の喘息設定。正直咳混んでる場面を長々見せられてもうるさいし不快…かとおもえば後半全くそういう様子がなくなる。
【■良かった点】
・個人的には人間の内面描写にテーマを置いたことは否定派ですが、それを加味した上で見返すと上記の悪かった点に上げた要素も意味があり、主人公たちの抱える問題と異変がリンクしている点はうまいなと感じました。
・おじさんの掘り下げ。原作ゲームでは一切が謎の存在であるおじさんでしたが、映画での味付けは嫌いじゃなかったす!
・異変を見せる際のカメラワークが良く(特に前半)てゲームを知ってるとニヤリとできる場面が多かったてす。
・原作にない異変ポイントがありワクワクしました。
・異変の中でスマホや置いていった荷物がどういう扱いになるかなどちょっとした気になるポイントを見れてよかったです。
・俳優さんたちの演技はいずれも迫真で素晴らしいです。
個人的な総評としては「8番出口としても人間ドラマとしてもホラーとしても中途半端な作品」といった感じでした。
映画にする以上何かしら惹きつけるテーマを決めて作らねばならないのは承知ですが、私が求めていた8番出口はコレジャナイ。もっとシュールな作品なのかと思いきや中身は終始シリアスで息苦しく前提条件から合っていなかったんだと思います。
ただ、異変と人間の内面を織り交ぜた脚本は挑戦的でよくできており、雰囲気や俳優さんの演技などは申し分ないので作品としてはそこまで悪くないと思います。
私のようにゲーム版のイメージを強く抱いている人よりも完全初見の人のほうが楽しめるかもしれません。
最後に一つ書きますが、最終的に主人公は8番出口のルールを一つできていないんですよね…その意味ははたして?
自分なりにラストシーンを考えてみました
歯医者、エッシャー、司法書士、おじさん、・・・異変に気付いてハイもう一度。ちょっと飽きてしまいました。
現実の問題から目を背けてスマホばかり見ていると、心の迷宮に迷いこみ、問題を解決する行動を起こさない限り、困難な事が繰り返し襲って来ますよ。自分は、そう解釈して見ていましたがどうなんでしょう。
主人公・二宮君の心の迷宮にしては、歩くおじさんがやたら登場、自分のパートまであるのに対して、元カノの存在は気薄で、ほとんど描かれません。この事に凄く違和感を感じました。
奇形ネズミや洪水は二宮君のトラウマなのでしょうか。あの程度の異変を克服して戻ってはいけません。
自分だったらラストは、駅員役の桜井君(別に大野君でもいいけど)が登場、「大丈夫ですか?出口は、こっちです」引き返せ引き返せの看板の下、駅員さんの方に笑って近づいていく二宮君の後姿で終わります。
予備知識ゼロで鑑賞、ストーリー展開に映画としての魅力を感じる事が出来ず★★とします。
明るい明るい不条理劇
◉哀しげなワン・シチュエーション
達者な役者がほぼ一人で芝居を演じているのだから、そこから何かを感じ取れるはずと言う割切りとか、まだまだ物語にはこの先のドラマがあるのだと言う強烈な想像力とかが要求されていたのかも…と思ったのは、映画が終わってからのこと。
やはり強烈な肩透かしには違いなく、寸劇が続いただけだった…ような気もします。ポスターに恐るべき映像が現れるとか、脱出先の酷く悪い未来が垣間見えるとか、気持ち悪くもいつの間にか現実世界の苦悩が解決してるとか、別の展開を強く差し込んでくれないと足りないように感じました。
◉さぁ、不条理の海に身を預けて
ところが、通路と言う単なる手段だけを延々と見せられる、実に不思議な展開であるのに、目が離せなくなっていたのは、紛れもない事実。微妙な差異が面白かった訳ではないです。
そうではなく、車内で赤ん坊を抱いた母親が怒鳴られる事件があったが、男はいつも通り、会社に向かっていただけではないか? 何がいけない、何が男に起きたのか。何でこの運命を享受しないといけない?
きっと私らは(勝手に複数にしますが)不条理から目を離せなくなったのだと思います。みんな、薄々感じていながら直視出来なかった、自分の人生や、すぐ身の回りの世界の理不尽を噛み締めたくて、この不条理劇を観続けたのだと思えてきました。当たり前に存在して、私らを簡単に絡め取る不条理を、現実を取りあえず忘れて見ていたかった。
「ありきたりの日常」がもっとも怖い
通勤や移動でよく東京メトロを使うので、映画のタイミングでメトロが開催したツアーの本の宣伝や、実際にただの地下鉄の出口に黄色い映画のタイトルが入ったショッパーを持ったひとたちがたむろしているのが気になっていた。今回ヒットしてから鑑賞したが、実際休日の映画館はカップルや親子連れが多く、ホラー映画などを見ない客層も取り込んでるんだろうな、と実感した。
映画そのものはそんなに複雑ではなく、自分は知らなかった有名なゲームを映画にした、というのがどうやら見どころのよう。原作はプロデューサーで小説家の川村元気とあって、視点というか、この映画のポイントとなるようなミニマムなキャラクターと、人物設定がなかなか良いな、と思った。小説と違って背景説明がなく、そのまま「8番出口」に連れてこられたような錯覚を観客にもってもらう演出は、なかなか作り手としてはしんどかったように思うので、その点はなるべくドラマのテンションを保つ工夫(音や明かり)も欠かせず、よくできていたと思う。
映画そのもののテーマは、たぶん「日常がもっとも怖い」ということなんではないかと感じた。赤ちゃん連れの母親を怒鳴るサラリーマンというのは非日常的だが、見て見ぬふりをするひとたちはそのまま「日常」で、恋人から妊娠を告げられる主人公は非日常的だが、電話に出づらいところで声をひそめたり、とまどったりするのは「日常」だ。
そんななんでもないところの「日常」の恐怖の象徴が、この「8番出口」の殺風景な地下道なのだと思う。そして、出られないというのは、おそらく「永遠に繰り返される日常」の比喩で、そこから出るためには、ささいな違和感や異変に見て見ぬふりをせず、同じことを繰り返すのではなく、「引き返してもう一度そこを通る」必要がある。恋人との象徴的なシーンは、人生を繰り返しにしないため、無感動な日常から「生きる」ために必要なつながりを示している。
歩く男と少年が、いっしょにいるのに意思疎通が出来ていなかったように、異変に気が付かなければ、無理やりいっしょにいる人間を道連れにし、永遠に出口から出られずにとらわれてしまう。この対比として主人公と少年は、言葉を交わして意思疎通ができるようになり、地下鉄で見て見ぬふりをしていた自分を客観視できるようになったことで、出口を見つけられるのだ。
その意味では短い映画ながらシンプルで筋が通っていて、ホラー映画にありがちな理不尽な死では終わらず安心して見れる作品である。
意見は分かれるかも?
これ、ホラー寄りの作品だから、意味を求めすぎないほうがいいと思う。
原作はゲームでありプレイはしたことないが、たまたま映画を紹介していたTV番組でゲームを芸能人がプレイしていたので、ルールは理解して映画に臨んだ。
難解な迷路に閉じ込められた主人公(ニノ)がルールをつかむまでの過程を長めにとっている。それでもテンポが悪いこともなく、別の人視点(歩くおじさん)に移っても、その視点が戻ってきても、流れがスムーズだった。
そういえば!歩くおじさん、子供を置いて「偽の出口」に行ってしまったので、自動的に歩くだけの人になってしまったのだろう。。。
それでも、1時間半ほどの映画なのに長く感じたのはなんだろう?決してつまらなかったわけではないのにね。人の感覚というものは不思議だ。
内容が非常にチープ過ぎで残念だった。
赤ちゃんが泣くシーンから始まり泣くシーンで終わる、非常にチープな映画であった。「8番出口」という面白いゲームを、主人公が父親としての自覚を持ち始める映画にしてしまった(印象を与えた)ことが非常に残念であった。辛口で大変申し訳ないが、良い映画ではなかった。
全373件中、1~20件目を表示