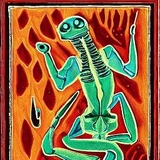ドールハウスのレビュー・感想・評価
全428件中、161~180件目を表示
面白かった
・展開の調子が観ていて気持ちよかった。子供たちだけで遊んでいる際に包丁などを片付けて普段から気にしていますっていう日常でまさかドラム式洗濯機の中で窒息しているなんてと身近にある事故の原因というのは色々あるのだなぁと怖くなった。
・ドラム式洗濯機の蓋を開けた時の長澤まさみの顔が楳図かずおのぎゃあばりの迫力だった。
・何で夫が看護師なのかなぁと思っていたらケガを逐一治療したり、セラピーを受けた際に現場に近いとこにいたりとかっていうためかと思った。
・人形に自分の心の欠損を埋めてもらうっていう長澤まさみの感覚はわからなくないなぁって思えたりする。かなり情を注いでいたのかと思ったらあっさり物置の片隅にってなってかわいそうだった。けど次第にその人形がやばいことが分かっていくとあのまま置いておいて処分できたら・・・と思った。
・礼はとりつくタイプなのか、お祖母ちゃんにかみついて血が口周りについていたようだった。腕時計の金具も嚙み切っていたようだった。
・人形に人間の骨が使われているというのはとても怖かったのと意外と考えた事なかったなぁと思った。人形なのに動けるのも骨格がしっかりしているからなのかな。
・途中で、人形がどういういきさつ出来たのかの話がわからなくなり、娘、行方不明になったって言ってたっけとかで少しつまづいてしまった。その後、改めて説明があって助かった。娘の生き人形を母親の遺体とともに土葬して埋めたのか娘の遺体と一緒に埋めたのかでこんがらがってしまった。
・土葬の甕?から抜け出そうとした際に幻覚に2人が囚われた。その世界から抜け出す際に亡くなった娘が人形にとりついている礼を連れていく所が泣けた。あぁこれで成仏したのかと思った。しかし最後の最後で霊の娘は母親の事が嫌いだったという話になって埋めたはずの人形が戻ってきて映画が終わった。
・そんな嫌っていた礼を母親は何で一緒に埋めてくれといったのだろう、と思った。証拠隠滅だったのだろうか。
・ただその危ない人形が地域のフリマに出てたのと出所の曖昧さがほんのり気になった。
・長澤まさみって美人だなぁと思った。
ねえ、途中で監督代わった?
ドール物で怖い(面白い)のは既にミーガンあるからさー、と少し斜に構えて観てました。観てたんです。そしたらちゃんと日本的湿度の高いホラー要素満載のミステリ作品でした、が、子供が酷い目に遭うのは本当にダメだしストーリーに必要な要素だとしても安易にそういうエピソードを使って欲しくないかな。辛いので。
ということで、海野(ポリス/安田顕)と冷泉(呪禁師/田中哲司)出てきたらもうそれは堤監督のSPECなのよ。祝詞唱えたらポニシュシュで「AKBかよハロプロにしろよ!」と脳内でセリフが再生されてしまうのよ。絵作りも光も意図的に代わってる感じもするし。絵作りと言えば大禍時みたいなユーチューバーのやっすい感じがめちゃ良かったけどあれ本当ならばかバズるだろ?普通。
心の中の声としては、見守りカメラの映像は最後まで見ろよ、です。
とはいえしっかり怖いので舐めてかかると椅子から飛び上がるよ。
あと、エンディングがずと真夜で少しだけ嬉しかったな。
やっぱ久々に劇場で見る映画は最高。ICEE最高!人工甘味料反対!
それではハバナイスムービー!
生き人形
日本のアナベルになれるかな
やっと観に行けましたー💕
全体を通して、とてもよく出来たホラー作品で、とっても面白かったです。
最近のホラーの中では1番良かったです。
最後まで二転三転していって、どこまでが現実なのか幻覚なのかわからず、ずっとドキドキしてました😊
ドキッとする場面もあって、怖さもあり本当におもしろかったです。
これで終わるの?まだ続くの?どうなってるの?と、すんなり終わらないところも楽しめました。
私の家にも10cmから60cmまでのドールが30体ほどいます。もちろん日本人形ではないですが、
最近はなかなか可愛がってあげれてなくて、3、4年も同じ服着てる子もいるので、少し構ってあげないと、30体全てがワサワサ動き出したら大変だわって思ってしまいました(笑)
ツッコミどころはちょっとあります。
神無島へ行くとき、人形除霊師の神田は釘を踏んだから一緒に行かなくて、「それくらいで行かんのかい!」と思ってしまいましたね。
神田が一緒に行っていれば、もしかしたらラストが変わってたかもと思ってならないです。
あと、ガラスの破片で髪の毛はあんなに切れないでしょう(笑)
ありえないよねって笑ってしまいました。
母親から虐待を受けていた礼(あや)は、人形になっても一緒のお墓にいるのが嫌で、自分の意思で逃げ出したように感じます。
誰かに愛されたかったのかもしれないですね。
佳恵が礼の事を可愛がってた時は、怪奇現象が起きなかったし、人形の顔もだんだんと可愛くなっていって、幸せそうに微笑んでるように見えました。
貞子も伽倻子もアナベル人形も呪いの裏には、全て悲しいストーリーがあります。
そう思うと少し悲しいお話に思えてきます
しかし、悲しみや苦しみを、憎しみや恨みに変えて、直接関係のない人に向けて、怖い表現の仕方をするのは本当にやめて欲しいです。
この終わり方だと、続編がいくつでも作れそうですね。
礼は、日本のアナベルになれるでしょうか。
Jホラーはあまり観ないのですが
期待してなかったけど良かった
じわじわと怖がらせる手法が丁寧で面白い。「エクソシスト」の影響も感じる。
矢口史靖の作品は結構好き。ただこの人は、いつもシングルヒット的な作品ばかりで、いつかホームランを!とコチラは見ているのですが…。
今回も残念ながらシングルヒットか二塁打ぐらいの作品でした。
それなりに娯楽作品のレベルを維持していること自体は素晴らしいことだと思いますが。
で、今回は「ホラー」。
じわじわと怖がらせる手法が丁寧で面白い。
「エクソシスト」の影響も感じる。田中哲也はマックス・フォン・シドウだね。
もっと怖く演出できそうだけど、そこは矢口史靖らしくどこかユーモラス。「エクソシスト」のようなゾクゾクする怖さまでいかない。そこまで狙っていないんだろうね。
「もしかして、あれが幽霊?」的な後で気づくと、ゾ〜とするような趣を目指している。それが「リング」を代表とする今までの日本のホラーへのアンチテーゼでもあるのかもしれない。
ラストにかけては、結構編集が凝っていて、見る側を混乱させながら、ハッピーエンドを迎える。だが、その後に実は、と本当の恐怖が襲ってくる…。
このラストを矢口史靖はやりたかったのでしょう。ここが一番面白い。
(本当の娘は車の中で叫んでいるが、長澤まさみと瀬戸康史の夫婦は、気づかずに呪いの人形をベビーカーに乗せて幸せそう。それは人形の思いが叶ってしまった!という…。)こわ〜。(笑)
ホラー苦手な自分でも。
ホラーは苦手です。最近知った言葉ですが「ジャンプスケア」が苦手なんです。
「ジャンプスケア」(ご存じの方は多いと思いますが)突然大きな音や恐ろしい映像を出すことで観客を驚かせる映画テクニックなのですが、このびっくり箱みたいなのがダメなんです。
このテクニックは、ハリウッド映画や日本の映画でも多用されています。
「ドールハウス」でも使われていますが、多くは使っていませんでした。
「ドールハウス」は、誰でもわかるびっくり箱のような怖さ驚きではなくて、ちゃんと考えさせてくれる、お話しでちゃんと怖くさせているように思えました。
個人的に好きなホラー作品「リング」とかと似たような演出展開だったように思います。
繰返しになりますが、ドッキリ(ジャンプスケア)を繰り返して怖い印象を与える作品よりも、日本の怪談のようにぞわぞわっとする、そういうホラー映画が好きです。
お話しはぞわぞわとさせてくれて盛り上がるのですが、その途中の佳恵(長澤まさみ)の言動が「仄暗い水の底から」の母・淑美(黒木瞳)を思わせたり、ラストの方では、佳恵と忠彦(瀬戸康史)が連れ立って「場所」に向かうシーンは、まんま「リング」の竜司(真田広之)と玲子(松嶋菜々子)なのかと思えました。
これは 中田秀夫ホラーをオマージュしてるのでしょうか。
観終わって、そんな感想も持ちましたが、トータル的にいい感じなホラーだなぁって好感が持てました。
その理由は、やはり、びっくり箱をあけるような単純な怖さ=ジャンプスケアが少なかったことだと思います。そして、日本のねちっこい怪談話のような怖さも好きな理由のひとつだと思います。
もちろん、ジャンプスケアが好きな方も多くいると思いますが、Jホラー=怪談のような作品ががもっと増えてほしいと思いました。
怖かった、、、
なかなか怖かったです。悲しい物語でもあったし不気味でホラーとしては十分楽しめました。けれど後味が悪いです💦謎が謎を追っていっても、エンドレスの恐怖というのは解決された感がなくて不消化気分。「しまった」じゃないよ。と思った方が私の他にもいらしたら、ちょっと一緒にそうですよね~と共感したい気分。
長澤まさみさんはさすがに上手かったし、人形も怖かった。田中啓司さんはどんな作品でも安定の演技で出ているのですが、今回はなんかちょっとコメディっぽくなってました。そのためホラー感が薄まりました(笑)こういう歴史をもってきたホラー話というのは最後未解決的な感じで終わることも多いですが(リングもそうだし)私としては人間が巻き起こした怨念であれば、それが成仏=浄化した形で終わって欲しいと思ってしまうため、後味のよいホラーが次は見たいです(おススメあれば教えて下さい)とにもかくにも十分怖くて楽しめたのでぜひ♪
ちゃんとしてるなぁ
2025年劇場鑑賞185本目。
エンドロール後映像無し。
日本人形の恐怖を描いた「恐怖人形」を観てオレの思ってたんと違う!とツッコんだ皆さん、お待たせしました、思ってたやつです(笑)いや恐怖人形はある意味面白ホラーなのであれはあれで観ていただきたいのですが。
人形ホラーだとチャイルド・プレイとか、アナベルシリーズが有名で、洋画が優勢ですが、髪が伸びる日本人形の話は昔からあって、明るいところで見ても普通にちょっと怖い日本人形でホラーをちゃんと作ってくれた事に感謝です。
今回の人形、意外と優しいところがあって、半殺しで済ませてくれます。後結構取り返しつかなくなったら夢です。血もなるべく最低限になるよう抑えめにケガさせますし、突然大きな音で脅かすなんて絶対しません。
観てる側は観てる側で、そんな雑に人形扱って大丈夫か?と特に風吹ジュンが心配になりますし、唐突に安田顕やら田中哲司が割と後半に出てきますし、緊張感が高まる中今野浩喜がお坊さん出てくるのはコントになっちゃうから!
人形の正体もちょっと自分には予想外でしたし、田中哲司が出てきてからはもしおうちに呪われてるっぽい人形来た時はこういう事が必要なのかぁ、と参考になったり、なんで自分がやってほしいことやってくれてるのに邪魔してるんだろう、と思っていたら納得いく展開でちゃんとホラー作ってくれてるなぁと感動しました。
子役の子がある時見せる表情が怖すぎて、自分も他のお客さんもちょっと笑ってしまいました。
あまり怖くなかった
ジャンプスケアを狙った演出はところどころあったのですが、お約束な場所での演出だったので怖さとしてはそこまで感じられませんでした。
最後の展開「霊媒師さん、そりゃないでしょ〜」って思ってしまって、そこがモヤモヤしてしまいました…あんな偉そうなこと言っておいて、そこ間違えるんかい!!みたいな。多分ドンデン返しを狙ったのかもしれませんが、「えー!そうくるか!」という感じではなく「いやいやいや!それはないでしょう!」という感想を持ってしまって、なんだか不完全燃焼でした。
完成度の高い映画で、無駄なく、暇な瞬間がなかった
非常に伏線が細かく、丁寧に描かれており、無駄なシーンが一つもなく、完成度が高い映画
見ていて、暇だなと思う瞬間が一度もなかった。
洗濯機という、特定のオブジェクトを印象図ける手法もすごいなと思えた。
キンキンといった音で危険を表す様にも間違いがなく興奮できた。
たが、引っかかる点が1つある
これは母の愛を描いた物語ではなのだろうか?
途中まではすごく感動的に思えるシーンもあった
確かに、これで正解なのか?と一瞬思ったりもしたが
ああいった着地もあるのだろうと、
過去のトラウマを乗り越える
母の愛と再生を描く物語なのかと思っていた。
だが最後のあのオチはどうなのだろう?
救いがないなと、もう少し描くべきではと思ってしまう…
ホラーを扱う娯楽映画だから仕方ないのだろうか…
またオチを知ったうえで振り返ると、気になる点がある
人形と出会う直前に母は、一瞬決意をしたように見えた、娘の遺品を捨てようと
だがその時、人形の意思に導かれ人形と出会わされたように見える。
だとするとこの母は人形などなくても構成できていたのではないか、
人形がむしろ母の、家族の再生に無理やり入りこみ、悪さをしているだけなのではと思えてしまう
…まぁ、オチがきちんと人形を供養してくれていればこういった
人形が悪なのではなんて見方をせずに、良い物語だと思えたと思う
賞をとれたので、「2」を狙ってオチを変えたなどあるのだろうか?
2がもしあるなら、描き切ってほしいと願う
(勝手な予想と感想です)
ホラーだけどミステリーとしても秀逸…
善意は人の為ならず/地獄への道は善意で敷きつめられている
寝落ちせず観れました!
評判どおりおもしろかったです
エンドロール後の映像はナシ(good)
おもしろいな、と感じた点
・序盤の「1年後…」の左上のテロップがPAN-DOWNと連動して画面上の電線沿いに消えるカット(gJ)
・電話で「触らないでください!」って喋った側からツカツカと傍らから同僚がやってきて、パチパチと拘束を手際よく外して「わー!」って持ち上げるシーンの間合い。吹き出しそうになるのを堪えるのが大変でした!
・ナマグサ坊主が実際に居そうなキャラクターでおもしろかった
・ドラム式洗濯機のドアガラスの歪みと主演の表情を組み合わせた心理表現(ベタではありますけどよかった)
ホラー要素はありますが、そんなに怖がらせることに重点を置いた作品では無いですね。ミステリー寄りかな~。
怖いのはそうなんですけど、わりとソフトに抑えてる印象です。
直接作品には関係ない話ですけど
猫を先に飼っている夫婦に赤ちゃんが出来ると、大概の猫は赤ちゃんに嫉妬するから手放す事になっちゃうって話もありましたね。
この作品では、自分たちの常識や価値判断をそのまま思い込みで「善かれ」と終盤の行動を見誤ったわけですけど、そういうのってよくあるよね~。とは思いました。ちゃんと相手の話や気持ちを聞き出したり引き出す作業を怠って、自分たちの都合で拙速の行動を起こして余計に状況を悪化させたりするパターンて太古の昔から連綿とありますよね。
最初の事故についてですが、軽く確認したところ少ないながらも数件発生しているそうですね。そんなことあるのかな?って気にはなったのですが、大概は閉じ込められて酸欠によるものらしいです(稼働して…というのはまず無いようで)気を付けたいですね。
しょーもないYoutuberが、まさにしょーもなく表現されていたのも良いですね。
そのあたりの後から本筋とは関係のなさそうなフラグ回収?については、ん?でしたけど。
刑事が1人で動いてるのもちょっと引っかかりは感じたかな。警官ですと基本二人行動厳守なはずですし。
ガラスでアレを切るのはちょっと無理があるかな~?とは感じました。手も血まみれになっていないし。まぁどこまでが妄想で現実なのかあやふやですけど。
彷徨える魂に成仏していただく事は難しいお仕事だと思いますほんとに。
あまり、というかほとんど俳優さんを覚えない私でも、長澤まさみさんは名優だと改めて感じる一本です。
比較的、手堅く仕上がった佳作という印象です。
ネタバレ制限つけたほうがいいかな?とりあえずナシで
新しさのある人形Jホラー
人形ホラー。古くからある題材だけど、昨今、邦画としては無かったのかな?
Jホラーとしても人形物は無かったので、世界に通用するJ人形ホラーを、という意気込みを感じる。
日本人形というのは、美しさと怖さを兼ね備えている。
また、この映画が普通のホラー映画と違う所は、何と言っても一流感溢れてる。これはホラーでは珍しい。ホラーは一流の匂いがすると、日常から離れ怖さが無くなっていく。だから敢えて2流感を出したりしている。この一流感でちゃんと怖いのが素晴らしい。
本作と「見える子ちゃん」は現在のJホラーを代表する作品だと思う。
気合いの入ったJドールホラーなので、日本を代表するホラーへと世界へ育っていって欲しい。
#ドールハウス
正面から貫いた!
呪いの人形という今更な題材を、正面から描いて成立させている。
●最後まで人形自体が動くカットがない。狙いが徹底している。
人形を動かす描写が見せ場とも言える題材だが、それを一切しない。
観客もそれをどこか期待しているが、どうしても人形を動かした時点で、恐怖が持続しないことを監督はわかっているんだな。
人形を動かさない事でジリジリと不気味さのボルテージを上げている。
●緻密な計算がすごい。それ自体は見せない人形が動く描写をあの手この手で成立させている。それによって恐怖が上がるのはもちろん、ただの人間のノイローゼかもしれないというサスペンスを盛り上げている。
●矢口監督のいつもの緻密な演出。本当に緻密に丁寧に重ねている。それによってリアリティが生まれる。
ごまかさず正面から取り組んだからこそ、ここまで面白い!
全428件中、161~180件目を表示