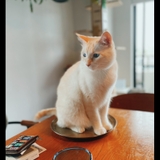マリア・モンテッソーリ 愛と創造のメソッドのレビュー・感想・評価
全22件中、1~20件目を表示
物語的には愛の移ろい易さが大きなターニング・ポイント
面白かったですね。
19世紀終盤から20世紀初頭のイタリアが舞台。
アンネ・フランクや藤井聡太も受けたという「モンテッソーリ教育」を生み出した女性医師・教育家のお話し。
現代の我々が家庭で常識的に行っている幼児教育(積み木とかパズルとかの知的玩具)も、この教育家の思想が大きく影響しているようです。
物語的には、愛の移ろい易さが大きなターニング・ポイントになっています。
「メソッド」というより「新しき女性」の物語
母の気持ちに泣けた
モンテッソーリ教育に興味があり鑑賞。いかにして成り立ったのか?と言うよりはマリアの愛や仕事との格闘の日々というドラマでした。子供を引き取れない辛さに泣けてしょうがなかった、、好んで子供より仕事を取ったわけではなかったようなところや、恋人があっさりマリアを捨ててしまったところは本気で憤慨してしまいました。見て良かったです。
男尊女卑の突破口を開く女傑
全くの不勉強ながら、
20世紀初頭に、
知的障害のある子どもたちの教育メソッドを構築した女性がいたことにまずは驚き。
高級娼婦リリの娘に知的障害があり、外面を気にする彼女は娘のことを恥ずかしいと思っていて
外では娘を酷い扱いをしている。
ただ、マリアの教育を受け日々成長する娘を見るにつけ、リリの気持ちも変わっていくし、
マリアへの信頼・共感が増していき、マリアへ助力をしていく。
モンテッソーリ・メソッドの根幹が母の愛情というのも、ちゃんとその背景が描かれていて、
人間ドラマとしても秀逸だ。
この映画を観なければ、恥ずかしながらモンテッソーリ・メソッドを知るきっかけは
なかっただろうと思う。
こういう出会いが映画ならではだと思うし、私が映画を観るモチベーションにもなっている。
半世紀生きてきて、まだまだ知らないことがあるというのは、
私自身の生きるモチベーションにもなる。
女性の医者に賃金払わないなんて
世界的に広がりをみせる教育法、モンテッソーリ教育、の生みの親マリア・モンテッソーリの半生を映画化。
1900年頃のイタリア・ローマで、イタリア初の女性医師・マリア・モンテッソーリはフランスの有名な高級娼婦リリ・ダレンジと出会った。リリは娘に学習障がいがあることを世間に知られそうになったため、自分の名声を守るためパリからローマへ逃げてきたのだった。この時マリアはすでに画期的な教育法の基礎を築いていて、リリはマリアを通して、障がいを抱える子どもとして見るのではなく才能を持つ1人の人間として、ありのままの娘を知っていくようになった。マリアに共鳴したリリは、男性中心社会の中で悪戦苦闘する彼女の夢の実現に手を貸し・・・そんな話。
モンティソーリという言葉だけ聞いたことが有る、程度の知識で鑑賞。
女性だったのか、とか、医師だったのか、とか、押し付け教育じゃないんだ、とか色々知ることが出来た。
マリアがイタリア初の女性医師で、当時男性社会の中、医師としての仕事はもらえず、最初はボランティアだった事に、時代を感じた。なんでもパイオニアは大変だったんだと改めて思った。
ただし、もう少し教育法について特徴を知りたかったが、そこはサラッと流された感じで少し不満。
マリア役のジャスミン・トリンカとリリ役のレイラ・ベクティは2人とも美しく華があった。
フランス語の原題は「新しい女性」
19世紀の末から20世紀の初頭にかけて、ローマの若き女性医師マリア・モンティソーリが、障害を持つ子どもたちの教育に携わるうち、女性として自立する道を歩み始める物語。
まず出てきたのはパリで大人気のクルチザンヌ(高級娼婦)リリ・ダレンジ。障害のある娘ティナが、自分の存在を脅かすことを恐れて、ローマに連れてきて、アンナに託そうとする。最初は、ティナを見ようともしなかったリリだったが、マリアの指導により娘の能力が引き出されてゆくのに気づき、ティナに愛情を感じるようになる。特に、自分で弾くピアノの音楽が、子どもたちに響いてゆくところに心躍らせるところがとても良かった。リリに扮するレイラ・ベクティはマグレブ系のフランス人で、美しく好演!
続いて、今度は、リリがマリアに、自分の教育メソッドに自信を持って、経済的に自立するよう強く促す。社交界も巻き込んで。しかし、マリアにも秘密があった。仕事の上でもパートナーである医師で研究者であるジョゼッペとの間に認知されていない息子マリオがいた。最愛の息子マリオは田舎で乳母に託し、自分は障害児教育に身を捧げる、この矛盾!しかも、ジョゼッペからは、結婚することを迫られているのに、女性として自立することが難しい時代背景の中で、それを拒む!あのカトリックの強い、女性の自立が、戦後になってもなかなか進まなかったイタリアならではの情景か。
美しくて賢く、教育界ではよく知られたマリアだけでなく(演じたのは、若い頃「息子の部屋」に出ていたジャスミン・トリンカ)、フランス語を話し、褐色の肌と黒い髪を持ち、どこかエキゾチックで魅力的なリリが出てきて、この二人が刺激しあいながら、障害児の教育と女性の自立を進めてゆくところが、とても良かった。ドキュメンタリー以外では初めて脚本と映画に挑んだフランス人の女性監督レア・トドロフに感嘆!
よくわかった
札幌狸小路のシアターキノで観ました。
単に知性を開発する教育法だと思ってきたけど、知的障害者教育が発端だったこと、母性が中心にあることを初めて知りました。
でも、この映画館はいいわ。
モンテッソーリの教育・ポリシーが理解できる作品
モンテッソーリはドキュメントで、観たことがある。今回はモンテッソーリの教育・ポリシーが、ドラマ化だがこの作品を通じて理解できた。当時のイタリアの時代背景、女性、障害者の立場・権利をモンテッソーリは教育を通じて尊重させたい思いが物凄く伝わった。当時の時代背景、障害者への偏見、女性の社会進出よりも家庭ありきの現実もこの作品で知ることができた。見事な作品でモンテッソーリの考えを知ることができた。残念だったのが、公開前の予告編PR。日本の配給会社は予告編で将棋の藤井聡太七冠も受けた教育メソットと積極的にPRしていたが、このPRは余計。むしろ、モンテッソーリの何を知りたいかもっとPRしても良かったのではないか。モンテッソーリのドキュメントなら分かる。作品が良くて日本の配給会社のPRががっかりの不思議な作品。作品は素晴らしかった。
自分の子を手放さざるを得なかった女性たちの物語 偉大なる母の愛のメソッドとは
子を持つ親ならだれもが知るであろうモンテッソーリ教育の生みの親であるマリア・モンテッソーリ。これは彼女が自分のメソッドを確立させた30歳前後の時期に的を絞り、架空のキャラクター、リリとの交流を通して彼女をけして美化しすぎることなく等身大の女性として描いた物語。
イタリア人のマリアとフランス人のリリ。ともに女性にとって生きづらい時代、国も立場も大きく異なる二人を結びつけたのが子供という存在だった。
リリはフランスの社交界で名の知れた高級娼婦だった。しかし母の死をきっかけに彼女のもとに財産が転がり込む。それは彼女がかつて捨てた自分の娘ティナだった。彼女の結婚を壊し、自分を高級娼婦の道へと歩ませた障害を持って生まれた娘ティナ。
彼女は障害児が娘であるというスキャンダルを恐れて、自分に言い寄る王子を頼りにイタリアへと渡る。娘の存在を疎ましく思うリリは障害児の研究施設に預けるために訪れた場所でマリアと出会う。
露骨に自分の娘を毛嫌いするリリの姿に眉をひそめるマリアだが一概に彼女を非難できない自分がいた。
彼女も実の子を手放し乳母に育ててもらっている事情があった。愛するジョゼッぺとの間にできた婚外子のマリオ。自分の野心を達成するには結婚だけは避けたかった。当時女性にとって結婚は自分の夢を捨てることを意味する。女性が家庭に入ることは夫の所有物に成り下がることでありそこに人間としての自由はなかった。
婚外子の子供を認知するには当時の人たちには醜聞でありそれは認められず、泣く泣く彼女は乳母に自分の子を預けるのだった。子供たちの教育の研究のために皮肉にも子育てをあきらめざるを得なかったマリア。
一方、対照的にリリは婚姻関係においてティナを生んだが、ティナが障害児ということで無理やり離婚させられる。この社会で女性一人生き抜くには自分で金を稼がざるを得なかった。だから彼女は娘を捨てて高級娼婦になったのであり、いわば当時の社会の風潮が彼女にそうさせたともいえた。
娘が可愛くもあり疫病神にも思えるリリ。彼女は自分は罪を背負ったのだという。健康な子を産むという女性としての義務を果たさなかったから罪を背負ったのだと。
もし当時の社会がたとえ障害児であろうともリリに対して良い子を生んでくれたねと優しく言ってくれたなら、そして障害児を理由に離婚させられることなどなかったなら、リリはここまで娘を疫病神と思っただろうか。
障害児を生んだ自分のせいなどと罪悪感を感じさせるような社会でなければ彼女は娘をそんなふうに思わなかったのではないか。彼女と娘との間に壁を築かせたのは当時の社会の風潮のせいだと言えないだろうか。
障害児の研究をしていたマリアにはその当時の社会の風潮がいやというほど理解できただけに一概にリリを責めることはできなかった。リリは当時の社会風潮に縛られる典型的女性像として描かれている。そしてマリアはそんな彼女たちの姿や自分が学問研究を極めるためにこの社会で強いられてきた苦難を思い女性解放が子供たちの権利を守るために何より重要だと考えるようになる。
障害児への偏見が子供と社会との間に壁を作らせる。しかしたとえ障害児であろうとも彼らに応じた環境作りさえしてあげれば彼らは自分の能力を発揮させることができる。
障害者への無知により築かれていた世間の壁を取り払うのがマリアの目指すところでもあった。
そして偏見により築かれる壁は障害児だけではなく当時の女性への差別も同様だった。当時は体型的に劣る女性は男よりも劣るという理論がまことしやかに信じられていて脳の質量が男より小さい女性は頭脳が劣るとまで言われていた。そんな理論に彼女は同じく実証主義を用いて女性の体における脳の割合は男よりも大きいと反証したという。
無知から生まれる偏見は障害児に対しても女性に対しても同じだった。だからその偏見の根底となる誤った知識を改善する必要があった。それを彼女は覆してゆく。
彼女はフェミニストとして女性の地位向上のために労働条件の改善も訴えたが、彼女の女性への解放運動は子供教育に向けられると教育段階での女性解放運動にシフトしていく。子供の教育において男女分け隔てなくすることがいずれ女性の解放にもつながるとして。彼女の子供教育はフェミニストとしての彼女の活動と深く結びついていた。
そしてそののち、二度の大戦を経験して世界平和を訴えていくことになる。子供の教育に適した環境づくりのためには母親の存在が不可欠であり、そのための女性解放、そして教育環境づくりの土台となる平和な社会が大前提。子供のための女性の社会的地位向上そして世界平和を目指す必要があった。
そして彼女は子供の教育が世界平和をもたらすと信じていた。子供を適した環境で育てることはもとから持つ人の優しさを培うことができ、戦争を起こすような人間には育たないというのが彼女の持論だった。平和な世界を目指すことが子供教育の環境づくりのためになり、その環境づくりが戦争を起こさない人間を育てる土壌になる。女性の解放が男女分け隔てない子供の教育の環境づくりに必要だし、その環境づくりが女性解放にもつながる。そして世界平和にもつながる。これが彼女が目指した愛のメソッドだった。子供の教育、女性の解放、世界平和、この三つが彼女の中では同じ一本の線でつながっていた。
彼女のこの壮大な目的を達成するにはいくら聡明で優秀な彼女でも子育てとの両立は不可能だった。ようやく父に認知してもらえた我が子を彼女は泣く泣く手放す。しかしそれは我が子にとって必ず役に立つ日が来ると信じての苦渋の決断だつた。
リリはマリアのお陰で娘との壁が取り払われ距離を縮めることができた。これは障害者と世間との距離を縮めたマリアの功績を描いている。
そんなマリアが無償で働かされてることを知ったリリは彼女に仕事を斡旋する。この社会で女性が自由を勝ち取るためには稼がないといけないと。
そうしてマリアの道も開けることとなる。男に従属するかあるいは結婚を拒否して研究を続けても自分の功績として認められない彼女に道が開けた瞬間だった。
自分で経済的に自立することこそ当時の女性が自由を獲得する唯一の方法。二人の女性が協力し合い、女性の道を切り開いていく瞬間が描かれている。
しかしマリアは職を得るその代償として愛するジョゼッぺを失う。彼も当時の家父長制の社会には逆らえなかったのだ。
大きなショックを受けたマリアだが、そんな彼女に救いの手が差し伸べられる。今までマリアの生き方を否定してきた父がマリオを認知してくれたのだ。
そして彼女は人生最大の決断をする。何としても自分のメソッドを完成させると。自分の研究成果を確立させるためにようやく手元に戻ったマリオを手放すのだ。
彼女は言う。私の息子、お前は私の命、すべてがあなたのためになると信じている。あなたが将来幸せになれるために私はあなたと離れる。私は十字架を背負う。子どもの権利を勝ち取るために闘うと。
15歳になったマリオは活動する母の姿を通して学び、その後の人生を彼女と共に歩んだという。
お札にその肖像が描かれるほど偉人とされるマリア・モンテッソーリ。彼女は二度の大戦にわたる時代を生きた人物であり、語りつくせないほどの波乱万丈な人生を送った人物。
イタリアのファシズム政権下で国民の識字率向上に寄与する彼女の教育メソッドが注目され、ひと時ムッソリーニからも重宝された彼女だが、平和活動に傾倒する彼女は次第に毛嫌いされたという。それは当時のムッソリーニをして「面倒な奴だ」と言わしめたほど。そして彼女の学校は当時のナチスドイツやイタリアではすべてが閉校に追い込まれたという。独裁者たちにここまで嫌われる彼女の平和への取り組みが本物だとうかがわせる。
その後もインドに移り住むが、イタリア人ということでイギリス側のインドから敵国人扱いされ息子マリオが収容所に入れられたりと波乱万丈な人生を送り続けた。そんな彼女だけに平和への思いはひとしおだっただろう。
本作はそんな彼女の波乱万丈な人生のひときわ転換期ともいえる「子供の家」開設までに至る時代を描いた。彼女を等身大の女性として感じることができるとてもよくできた作品。
あまり注目されてないのが残念なくらい素晴らしい作品なので多くの人に鑑賞してもらいたい。
ちなみに監督の娘さんが障害を持って生まれたことから本作が生まれたこと、実際の障害ある子供たちの見事な演技など、描かれた人物、製作に携わった人々、すべてがこのモンテッソーリメソッドを体現してるかのようだった。
知育玩具はこの人から始まったのかな?
タイトルなし(ネタバレ)
20世紀初頭、パリの歌姫リリ・ダレンジ(レイラ・ベクティ)には、発達障がいの娘ティナ(ラファエル・ソンヌヴィル=キャビー)がいた。
シングルマザーでもある彼女は、ティナの存在を隠そうと、イタリア・ローマに障がい児教育施設に預けようと試みた。
施設長は男性医師のジュゼッペ・モンテソーナ(ラファエレ・エスポジト)であったが、教育全般を受け持っているのは女性医師マリア・モンテッソーリ(ジャスミン・トリンカ)だった。
マリアの教育を通じて、ティナの本質を知るリリであったが、実はマリアにもジュゼッペとの間にひとり息子がおり、その子もまた障がい児なのだった・・・
といった物語。
20世紀初頭、障がい児教育に新たな道を開いた女性の物語で、ポスターデザインや予告編からその教育方法についての映画かと思っていた。
しかし、原題「La nouvelle femme(新しい女性)」のとおり、隷属からの解放を描いた映画であった。
当時の教育方法は、教育を受ける側を隷属させることからはじまり、特に障がい児教育はその側面が強かった。
それをマリアは、隷属させるのではなく、愛情を持って接するという方針に変えるわけだ。
本作では、教育を受ける障がい児たちと男性たちに隷属を強いられる女性を同じレベルで描いている。
前半やや演出はもたついた感があるも、以上のような当時の女性の立場、障がい者の立場などがわかってくると俄然ドラマ的にも面白くなってきて、マリアとリリという障がい児を抱えるシングルマザーとして描いたあたりに深みが出てきます。
ただし、映画の性格上仕方がないのかもしれないが、終盤はやや説教臭い台詞が多く、そのあたりがドラマ性を殺いでいるかもしれません。
また、実際の障がい児が多数出演しているのも興味深いです。
トットちゃん繋がりで
見ました 🇮🇹初の女医さんだそうで 日本でもだけどやはりフロンティアとなる人は大変苦労されている 当初は男性の陰で障害児向けの教育、カトリックと相性良さそうな教育法だなと思いました この時代仕事と家庭両立は不可能なのか、結局はキャリアコース邁進となっているのは本人にとっては果たして幸せだったのかは疑問でしたが 母の愛を説く一方自身は息子と一緒に暮らせず、現在なら非難浴びそう...
2人のファッション素敵、子役さん達はリアルなの?芸達者であった
今度はシュタイナーの方も見てみたいな
子役の謎
Netflixで「窓ぎわのトットちゃん」を
見直し復習していたところ
この作品を知る。
履修しておかねば! と、劇場へ。
まず、テーマが散漫!
家父長制に対する職業を持つ自立した女性
フェミニズムがテーマなのか
障害児に向けた教育メソッドなのか?
マリアと、その子供の父との関係も
時代性もあり、イマイチ理解に苦しむ。
医者なのに、計画出産しないのか?
当時は まだ妊娠の科学は解明されていない?
女性最古の職業「娼婦」と
女性医師の先駆者。
「テルマ&ルイーズ」的な場面もあり
シスターフッドにフォーカスした
場面ももっと見たかったし。
障害を持つ子供達が
ピアノ(音から言うとチェンバロか?)
あわせて思い思いのダンスを踊るシーン
あの子役達は何者なのか?
本当の障がい者を、集めて
演技をさせたのか?
或いは 天才子役に特殊メイクを施し
たのか?
ただ、その辺のドタバタもあり
飽きずに見ることは出来たが、
ラストシーンもキャプションで
説明が有り、プツンと終わる
面白くてためになる ヘンな映画だった
【4/12追記】
子役について、掘っていったら
監督に関する 以下の記事に当たりました!
どうりで、リアリティ&さりげない愛が!!
「School Revolution: 1918-1939」の脚本を執筆。そして、遺伝性疾患を持って生まれた娘の誕生が本作制作への決定的な契機となった。本作が長編劇映画、初監督となる。
リリの娘・ティナを演じるのはラファエル・ソンヌヴィル=キャビー。本作のマリア・モンテッソーリのもとで学ぶ障がいを抱えた子どもたちの役は、同じ立場の子どもたちが演じているが、キャスティングのワークショップに参加したラファエルと監督は出会い、ティナ役にぴったりだと初日に感じ抜擢した。本作が彼女のデビュー作となる。
やはり良い環境づくりが大切だったのか
マリア·モンテッソーリ博士(1870年8月31日−1952年5月6日)は19世紀のイタリア初の女性医師(ローマ大学医学部卒業)。両親は教育者だったが反対を押し切って、医学部へ。当時は男女差別が酷く、遺体解剖実習は別室でたったひとりでさせられた。
ヒポクラテスたち(大森一樹監督作品)を思い出すと怖い😱
卒業しても精神病院しか勤め先を斡旋してもらえなかったので、障害児施設に無給同然で勤めることに。旦那がいるのに子どもは乳母夫婦に預けられ、離縁後はシングルマザーに。フェミニスト活動家の話でもでもあったような。
モンテッソーリ教育法は藤井聡太ら各界の天才、有名人たちも就学前に受けていたらしい。当方は公文式さえちんぷんかんぷん。やはり良い環境づくりが一番大切だったのか。
知的障害や脳性マヒの子供は精神病者同様、一家の恥として幽閉され、放置された。そんな時代に潜在能力を引き出す試みを根気よく続けた愛情深いマリア様。
障害児の娘の存在が営業の支障になったため、パリからローマに移って来た高級娼婦のリリに背中を押され、社交界を味方につけ、「子どもの家」を建てたマリア様。結局医者ではなく教育者として花を咲かせた。教育者よりも高級娼婦に釣られて観たもので、19世紀の高級娼婦の逞しさのほうが印象に残った。シングルマザーの銀座のナンバーワンホステスが、貧乏苦学生を助けて、銀座に託児所を作る話のほうが身近に感じたかも。
さぁこれから楽しくなるって言うときに、早くお片付けしなさい💢って怒られてばっかりだった。だから知能が伸びなかったんだな。
サリバン先生
『奇跡の人』で、
ヘレン・ケラーの手に井戸の水をジャージャー当てながら、
「water!」と叫ぶサリバン先生。
ミラクル・ワーカー、サリバン先生が実践していた教育方法こそが、
モンテッソーリ教育メソッドだ。
そのメソッドを築いた人物、
それがマリア・モンテッソーリである。
日本でも名称だけは、
かなり浸透しつつあるモンテッソーリメソッド、
この映画は、彼女がどのようにしてそのメソッドを開発し、
世界に広めていったのかを描いている。
メソッドつながりで、
ストーリーをシナリオメソッド風に分解すると、
次のような構造が見えてくる。
●メインプロット: メソッドの誕生と普及。
名もない教育法が、世の中に認知され、広まるまでの過程が描かれる。
この部分が映画の中核を成しており、
モンテッソーリの理論がどのように現実の教育現場に反映され、
どのような革命的な変化をもたらしたのかが※描写されている。
※描写が弱い理由は下記総評で。
●サブプロット1: 女性解放と教育方法。
マリア・モンテッソーリ自身の人生が、
彼女の教育メソッドの土台となっている。
子どもたちの教育に対する情熱が、
彼女の女性としての自由と解放の意欲と深く結びついていることが、
映画を通して強調される。
マリアの個人的な葛藤と、
教育における理念の追求は一つのストーリーラインとして、
しっかりと成立している。
●サブプロット2: 教え子の母親リリの覚醒。
マリアの教育法を受け入れた教え子の母親リリが、
我が子に向き合う姿勢を変えていく過程が叙情的に描かれている。
(メインプロットのメソッドそのものが壮大過ぎて、
叙事的に描かざるを得ない、
なので逆説的にこのシークエンスの叙情が、サブ4と共に効いている)
母親の成長と、子どもへの接し方が変わることで、
教育メソッドの実際的な影響力が視覚化されている点が優れている。
●サブプロット3: 夫との確執。
夫との関係が、
モンテッソーリの教育活動にどのような影響を与えるかもひとつのテーマとなっている。
個人的な葛藤を抱えながらも、
教育という大義を追い続けるマリアの姿は、
観客にとって共感を呼ぶ要素である。
●サブプロット4: 母親リリからの逆メソッド的な指導。
リリが逆にマリアに対して「メソッド風」のコーチングを行うシーンは、物語に一つの転換点をもたらす。
教育方法の普及を進めるために、
他者の視点を受け入れる柔軟性を見せるマリアの姿は、
非常に印象的だ。
●総評
ストーリー全体全体としては、
良いシナリオであるが、
感情的なインパクトがやや薄いと感じる部分もある。
その理由は、おそらく以下の二点に起因する。
①子どもたちのシークエンスの尺が長い事と印象が強すぎて、
各プロットの縁取りが薄れている。
映画が子どもたちを中心に展開される中で、
各サブプロットの細かなディテールがやや犠牲になってしまっている。
②登場人物たちの内面的な葛藤がもう少し強調されれば、
メソッドそのものの物語にもさらなる深みが出たであろう。
実際の人物や出来事に基づいているため、
ドラマティックな葛藤はあるものの、脚色が控えめである。
リアルさを重視するがゆえに、
視覚的・感情的に劇的な瞬間がやや少ない印象を受ける。
◆最後に。
とはいえ、映画の魅力は決して薄れていない。
特に、
フィクション以上、ノンフィクション未満という絶妙なバランスの空間に、
カメラを入れた子どもたちのシークエンスは心に残るものがある。
彼らの成長や学びの瞬間を通して、
モンテッソーリ教育が持つ革命的な側面、
幼児教育、障碍児教育のみならず、
人間の尊厳、征服と解放の歴史に翻弄される人間と尊厳、
という原点に立ち返って人と人が共存するためのメソッドを、
体系化した功績が、どのように世界を変え、
今日に至るまで多くの子どもたちに影響を与えているのか、
その歴史的な意義を知る為の入門書のような作品に仕上がっている事はまちがいないだろう。
周りに流されない力
「モンテッソーリ教育」の
生みの親であるローマ大学初の医学博士。
マリア・モンテッソーリの物語。
20世紀初頭のイタリア。
男性優位社会の中、無給で働くマリア。
差別と偏見に対して苦悩に満ちた日々を
送りながらも教育者として障がい者を支え
女性の自立を目指していく。
この時代に産まれてきた知的障がい者は
隠すものであり、お荷物扱い。
当事者の身内からは
『お前が産んだ財産をいつまでも
置いておけると思っているのか!』と罵倒される始末。
障がい者のことを
『私が産んだ悪の産物』
『厄介者』
…といった強烈なワードもでてきます。
障がいを持つ子供の親が
マリア氏がいる研究所へ助けを求め
子供にメソッドを受けさせると
少しずつ読み書きや計算が
できるようになっていく。
様々な方法で学んでいく子供たち。
日々の成長の過程に目頭が熱くなりました。
障がいを持つ子どもたちの役には
同じ立場の子どもたちを起用。
素晴らしいパワーを発揮していました。
マリア氏の存在感はちろんのこと、
高級娼婦のリリを登場させたことで
より一層、重厚感のある作品に
仕上がっていました。
全22件中、1~20件目を表示