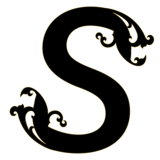シンシン SING SINGのレビュー・感想・評価
全103件中、41~60件目を表示
生きているからこそ
まず初めに、ワタシは大きな勘違いをしていて、作品名から韓国の動物園を舞台にしたパンダの物語だとばっかり思い込んでいて、全くのノーチェックだったことに最近気が付いて観に行ったのでした(トホホ)。
そうしたら、重たいテーマでしたね。生まれた時には同じスタートラインに立っていると思ったら違っていた、そんなCMも流れていますが、生まれた地域や境遇においては自然と法を犯さずには生きられない場合もある。
その後の人生においても何らかの理由で踏み外さなければならない場合もある。
けれど塀の中の彼らは「人生が二度あれば」などとは考えず、今いる場所でできる精一杯のことをしようと取り組んでいる(中には、ここが一番良いとか、ここしか居場所がないと考える者もいましたが)。
どこにいたって、どんな人だって、一所懸命取り組む、仲間と協調する、それは素晴らしいことだと再認識させられました。
その反面、それでも厳しい現実は待ち受けていて、なかなか世の中は変わってはくれない、そんな無力感も見せられた気がします。
出所する【G】を出迎えた【I】、抱き合い涙する二人にはシャバに出られて打ち震える喜びと、これから突き付けられる現実の情け容赦ない刃に恐れおののき震える、その両方が垣間見えたような気がしました。
あらすじ8割、大体の囚人が本人役2割
あからさまにあざとい感じにしていないのは好感持てるが、意識の移り変わりの説得力が今ひとつ。
ただこちらが無知ゆえに『リア王』とか『ハムレット』とか笑うべきところに反応鈍くなってしまうのは、何とかしたい。
海外の刑務所は日本より自由度が高めなのか
エンドクレジットでは登場人物の多くは“as Himself"の表記で出演していて、どうやって撮影したのか気になったのでパンフレットを読んだら、かつて収監されていた方々だった。そりゃさすがに現役の人は出せないか。
同じく収監者の演劇をモデルとした『アプローズ、アプローズ!』も面白かったけれど、今作は本人出演だからか、ところどころドキュメンタリーのように進んでいく。ステージを境に外の世界に触れ、それぞれの希望や葛藤などが交錯し、彼らの言葉が時にズンとくる。
パンフレットによると主要なシーンは18日間で撮影されたそうだから、リアルな雰囲気にも納得。
ステージのシーンもあるかと思って期待していたけど、そこはあまり重要ではなかったようで、そこまでの過程を観るものだった。
今年ベスト級!
アートとというプロセスが如何に人間性の回復に寄与するか。
実際にRTA"(Rehabilitation Through the Arts)演劇・ダンス・音楽・文芸・視覚芸術などのワークショップを通年開催する更生プログラム"を修了者は全米の再犯率60%に対し、3%となっているようで、また、本作の出演者の多くが実際のRTA修了者で構成されているということもあり、非常にリアリティある話となっていた。
さらに映画が描いているのはRTAに限った話ではなく、アートというプロセスそのもの(映画をつくること、さらに映画を観るということ)まで、本作は讃えてくれるような暖かさがある。観賞中何度も目頭が熱くなった。
また、劇中のRTA演劇の演出家ブレントが行ったワークショップで「あなたの人生で最高だった瞬間を思い浮かべて〜(中略)」から、それぞれが自分の人生のことを語り、「さぁあなたはもう役者だ。」というシーンがとても印象に残っている。まさにアートというプロセスが人間性を取り戻すという瞬間である。とても活力が湧いて来るセリフだ。
「怒る演技のは簡単。」、「傷付く演技は難しい。」、このセリフは他人に弱みを見せられないという刑務所内での鉄則のようにもみえるが、ディヴァインGを通して上手く他人に助けを戻られない、1人で頑張りすぎてしまう全ての人に当てはまることだと思った。
プロセス
刑務所であることを忘れ、一人ひとりの尊厳に目がいく
芸術を通じて更生を図るプログラムのRTA (Rehabilitation Through the Arts) は1996年にシンシン刑務所で始まった実在するプログラムで、RTAのサイトによれば、このプログラムを経た者たちの再犯率は、プログラムを受けていない者たちよりずっと低いそうだ。
彼らは演じることを通じで自分の内面と向き合い、他人の立場に身を置くことを通じて自分では気づかなかった新たな一面を発見する。また、決して一人では成り立たない演劇で互いに信頼し合うことを学び、協同して作り上げる喜びを感じ、人としての尊厳を取り戻していく。
鑑賞中、彼らの人間としての悩みや役者・芸術家としてのもがきを見ているうちに、彼らが収監されていることなどつい忘れてしまい、途中に挿入される減刑聴聞などの場面で「そうだ、ここは刑務所の中だった」と思い出さされる。
刑務所だから、犯罪者だから、といった色眼鏡を外して一人ひとりと向き合うことで、それぞれの人の素晴らしさが見えてくるのではないか。逆に言えば、我々は様々なレッテルを人々に貼って偏見で見ることが多すぎるのではないか?
初めから犯罪者として生まれてくる人間などいない。個人の責任がまず問われるのは当然のこととして、一方で、貧困や差別、偏見など社会的・経済的環境、あるいは家庭内での虐待などによって、いつの間にか犯罪手を染めざるを得なくなった人々も少なからずいるであろう。
だからこそ、個人の尊厳を踏み躙ることなく尊重することが大切なのだ。そして、一人ひとりが尊重されることが学べるのであれば、矯正プログラムだけではなく、学校などにおける通常の教育プログラムにおいても演劇はもっと取り入れられても良いのかも知れない。
表情が素晴らしい
米ニューヨークで最も厳重なセキュリティが施された
シンシン刑務所で行われている収監者更生プログラムの舞台演劇を題材に、
無実の罪で収監された男‘ディヴァインG’と収監者たち、
そして、途中参加の刑務所で一番の悪人として恐れられている男、
通称ディヴァイン・アイこと‘クラレンス・マクリン’との友情を描いた実話の映画化。
粛々と感動しました。
個々のバックボーンは深追いせずでしたが、
このような刑務所と更生プログラムがあることを知りえましたし、
また演劇に関わることが彼らにとって、とても大切なものであることが伝わってきました。
そして、演じている収監者の表情がとても魅力的。
俳優のコールマン・ドミンゴ(ディヴァインG)や、
ショーン・サン・ホセ(マイク・マイク)はもちろんなのですが、
本人役のディヴァイン・アイも良いのですが⋯
わたしは、個人的にこれまた本人役のショーン・“ディノ”・ジョンソンに惹かれました!
稽古中に後ろを歩かれて、イライラして喧嘩になったところを止めたシーン。
あの話は本当なのかなぁ⋯。涙が本物みたいだったから。
みんな涙がポロッと流れるのが自然で、とてもキレイでした。
「劇中劇」を超え、「劇中劇中劇」という新しいジャンルを確立した作品
NY、<シンシン刑務所>。無実の罪で収監された男ディヴァインGは、刑務所内の収監者更生プログラムである<舞台演劇>グループに所属し、仲間たちと日々演劇に取り組むことで僅かながらに生きる希望を見出していた。そんなある日、刑務所いちの悪党として恐れられている男クラレンス・マクリン、通称“ディヴァイン・アイ“が演劇グループに参加することになる。そして次に控える新たな演目に向けての準備が始まるが――(公式サイトより)。
演劇グループに所属する一義的な意味は、自由が制限され、娯楽が少ない刑務所の中で自由に楽しめるから。しかし本質は二義的な、「何者かを演じることで、自分に返ってくるから」であろう。掛け声にもなっている「RTA」とはRehabilitation Through the Artsの略称。これはどこまでに行っても更生プログラムである。
一方で、過去の罪を、自らではどうしようもなかった出自を、そこから連綿と続く現在の自分を乗り越えるのはなかなか難しい。娑婆に居るわたしたちにだって難しいのに、まわりが自分と似た犯罪者だらけの刑務所であれば、どこか赦される感覚を覚えることや却って居心地が良くなることもあるだろう。全体の出演者の85%が元収監者という本作は、いわばそういう虚無的な堕落を乗り越えた人たちによる、自分次第で何者にでもなれるのだという、静かな賛歌である。
その意味でこの映画は、いわゆる「劇中劇」を超え、「劇中劇中劇」というか、「ハーフドキュメンタリー」というか、何かしら新しいジャンルを確立したと言える。さらに、アカデミー賞にまでノミネートされたことで、「何者にでもなれる」がより強化された。さぞかし本人たちも驚いたであろう。
デジタル撮影が主流の現代において、16ミリフィルムで撮影した意図は、合間に挿入される刑務所での本当の記録映像との地続きを表現するためだろうか、デジタルに比べピクセルがでかい分、色が濃く、鮮やかに映える。
チームに仲間ができる流れが素晴らしい
刑務所で行われている演劇による更生プログラムを扱った映画と聞くと、不思議とフランス映画をイメージしてしまった。フランス映画をリメイクしたんじゃないかと疑ったくらい。でも、何より驚いたのが本当に元収監者たちが多数出演していたこと。この更生プログラムに参加していた人はほぼリアルな収監者じゃないか。そりゃ知らない俳優だらけだよな。
実際にあった出来事をベースにしているから、それほどドラマティックな事件が起こるわけではない。一からプログラムを作っていく姿を描くのではなく、何回か上映した状態の彼らと新たに参加した収監者を描く手法。でも、皆で何かを作り上げようとするだけでちょっと感動してしまう。一応のトラブルは待ち受けている。最初は壁を作って嫌な奴全開だったディヴァイン・アイが、プログラムの仲間になっていく過程もすごく好きな流れだ。途中から、ラストの感動はもう約束されたようなものだった。
ディヴァインGは無実の罪で収監されているから別の感情になるが、他の収監者たちは基本的に何かしらの罪を背負っている。そんな彼らにどこまで感情移入できるのかが大きなポイントに思える。だから彼らの罪名は基本的にわからないまま。変に知ってしまうとその罪の重さで観ている側に先入観が生まれることを懸念してのものだろう。正しい判断だと思う。
何かしらの罪を犯したとしても人間であることに変わりはない。シャバに戻った人間が訪問し、現在の気持ちを吐露するシーンはそれを象徴するいいシーンだった。つーか、アメリカの刑務所自由すぎないか!?人間的に生活できるよう配慮されている気がする。日本との違いを感じた(日本の刑務所は知らないが)。
出演していた人たちは基本的にいい人に思えたが、他の収監者たちの中には減刑を審査する人に対して平気で嘘をつく人も多いかもしれない。だからこその「今も演技しているのですか」という質問なのだろう。あの発言に対して自分ならどう答えるのか考えてしまった。アンガーマネジメントのいい事例なんじゃないか。自分の成熟さを問われる嫌な質問だ。単純に感動させるだけではない、奥深さを感じる映画だった。
ドキュメンタリーを観ているような・・・
元受刑者だった出演者たちの面構えが、存在感が素晴らしい
ドラマティックな展開があるわけではない。原則として俳優たちが大見得を切ったりもしない。一見、「治療共同体(TC)の車座対話」を淡々と追ったドキュメンタリー作品のようにもみえる。劇映画らしからぬ静かな作品だ。
刑務所の収監者たちが演劇を上演するというコンセプトは、過去にタヴィアーニ兄弟の『塀の中のジュリアス・シーザー』などの作品にもあった。しかし、本作では舞台本番に向けてドラマが収斂していくというより、むしろそのリハーサル過程における人間関係の微妙な変化をじっくり見つめることの方に主眼が置かれている。
言葉にしづらい感情をカタチにする作業を地道に重ねていく行程において、「自分」という殻の奥底に閉じ込めていた心の声に向き合い、ひいては周囲の他者の声にも耳を傾ける——この「RTA(芸術更生プログラム)」への参加経験を有する元受刑者が本作に大勢出演していることもあって、この映画自体が、一種の「ドラマセラピー」ともいえそうな演劇の有効性を証明するものとなっている。
見方を変えると「アマチュア演劇が上演に漕ぎつけるまでの過程を追う」という設定だから、「演劇本来の魅力」や「戯曲の台詞」をしみじみ噛みしめることができるようなシーンはほぼない、とも言える。
それでも、コワモテの収監者がRTAへの参加希望理由を問われ、獄中でたまたま手にした本の一節「人間、生まれてくるとき泣くのはな、この阿呆どもの舞台に引き出されたのが悲しいからだ」(※小田島雄志訳『リア王』より)に激しく共感したから、と答えるシーンなどは、演劇ファンなら大きくうなずくところだろう。
このコワモテの男を演じるのが、元受刑者のクラレンス・“ディヴァイン・アイ”・マクリン本人だ。彼の面構えががイイ。前歯の欠けた口元が実にいい。映画後半ではにかむような表情をのぞかせると人間味があふれ出す。
彼以外に本作に起用された元受刑者たちも一人ひとり、佇まいそのものが存在感を放っている。ちなみに映画前半で、彼らが刑務所内の舞台オーディションを受けるユーモアたっぷりのシーンがあるが、これは本作における実際のキャスティング・オーディション時の映像を使っているのだとか。
そんな彼らに対し、主役のコールマン・ドミンゴらプロの俳優陣も抑え気味の演技で応え、あたかもフレデリック・ワイズマン作品のような日常感を保つことに貢献している。それだけに、コールマン・ドミンゴの仮釈放審査委員会のシーンをはじめ、幾つかの箇所で見られる「典型的な劇映画」的演出には少々違和感を覚えた。また、仮釈放の希望を閉ざされたうえに大切な仲間も喪った彼が周囲に八つ当たりしてしまうあたりの描写も、演技臭が強く出過ぎており、全体の雰囲気を破ってしまって惜しい。
良作ではありますが
エンドロールまで見てね
囚人と刑務所なのでケンカや血みどろもありかなと思ったら全然なく…人は亡くなるけどね、そうゆう亡くなり方かと思うと世間を凝縮した世界にも思う。自由はないし、愛する人にも会えないけど。
エンドロールも良かったので最後まで観て下さいね。
凄く凄い映画かも
アメリカの刑務所内には、こんな更生プログラムがあるなんて驚く。
全103件中、41~60件目を表示