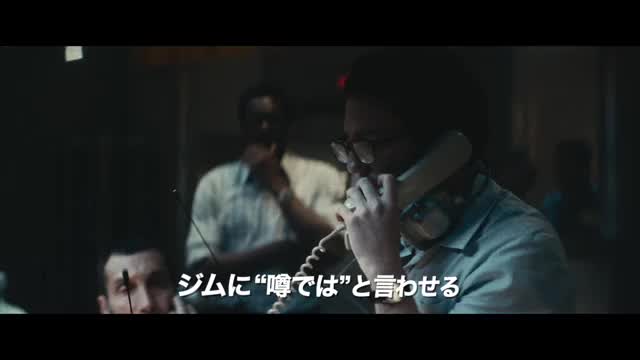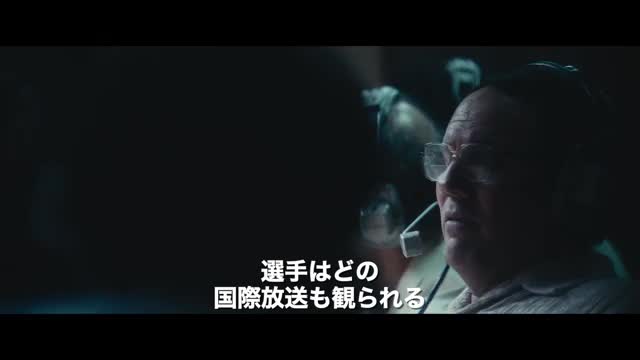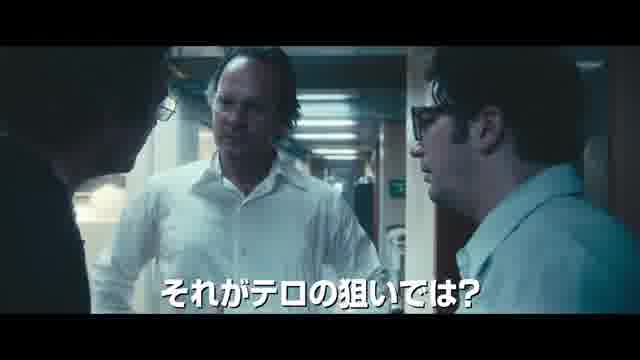「伝えなければいけないのは何か」セプテンバー5 近大さんの映画レビュー(感想・評価)
伝えなければいけないのは何か
1972年9月5日、ミュンヘンオリンピックで起きたパレスチナ武装集団“黒い九月”によるイスラエル選手村襲撃のテロ事件。
犯人グループ8名の内5名が死亡するも3名が逃走。選手やコーチ含む人質11名は全員死亡という最悪の結末となった。
これを受けてイスラエル政府は報復。諜報機関“モサド”による報復作戦はスピルバーグ監督で『ミュンヘン』として映画化された。
本作はオリンピックを中継していたTVクルーたちがテロ事件に遭遇し、図らずもテロ事件の一部始終を生中継。事件発生から顛末までの一日の出来事を、TVクルーらの視点から描く。
事件は僅か一日の出来事。映画も100分弱。
しかし当事者たちにとってはいつ終わるか分からない。中身の濃い100分弱。
カメラはほとんどスタジオ内のみで、スタジオの外には出ない。
スタジオの外とは現場に赴いたスタッフとの電話でのやり取りや現場からの映像。
今、現場で何が起きているのか…?
ワンシチュエーションの設定を活かし、情報滞る息詰まる緊迫した雰囲気を活写。我々もスタジオ内にずっと居るような錯覚に。
実際の映像も織り交ぜ、リアリティーはたっぷり。
監督のティル・フェームバウムはドイツ時代にローランド・エメリッヒのプロデュースでB級SFを手掛けていた新鋭らしいが、これ一本でエメリッヒ以上の確かな演出力を見せた。
情報や状況が錯綜し、スタジオは対応に追われ追われ…。
他局のドイツ人関係者インタビューを、スタジオのドイツ人女性スタッフにその場通訳。
その途中、男尊女卑な中年男スタッフが彼女をお茶汲みに用立てる。
このテロでオリンピックは一時停止。するまで時間が掛かり、すぐ近くでテロが起きているのに競技は続けられ、継続中の競技は終了するまで。テロを報じながらも競技を見、時に歓声も上げる。
社会派アンサンブルの中で細かい人間臭い描写も。
ネームバリューのある役者には乏しいが、皆が完璧なアンサンブルを奏でる。
『ミュンヘン』が報復の行く末なら、本作は報道の在り方や倫理観を問う。
警察は給仕に扮して選手村に入ろうとするが、犯人側に知られ失敗。
立てた作戦いずれも知られ、ことごとく失敗続く。
何故犯人グループはこちらの動きを知っている…?
理由はバカみたいに簡単。TVで生中継してるから。
警察が立てた作戦をTVで報じる。それを犯人たちが選手村内でTVで見て知る。
クルーたちもようやく気付き、バカか!…と笑いそうになるくらい。
おそらくTVでの生中継などほとんど無かったのだろう。
TVを通してどれだけ情報が流出し、影響あるか。
TVで初めてテロ事件が生中継された事件。誰もが覆面を被った犯人たちの生の姿に戦慄した。
犯人グループの要請でヘリがチャーターされ、人質全員を連れて空港へ。
そこで今、何が起きている…?
人質全員解放されたとの情報が。
が、未確認。
いち早く報道するか、否か。スクープか、事実確認か。
上層部は事実確認。間違った報道をしてしまったら…?
今、その情報を掴んでいるのはウチだけ。報じれば全局を出し抜いて独占スクープ。
報道マンとしても最大の究極選択。そしてディレクターは…。
見事独占スクープと人質解放即ち一定の事件収束に沸く一同。
TVマンとしての勘は外れていなかった。…と思えたが、
誤報だった。
実際は…、言うまでもなく。最悪の結末。
誤報も正しい情報も混乱していた。情報がしっかり伝わり切れなかった。仕方なかったかもしれない。
が、あの一瞬、己の欲を抑えて事実確認を出来た筈だ。それを怠った。
一番悪いのは非道なテロリストたち。しかし…。
TVマンもジャーナリストの端くれ。真実を報道する者として、その魂を自ら葬り去ったも同然。
ラストシーン。
犠牲になった11名の顔写真を一人見つめる。
その時、何を思っているか…?
ジャーナリストとして、一人の人間として、問う。