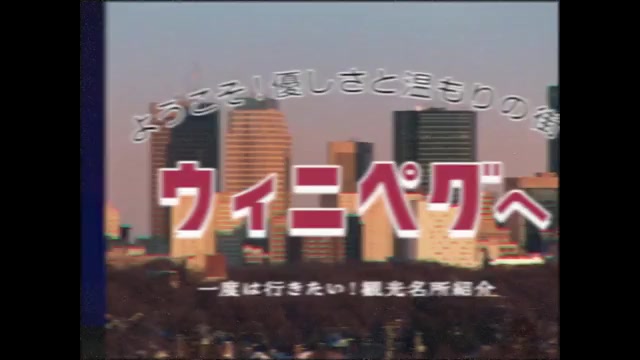ユニバーサル・ランゲージのレビュー・感想・評価
全3件を表示
メガネが見つかる頃には、ご縁が見えてくる不思議ー
轟音が行き交う高速道路とその隙間の墓地や時が止まったかのような地元カフェとの対比、無機質な建物が入り組んだ凍える吹雪の街と華やかなペルシャ家具に囲まれ家族が団欒するThe幸せな家庭との対比で、観てる方まで心身ともに体感温度が変わる。
小さな都市の群像劇であり、はじめは場所も人も何だかわけがわからないが、段々線が繋がってきて、最後には一つの円になる。川が合流するウィニペグ湖のように、、、
人それぞれ、話す言語はその人の経験や歴史、居を構えた地域などを表すが、垣根を越えて繋がれるたった1つだけのユニバーサル・ランゲージとは、思いやり、なんて安っぽい複雑なものじゃなくて、我々は結局どこかで一つに繋がっているのだというシンプルな認識なのかもしれない。
そうしたニュートラルなスタンスが、いつでも誰かの涙に差し出せる全開きティッシュのような、脱力した最も強い優しさを生むのである。
人を飽きさせるくだらない大切なものツアー、地元でやってみようかなー笑
―そしてまた誰かと誰かを繋ぐかもしれないピンクのお金を、そっと凍らせる
Idiolect
アート系の香りを感じつつも、可愛らしくユーモアのある話かもと期待したが…
正直、何がしたいのか分からなかった。
メガネを紛失したクラスメイトのために姉妹が奮闘するというのはいい。
しかし、ここからというところで別の男の話になる。
観光ガイドの様子なども含め、どう関連するのかも分からない映像が延々と続いて退屈。
姉妹に話し掛けてきた男や観光ガイドがマスードだと気付いたのも大分後になってから。
(何故か引きでしか映してくれないんだもん)
途中で3回くらいBGMだけの断片的なカットの羅列があった。
マシューが映ってるものですら眠くなったが、景色やスケーターの場面は苦痛でしかない。
移動を真横から捉えるカットもしつこい。
カーリングする生徒や号泣する男など、本筋と関係ない描写の主張も強過ぎる。
終盤やっと登場人物たちが繫がるが、逆に先生など大半のキャラの意味の薄さを察してしまう。
そしてマシューとマスードの外見の入れ替わり?同一化?もあまり意義を感じず。
そもそもペルシャ語とフランス語が公用語になってるとか、ウィニペグが舞台とかの意図も不明。
異世界にまですると違うのは分かるが、架空の町ではいけなかったのか。
少なくとも自分には何も汲み取れず…
タイトルとは裏腹に、特定の人にしか伝わらなさそうな、まったく開かれてない作品でした。
親切さというものは対象者に向けた一本の矢であり、それを知らない人にとっては凶器にも見えてしまう
2025.9.1 字幕 アップリンク京都
2024年のカナダ映画(89分、G)
英語の代わりにペルシャ語が公用語となったカナダ・ウィニペグに住む人々を描いたヒューマンコメディ
監督はマシュー・ランキン
脚本はマシュー・ランキン&ピロウズ・イーラ・フィルザバディ
原題は『Universal Laungage』で「世界共通言語」という意味
物語の舞台は、カナダのケベック州とマニトバ州
ケベック州に住んでいるマシュー(マシュー・ランキン)は、離れて暮らす母()の元を訪れるためにバスに乗って生まれ故郷のマニトバ州ウィニペグへと向かった
どうやらマスード(ピロウズ・ネマティ)という男と一緒に住んでいるようだったが、そのいきさつは不明のままだった
とりあえず父の墓参りと生家に向かうことになったマシューは、そこに住んでいるダラ(ダラ・マジマバディ)に逢って話を聞くことになった
一方その頃、ウィニペグの小学校では、担任のビロド(マニ・ソレイマンルー)が生徒たちを叱りつけていた
休みが明けても成長しない生徒たちを怒っていたのだが、そこにオミッド(ソブハン・ジャヴァディ)が遅刻してきてしまう
先生は理由を聞くものの、オミッドは「駐車場で七面鳥にメガネを奪われた」と言い、先生は作り話だと思って、「メガネが出てくるまで授業はしない」と怒ってしまった
その後、オミッドを心配するクラスメイトのネギン(ロジーナ・エスマイリ)は、彼の言う駐車場へと向かった
だがメガネは見当たらず、そこで氷の中に閉じ込められていたお札を見つけてしまう
ネギンは姉のナズゴル(サバ・ヴァヘドユセフィ)に助けを求めるものの、そこにお金を狙う不審者がやってくるのである
物語は、マシューが母を探す旅と、ネギンとナズゴルがお金を得るために道具を探す様子が同時並行していく
その関係性が最後に明かされることになるという構成で、この狭すぎる人間関係の妙を楽しめるかどうかによって評価が分かれるのだと思う
お金を盗んだ男はマシューの母を保護していたマスードであり、彼はオミッドの父親でもあった
またマスードの妻は涙を集めている女性サハル(サハル・モフィディ)だったりする
マシューの生家に住んでいたダラは訪ねてきたマシューを快く受け入れ、そして彼の身を案じて抱擁をする
このシーンが海外版のポスターに使われていた
映画には、数多くのキャラが登場し、ネギンたちが氷を割る道具を探す過程で、花屋でマシューと出会っていたりする
その花はマシューの父の墓前に飾られることになるし、墓地に来ていたのがサハルだったりするし、ビンゴゲームの会場でも出会っていたりする
かなり狭い範囲で何度も交わっているのだが、肝心なことは最後までわからない
マスードは貧困にあえいでいて、息子のためにメガネを買ったものの、七面鳥に奪われてしまった
その七面鳥は七面鳥屋のハーフェズ(バフラム・ナバティアン)の弟アブデル(ムハンマド・サラビ)の入賞した自慢の七面鳥だったのだが、アブデルとマシューはカフェで同じ場所にいたりする
このカフェにはサハルもいて、そこには編み物をしている女性たちがいたりするのだが、彼女たちと母親を重ねてみていたり、サハルも在りし日の母親のように誤認している
そして、母親は認知症が進行していて、マシューのことを息子だとわかっていない
長い間、マスードがマシューの役割を演じてきたからなのだが、マシューが母親との対話を避けてきたことが要因のようにも思えた
映画では、言葉よりも伝わるものがあるというテーマになっていて、それは人類共通の言語であると描いている
ダラの抱擁、サハルを見間違えるなどのマシューの感情も然ることながら、お金を奪われると感じたネギンの感覚も正しかった
そう言った人から溢れてくるものがたくさんあって、それは言葉を超えて直接的に伝わってくる
だが、その雰囲気や感覚を作り出している原因までは相手に届かず、それを補完するために「言語」が必要となってくる
言葉がいらない瞬間もあれば、言葉が必要な場面もある
それこそが人類の普遍的なテーマとしてあり、多言語が交錯するゆえに人の間に軋轢が生まれてしまうと言えるのではないだろうか
いずれにせよ、感覚的に捉えればよい映画で、あえて見せないことで対象者(画面に映る人物)の感情を引き出して描いていたと思った
不審者がマスードであるというのは最後までわからないし、それゆえにネギンたちの感情が高ぶったままになっていたりする
だが、お金がないので拾ってでも息子にメガネを買ってあげたいとは誰にも言えないもので、そんな彼はマシューの母に献身的な時間を与えていたりする
親切さというものが行動規範になっているものの、それは誰かに向かう一本の矢のようなもので、それを俯瞰している人を置き去りにしている部分もある
今回の場合だと、マシューの感情は置き去りにされているし、ネギンたちも同じ想いを抱えていた
そう言った部分を補完するためには相互理解が必要であり、そのために「言語はある」と言える
そう言った意味合いにおいて、単純そうに見える人間関係の深いところを描いていた作品だったのかな、と感じた
全3件を表示