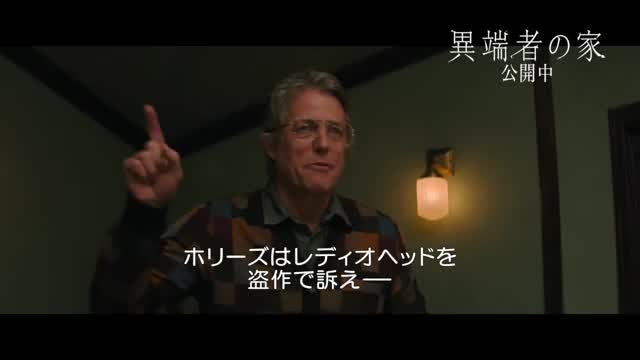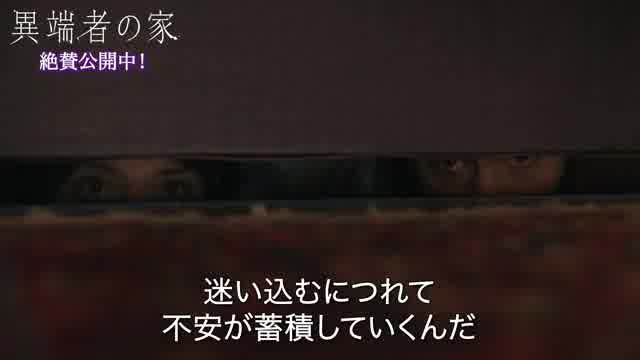異端者の家のレビュー・感想・評価
全298件中、101~120件目を表示
評価不能なれどスリラー最高潮
サイコ劇?クライム劇?スリラー?宗教劇?なんとも独特な感触の作品です。
宗教論争らしい会話が延々と続き、キリスト教に関心も興味もゼロの身には、真面目な議論なのか単にヨタ話なのか皆目理解不能ですが、内容はどうでもよくて、グラント先輩の偏執狂でクレイジーな雰囲気が伝わればよしです。
よく言えば不条理劇ですが、端的に話は破綻しているので、真面目に追及しないでキャリー、サイコばりの圧倒的なスリラーを味わえばいい作品です。
もっとソウ的なエグイの期待してたんですけど・・・
日々モルモン教の布教に勤しむ、しっかり者のシスターバーンズ(ブギーマンの子!)と若干おっとりさんのシスターパクストンは吹雪の日に胡散臭い説教爺の家を訪問しーのあーだこーだ宗教問答した挙句に地下室に閉じ込められてしまう。
真実の宗教を教えたるわいと息巻く爺に敢え無くシスターバーンズが惨殺された後、おっとりシスターパクストンが覚醒し脱出って・・・単なる監禁壁のある変態爺の屋敷からの脱出劇でした。。。特に何の捻り無し。
脱出モノではない
開始から衒学的な会話が小一時間ほど続き、やっと場面は動く。宗教談義に興味ないので最後まで集中力が持たなく、飽き飽きする。脱出モノの映画かと思いきや実はそうではないので、結局、家の構造も視聴者には最後までよく分からない。終盤、なんでシスター・パクストンは地下に引き返したのだろう。プロットはかなりイマイチだった。
70点ぐらい。2回観たけど同じとこから眠くなる…
居心地悪い…薄気味悪い…ヤバい、この人!
恐ろしい仕掛けのカラクリ屋敷に閉じ込められる話かと思ったら、恐ろしいのは人間でした。
信じる事の怖さや強さ。また、基本的な考え方が自分とは全く違う相手には嫌悪感を抱いてしまったりするのだなと思いました。
若い女性が、女性のスカートを"公衆の面前で"下ろすなんて酷い事を、どうして出来るんだろう。やられた相手の気持ちもだけど、自分が軽蔑されるかもという思考は無いんだろうか。その感覚が気持ち悪いです。
そのショックから立ち直れぬまま、布教活動に向かったシスターパクストンとバーンズ。正反対のキャラクターでどちらもキュートです。が、バーンズが布教の話を始めると、宗教に疎い私は奇妙に感じてしまいました。むしろ、すべての宗教を否定して持論を展開するリード氏の例え話の方が受け入れられます。しかしリードも、一方的に話題を変えたり、大声は出さないものの、時に強い口調になったり、急にキャンドルを吹き消したり、次第に不気味に見えて来ます。そして、2人を帰す気が無いと分かった時の恐怖。
「君たち2人のうちどちらかが嘘をついている」と言いながら、騙していたのはリードの方で、2人の反応を見て楽しんでいたのでした。
R15ですがホラーとしてはそれ程怖くはなく、それより、話が全く通じない気持ち悪さがあります。
ここからネタバレです。
屋敷には玄関以外に出口は無く、どちらのドアを選んでも地下室行きでした。正しい選択をすれば出られるのに、リードのミスリードによって間違った方を選ばされてしまう、という方がお話的には面白いのにな、と思います。
地下に閉じ込められていた女性たちの檻は動物用で、長く生かす気は無さそう、それなのに何人も居るからこれまでにかなりの犠牲者がいたと想像できます。バレないの?
リードの狂気は恐ろしいですが、彼の言う「支配」は心の支配ではなく物質的な支配でした。
自ら毒を食べた女性は、洗脳されたというより、解放されたくて自殺したのでは?と思いました。
玄関のドアのロックのタイマーも解除不可能も噓だから、脱出劇としては、見事解除する方向が望ましかったですし、リードがこっそり抜け出した出入り口も実はあったはずなので、その辺の種明かしは欲しかったです。
トリックにはちょっと無理があったので、脱出劇には重きを置いていないです。3人の演技はとても良かったです。
老害と若者
宗教への懐疑と狂気を描いた良作
私は日本生まれ。神社や寺には何らかのタイミングで行くが、信仰心がある訳ではない自称無宗教家だ。
その為、本作を完全に理解出来たかどうかの自信は無い。
特にモルモン教については無知だったので、キリスト教も色々あるんだなぁと思った。
そりゃそうか、日本にも幸福の科学だのエホバだの創価学会だの派生宗教があるんだし、そりゃ宗教が盛んな国であれば多岐に渡るだろう。
本作は、そんな宗教への懐疑と学問的探究が行き着く先にある狂気を描いた良作だと思う。
主人公であるバーンズとパクストンの2人、ソフィー・サッチャーとクロエ・イーストは昨今の映画としては、どちらもビジュも演技も良く、顔面アップの演技が多い中でも画面の満足度は高いままだったのが好印象。
だがしかし、やはりヒュー・グラントのミスターリード役の怪演。
目尻の皺に安心感と底知れない不快感を両立させるのは見事な演技だ。
語る言葉は全て嘘が混じり、不信感を与えつつ、納得させられるような語り方は見事としか言いようがない。
特に教授のように宗教の反復を語るシーンは、本当に面白い。モノポリーや音楽に例えるシーンは本作の中でも突出して面白い名シーンだと思った。
その後、帰るために2つの扉を選ばせるのだが、ここからはスリラー要素が強くなり、大衆的なスリラー映画の立ち位置に戻ってしまった。
個人的には、ここが一番残念だったのだが、
「BELIEF」と「DISBELIEF」の扉を選ばせるのだが、この扉は結局同じ地下室へ繋がっているのである。
この時点で、リードが示す選択は結論ありきであり、対話を望んでいるキャラでは無い事が露呈してしまうのだ。
その後、なんやかんやあり、彼の終点思想は「宗教=支配」かつ「支配者=神」である事が分かる。
この辺りが恐怖と暴力を用いた結論ありきの行動で、前半の対話を用いて動いていた姿との乖離がモヤっとしてしまった。
最後、シスターパンクストンが語る祈りと、バーンズの奇跡の一撃。
特に祈りについての言葉。実験の結果、祈りに効果はないけど、その姿は美しいし意義はある。これは人が信仰する上での本質だと思わせられる名シーン。
脱出後のラストシーン。
パンクストンが語る「生まれ変わったら蝶になりたい。私だと分かるように指先に停まるの」と語ったように、彼女の指先に蝶が停まり、それは幻覚のように消えてしまう。
彼女の死の直前に見た幻だったのか、その語りを聞いていたバーンズが別れの挨拶に来たのか。それとも全ては映画の中と言う「胡蝶の夢」だったのか‥‥。
雪の中の屋外シーンは、空気の澱みからの解放もあり、爽やかさも感じる美しさだった。
残念な印象の箇所もあるが、悪役の新たな形を示してくれた良作だったと思う。
今後、この方向のヒールキャラを扱った、スケールの大きな作品を期待したい。
ココ最近見た中でNo.1のコメディ映画(褒め言葉)
人体を傷つける描写はウゲっと思ったが他の箇所に関して言えば、映画館で誰1人笑ってなかったが自分は笑いをこらえるのに必死なくらいに面白くてココ最近で1番笑えたコメディ作品だと思った。よく「優れたホラーはコメディと紙一重」っていうがあれはホント。人間、訳が分からない人やものを見ると奇妙に感じて恐怖を感じるがあまりにもその奇妙さが行き過ぎるとコメディになるんだなと実感した。
人によっては「今年1番のホラー」と言ってる人もいるから人の価値観はそれぞれだなと思う。
ネタバレで笑いどころをいくつか。
雨漏りの下にししおとしw
あそこは笑うw
モルモン教の牧師?が一旦帰って引き返してきて「これ忘れてました」って冊子渡すとこも笑えたな。
(すごく頼りになって助けてくれそうな人に見せ掛けて見掛け倒しってとこがねw)
あと預言者の人がパイ食べた後に亡くなったと思ったら動いた!ってとこで持ち上げてた頭落としたとこがギャグ過ぎて笑ってしまった。
ガチンコサイコ宗教論争
からくり屋敷の脱出劇とは違ったが?
ヒュー・グラント見たさ
ヒュー・グラントの老害マウンティングサイコパスぷり❗️迷路の様な屋敷に宣教師、勧誘に来た女性達を監禁し自らが教祖になると意味不明で何がしたいのか全くわからない。
囚われた2人の女の子の脱出サイコスリラー。
ほとんどが宗教論争といか会話劇でキリスト教徒やモルモン教徒ならわかるかもしれないけど、自分はハナから唯物史観の無神論者なので、あまり怖くはなし。
とは言えヒュー・グラント見たさなので、痛さを楽しめました。
期待度○鑑賞後の満足度◎ 久しぶりに扇情的でない(受け狙いでない)スリラーを観た思い。布教者が布教される側になる宗教談義の緊張感とサスペンスの盛り上げとを上手くシンクロさせたクレーバーさ。
①完全に狂っているのに上品さ・知的さを漂わせ紳士然として(一聴すると)正論を吐いているように思わせる男をヒュー・グラントが適役好演(彼女達が女性の姿がないのに家の中に入るという、やってはいかないことをやるのを自然に見せるにはヒュー・グラントの様な個性を持つ俳優が必要、一方英国映画界のイケメンの一人で“ロマコメの帝王”と呼ばれていたけれども、どうも私にはこの人に対して胡散臭いイメージが付きまとう)”
②女の子二人もなかなか魅力的。
③鑑賞前に予想していた話とは随分違っていて途中まではやや戸惑っていたが、弁舌巧みに自分の宗教感を披露する男に布教にやって来た二人が逆にやり込まれていく緊張感をred herringとしているストーリー展開に徐々に引き込まれていく。
④自分が布教する宗教である『支配』に容易く洗脳されそうな女の子の方を残したのに、彼女にやられる展開が面白い。
親切な作品
私にはぴんとこず
ジャー・ジャー・ビンクス? 何?知らんがな!
(一般的に胡散臭いと思われている)宗教勧誘が、もっと胡散臭く邪悪なものに絡めとられていくところに、観る者の興味がそそられます。
二人のシスターの組み合わせが(あざとくも)なかなか上手いです。利発で論理的、負けん気も強そうな黒髪のシスター・バーンズ。かたや気弱で従属的だが柔和で優しそうなブルネットのシスター・パクストン。この対比!衣装でも分かりやすく違いを表していました。
ラスト 瀕死のバーンズが生き返り、逆転の一撃をふるったのは、確かにご都合主義に映ります。
でもこう解釈するのはどうでしょう。
ミスター・リードは「シスター・バーンズは復活する。でも金属が入っていたから復活しないよ」と金属片を除去してしまいました。
邪魔してたものが除去されたんだから、当初の預言通り復活が起こったと。すなわちリードは「宗教は支配だ」という自身の教義に絡めとられ、最後は自らの預言に支配されてしまったのではないか、もっと言うとあれはリードの胡蝶の夢なのではないでしょうか。
一方でシスター・パクストンは「祈りにより神の加護があったから脱出できた」と考えるでしょうか?そして今後もっと信仰に励む?
それとも最後に指に止まった蝶(=自分)が消えてしまったということは、これも胡蝶の夢なのかも、そうすると。。。
いづれにせよ、3人の熱演がいろいろと考えさせてくれる異色作です。
2倍で楽しめる
思ってたのと違うサイコパス映画
てっきりヒュー・グラントが「さあゲームを始めましょう」
とか言い始めて閉じ込められた女の子2人が知恵を絞って
トラップ館から脱出するアクションホラーかと思っていたら
延々と面倒くさいおじさんの持論を聞かされ宗教論争に
花を咲かせる家庭訪問(布教活動)の話。
ちょっとだけ予告編詐欺。
後半から少しホラーテイストで話が盛り上がってきたと
思ったら結局は若い(?)女性を監禁するキモいおじさん。
ヒュー・グラントなのでそれほど嫌悪感がないのは
男目線だから?
キリスト教関連のネタに詳しくないと会話の全てを
理解するのはやや難解だけどストーリーにはあまり
関係ないのでスルーしてもOK。
全298件中、101~120件目を表示