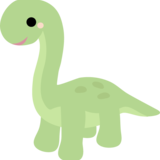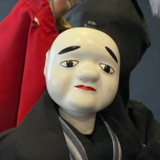お坊さまと鉄砲のレビュー・感想・評価
全88件中、41~60件目を表示
民主化によって発生する争い、分断の面と 自由意思の尊重の大切な面と...
民主化によって発生する争い、分断の面と
自由意思の尊重の大切な面と
どっちもあると思った。
例えばその前の状態で平和で幸せなら
もともとゴールに居るのでは?とか。
ともあれ、価値観ギャップ凄かった(笑)
未体験ののどかさ感じる
年の初めに幸せになれる映画だった。(笑)
美しい自然と欲のない国民
2006年、国民に愛されてきた第4代ブータン国王が退位し、王子に国王を譲位するとともに、行政の長(首相)を選挙で選び、民主化へと転換を図ることが決まった。そんなブータンで、選挙の実施を目指して、まずは模擬選挙が行われることになった。山に囲まれたウラの村で選挙の事を聞いた高僧は、なぜか次の満月までに銃を2丁用意するよう若い僧に指示し、若い僧は銃を探しに山を下りた。同じ頃、アメリカからアンティークの銃コレクターが幻の銃を探しにやって来て、南北戦争当時の貴重な銃がなぜかブータンのウラ村に有り、その銃を高値で買い取ろうとした米人に対し、仏に寄付する事を選んだ持ち主、その後のドタバタ劇が・・・そんな話。
本作だけを観ていたら、王国から共和国になったように誤解してしまったが、そんなはずないと調べてみたら、ブータン王国は現存し、イギリスなどのように王が行政を行うのではなく、選挙で選ばれた行政の長、つまり首相を決めようという事なのだと理解した。
選挙などしたことは無く、必要なのかもわからない、テレビもインターネットも無いような地方では、選挙をするということがいかに大変だったのかが観ていてわかった。
銃を何に使うのか興味深かったが、争いをなくす象徴として埋める、なんて発想が素晴らしい。
物や金に執着せず、必要なものを必要なだけ大切にするという、人間の本質のような住民の美しい心に打たれた。
ブータン山の教室、でも思ったが、これからどんどん世界中の情報が入ってきて、俗世間の金に汚い人たちも増えていくのだろうけど、心の綺麗な人々が多くいて、山の自然が美しいブータンにぜひ行ってみたい、改めてそう思った。
お坊様と説法....なら納得(笑)
予想できない結末に思わず涙した
ブータン王国について、我々は何を知っているだろう。場所はインドの北あたりか。政治?ワンチュク国王という今時珍しい王政国家。隣国でインドの強い影響下にあるだろう。価値観は国民総幸福。しかし経済的には裕福ではない。文化?インドの近くだから、カレーとか?最近では、高額の観光税導入なんてニュースもあった。映画のタイトルの「お坊さまと鉄砲」って?仏教国だろうけど、鉄砲くらいあるだろう。だから何?それくらいのこの国に対する知識を肉付けするのもいいかな。くらいの気持ちで映画をみた。そしてその知識が偏見でしかなかったことを知らされる。もう少し私が持っていた偏見が続く。
ブータンに突如もたらされた民主主義
2024年は選挙イヤーだった。国内は都知事選、衆院選、知事不信任に伴う兵庫知事選、海外ではアメリカ、イギリス、ロシア、台湾などなど。そして民主主義そのものが問われることにもなった。AIの進化に伴いAIを活用した選挙活動やフェイクニュース、AIに政治を任せると主張する候補者まで出現しただけでなく、SNSの影響など「危機に瀕する民主主義」のような言葉までも駆け巡った。そんな「民主主義」に対してどんな示唆があるのか?そんな期待を裏切る映画だった。強烈だけど優しい衝撃だった。ワンチュク国王の独断?で突如、民主主義で行政の指導者を国民が選択することが決められた。国民は民主主義に対して無知、というより興味を持っていない。それはお近くの専制国家における絶望的な民主主義とは全く異なる。国民は王政に対し何の不満も持っていない。それは自由主義を掲げる国家を見ていないからではない。為政者と国民が相思相愛だからなのだ。そんな国民に突如もたらされた選挙という仕組みに戸惑う国民をこの映画は描く。
今こそ民主主義を考える映画?という浅はかな先入観
選挙制度に対する無知な様子には思わず笑ってしまう。親族を巻き込んだ選挙活動、投票のための贈賄や恐喝まで繰り広げられ、それは子供達にまで浸透する。これまで世界中で繰り広げられたであろう選挙違反の姿の一端がここでも見られる。選挙委員会のような、選挙を啓発ではなく啓蒙しようとする機関が、対立を煽り、憎悪を伴わせる場面がある。それを目の当たりにする国民は、選挙制度そのものに対する不信感を募らせる。そうした人々の姿を上から目線で見ていた観客は私だけでないだろう。
子供が消しゴム一つ買うのに苦労する国は貧しいのか
この映画の舞台であるウラという村で、一人の娘が学校で消しゴムを使わなかったために本を破ってしまったというなんとも小っぽけな理由で先生に怒られ、友達からも仲間はずれにされて悲しむ。住民の大半が周囲に流されて投票する中で、異を唱える父親。その娘にまつわるエピソードでは、たかが消しゴムが重要な役割を果たす。それを母親の仕事のおかげで出会えた選挙委員会の役員からもらうことになったが、そんな大事なものなのに、翻って与えた役人にとってはさほど大切ではないであろうものなのに、少女はなんの躊躇もなく、役人に返してしまう。豊かさとは富:物質的に、経済的に恵まれていること、ではないという価値観が子供にまで沁み渡るこの国を支えている基盤的な道徳感の盤石さが伝わってくる。
ブータンの人々が望む政治のあり方
模擬選挙では、住民が赤・青・黄3つの色の党に投票する。それぞれ自由、発展、伝統、どれを大切にするかを選択させてみよう、という試みなのだ。結果は黄色、つまり伝統に軍配があがるということだったのだが、圧倒的というかほぼ全員が黄色に投票しているという統計学的にはありえない結果。不正ではない。模擬選挙だから不正の意味はない。だから現状に満足しているから伝統を重視したブータン人の心に合致しているということか。これさえもどうやら違うのである。
無垢なブータンの人々の国民性
選挙人登録をしようにも生年月日を知らない、鉄砲は見たことがない。21世紀なのに外国の文化といって見聞きしているものは80年代の音楽、テレビ、映画にブラウン管のテレビなど、タイムスリップしたかのような懐かしさを感じさせる。それでもそうしたものがもたらしてきたものが少しずつでも浸透している様子を描いていた。しかしこうした国民の物に執着しない、豊かさを物質的なものだけで図らない価値観は経済成長を遂げていくことを発展と考える世界の国々の人々が考え直す必要があるかもしれない。
傑作!すごい才能!!
傑作! パオ・チョニン・ドルジ監督はすごい才能だ(『ブータン 山の教室』も素晴らしかった)。
まさにこの分断の時代に向けた作品。
どこが傑作なのか、どういうふうにすごい才能なのかは、僕がごちゃごちゃ書くより本作を観ていただいたらすぐにおわかりになると思います。
追記
コロナやインフルや風邪が大流行しているということもあってか、今日も鑑賞中、洟をすすったり咳き込んだりしている方が何人もおられました。
なかにはずっとゴホンゴホンを連発しているひともいて、大変な迷惑でした。
やはり体調のすぐれない時は出歩かないほうがいいと思います。
自分の欲求を優先したい気持ちも理解できますが、少しは周囲への気づかいもしていただきたいものです。
いい歳をして、こういう配慮が欠如した大人が多すぎるなぁ。日本は。
謙虚な心の美しさと清々しさに涙
初めての選挙に戸惑うブータンの山間の村民と、
銃を巡るお坊さんとコレクター(ブローカー?)の交流を軸に話が進みます。
なにより西欧的な価値観をもつ人たちと
村民、お坊さんのなかなか嚙み合わない会話のやりとり、展開が全編にわたって楽しい。
資本主義(お金を中心とした価値観)への問いかけ、
さらには戦争の否定はもちろんテーマのひとつではあると思うけれど、
それらを皮肉的ではなく、ユーモアに溢れ、
声高に主張せずに、拍子抜けするほど爽やかに描いているので、
ピュアな村民たちの様子も相まって、
清々しい幸せな気持ちで映画を観終わることができました。
映像もブータンの山間の広い景色がお坊さんの赤い衣装にも映えてほんとうに美しく、
異国ですが、お祭りの衣装、音楽もどこか懐かしい感じがしました。
今のブータンでしか描けない、また時勢的にも今こそ観られるべき映画だと思いました。
ブータンの雰囲気が分かった。
不思議で幸せな国
民主主義の限界
「山の教室」をアマプラで見て感動して「お坊さまと鉄砲」は劇場で見た。「山の教室」のようなわかりやすさはなく考えながら見る映画となっていた。お坊さまがなぜ銃を必要とするのかという点は最後までわからないため眠くなることも・・・。私なりの解釈は「民主主義の未完」だと思った。民主主義がそんなにもいいモノであるならなぜ米国は銃社会であり、銃を捨てられないのか?という点と、すべての災厄の元は結局「銃」を使った民主主義とは真逆の力による統治ではないかと監督は観客に訴えかけているのだろう。しかし王様が退位してまで体制移行を決意したのだから民主主義自体は悪いモノではないとも言っているのだろう。また選挙による分断が描かれる点はトランプをこすっているのだと思った。「山の教室」のような見る薬のような映画ではなく私としては政治色が強すぎると感じた。しかし日本のようにトンデモ政治家や評論家が「民主主義の危機、民主主義を守れ!」と叫んでいる国よりよほど健全だとも思った。
幸福度ランキング一位の憂鬱
文明の発達は、必ずしも人間の幸福に結びつくわけではない『お坊様と鉄砲』、いや不幸にすることのほうが多いのでは、そう考えさせられる映画です。でも、もう後戻りはできないですよね、後は破滅に向かって急ぎ足でゆくか、足るを知るがごときノンビリ生きるか。
世界一幸福な国「ブータン」のはずなんですが
物語は、2006年のブータンが舞台。
それまでの国王による王政から、民主主義国家へ向けて初めての選挙が。
それまでの、ブータンはほぼ鎖国状態に近い国。
日本では、「世界一幸福な国」として、有名なんですが。
その根拠は、世界幸福度ランキングなるもの。
2013年に欧米の国に次ぐ、8位にランキング。
あの、後進国がなぜとなったわけで。
まあ、国際舞台にいきなり登場して、アジア最上位ですから。
みなは、驚いたんですが。
しかし、この話は後日談とでもいいますか。
その後のランキングは、2019年に59位にランキングされたのを最後に。
もはや、ランキングインすることは、ありませんでした。
そんな、アジアの仏教国ブータンの初の選挙。
鎖国は、悪いことばかりではない。
日本だって、徳川家が政権を担っていた江戸時代、300年間鎖国をしていたわけで。
その間に、科学技術や産業面、とりわけ庶民が困ったのは、医療の立ち遅れでしょうか。
平均寿命も短かったし。
子供の死亡率も高かった。
だけど、文化面では、庶民の芸能や浮世絵を中心に。
世界で類を見ない、独自な表現と発達。
いまでも、世界に誇れる文化が、開花した時代。
ブータンとて、どうだろう、文化面では、詳しいことはわからないけど。
人々の幸福度は、この映画をみれば、自ずと伝わってくる。
とりわけ日本もそうだけど、仏教国は、穏やかで、質素な国民性。
それは、この映画でも随所に感ぜられる。
産業革命とキリスト教を同列で捉えることはできないけど。
どうしても、文明開化、産業の発達、キリスト教の布教解禁。
そんな、キーワードでみてしまう。
幸福の度合いっていったい。
映画でも、素朴な生活しか知らない、村の民は、幸せそうだ。
そう、幸福と感じる器の大きさが、小さいのだ。
だから、僅かなことでも幸せと感じてしまう。
でも、日本でもそうだけど、産業の発達、恵まれたインフラ。
生活をより便利にする環境と道具。
文明の発達とともに、幸福と感じる器が、だんだん大きくなるのです。
ですから、ブータンも幸福度ランングから外れてゆくのも納得。
映画は、まさにその入口あたりで終わってます。
ただ、あの頃は良かったで終わらせたくないなと。
現代日本だって、そう悪くはないと。
まあ年齢にもよりますが。
若者が、より良く、より多くは当然のこととして。
かたや、生きていく最小限が満たされていれば、あとは儲けもの。
こんな考えになれればいいなと。
蛇足ですが、これをお薬で満たそうとすると。
ヘロインということになります。
代表的な、幸福と感じる器を小さくしてくれるお薬。
ただ、手を出せば、短い人生が。
あと、薬欲しさに犯罪にとか。
まあ、やめといたほうがいいですね。
とにかく、人間は、欲の生き物。
これを上手くコントロールしながら。
あるいは、適当にごまかしながらやっていくしか。
しょうがないですよね、それが、人間ですから。
ブータンに行ってみたい
ゆっくり流れる時間を画面いっぱいから感じられる
微笑みの国ブータンが、繁栄の象徴(と思われている)民主主義を
平和的に親愛なる国王から奉還され
「これで近代国家の仲間入りだ」
「これで幸せになれる」という言葉と裏腹に
村の中はいじめや争いが生まれ始める矛盾
独裁者から血みどろになって民主主義をつかみ取る構図が多い中
国民の誰もが望んでいない民主制が無理やり与えられ、選挙が生まれる
プロセスが面白い
田中芳樹さんの「銀河英雄伝説」を思い出した
善良な君主制と腐敗した民主制は果たして国民はどちらが幸せなのか?
銀英伝とブータンが重なった
「あぁ、ブータンに行ってみたいな」と
エンドロールが流れる間、満月が地平線からゆっくり昇るシーンを眺めながら
思ってもらいたいなぁと思う映画
王制国家から民主国家へと変化するブータン。その過程を描きながら観る者に「ブータンらしさ」と「幸せとは」を語りかけてくる作品です。
「ブータン 山の教室」の監督作品第二弾です。ふむ。
ペム・ザムちゃん元気かな…(←登場しません @-@;エッ)
まあ、何はともあれ観てみましょう、ということで
鑑賞した訳なのですが
作品として、何を描きたいのか何を伝えたいのか。
そういったメッセージが余り伝わってこなかったカモ…。
というのが正直な「鑑賞直後の感想」でした。 ・△・;
王国制度から民主国家への転換。
初めて行われる、国の代表を決める選挙。
その選挙に向けた、模擬選挙の実施。
選挙のことを理解していない村人への周知。
そのために、選挙推進の役人がやってくる。
投票先の政党を「色」で選ぶという投票スタイルなのだが
国王のイメージ色「黄色」が圧倒的に票を獲得。…・_・;
” 模擬選挙は失敗だ… ” と、思わず口にするお役人…。
◇
この、「国王の色に98%の票」が入るという結果は
選挙の趣旨からすれば「選挙が理解されていない」と
いうことになってしまうのでしょう。 …けれど
” 王様のイメージ色に98%の票が入る ” ということは
どれだけ国王が国民に慕われているか、のバロメーター
になっているとも言えるのではないかと。・-・
転換期の混乱はありながらも、近代化を図るブータン。
#国の在り方の変革は、誰が求めたのか?
#誰のための、そして何のための民主化なのか?
#民主化が争いや対立の元になるのなら本末転倒だし…・△・
…そんなことを考えながら1週間が経過。…@-@;;
原点に帰って考えてみました。・-・
◇
僧侶が銃を求めたのは何故なのだろう。
1丁だけではダメらしく、「2丁」必要だという。
模擬選挙の話と並行して、銃の入手に関わる話が進む。
それに伴い、次第に明かされてくる僧侶の胸の内。
” 古来、争いの元は大地に埋め上に仏塔を建ててきた ”
#いま、民主化の名の元に国民が割れている。
#この状況が続くことは、国のために良くない事。
#2丁の銃は、争いの象徴。埋めよう。
銃を調達してきた売人は、インドから密輸してきたらしく
バレたら当然、やばい。実際、仏塔建立の式典会場で
「なぜ外国人がここに?」
と咎められかけ
「この銃は仏塔の礎に埋めるため持参した」
と理由を説明して、地元警察を納得させていた気がする。
そしてその銃2丁は、平和を願う仏塔の礎となった。
” 武器よさらば ”
ブータンに争いはふさわしくないよ と。
これが、監督の発信したい一番のメッセージなのかも。
そう理解しました。・-・
※銃が2丁必要な理由は、「敵も味方も」争いの元を手放さ
なければならない という想いからなのでしょうか。
◇
話全体の構図が分かりにくい気がしましたが(…かなり・_・;)
ブータンの行く末を案じる気持ちは、じわっと伝わってくる
そんな作品なのだと思います。
※ただ、前作(ブータン 山の教室)のように、映像的に心に残る
場面はあまり無かったような気がして、それは残念でした。
※ブータンの2000年代にはいってからの国の状態や変遷を抑えて
から鑑賞しないと、本当の理解が難しい作品なのかもしれません。
◇あれこれ
■タイトル
英題「The Monk and the Gun」
翻訳「お坊様と銃」
お坊さま=モンク 。
初期の「ファイナルファンタジー」のジョブに「モンク」というの
があったなぁ と、遠い目になりました。
FFはⅣくらいまでしかプレイしていないので、モンクという職業が
いつ頃まで存在したのかは分かりません。
個人的にはドラクエシリーズの「武闘家」という職業が好きでした。
素早いし改心の一撃出やすいし。 モンクなしです。 …あ。
■銃
タイホから逃れるためとはいえ、高価な銃を穴に埋めた売人。
その嘆きと損失は如何ばかりか。これはこれでお察しします。
平和の礎となってめでたしめでたし。
※ブータンの軍隊にも無い最新式の銃、と言っていた気が。
後でこっそり掘り返しに戻っていたりして…。
■作品の順番
今気付いたのですが、この作品のほうが
「ブータン 山の教室」より前の時代を描いた作品なのでしょうか?
民主化は2008年で、この作品はそのころを描いたお話。で
「ブータン 山の教室」は、2019年の制作。
うーん。ま、いいか。 ・_・/☆
ベグ・ナムちゃん達が元気で静かに暮らしているのなら。
■メイド・イン・ブータン
作品鑑賞特典に「ブータン産レモングラス入り煎茶」のティー
バッグが付いてきました。
ヒマラヤ山中に自生している葉を地元の農家の方が積んでいる
のだそうです。ブータンからの輸入品です。・_・~
どんな味なのかな。
もったいなくてまだ飲んでません。 ← ケチ
◇最後に
ブータンを更に知ろうとするきっかけになる作品かと思います。
前の作品「ブータン 山の教室」が、そこに暮らす人びとの
「個人の生き方」を描いた作品とするなら、 今回の作品は
「国の在り方」「人の心の在り方」を描いた作品なのかと。
そんな風にも思いました。 ・-・ハイ
☆映画の感想は人さまざまかとは思いますが、このように感じた映画ファンもいるということで。
ブータンからの問いかけ:成長志向の意味と幸せとは?
楽しく、考えさせられ、予想外の展開で驚きと余韻を残す作品でした。銀座の映画館は空いていましたが、こんなにも心に響く映画は滅多にないと感じます。
この映画は、2004年のブータンにおける王政から民主化への歴史を背景にした現代の寓話です。ストーリーや一つ一つのエピソードには、実際の歴史を象徴する説得力がありました。
村人たちの戸惑いが特に印象に残ります。民主化することや投票権を得ることに対して、彼らは混乱し、受け入れられない様子を見せます。
歴史的に見れば、独裁政権や軍事政権からの民主化や、女性参政権のための闘争など、民主主義は人々が血を流して勝ち取ってきたものです。
しかし、この映画では、敬愛される王が統治するもとで国民が幸福を感じ、現状に満足しているブータンという特異な状況が描かれます。そのため、王権を手放してまで民主化を進める王の決断や、村人たちが投票権を与えられて戸惑う姿には、大きな意味が込められていました。
映画の主軸である「鉄砲」を巡るエピソードは、ネタバレを避けるため詳細は伏せますが、尊敬される高僧が瞑想を中断し、選挙の模擬演習に関与するという展開は、サスペンスを生みつつも不安感を煽るものではありません。
その結末は意外でありながら、ユーモアと幸福感に満ちており、見終わった後に温かい気持ちになりました。
映画が提示する「幸せな国のあり方」には明確な答えは示されません。それは、ブータンという国自体がいまなお壮大な社会実験に挑戦しているからです。
しかし、個人が幸せに生きる方法については、仏教国らしい一つの解答を示してくれます。この解答が、現代資本主義の中で生きる「普通の人」として登場するある人物に、幸せをもたらすであろうと予感させてくれるのです。
この映画は、成長や進化を志向する現代社会に対し、幸せの本質とは何か、変化を受け入れることの意味とは何かを改めて問いかけてきます。そして、その問いを観客一人ひとりに委ねるのです。
AK-47がぁぁぁ・・・‼️
この作品、名作「ブータン 山の教室」の監督の作品とのことで、期待してたのですが、期待通りの名作でした‼️2006年、民主化を進めるブータンで模擬選挙が行われることに。初めての選挙にブータンの人たちは緊張と困惑気味。そんな時、周囲を山に囲まれたウラの村で、高名なラマ僧が若い僧に次の満月までに二丁の銃を準備するよう言い渡す。そしてアメリカから来たロンは、アンティークの銃をウラの村で探していたが・・・‼️突如訪れた民主化、近代化に戸惑う人々の姿を描いた、まるで昔の日本の市井映画のような味わいの作品ですね‼️同じかどうか分かりませんが、初めてのストリップショーに村中が大騒ぎになる、木下恵介監督「カルメン故郷に帰る」を思い出しました‼️民主化に戸惑う様々な人間ドラマが描かれるわけですが、支持の違いから母と口も聞かない夫や、学校でイジメに遭う娘を持つ女性の「民主化じゃなくても、今までだって幸せでした」のセリフが胸に沁みる‼️そしてアンティークの銃を手に入れようとするロンと、ラマ僧のために二丁の銃を手に入れようとする若い僧のシークエンスが絶妙に交錯し、ドタバタを繰り広げるわけですが、なぜラマ僧が銃を手に入れようとしていたのかが判明するクライマックスは、民主化、近代化への移行を理想的な形で人々に納得させる、善意に満ちた名場面ですね‼️ホントに素晴らしい‼️若い僧が美しい花畑を横切るラストカットも郷愁に満ちていて印象的でした‼️前作「ブータン山の教室」といい、今作といい、今後ブータン映画には要注目ですね‼️
微笑みと幸せ
変化の時に本当の幸せと平和な世界を問う
ピュアが過ぎる
ブータン映画は『ブータン 山の教室』に次いで2作目。同じ監督の作品なのですね。
とてもロケーションが美しい国だけど、今作では車が通れる所だから、だいぶ低い村なのかな?
タイトル通りお坊さんが銃を手に入れる話と、ブータン初の選挙という2つが並行するお話。
ちょっとずつニアミスしながら繋がっていくなかで、出てくる人が揃いも揃ってピュアなのがかえって可笑しい。
便利を知ってしまうと不便を感じるのだろうけど、そもそも村の人々は幸せに暮らしているから、何も不満はなさそう。
とはいえ選挙の仕方を役人が教えに行くとか、この話からまだ20年経ってないのがなんとも。
終盤、うまく2つが繋がるものの、銃が必要だった理由は予想外。お坊さんも村の人々も警察までも、ふざけてるのかと思うほどにド天然で面白かった。
そしてあんなんお礼に貰っても困る。
物騒なタイトルとは裏腹に楽しくハッピーな映画。
ブータン愛溢れる作品
掘ってたのそれかよ・・・
・・・って思ったのは私だけじゃ無いはず(詳しくは本編を見てくれ)
ブータンは最後にテレビと携帯(通信)が整備された国である。とはいえまだ一家に一台とはいかないのでテレビのある家や茶屋にみんなが集まってテレビを見ている。「ALWAYS 三丁目の夕日」で描かれていたような昔の日本と変わらない。顔立ちがモンゴロイドなのもあって行ったことない国なのにどこか懐かしさを感じる風景だ。蕎麦の花ってあんなに美しいのか。
映画の舞台は2006年だが田舎の山間部でも携帯がちゃんと通じることにむしろびっくりする。ちゃんと基地局あるんだなぁ・・・。
国民に慕われていた国王が平和的に退位しブータンが民主化したことで、初の選挙に振り回されるブータンの人々。
今まで国王のもとで幸せにやってきたのに何故わざわざ選挙なんて必要なのか?と疑問に思う村人を必死に「啓蒙」する選挙委員のツェリンも中々上手くいかない。「多くの人が命をかけて必死に勝ち取ってきたもの(選挙権)が与えられたのだ」と言われても村人にはピンとこない。フランスやロシアのように民衆が血みどろの戦いで王制を倒して民主制を勝ち取ったわけではないからだ。日本人としても身につまされる部分ではある。日本も普通選挙のために闘った人々はいたが勝ち取るには至らず、結局GHQから占領後におまけで選挙権が与えられた。現在も選挙率は2割程度。「投票しても何も変わらない」「誰に投票したら良いかわからない」なんて言う人たちが嘆かわしい。
もちろん王政とてうまく機能するのはあくまで「民に尊敬される良き王」が上に立つの場合だけなのは言うまでも無い。タイも国民に慕われていたプミポン国王が泣くなって国民は皆むせび泣いたが、後を継いだ長男はあのざまである。(せめて国民に慕われる長女が継げれば良かったのに・・・)
選挙に関する真面目な話は映画「サフラジェット」(誰だよ「未来を花束にして」なんて残念な邦題つけた奴は・・・)あたりを見てもらうとして、これはブータンの民主制の善し悪しを問う映画ではない。むしろ幸せとは何かを問う映画だ。
選挙に執心している夫は支持者が違うことで義母とも仲違いし、娘も学校でがいじめられることを嘆く母親。
月イチで干し豚を食べるだけが楽しみの田舎暮らしなんて嫌だ、娘をもっと良い学校に通わせたい、という夫の気持ちも、いままでの田舎暮らしで十分幸せだという妻の気持ちもわかる。選挙にかまけて娘のための消しゴム一つ買うことも失念してる父親のせいで娘は先生に怒られる。大人に振り回されるのはいつも子供だ。
ブータンの田舎では仏教が生活に根付いていて、みんなお坊さんのためなら対価も求めず何でも差し出すし快く手伝う。そこに資本主義の介在する余地はほとんどない。お坊さんも「選挙は仏陀の教えにかなうものか?」と民主化も近代化もさして興味なさそう。
アンティーク銃コレクターのアメリカ人ロンと、仲介する都会民のベンジが資本主義の象徴として物欲に振り回されている様は村人たちと対照的だ。
坊さん相手には米ドルも価値がないのでロンとベンジは銃を求めて奔走するも中々上手くいかない。それを追う警察。のどかな田舎で物語は淡々と進むものの、中々展開が予測できないなか、僧侶がなぜ鉄砲を求めたかが明らかになり、綺麗にたたまれるラスト、そうきたか。
ラマ役の役者さんは本物の僧侶だったらしく本作が俳優デビューだとか。どうりでガンダルフのような威厳溢れる佇まいに引きつけられる。ラマの言葉が選挙よりテレビより誰よりも村人には響く。
お金があっても都会で物に囲まれていても幸せとは限らないのは当たり前だが、物欲に関する話は映画「365日のシンプルライフ」あたりを見るとして、どちらにしても一度民主化や近代化に舵を切ったら後戻りは出来ない。どんなに日本人が「ALWAYS 三丁目の夕日」の時代を懐かしんでも、スマホ無しの生活はもう考えられないように、村人たちもテレビのない生活にはもう戻れないだろう。
ブータンは発展途上国の中でも珍しく近代化を目指さない国として、長らく世界幸福度ランキング上位にランクインし「世界一幸せな国」として知られていたが、やはりラジオやテレビ、ネットから海外の情報が入るにつれて自分たちの生活と他国との差異が可視化されたためか、2019年度以降のランキングで幸福度は大幅に下がってしまっているらしい。残酷ながら幸福度は他社との比較という物差しで決まってしまうことがある。
いつか坊さまがブッダの教えより米ドルを選ぶ日が来るのだろうか。それはわからない。けれどラストの村人達を見るとこの国の未来は明るいんじゃないかと思えてしまう。
全88件中、41~60件目を表示