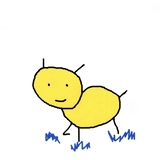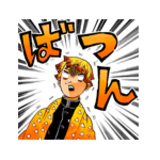どうすればよかったか?のレビュー・感想・評価
全204件中、41~60件目を表示
流れぬ水はどんどん腐る、と思ったけれど……
原一男監督『ゆきゆきて、神軍』をちょっと思い起こさせるような緊迫感があり、力のある、質の高いドキュメンタリー作品だと感じました。
ほかの鑑賞者の方もそうだと思いますが、ぼくはこの映画を見ていて、とてもしんどくなってしまいました。
外の空気が入ってこない、外部と交流がないということは本当にこわいことです。
この閉塞的な家庭環境を見ていると、「流れない水は、どんどんと腐っていくのだな」とそんな考えが頭に浮かびました。
スクリーンに映し出される病気の症状は時として激越なものがあり不安にも襲われましたが、それよりも恐ろしいのは、やるべきことがはっきりしているのにもかかわらず、両親がそれに目を背け続けていることでした。その理由はプライドや世間体なのでしょうか。権威主義的傾向の強い親ほどこういうふうになるのかもしれないなと考えたりもしました。
そして、この家族はタフだなぁ、とも。
あんな状態を何十年も続けられるのだから。一歩間違えると取り返しのつかないことになりかねない修羅場を何度も経験したことでしょう。
しかし、そのタフさが問題を長引かせたとも言えるのではないでしょうか。
それに、本当に家族のことを思えば、早期解決を考えたなら、本作の監督=弟さんも、行政に頼るなど多方面に相談するべきではなかったのか。電話相談なんかではなく、役所などに足を運んで担当者と顔を合わせてどんどん話をするべきではなかったのかと思いました。
また、こんなことも感じました。
だんだんと症状が増悪するお姉さんは、髪も乱れ、狂人の様相を呈していたけれど、その表情はどこか安らいでいるようにも見えました。まるで悟った聖人のように。
ぼくはその表情を見て「人間は解決できない問題があるとき病気の中に逃げることがある」という、むかし読んだ文章を思い出しました。
――と、ここまで書いて、少しほかの方のレビューを読んでみたところ、「あーっ」と、また気づかされました。
ぼくは、あの両親や弟の責任を追求するような見方ばかりしていて、時代を考慮することに欠けていました。その点が足りなかった。
たしかにお姉さんが発症した当時は、いまとはちがい精神疾患や精神医療に対して様々な偏見がまだまだ根強く存在している時代だったなぁ、と。
ぼくも若いころ、不安障害で精神科にお世話になりましたが、やはり受診するまでなかなか踏ん切りがつかなかったことを覚えています。
精神病院や精神科を受診することは、自ら「まっとうな人間でない」ことを認めるようなものであり、恥ずべきことだ、と思っていたところがあったからです。
ましてや入院なんてことになると……。身体の拘束や虐待が行われることも少なくなかったかもしれないし。
そんな時代背景であったのだということをよくよく考えなおすと、この家族への見方も少し変わりました。両親の葛藤も少しは理解できるような、非難ばかりもできないような、そんな気持ちに変化してきた。
というわけで、今回も自分のものの見方の浅さを痛感したのですが、うーん、……それでもやっぱり両親の責任は大きいなぁ、と思ってしまいます。
追記
ハンディ・カメラ(と言っていいのかな?)で撮った家族の記録が全国公開され、多くの観客が鑑賞することになった本作。
大むかしに、ヴィム・ヴェンダース監督が「テクノロジーの発達により、いまに誰でも映画を撮れるようになる」と語っていたことを思い出しました。
本当にそうですね。その気になればスマホでも映画が撮れる。すごい時代になったもんだと思うと同時に、未来を予見するヴェンダース監督の慧眼に感心させられました。
当然ですが、現実です。
壮絶な、家族の記録
冒頭、音声のみが流れますが
それが一番最初の記録だそうです。
丁度、
知りあいの内科医が、メンタル不安定だったのですが、いよいよ症状が出てきて入院された所でした。その内科医も、ご両親も医師だったので、このドキュメンタリー映画と重なり、ぜひ観たいと思いました。
驚いたのは、弟である監督も
お姉さんの事で精神的に病んでいた事、
当然、そうなりますよね…
10代の少年期に、姉に襲われたらどうしようもないから反撃して、そうすると殺してしまうかもしれないけど仕方ない、とまで考えていて。
安心できるはずの「家」が
全く安心出来ない場所なんて、辛すぎます
メンタルやられますよね。
そんな少年時代を過ごし
全く進歩しない実家の危機を変えるべく
映像を撮り続ける後の監督である弟。
昔の8ミリの映像に(監督が生まれる前の映像)
とても裕福な家庭
知的なご両親が映っています。
監督は1966年生まれ、私も同世代です
全く私とは生活環境が違う…
監督も将来は研究者になるかも、と幼い頃考えていたそうです。
やっぱり環境が与える影響って、凄いですね。
そういう環境の家庭だったんですね、
お姉さんは疑う事なく医師になる道を選んだけど、結果的には、
どうやら合っていなかったのでしょうね
4浪して医大生に、
座学?が終了し
研究実習が始まり最初の症状が出たそうです
それからのお姉さんの症状は壮絶です
印象的だったのは…
夜中の大声、
母親が部屋に入って行って、それでも止まない声
で、普通の顔をして部屋から出てくる母親
異常が日常で
異常を異常と認識しない両親
お姉さんを病院に連れて行かない理由を
母親は「お父さん」のせいにして
父親は「お母さん」のせいに
でも、冒頭の音声で
「どうしてよ!?私の家族に精神分裂症なんか!?」って、母親が叫んでたんですよね…
どっちだったんでしょうか?
いや、どちらも、なのかな…?
お葬式で
「彼女なりに充実していたろう」と言っていた父親
そうであろうと思いたかったんだと思う。
叔母さんは
「まこちゃんは本当に天使のような子供だったけど、少し神経質だった」って。
こうなってしまったけど、家族としては仕方なかった、、的な事を言っておられてびっくりしたけど、それは息子である監督の気持ちを汲み取って、ご両親を庇った発言なのかな、と後から思いました。
最後のインタビューで父親が
「失敗はしていない」と言っていて
娘のことは愛してはいたけれど
そういう人種の人だと感じました。
もしくは
息子には後悔してるなんて懺悔するのは
父の権威があって言えないのかな…
その方が、人間らしいと思いました。
【"自覚無き、両親による治療無き監禁”今作は、精神疾患を患った娘を、医者である父と研究者の母が家に閉じこめた20年を記録した、恐ろしきも哀しき鬱ドキュメンタリーである。】
ー ご存じの通り、日本には”恥”という文化がある。武士階級から始まった文化だが、徐々に庶民まで広まって行った。
故に、古来、日本では精神疾患に罹った者を地下牢などに隠したりしてきた。その流れで1900年に「精神病者監護法」が施行された。”看護”ではなく、”監護”である。その後、この法律は名を変えて来たが、1965年まで続いていた。
無くなった主な理由は、人権と、精神病院の普及である。
だが、今作では恐ろしい事に現代の"自覚無き、両親による治療無き監禁”が、ドキュメンタリー映画として記録されているのである。ー
◆感想<Caution!内容に触れています。>
・今作は、ハッキリ言って恐ろしいし、哀しいし、観ていて気が滅入るし、精神状態が安定していない方は観ない方が良いのではないかと思った程、重い作品である。
・自分に対し面倒見がよく優秀だった姉が、医学部在籍時代に精神状態がおかしく成る。だが、医者である父と、研究者の母は、その事実を認めずに20年近くが経過する。今作の監督であり、弟でもある藤野は、映像制作を学び、自宅に頻繁に帰り、姉と両親の姿を映し続ける。そして、両親に今の状態はオカシイと説得し続けるのである。
・だが、両親、特に母親は発症時に精神病院に行き、問題ないと言われたと真面目な顔で言い続けるのである。そして、”姉の様子がオカシクなったのは変な奴が来るからだ”。”とか訳の分からない事を延々とカメラに向かって話す。観ていて滅入る。この人は、自覚無き治療無き監禁を20年以上して来たのだと思うと、恐ろしくなる。
母が、認知症気味というナレーションも入るが、常軌を逸している。
・父親も、強くは反駁しないが、娘の状態を観ても医者に連れて行こうとはしないのである。
・そして、母が亡くなり、ステージ4の癌に侵された娘は、漸く治療に行き精神的に落ち着いた様子の映像が流される。故に哀しいのである。何故に、発症時に心療内科医に連れて行かなかったのかと思うからである。
<そして、還暦を迎えた姉は亡くなる。藤野監督は残った父にこの映画の制作の許可を得る際に父の考えを聞くのである。
その時に、初めて老いて腰の曲がった父は、”妻に引きずられて、恥の概念があったために心療内科に連れて行かなかった事”を認めるのである。
今作で描かれたような家庭は、まだあるのだろうか・・。心療内科に通院している人の数が激増しているストレスフルな、現在の日本において。
今作は、精神疾患を患った娘を、医者である父と研究者の母が家に閉じこめた20年を記録した、恐ろしくも哀しき鬱ドキュメンタリーなのである。>
家族の記録
統合失調症の有病率は約1%と言われており、100人にひとりは統合失調症を患っている可能性があるので、身近にそのような人がいることも十分にあり得ますが、適切な医療を受けることで改善できることが理解されていないことも多いのかもしれません。
現代はYouTubeなどで専門家による統合失調症に関する正しい情報も入手しやすい時代ですが、高齢者など情報へのアクセス手段が限られていると、古い固定観念のままということもあり得るかもしれません。
映画の後半でビートルズの曲が流れてきますが、40数年生きてきて、ビートルズがこんなにも心に染みたのは、この映画が初めてです。
多くの人に見てほしい、そして考えてほしい映画です。
「どうすればよかったか?」って? すぐ受診しろよって話。 認めたく...
統合失調症の家族を持つものとして
①弟が統合失調症を患っています。
統合失調症は昔は精神分裂症という名前で、精神分裂症=(今は禁止用語になっていますが、昔は普通に使っていた)“キ○○イ”というイメージで見ていられました。
弟は私がシンガポール駐在中に発症したのですが、帰国してみると「手遅れ(と最初に入院した精神病院の医師に言われた)」の状態で、質問をしただけでしたたかに殴られました。
当時住んでいたのは奈良県の片田舎の旧村、父母は戦前(昭和初期)生まれのザ・昭和人。
母によると父は体裁を気にかけて弟を医者に連れて行かなかったそうです。
だから、この映画の内容は他人事だとは思えず冷静な判断は出来ないかもしれない。
②「どうすればよかったか?」。後で悔やんでも仕方のないことだし、家族にとっても答えが出せない問いかけではありますが、やはり弟の姿を見る度にその問いを繰り返さずにはいられなくなります。(現在は施設に入っております。)
③私も最初は統合失調症に対する認識が乏しく、暴力を振るう弟を力で屈服させたら大人しくなるのではないか、と馬鹿な事を考えて大喧嘩をし、後々敵視されて“増悪”したときは集中砲火を浴びるようになり、家を出ていく羽目になりました。
もっと統合失調症について学べばよかったと後悔しています。自分のためにも弟のためにも。
③統合失調症と一言で云っても、人によって症状は千差万別。そこにその人が元々持っている性格も投影されるので、一言で「こう対処すればよい」と言えないのも難しいところです。
本作の監督のお姉さんは、医者に診て貰えなかったのはが両親が断固として拒否していたのが原因で、二人が折れてからは素直に(と思うけれども)医者に行ったようだし薬もちゃんと呑んでおられたようだ。遅かったかもしれないけれども晩年は穏やかに過ごされたように思う。
私の弟は元々頑固者で人の言うことを素直に聞かない(B型だから?)し、人に注意されたり怒られるとその人を避けたり反発する性格だったうえ、病識が無かった(これは統合失調症患者によくみられる傾向)ので、こっそり好きなジュースに入れて呑ませたりして結構苦労しました。
市の福祉課の親切な職員さんのお陰で施設に入ることが出来、やっと素直に薬も呑んでくれるようになり、煙突の様にふかしていたタバコも止めて穏やかに過ごせるようになっています。
発症から実に30年近く掛かりました。
我が家族にも(父は弟が施設に入る前に他界しましたが)やっと平穏な日々がやって来ましたが、それでも弟は一生をほぼ無駄に過ごしてしまったように思われて(統合失調症の人でも社会復帰して自立して働いておられる方はおられるのに)、自分はこうして好きな映画を観て人生を楽しんでいるのを考えると後悔の念が時々は浮かびます。
「自分がもう少し真剣に向き合っていたら(正直、逃げていた時期もありましたから)」「あの時どうすればよかっただろう」と…
最近さすがにそう思う回数はかなり減ってきましたが、本作を観て再度来し方を振り返りました…
間違いだったのかな
あえて酷い親であったと言いたい
監督の藤野知明氏は1966年生まれ。
お姉さんはぼほ私と同じ年齢だと思う。
時代背景を考えると両親の姉に行なったこと、行なわなかったことは同情できる、というのが優しい態度なのだろう。
しかし、
統合失調症と呼び名が変わったのは2002年。
知らなかったとは言わせない。
私は同時期に地方都市に生きたものとして、時代の空気のせいにはしたくない。
父親は最後の最後まで、25年の過ちを母のせいにし、あまつさえ「娘の人生は充実していた」と正統化をはかる。
監督の親に対する怒りは、親の姉に対する態度のみならず、自分自身への親のあり方に対しても向けられていると抑制的なインタビューの端々から感じられた。
皆、それぞれに辛い想いを抱えて来たのだ、無理もないことだ、というのは簡単だ。
しかし娘を医療につなげなかった責任は両親にあるとあえて言いたい。
親も可哀想なのは当然だ。
しかし最後まで見終えて、親の、特に父親の無責任さは強く指摘すべきだと、最後の父親へのインタビューのあとの監督の「カット、カットしてください」に感じざるを得なかった。
ポイントは弟である監督が、姉のことでよい結果を導けなかった忸怩たる想いだ。
責任の一端を負っている身内としての感情だ。
死顔をさらす背景に、姉と弟の悔しさを感じないではいられない。
20年にわたる苦しみは数ヶ月の入院の投薬で劇的に改善されてしまう。
このあっけなさに対する監督の想いをくみ取らなくてはならない。
この映画は「悲しみ」で終わらせてはならない。
「怒り」を伴って観なくてはならない。
25年は実はあっという間の時間だ。
どうすればよかったのか?
に明確な答えがあるはずがない。
だからこそ、監督の抑制的な言葉の裏の激しい感情を読み取らずにはいられない。
あの簡易な神棚への礼拝が合理性一辺倒でない一家の闇を深く表してしていると感じた。
結論「どうしようもなかった」
公開以来観に行かねば、と思いながら内容の重さに腰がひけており…やっと観てきました。
途中で何度も胸が苦しくなり、緊張で心臓がバクバクし、並のホラー映画より恐ろしく、悲しみで胃がギュッとなるような、なかなかない貴重な映画体験でした。
観てよかった。
この映画を理解するに当たり。
お姉さんが統合失調症を発症した1980年代半ばは、精神病に対する差別や偏見は今よりもずっと酷かったことを心に留めておく必要があります。
キ○ガイ、気○い、などの放送禁止用語がTVなどでもバンバン流れていた時代です。
2000年代になり、確か皇后雅子様(奇しくもお姉さんと同じ名前…)が適応障害になり、そのあたりから鬱病、新型うつなどの病名が広まり、精神疾患への理解がだんだんと広まっていった記憶があります。
ですので初動に関してはこのご両親を責める気にはなれませんでしたし、途中で何度か弟さんが方向転換を試みようとしたにも関わらず頑なに診療を拒否をされたのは、夫婦揃って医師(研究者)ゆえのプライド、また老齢故の頑固さが勝ってしまったのかなと。
大事な娘に精神病の烙印を押すなんて恐ろしくてできない、両親のその優しさが仇になってしまったんだろうと涙が出ました。
医者にも診せず南京錠をかけて監禁、なんて字面だけ読むと鬼畜の所業のように見えてしまいますが、なりゆきでそうするしかなく、いつの間にかその状態が恒常化してしまったというのが映像を見るとよく分かりました。
母親の認知症をきっかけに支援につながれたことは幸いでしたが、監督ご自身、数十年間にわたり老いていく親と病状が悪化していく姉を側で見ているのはどんなに辛かっただろうと想像します。
父親が姉の葬儀で「彼女なりに充実した人生だったと思う」と述べ、お棺に医学論文を入れたシーンはなんとも言えない気持ちになりました。
父親の欺瞞だ、と怒る人もいるかと思いますが、今自分は子育ての真っ最中ですが、自分の至らなかった点を将来子供になじられたとして、素直に謝罪できる自信がありません。
この父親のように「なかったこと」にしてしまう可能性は誰にでもあるかと。
もう一点、母親と仲が良かった妹さん(監督にとっては叔母さんにあたる方)が語るシーン、「あんな風になってしまって、でも身内だからこそ何も言えなかった、口出しできなかった」みたいなことを口にされていて、これにも深く頷きました。
大事な人を傷つけたくなかったり、関係を悪くしたくないから真実を言えない、ってことは往々にしてありますよね。
残酷な見方をすればお姉さまはご両親の判断ミスの犠牲になったと言えますが、監督がこうしてお姉様の人生を撮影し続け、映画として公開されたことで浮かばれる部分もあるかと思います。
身内の恥部を晒すことはなかなか出来ることではありません。
監督の勇気に拍手を送ります。
監督の親に対する断罪
2025年劇場鑑賞54本目。
エンドロール後映像有り。
統合失調症の姉を弟は病院で診てもらいたいのに、なまじっか父親が医学の研究者であったために、必要ないと言って診せず、母親は診せたら父親はプライド折られて死ぬからダメと言って診せようとしない。ついには家に内側から鍵と鎖をかけて母娘共々家から一歩も出なくなってしまうが、あるきっかけで姉に劇的な変化が起こり・・・というドキュメンタリー。
若かったお姉さんが最後おばあちゃんになっていくくらい長い期間のドキュメンタリーで、ここまで出すのよく我慢したなぁ、というのが一つ。
後、タイトルにある断罪云々は、自分がこの映画を見て感じたことで、いやそうじゃない、という解釈も当然あると思います。
自分も福祉関係に勤めていて、それこそ最初は上司に薬は悪で、必ず対話や関わりでなんとかなるんだ、という風に教えられましたが、人によっては多少大人しめにはなるものの、その薬を飲んでいる間は本当に落ち着いていて、別に笑顔もなくなるわけでもないのに、親がなんか元気なくて可哀想とその薬をやめた途端また自傷行為をするようになった方を知っているので、病気なんだから薬飲めばいいじゃん、と自分なんかは思いますので、この監督の親に対する憤りが分かります。
身につまされる
両親の深い愛情を通じて、かつての精神科医療の実体もほの見える?
この日本では、精神障害者は、長らく人間扱いされてこなかったとも言われます。
いまでこそ「統合失調症」という病名ですけれども。
しかし、2002年に呼称変更される以前には、あたかも患者の人格を否定するかのような、差別的・侮蔑的な病名だったことは、周知のことです。
(まだまだ評論子が子供だった頃は、周囲の大人たちが精神科病院を指して、まったく侮蔑的な名称で呼んていたことを覚えてもいます。そのニュアンスから言っても、当時の世評として精神科は、不幸にも精神面が正常でなくなってしまった人を隔離・幽閉するための施設であって、医療者の継続的な管理下で病気を治療する施設という受け止めではなかった)
そうして、お二人とも医学方面の研究者だったという藤野監督のご両親は、そういう精神科医療の(当時の)現状をよくご存じで、それゆえ、件の医師が書いたという論文に難くせをつけてまで(?)、お嬢さま(藤野監督の御姉さま)に医師の確定診断を経ることを避け、精神科病院に入院加療させるという方途に躊躇(ためら)いがあったのではないかと、評論子には思われます。
それは、世間体とか、医学の研究者としてのプライドとかいうものでは、決してなかったと、評論子は受け取りました。
(むしろ、神の御業なのか病を得てしまっても、なお愛娘には、あくまでもひとりの人間として接したいという、ご両親の深い愛情すら感じられる)
「身体の病気も、精神、つまり心の病気も、病気に変わりはありません。早期の治療が望ましいことは、いずれも同じです。しかし、長い間、心の病気は、病気としての正し
い扱いを受けてきませんでした。(すなわち)長い間、精神障害者は、いわれのない差別を受けてきました。精神障害者は危険で隔離すべき対象とされてきたのです。明治の中頃まで、精神障害者への対応は、加持祈祷などの民間療法と私宅監置が中心でした。
1950年に一応の近代立法である精神衛生法が施行されましたが、私宅監置が精神病院への収容に変わっただけで、それまでの精神障害者に対する危険視と隔離の発想は引き継がれました。精神衛生法はその後改正を重ね、精神保健法を経て現在の精神保健福祉法になりました。しかし、長年にわたり精神科病棟の職員配置は一般病床より低く抑えられてきたなど、精神障害者に対する差別は医療の現場にも根強く残っています。閉鎖病棟の多さ、解放処遇の不十分さ、社会的入院など、今後改めなければならない。多くの課題があります。」(「Q&A高齢者・障害者の法律問題」日本弁護士連合会高齢者・障害者の権利に関する委員会編、民事法研究会刊、2005年)
前同書は、また「心の病気は、身体の病気と同じように誰でもかかるかもしれない病気であり、そして心の病気に必要なのは隔離ではなく医療であるという当然のことが、一日も早く社会全体の共通認識となることが望まれます。」とも指摘しています。
タイトルにもなっている「どうすればよかったか?」という藤野監督による本作の投げかけ―それは、とりも直さずご家族をめぐる藤野監督の葛藤―も、ここにあったことは、疑いがなかったかとも思います。
(藤野監督のお父様が、「多くの人に観てもらいたい」という本作の公開を快諾なさった真意も、他ではない、そのことにあったことも、明らかだと思います)
それらの点において、本作は、十二分な佳作だったとも、評論子は思います。
(追記)
蛇足を加えれば、評論子の周囲にも統合失調症を患って休職し、今は復職を果たしている方もいらっしゃいます。
今は、良い薬も開発されて、必ずしも難治の疾患ともされてはいないようです。
しかし、それは、あくまでも令和の「今」でのこと。
その尺度で評すると、本作の前提(時代背景)を誤るように思います。
問題作
「どうすればよかった」に正答は存在しない
両親の不都合な真実を追究する魂の記録
家族の物語
「家族」
答えは出ているので、題名がしらじらいという論調もありますが、問題なのは何故両親は、弟の懸命な説得に耳をかさず、受診から遠ざけたままにして、状態を悪化させてしまったのかということにつきると思います。
詳しくは書きませんが、家族の情愛やエゴは得てして、冷静な判断を下せなくする機能を果たすということかと思います。そのような事実が、ごろりと観客に提示されているように思いました。それが観客の自らの経験と化学反応を起こし、ある種の共感を呼ぶのだと思いました。
やっかいな存在。その名は「家族」。
それでも、憎み合うだけというわけではなく、いろいろあったけれど、多分それぞれが大切な存在として意識されていることがうかがわれる点でもよかったと思います。
父母ともに優秀な医師の元に生まれた優秀な医学生だった姉。そんなエリート一家もやはり家族故の情愛やエゴは普通の家族と多分変わらない。
ラストシーンが目に焼き付いて離れません。
両親の思いと本人の重圧
全204件中、41~60件目を表示