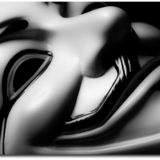名もなき者 A COMPLETE UNKNOWNのレビュー・感想・評価
全338件中、61~80件目を表示
ボブ・ディランって、意外とロックなんだね
冒頭のウディ・ガスリーを讃える歌でもう泣けました
人生、終わりかけのウッディにとって、あんな歌、歌われたらね
グッときました
最後のフォークフェスティバル、昔は体制批判していたフォークソングが、体制になってしまってたんですね
ぶっ壊したディランが痛快でした
結局、最後にフォークを歌っておさめたのは、フィクションじゃなくて、また趣きがあった
ボブ・ディラン世代って、もうかなりのお歳なんじゃないかな
三田の田舎では客が入らなくて、さっさと終わる見通しです
実際、僕もあまり知らない
”学生街の喫茶店”で名前が出てくるレジェンドらしい人
”風に吹かれて”くらいは知ってるけれど、ジョーン・バエズが歌っている印象が強い
ジョーン・バエズ
深夜のラジオでよく流れてました
よくとおる美しい声に聞き惚れてましたが、ボブ・ディランが同時期に活躍してるとは知りませんでした
もっと昔の人だと思ってた
ビジュアルといい、既成概念をぶっ壊すハートといい、意外にロックンローラーなんだ
身長、170cmを切るヤサ男だったのも驚き
あんなにタバコ吸ってても長生き
神に選ばれ許されている人なんだろうね
立ち止まりたくないのに…
音楽映画に外れなし
とても良いボブ・ディラン作品
採点3.9
尺が長めなので時間が中々合いませんでしたが何とか足を運べました。
ボブ・ディランが無名の少年から、稀代のフォークシンガーとして駆け上がる時代を描いた作品。
ティモシー・シャラメがまずすっごい合っている。
歌も頑張っていたが、それよりも気だるい喋りや掴めない雰囲気が実に良かった。
もちろんエドワード・ノートンにエル・ファニングもとても良かったです。
いわゆるロックスターと違い派手な浮き沈みがないが、その淡々とした描き方が余計に彼にフィットしてました。
ジョーン・バエズとのステージや距離感がやっぱり印象的になってましたね。
そしてブリティッシュインヴェイジョンへ触れてから、徐々に変化していく音楽性。
クライマックスは「フォークへの裏切り」を確実にした、ニューポートフェスティバルのステージ。
このシーンが凄いよくできており、実に見応えがありました。
ここから更に大化けするのでもう少し見てみたい気持ちもあるのですが、ここで止めるのも収まりが良かったとも思います。
若かりし、とても良いボブ・ディラン作品でした。
謎は謎のまま・・
当時のクラブの雰囲気とか時代背景とかが想像できた点面白かった.
フォークからの転換期の雰囲気などなかなか良かったし,歌い方もディランそっくりで見どころのひとつだった.
だけど,映画のディランは気取っていて,二人の女を転がすだけ転がすあまり好感が持てないやつだった.あれだとなぜか音楽の才能だけものすごい謎のロクデナシじゃないか.
あまりにもステレオタイプのディラン像すぎて新鮮味が全然なかった.
ディランの実像や人間性とかそのへんもう少し掘り下げてほしかった・・・
まあ,結構ディランは詩人であったり歌手であったり時にはペテン師みたいであったりと,一般人には謎な人なので,謎は謎なまま,この映画では何も解き明かされることはなかったということか.
偉大な音楽家誕生の瞬間
ボブ・ディランのファンでもなく、60年代のフォークソングに興味があるわけでもない。
鑑賞の目的は今をときめくティモシー・シャラメがボブ・ディランをどう演じたのかに興味があることと、名将ジェームズ・マンゴールドが監督だから。
演奏も歌もシャラメ本人が演じたボブ・ディランはあえて似せようとはしていないが、時代を先取りするカリスマを圧巻の演技でシャラメ流のディランに昇華していた。
なのに、映画全体を通して心が揺さぶられるものがない。なぜだ。
映画はボブ・ディランの伝記映画ではなく、19歳の青年が故郷を離れ、ギター片手にニューヨークにやってくるところから、才能を認められ天才フォーク歌手として成功するが、フォークのレッテルに嫌気がさし、65年のニューポート・フォーク・フェスティバルで禁断のエレキギターをかかえ「ライク・ア・ローリング・ストーン」を歌い、会場の大ブーイングを受けながらも歴史的パフォーマンスと称賛され、時代が移り変わる、というおよそ5年間を描いている。
個人的ではあるが、登場する当時のフォーク歌手ピート・シーガーもジョーン・バエズもジョニー・キャッシュも知らない。
ディランのこの頃の曲はどれも名曲でよく知っているが、あまりにスタンダードで当時のフォーク界においてどれほどの衝撃を持って迎えられたかの実感がまるで無いのだ。
また、ディラン本人がそういう人なのかわからないが、曲作りの苦悩や人間関係の苦悩などはまるで描かれない。
恋人のシルヴィ(エル・ファニング)や恋仲にもなるフォーク歌手バエズ(モニカ・バルバロ)もいつの間にか部屋にいたり別れたり、復縁したり経過は描かれない。
実話の音楽映画と人間ドラマの両立はなかなか難しいのは過去の音楽映画をも然りだが。
ただ、本当に20世紀を代表する音楽の天才は人間関係は苦手なのかもしれない。
尾崎豊が長生きできたら‼️❓ノーベル賞を貰えるだろうか‼️❓
“ファンダム”の根源
本作もアカデミー賞関連での興味で見に行きました。
個人的に伝記モノは苦手なのですが、“ボブ・ディラン”には興味があったので敢えて見に行ったという感じです。
しかし、アメリカ映画では一つのジャンルにしても良いくらいにシンガーの伝記映画が多くありますが(日本映画では見たことありません)、他の分野の偉人伝・伝記に比べて、歌唱シーンをどのように見せるのかというのが付加されているので、別の興味が湧いてきます。
元々洋楽に対してはド素人な私でも、ボブ・ディランは私世代と近い世代の中でも神格化されている人であり、音楽自体はよく耳にしていたので興味深く見させて貰いました。
で、一般レビュー評価値も凄く高くて、彼のファンや音楽そのものが好きな人が喜ぶのは凄く理解できるのですが、「ちょっと高評価過ぎないか?」という疑問も感じてしまいました。勿論、役者の演技や音楽の使われ方とか評価する部分は多々ありましたが、伝記映画としては個人的には特筆するような内容だとは思わなかったし、ごく普通の物語だったような気がしました。
ただ面白いと思ったのは、本作の核となる部分だとは思うのですが、ラストのコンサートでのあわや暴動にもなり兼ねない様なファンの様子がちょっと異常な気がして興味深かったです。
あれって、コメディーですが『ブルース・ブラザーズ』の中にも似た様なシーンがあって、カントリー専門のライブハウスで全く違うジャンルの音楽を演奏して客が暴れるシーンをちょっと思い出してしまいました。
アメリカにはああいう音楽ジャンルでの嗜好がハッキリと分かれていて、自分の好きな音楽でないと認めないという文化が根付いているのでしょうかね?
これこそ今の“ファンダム”という言葉(現象)の意味の根源ですよね。
たまたまなのかも知れませんが日本の場合の音楽(歌謡曲)というのは、戦後テレビ番組を中心に広がり、そこでは民謡・演歌・ポップス・フォーク・ロック全てのジャンルが融合した形で見せられていて、それぞれにファンは存在するが、他のジャンルを完全否定するという文化には(幸いにして)ならなかった様に感じるので、こういう風景を見せられると「なんで?」という気持ちになってしまい、あまり理解出来ないのですよ。
本作の核である、ボブ・ディランという音楽の天才が(後にノーベル賞受賞)、一つのジャンルに捉われず創作して行く過程に於いてのアメリカ人気質(文化)に対する反逆児として、時代の申し子的な存在として描かれていた様な気がしました。
そして、今やアメリカは気持ち悪いくらいの、行き過ぎた多様性・ポリコレ病を患ってしまっていますけどね。
追記.
昔見たけどどんな映画だったか完全に忘れてしまった『ウディ・ガスリー/わが心のふるさと』をもう一度見たくなりましたよ。
ボブ・ディランを知るきっかけになりました
知らないからこそ楽しかった
60年前のアメリカのこともボブ・ディランのこともよく知らないけど、映画の雰囲気、ストーリー、音楽、魅力的な俳優達がとても素敵で、映画館で観てよかったと思える作品でした!
あと、60年前の喫煙マナーが無茶苦茶すぎてびっくりした。
難しい
おもわず曲を聴きたくなる
全338件中、61~80件目を表示