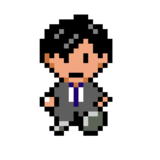「アメリカ現代史とともに歩んだボブ・ディラン」名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN minavoさんの映画レビュー(感想・評価)
アメリカ現代史とともに歩んだボブ・ディラン
前情報でティモシーがボブディランのイタコ芸するのはわかってたので、まあまあ楽しみにIMAXで鑑賞。
結論から言うと、アメリカの20年代から60年代に生まれた広義の大衆音楽の歴史をディランとともに俯瞰できるという、ついに数多のミュージシャン映画の決定打がでた印象。アメリカ音楽の歴史の目撃者になれる映画と感じました。
正直に言えば、裁判所前でピートシーガーが「我が祖国」を歌ったときにもう泣きました。(その時点ではボブディランはまだ歌ってません笑)そこから始まるボブディランとウディガスリーの出会いの意図や、劇中で語られる音楽について解説します。
ボブディランの憧れの人、ウディガスリーの音楽は、1920年代にまだ荒地のロスアンゼルスに季節労働者として移転してきて、作物が育たないばかりかひどい砂嵐が襲いかかり、貧困にあえいだという経験がバックボーンにあります。映画の中で繰り返し流れる、砂嵐の歌はその頃の経験から生まれたもの。ちなみに冒頭でピートシーガーが歌う「祖国の歌」はウディガスリー最大のヒット曲。明るいメロディですが、実はアメリカに裏切られたという思いを裏に潜ませた曲だと想像することは難しくありません。劇中では、ボブディランがウディガスリーからどういう影響を受けたか語られないため、こちらを補完することをおすすめします。
次にディランがジャンルレスな発想だったことを示すエピソードをきちんと見せた意義は大きいと思いました。黒人教会のライブでディランの次にブルースデュオのサニー・テリー&ブラウニー・マギー が出て、ディランのハーモニカにお世辞をいうなんてブルースファンにはたまらないシーンもあります。
また、ディランが「追憶のハイウェイ61」のためにセッションバンドを組む時に、名指しでマイクブルームフィールド(劇中に名前だけ出てくる白人ブルースバンド、ポールバターフィールドブルースバンドのギター)に依頼するところにも痺れました。ディランが音楽的にブルースに近い距離感だったことがわかりました。
ポピュラー音楽の歌詞の世界に詩的世界観を持ち込んだディランは、サウンドの面でもさまざまなジャンルを取り込み進化させたことが伝わりました。