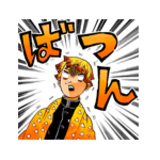敵のレビュー・感想・評価
全263件中、201~220件目を表示
25-007
「敵」がいることが不幸なのかあるいは幸せなのか、考え込んでしまう一作
モノクロームで映し出される長塚京三の容貌は今までの役柄以上に年齢を感じさせますが、その所作の数々、特に食事を行う際の動きなど、クロースアップでも美しさを感じてしまうほどに洗練されています。
元大学教授なだけに、言動はあくまで物腰柔らかく知性的、かつ洗練されているけど、どこか高慢さを醸し出している「渡辺」という人物を、彼以外の俳優で演じることは不可能だったのでは、と感じさせます。
吉田大八監督はこの役を長塚京三を想定して練り上げていった(いわゆる当て書きした)と何かで読んだ気がするのですが、深く納得です。
物語が進むにつれて、彼の前に、「敵」なるものが付きまとってくるわけですが、それが何であれ、渡辺の理想的な生活を破壊しにかかってきて、静謐に保たれていた秩序やつじつまが千々に乱れていきます。その顛末を、観客も渡辺とともに体感していくことになります。
原作小説の出版(1998年)以降だけをとらえても、(本作のとらえ方にもよりますが)某アカデミー賞受賞作品を含め、本作に近しいテーマ設定の映画作品は、実は決して少なくないのですが、ということは、観客が本作のテーマを映画作品という形式で解釈し、受容する解像度も高まっているということでもあります。
その意味で、原作出版時のような新鮮な心理的衝撃を現代の観客が感じる余地はやや少なくなっているかも知れませんが、一方で本作の中核的なテーマを映画作品として味わい、理解するのに、今この時代はむしろ適切なのかも知れません。
渡辺が怯える「敵」の存在。その正体が見えてきたとき、それは渡辺にとって不幸なのか、いやむしろ幸福なのか、考えさせられる結末でした!
老いていくのは怖いけど…
“おい”の棲家
コロナ禍中、30代に読んだ筒井康隆の小説『敵』を再度読み直していた吉田大八監督はこう思ったそうである。家の中に閉じこもっている男の日常が妄想に侵蝕されていくストーリーは、ロックダウン下にある現代社会にも相通じるポテンシャルを持っている、と。脚色大魔王の異名をとる吉田大八監督曰く「今まででもっとも原作に忠実な映画」だそうで、90歳をこえて車椅子生活状態の筒井康隆があと20歳若かったら、実際主人公へのキャスティングをオファーしていたかもしれない、と語っていた。
奥さんが20年前に他界後フランス語大学教授を退官した渡辺儀助(長塚京三)は、古い家で独居生活を送っていた。原作小説同様、炊事洗濯掃除の作務を執拗に追いかけた前半を見ていると、こりゃヴィム・ヴェンダース監督『PERFECT DAYS』とおなじ“小津安二郎”へのオマージュか、と錯覚させられる。渡辺家に度々現れる色っぽい元教え子鷹司を演じた瀧内公美には、実際吉田監督から「原節子のイメージで演じてほしい」というオーダーがあったそうなのだ。あれあれやっぱり小津なの?と思いきや...
この映画、同じモノクロで撮られているのだけれど“小津調”とはどこかニュアンスが違っている。劇場で見ながら誰かのモノクロ映像に似ていると思ったのだが、監督自らがインタビューで白状していたようにおそらく“ホン・サンス”のパクリだろう。硬派なようでどこか胡散臭いコントラストを効かせたモノクロ映像は、まさにホン・サンスそのもの。明確に死を意識させるキャラをどこかで茶化しているホン・サンスの近作同様、預貯金が底をついたら自殺しようと遺書まで用意している殊勝な儀助を、筒井や吉田はどこか覚めた目で見つめているのである。
「健康診断じゃ健康にはならないよ」なんて、悟りきった名言を友人(松尾貴史が筒井康隆にそっくり!)に披露する儀助ではあるが、(妄想の中では)瀧内公美や河合優実演じる若い娘に手出しする気満々だし、(やはり妄想の中で)死んだ女房(黒沢あすか)と念願の湯船につかったり、(これもやっぱり妄想の中で)キムチの食いすぎで出血した肛門に内視鏡を激しく突っ込まれたりと、本音ではまだまだ“若さ”の象徴でもある“春(性)”にしがみつきたい儀助77歳なのである。
が、そんな儀助のパソコンに謎のスパムメールが入り始める.....「敵が北からやって来る」何かにしがみついても、逃げても、物置小屋に隠れても、棒切れを持って立ち向かおうと抗っても、どこまでもどこまでも追いかけてくる“敵”。隣の『裏窓』から眺める分には暇潰しの格好のネタになる“敵”。“枯井戸”のごとくけっして甦ることのない“敵”。フランス人なら絶対道端から拾いあげない“犬の糞”のように悪臭を放ち、しまいにはふんずけられる運命の“敵”。そんな“敵”が、自分が予想すらしない時に目の前にふいに現れたら、あなたは素直にそれを受け入れますか、それとも.....
※因みに遺産相続を受けた槙男くんは儀助の“おい”でしたよね。お後がよろしいようで。
転調する映画
『PERFECT DAYS』が綺麗すぎるなと思った部分を補ってくれ...
敵とは?
人間が弱ると、わき出て来る「敵」
原作未読。筒井氏の作品なら面白いだろうし、吉田氏の演出なら外す訳もない。
長塚氏の少し気の小さい感じもじつに役にあっていたし、女子部の存在もぶ厚く彼の計画を妨害する敵として素晴らしい。後半から入ってくる音楽も丁寧に積み上げられた前半を壊す事なく寄り添ってくる。
原作自体1998年出版、筒井氏64歳ころ書いたものでおそらく老いと、煩悩、思い通りにならなくなっ肉体という檻に閉じ込められた自分の被害者意識からくる妄想も自身のなかから抽出されたのではないかと思う。
調子こいて仕事や飲み屋でモテた気になっている自分自身も、映画と被ってお恥ずかしい次第である。
何とか清潔に老いて、サラッとこの世から消えたい物だと切に思いながら映画館を出た。
凡人には理解不能?でした
モノクロ映画なのに色を感じる不思議な作品
「土を喰らう12ヶ月」みたいになって欲しかった
長塚京三さんの主演映画を観たくて、特に吉田大八監督とか、筒井康隆さんに興味はなかったので 、もうどうせなら前半のような、寝て、起きて、食事を作って食べて(いろいろな食事が登場しましたね)、買い物して、執筆して、時々美人(編集者というあたりも、、、)が訪ねて来て、もやもやして、死生観を語って、このままで映画は最後まで行っても良かったです。
途中から敵が出てきてしまいます。
筒井さんですから、そりゃ、訳が分からなくなってきます。
上手くまとめたのは流石だと思いました。
長塚邸の醤油差しとか、エメロン石鹸とか、細かいところまでしっかりしているなと感心しました。
長塚京三さん、最近な長野の自宅をメインに暮らしているとのこと。無理をせずに、まだまだ演技を見せていただけるところを楽しみにしています。
「敵」とは
長塚京三さん主演のモノクロ作品でタイトルは「敵」って、これだけで何だか興味をそそられてしまい、公開2日目に鑑賞してきました。中高年中心とはいえ思いのほか観客が多く、邦画への期待感のようなものを感じました。
ストーリーは、妻に先立たれ、子供もなく、大学教授も辞めて、今は古い一軒家に独りで暮らす70代の渡辺儀助が、時には友人と酒を飲み、たまに訪ねてくる教え子と語らいながら、折目正しい生活を送っていたが、ある日、パソコンに「敵がやって来る」と謎のメッセージが届き、儀助の生活がしだいに変化していくというもの。
前半は、大学教授をリタイアした儀助のつつましく丁寧な生活が穏やかに描かれます。規則正しい生活、手際のよい自炊、近所付き合い、知り合いへの言葉づかい等、儀助の日常生活と共に、儀助自身の人となりも伝わってきて、作品世界へと静かに誘われていきます。とりわけ食事シーンは多く、米を研いで炊き、魚を網で焼き、焼き鳥の串を打ち、漬物さえも小鉢に盛り付けて落ち着いて食事する姿は、悲哀や孤独とは無縁で、男の独り暮らしはかくあるべしと訴えかけてくるようで、ちょっとかっこいいぐらいです。加えてモノクロ映像が、多くを望まぬ儀助の心情とマッチしていて、よい雰囲気を醸し出しています。
そんな暮らしに転機が訪れます。パソコンに届くフィッシングメールに紛れて届く、敵の接近を知らせる警告メール。ただのイタズラと流しつつも、儀助の心のどこかに引っ掛かっていたのでしょう。淀んだ不安がさまざまな形で現れ、後半は妄想と夢と現実が曖昧となった描写が続きます。なんとなく既視感のある描写にも思えますが、儀助同様に観客も不穏な雰囲気に包まれていきます。
果たして、この”敵”は何だったのでしょうか。明確に答えが示されているわけではありませんが、これは、過去の儀助が無意識に作ってしまった敵なのではないでしょうか。むろん実際に敵対しているわけではありません。自分の言動が相手に不快感を与え、敵対心を生んでしまったのではないかという不安が、架空の敵を作り出し、彼の心を苦しめたのではないでしょうか。死期が近づき、これまでの人生を思い返すに至り、そんな心境に追い込まれたのではないかと思います。妻への罪悪感、教え子への邪な思い、若い女性への下心など、それに加えて一人暮らしの侘しさや孤独など、自覚しつつも立場とプライドで否定してきたこれらの思いが、妄想や夢となって現れてきたのではないかと思います。”敵”とは、内に眠る自身の後悔や懺悔なのかもしれません。
また一方で、どんなに清貧な暮らしを送っていても、さまざまな欲から死ぬまで解放されることはないという、人間の本質について訴えかけてくるようで、ちょっと考えさせられてしまいます。
主演は長塚京三さんで、彼でなければなし得なかったであろうと思わせる説得力のある演技が秀逸です。脇を固めるのは、瀧内公美さん、黒沢あすかさん、河合優実さん、松尾諭さん、松尾貴史さん、カトウシンスケさん、中島歩さんら。
認知症ではなく「夢」の物語
独居老人の日常が丹念に描き出される序盤は、生活レベルの差こそあれ、役所広司の「PERFECT DAYS」のような趣きがあり、静謐なモノクロの画面と几帳面で「こだわり」に満ちた生き様に引き込まれる。
ところが、艶めかしい教え子とセックスをしそうになったり、女医からSMまがいの診察を受けたりしたことが夢だったと分かる辺りから、現実と夢の区別が曖昧になっていって、徐々に不穏な空気が流れ出す。
こうしたサスペンスフルな雰囲気は、アンソニー・ホプキンスの「ファーザー」と似ていなくもないが、本作の妄想は、すべて夢の中での出来事なので、主人公は、必ずしも認知症を患っている訳ではなさそうだ。
むしろ、主人公の認知機能は正常で、理性や知性で抑え込んてきた欲求や願望が夢の中で顕在化し、それを整理しきれなくなっているのではないだろうか?
女子大生に大金をだまし取られたり、雑誌の連載を打ち切られたりしたことは、おそらく現実の出来事で、そうした金銭面での不安が、自殺願望や「敵」という強迫観念を生み出したのではないかと解釈できるのである。
ただ、「敵」の正体が、「老い」とか「死」とか「困窮」とかであるならば、北から日本に侵攻してきた外国勢力という設定には、これといった関連性が見い出せず、メタファーとしての唐突感が否めない。
「戦争」とか「殺戮」とかに対する恐怖心を否定するつもりはないが、それを描こうとするならば、それなりの背景なり、伏線なりが必要だったのではないだろうか?
いずれにしても、この映画の主人公のように、下手にボケずに恐怖や不安の中で最期を迎えるよりは、死への恐怖を抱かない程度にボケることは、決して悪いことではないと思ってしまった。
夢と妄想と現実
タイトルから想像した話とは違った
2025年劇場鑑賞19本目。
エンドロール後映像無し、音だけあり。
引退したフランス文学の元教授が、収入と貯金を割って生活費が底を尽きる日をエックスデーと呼びながら暮らしている日常を最初描きながら、徐々に虚実入り混じる構成になっていきます。
あらすじでは敵が現れる、とあったので、カラスや野良猫なのか、詐欺集団なのか(こうなるとビーキーパー)、隣人なのかと色々想像したのですが、思ったより敵でした。いやそういう敵なんかい。
虚実の虚の部分は悪夢といってもいい内容で、そのパートになると調子の悪いボイラーのようなブァァァァンという音が爆音でかかり、不穏感が増していたのですが、最後付近の不穏でもないシーンでもかかっていて、この場面は実は何か恐ろしい事が起きているのかと思ったのですが、スクリーンを出て支配人がいたので「まさか工事とかやってます?」と聞いたら「うるさかったでしょうか?申し訳ございません」ですって。おい!ふざけんな!金返せ!
支度
八十に近づくと三人の女がやって来た!愉しみました。
敵
静謐な老後を過ごす独居老人であるはずが、
既に無くなっている欲望が突然やって来る。
やがて、寝ていたはずの欲望を現実化をできないと、妄想として実現し、
欲求が更に拡大化する。
その結果、
死んだ妻を甦らせ、浮気者と罵倒され!
元生徒を贔屓したことを、アカハラと指摘され!
行き付けのバーの学生女給に好意をもったら、300万円を持ち逃げされる!
終活して紳士面して過ごしていても下心が往年を回顧し暴かれて行く、
その結末は、
かの静謐な生活音はなく、平穏を無くした混沌と妄想の中で自死へと進んで行く…
唯一、老という敵を回避ではなく真正面に立ち向かった時に開放感を気付いたように見えた…
その執着心は、
古い住居にまだ生きずかせているところが、筒井らしい。
オッサンって助平です。
同感です!
( ^ω^ )
敵
筒井康隆の同名小説を、「桐島、部活やめるってよ」「騙し絵の牙」の吉田大八監督が映画化。
穏やかな生活を送っていた独居老人の主人公の前に、ある日「敵」が現れる物語を、モノクロの映像で描いた。
大学教授の職をリタイアし、妻には先立たれ、祖父の代から続く日本家屋にひとり暮らす、渡辺儀助77歳。
毎朝決まった時間に起床し、料理は自分でつくり、衣類や使う文房具一つに至るまでを丹念に扱う。
時には気の置けないわずかな友人と酒を酌み交わし、教え子を招いてディナーも振る舞う。
この生活スタイルで預貯金があと何年持つかを計算しながら、日常は平和に過ぎていった。
そんな穏やかな時間を過ごす儀助だったが、ある日、書斎のパソコンの画面に「敵がやって来る」と不穏なメッセージが流れてくる。
主人公の儀助役を12年ぶりの映画主演になる長塚京三が演じるほか、教え子役を瀧内公美、亡くなった妻役を黒沢あすか、バーで出会った大学生役を河合優実がそれぞれ演じ、松尾諭、松尾貴史、カトウシンスケ、中島歩らが脇を固める。2024年・第37回東京国際映画祭コンペティション部門に出品され、東京グランプリ/東京都知事賞、最優秀監督賞(吉田大八)、最優秀男優賞(長塚京三)の3冠に輝いた。
敵
2023/日本
配給:ハピネットファントム・スタジオ、ギークピクチュアズ
tekinomikata
人生後半の課題
こういう映画が好きな愛好家がいるのでしょうね。東京国際映画祭で3冠受賞作ですし。
でも私にはかなり難解でした。残念ながらお勧めは出来ないです。
渡辺儀助氏が自死を選んだとは思うのですがその様子は描かれていませんし、どのように発見されたかも教えてくれず、次の展開で関係者が集まり遺言書を公開しています。
それまでは彼の現実か夢か痴呆による妄想かの世界に付き合わされます。それはそれで良いのですが彼の死は確かに現実ですのでその最期が解らないと置いてきぼりにされた感じです。
敵とは?メール?北から?黒い顔?銃撃?
何も教えてくれません。見る側に任せるにしても映像が具体的で想像は難しいです。
渡辺氏がプライド高く、自分を律して、人に頼らず、自分を安売りせず、理屈ぽく生きているが、教え子に邪な想いを寄せながら彼女から今ならハラスメントだとなじられたり、若い娘に相手にされ舞い上がた後に騙されて金を取られたり、亡き妻に叱られて、それを後悔して詫びている。
端から見たら何やってんだ、てなもんです。
歳を取ること、受け入れることの難しさと大切さを言っているのかなぁ。
世間や社会を敵と見ず暮らして行くことかなぁと思いました。
これから63歳の自分が人生で向き合う課題です。
全263件中、201~220件目を表示