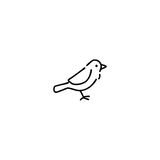この夏の星を見るのレビュー・感想・評価
全225件中、121~140件目を表示
夏の夜空の星座たちを見てみるか〜
みっけもんの良作でした。天体観測に興味をもったことはなかったが、映画の中で紡がれる小さな感動の連続に心を震わせ、自分自身を高校生の彼ら彼女らの気持ちに同期させてくれた。
え!天体望遠鏡って手作りで出来るんだ〜しかも覗いてみたら、ちゃんと月のクレーターまで見える。スターキャッチコンテストてどんなことって思ってたが、先生が呼びかける星座を皆が俊敏な動きでレンズに捉えていた。ISSって「国際宇宙センター」かぁ、。調べたら平均高度400 km(250マイル)の軌道を維持してて、約91分で地球を一周し、1日あたり地球を15.5周回ってるんだとか、それを捉えるってのも凄いわぁ、。
桜田ひより、黒川想矢は主役を張れるようになり有名だが、中野有紗、早瀬憩、星乃あんな、水沢林太郎らの若手の皆さんも(マスクで顔がちゃんと認識できなかったが)、これから期待できますね。あと岡部たかしをはじめとする先生たちが良かった。コロナ禍でまともな学生生活が送れなかった生徒たちにこのような煌めきをを届けようと頑張った先生は沢山いらっしゃったんじゃないのかなぁ、と思います。
映画を見終わった後はSCに入ってる書店に寄り、辻村深月の原作本も買ってしまった。
夏の夜空に浮かぶ星座たちを見た後、ゆっくりと読み始めようと思う。
ストーリーや演出は素晴らしいのだが......
公開一ヶ月後に駆け込みで観てきました。
おそらく重複してる感想もあると思いますが、個人的にはとても惜しい作品でした。
分かってはいましたが前半冒頭以外は、ほぼほぼマスク着用が常でしたのでただでさえ暗い星空の下のシーンが多いのにマスクをしている為、主要キャスト以外誰が誰だか分かりませんでした。
リアリティを追求するのは理解できるのですが。
あと上映館が少なすぎて田舎だと車で1時間位かかる劇場まで行かなければならないので、観客は共感できる世代は見当たらずオッサンや大人率高めでした。
ほんとストーリーや演出効果は最高だったので残念過ぎました。
早瀬憩ちゃんとかマスクなしでもっと観たかった......。
コロナって
コロナでも文化部でも、星の下で心はひとつ(本当に?)
好きそうな映画と思ったし、つまらないわけではないけれど、好きというほど心が動かず。すでに高評価のレビューはたくさんあるので、あらすじなどは省いて理由を考えてみる。
アサ(桜田ひよりさん)が宇宙飛行士に憧れ、高校で天文部に入ってISS(国際宇宙ステーション)を観測する話はワクワクした。
スターキャッチコンテストの場面のアサはもはや顧問の先生を軽く越え、イベントMCのような統率力、推進力。
のほほんとした不思議な包容力と、知性とリーダーシップを兼ねそろえるアサを嫌みなく演じられるのは、桜田さんあってのことだと思う。
それが後半、せっかくISSを観測するのにリクの転校話がテーマになり、主軸がブレてしまった印象。アサのポテンシャルを生かし、恋心は秘めた感じで描く程度がよかったんじゃないかな。
一方、3つの地方(茨城、東京、長崎)の同時進行で描かれる中高生たちは、何か違う世界線の話を無理に同居させている印象。
元サッカー部や旅館の子どもが天文に興味を持つ経緯はちょっとご都合主義で、最初から天文部の設定でもよかったのではないかな。そのほうが、何かNHK教育テレビのような雰囲気にも合っていたと思うし。
何より、天文部なのに元運動部のイケメンを揃えて恋バナにもっていこうとすることに違和感。こういう映画こそ、眼鏡をかけた地味な男子に活躍の場を与えるべきでしょ(偏見?)。この点、映画「君は放課後インソムニア」に出てくる天文部のほうが共感できた。
オンラインでつないで天体を見るというアイディアは良いし、映像はきれい。細かいことは気にせず雰囲気を楽しめばいいのかもしれません。
しかし、コロナで失われた青春を救済するための「奇跡」だったり、オンラインの謎の一体感だったりが、天体観測の良さを減らしてしまった感はあります。
*加筆修正しました。
みんなが言うように大傑作ということは分かった……が
Twitter上で「今年イチ」「人生ベスト級」との意見を多数見かけ鑑賞。原作は未読です。
テイストとしてはゼロ年代の大傑作『夜のピクニック』て似ている。学生たちのひとつのイベントを舞台装置とした群像劇。
見初めて、確かにこれは心が揺り動かされるというシーンはいくつもあり、特に本作の登場人物たちの大目標となる「スターキャッチ」のシーンは本当に素晴らしい限りです。確かにこれは大好きという人が多い映画だと思います。私も大変好みです。
しかし、この映画の欠点と思える点が、この「スターキャッチ」のシーンがクライマックスではなく全体の三分の二のあたりに置かれていることです。
いわゆる三幕構成としての第二ターニングポイントの部分でメインの主人公といえる人物たちに係る悲劇的なシーンが置かれているのですが、
これは本作にとっての明確な役割上の敵対者である『コロナ』とは別の要因によって引き起こされる悲劇なのです。
言ってしまえばこの悲劇とは「主人公の思い人の転校」ということになるのですが、これは(劇中コロナが原因の離婚が理由とは説明されるが)コロナ自体とは全く別の障害です。
「転校してしまう同級生のために頑張る!!」というのは過去数多くの映像作品で観た展開であり、
正直、「スターキャッチ」のシーンまでにあった本作の魅力的な部分が極端に減じたように感じました。
また「スターキャッチ」のシーンとクライマックスにおける「ISSキャッチ」のシーンは、我々素人からしたら難易度の差が分かりにくいのもあります。
鑑賞者からしたらどちらも望遠鏡を覗き込み、目標にセットするという画に違いはありません。
同じ展開を二度やってるようにも見えてしまいます。
ここもなかなか上手いとは言えないように感じます。
なんにせよ、「離れている場所にいるみんなでひとつの目標を狙う」という感動的な「スターキャッチ」のシーンがクライマックスではなく、似たようなシーンである「ISSキャッチ」のシーンを繰り返している(ように感じる)のは本作の明確な弱点であるように感じました。
「スターキャッチ」のシーンをクライマックスにすれば『青春映画としては』より感動的になったのではないかと感じます。
また全体に漂う悲劇的な雰囲気。
コロナは若者の青春を奪ったという雰囲気。
もしこれを徹底するための第二ターニングポイント以降なのだとしたら、もう少しはっきりと『大人達の罪』を描くべきと感じます。
主人公たちの身に降りかかる悲劇、主人公たちから様々な物を『奪った』のは間違いなく『大人』です。
本作の画面上に登場する大人たちは皆『善き人』です。
離婚した親、旅館に嫌がらせした大人。
こういった『悪』を明確に描写し、なんらかの映画的な決着を彼らにつけさせるのであれば、『スターキャッチ』以降の展開も無駄ではないように描けると思います。
少なくとも製作者たちも「大人が若者たちから青春を奪った」という自覚は作品内からも見受けられたので、そこの色を強くする方向性もあったのではないかと思いました。
結論として、
とても魅力的な作品ではあると思いますが、後半部に関して蛇足感を覚えるような点がありました。
刺さる人にとっては確かに人生ベスト級と言わしめるほどの力がある一作ではあると思います。
良作です!!
コロナ禍の時代。自分にできることを探しながらネットで繋がりを広げていく若者たち。理不尽に負けまいと抗う彼らの姿からは、悲壮感だけでなく清々しさすら感じられます。
このサイトを何とはなしに眺めていて気になりました。
コロナ禍、行動が制限される中で活動を続けた高校生のお話。
面白そうなので、早速観にいくことに。・_・シマシタ
" 今 何ができる? "
という、このキーワード。
コロナ禍の始まりの頃の、この問いかけに込められた意味は
「否定的な」ものだったに違い無いと思うのです。
そうつぶやいたメインヒロインは「溪本亜紗(桜田ひより)」。
幼少期よりの憧れの女性宇宙飛行士に追いつき追い越すこと
を目標に、天文部へと入部していました。
同じ日に、部の入部希望者への説明会で顔を合わせたもう一人の
登場人物が、「飯塚凛久(水沢林太郎)」。
彼は、自作の望遠鏡を作ってある人に星を見せるのが夢でした。
そんな中、2020年の2月に始まったコロナ禍の時代。
高校2年に進級し、天文部の活動をもっと活発にやっていきたいと
願う溪本亜紗たち。
それを阻むのはコロナ禍による活動制限。
合宿は出来ない。
対面での活動も時間制限あり。 …うーん
" 今 何ならできる? "
コロナ禍の渦中にあっても、出来ることは何かあるハズ。
当初の問いかけと似たようなこの問いに込められた意味は、
出来ることを見つけ出そうとする「肯定的な」ものでした。
" 集合合宿が無理でもオンライン合宿なら "
" オンライン開催でならスターキャッチのコンテストができる "
" 呼びかければ全国の学校からの参加もできる "
広がる夢。
悪化するコロナ禍の状況。
変化する仲間たちの事情。
無事に「第一回スターキャッチ・オンライン大会」は
開催することができるのか?
と、そのようなお話です。
コロナ禍にあってもボジティブに活動できることを模索する
主人公たちには、ただ拍手を送りたいです。
途中途中に組み込まれてくる「コロナ禍の悪化状況」の映像には
何度も現実に引き戻されながらも、作品全体を通して感じられた
のは、前向きな姿勢でした。
鑑賞後は、「達成感の共有」ができたような気すらします。・_・
観て良かった。
満足です。
◇あれこれ
■ポジティブシンキング
コロナ禍という、真っ暗に思われる時代にあっても
" 今だから出来る事もある "
" コロナ禍でなければ無かった出会い "
そういったポジティブなものを描き出したストーリーでした。
オンライン大会に登場した高校生や中学生たち。
その存在感も素晴らしかったです。眩しいくらいに。
天文部長の女性の存在感も良かった。
「あ、いそう」な感じが十分に感じられて好印象です。
■人って逞しい
そしてまた同時に、若さって逞しい。
そして、同じ目的を持つものが集まる事で、それは一層逞しくなる。
そんな想いを改めて感じました。
ただ、鑑賞していて分かりにくかったのが一点。
茨城・長崎・東京と、ストーリーの展開にしたがって登場人物が増えて
いく訳なのですが、キャラの見分けが付きにくくて混乱も少々。
みんなマスクをしているので、人の区別がわかりにくかったようにも
感じました。 ※ マスクした顔って同じに見えてしまう…
■スターキャッチ
うわ。この競技、難しそう。 ・△・;;
星の名前は当然のこと、現在その星が全天のどこにあるのかとか
それを頭にたたき込んだうえで、望遠鏡で捕まえにいく。
今から始めようか …などと思うには、ウン十年遅い気が… @~@
ただ、寝転がって星空を眺めるのは好きかも。
標高1000メートル位の高原で眺めると、頭上には満点の星空☆です。
星が見えすぎて、いつも見ている星が探せなくなるほど。
素晴らしい眺めです。
※ レビュー書きながら途中まで「スターシューティング」大会と
覚え違いをしていたのは私です。@△@
星を破壊するデススターになってしまう…(SW)
◇最後に
同じコロナ禍の時代を描いた話なのに、ふと比較してしまう作品が。
「 あんのこと 」
生まれ育った環境が違ったら、「あん」にも誰かと手を取りあって、共に
笑いあえる未来もあったのかも。
そう思うとなんとも切なさが込み上げてきてしまいます。
たとえ綺麗事のようなお話に思えたとしても、この作品の描くような
希望の持てる未来が、どんな時どんな人にもあると信じたいです。
☆映画の感想は人さまざまかとは思いますが、このように感じた映画ファンもいるということで。
星の煌めきのごとく、美しき彼ら
通常スクリーンで鑑賞。
原作は読了済み。
本当に、コロナによっていろいろなものが変わってしまったと感じる。日常が制限され、思いどおりにいかなくなった当時のもどかしさを思い出して、なんだか泣けてしまった。
大人でさえこうなのだから、思春期真っ只中の彼らにとってのコロナ禍の日々は想像するに余りある。精彩を欠き、青春の輝きからは程遠く、とても悩ましいものだっただろう。
とあるきっかけから、今しか無い彼らの青春が徐々に色づき始める。人との直接的な接触が憚られる時節に、距離を超越してオンラインで繋がった仲間と2020年の夏を迎え撃つ。
原作では殆ど描かれていなかったスターキャッチコンテストだが、巧みなアングルやカット割りを駆使した躍動感溢れるシーンになっており見応え抜群。映像化の勝利と言えよう。
手づくりの望遠鏡で星を導入しようと、楽しみながらも真剣に取り組む彼らの姿は、まるで失ったものを取り戻そうとしているみたいで、その切実さに涙が流れて止まらなかった。
彼らを全力で支える大人たちの姿にも目頭が熱くなった。生徒たち抜きのリモート会議でのセリフにグッと来た。
もうあんな日々は二度とごめんだが、コロナ禍が齎したものは決して「負」だけだったわけではないと信じたい。
多くの制限がある中で何が出来るかを模索し、やりたいことや「好き」を諦めなかった彼らの姿は、星の煌めきの如く美しかった。この夏、多くの人に観ていただきたい一本である。
[余談]
原作からの改変でとても良いと思えたのは、円華の親友・小春がスターキャッチコンテストへ参加する部分である。
原作を読みながら予想していて外れた展開を、映画で描いてくれていたのを勝手に私信のように感じて嬉しかった。
星空は美しく、青春は眩しい
辻村深月に惹かれますな
厨二病みたいに劇場必須とか言いたいw この映画は見上げる視点と画面...
思えばあの時、れいわにおける【戦争体験】だったんだろうな。
この土日に…と思っていたら、近くの映画館の上映は金曜まで。
慌てて時間をやりくりして木曜日に見に行ってきた。
僅か8日って短くないか、こんなにいい映画なのに・・・・と思ったら、
上映回数減ったけど新しいスケジュール更新されていた。
また見に行こう。
映画.comの他の方の映画評で
「この星空は映画館のスクリーンで味わうべきだ」とおっしゃっていたが、
ホント、映画館で見て正解だった。サブスクで見たら全然違う印象だったろう。
あのとき・・・、
全く先が見えなかった、なぜ、こうなったのか&こうしなければいけないのか、
大人は誰も説明してくれなかった。
また、テレビと政府だけは自説と仮説でしかない「コロナに勝つ方法」を
自信たっぷりに喧伝し強制し、それを取り締まる匿名の自粛警察がそこいら中にいた。
「コロナ禍という時代に従うしかなかった僕がいました」と
安藤真空役(サッカー少年)の黒川想矢がインタビュー(パンフレットより)で話しているが、
まさに「(自由は)ほしがりません、勝つまでは」の時代だった。
そういう環境下で渓本亜紗(桜田ひより)が提示したのが、
「何ならできるか」。
あれもダメ、これもダメ、マイナスばかりの社会のなかで、
ある意味、希望を見出したいという“もがき”と“渇き”。
その気持ちが地を越えて他の人にも伝わっていくすばらしさと面白さ。
ただ、つながっていく、希望を得ていくなかで、
喜びも悲しさも悔しさもがっかりも
登場人物たちの表情も気持ちもマスクで隠れていたし、隠してもいた。
(ホント「そんな時代だったのだ」と、この映画を見て改めて思う)
演じる彼らの声に目にその言葉に(&時折マスクのない表情に)、
そして巧みな演出に風景と心情がシンクロした映像に抑えた音楽に、
決して泣かせる映画じゃないのに感情が高まり何度もウルウルした。
コロナと言う“戦時下”を戦争を知らない我々は経験した。
克服はしていないが、
上を…いや違った「空を見上げて生きてりゃなんとかなる」という経験値を得た。
そんなことを考えた映画だった。
次は原作だな。
「国宝」や「ザリガニの鳴くところ」はあえて逆にしてしまったが、
やっぱり映画を見てから原作の方が深く味わえる。
追記>
この映画の監督、山元環氏は大阪芸大出身。
初の劇場長編映画だという。次の作品がすごく楽しみ。
脚本は森野マッシュ氏。
パンフレットによると、原作者の辻村深月氏に出した最初の脚本は
「森野さんは自分らしさを封印している印象を受け」、
「もっと森野さんらしく書いてください」と愛あるダメだし。
次の稿はOKだったという。
(没と正の両方のシナリオ、読んでみたいわー)。
思いの外良い青春映画でした
あのコロナ禍を、天文観測を通して、自問自答しながら前向きに自分らしい生き方をしてゆく。
これがかなりの掘り出し物(と言っては失礼か)。正直言って今年のベストワン!(見たばかりで熱くなっているせいもあるが)
コロナ禍の高校生、中学生たちが天体観測を通して全国で交流した話。
あのコロナ禍の切なさや大変さ、ストレス、青春の一番大切な時期を「なんで、私たちが?」と自問自答しながら、前を向きに天体観測を通して、自分らしい生き方をしてゆく。
なんていうか、映像と、モノローグとセリフと音楽と渾然一体になって展開する。映像と音楽で語ろうとしていて、それがとても上手くいっている。
アップを多用して、カット数も多い、時折のロングショットが決まるし、音楽ととてもうまくシンクロする。その心地よさ。新人監督ながら、なかなか侮れない。
高校生や中学生の日々のシーンは、当然こちらもコロナ禍の大変さを経験済みなので、切実に思えて、途中からウルウルしながら見てしまった。
主演が、桜田ひより。あまり気にかけたことがない子だったが、この子がいい。他にも若い役者たちは、「PERFECT DAYS」の姪っ子役の中野有紗や、「国宝」の黒川想矢など、最近の映画、ドラマでよく見る若手役者が多く出ている。それぞれがとてもいい顔をしている。
で、岡部たかしが素晴らしい。彼は、数年前のドラマ「エルピス」で初めて見て、なんだこの人は!と驚いたものだが、それ以降は器用貧乏な役者になってしまった感があった。今回は素晴らしい(後半のみんなに声掛けする長セリフは泣ける)。他、「虎に翼」の兄役だった上川周作も良かった。出ているみんな良かった。
今回は、原作の良さもあったと思うが、監督を中心とする制作陣が素晴らしい。演出、編集が良かったが、特にカメラが驚くほど良かった。抜けが良く(星を写すので)精緻な映像が違和感なく撮られていて素晴らしい。
ただ題名が、ストレートすぎてイマイチ見たくなる題名ではなかった。これでソンをしている。もっと見たくなる題名だったら、と思う。大勢の人に見てもらいたい映画だけに。
特別な一年
7月7日の夜にこの映画を観たんです。
七夕っぽい映画って言うと『7月7日、晴れ』くらいしか思いつかないんだけど、この映画でベガとアルタイルの名前を聞けたから、ほんのちょっぴり七夕気分を味わえました。
コロナ禍の若者に対して、おっさんの私は当時、青春に制限がかかって可哀想だと思っていたんです。
けれど、この映画を観たら青春はコロナなんかに負けないんじゃないかと思えてきたの。
そう思わせてくれた最大の要因はスターキャッチのシーンが良かったからなんですよね。
あのシーン、想像以上の躍動感で若者たちが活き活きとして見えたの。
それに表情も良かった、マスクをしていても充実した良い表情をしているのが伝わってくるんです。
もちろん、この映画はフィクションなんだけど、あの当時の状況でも数多くのこうした青春が存在したのだろうと思わせてくれました。
コロナ禍で制限が有ったのは間違いないのだけど、熱中できる物に出会えてしまえば、たとえどんな状況であっても若い頃の一年はやはり特別な一年になるんだろうなと思います。
何気なく見上げた夜空に輝いていたような映画だ
原作も監督も脚本家も知らない。
メインのキャストも桜田ひよりは知っている程度で、あとの若手キャストは認識していない。
星や天文学に興味や知識がある訳でもなく、コロナ禍によって奪われた青春の時間という部分が唯一の惹かれるところだ。
観賞しようか悩んだし、大きな期待はなかったのだが、この映画を見逃さなかったことに幸福を感じない訳にはいかない。
間違いなく本年度の邦画を代表する1本と言える。
監督、脚本、若手俳優たちの新しい才能との出会いに喜びを感じる。
星、宇宙、青春、夢など掴みどころのないものに、まんまと雰囲気で騙されているのじゃないかと思えるほどに心を揺さぶられてしまった。
よくよく考えると、映画というものは観客を騙して楽しませるもの。
「転校したくないな〜」、そんな一言で心を奪う瑞々しい映画だ。
コロナ禍で学生たちの青春というのは苦い思い出になってしまった人も多...
悪いところが無さそうなのに、面白くない
すごく素敵な旅館で、綺麗な食器によそった、魚沼産コシヒカリを、最高な板前が炊いたのに、ごま塩も無い状態。美味しいのは、分かるのだが、満足感が無い。
昔は天文年刊くらいは買っていた程度の知識はあるけど、キャッチした喜びが伝わってこない。ゲームのルールが実は不公平がありそうだし、ターゲットの選ぶ基準がよくわからない。失敗することが描かれない、作戦も無い、機材の工夫も、レギュレーションも分からない。競技として面白みがない。
3つの舞台が交叉しているが、あんまり差異を感じない。同じことが、3回繰り返されてるように感じる。
コロナ禍の使い方が中途半端。合宿だめなのに、結局は密になっている。コロナに奪われたものは何?子供たちはそれなりに淡々と生きていたと思うけど。だって、コロナがない世界を知らないのだから。
中高生の話なのに、それぞれ男女混成チーなのに、オマケのような恋愛劇は何?男女で遅い時間に居残っていれば、もっとソワソワするでしょう。カマトトぶりが極まっている。
リクの作った望遠鏡は使ったんだっけ?よく分からなかった。お姉ちゃんの障害は大変そうだけど、随分と元気じゃん。バリアフリー環境を整えれば、一人で大学とか通えるでしょう。
君は放課後インソムニア(アニメの方、実写は未見)はあんなに面白かったのに。
まとめると、事件の起こらない中学生日記のようでした。
天体好き必観!
全225件中、121~140件目を表示