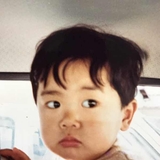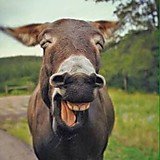遠い山なみの光のレビュー・感想・評価
全146件中、141~146件目を表示
⭐︎3.4 / 5.0
9月5日(金) @映画館
遠い山なみの光
---
見事なとっ散らかり脚本🙄(長崎である必要もないし三浦友和の無駄遣い)「ある男」より終わり方はスッキリだけど🙄いまひとつ
---
#movie 🎬2025
#備忘録
#遠い山なみの光
#映画
#映画鑑賞
#映画レビュー
#映画好き
#映画好きと繋がりたい
#映画好きな人と繋がりたい
隠したい過去
吉田羊(歳を重ねた広瀬スズ)が、英国人との夫との間に設けた娘(次女)に、長崎時代の話を聞かせるストーリー。その中で、知り合いになった二階堂ふみとその娘(恵子)との関わりを話すのだが… 映画の最後で次女が発見する過去の想い出に繋がる幾つもの品が、実は二階堂ふみは存在せず、恵子は実の娘であったことが観客に判明する。即ち、幸せな結婚生活をしていた夫(松下洸平)も義父(三浦友和)も存在などしなかったのだ。娘に語るのは、嘘の過去なのだ。何故か、被爆者として生きねばならぬ中で隠したい後ろめたいことををしながら、漸く掴んだチャンス(英国人夫)だったから。最後で、本作への評価に星一つ追加ですね。
選択を肯定したい自分と、後悔している自分を同時に語っているような映画
2025.9.5 一部字幕 イオンシネマ久御山
2025年の日本映画(123分、G)
原作はカズオ・イシグロの小説『A Pale View of Hills(邦題:遠い山なみの光)』
原爆直後の長崎を生き抜いた母と疎遠の娘を描いたヒューマンドラマ
監督&脚本は石川慶
英題の『A Pale View of Hills』は直訳すると「丘の上の淡い景色」という意味
物語は、1952年の長崎のことを1982年のイギリスにて回想するという構成になっていた
1952年の長崎には、原爆を乗り越えて専業主婦をしている悦子(広瀬すず)がいて、彼女には多忙な夫・二郎(松下洸平)と2人で暮らしていた
ある日のこと、2人の元に二郎の父・誠二(三浦友和)がやってきた
彼は息子の同窓会に併せて訪れていたのだが、一週間も早く到着していた
やむを得ずに息子の家で泊まることになったものの、父親とあまり一緒に過ごしたくない二郎は、仕事を理由に帰宅を遅らせ、父との将棋指しも拒んでいくようになった
父にはとある目的があったのだが、それに向かうためには心の整理が必要で、息子との会話が必要だと考えていた
それは、誠二の元教え子で二郎の友人でもある松田重夫(渡辺大知)が、ある雑誌書評にて、誠二の教育方針に対する意義を唱えていて、さらに「追放されて当然だ」という強い言葉で締めくくられていたのである
映画は、1952年と1982年を行ったり来たりする構成になっているが、1952年に関しては悦子の回想とニキが残された荷物から想像するものが入り混じっている
悦子は新しい時代に向かう中で、新しい生活をしたいと考えていたが、夫はそうは考えていない
これまでの日本と同様に「母親は母親らしく」という考えに固執していて、おそらくは子どもが生まれれば一切の自由を与えない夫になっていたと思う
この考えは、彼の父から受け継がれているものであり、それが時代の変化とともに古きものとして断罪されていく
教え子との会話では、かつて反発していた者が今の教育の主流となっていて、戦争に向かわせた教育を全否定されていた
誠二は師に対する敬意とか当時の努力を語るものの、松田たちの世代からすれば、結果こそすべてであると言えるのだろう
物語は、実は悦子=佐知子だったというカラクリがあり、記憶が時を経て分離しているのか、混在しているのかが不明瞭になっている
景子=万里子(鈴木碧桜)であり、1952年時点でのお腹の子どもとなるのだが、同時進行で万里子が描かれているので、とてもややこしい演出になっていた
1952年の悦子は少し先の未来の自分(=佐知子)を同時に語っていることになり、そこに嘘があるのかは何とも言えない
だが、ありのままを話せない自分がいて、あの選択は間違っていなかったと思い込みたいのだと思う
それでも、アメリカに来たことで景子は自殺してしまっているので、選択の正しさを思い描けない部分はある
そう言った後悔と肯定の間において、記憶はあたかも自身を分離させるかの如く、同時期に存在するという構図を生み出していたのではないだろうか
いずれにせよ、余白の多い作品で、観終わった瞬間にスッと入ってくる作品ではなかった
ニキが見つける遺物によって悦子の話の真実がわかるのだが、景子=万里子という関係性の他にも「佐知子が万里子を捨てて1人でアメリカに行ってしまった」とも考えられてしまう
それは、二郎との夫婦関係がどうやって終わったのかを描いていないからであり、かなりの部分が抜け落ちた回想になっているからだと思う
アメリカではなくイギリスを選択した理由もわからないし、佐知子をあたかも他人のように説明するための嘘であると言えるのだが、やっぱりわかりにくいよなあと感じた
予想外に面白かった
レトロ昭和、広瀬すず、毎度の苦手系。
でも今作品は良かった。面白かった!
凛とした役をこなす広瀬すずは相変わらずいいねー
結局、二階堂ふみの役は幻⁉️
あれは広瀬すずだったのかな?
中々長女の詳細が明かされないなーって思っていたら、まさかあの娘が長女だったとは。やられた。
広瀬すずの旦那さんは昔の写真だと外人で、過去のシーンでは松下くん、あのカラクリは謎でした。ん?
猫の最期のシーン
あれは嫌だねー
わざわざ必要だったのかな。
そんな事するなら猫の登場を遠慮して欲しい。
無駄に悲しい。
8番出口
これの前に観た「8番出口」よりは見どころがありましたが、映画を観ていてよくわからない度は同じくらいでした。
きれいな人が出てるぶん、こっちが少しだけ勝ちかも。
映画を観てからみなさんのレビューを読んで、なんとなく理解したふうを感じてますが、明日には忘れる程度の映画でした。
簡単なお話を、わざわざわかりにくくして映画を製作する人の意図ってなんなんでしょう。感性が腐ってるとしか思えません。
こりゃあと2回観なきゃ
僕ごときが一回観て全部理解して解釈して評論なんか出来るような単純な作品ではありませんでした。
「海街diary」みたいに、爽やかハッピーに終わる作品だと勝手に思って観たら全然違う。
戦争が日本国民全員に大きく深い傷をつけ、人それぞれに消化しようとしつつ、でも飲み込めず、体も傷み、心が七転八倒し、なんとかかんとか、もがきながら生きていた。
そんな時代に生きていない僕なんかがわかるわけがない。
登場人物全員がそれぞれの辛さに溺れまいと何かにしがみつき、ひたすら生きる。
「希望はたくさんある」・・・逆光の中の台詞
そうだ。何かを失っても、沢山失っても、大きく失っても、希望は必ずたくさん見つけられる。
苦しく辛い中でも、探せば希望はたくさんある。
ちょうど、僕が今、大きな物を失いつつあり、ターニングポイントの最中にあり、そのストレスにげんなり。
そんな時にこの作品が乗り越える希望をくれました。
最後は、実は全ての登場人物が同一人物の時間の線の中にあったというオチ。主観と客観の錯綜。あの時代の全ての人が、"戦争"という同一の大事件に巻き込まれ、葛藤し、それでも何とか生きて、そして未来に今の僕らに繋がっている。みんな同じ一本の線の上にいた。
いつの時代も苦しみや辛さは変わらずあり、でも、遠くの山際に薄暗く仄かに見える光に向かってただ歩くしかない。それが人生なんだろう、きっと、多分、恐らく。
文化も価値観も全てが変わりゆく。今もそうだ。昭和では普通の何ともないことが、今ではタブーだったりアンモラルだったり。三浦友和の演技はさすがでした。
この作品が魅せる光と影、そして音と風。素晴らしかった。
(滅裂、書き殴りです。)
全146件中、141~146件目を表示
映画チケットがいつでも1,500円!
詳細は遷移先をご確認ください。