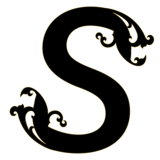遠い山なみの光のレビュー・感想・評価
全284件中、101~120件目を表示
広瀬すずの美麗さと存在感に終始見惚れる!
原爆を投下された長崎で戦後を生き抜き、その後、渡英したひとりの女性・悦子の半生を、彼女の口述から悦子の娘・ニキが綴っていく。
長崎時代に知り合った謎の女性・佐知子、その娘・万里子、そして悦子の夫・二郎などが登場して、長崎での生活が語られていくが、全体的にその生活を支える人間模様が謎めいており、ひた隠しされた「何か」が見え隠れして不穏当な雰囲気が漂う。そして終盤、その「何か」の正体が明かされて──。
うーん、お恥ずかしながら今ひとつ理解できないまま上映終了。「何か」はわかったものの、そこから生じた真実が何を指し示すのかが、よくわかっていない模様。
多分に戦後長崎の歴史的背景とその文脈を、私が知識として持っていないからだろう。ひとまず解説レビュー等を見て知識を補完したうえで、サブスク化したら改めて鑑賞したいと思った次第。
追記)
ふと思い至ったことがあったので追記。
吉田羊(悦子)の回想は、二つの時代を混ぜ合わせての嘘を構築していたのか。
子を産む前の広瀬すず(悦子)と、万里子(景子)と二階堂ふみ(佐知子/悦子)母娘。被爆した者としての差別に遭いながら果敢に生き抜き、渡英に漕ぎ着いてようやく幸せを掴みかけたが、景子の自死が大きな影を落としている。
回想での、広瀬すず(悦子)が万里子に優しく接している様は、後悔の念だからだろうか物悲しく切ない。
時代の変化がもたらすもの
美しい映像は薄く弱い灯りの下描かれていて、くっきりとしない輪郭の描き方が後に見せるストーリーの行方を暗示するように、強い感情を描いているのに敢えておぼろげに映しているかのようだった。
二人の女優の作り込んだ演技が素晴らしい。長崎で窮屈な思いを抱きながら生きている戦後の女性をしっかり演じている。
クライマックス近く、あっけに取られる事になるのだが、原作未読のため、映像ではなく原作ではどのように描かれているのか興味が湧いた。戦後日本は常識も正義も変わり、被爆地域はさらに被爆者を見る目もあり閉塞感から逃げ出したいと思う人もいたのだろうと想像。忘れることが出来ない過去を生き、それでも将来を生きるために皆必死だったに違いない…思いを馳せる最後だった。
3人の女優がいい演技
原作者のカズオ・イシグロがノーベル文学賞を取ったことは知っていましたが読んでおらず解釈が間違っているかもしれませんが心に残るいい映画でした。
原爆のように衝撃的な出来事による喪失体験、罪意識、恐怖で人間を一生苦しめる。その苦痛に耐えられず空虚感を抱えてしまう。それとは真逆に人生を前を向いて生きようともする。絶望と希望の葛藤を広瀬すずと二階堂ふみ2人の女優が見事に見せてくれていて、さらに葛藤の先の未来を吉田羊が英語で演じていてこれがまた素晴らしい。それぞれがその内面にあるものをしっかりと表現できていたように思いました。良いキャスティングでした。ニキが姉や母に対して不信感、疑問を持っていたが最後に希望を持って生きていけそうでほっとしました。
今世界では各地で悲惨な戦争、紛争が起きています、命をぶつけ合って戦い死んでしまう人がいて、生き残った人々の心の中に悲しみ、苦しみ、憎悪など様々な形でずっと残ります。戦後80年の今、忘れてはいけないことをあらためて思いました。
うっすらと見えてくる、希望のようなもの。
映画「遠い山なみの光」を観てきました。原作未読だったのでかなり戸惑った。ストーリーの重心が意図的にずらされ、感情移入しにくい作り方。むしろ、観客に安直な共感を許さない、そんな意志を感じたよ。たぶんそれでミステリー扱いされたんだろうけどさ。
いつも思うけど、過去と繋がっていない未来なんてない。でもどこまで囚われるべきなんだろう。答えのない世界。さておき。
広瀬すず、二階堂ふみという当代きっての演技派のやりとりは、ひりひりして目が離せない。加えて吉田羊だ。リアリティがすごかった。蜘蛛や猫のエピソードが、物語に強い陰影を与える。とにかく、息を飲むようなシーンの連続です。これから観る人が羨ましい。だけど★★★★☆です。彼女をどうか許してあげて。
ストーリーは二の次、それよりも・・・
約25分の短編映画『点』をU-NEXTで観て衝撃的な感動を受けた、石川慶監督作品だけに、あの抒情的な静止画カット、光と影のコントラストの効いた画像、意味ありげな間、サスペンス的な不安さ、が長編でしかもロンドンと日本の交錯で観ることができると思い、観ました。
案の定、ストーリーは二の次、まさに映像と静止画の美、抒情さを感じられた映画でした。最後の辺りで、ストーリー的にはあれ??どういうこと??となって、エンドロールの間に考えをめぐらしても、わからないのまま、ジエンド(特に二階堂ふみ演じた女性は実物だっのか、主人公がみごもっていた子どもはニキだったのかどうか、怪しい年配女性は幻影だったのか・・・わからない・・・考えれば考えるほど矛盾するので、考えるのをやめました)。
石川慶監督作品に、ストーリーテリングは期待していなかったので、こうした映画になる可能性ありと思っていたので、まぁ、わからないままでもいいやってなってます。そうえば、私にとっての衝撃作品『点』は、ストーリー的なもの”何も起きない”(少なくとも表層的には)。
ストーリが知りたければ、原作読めばいい思う次第。それよりも、石川慶監督の静止画カット、映像美、カットつなぎの間、これは確かにこの作品にも息づいていて、単なるサスペンスストーリをつくる気はない、徹底的な感性へのこだわりを感じます。
吉田羊の英語は良かった
致命傷から身を守る術としての「嘘」には、「捏造」ではなく「脚色」ということばを充てたい
日本人の母とイギリス人の父を持ち、大学を中退して作家を目指すニキ。彼女は、戦後長崎から渡英してきた母悦子の半生を作品にしたいと考える。娘に乞われ、口を閉ざしてきた過去の記憶を語り始める悦子。それは、戦後復興期の活気溢れる長崎で出会った、佐知子という女性とその幼い娘と過ごしたひと夏の思い出だった。初めて聞く母の話に心揺さぶられるニキ。だが、何かがおかしい。彼女は悦子の語る物語に秘められた<嘘>に気付き始め、やがて思いがけない真実にたどり着く──(公式サイトより)。
痛みを伴った記憶が自分だけの中にある時、それはとらえどころのないぼんやりとした断片的ななにかだが、だれかにそれを伝えるためにことばを与えた瞬間、「断片的ななにか」は形象化され、輪郭を伴った塊になる。
前者によってもたらされる痛みが黴や腐食のようにじわじわと長きにわたって蝕んでくるのに対して、後者のそれは刃物や鈍器のように瞬発的な攻撃性で向かってくる。致命傷から身を守る術としての「嘘」には、「捏造」ではなく「脚色」ということばを充てたいが、本作は戦後の被爆地・長崎で男尊女卑の社会の中で懸命に生きるひとりの女性の「脚色」の物語といえる。
直接的な映像表現や説明的な科白を排し、余白とメタファーに満ちた映画らしい映画で、生活力のある母性にあふれつつもうっすらと影を纏う吉田羊と、九州男児に連れ添い、自責と悲観を抱えながらもまっすぐな眼で母であり女性であることに光を見出そうとする広瀬すずがシームレスに連なっていた見事だった。「わたしとあなたは似ている」と呟く得体のしれない垢抜けた女性を演じた二階堂ふみも良かった。
本原作は、長崎で生まれ、5歳で両親とともにイギリスに移り住んだ原作者のカズオ・イシグロの長編デビュー作で、本作と『忘れられた巨人』というふたつの作品以外の長編小説はすべて著名な文学賞の最終候補になっているという逸話までついている。しかし、デビュー作からかれの特徴である「信頼できない語り手」の原型がすでにここにあることに驚く。
理解がなかなか追いつかない
事実と嘘と夢と時の流れ
私は「嘘」をつくことがあるかもしれない。
正確には「嘘」を重ねて生きてきたと思う。
過去を振り返り他者に自分を語る時、美化したり、かなり湾曲して事実を違った解釈で話す事があるかもしれない。
それは自分本位の現れでもあり、違った解釈にすることにより「事実」に蓋をしてしまう。
いつしか「嘘」が「事実」になっている。
この作品は人間が持つ過去の心の傷や虚栄心の裏側を奥深く描いている。
悦子の過去の心の傷と嘘
佐知子の虚栄心からくる謎
緒方の過去を脱却できないプライド
人は傷や挫折なしには生きていけない。
生き抜く為は「嘘」も必要かもしれない。
しかし必死に時代を生きていた。
生き方に「嘘」はなかった。
この作品は捉え方は観客主体の作品。
好みは分かれるが、見応えのあるエンターテイメントであった。
広瀬すずと二階堂ふみの邂逅は夢か幻か。
見事にスクリーン映えする瞬間であった。
時間があれば再度鑑賞してみたい。
辻褄が合わない
「あの人はあそこにいたらしい」
誰かと語りたい映画
そういうことだったのか!という感じでした
美しい映像と文学性、それでいてエンタメとしても楽しめる傑作
広瀬すずさんも二階堂ふみさんが揃い踏みで、監督は「ある男」の石川慶さんとあれば、見ないわけいきません。
戦後の長崎を生き抜いた女性が、遠く離れたイギリスの地から当時を振り返る作品。淡々と描かれる現在と過去は微妙に齟齬があり、観ていて何かがおかしいと思いながら、それらを回収する形で物語は結末を迎えます。
映画としては鮮やかに終わりますが、一部に飲み込みにくさもあり、映画を見終わった後のあれこれ解釈を考える要素もあり、余韻も長く楽しめます。ある種のミステリやサスペンスとして楽しめつつも、混乱の最中で過ごした一人の女性の生き様を描いた文学的な香りも感じさせる複合的な傑作の一つかと思います。
2025/9/7 私の頭にはちょっと難しかった(笑) 最後までしっ...
2025/9/7
私の頭にはちょっと難しかった(笑)
最後までしっかり観たけどなんかもやっとな感じ。なんとなくそーかなと思いながら観ていたが、時系列と登場人物のいりくみで混乱してしまったというのが正直な感想。でもカズオ・イシグロの話は割とそんな感じだからいいかなって感じ。ふみちゃんとすずちゃんよかったなぁ
冒頭の連続絞殺事件からすでに悪夢=嘘なのか?
ノーベル賞作家カズオ・イシグロが物語の現代パートと同じ1982年に書いた処女作で自らの「移民」としてのアイデンティティを長崎から渡英してきた主人公・悦子(広瀬すず/吉田羊)の娘に作家(インタビューアー)として重ね、悦子が見る悪夢と30年前のあいまいな記憶を混在させて描くミステリーでチラシ等の惹句に「ある女が語り始めた・・・心揺さぶる<嘘>」と明示されているように悦子の話には嘘が含まれていることを承知しながら観客は物語を辿り、長女を失った事情を知るにつけ、そりゃそうだよなと<嘘>を交えなければ語れない彼女の心中を察するのである。被爆者に向けられた差別がテーマの根底にありながら直接的には描いておらず、その非人道的な言葉を発したうどん屋の客にコップの水をぶっかける佐知子(二階堂ふみ)の毅然とした言動にもう一つテーマである女性差別問題とタッグを組んだツープラトンで一気にかましており歴代映画・ドラマの「水ぶっかけ大賞」ものであろう。冒頭、庭に降る雨の音から始まり1950年代の長崎を活写したスチル写真を80年代の英ロックバンド・ニューオーダーの楽曲に乗せて一気に物語の中心に誘ってくれるやり口が見事でアバンタイトルフェチの私としてはたまらなく、広瀬すずが松下洸平の首にネクタイを結ぶアクションカットつなぎを見た段階で石川慶監督への信頼とこの映画の成功を確信した。オーソドックスにして斬新・緻密なのである。松下洸平もそこまで亭主関白でなさそうに見せながら、すずちゃんを土下座させたような靴の紐結び俯瞰アングルに込めて描く巧みさ、「オムレツを作れるようになりたい」と言わせながら戦時中の教育を反省しようとしない三浦友和のアンビバレンツ。そもそも「お茶でも飲んでいかない?」と招く英国夫人的描写にすでに悦子(吉田羊)が匂っており脚本にはカズオ・イシグロも様々なアドバイスをしたというだけにその構成の上手さが見事。そしてなんといっても広瀬すずがあまりにすごくてバイオリンシーンの逆光での落涙は今年の主演女優賞を確定させた。
全284件中、101~120件目を表示
映画チケットがいつでも1,500円!
詳細は遷移先をご確認ください。