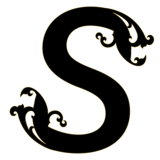遠い山なみの光のレビュー・感想・評価
全429件中、161~180件目を表示
吉田羊の英語は良かった
カンヌ映画祭や最近ではトロント映画祭と海外の映画祭で称賛される映画ってなかなか大衆ウケするものじゃないっていうのは私の個人的な意見だけど、この作品も大衆ウケはしないんだろうな…
テーマが重いというのは覚悟して観たけど、鑑賞後の後味もいいものではない。
ただ、吉田羊の英語の演技は素晴らしかった。
もともと英語が得意でもすごく話せるわけではないってなにかのインタビューで話してたけど、短期間で、30年イギリスに暮らしてる人なりの英語を身につけるためにホームステイなどをして特訓したと言っていたけど、それであそこまでイギリス訛りの英語で演技できるほどになるのはホントすごい!
エンタメとしてでなく芸術としてなら
ノーベル賞の文学賞の作家の長編小説デビュー作品を自分でエグゼクティブプロデューサーとして映画製作にタッチしているだけで凄いです。
しかし観に来た横並びの客は寝ていて大いびき。私は原作未読で難解なストーリーに加えて、戦後の女性の精神的解放に主眼があるみたいですけど、あんまり得意な題材ではないので苦しみながら観ていました。
広瀬すず、二階堂ふみに吉田羊まで揃う作品はそうないのでと思って観ていました。ドキドキ、ワクワクを求めて観ていたらつまらないでしょう。
純文学を紐解く映画を求めているなら本人がプロデューサーなんだから良き作品になっていると思います。
人の苦しみがここまでくるとは
悦子には(きっと自分のことを真理子と悦子が語る場面にはあるが)2面性の顔があって優しく子供に接することができる悦子、残酷なことをし、残酷な言葉をかける悦子がいたと考えます。
もしくはあの時の自分に対し、今の自分があの時の自分にこうしたら良かったのではないかという後悔が生じていたのではないでしょうか、
その顔に自身で気づいていたが、どうすることもできず、イギリスに行けば状況が変わるだろうと悦子は信じていたのかもしれません。
最後の方の場面で、悦子が船に座って、アメリカに行きたくないと言っている子供をみている傍ら、草のつるをもっており「子どもはなんでそれを持っているの?」と疑問形で問いかけている場面がありました。私はそこで子供を殺そうとしていたのではないかと読み取りました。子供も殺されるという考えに一瞬よぎった瞬間でもあったのではないかと思います。子供を無理矢理イギリスに渡英させましたが、あの時の苦しみは癒えるものではなかった。そして、あの時の場面を思い出す日々が続いたのかもしれません。そして子供はその記憶の伏線をなぞり(なぞりたかった訳ではないと思う。顕在化された記憶の中で苦しみ、いつの間にか「草のつた」という苦しみから逃れたくて)、つたに似た紐で首をつって亡くなったと私は捉えました。あくまで、一度映画を観た私の捉え方のため、もし違う見方の方がいたら教えて頂けたら嬉しいです。
難しい作品
現代のイギリスと戦後の日本のシーンが交互に物語が進む。
この先どのように展開してイギリスに行くことになるのか。ずっと考えていましたが、まさかの展開に。戦後の日本のシーンは、悦子は回想する自分で、当時の自分が佐知子ってことでしょうか。
難しい作品ですね。でもとても面白かったですよ。
団地とオムレツとそしてバイオリンと憧れと
不条理、そしてデビッド・リンチ作品が大好きな人なら
あのラストは充分に理解できる良作だったと思います
原作は読んでないけど監督さんには一本取られたなと…
ネタバレになるといけないんであまり書けないけど
戦時下、特に原爆で夢見る女性が惨状下でも生き延びなければならない
過去を打消したくても打ち消さすことができない
実際の日本人の夫は恐らく戦死していて、戦時中に生まれたのが
あの長女なのでしょう
演者さんたちもお見事でした
致命傷から身を守る術としての「嘘」には、「捏造」ではなく「脚色」ということばを充てたい
日本人の母とイギリス人の父を持ち、大学を中退して作家を目指すニキ。彼女は、戦後長崎から渡英してきた母悦子の半生を作品にしたいと考える。娘に乞われ、口を閉ざしてきた過去の記憶を語り始める悦子。それは、戦後復興期の活気溢れる長崎で出会った、佐知子という女性とその幼い娘と過ごしたひと夏の思い出だった。初めて聞く母の話に心揺さぶられるニキ。だが、何かがおかしい。彼女は悦子の語る物語に秘められた<嘘>に気付き始め、やがて思いがけない真実にたどり着く──(公式サイトより)。
痛みを伴った記憶が自分だけの中にある時、それはとらえどころのないぼんやりとした断片的ななにかだが、だれかにそれを伝えるためにことばを与えた瞬間、「断片的ななにか」は形象化され、輪郭を伴った塊になる。
前者によってもたらされる痛みが黴や腐食のようにじわじわと長きにわたって蝕んでくるのに対して、後者のそれは刃物や鈍器のように瞬発的な攻撃性で向かってくる。致命傷から身を守る術としての「嘘」には、「捏造」ではなく「脚色」ということばを充てたいが、本作は戦後の被爆地・長崎で男尊女卑の社会の中で懸命に生きるひとりの女性の「脚色」の物語といえる。
直接的な映像表現や説明的な科白を排し、余白とメタファーに満ちた映画らしい映画で、生活力のある母性にあふれつつもうっすらと影を纏う吉田羊と、九州男児に連れ添い、自責と悲観を抱えながらもまっすぐな眼で母であり女性であることに光を見出そうとする広瀬すずがシームレスに連なっていた見事だった。「わたしとあなたは似ている」と呟く得体のしれない垢抜けた女性を演じた二階堂ふみも良かった。
本原作は、長崎で生まれ、5歳で両親とともにイギリスに移り住んだ原作者のカズオ・イシグロの長編デビュー作で、本作と『忘れられた巨人』というふたつの作品以外の長編小説はすべて著名な文学賞の最終候補になっているという逸話までついている。しかし、デビュー作からかれの特徴である「信頼できない語り手」の原型がすでにここにあることに驚く。
理解がなかなか追いつかない
事実と嘘と夢と時の流れ
私は「嘘」をつくことがあるかもしれない。
正確には「嘘」を重ねて生きてきたと思う。
過去を振り返り他者に自分を語る時、美化したり、かなり湾曲して事実を違った解釈で話す事があるかもしれない。
それは自分本位の現れでもあり、違った解釈にすることにより「事実」に蓋をしてしまう。
いつしか「嘘」が「事実」になっている。
この作品は人間が持つ過去の心の傷や虚栄心の裏側を奥深く描いている。
悦子の過去の心の傷と嘘
佐知子の虚栄心からくる謎
緒方の過去を脱却できないプライド
人は傷や挫折なしには生きていけない。
生き抜く為は「嘘」も必要かもしれない。
しかし必死に時代を生きていた。
生き方に「嘘」はなかった。
この作品は捉え方は観客主体の作品。
好みは分かれるが、見応えのあるエンターテイメントであった。
広瀬すずと二階堂ふみの邂逅は夢か幻か。
見事にスクリーン映えする瞬間であった。
時間があれば再度鑑賞してみたい。
辻褄が合わない
「あの人はあそこにいたらしい」
タイトルなし(ネタバレ)
原作を読んだのは二年ほど前。早川が出してるんだ、と、ちょっと珍しく思って手に取ったのかもしれない。カズオ・イシグロの作品で読んだことがあるのはいまのところこれだけ。
カズオ・イシグロが英語で書いたものを翻訳したものなので、ちょっと日本の文学と比較するのも違うかもしれないが、どことなく庄野順三とか辻邦生とかを思い起こすような雰囲気を感じた。
原作でも若干ホラーテイストだったが、映画の方もそれは同じで最後の方は悦子が語った佐知子という女性とその娘の万里子という過去に会った人々というのは悦子の体験をもとにした空想か妄想という表現をしていた。小説の方ではそういうことは想像をたくましくしないと特に感じ取れないくらいには具体的な記載は無かったとおもう。それ以外にも映画化に当たっては少々変更された点もある。
悦子役の広瀬すずは私のイメージに近いだろうか。佐知子にはもう少し影があるような雰囲気だったので、二階堂ふみだとちょっと明るい感じに見えてしまう。
役者も演技など悪くは無かった。三浦友和はこういう役が多くなった。吉田羊とカミラ・アイコはあまり親子には見えなかったがそこは特に気にならなかった。
1950年代の再現は結構頑張っていたように思う。当時を知っているわけではないけど。おなじく1982年もだいぶ過去になったので、そこも当時の雰囲気が再現されていた。
正直、原作自体面白いとかそういう印象もなく、全体にじめっとしたウェットな雰囲気の小説だな、という感じを受けたくらいだったので、映像化されてそこはさほど変わらなかった。ただ、映画の方が、色々とメッセージ性が強くなっているというか、原作にこんな意図はあっただろうかという印象を映画の方には感じた。
思い出とは消えていくことである
人の記憶というものは、曖昧なものだ。そして、思い出として残っていたものもいつかは消えていく。
年月が過ぎるにつれ、記憶というのは姿かたちを変え、正確に覚えておくことはできない。
もちろん良い記憶だけではなく、嫌な記憶はある。
誰しも何かにあこがれて、嫌な記憶からは目をそらす。事実を歪曲してしまう。
この映画はかなり「曖昧」な部分を意図的に盛り込み、どこまでが真実なのか、をとらえることが難しく描かれているが、時代の変化というものを例えたかったんじゃないかと感じた。
誰かと語りたい映画
久々にテーマのはっきりした映画でした
難解とのレビューが多かったので、覚悟をもってみましたが、悦子の回想を通じて見えた、戦前教育からの脱却と女性の地位向上というテーマがしっかりと伝わって来ました。
何故、次郎と悦子が離婚したのかとか、広瀬すずにはちょっと役どころが重すぎたのではないか、とかの細かい不満はが私にはありましたが、見てよかったと思える作品でした。
そういうことだったのか!という感じでした
美しい映像と文学性、それでいてエンタメとしても楽しめる傑作
広瀬すずさんも二階堂ふみさんが揃い踏みで、監督は「ある男」の石川慶さんとあれば、見ないわけいきません。
戦後の長崎を生き抜いた女性が、遠く離れたイギリスの地から当時を振り返る作品。淡々と描かれる現在と過去は微妙に齟齬があり、観ていて何かがおかしいと思いながら、それらを回収する形で物語は結末を迎えます。
映画としては鮮やかに終わりますが、一部に飲み込みにくさもあり、映画を見終わった後のあれこれ解釈を考える要素もあり、余韻も長く楽しめます。ある種のミステリやサスペンスとして楽しめつつも、混乱の最中で過ごした一人の女性の生き様を描いた文学的な香りも感じさせる複合的な傑作の一つかと思います。
2025/9/7 私の頭にはちょっと難しかった(笑) 最後までしっ...
2025/9/7
私の頭にはちょっと難しかった(笑)
最後までしっかり観たけどなんかもやっとな感じ。なんとなくそーかなと思いながら観ていたが、時系列と登場人物のいりくみで混乱してしまったというのが正直な感想。でもカズオ・イシグロの話は割とそんな感じだからいいかなって感じ。ふみちゃんとすずちゃんよかったなぁ
全429件中、161~180件目を表示
映画チケットがいつでも1,500円!
詳細は遷移先をご確認ください。