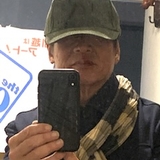遠い山なみの光のレビュー・感想・評価
全429件中、81~100件目を表示
アレコレ思うことが次から次へと!
いや〜〜〜〜感想が全然書けない!少し経ったらまとまるかな?と期待してたけど時間が経てば立つほどいろんなことが頭をよぎり結果なんにもまとまらない💦
だからとりあえずメモして次に行く😤
カズオ・イシグロの長編デビュー作。
この作品を20代で書き上げてるのが凄すぎる。
でも若い頃の記憶として保存したからこうなったのか。
きっとこれを50代で書いていたら全く別のものになったんだろーな。そして石川監督もよくまぁ映像化したもんだ…
カズオ・イシグロ氏の必要最低限しか語らない語り口と石川慶監督の醸し出す不穏な空気とがとにかくマッチしていた印象。原作は昔一度チャレンジしたけど難解すぎて読了前に諦めた…
昭和の夏のじっとりする気温が画面から伝わってくる感じが凄く好き。また音楽が素晴らしすぎた。ストーリーが良い意味と悪い意味での不思議感で進んでいく中、出演俳優陣の厚みを実感。この作品で広瀬すずがすごく好きになった。全方位どの角度から見ても美しいこの女性の魅力を引き立たせる衣装と髪型。前半で緒方と居間で話しながら大粒の涙を流すシーンの美しさには心奪われた。
考察パートについては映画だと割とはっきり明記しているけど、原作のレビューではそう書いてる人は少ない……。カズオ・イシグロ氏はどういうつもりだったのか。もう一度原作にチャレンジしてみようかな…
なるほど〜😳
鑑賞後にここの皆さんのレビューを拝見しての感想が「なるほど」です。原作は未読です。
まったりとした映画の中にサスペンスを差し込んだ作品で鑑賞後にも一人でストーリーを反芻する難解さが心に残るいい作品だと感じました。
欲を言えば、背景のCGやセットが全体的に安っぽい感じが作品の質に影響してないか気になった事と、終盤の展開に少しインパクトが足りなかった?ような、言うならばシックスセンスのようなインパクトで締められたら名作になれたと思います。
一見では理解の難しい所も皆さんのレビューでかなりスッキリすることが出来ました。ありがとうございます。
ただし未見の方には無心で鑑賞される事をお勧めします。
最後に広瀬すずさん、宝島も拝見しましたがいい役者になりましたね。
期待感が高かっただけに、
1982年、ロンドン近郊の富裕層向けの住宅街に暮らす日本人の母・悦子(吉田羊:英語上手)を、しばらく疎遠だった二女・ニキ(カミラ・アイコ)がロンドンから訪ねて来る。悦子は自宅を手放す準備を始めていたが、作家志望のニキは、想いの残る自宅で、母の長崎時代のことを知りたいようだ。悦子は、長崎で英国人の夫と出会い、前夫との娘、恵子を連れて英国に移住し、その後ニキが生まれるが、年月が経って、夫と恵子を喪ってから、ニキが寄り付かないこともあり一人暮らしをしていた。
次に場面は、1952年頃の長崎に移る。当時、悦子(この時代は、広瀬すず)は、南方から負傷して帰ってきた恩師の息子と結婚し、妊娠していた。ただ、この場面は映像等に現実感が乏しく、見ていることがつらかった。特に、疑似長崎弁がどうにもならない。俳優さんたちは、単語起こしした長崎特有の言葉を話すだけ。方言は単語(ボキャブラリー)のみでなく、イントネーションを含み個々の音節の発音などすべてが違うはず。しかも相手によっては、共通語を話していた。住んでいた集合住宅は、原爆被災者向けの高層住宅を模したのかもしれないが、病院か何かの建物にしか見えず、感情移入ができなかった。
ところが、場面が英国に戻り、ソファーで寝ていた悦子が、この頃、悪い夢を見るのでベッドでは寝られないと言ったとき、長崎の場面は基本的に彼女が見た夢かと思ったら、つじつまがあった。夢は、現在の解釈では、過去に起きたこと、それを受け止める本人の感情の反映とされている。単なる絵空事ではないわけだ。夢の内容は、悦子とやや得体のしれない東京出身の女性・佐和子(二階堂ふみ)、その6歳くらいの娘・万里子との交流が中心。しかし、万里子は服装といい、母親からの扱いは余りにも粗略だった。おそらく、佐和子は悦子の分身、万里子は最初の夫との間に、その後生まれた恵子を投影しているのだろう。
58年頃、何らかの事情で最初の夫と別れた悦子は、英国人の夫、恵子と共に英国に移ってきて、ニキが生まれたというわけだ。残念なことには、夫が亡くなったあと、養父にも英国にもなじめなかった恵子はピアノを弾いて、たくさんのトロフィーや賞状をもらっていたのに自死する。
困ったところもたくさん。特に、妊婦に野生の猫は、ご法度のはず、昔も今も。長崎時代、喪服で出てきた女性は、英国に移住した後年の悦子が迷い込んだのだろうが。ニキは英語の発音はnativeだが、なぜか日本語は読める設定で、風貌は日本人寄り。タイプライターの取り扱いは素人同然。
母の話を聞き終えたニキは、やがてロンドンに帰って行くが、それを悦子が、さりげなく見送る姿に、はじめて我々が、これまで親しんできたカズオ・イシグロを見た気がした。彼自身、6歳の時、家族と共に長崎から英国に移住している。おそらく、関係者の多くが存命のためもあり、ストーリーの詳細は明らかにされず、我々の理解が問われる内容だった。原爆投下時のこと、戦時下の日本の教育のこと、日米欧で、日本人女性がどのように生きるかなど、何も深遠な内容を含んでいた。
そう言えば、最近のレポートで、乳糖不耐症の人は、夕食にチーズを食べると悪い夢をみることがあるそうだ。日本人の10%は、牛乳を飲んだ後、お腹がゴロゴロする乳糖不耐症、厄介なことに、そこまで行かないとしても、年齢を重ねると酵素の活性は下がる。
ママはいったい何から自由になりたかったの?
遠い山なみの光とは、被爆差別と苦しみの中、被爆母親が罪悪感に苦しみつつ生き抜いた証の回想録
被爆差別と被爆による苦しみの中、長崎ではない渡英に一縷の望みをかける悦子が景子と共に将来の生きる道を見出すも、結果的に景子の将来を奪うことに至る悦子の罪悪感に沈む人生が、遠い山なみの光のように回想録として描き出される、重く辛く苦しい文学的作品。
鑑賞後の仮説(考察、分析)です。
①万里子は被爆者(←腕の痣)
②万里子が被爆者なので、母親の佐知子も被爆者
③佐知子=悦子なので、悦子も実は被爆者
(←悦子が佐知子に対し「私も隠していることがある」)
④子供の景子、妻の悦子共に被爆者と判明し、被爆者なので二郎に捨てられ?強制離婚
(←悦子「私が被爆してたなら、結婚しなかった?」 二郎「バカな事聞くな」)
⑤被爆した子持ち女性として生き抜くために娼婦を選択
(←米兵を連れ込む佐知子の話として登場)
⑥悦子、景子の母子ともに長崎にいても明るい将来はない、景子とともに悦子は渡英を決断
(←悦子が渡英した理由)
⑦現在も英国居住、ニキとの会話
<対峙/対比構造>
■夫婦関係
悦子(夫都合優先)vs二郎(自分都合優先)
■親子
二郎(遠ざける)vs緒方(近づく)
■生き方
悦子(光)vs佐知子(影)
悦子(離婚前vs佐知子(離婚後)
悦子(非被爆)vs佐知子(被爆←万里子の腕の痣)
■教師としての罪悪感
悦子(あり)vs緒方(なし)
■洗脳教育の過去
緒方(肯定)vs重夫(反省)
■殺人
連続殺人犯(少女絞殺)vs悦子(景子縊死)
佐知子(猫殺害)vs悦子(景子自殺)
連続殺人犯(絞殺ロープ)vs悦子(足のロープ←景子を縊死に追い詰めたメタファー)
猫(佐知子の他殺)vs景子(自殺)
(←渡英により結果的に景子を縊死に追い詰めた≒悦子による間接的景子殺害→罪悪感)
無言歌集
ファンタジーではあるが、リアリティも色濃い
1982年イギリスに住む日本人女性と駆け出しジャーナリストでハーフの娘の会話劇と、20年前、長崎時代の回顧録を行ったり来たりしながらファンタジー要素色濃く描く物語
ゆったりとしたシーンの連続の中に、戦争被害者の負った深い傷がジワジワと迫ってくる
見応えのある映画だと思いました
回想シーンは現実とはちょっと異なり、観る側を混乱に誘導しますが、次第に脚色部分がなんとなく透けて来て、最後にはちゃんとネタばらしもある
前日に「宝島」を観ましたが、ほぼ同じ時代の日本を描きながら、描かれる舞台も、視点も、問題提起も大きく違う。しかし、太平洋戦争を起こした国の、戦争被害者を描く、という意味では完全にてい通底するものがあります
比較しながら観るとより味わい深いです
どちらも観るべき映画と思いました
違和感を抱えたまま幻想夢に耽る
原作未読で鑑賞。
長崎編をサラリとやったあと、すぐにイギリス篇に飛ぶ。あらかじめキャスト一覧で、長崎篇の悦子を広瀬すずさんが演じ、30年後のイギリス篇では同じ悦子役を吉田羊さんが演じると知っていたので、つながりは何とか見えたが、予備知識の無い人は大いに混乱したと思う。
その後も、長﨑篇とイギリス篇を自由に往来するので、戸惑った向きも多いだろう。
若い時と年をとったときの役を演じる俳優が異なることはよくあるが、それは年齢差がかなりある時が普通だ。
広瀬すずさんは実年齢は27才で、長崎篇はもちろん、イギリス篇の50代を演じることは不可能ではない。
しかし敢えて観客を混乱させるようなキャスティングにしたのは、原作者でありエグゼクティブ・プロデューサーでもあるカズオ・イシグロ氏の強い意向ではないかと想像している。
本作はミステリアスな幻想話と言ってよく、観客の混乱は制作サイドの意図だと思う。
どこまで現実でどこから幻想なのか、敢えてぼかしている。
悦子と佐知子も長崎の原爆での生き残りという設定だが、二人とも長崎の城山で被爆したというので調べると、城山は原爆地から500mに位置するという。生き残ったのはわずかで(Youtubeに生き残った方の証言があった)、その生き残った2人が出会うというのも出来過ぎだろう。
普通にかんがえれば、被爆した過去がある悦子が妊娠して不安になり、被爆しても無事に子供を産んだ佐知子という幻想を創り出したというのが通常の解釈だろうが、本作には描かれないものが多く(悦子と二郎の離婚から渡英への経緯などが省略されている、原作にあるのかも不明)、観客をすんなりと納得させてくれない。
夫の二郎は父親と他人行儀な口ぶりで、出征時の父親の態度を今も恨んでいるようだが、教師という仕事故に、戦時中では仕方の無いことと思えるが・・。
二郎というから次男のはずだが、長男の影は無い。長男は戦死したという設定なのだろう。
父親は教え子に雑誌に批判的な記事を書かれ、その教え子に会いに行くも、和解には程遠い。
ざっくり言うと、テーマ的には「断絶」ということになるだろうか。
戦争と原爆は、人々に癒やし難い深い傷を与えた。人々はその渦中にあって、喘いでいる。
その喘ぎを今に生きる我々は聞いているのだろうか。
原題は「pale view of hills」。イーストウッドの「Pale Rider」から想起出来るように、paleには不穏な死のイメージがある。
50年代の長﨑は、原爆投下の事実が信じられぬほど復興していただろうが、その復興のしたには無数の死が横たわっていたはずだ。
最後に、「徹底解説 遠い山なみの光をもっと面白くなる超分かりやすい解説・考察動画」というYoutube動画があるので、参考までに。
戦争と被爆
曖昧ながら所々で原爆と戦争の記憶が描かれている。
ペラダイムシフトに直面した女性の悦子。
佐知子という女性を通して悦子の内面が描かれ
出産後、自分の娘、憧れ、離婚後の生活、娘に行った
行動と心情が浮き彫りになっていく。
多面性を奏せざるしかなかったのだろう。
原爆と被爆の生々しい傷跡と苦しい思いが蜘蛛や縄で
示されていた。あの川向こうの黒い髪の女性も
本人。娘にした事が最大の嘘であり、現実に手をかけてしまった。その嘘が降りかかってくる。
どれ程辛い過去でも人は生きて、変わり、未来に
繋がる。希望の光が差す場所に進み受け繋がれていく。
やっぱり戦争
戦後80年での映画化なのでしょうか。
ミステリー的な部分、ヒューマンドラマ的な部分、いろいろな解釈はあると思いますが、わたしはやはり戦争を意識せずにはいられませんでした。
「あの頃とは変わったのよ、新しい時代なんだから、変わらなきゃ!」
戦後におけるあの頃との違いとは、今の世の中のあの頃(何年か前)と今と比較して、それは余りにも大きすぎませんか。しかも長崎は被爆地です。
悦子さん、被爆して、七年後の街を高いところから見て、新しい時代=変わらなきゃ、そして女性の自立 凄い強さだと思います。
松下さんが発する三浦友和さんの万歳が憎い、その三浦さんも洗脳教育を渡辺さんから責められる、皆さん戦争を通過しているんですよね。
この映画、どこを期待して見るかで感想は変わると思いますが、わたしはとても良かったと思います。全く長くないです。
石川監督は今まで余り好きではなかったんですが(「ある男」なんて褒められ過ぎ)、今回はよくまとめたなと思います。
二階堂ふみさんも迫力満点ですが、大ファンの広瀬すずさんも嵌ってましたね。目力アップしてます。怖いシーンもありました。もっとも、広瀬すずさんの主演じゃなければ、今作見てないかもしれません(でも「宝島」は見る気しません)。石川監督嫌いでしたし、イシグロさんもそれ程のファンでもありませんし。
タイトルの意味は最後までわかりませんでした。
「嘘」をどう描くか?
広瀬すずさんと二階堂ふみさんの好演が印象に残る作品。
「嘘」の部分は早い段階で読めてしまった。大体、ポスター等のキャッチコピーに「嘘」って使うとダメでしょ、ネタバレでしょ。何故日本映画の宣伝はこんなに無能なの?
それに、この「嘘」をラストのどんでん返しに使ってるから、本来回収しなければならない伏線が置き去りにされている。
なら、「嘘」をどんでん返しにせず、しっかりそれも含めてのドラマとして描いて欲しかった。
非常に勿体ない作品。
#遠い山なみの光
魂を作る素材としての記憶
人間の記憶は時間の経過とともに単に薄れるだけでなく、形や内容が変容していき、元のかたちから大きくかけ離れることがあります。これは実験的に確認された心理学の基本知見だそうですが、「記憶」は、その人がある事象とともに感じた、喜びや恐怖や耐えがたい罪の意識などそのときの「感情」と深く結びつき、自身の精神の崩壊を回避するような合理的なカタチで保存され、その人の魂を構成する素材になるのだと思います。
この作品は、映画的表現を存分に駆使しながら、この「人間の記憶の曖昧さ」という性質を、実に巧みに利用していて、そのときどきの感情と結びついた記憶の断片を、サスペンス仕立てで観客に見せてゆきます。そしてその保存のカタチの変容の全体像が判明する瞬間に、主人公達の中に潜んでいた感情の傷の、時代背景とその強さが観客に理解されるような構成になっているように思いました。
「壮大な感情の力を持った小説を通し、世界と結びついているという、我々の幻想的感覚に隠された深淵を暴いた」2017年のノーベル賞受賞理由ですが、最近鑑賞した「私を離さないで」にも同じ物を感じ、なるほどと思いました。
主人公3人の演技も素晴らしく、大変見応えのある作品でした。
「ある男」も良かったですが、今後も目が離させない監督さんになると思います。
二度観ると印象が変わった
一度目は、戦争(原爆)への憎悪とヒューマンミステリーの余白を考察して愉しませて貰った。悦子が教え子を原爆から守れなかった悔恨と自身の被爆により我が子に遺伝させてしまった罪悪感を抱えバイオリンの前で涙する姿に感情移入が収まらなかった。そして、佐和子と悦子・万里子と景子の関係に思考が支配されつつ広瀬すずと二階堂ふみの凛とした美しさに目を奪われていた。しかし、結末を知り自分なりに埋めた空白を確認する為に二度目を観るとその印象は変わった。この映画は、ミステリーの空白を埋める作業と反戦的な高揚感に没頭しがちではあるが、その芯は、悦子がイギリスに渡って来た生き様と胸にしまってあった景子に対する母としての悔恨をニキが知るに至り、コレまで疎ましく感じていた母への感情が愛情とリスペクトに変わり、自分自身も母になることへの覚悟を決めた家族愛の再生をニキの目線で描いたドラマではないか。それは、もしかしたら原作者(イシグロ氏)が自分の母に対する感謝と尊敬する想いをニキを通して語っている様にさえ思えた。余談ではあるが、悦子が二郎と別れた理由は自身と景子の被爆が起因と云うより、むしろ義父の緒方に対してぼんやりと恋心を抱いていて、その葛藤の結果、別れる決心をしたのではないか? 二人への接し方の違い(特にオムレツを焼くくだりでのセリフ「今日は私の機嫌が良くて運が良かとね…」に滲む距離感)を見ているとそう思えてならない。
テーマが流石に深く名作
ストーリーは一度で分からず、ネットで再確認。
商業的な脚本作品ばかりに接しているようで、だからこういう純文学的テーマがある作品にアジャストできない自分にテーマの浅さを痛感。
文学賞作家の原作だけあり流石にテーマが深く、とてもいい視点だと感じました。
映像もとても文学的で美しく、
広瀬すず、二階堂ふみもとてもよく、三浦友和の飄々とした演じが映画に風を与えており、実力者かなと思う。
脚本家の力量と監督の力量を感じざるをえない作品でした。
映像の美しさ、脚本の無駄のなさ、テーマの深さ、俳優さんの充実ぶり、ストーリー構成の斬新さで、過去一と言ってもいいかな。
広瀬すず、二階堂ふみの演技力が冴える!
辛い思いをすると 記憶にまで障壁が残るのかと…
全429件中、81~100件目を表示
映画チケットがいつでも1,500円!
詳細は遷移先をご確認ください。