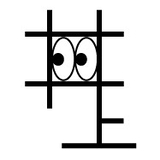遠い山なみの光のレビュー・感想・評価
全429件中、61~80件目を表示
謎が謎を残したまま…
イギリスに帰化したノーベル賞作家カズオ・イシグロの処女作の映画化。
原作未読もあって、娘に語る回想に紛れ込む嘘に、最後の最後に気付かされる不穏さ。
しかし長崎の被爆が体験者にもたらした傷は、たしかに一筋縄のものではないはず。
それにしても彼女の周囲の男の無頓着さ、頑迷さは如何ともし難い。
あと二階堂ふみ演じる佐知子が娘から取り上げた子猫を川に沈めるシーンは、鬼気迫って出来れば見たくなかった。こういう役、彼女は上手い。
広瀬すずは、今年になって「ゆきてかへらぬ」
本作、「宝島」とあいついで文芸作品で大正、昭和の大人の女を演じ心境著しい。本格的な女優の途を登り始めていると言えるだろう。今後が楽しみである。
「遠い山なみの光」という表題がいかにも読書心を誘い、原作を読んでからもう一度噛み締めながら映画を見直したい気持ちになった。
鑑賞後の考察で忙しい
原作未読です。読んでない者として…
長崎 原爆投下後・敗戦によって心身に受けた傷と幼い娘を抱えながら前に進み出している佐知子と、彼女と出会うことで、自身も被爆の事実を隠し、心の傷を抱えた悦子に起こる心境の変化。
戦時中の価値観・思想を唱えてきた元教師と、戦争で傷ついた息子との冷えた関係性。戦後の新しい思想を得た教え子との断絶。
次第に思惑と違う方へ向かう事態と現状に折り合えない娘の聞き分けの無さに苛立ちを隠せなくなる佐知子の行動。
そして、30数年後に漸くそれらを語ってきた悦子の正体。
ほとんど最後に仄めかされる悦子の真実(?)で、頭の中がいっぱいになり、自死した長女の謎(?)や成長してなお屈折している次女の状況など吹っ飛んでしまいました。嫌いじゃないです。
1980年代の作者のデビュー作らしいのですが、40年経った今なら観覧者の理解はスムーズに受け容れられるのではと思います。が、原作発表後すぐに映画化されれば相当の衝撃作になり得たのではないかと想像しました。現代だと…。(おそらく1980年代では映画化は不可能でしょうが)
空気感はお馴染みの不穏な感じ
公開2週目に鑑賞。原作未読。
ミニシアターで観たが観客のほとんどが女性
こちらの監督作品は気がつけばいずれも観ていたことに気がついたが、どの作品もお馴染みの空気感が映像と音楽で表現されている。曇り空のような色彩、抑えた演出、静かな音楽で全体的にえも言われぬ不安感や不穏な感じである。
広瀬すずさんと二階堂ふみさんの演技対決は二階堂さんに軍配。実年齢の差以上に醸し出す雰囲気に違いを感じたが、広瀬さんがそれを計算して演じているならそれは凄いかも。
演者はいずれも実力派で安心して物語に没入できた。
お話の方はミステリー仕立てだと捉えつつ、ラストシーンを経ていくつか辻褄が合わないというか、何故国が変わった?長女は何故行動を共にした?おやおやそもそも日本パートの話は主人公の頭の中の世界だったのか?など答え合わせが必要と感じたので、パンフレットと原作本を急遽購入。
まだ読みはじめて半分ほどなのだが、結構筋立てや人物の掘り下げ方が変わっているというか浅いことがわかった。
結果、原作を知っていれば映像はダイジェスト的により楽しめたかもしれないが、話を知らない人向けにはやや不親切なのかもと思い直し星マイナス1
ぜひ事前勉強の上で臨んでいただきたい。作品としては素晴らしい!
もう1人の自分
テクノ、ニューウェーブミュージックのアーティストのニューオーダーの「ceremony」で始まる、この話の主人公は進歩的な人なのかと時代背景からして少し違和感を感じた。
不気味なほどオレンジ色の夕焼けは、どれだけ遠く離れていても悲しい事を思い出させてしまったのではないだろうか。
話の終盤で考えが180度変わったと言うより、目を覚まされた。
戦争や原爆で運命が変わってしまった人、其々の苦悩が伝わって来た。そんな中でひたすら前を向き運命を切り開いて生きて来た主人公の生き方は、次の世代に伝わったのだと思う。例え嘘だと判っていても、それくらい大変な時代の中で自分を育ててくれた感謝を感じずにはいられなかったから。「ceremony」はこの人生の節目に改めて納得のできる音楽だと思った。
背景の安っぽさについて
重厚な映画
2時間ドラマとは別格の、質の高い映画を観たという満足感の高い作品でした。
評判が良かったので、ポスターさえまともに見ずに鑑賞しました。そのため予想外に騙され、しばらく思考が停止しました。
騙し絵を見たときのように、自分の脳が信じてしまったものを新しく塗り替えるのが難しかったです。
お腹の中の景子と小学校低学年くらいの万里子が同時に存在していたのが特に混乱した理由だと思っています。
強い余韻が残り、久しぶりにもう一度観たいと思いました。ただ、星の数は迷いました。単純なストーリーだけの面白みはどうなんでしょう。原作も読んでみたいけれど、翻訳本よりも原書がおすすめのようで、躊躇います。
悦子の嘘は、多重人格者が自己防衛のために新たな人格を形成するのと似たようなもので、景子を死に追いやった罪悪感から己を守る術ではないかと感じました。
広瀬さんは文句なく美しかったけれど、それより二階堂ふみさんの演技に釘付けになりました。気取った、でもたくましい昭和の女性そのものでした。あの頃の女優さんってああいう喋り方しますよね。
被爆者は、当時は無知ゆえの差別をたくさん受けたんでしょうね。また、あの時代の女性の離婚や海外移住の重みにも思いを馳せました。
最後になりましたが、ニキは山田麻衣子さんが演じているのかと思っていました。もう芸能活動はされてないんですね。
普通に見て、登場人物と主人公のホントの関係を理解できる人はいるのかな?
ノーベル賞作家のカズオ・イシグロの原作
だからというわけでは無いんだけど、見ていて文学作品って感じの映画だなと思った。
どこがと言われると難しいけど、展開と話し方でだったのかな。
あいかわらずに感じてしまったのが、広瀬すずが可愛すぎって事。
童顔で可愛いので、良いところの若奥様感が凄かった。。
そして、吉田羊って英語が出来るんですね。
あとは、ニキ役の女優さんが良かった。
実は途中から悦子はこっちなんじゃないかと思いながらの鑑賞。
この手のパターンだと単純に二人が入れ替わった視点だったというオチのはずなんだけど、今回は?がいくつかあった。
夫(松下洸平)、義父(三浦友和)は実在したの?っていうのと、悦子のお腹にいた子供がニキ?って事。
見たあとに口コミサイトを見てみると、戦前が広瀬すず、戦後が二階堂ふみらしい。。
そして、夫の松下洸平と義父の三浦友和は死んでいる?っていう事らしい。
戦争によって、生活が荒んだでしまった自分を受け入れられなかったという事なのだろうか。。
なぜ景子が自殺したのか(被爆の後遺症でも出たのだろうか)、義父の教育の内容(お国のため、反戦?)、なんとなく想像できなくもないけど。。
ただ、見ている時は、この辺はまったく分からなかった。
二階堂ふみが悦子っていうのは分かったけど、戦前や戦後の違い、夫と義父の謎まで普通に見ていて分かる人っているんですかね。
分かりづらい映画でした。
原作を読んではいないので分かりませんが、映画と同じようにわかりづらい描写なのだろうか。。
映画については、見る人に委ねるという事を狙ったんでしょうかね。
戦後問題、原爆と被ばく、働く女性の問題、社会問題をたくさん取り入れていた。
私は、あまりハマらなかったかな。。
衣装を楽しむ
広瀬すずも二階堂ふみも綺麗でかわいいし吉田羊も悪くはない
ストーリーがわかりにくいし
戦後海外で生き抜いた女性増を描きたかったのか、戦後の女性の自由がなく生きにくさというところを描きたかったのか、それとも、戦争のせいで失った過去の栄光の苦難も入れたかったのか、
無理やり詰め込み過ぎた感があって、それをわざわざミステリー仕立てにする必要があったのかな
わざわざ不協和音を流してちょっと不気味なシーンもあって
もしかしたら、原作を読めばなにか打開できて、面白みが湧くのだろうか
この映画の楽しみといえば、戦後の衣装だろう
わざわざ当時の装苑と言う手芸雑誌から型を取り当時の衣装を仕立てたと言う
とても主人公達に似合っている素敵な装いであった
そして、新婚夫婦の部屋のしつらい
足踏みミシンやレトロな雰囲気の家電や部屋の雰囲気
広瀬すずの作るお弁当のオムレツ⇨じゅ〜っと卵に火が通る音と美味しそうに焼き上がるシーンがなんとも言えない
また、吉田羊がお料理をするシーンの海外の可愛いキッチンなんかも目が離せない
そう、この映画はストーリーではなく、映像を楽しむ映画だと思うと退屈しない
ストーリーとしてはやや残念だが、映像として楽しめるところが多いので⭐️3つ
映画は観ないとわからない!
遠い日の記憶
こういう映画が好きなら
昨年「敵」という映画を見てこのサイトでもレビューしましたが、なんとなくその映画に似ていました。(私の中では)
見ていくにつれ何が真実で何が嘘(記憶が塗り替えられたもの)なのかわからなくなり、はっきりとした答えも提供してくれません。
小説はもっとあいまいになっているみたいですが、この映画ではあいまいな中でもあるひとつの答えに観客を導こうとしています。
しかし、その導かれた答えの答え合わせをするのは私の限られた記憶では無理でした。
もっとも、もう一度見ればその答え合わせができるのかと言われれば、そこまでの描写が映画では描かれてなかったようにも思います。
全ては藪の中。
こういう映画、わたしは嫌いではありません。
悦子さん… 怖いよ…
観てきました。・・・しかも、2回。
予備知識なしで観たので、最後に「は? え⁉︎」となりまして。
モヤモヤしてたら、妻が同じ日の違う回に行くというので、私も一緒に行って、もう1回 観てきました。
2回観ると、いろいろと伏線があったことも分かりましたし、全体像がやっと見えてきました。
なるほど、深いですね。
”信頼できない語り手”による戦後の物語。
終戦による「価値観の変化」
戦時中の「苦い記憶」
被爆が生んだ「人生の障壁」
様々な事情が絡み合って「ここに居ても希望はない」と、海外移住に望みを託す主人公。
子どもや、子どもが大切にしているものを踏み躙ってでもと渡航のチャンスに縋りつく様は、鬼気迫るものがありました。
そして、イギリスでそれなりの幸せを得たはずなのに…
共に渡英した長女は、それに背を向けて世を去る。
主人公はその責任が自身にあることを認識しているが故に、悪夢にうなされる。
そして、昔のことを次女ニキに語るにあたり、一連の出来事を自分ではない「あのひと」のこととして語ってしまう。
そうでないことは知っているはず。
でも、そうであって欲しい、私のことではないと思いたい。
今の「冷静な私」は、思い出話の中では「常識ある主婦」の視点で一連の出来事を観察している。
でも、本当は…
うん、おもしろかったです。
2度目を観て自分なりの解釈ですっきり
1回目を観終わってもやもや
色々とレビューを参考にしてから2回目の鑑賞鑑賞
あ〜やはり
佐和子は悦子で、万里子は恵子
そして昔の記憶は全て置き換えって考えると全部つじつまがあって納得
まあ一般受けしない映画だが、いい映画だったな〜
やっぱ映画はこうでなきゃ
しかし、2回観て2回とも泣けたのは未だに謎である
追記
その後、毎日新聞の論評を読んでさらに深まりもう一回観たいと思った
監督下手?
タイトルなし(ネタバレ)
80年代の英国。
ロンドンで暮らすニキ(カミラ・アイコ)が久しぶりに母親・悦子(吉田羊)のもとに帰って来た。
悦子が、一人で暮らす家を処分することにしたからだ。
こんな際にもかかわらず(こんな際だからかもしれないが)、作家を目指す(目指そうとしている)ニキは、悦子から長崎時代の彼女の話を聞き出すことにした・・・
といったところからはじまる物語。
悦子の口から出てくる長崎の話は、戦後7年、1952年の夏の話だった。
新しく建ったアパートに暮らす悦子(広瀬すず)。
彼女は、恩師緒方(三浦友和)の息子・二郎(松下洸平)と結婚し、妊娠していた。
ある日、悦子は河原でいじめられている小学生低学年ぐらいの女児を見つけ、女児の暮らす家へと連れて行った。
その家は、悦子の部屋の窓から見える、河原の掘っ立て小屋だった。
その掘っ立て小屋には派手な格好の女性が暮らしていて、時折、駐留兵が訪れることを悦子はみていた。
果たして、現れた母親(二階堂ふみ)は見るからに派手な格好をしていた。
佐知子と名乗り、女児の名は真理子と紹介する。
悦子と佐知子と名乗った女性との間に奇妙な友情のようなものが芽生え、あるとき、互いが被曝していることを知る・・・
日本映画っぽくない雰囲気の映画。
巻頭から謎や違和感が充満している。
あらすじに書きそびれたが、
ニキは悦子と死別した英国人夫との間の子どもであること、
ニキの上には景子という姉がいたが自殺してしまったこと、
が冒頭で示される。
観終わっての感想は、(以下、ネタバレ含む)
「『マルホランド・ドライブ』か!」でした。
というのも、『マルホランド・ドライブ』を観た後の映画サークルの合評会で、『これ(マルホランド・ドライブ)って、一人の女性を二人の女優に分けて描いただけなんじゃない?』と発言して、周りを驚愕させたことを思い出したから。
(ネタバレここまで)
さて『遠い山なみの光』に戻って。
大いに感心したのは次の2点。
ひとつは、長崎の山をロープウェイで登るエピソード。
女性ふたりの衣装の類似・相似性。
これは、佐知子の掘っ立て小屋にある百合と、英国の悦子の部屋の百合にも符合します。
もうひとつは、娘ニキのキャスティング。
吉田羊似というより・・・
非常に、面白く観ることができました。
<以下、余談>
で、観ているときに、わたしが拘泥したのは、
佐知子の娘・真理子がみる幻想めいたもの。
佐知子と真理子が原爆被害のなか逃げ回っていた際、女性が何やら小さいモノを水の中に沈めていたというもの。
モノは赤ん坊のように思える。
この挿話は、佐知子が出国直前に子猫を水に沈めて殺す「猫殺し」に重ねられ、「猫=子ども」かしらんと思ってました。
なので、子どもは3人。
長女、嬰児、再婚外国人との間との子。
と。
で、長女が、次に生まれた嬰児殺しを目撃しており、そのために精神を病んだ、母親が信じられなくなった・・・
という謎が隠されているのかと思ったわけで。
そうすると、子どもたちの年齢に齟齬が出てくるので、「考えすぎかぁ」として、捨てた次第です。
ミステリアスなエンディングの深い余韻に浸る
これは見応えのある作品だった。
今年の日本映画のベストの一本だろう。
1980年代のイギリス。長崎で原爆を経験した母・悦子(吉田羊さん)が次女のニキ(お初のカミラ・アイコさん‼︎)に戦後の出来事、あるいは夢を語るスタイル。イギリス人の夫と日本で産まれた長女(ニキの異父姉)は何年か前に亡くなったようだ。
1950年代の長崎。悦子(広瀬すずさん)と夫の傷痍軍人・二郎(松下洸平さん)、そして二郎の父でかつて悦子が働いていた学校の校長・緒方(三浦友和さん)がいた。
決して癒えることのない傷。
まだ戦争が近くにあった。
アメリカ人と一緒になりアメリカへ渡るという謎の女性・佐知子(二階堂ふみさん)、そして彼女の娘との出会いが悦子を新たな世界に導こうとしていた。
悦子と佐和子が同化し、夢と現実の、嘘と真実の狭間がなくなるミステリアスなエンディングの深い余韻に浸る。
冒頭とラストを飾るNew Orderの“Ceremony”が深く沁みた。
メタファーの連続、思わせぶりに疲れた
不親切な突き放しで、理解できる人が理解できれば良いという、スノッブさに疲れる展開。
この手の映画を味わえる人は、限られた人なんだろう。
終演後、観客が無言で席を立つ様子を見ていても、戸惑いが伝わってきて、素直に良かったとは言えない。横たわるテーマが重いだけに、それが充分な説得力を持たないまま、チラチラするだけに終わっていて、時折、声高に強い口調で挟まれるシーンが、唐突に思えて、なんだかなぁと。
映像は、絵画を見るような美しい映像美と、織り目正しい撮影技術がひかるのだけれども、挟み込まれるカットがその余韻を切り裂いて、意味不明。。。
思わせぶりと、独りよがりの世界、自分はその遠くにほって置かれた感が強かった。
渋くて薄味
泥の河や冬冬の夏休みを思い出すが、その2つも渋いがもっと渋いというより薄味。三浦友和のエピソードも軍国教育していた教員が己を鑑みるというのも薄い。ドラマが薄いというか。広瀬すずはここ最近明らかにあえて地味だったり渋い作品選びをしてネクストステージに向かっているがそんな一本。ラーゲリみたいな泣きの湿っぽさに行ったらそれはそれで満足度は高い。撮影のピオトル・ジエリンスキはいつも良い。枠内や仕切りの使い方もとても有効。二階堂の芝居がちょっとザマす方向なのだがそこが少しむず痒い。こんなふうにカッコつけてる割に子供の教育をまともにしてない家庭は確かにあるけど。分かりやすい敵や壁をつくらない作品なので、この主人公は何から逃げたいのか最後までよくわからない。広瀬の視点で進むのでそんなに問題に感じないし、二階堂だって生活が苦しいんだろうけど、足掻く泥臭さは描かない。そうするとどうしても味が薄く感じてしまう。
全429件中、61~80件目を表示
映画チケットがいつでも1,500円!
詳細は遷移先をご確認ください。