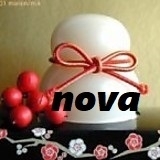遠い山なみの光のレビュー・感想・評価
全430件中、21~40件目を表示
忘却の彼方から蘇る長崎の原爆の記憶の語り直し
長崎は原爆で壊滅的で放射能によるずっと続く不安も含め、悲惨な被害を蒙った
戦後復興のなかで、そこに住む原爆の被害をこうむった人々は、勇気を奮い立たせて前に進むために仕方なく、子供たちへの放射能の影響や日々の生活の苦しさや葛藤などの封印していた辛い記憶を抱えて戦後を暮らしてきた
復興が一段落し観光地として脚光を浴び始めていた長崎を舞台に、その一度、封印した記憶をあたかも遠い山なみから層をなすように浮かび来る仄かな光のように描き出す
母が語る記憶を見事に描いたのがノーベル賞作家カズオ・イシグロの「A Pale View of Hills」は傑作文学であり、石川慶監督が映像化に真正面から取り組んだのがこの映画「遠い山なみの光」だ
記憶の中で形作られる嘘も含めて、戦後における原爆が心に落とした影だけでなく、復興に取り組む人々の逞しさが放つ希望の曙光など、さまざまな記憶をしっかり胸に抱き留めた上での"語り直し"をしっかりと映像化している
タイトル「遠い山なみの光」は過去 現在 未来へ向かって逞しく生きる女性たちの放つ光が層をなして光っている情景そのものだ
過去のものだけではなく、現代を生きる娘のニキの葛藤を通して、この物語は、あなた自身にも照らしてみて欲しいというメッセージも伝えている
映画は記憶の中の嘘や混乱に明確な答えを用意していない、敢えて最後まで曖昧のままだからこそ、観客は映画館を出た後もモヤモヤを感じて自分や他者と語り合うことだろう
そして何遍も観ることで、自分なりに答え合わせが出来る、優れた文学のように余白を描いてみせた、紛れもない傑作だ
珍しく感想を言葉にするまで長い時間を要したが、その煩悶は心地よい時間でありました
記憶に残る美しい映像を是非とも映画館で観て欲しいと思います
前半が物足りない
イギリスに住む悦子が娘に昔、長崎に住んでいた頃の話をして欲しいと、過去を回想するお話。
前半の話の長崎パートは面白く見れるが、ロンドンパートが面白くない。娘と母の煮えきれない会話が延々と続いて飽きてしまった。
全体が後半につれ面白くなっていくだけに勿体無いと思った。
悦子の信頼できない語り手として、二面性を上手く演じた広瀬すずさん、とても良かったです。
猫を水死させるシーンの広瀬すずをどんな顔するか見たかったなぁ。
せっかくならもう少しお金をかけてCGとセット感を無くして欲しかったです。
いつまでも変わらない男性と、変わっていく女性をこの映画から感じた。そらが、やりたかった事だとすればとても上手く出来ている作品でした。
人の人生は意外とこういうものかもしれない
いわゆる「これは友達の話なんだけどね」と言いつつ自分の話だったという話。
現在パートを軸に回想交えながら過去パートが展開される。
過去パートの雰囲気はちょっとミステリアスで徐々に伏線がばら撒かれて違和感が増していく。
最後の最後で答え合わせのようになるのだが、よくよく考えると、人の人生は映画のようにずっと記録されてきるものでもないし、関わる人々の目線でしか語られない。ましてや自分しかいないとなると、たとえ過去を偽装したとしても誰も確かめることができない。
本作の場合はあきらかに恣意的な捏造の記憶ではあったが、意外と人間の記憶は曖昧なもので、無意識に都合の良い過去の改変をしてしまっているかもしれない。
ところで、広瀬すずも二階堂ふみ他、過去パートの雰囲気ある演技はとてもよかった。
関東屈指の大きなSCREEN😧贅沢!!🤣
UNITED CINEMAS豊洲で映画『遠い山なみの光』を観ました。しかも10番SCREEN🤩封切りから1ヶ月経ちますが新作や話題作を抑えての上映 ほぼ貸し切り状態で贅沢すぎます。これだから映画は映画館で観るに限る。場所はららぽーとなので映画以外でも楽しめます。映画はカズオ・イシグロさん原作ですが脚本は石川慶監督なので彼の色が反映されているのでは🤔🧐(?) 彼が手掛けた作品の中で芳根京子さんが主演した『Arc アーク』は邦画の仮面をしたFrance映画で内容が難解すぎて玄人向けだという批評もあります。吉田羊さんは映画『ハナレイ・ベイ』と同様にこの作品でも輝きを放っていました。最初の感想は、昭和時代の邦画を鑑賞した後の余韻に似ていますね。横溝正史よりは松本清張かしら🤔🧐
真実と嘘と夢と、現在と過去が重層的に重なり合って…
ずっと考えている
広瀬すずさん素晴らしい
「夢」か?「騙り」か? 匂わせか?
10月6日と公開から1ヶ月後の鑑賞です。間が合わず見逃していましたが、TAMA映画祭での主演女優賞に推されて劇場に行きました。
予備知識は、Kazuo Ishiguroが原作、長崎とイギリスが舞台といった程度で、原作未読のまま観ました。素直な初見の読後感は「混乱」です。最終盤の種明かしで、プロットのトリックこそ理解できるのですが、だとすると語られた半生の何処から何処まで信じていいのか直ぐには整理できず、混乱したままエンドロールも終わっていました。
🗻
1. 夢か? 騙りか?
本作は渡英後のヒロイン悦子(吉田羊)が、次女⋅ニキ(カミラ⋅アイコ)の取材に重い口を開き、しぶしぶ長崎での半生を語るという構成ですが、最終盤に、都合の悪い? もしくは自身で自身を許せない部分は、他人⋅佐知子(二階堂ふみ)の出来事のように騙っていた事が明かされます。正直に語れなかった動機は、渡英を拒んでいた長女⋅景子が、渡英後に自死してしまった事や、長崎で長女を充分愛してやれなかったという贖罪に起因する事も明示される。
ただ、本作のズルいというか、敢えて説明不足なのは、描かれた長崎での半生の内、どの部分が「夢」でどの部分が覚醒時に騙ったものなのかが判然としない処。長崎での過去のパートの後に、渡英後の悦子が目覚めた描写があれば夢で、次女に語っている場面があれば覚醒時の騙りと判断できる。配信されたり、DVDを手にしたら、その部分をチェックしながら観てみたい。
同じ嘘でも「夢」の中なら、自己防衛の為の無意識な自分自身に対する無意識な嘘だろう。一方、覚醒時の騙りは、長女に対する贖罪を次女に隠す為の自覚的な嘘であり、意味が大分変わってくる。母⋅悦子は若き自分が、夫(松下洸平)にも従順で、義父(三浦友和)にも優しく、友達の娘(鈴木碧桜)さえ気遣う大和撫子だったと思わせたかったのか? 離婚後解放された女として、長女を蔑ろにしていたかもしれない過去を、次女には隠しておきたかったのか? 長女の部屋にあれだけ物証が残っていたら、バレない方がおかしい気もするが、それでもありのままを証言する勇気がもてない程、悦子にはトラウマだったという事か?
🚵
2. 貞淑な団地妻であり、解放された女であり、喪服の女でもあった?
種が明かされると、冒頭から悦子は、離婚前に団地にすむ裕福な妊婦(広瀬すず)としても、離婚して川岸の小屋に住まざる得ないシングル⋅マザーの「パンパン」(二階堂ふみ)としても同時に登場していたと分かる。
ここまでの解釈に異論はなさそうだが、問題は乳児を溺死させた「喪服の女」でもあり、川岸の子供の前でロープを手にする絞殺魔(誘拐犯)でもあったのか?という解釈。仮に本当に悦子が絞殺魔だったとしても、川岸の子供に近づく場面で、何故かロープが自分の周りにある事を、次女に意識的に騙る必要性がない。なので、ロープを手にする場面は夢と考えるのが自然。それでも、解釈は2つできてしまう。1つは、大方の解説記事通り、猫を溺死させてまで長女を渡英させて、自死に追い込んでしまった事への自己批判が、夢に現れた形。つまり、悦子が絞殺魔でもあったなんてbad endじゃない。ただ逆に、実際に絞殺魔であった過去を必死で忘れ去ろうとしていても、夢の中で繰り返し自身が自死を告発し続けているという解釈も完全には否定できない。未読なので原作のニュアンスは不明だが、本映画はそう匂わすように脚色されていた。
🗻
3.神秘性を評価するか?
英語版のwikiによると、原作出版直後、The New York Times は "infinitely ... mysterious"と神秘性を評価している。映画版も長崎の風景や広瀬すずと二階堂ふみの表情は神秘性を秘めていた。ただ、個人的にはヒロインが絞殺魔だった可能性までありえてしまう終わり方にはあまり賛同できない。「私が原爆症だったら結婚しなかったか?」との問いに向き合わない昭和男からの解放という観方もできなくないが、解放後の自分を他人だと騙ってしまう程恥じていて、貞淑な団地妻が結局理想だったと思っている節もあり、もうちと明確なメッセージが欲しかった。
レトロな美しさ
どこまでが
主人公の回想ということで、妊娠中の主人公と、出産後に娘を育てる主人公が混在しているような感じかと解釈していますが、どこまでが事実でどこまでが夢なのかは分かりにくかったです。
死んだ娘に対する罪悪感が現れていると思いますが、殺人事件の新聞記事とか猫のくだりとかは事実だったのか、罪悪感を示唆しているのか。
明るさの中にも暗い影がつきまとう主人公の様子や、被爆した母子の生きづらさ、娘への罪悪感などは、やはり戦争の影響が色濃く理不尽でやるせないです。
回想シーンについては、主人公が下の娘に語っているものを映像で観ているということだとは思いますが。
映像を見ているこちらとしては、あの箱を見たタイミングで明確に二人が同一人物だと分かるのですが、話として聞いている下の娘も同じように分かったらしいというのは、やや違和感がありました。
箱の外観について細かく話していたとか、中身も見て察することが出来たという感じかも知れませんが。
また、主人公が意図的に嘘をついているのか、それとも辛い記憶が改ざんされているのか、下の娘に対して思い出話として話しているのか、あくまで夢の話として話しているのか、それも分かりにくかったです。
下の娘が主人公に対して、娘の死について主人公は悪くないということを言いますが、主人公の辛い過去や罪悪感は理解できるものの、娘の死の原因がよく分からなかったので、この場面もモヤっとするものがありました。
個人的には、序盤から友人役の二階堂ふみの演技が妙にわざとらしいため(そういう演出だと思いますが)、この友人は妄想なのではないか、途中からは二人が同一人物なのではないか、という点に注目し過ぎてしまったような気がするので、全体の印象がぼやけてしまったかもしれません。
終わらない被爆
ナガサキとグリーナム・コモン女性平和キャンプ
(末尾に追記)
長崎原爆を経験した女性がイギリスに移住、映画は1982年の娘ニキとの対話シーンと、過去の1950年代の長崎での生活のシーンとを行き来する。冒頭の、母と娘の会話の短いシーンにしか込められていないのだが、この作品の底に流れているのは、核兵器への強い否定の精神と、これと戦う人々、特に女性たちへの応援のメッセージだと言うのは、反核運動に関わる私の思い込みだろうか。
この映画と、有名な80年代の英国の反核運動「グリーナムコモン女性平和キャンプ」との結び付きは、冒頭の、ニキが当時始まったばかりのこの運動を取材していることの描写と居間のテレビのニュース画面、そして母・悦子と娘・ニキの短い会話シーンだけに過ぎないが、この二人の次のやりとりに凝縮されて、今の私たちに問いかけるものになっていると思う。
ニキ ナガサキに関する家族の回顧録を出版しないかって言われてるの。
悦子 誰がそんな話に興味があるっていうの?
ニキ みんなよ。今だからこそ ちゃんと伝えなきゃ。
悦子 グリーナムと長崎は全然別の話よ。
実は、このグリーナム女性平和キャンプについては、つい最近、事件から40年も経った2021年にフランスで1時間のドキュメンタリーが作られていて、翌年NHKが放映した。つまりこれだけ「古い」話が「今だからこそ」伝えるべき、と作者やNHKの担当者が考えたためだろう。軍拡や戦争の影が濃くなっている今こそ必要な作品だと思う。そのドキュメンタリーの拙ブログの紹介記事もご覧頂ければありがたい。
「NHKが放映した「核ミサイルを拒んだ女たち - 証言 グリーナムコモンの19年」がネット上にオリジナルで復活!」(ペガサス・ブログ版)
ナガサキの惨害を潜り抜けた登場人物たちの苦しみを考えれば、非暴力である限り、ありとあらゆる手段と行動で「核」をこの世界から除去しなければならないと思う。
10/21追記:この小説が出版された1982年はグリーナムコモン女性平和キャンプは始まったばかりで、時間的に小説の題材にはなり得ません。つまり、この部分は映画で初めて盛り込まれた内容で、しかもそれは原作者イシグロ自身の意図だったということです。
それでも前を向いて生きていく
公開から少し経った、日曜朝8時という上映回なのに結構お客さんが入っていた。
原作未読。
ザックリと「ミステリー」だということだけ把握して劇場へ。
戦後直後の長崎、そして30年後のロンドンを舞台に過去と現在を行き来する物語。
敗戦・被爆・性差別・妊娠…といった社会的環境による苦難の中で生きていく女性たちの姿が描かれる。
冒頭に「ミステリー」と書いてしまったが、ミステリーと言うには曖昧な表現が多く、直接的に回収されないパーツも多いので、そういう前提で観てしまうとモヤモヤするかも。
振り返ってみると、冒頭のシーンからいろんな伏線が張ってあることが分かる。
この主人公は、当時における「良き妻」に見えながら、決して戦後の男性社会の中で貞淑に生きていくことを良しとはしていない。
そんな、画面内で描かれること、話されることが、どこか一貫しない違和感。
これが最後の展開に生きてくる。
ただ、何にせよ全体として表現が曖昧なので、多様な解釈ができる、という意味では真っ直ぐエンタメ的な「ミステリー」とは言い難く、より「文学作品」に近い。
戦争という異常な時代を必死で生きてきた人々が後の世代に非難されたり、完全な被害者である被爆者が、同じ長崎の人々に差別されたり、女性は男たちの身勝手に振り回されたり。
それに抗うにせよ、飲み込むにせよ、人は前を向いて生きていくしかない。
表現は、ことさらに「映画的」。
ケレン味とも言える「溜め」「ズームアップ」「光」。
「うわぁ、映画っぽいなぁ」と思いながら観てた。
観た後の正直な感想は
「んんんん。つまり…どゆこと?」
でも、そんなわからないことが不快ではなく、思い出してパーツを繋げていく過程が楽しめるタイブの作品でした。
その辺りは好き嫌いが別れるかも。
【余談】
分かりやすく面白い映画より、こういうモヤモヤした感想の映画レビューを書く方が、記憶の整理ができるし、何となく思ってたことが文字化できた時の満足度も高いなあ。
掴みどころのない映画
戦争ってのは、全ての人生を狂わせる
戦後の長崎の当時最先端の団地でのお話と
その数十年後のイギリスの静かな地方の閑静な住宅でのお話。
最初は昔を懐かしむお話かと思ったら
観ているとだんだんに
あら?それって??どう言うこと???
真剣に観れば観るほど迷路に落ちてゆく映画(笑)
でも、観た後に、戦闘シーンも無い、空襲シーンも無い、
飢餓や大きな怪我も無い、一見平和な市民の話だけど、
戦争の無惨さ、原爆の非常さ、
戦争ってのは、全ての人の人生を狂わせる
その本質が、静かに立ち昇ってくる映画でした。
ぜひ映画館で集中しての鑑賞がお勧めです。
で、月に8回程映画館で映画を観る中途半端な映画好きとしては
いろんな方が感想を書かれてる通り
なかなかにトリッキーな流れの作品。
豪華キャストでカズオ・イシグロの原作なので
映画好きは期待大で観に行かれた方も多いでしょう。
前半にも書きましがこの映画も「リアル・ペイン」と同じで
当事者でなけれな分からない戦争の傷痕の苦しさ、重さ。
戦争に直接触れていなくても、その惨禍は
深く人の思いを捻じ曲げ、捻じ曲がった状態で起きてしまった事実に
後年になってさらに傷つけられてしまう。
「戦争」に限らず、人生の一時期には
後で消せるものなら消してしまいたい出来事なんて
誰にも何かしらあるとは思うが
「戦争」と言う惨禍はあまりにも大規模で深すぎて容赦無い。
この作品はカズオ・イシグロ氏による反戦メッセージなのかな〜と
私は受け取りました。
覚書
2025年の夏は人生最初で最後の大イベント「万博」に全集中してたので
映画鑑賞が極端に減ってしまった。
今年もあと2ヶ月半、何とか残りは映画鑑賞頑張りたい!
原作未読で不安しかなかったが問題なし!
りんご取り放題
原作はかなり昔に読んだが、あまり覚えていない。川のあたりが暗く、不穏な雰囲気だったことだけ、うっすら記憶している。カズオ・イシグロの小説は一貫して、影のような暗さと、痛みや悲しみなどが感じられ、異国で育つ上で体験したことが反映されているのでは、と想像する。
イギリスの家や庭などはすごく素敵で、この背景で撮影されると、ほんと映画に没入できる。庭に生ってるリンゴをもぎ放題。いいなー。ジャムにコンポートにパイ、うわー最高じゃん。母と娘で食事しているところも、お料理がおいしそうで、映画の中に入って一緒に食べたくなった。室内の設えも素敵で、花瓶に花をさすシーンなど、さりげなくおしゃれだった。吉田羊さんがこの家の中で、ものすごく自然で、30年住んでるかのように溶け込んでいた。滑らかな英語も素晴らしい!
終戦後8年の長崎は、こんなにキレイだったのかな。復興はみんなでがんばっただろうが、ずいぶん小綺麗。若い悦子も、いい色でいい布地の服を、とっかえひっかえ着る、素敵な若奥様。なんでこんないい暮らしができてるんだ。まぼろし〜? 河原で暮らす佐知子も、建物はボロいが、けっこういい服を着てる。それに、茶器や花瓶などが高級そうで、ほんとこの人どうやって金稼いでるの、と思った。長崎の話は、なんだか現実感が薄めだった。あと、夜の河原で、あんなに早く走れないんじゃないかな。暗くて転ぶよね。昼間に撮影して、色を整えたんだろうな。
原作に謎が多いのだろうが、映画で解説しているように思えた。でも、謎はそのままでもいいんじゃないかな。わかりやすくするのが良いとも限らない。それに、別にイシグロの小説じゃなくてもいいのではないだろうか。なんでか自分でもよくわからないが、鑑賞後なんとなくモヤモヤしている。
全430件中、21~40件目を表示
映画チケットがいつでも1,500円!
詳細は遷移先をご確認ください。