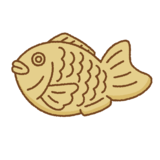リアル・ペイン 心の旅のレビュー・感想・評価
全49件中、21~40件目を表示
誰にも言えない痛みを抱えながら、それでも人生は続いていく
旅好きの私にとって、ようやく「観たい!」と思える映画が公開された。
40代を迎えた従兄弟のデヴィッドとベンジー。幼い頃は兄弟のように育った二人も、大人になった今ではすっかり疎遠になっている。デヴィッドは、破天荒でトラブルメーカーなベンジーに振り回されながらも、どこか羨ましく思っている。一方のベンジーは、周囲には陽気にふるまうものの、実は誰よりも繊細で、人の痛みに敏感な一面を持っている。
そんな二人が、亡き祖母の遺言によってポーランドのホロコーストツアーへと旅立つことに。歴史の重みを感じながら過ごす時間の中で、彼らはそれぞれが抱える不安や葛藤と向き合っていく。デヴィッドは軽度の強迫性障害に悩み、ベンジーもまた心に傷を抱えている。年齢を重ねることへの漠然とした不安、誰にも言えない心の痛み—それはきっと、誰にでも共感できるものではないだろうか。
人はそれぞれ違った「生きづらさ」を抱えて生きている。
「もっと大変な人がいる」と言われたとしても、自分の苦しみを他人と比べることはできない。でも、違う痛みを想像し、寄り添うことはできるはず。ショパンの旋律が静かに心を癒してくれるように、この映画もまた、観る人にそっと寄り添い、優しく語りかけてくれる。
軽妙なユーモアと、胸を打つ切なさが見事に共存する脚本。くすっと笑ったかと思えば、ふと心を揺さぶられる瞬間が訪れ、気づけば深く考えさせられている。
旅の醍醐味とは、美しい景色や美味しい食事を楽しむことだけではない。そこで生まれる出会いや経験が、私たちの心に刻まれることこそが、旅の本当の意味なのだと思う。デヴィッドとベンジーにとっても、この旅は祖母との思い出を辿るだけのものではなく、自分自身を見つめ直す時間になったのだろう。
観終わったあと、そんな「心の旅」について考えずにはいられない作品だ。
バカリズムさんの脚本みたいな映画(笑)
【ポーランド3日間 ユダヤ人強制収容所見学、英語話者の歴史専門家によるガイド付き、ワルシャワ現地集合】
このツアーに参加したアメリカ人の中年男性2人(いとこ同士)が主人公。出発する空港での待ち合わせから、ふたりのキャラの違いが浮き彫りにされる。道路の渋滞で乗り遅れそう!と必死にベンジーのスマホにメッセージをひたすら送り続けるデヴィッドと、それに全く気づかないベンジー
飛行機で一睡も出来ず、ようやく到着したワルシャワのホテルでシャワーでも浴びようとするデヴィッドと、半ば横入り的にデヴィッドのスマホを奪い、彼のスマホで音楽を聴きながら先にシャワーを浴びるベンジー
(そしてスマホが水没…かなと思ったけど、そこはセーフ)
ホテルロビーでのツアー同行者との顔合わせ。強制収容所見学も組み込まれたツアーだけに、何故このツアーに参加したかをそれぞれが自己紹介とともに語る
外国の団体ツアーってそうなんだ!と発見。日本の団体ツアーは参加者同士の横の繋がりを促すイベントは無い。添乗員が旅行の注意点をそれぞれに集合した時点で説明するだけ
確かに横の繋がりって、日本人の気質から言って面倒に思うけど、最低限メンバーのプロフィールくらい知っておきたいとも思う(個人的見解)
ゲットー蜂起を称えた大きな像の前での記念写真、それを各々のスマホで撮影する羽目になったデヴィッド(笑)
昼食時、デヴィッド以外がひとつのテーブルに付いて、何となく仲間外れみたいになった時、サッとデヴィッドの真向かいに座って食事を始めるベンジー
「あっちに座るかと思った」
「…え?なんで(笑)」
こういうことって、結構ある
ひとつひとつは大したエピソードではないけど、そうだな〜、バカリズムさんの脚本(ホットスポット)みたいだな
凄い事件が起きるわけではないけど、ちょっとしたニュアンスの連続でふたりの交流が描かれる
ラスト、二人で訪ねたおばあちゃんが暮らした家も、感動のエピソードがある訳でなく。むしろちょっとした行き違いが生じるくらいで、泣けるようなシーンもなく、むしろ後半はちょっと眠くなったくらい
強制収容所に行く為の列車の一等車、動物が乗る貨車に押し込められて運ばれた先人達の労苦を思えば、乗りたくない!と拒否
ユダヤの偉大な故人の墓の訪問には、その歴史や背景を表す数字より、故人に思いを馳せることが必要なんだ!とブチ切れる
列車で眠りこけたデヴィッドが寝ぼけて間違えて、違う駅で下車しても止めなかったり
ベンジーの周りを困惑させるエピソードは数しれず
でも彼の、人の懐にするりと入り込むキャラクターゆえに、嫌われずに済むギリギリの人生だったんだろうなと推察、イヤ、日本だったら確実に迷惑な奴認定されるな
強制収容所見学シーンはそんなに時間をかけていない。感傷的になるような演出もなく、そういう背景の施設が今も遺されていること、遺された大量の靴がその主がいたことを教えてくれる
感動作ではない
わたしはちょっと眠くなったくらいだし
ツアー参加者とのふれあいで、何か特別なストーリー展開が生まれるわけでもなく
帰国して、デヴィッドは家族の待つ家へ
家に持ち帰った小石、彼はじきにその存在を忘れてしまうのだろうし
ベンジーは空港の待合室でもう少し人間観察する、と残って
淡々と終わる映画だけど
何かを心に遺してくれる映画
ふと気づくと、玄関の前に転がっている小石のように
しんどくても自分を抱えて生きる
個人的な思い出として、昔ワルシャワに数日間滞在したことがあり、自分の思い出を辿ることができたら、と思って映画を見ました。
ずいぶんと考えさせられる映画でした。
主人公のデヴィッドは映画冒頭で空港へ向かうタクシーの中から繰り返し繰り返し、旅の相棒である従兄弟のベンジーに電話をします。電話をするデヴィッドが神経質な危ない人に見えたのですが、話が進むにつれてデヴィッドは普通の人で、相手のベンジーの方が問題であることが判ります。
ポーランドでのナチスによるユダヤ人迫害を知るツアーで、デヴィッドはベンジーに振り回され続けます。ベンジーは自分の感情に正直な人で、ツアー参加者と衝突しそうになりながらも、正直であるがゆえに人を惹きつけ、愛される魅力を持ちます。
ツアー参加者と別れるシーンで、彼らはベンジーに感謝し別れを惜しみ、一方のデヴィッドにはベンジーのオマケのような対応をします。
その日の前の夕食のシーンで、デヴィッドはベンジーに対して持っている感情をツアー参加者に明かしますが、それは嫉妬と羨望が入り混じった複雑なもの。自分の感情を赤裸々に表現したのですが、ベンジーがピアノを弾き始め、注目を持っていってしまいます。
それでもデヴィッドはベンジーと葉っぱを吹かし、おばあさんの家でベンジーを真似て石を置き、旅の終わりではベンジーを自宅に招き、ベンジーの心に近づこうとします。
ベンジーとの旅で傷つくこともあったものの、思い出を作ったデヴィッドは家族の待つ家に戻り、旅を終えます。
一方のベンジーは、映画の終わりで一人空港に佇み笑顔を浮かべます。
ベンジーはまた、一人に戻ってしまったのです。
ツアー参加者を楽しませ感謝されたベンジーでしたが、旅を強く印象付ける存在としてありがたい、でも彼のような存在は日常生活で刺激が強すぎ、疲れてしまうのです。
ベンジーと辛抱強く付き合ってくれるのは、亡くなったおばあさんとデヴィッドだけ。
デヴィッドから家に誘われても、デヴィッドの家族を苛立たせて関係を壊してしまいそうだから訪問を断った、自ら孤独を選ばなければいけないのがベンジーの日常であり、彼が抱えている苦悩なのでしょう。
映画ラストのベンジーの笑顔は、自己憐憫の気持ちが表れていたように思います。
傷つけ合いながらも相手を思いやる、生きていくのは切ないものだ、そんな気持ちになりました。
「今ある痛み」には鈍感な主人公
・終わり方が雑
主人公が成長したわけでも変化したわけでもなく、空港でニヤニヤ「変人観察」をするというラスト。「痛み」は? 他者や過去、さまざまなルーツに対するリスペクトは? 主題を小馬鹿にするようなラストに疑問を感じる
・ストーリーの起伏がない。内容に比して長い
心の旅を描いていることは理解したが、ストーリーの起伏のなさや主人公の情緒不安定さについていけず。
・「今ある痛み」には鈍感
主人公は周囲に対して、過去の出来事や自分が感じたい痛みには敏感であるが、自分の目に映らない現実には鈍感である(感傷から玄関扉の前に石を置いたりはするが、そこで生活する人の日常の危険には鈍感)
総じて、脚本が失敗している。
もし真面目な作品にしたいのであれば、よりテーマを強調して扱うべきだし、コメディにしたいならより登場人物のからみや魅了を引き出すべき。
同じテーマを扱うなら、ドキュメンタリーで撮る方が有意義だと思う
コメディにちらっと覗く痛みの描写がうまい
ベンジー役のキーラン・カルキンは、マコーレー・カルキンの弟らしい。そういわれれば似てる。
ガイド役のウィル・シャープは、「エマニュエル(2024)」で欲望が枯れたというケイ・シノハラを演じた人なんだけど、映画監督でもあるんだね。
字幕翻訳は松浦美奈さん。『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』から二連続。
兄弟のように育ったいとこ同士のデイヴとベンジーだけど、近頃は疎遠だった。どうやら40過ぎらしい。わたしと同世代。亡くなったおばあちゃんの遺言で、彼女の故郷ポーランド行きのツアー旅行に参加する。英国人ガイド(非ユダヤ系)が主催?するツアーで、ソマリア虐殺をサバイブしてユダヤ教徒になった人や、最近離婚したアメリカ人女性や、テキサス?のアメリカ人夫婦と、強制収容所や墓地を巡る。
ベンジーは明るくて陽気なんだけど、躁鬱ぽいってゆうか、不安定な感じがする人。
デイヴは常識的なふるまいをする人だけど、こちらも何らかの薬を飲んでいるし(のちにOCDとわかる)人付き合いは苦手そう。
ベンジーは人好きするらしく、みんな振り回されるけど二人を比べると、ベンジーの方が好かれる。デイヴはそれをわかっているので、憧れつつも、自分にないものを持っているのに何であんなことした?という言うに言えない気持ちがある。
どうやら、ベンジーは数か月まえに睡眠薬の過剰摂取をしているらしい。
定職もないっぽく、母親の家の地下で暮らしている。
いとこに限らず、兄弟や友人でもありうる、愛憎入り混じるふたりの関係が、わざとらしくなくさりげなーく描かれていて、とてもいいと思った。
主軸は、”本当の痛み”を抱えながら生きているいとこ同士のロードムービーであり、ポーランドのユダヤ人の歴史をなぞるロードムービーでもある。金は金持ちのヘロインだからとか、数字や事実は控えめにして人と繋がるべき(どっちも言い回しはうろ覚え)とか、セリフも強くてよかった。
墓地に石を置くがなんなのかはじめはわからなかったけど、ユダヤの習慣で、墓地に来たよと死者に伝えるための風習との事。おばあちゃんのかつての家のまえで、2人が石を置いてたら、地元の人に、住んでる高齢女性がケガするからやめれって言われるところで判明した。
基本はコメディなんだけど、ほろっとしたり、ちくっとしたりする。
笑いのなかに、差し挟まれるささやかな痛みの描写が、うまいと思った。
劇伴はほぼショパンのピアノ。
ベンジーが弾いたのはショパンじゃなくて「TEA FOR TWO」。
空港でぼーっとするベンジーで始まり、再び空港でぼーっとするベンジーで終わる物語。
何がベンジーを悲しませるのかは描かれない。
たぶんそれは、人とわかちあっても癒えることのないなにか。
自分だけが感じて生きるなにか。
しんみりと
ジェシーアイゼンバーグが、監督、脚本、主演 カルキン君の弟のキーランカルキンと従兄弟を演じる。
彼らのルーツであるポーランドへのユダヤ収容所巡りツアーを参加 亡くなった祖母の家も見に行く。
対象的な2人の心の旅です。他の参加者の皆様も個性的でした。ラストはまたそれぞれの世界へ
ベンジーのパーカー
2人のいとこ同士のロードムービー。祖母の育った場所、ルーツに向かう。
冒頭から最後まで、ショパンの曲にも惹き込まれます。
なんとなく危なかしいベンジーの性格が、あの黒くて所々に脱色した変わったパーカーにとても表れていた気がしました。
空港で始まり、空港でおわる。
ラストシーン、2人が空港で別れた後のベンジーの時間の過ごし方が、とても良かったです◎
ユダヤ人の風習でお墓に敬意を払って石を積むのは、『シンドラーのリスト』でも観たことがあり、懐かしく思い出しました。
自分と出会う旅
ポーランドってなんて美しい国なんだろう、『リアル・ペイン心の旅』では、そう思ってしまう。旅を通じた大人になる旅なんでしょうか、子供のままで大人になってしまった40男のお話です。けっしてイスラエル人の過去の悲惨な歴史との関係を探ることのないように。
ニューヨークに住むイスラエル人
知的レベルが高くて。
しっかりした教育受けていて。
なんだけど、とっても落ち着きのない40歳を過ぎた、従兄弟どおし。
アメリカのイスラエル人というのが、よく伝わってくる。
心に、余裕がないのだ。
十分満たされているのに。
片方は、家庭を持っているが。
もう片方は、最愛の祖母の死を受け入れられず、自殺未遂。
その祖母の遺言で、祖母のかつて住んでいた、ポーランドを旅するふたり。
問題なのは、自殺未遂をしたほう。
マザコン、いやグランドマザコンとでもいいますか。
ポーランドを旅している気分にしてくれる。
この映画の素敵なところですが。
問題の自殺未遂をしたほう。
ツアーなのに、他の客を巻き込んで、迷惑を。
この御仁、感受性がとても強くて。
人の痛みも自分の痛みとして、強く感じるタイプ。
だから、ポーランドで旅行するときも、列車の一等車に乗っていることが、気に食わない。
ホロコーストに向かう、この路線で、過去の苦しみを感じると。
とても、一等車でのうのうとしてられないと。
それは、そう感じるのはその人の自由なんですが。
この方の問題は、一人黙って二等車に移ればいいものを。
他のツアー客を不愉快にさせながらという点。
つまり、周りを巻き込むタイプ。
どうも、祖母なき後は引きこもりのよう。
いい子をやっている人の典型。
大人になりきれない大人を見ている気分になる。
太宰治や尾崎豊のような人。
いや、この二人ならまだ、小説や歌に表現することで、承認欲求がみたされるからいいんだけど。
でも、最後は悲惨な結末ですね。
芸術家でもない普通の人は、生きづらいと。
だから、自殺未遂をするわけですが。
豊かさが、引き起こす副産物
ホロコーストに向かう人々は、彼のように悩んでられなかったでしょ。
生への渇望、僅かな希望と大きな絶望。
彼のように、感傷に揺さぶれる暇などない。
彼は、大人になりきれてない。
祖母の庇護の中で、世の中のストレスから逃げてきただけ。
その祖母が、なくなり自分を守ってくれるものがなくなった。
それが、自殺未遂の原因だろうなと。
ニューヨーク、アメリカという過酷な社会もそれを加速したのかも。
このような人を自己愛性パーソナリティ障害とか、境界型パーソナリティ障害と。
でも、世の中の矛盾とかストレートに表現するから。
人々に共感されたり、愛されたりするのも事実。
でも、尾崎豊が、「十五の夜」で歌っているように。
「自由になれた気がした十五の夜」
つまり、本当の自由を手に入れたわけではない。
それが、本人にわかるから、絶望的になるわけで。
ユダヤ人の悲しい歴史と彼の現在は、別物。
映画の主題は、自己アイデンティティーの確立かな。
確かに、ユダヤ人の悲しい歴史は、祖母を通じて聞かされていただろうし。
でも、その事と現在の彼のありようは、分けて考えるべきだと。
この彼の悩みは、かつては、十代や二十代前半の特有のものだし。
それが、やがて三十代へと。
それが、映画の彼は、四十代である。
社会性は備わっていそうだから、やっては行かれるだろうけど。
結構険しい道のりだろうなと。
その逃げ場が、薬や酒、ギャンブルにならなければいいけど。
そんな彼が、社会に戻ってゆくだろうと感じさせるラストで終わっているのが、幸いか。
でも、彼が、このツアーで、ある程度旅仲間から受け入れられたのは。
あくまでも、その人たちが深みのある、大人たちだったという点と。
旅という、非日常の空間だったということに過ぎないと。
となると、現実社会で彼を待ち受けているのは。
そう容易いことではないな。
なるべく若いうちに、家族以外の社会と関わろう。
ストレートに感動できる作品ではない
真面目で余裕がなさそうに生きている主人公と空気など読まずに好き勝手に生きる従兄弟が、彼らのルーツであるポーランドのツアーに参加する様子を描いた映画。
タイトルが「リアル・ペイン」であることから、これこそが制作陣の狙いかもしれないが、主人公と従兄弟に対する共感性羞恥に似た苦い感情を強く覚え、観ていてやや苦痛を感じる作品だった。
そこで何が行われたのかを知ることも大事だが、その空気から何を感じるのかも大事なのことだと思う
2025.2.5 字幕 TOHOシネマズくずはモール
2024年のアメリカ映画(90分、G)
祖母の生家に向かうユダヤ人のいとこ二人を描いたロードムービー
監督&脚本はジェシー・アイゼンバーグ
原題は『A Real Pain』で、直訳は「本当の痛み」、スラングは「困った奴、面倒くさい奴」という意味
物語は、NYからポーランドに向かうユダヤ人のベンジー(キーラン・カルキン)と、そのいとこ・デヴィッド(ジェシー・アイゼンバーグ)が描かれて始まる
出発の2時間前にチェックインをしたベンジーは、ずっと変人観察を続けていて、デヴィッドの電話には一切出なかった
その後、なんとかワルシャワに着いた二人は、そこでツアーガイドのジェームズ(ウィル・シャープ)たちと合流することになった
二人が参加するのは「ホロコースト歴史訪問ツアー」で、参加者はユダヤ人老夫婦のマーク(ダニエル・オレスケス)とダイアン(ライザ・ザトビ)、離婚直後のルーツ探しをするマーシャ(ジェニファー・グレイ)、ボスニアの大虐殺を生き抜いてユダヤ教に改宗したエロージュ(カート・エジアイアワン)たちだった
ジェームズもホロコーストの経験者でもユダヤ人でもなかったが、彼らの生き方に興味を持っている存在だった
彼らは、ワルシャワを皮切りに、最終的にはマイダネク強制収容所に向かうことになっていた
そんな道中にて、いろんな歴史の爪痕を見学していくことになるのだが、ベンジーだけは「ツアー」に違和感を感じていた
それは、歴史と統計を強調し過ぎているというもので、現在のポーランドとの関わりがほとんどないというものだった
ジェームズにもツアーを初めて5年のキャリアがあり反論するものの、とりあえずはベンジーのアドバイスに従って、説明を少なくすることに努めていった
物語は、レンジーの自殺未遂半年後という時期で、ツアーに申し込んだのはデヴィッドの方だった
彼は、レンジーを元気づけるためにツアーへの参加を促し、祖母の生家と対面することで何かが変わるのではと思っていた
実際に何が変わったのかはわからないものの、レンジーの存在は参加者のマインドを少しずつ変えていた
別れる前夜のレストランでの出来事はそれぞれの心に深く刻まれていて、ベンジーとデヴィッドの本当の痛みとは何なのかを追体験するようでもあった
ベンジーはかなり多感な人間で、収容所に立ち寄った後のバンの中では、他の人が普通に談笑しているのにも関わらず、一人で何かに祈りを捧げていた
デヴィッドはここまで命に寄り添えるのに、どうして自殺騒動を起こしたかが不思議に思えていた
だが、ベンジーとデヴィッドが感じる「痛み」には違いがあって、種類も違えば、受け止め方も違っていたのである
ユダヤ人の慣習として、お墓参りに行った際に石を置くというのがあって、ラストでは祖母の生家の玄関先に石を置くことになった
近隣住民からの苦言でそれをどけることになったのだが、デヴィッドはそれを持ち帰って家の中に置いていた
それは「来ましたよ」という合図から、「行ってきたよ」という合図に変わっていて、その石には祖母の記憶とベンジーとの思い出も刻まれているのではないだろうか
いずれにせよ、自分のルーツを探る時、多くの人が「自分の命が繋がっているという奇跡」を目の当たりにすると思う
もし、ホロコーストがなければ、ベンジーもデヴィッドもポーランドにいたかもしれないが、同時にこの世に存在していなかったかもしれない
自分の人生を生きているようでも、実際には長く受け継がれてきたものを次世代にバトンタッチをする役割を担っている
それでも、戦争などがなくても途絶えるものは途絶え、続くものは続いていく
そう言った生命の因果を鮮明に映し出しているのが、あのガス室の空気で、あの場所の生命を敏感に感じ取れるのがベンジーという人間なのかな、と感じた
二人の掛け合いが最高
観てよかった、じつに染みる佳作。
ナチスドイツによって親や祖父母が強制収容所へ送られ、戦後アメリカに移民したユダヤ人の子孫たちが、ポーランドのユダヤ人ゆかりの地を巡る「ホロコースト・ツアー」に参加し、参加者視点でそれぞれの胸の内を語っていく。
かつてのユダヤ人街(ゲットー)、墓地、反ナチスのレジスタンス運動を行った人々の銅像、そして強制収容所跡……
観光地となった土地を巡る中で、W主人公である従兄弟二人によって、現代40代アメリカ移民の生きづらさや、直面する悩みが露になっていく。
監督・脚本のアイゼンバーグが論理的で真面目だけど人見知りのデヴィッド、兄のマコーレー・カルキン主演『ホーム・アローン』で主人公のいとこ役を演じたキーラン・カルキンが奔放で自由な従兄弟ベンジーをそれぞれ熱演。
実際に真横にいたら迷惑極まりないベンジーですが、創作物の中なら面白いキャラ(そして実際にあちこちにいそうな人でもある)。
二人の掛け合いが最高で、これだけもう少し長く観ていたかった。
(ハッパ=マ〇ファナだけはいただけないけど)
万人向けではないけれども、40代以上、で肉親を亡くした経験のある人には薦めたくなった。
厄介者のピエロの涙
監督・脚本・主演を果たしているのは『ソーシャル・ネットワーク』(2010年)でザッカーバーグを演じたジェシー・アイゼンバーグ。そんないろいろな才能の持ち主だったなんて知らなかった。
さほど大きな事件が起きるわけでもなく、40代のおっさん2人旅の様子が淡々と描かれるロードムービーで、ポーランドの美しい街並みを一緒に旅しているような気分にさせてくれる。ただ、強制収容所を訪れる場面では、ポーランドには行ったことがないが、代わりにポルポト時代の虐殺の様子を残しているプノンペンのトゥールスレン博物館を初めて訪れたとこのことを思い出して胸が締め付けられた。
ちなみに、劇盤は基本的にショパンのピアノ曲。そのピアノ曲が場面や登場人物の心情にマッチして、ときに楽しく、ときに物悲しく響く。
普段の日常生活から離れてみることで、自分では意識していなかった仕事や家族その他のことに起因するストレスや残りの人生に対する不安感など、いわゆる「ミッド・ライフ・クライシス」を抱えていたことに気付かされるデイヴィッド。一方、ピエロの顔に必ず涙が描かれているように、自分の唯一の理解者だった祖母の喪失以来、大きな苦しみと悲しみを心の中で抱えているからこそ、人前では過度におどけてしまうペンジー。その2人が本当に素直になれるのは、祖母が奇跡的に生き抜いた強制収容所を見学し、昔住んでいた何の変哲もない家を見てから。自分が今ここにあるのは祖先たちの存在があるからこそと感じる二人。我々アジア人のような先祖信仰を持たない欧米人でも、歴史の積み重ねで現在があるという事実の重みをやはり感じるのではないだろうか。
移民の歴史を軽んじる人物が楕円形の執務室にいる時代にこんな作品が作られたのはただの偶然なのだろうか?
なお、タイトルの「リアル・ペイン」は文字通り主人公たちが抱える心の「本当の痛み」であるのと同時に、英語で He is a real pain in the neck/ass. と言うと「アイツは本当に面倒くさい、厄介なヤツだ」という意味になるので、〈厄介者のペンジー〉をも指してもいるのだろう。
中年ロードムービー
まず、主人公ふたりが従兄弟同士という関係なのがいい。
祖母を通じたつながりは近すぎず、遠すぎず。
祖母の故郷を訪れがてら、ホロコースト・ツアーに参加することで、2人はそれぞれの抱えた傷を癒そうとする。
多くの説明があるわけではないが、台詞や演技で段々と2人の背景がわかってくる。
40代でもう若くはない中年の閉塞感。
ベンジーの痛々しいまでの繊細と、本当は同じくらい繊細なのにそれを隠して社会人として真っ当に生きようとするデイヴィッド。
キーラン・カルキンの動の演技に目を奪われるが、受け止めるジェシー・アイゼンバーグの静の演技も素晴らしい。
(レストランで心情を吐露するシーン、怒鳴ったり泣いたりするわけではないのに、揺れ動く感情がよく伝わってきた)
ポーランドを一緒に旅行している気分になれたのもよかったし、劇伴がすべてショパンのピアノ曲だったのもポーランドへの敬意を感じた。
(監督、脚本、製作も務めたジェシー・アイゼンバーグはポーランド系ユダヤ人)
おまけ。
旅が終わり、頑なに空港にとどまろうとするベンジーにやや違和感を感じたのですが、ベンジーは実はホームレスなのでは?との考察を読んで腑に落ちたのと、いっそう心が重くなったことを記しておきます。
2025/3/3 追記
キーラン・カルキン、アカデミー助演男優賞受賞おめでとう!スピーチも喋りまくりで面白かったです。
痛み・苦しみを抱ける映画として唯一無二の映画
最初なんか不愉快な気持ちでストーリー進んでいく。ポーランドとなかなか行くことのないツアーを映画を通じて観光できる。気づいたら、過去に自分がベンジータイプの人間に愛憎を抱き、ディビットと同じパターンに陥っていることと重なっていることに気づく。
ひたすら投影されて、ホロコーストの悲しみとリンクして心の中で混ざり合う。かと言って救いもない。
映画を見終わった後は、物足りなさを感じて、「なんでこんなにレビューが高いのか?」わからなかったが、みなさんのレビューを見たりして、映画の本質を答え合わせできるとともに後からボディブローのように効いてきて、気づいたらリアルペインを抱かされている笑。
鑑賞直後は3.0ぐらいの評価だったが、痛み・苦しみを抱ける映画として唯一無二の映画だと思いプラス1.0となった。
いとこ同志‼️
いとこ同士であるユダヤ人のデヴィッドとベンジーは、亡くなった祖母の生家を訪ねるため、ポーランドへのツアーに参加する・・・‼️明るく社交的なベンジーと内向的なデビッドという正反対な性格の二人の珍道中が描かれます‼️特にデヴィッドの主観で描かれるわけですが、自分とは違う魅力で他のツアー客とも仲良くなっていくベンジーを羨む一方、過去にベンジーが起こしたある出来事に心を痛め、ベンジーの事が心配でたまらないデヴィッド‼️自らも精神的な病を抱えるデヴィッド‼️そんな二人の姿を自らのルーツであるポーランドへの旅、ホロコーストの地を巡る旅の中で描いていて、そしてそんな旅を彩るショパンのピアノ曲の数々がホントに効果的ですね‼️祖母の家に自分たちの軌跡である石を置こうとするも、近所の人に危ないからと注意を受けたり‼️ラスト、空港での感傷的なハグも、多分、次に会った時もケンカするんだろうなと思わせる‼️そして家族の元へ帰るデヴィッドと、空港に一人残って人間観察するベンジーの対比が、切ない余韻を残す秀作です‼️
ロードムービー苦手です
予告編、なかなか面白そうでした。それに、アカデミー賞受賞作品ということもあったので観に行きました。
…が、始まって冒頭から、ベンジーの自己中っぷりにイライラ。デヴィッドのこと、バカにしてるのかな?中盤から、少し、大人しくなったところで、私のイライラも落ち着きましたが。正直、面白いと思えず。どうも、ロードムービーと言われるもの、私は苦手みたい。
ジェシー・アイゼンバーグ、変わり者の役が多いイメージだけど、今回は、振り回されてる印象だったし、いつものように早口だけど、いつもよりセリフも少なかったので、ちょっと印象が違って見えました。
生きづらくても生きていくことに価値があるんだろうなぁ。
2人の従兄弟、性格も生活も全く違う暮らしをしていたけれど,祖母の死をきっかけに自分たちのルーツであるユダヤのツアーに参加する。
いとこのベンジー、なんて繊細で生きづらいタイプなのか。明るく人を巻き込んで楽しくさせる才能と自分の内面に深く向き合う志向を持つ。ツアー中もそんな彼に周りは振り回されてつつ、結局彼のことがみんな大好きになる。
一緒にいるデイビットはそれを見て,自分の不器用さが嫌になるのだ。こんな人と一緒にいたら自分でも羨ましく,また妬んでしまうなぁ。
最後に2人ともハッピーでもう大丈夫というわけではないところがまさにリアルペインだなぁ。これからもそれぞれのことに向き合っていくのだろう。でも少しだけお互いに勇気をもらっただろうか。ベンジーの空港での表情はなんとも言えない。悲しいわけじゃないけど涙が出た。
そして、映画に登場するホロコーストの収容所の映像には言葉にならない悲しさがある。負の歴史の重さを実感する時間だった。
神経質で繊細な、ふたりの40男
ベンジーは多分、食い詰めて空港で生活している。
兄弟のように育ったデヴィッドに久々に会って一緒に旅行、それで、自分の実態を知られないよう精一杯取り繕って振る舞っているように見える。
亡くなった、二人が敬愛するおばあちゃんは、ナチスの強制収容所から運良く生き延びたユダヤ人のひとり。そのおばあちゃんからのプレゼント(というか遺言)が、強制収容される前に、自分と家族が住んでいたポーランドの家への、ふたりの訪問。
これはベンジーにはキツイだろう、嫌でも「ファミリー」を常に意識させられる旅だ。
ベンジーには家族もなければ、家すらもない。
歴史ツアーの道中、ちょっとしたことで怒り、キレて、奇行をするのは、彼のもともとの性質に加えて、情緒不安定になっているからではないか。
かたや、デヴィッドには仕事があり、家があり、愛する妻とかわいい息子がいる。
デヴィッドが神経質で強迫神経症、コミュ障気味で生真面目で、ベンジーの「自由な」生き方と何故か人に好かれる魅力的性質に憧れを抱いてうらやましがっているが、それが分かったところでベンジーが自分を肯定的に捉えるほどでも、ましてや優越感に浸れるほどのものではなく、デヴィッドが本気でベンジーを愛して心配しているのが分かるので、憎むこともできない。何よりベンジー自身、デヴィッドを愛している。彼にだけは見捨てられたくないという、切なる思いがありそう。
それがさらに腹立たしいと言うか複雑な気持ちにさせるのだろう。
ベンジーは、そう見えないかもだが、相当神経質で繊細だと思う。
ショパンのピアノ曲がBGMというには大きすぎる音で始終かかっているが、これがとっても良かった。ショパンの曲は、よく合う映像と一緒に聴くと感動的に良さが増す気がする。
繊細なふたりの40男の内面を描く映画に大変良くマッチして、胸を打つ。
ショパンでもって、この映画の星が増えた。
このツアーに参加した人たちが、全員、人の話を遮らずに終わるまで聞き、合間に感想を述べあい、自分の番が来たらきちんと自分の話をする、という、対話のマナーというか暗黙のルールを普通に身につけていて、対話の文化が根付いているのを感じる。
日本では昔夜中から朝まで討論する番組があったが、ファシリテーター自らが人が話しているのに終いまで言わせず、遮りまくって被せて自分の主張をする、参加者全員がその流儀で我が主張だけを聞かせようとするがそれすら遮られるので、何一つ実りのないただの怒鳴り合いでうんざりしたのを思い出した。
今ではまっとうな社会人なら、いわゆる「会話泥棒NG」はマナーとして浸透しているが、それでも人が話しているのに遮って自分の話を被せ、ずっと「自分のターン」にするのが通常運転な人は時々いる。対話の文化が根付くまでには至っていない。学校では教えませんから。
アウシュヴィッツ、ビルケナウなど、有名なものだけではなく、マイダネク、ソビボル、ベルゼック、トレブリンカなどガス室・焼却関連施設を持つ大規模な絶滅収容所はいくつかあった。そのひとつひとつ、全てで行われた残虐行為の事実は、なかったことにできない。
ガス室に残るチクロンBの青いシミや、大きな金網のストッカーに貯められた大量の靴などを目の当たりにすると、ホロコーストの現実感が一気に押し寄せてくる。
亡くなったおばあちゃんも、かわいがっていた孫二人に、この事実を我が事として受け止めてもらい、次世代に語り継ごうとしたのだろう。
ユダヤ人のいとこ同士の40男ふたりは、それぞれに「生きづらさ」を抱えているが、デヴィッドの方は淡々と自分が果たすべき責任を果たし、社会のルールを守って他人と折り合いをつける気遣いをしての今がある。我慢もするが、その分得たものも大きい生活。
ベンジーには、常に「自分」しかいない。自由に生きてきたので、社会のルールより自分のルールが優先。人に好かれる魅力は今でもあるが、深い付き合いは多分無理。困難に出会ったらそこから離脱するのが処世術で、個性的すぎて他人や社会と折り合いをつけることが苦手なように見える。
良し悪しは別として、どこかで枝分かれした生き方の違いが、日々の積み重ねでいつの間にか大きく広がってしまったのが今のそれぞれの居場所でしょう。
この二人の場合、生き方は自分で決められる。自分次第です。
ありがちな40代男性の「危機」と友情(本作は親しいいとこ同士)の話、それにユダヤ人としての特殊事情が絡んで、さほど目新しさはないが、時代により多少変わっても常に存在する普遍的なテーマなんだろうと思いました。
観光映画としても良くできていて、ツアーの道中、自分も参加しているような旅行気分を味わえました。
(追記)
旅が終わって、デヴィッドは妻と子供が待つ温かい家に帰るが、ベンジーはひとり空港の椅子に座り込んでどこにも行こうとしない(行くところがない)。このシビアな現実感が秀逸。
ですが、あるレビュアーさんが
>最後、空港の椅子に佇むベンジーが「さあ、行こうか!」と明るい表情で立ち上がるのを願わずにいられませんでした。
と書かれており、俗っぽくなって映画的に台無しなのは分かっているが、私もそういうラストが観たかった。
でもベンジーは立ち上がらず。空港のベンチに根っこを生やしたように座っていました。
【”そしてユダヤの従弟二人は想い出の場所に石を置く。”今作は愛した祖母のポーランドの家を訪ねる二人が、夫々の哀しみを抱えつつも自らのルーツを旅する中で徐々に癒される様を描いたロードムービーである。】
■デヴィッド(ジェシー・アイゼンバーグ)は、従弟のベンジー(キーラン・ランキン)と愛した亡き祖母の故郷、ポーランドを訪ねるホロコーストツアーに参加する。
が、自由奔放で空輸でハッパを持ち込んでいる陽気なベンジーに、生真面目なデヴィッドは振り回される。だが、ベンジーは哀しみを抱えており、デヴィッドは心から彼に寄り添えない自分に悩んでいた。
◆感想<Caution!内容に触れています。>
・二人が集合する空港。デヴィッドは家から慌ててタクシーで駆け付けるが、ベンジーは二時間前から空港に居て、人間観察をしている。
冒頭のこのシーンから二人がかけ離れた生活をしている事が分かる。
デヴィッドは美しい妻と可愛い子がいて会社勤めだが、ベンジーはそうではないらしい。
・だが、二人は空港で会うと嬉しそうにハグして飛行機に乗る。ベンジーは荷物検査のお姉さんと軽口を叩き、機内ではデヴィッドの子供の動画を見て笑っている。
・ポーランドに着くと、空港ではツアーの英国人添乗員が待っていて、ツアー参加者同士で自己紹介する。自適の老夫婦、裕福だが夫と別れた中年女性、ルワンダ虐殺を生き延びユダヤ教に入信した男性。そんな中、ベンジーは際どい突っ込みをしつつ、ハラハラした表情のデヴィッドは、その度に謝るのである。
・更にベンジーは、移動の際の列車が一等車である事に”ホロコーストを経験した人たちは、こんなに恵まれていなかった。”と言い、普通車に勝手に席を移動し、ツアーガイドには”もっと数字だけではなく、リアルに感じたいんだ。”と話すのである。
だが、彼の言い分は真っ当であり、ツアー参加者たちは彼の言動を容認するのである。
この辺りの描き方が、嫌味にならずに逆にコミカルに思えるのは、ベンジーを演じるキーラン・ランキンのお陰であろう。
且つ、彼が少し前に睡眠剤を飲み過ぎて大変な事になった事が有るとデヴィッドが、ツアー参加者たちに申し訳なさそうに告げるシーンから、ベンジーが大きな哀しみを抱いている事が明かされ、デヴィッドはそんな彼に寄り添えない苦しい気持ちをツアー客たちに吐露するのである。
その後、強制収容所を訪れた後、ツアー参加者たちは粛然としているが、ベンジーは一人で列車の中で涙を流しているのである。
彼の心が、人一倍清らかである事だろうと思いながら、観賞を続行する。
・そして、二人がツアーから離れ亡き祖母の家に向かう時に、ツアーガイドは”貴方の指摘は的を得ていた。”と彼に言い、ベンジーは参加者たちとハグし、デヴィッドと二人で祖母の家に向かうのである。
着いた祖母の家が、余りに普通である事に驚きつつ二人はツアー途中で行ったように、家の戸の前に石を置くのだが、それを見ていたポーランド人のお爺さんからそれを咎められ、お爺さんの息子に事情を説明するが、結局持ち帰るのである。
このシーンも何だか、可笑しいのである。
・そして、二人は米国の空港に戻り、デヴィッドは自宅にベンジーを招こうとするが、ベンジーはそれをやんわりと断るのである。デヴィッドは自宅に到着した時に、祖母の家の前に置こうとした石を玄関先に置き、ベンジーは一人家に帰る訳でもなく、空港で再び人間観察をするのである。
<今作は愛した祖母のポーランドの家を訪ねる二人が、夫々の哀しみを抱えつつも自らのルーツを旅する中で徐々に癒される様を描いたロードムービーである。
今作を観て勝手に思ったのは、ベンジーとデヴィッドは自分達の祖先が受けた仕打ちを実際に目で見て自分達が抱える哀しみはそれに比べれば大したことではないと思ったのではないかなという事と、人の痛みが分かる人間は、他者に対しても優しくなれるのかもしれないなあ、と思った作品である。
ベンジーを演じたキーラン・ランキンの、悪戯っ子の様な顔や、悲しみに暮れる顔や、自分の意志を恥じる事無く皆に告げる姿は良かったなあ、と思った作品でもある。>
不思議な余韻が残る本当に素晴らしい傑作
この作品はユダヤ人の歴史を扱っているので、重い話ではありました。
だけど自分は前向きなメッセージも含まれているなとも感じました。
この作品で1番感じたことは過去と向き合うこと。
歴史や、自分の過去と向き合うということは、未来へと繋がっていく。
この映画に出て来る、ユダヤ人の歴史。
これも歴史を振り返ることで、同じ悲劇を繰り返さない、ということに繋がると思います
また、自分自身との過去と向き合うことで成長することがあるとも思いました。
そして人の温かさもたくさん詰まっているように感じました。
ツアーのメンバーがみんな良い人で、最初の銅像のシーンや、
デヴィッドとベンジーが電車を乗り過ごした時も優しく出迎えてくれたシーンは
人の温かさが伝わってきました。
お別れのシーンは悲しかったけど、みんなの優しさが伝わりました。
劇中で、
人は完全に幸せになんてなれない
というような(間違ってたらすみません)
セリフが出てきました。
今考えてみると今まで生きてきて、悩みがなかった時ってほとんどなかったように感じます。
でもそんな時でも家族や友達、先生が支えてくれていたから大丈夫だったんだなと改めて気づかせてくれました。
ジェシーアイゼンバーグさんは演技も上手いし、こんなに素晴らしい映画を撮ることができるなんてとても凄いです。
また、助演男優賞にノミネートされたキーランカルキンさんの演技も良かったです。
特にラストの何とも言えない表情は素晴らしかったです。ベンジーにはこれから、幸せな人生を送って欲しいです。
全49件中、21~40件目を表示