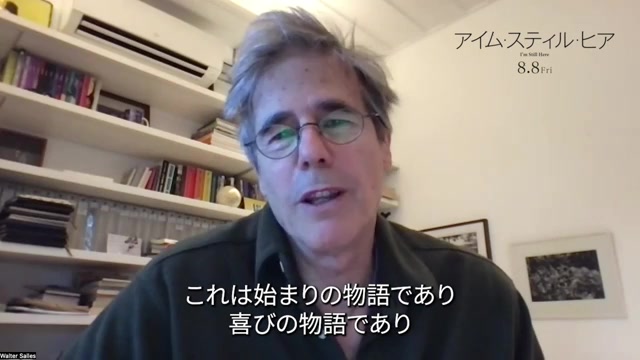アイム・スティル・ヒアのレビュー・感想・評価
全97件中、21~40件目を表示
アイム スティル ヒア
史実を元に、軍事政権下の恐怖と横暴が淡々と描かれていく。
特に抑揚も無く進んで行くストーリー。
映画としてどうかと聞かれたら、スミマセン、面白くなかったです。
テーマはわかりますが、惹きつけられる物が有りませんでした。
それでも★3なのは、世界への警鐘としての評価です。
力を持つ権力は暴走し、その暴走を肯定する為に拡張していく。
そして、自らの行いに恐れ、自らを守る為に更なる暴力を振るう。
私は戦争を知りませんが(幸運にも)、それなりに過去を学んで来たつもりです。
そして、今の世界からも。
誤解を恐れずに言いますが、やっぱり映画としては、製作陣の力不足です。
この題材なら、もっと刺さる作品にしてほしかった、率直に。
自然に涙がこみ上げる作品
1971年のリオデジャネイロ、軍事政権下で実際に起きた元議員の連行、残された妻子が歩んだ足跡を描く。
元議員ルーベンスと妻エウニセの息子マルセロ・ルーベンス・パイバの回想録が原作となる実話ベースの物語。
平和で愛に溢れる幸せな家族をしっかり描く前半部分、その後突然ルーベンスは連行され拷問を受ける。
次いで妻のエウニセも拘束され、ルーベンスの消息や生死は一切不明な中、エウニセは夫の行方を追い、軍事政権の犯罪と闘う不屈の人生を歩む。
ウォルター・サレス監督が描く、1970年代の景色が映像的に素晴らしく、弾圧がある中でも一般市民が明るい日常を送っているそのコントラストの描き方も秀逸。力強く生きるエウニセを演じたフェルナンダ・トーレスの演技は圧巻。
家族の笑顔が溢れる場面の多さが、涙を誘う。
更に実際の家族の写真を見て自然に涙が込み上げてきた。
体良くストーリーをまとめておらず、現実として、当時のブラジルの酷い国情を目の当たりにさせられる作品。撮影、演出を含め、映画としての造りが秀逸。
自分自身、圧政や弾圧とは無縁の国と時代に生まれ生きてきているが、昨今の戦争、紛争、弾圧のある国を見るにつけ、生まれ育つ国によって、人生があまりにも違ってくることを実感させられる映画。
予告編:
リベラル・プロパガンダ
アメリカ国内では、こういった反体制プロパガンダ映画が作られることはほとんどなくなった。トランプに目をつけられて逮捕されるよりも、反体制映画などはじめっから作らない方がマシと考えている計算高いグローバリストが増えているせいかもしれない。民主党がやとった“アンティファ(活動家)”が騒ぎを嗅ぎつけて暴動に発展させようとしても、地元民が怪しがって誰ものってこないらしい。オールドメディアによる偏向報道はもちろん、映画にしても暴動にしても、大衆煽動装置としては最早機能しなくなっているのではないだろか。
アメリカがダメなら今度は周辺国で、ときゃつらが考えたのかもしれないが、『セントラル・ステーション』『モーターサイクル・ダイアリーズ』等の傑作を世に送り出しているブラジル人名匠の名前を借りて、1970年に起きた誰も知らない“小さな事件”をわざわざほじくりだして来たリベラル・パヨクの狙いとは一体何だったのだろう。コロナ・ワクチンでぼろ儲けしたペド実業家がアメリカから逃げてきて日本の軽井沢に別荘を建てたらしいが、その理由を考えれば明白であろう。
免疫抑制効果抜群のワクチンはもちろん、ロシア・ゲートでっち上げに幼児人身&臓器売買、フェンタニル密輸、不法移民受け入れ…それら全てにからんできたリベラルパヨク勢力が、この映画を通じて「もう俺たちの過去をほじくりだして逮捕するような野暮なことをするな」とトランプに言いたいのであろう。映画紹介のためにSNSを通じて笑顔をふりまいていたヴァルテル・サレス監督の笑顔が、あのエプスタインに瓜二つというのは何かのギャグだろうか。
ロシアや中国では、反体制派の政治思想犯が軍にとっつかまって最前線に送り出されたり、死刑になった人体から根こそぎ採られた内臓を臓器売買に回されるなんてことは日常茶飯事だという。(本当に無実だったのかは極めて怪しい)旦那の方はともかく、たかが薄暗い刑務所に1週間程度留置されて三食昼寝付きの尋問をされたぐらい、それがどうだというのだ。その後めでたく釈放され弁護士&大学教授という社会的地位を回復した奥さんが、グローバリスト側に魂を売ったという証にしか過ぎないだろう。
何もプロパガンダの全てが悪いと言ってるわけではない。しかしなんの映画的演出も発見できない本作のような駄作を前時代的座席に座らされて長時間観させられるのは、“拷問”以外の何ものでもないのだ。過去には『カサブランカ』のような名作も生まれているわけで、パヨクもパヨクなりにもっと真剣に頭を使って映画を作らないと、アメリカ民主党や日本の自民党のように大衆の支持は受けられないということを言いたいのである。もちろん、ネズミの屁の音さえ宇宙から感知するという“エシュロン”を使えば“誰も嘘をつくことができない”、という十戒にも印されている前提条件をふまえたうえで。
家族、人間の意志の素晴らしさを感じられた作品だった。 こうだったら...
軍事政権というのは、本当にこの世からなくなればよい。明るく快活で美...
苦難を乗り越える家族の絆の実話
ブラジル軍事政権下に実際に起きた父親の失踪事件を作家の息子が回顧録として記し、ウォルター・サレスが映画化したものです。ウォルター・サレスのセントラルステーションやモータサイクルダイヤリーズのように映画としての脚色がそれほど施されてない感じで実話に忠実に作ってある40年以上にわたる家族の物語でした。父親が突然消えて、それぞれの心に様々な影響が及びます。死んでいるのか生きているのかわからない苦しみ、きっともう戻らないだろうと思ってもどこか期待してしまうのです。家族がそれぞれを思う強さと素晴らしさを教えてくれます。家族が支え合う姿に心を動かされます。自分もそういう家族を築くことができるとよかったのになと思ってしまいました。ラテンらしい家族の温かさでなくとも日本的な家族の絆で。
写真と8㎜フィルムで家族を追想しますが一枚一枚に込められる思い出は大事だとあらためて画像や動画を大切にしたいと思いました。
美しい街に起きる恐ろしい出来事
奪えないもの
137分に尻込みしてたけれどとてもおもしろかった。
声高に戦う様子は出てこないのに、不屈の精神が伝わってくる。打ちひしがれた顔で写真を撮ったりしない。
音楽の使い方がとてもいい。レコードプレーヤーから、ラジオから、ヘッドホンから、いろんなところから音楽が聞こえ、生活を彩る。
子供たちがそれぞれの年代や性格なりの感じ方で状況を捉える様子がうまい。これがこの映画を多角的にして面白くしていると思った。この子はこういう性格なんだろうなというのがちょっとした演出やセリフからうかがえる。大人になったときにもちゃんと誰が誰なのかわかるのもすごい。
写真や8ミリ映像の使い方もうまいし、文句のつけどころがない映画だった。
レジスタンスを描いた映画はたくさんあるけれど、こんなにも深く弾圧の残酷さを描いたものはなかなか思い当たらない。
暴力によって奪われたものと、暴力では奪えないものと。
収容施設が超こわい。泣いた。軍事政権側の人たちの人相がすごくてよくあんな人たち集めたなと思った。
時代や場所が違えば私も父と引き離された人生だったかもしれないなあと思い、リアルな怖さがあった。
映画の中で出てくるカエターノが軍事政権に対抗してたことくらいしか知識がなかったので、ブラジルにも酷い時代があったのだと知った。70年代、政治の季節。そんなに昔のことじゃない。
この物語はマルセロが書くことによって人々に知られ、映画になった。書くこと、記録することの強さを思う。
40過ぎて弁護士になるのもすごいし、先住民の権利擁護しててかっこいい。
ロンドンからの手紙でサウダージって言っててそういうふうにも使うんだなあと思った。
ママは凄いけど
実話・・・
若きゲバラを描いた「モーターサイクル・ダイアリーズ」の監督作品ということで鑑賞♪
ブラジルもこういう過去(つい最近かも)を経て今があるのですね・・・と言ってもブラジルの今がどれだけ素晴らしい国になっているのかは・・不明・・。
暴力、力で・・人を納得させる・・人を支配する権力には碌なものがない。思想、信条、考え方が違うだけで拘束され命さえも奪われる世界なんて勘弁して欲しい・・。一歩間違えたらそっちに転落しそうな危ういナイフリッジを歩んでいないか?今の日本・・・。
とはいえ、流石に・・単純な暴力での支配はしずらい仕組みになっているとは思うが・・随分と巧妙な暴力(言葉やお金)でマウント取ろうとする政治が、蔓延しつつあるような気もする・・。
気丈な主人公を演じた女優の実の母親も女優で・主人公の晩年を演じている。メイクにしては出来過ぎでは?と思っていた・・・どうりで似ているはずだ♪
家族から見た軍事政権の本質
ブラジルの軍事政権については何も知らず、この映画でチリのピノチェト政権と変わらない酷い政権であったことを認識させられた。反共なら何でも許された冷戦期の西半球で迫害された実在の人物の家族の視点に立つこの映画は、今再びあからさまな差別や抑圧が始まった時代に、二度と繰り返してはいけない過去に向き合わせてくれる。いきなり一家の大黒柱を失い、家財を切り売りしながらも家族を守ったヒロインの根性に胸打たれる。時間はかかったが家族の生きている間に民主化され、過去が明らかになったのは良かったが、失われたものはとても大きい。わが国も治安維持法成立から100年、他山の石としなければ。
60年代の続きのようなビートルズとマリファナの若者と軍事政権が同時にある70年代初のコントラストが強い。
闇と光が拮抗する時代と場所を描く
本年アカデミー賞の国際長編映画賞を受賞した作品である。他のノミネート作が「ガール・ウィズ・ニードル」「エミリア・ペレス」「聖なるイチジクの種」「Flow」と秀作揃いの中で堂々たる受賞だと思う。昔と違って国際長編映画賞と作品賞の同時受賞もできる。日本公開はかなり遅く今頃やっと実見したが、作品賞を受賞してもおかしくない出来だった。
ブラジルを軍事政権が支配していた1971年。軍ないしはその影響下にあった政府組織によって拉致され拷問の上殺害されたルーベンス・パイヴァ氏とその家族の物語である。
ルーベンスとエウニセの夫婦には四女一男の子供たちがいる(他にお手伝いさんと犬が一匹)だからこれは何十年にもわたる家族の物語であると位置づける解説もある。長男であるマルセロ・パイヴァ氏の著作が原作であり「家族」という視点が入ってくるのは確かである。ただ、物語の9割以上はルーベンスの拉致直後の時点に割かれ、家族の25年後の姿とさらに20年後の姿は短い尺で加えられているのに過ぎない。だから、本作は、家族の誰よりも、夫を拐われ自分も一時は監禁されて危ない目にあった妻のエウニセがまだ幼い子供たちを抱えながらも戦うことを決意するまでの経緯が中心になっている。
映画の冒頭、リオデジャネイロの海岸に住んでいるパイヴァ一家の日常を描く。裕福で友人たちにも恵まれ子供たちも明るく元気な幸せな家族である。それだけにやがて姿を現す闇の勢力のもたらす衝撃度は大きい。ルーベンスを連行する者たちは武装はしているものの制服姿ではなく一見、町のチンピラにしか見えない。リーダーは名前だけは名乗るものの所属等は明らかにせず、行動の目的も明かさない。ルーベンスの連行後にも家に居座り、妻や娘も一時的に連行する。彼女たちは頭巾をかぶせられて何処かの施設に連れ込まれ意図が不明な尋問を受ける。彼らが法的に不当であることを十分に承知しながら行動しているのは明らかであり徹頭徹尾、不気味で非人間的である。どうしようもない闇の深さが感じられる。
つまりこの映画は光と闇の対立と、その狭間にはまり込んでしまった人間の運命を描いている。もちろんブラジルの旧軍事政権に対する告発、遺族への補償をせよという主張はあるのだけど、これはどこにでも起こり得る、たぶん、今も世界のどこかで進行している人間社会の様相についての精緻な考察であるといってもよいかもしれない。
かなり重い家族愛の作品
思っていたのと違いました
恐いねえ。
奪われてはじめてわかる人権の尊さ
一見、民主主義国で憲法により人権が保障されている自由な国、今の日本で暮らしていて自分の人権が保障されていると日々実感しながら暮らしてる人は少ないと思う。
大半の人が自分の生きたいように生きることができる、自分の意思が権力により抑圧されてると感じてる人間は比較的少ないのではないか。
でもマイノリティの人々となると話は変わってくる。例えばLGBTの人々などは生きていくうえで様々な不自由を感じているだろう。
人は自分の人権が侵害されて初めて人権がいかに尊いかがわかる。たいていはマイノリティの人権が侵害されるため、人権侵害は他人事のようで社会ではなかなか問題視されにくい。
民主国家でない独裁国家でも国家に従っていれば安泰な生活を送れる。しかしそんな国家に逆らえば途端に人権は蹂躙され幸せな暮らしは奪われてしまう。
ブラジルの軍事独裁政権下、韓国の朴正煕軍事独裁政権下にも似た開発独裁の下で飛躍的な経済発展を遂げてブラジル国民の生活は潤った。
そんな経済発展に酔いしれる国民の中で民主主義を否定する軍事独裁政権に立ち向かう人々もいた。
これはかつてブラジルでリベラル派の政治家として活動していた人間とその家族の物語。
彼は軍事独裁政権に逆らう活動家を支援していたがために秘密警察に連行され帰らぬ人となる。そして事情を知らなかったその妻も長きにわたり拘留される。彼女は自分の幸せな家族の生活が奪われ、夫を奪われたことから人権の尊さに目覚めて法科に進み弁護士となり独裁政権と戦う。
長きにわたる戦いの末に夫の死亡証明を取り付けることができた。行方知れずで生死不明の夫、少なくともこの故郷のどこかの地に眠っていることだけは明らかとなった。
このリオの海岸沿いのどこかに眠る夫の亡骸は末娘の抜けた乳歯のようにいずれその在りかがわかるだろう。
夫を奪われたことから、幸せな家庭を破壊されたことから人生をかけて残された家族を守り国家権力と戦った主人公の女性の物語は現代にも通ずる物語だ。
本作の企画を監督が進めていたのがまさにブラジルのトランプとの異名を持つボルソナロ大統領就任の時期であり、彼はかつての軍事独裁政権を賛辞していた。
民主主義で自由の国であるはずのアメリカが独裁者トランプにより独裁国家に陥る危機になるのと同様、このブラジルもかつての独裁国家に成り下がると懸念しての本作の公開となった。
欧州でもいま極右政党の台頭により民主主義の後退が懸念される事態に。この日本もまた例外ではなく先の参院選では人権を否定する極右政党が躍進した。
日本もかつては百年前に制定された治安維持法の下での軍事独裁政権により多くの国民が拷問されて殺された。その被害者たちにはいまだ何ら補償もされておらず加害者が処罰されていないのもこのブラジルの独裁政権下の状況と同じである。
本作が世界的評価を得たのは、いま世界中で同様のことが起きようとしていることへの不安から、かつての過ちを振り返る必要性に迫られてのことであろう。
日本のかつての悪法、治安維持法を賛辞したカルト政党が今回の選挙で躍進した事実。まさに再び我々の人権が脅かされる事態に陥るかもしれない。
普通に人権を享受できていることが当たり前であると思えない時代が再び到来するかもしれない。
今現在平和と思われる生活が所詮かりそめのものであり、何かのきっかけで民主主義から独裁国家へとカードが裏返るようにたやすく転覆する危うさを感じる。そうでなくとも民主主義のこの国では信じられないような冤罪事件で人権が蹂躙される事態も起きている。
だからこそどんな時代であろうともつねに権力に対して訴えねばならない、「私はここにいる」と。けして権力の横暴により我々の人権がなきものにされてはならない。
軍事政権下のブラジルのヒリヒリするような空気感が封じ込められた美しくも重厚なドラマ
1970年のブラジル軍事政権下のリオで突然夫を連行されてしまった妻と子供達の物語。時代背景的にはスペイン産アニメ『ボサノヴァ 撃たれたピアニスト』と通底しているのですが、失踪の謎を追っていく『ボサノヴァ〜』とは違って、こちらは全く異なるアプローチで軍事政権下の過酷な現状を直接見せることを極力排除しサウンドトラックに語らせる。昭和歌謡もそうでしたが70年代はヒットソングが世相を反映していたのでその歌詞とメロディが時代を語るに任せて、その時代を生きた一つの家族は淡々と暮らし続ける。登場人物が多くを語ろうとしても主人公は遮る。残酷な描写は何もない。それがゆえにそこにある虐殺行為がくっきりと浮き上がる。この辺りは『関心領域』に近い感触はありますが、こちらは主人公はあくまでも現実と戦い続ける点が異なります。ずっしりと重い作品ですがサウンドトラックと風景がとにかく美しいのでやはりスクリーンでの鑑賞向き、70年代のリオの眩い風景の再現は見事ですし、曇天のサンパウロの日常がスクリーンに映し出されることはこの国では稀なので激しく郷愁に駆られました。
ところでもうこれ前から言うてることですがラテン系映画に英語のタイトル付けるなっちゅうねん。これは英題をカナ表記してるだけのやっつけ仕事なのでもうちょっと粋な邦題にしてたらもっとヒットしたんちゃうかなと思います。とはいえ主人公の目線だけがこれから起こることを暗示しているポスターは素晴らしいです。
ブラジルサッカーは隠れ蓑
お気楽な国、ブラジル。日系人が苦労し頑張った国、ブラジル。垣根涼介サウダージのブラジル。コーヒーとサンバのブラジル。しかし、こう言う黒歴史があったとは。どの国にも権力による暗黒政治があるのはある意味普遍的なことだが、本作でブラジルにも民主化前に、こう言う時代があったとは。勉強になりました。
全97件中、21~40件目を表示