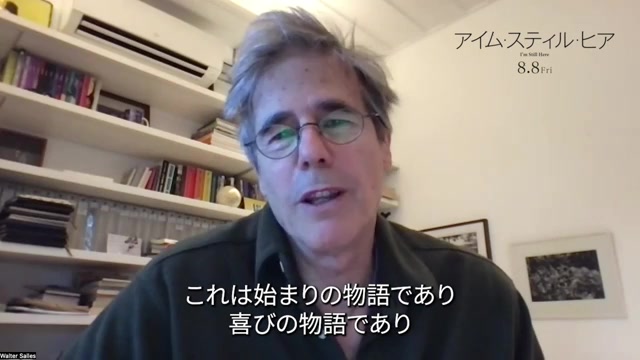「ある「小道具演出」に思わず落涙…」アイム・スティル・ヒア TWDeraさんの映画レビュー(感想・評価)
ある「小道具演出」に思わず落涙…
第97回アカデミー賞国際長編映画賞受賞を始め、数々の映画祭・映画賞で高い評価を受けた本作。私はいつもの如く、出来るだけ前情報を避けて鑑賞に至りましたが、この作品で扱われる「事件」について、ある程度は知ってから観れば良かったと思うくらい、劇中で説明されることはそれほど多くありません。(Wikipedia英語版『Rubens Paiva』の項目が参考になります)
舞台は1970年のリオデジャネイロから始まります。若者たちは欧米から届く最新の文化や流行に刺激を受け、活気があって大変に躍動的です。ところがその一方、当時のブラジルは軍事政権下であり、見上げればヘリコプター、公道には軍車両が時折見受けられ、平静時にも拘らず威圧感が拭えません。
なお、本作の主人公・エウニセを演じたのはフェルナンダ・トーレス。カンヌ国際映画祭女優賞の受賞経験もある実力派で、その演技力の高さは言うまでもありませんが、それにも増して印象に残るのは彼女の「目力」。それは「エウニセの意志の強さ」を際立たせて脳裏に焼き付き、気が付けば彼女の演技に支配されてしまいます。
また、「事件」の背景にある問題提起をしっかり訴えつつ、パイヴァ夫妻と子供たち(一男四女)の愛に溢れる「ファミリーの絆」が感じるこのストーリーは、パイヴァ家長男・マルセロ・ルーベンス・パイヴァ(小説家、劇作家、脚本家、ジャーナリスト)の自伝が原作であると知り、「事件」に対するアプローチとそ距離感について、より納得度が高まりました。
そして更に、本作に対して感情移入を助長させる重要な小道具2つ。
まずは、カメラやビデオに使われる「フィルム」。本作は3つの時代で語られる3幕構成となっていますが、物語り中に生じる距離や時間を縮めるツールとして写真や映像が多用されます。(ちなみに、本作のポスターアートやサムネイルで使われるシーンも、1幕目の冒頭において一家揃って訪れた海水浴での「集合写真の一部」)劇中、度々にある撮影機会とその時の状況、時間を経る毎の変化が一見して伝わって言葉が要りません。ただその反面、気になったのは3幕目に交わされる家族の会話シーン。デジタル化によって「データ」と化した写真について「とってつけた取って付けたようなセリフ」の数々は、急に下手くそに見えて苦笑い。。
そしてもう一つ、これは好きなシーンであるため若干ボカしますが、四女エリアナの「あれ」。1幕目、父がそれを密かに回収し、1幕目終盤で母からそれを渡され、2幕目に兄マルセロとの回想で「その時に確信した」と話すエリアナ。その当時は殆どの事を知らされることがなかった年少組の兄妹の会話と、父娘を繋ぐこの「小道具演出」に思わず落涙しそうになりました。
聞きなれないポルトガル語と、地味な作品性に正直1幕目途中頃は眠気も感じましたが、徐々に明らかになる事実と、それに立ち向かっていくエウニセと子供たちに引っ張られていつしか夢中になります。高い評価も納得な秀作だと思います。