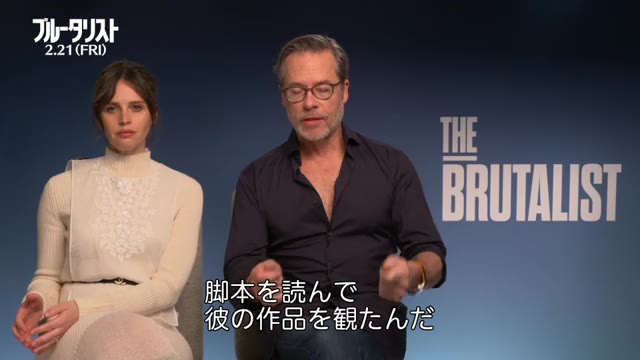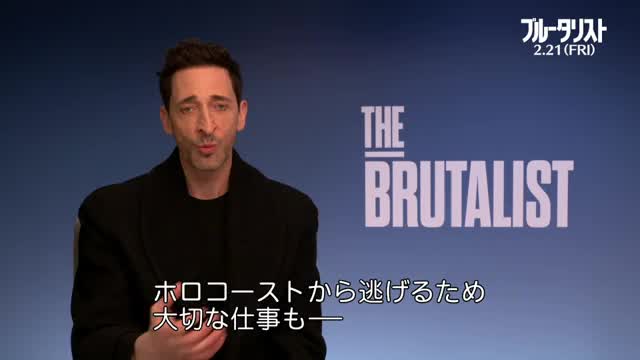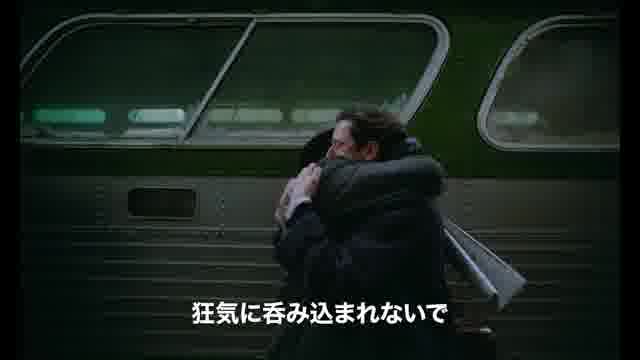ブルータリストのレビュー・感想・評価
全163件中、41~60件目を表示
リベラルかつスタイリッシュなものが好きな人向け
第二次大戦後混乱期のユダヤ人建築家の話なので、政治色、リベラル性が強く、今の保守に寄ったアメリカに警鐘を鳴らしているような作品でした。
そして、映像がかなりスタイリッシュ。
要は「通の好む」作品で、こういうのが賞を獲るんですよね。かなり長い(途中で休憩あり)のと娯楽性の少ないものでした。
僕はこういう「雰囲気」も嫌いではないので、楽しめましたが娯楽作品が好きな人は避けた方が良いでしょうね。
3時間半の長さを感じない隙のない大作ですが、唯一の隙と言えば、主人公の光と影、トラウマを描きたかったのか、女性の扱いがぞんざいというか、性的なオマージュにしか使ってない印象で、そこが残念でした。
時代がそうだったのかも知れませんが、わざわざこのシーンいるかなぁ?というのがいくつかありました。
皆さまのレビューで本作の価値観が大きく変わりました。ありがとうございました!!
あくまでも個人の見解ですが、映画は大衆娯楽ですから、あまり難しく考えるのは苦手です。
それでも、この作品に限っては最低限の予備知識を持ち、漠然とでよいので、主人公の出自、生き様、感情に思いを馳せるとより楽しめると思います。
よって、知識吸収のため、これまで以上にレビュアーの方の感想を丹念に拝読いたしました。
本作鑑賞の際にたいへん参考になりました。深謝いたします!!
【私の最低限の予備知識】
・本作はユダヤ人ラースロー・トートが主人公
・演じたエイドリアン・ブロディもユダヤ系(ハンガリーの血も流れている)
・ホロコースト(ユダヤ人迫害および大量虐殺)とシオニズム(イスラエル建国)
・ユダヤ教と基督教(プロテスタントとカトリック)。シナゴークと基督教教会
・戦後のハンガリーから逃避した米国(ペンシルベニア州、フィラデルフィア)が舞台
・R15+の制限。暴力、性描写、麻薬摂取などのシーンがあるので中学生以下NG
・日本語コピーは「荒ぶる、たぎる」。主人公の感情の起伏を表現したものでしょう
・建築家の「半生」を描いたヒューマンドラマ。215分長尺映画。覚悟が必要(笑)
・皆さまの素晴らしいレビューの数々
で、鑑賞後は、エイドリアン・ブロディの演技力に驚嘆しました。
ゴールデングローブ、オスカーの受賞、当然の結果ではないでしょうか。
以下、ラースロー・トートの出自、生き様、感情について。
真珠湾以外に攻撃を受けなかった米国は建設需要は少ないはずで、ラースローは、建築家としての勲章は捨てたのだなと。それでも米国を目指したのは、ホロコーストから生き残ったことで、何よりも自分自身や家族の命と精神的な自由を求めることを優先したのかなと。
生きているだけで儲けものと思っていたところ、わらしべ長者的なラッキーが重なり、当然、人間としての欲が出てきます。芸術家としてのプライドやそれによる葛藤が生まれ、それまでは穏やかな性格で他人との衝突は無縁であったのが、時として無碍にエキサイトするシーンがインサートされます。
米国上陸直後の娼館を出たときに、タバコを燻らす娼婦から掛けられた言葉で彼の性癖は〇〇かも?と。その後、性的なシーンがいくつかありますが、ラースローの苦悩を表現するような表情のカットが印象に残っています。♂としてダメなのでしょうね。妻エルジェーベトとの関係性にも大きく影響しているように思います。
芸術家気質ゆえの繊細さでしょうか? アル中(?)、ヤク中(?)も加わります。
このバックグラウンドと誰にもわかってもらえない孤独を演じるブロディの姿は、私の素人眼に強烈なパンチを喰らわせましたね。
半生ですから、老後もあるのですが、自由発想で。私は、家族仲良く穏やかな時の流れをイメージしました。
以下、作品と撮影、音楽について。
やはり、同じ時代設定のゴッドファーザーを思い出さずにはいられませんでした。
コッポラもラースローのセリフと同じようなことを言ってましたよね。
コルレオーネ・ファミリーがニューヨークで暗躍した同じ時代に、やや西側に位置するフィラデルフィアとペンシルベニア州の田舎町(ロケ地はハンガリーか?)を舞台にストーリーは展開します。
ただし、超有名なフィラデルフィアのロケ地(ロッキーステップ)は、残念ながら登場しません。
シークエンスの切り替え時に車載カメラが捉える道、空、道沿いの緑が印象的です。
おそらく、ラストメッセージの伏線でしょう。
驚いたことに15分間のIntermissionがあります。歌舞伎じゃあるまいし・・・。
たぶん、配慮に見せつつ演出ですね。
なぜなら、休憩時間にスクリーンに投影されるポートレートが意味を持っているからです。多くの方がトイレに席を立つでしょうが、よく観ておくことお勧めします。
撮影班、ロケ地の素晴らしい景観も奏功してとてもよいです。AI画像も自然に思えました。
カット割りと音楽のシンクロ、カッコイイと思います。時代に合わせた選曲もグッドです。
ただし、スタッフロールだけは面食らいました。何があったの???
プリプロ(脚本、コンテなど)もポスプロ(編集など)も観客心理を考え抜いた結果の大作でしょうから、製作側にとっては、一欠けらのミスもないのでしょう。恐れ入りました。
おまけ。
ガイ・ピアース、いいなあ。L.A.コンフィデンシャルの頃から好きだなあ。
オスカー取らせたかったなあ。
アメリカでのユダヤ人 リアルすぎるフィクション
映像が素晴らしくどのカットも見応えがある、誰かが言ってたどのカットをTシャツにしてもいい映画とはこのこと。
音楽も素晴らしく、作品の憂鬱感と壮大さを反映していた。
休憩時間に入ってもらったパンフレットを読むまで実話に基づく伝記映画の類だと思っていたので、完全なるフィクションだとわかった時はすごいびっくりした。第2篇からフィクションだということを意識すると、映画のリアリティのあまり、気持ち悪ささえ感じた。何年かけて構想したんだ!?
アメリカの白人富豪達はどんな人種でも実力は十分に認めてくれ、仕事させてくれるが、やはり人として下に見てくるんだなと感じた。
にしても、この映画は決して差別される側に甘い訳じゃなく。アメリカにいるユダヤ人達の被差別意識をやんわり批判し、シオニズム運動という名の幻の居場所探しもネガティブに表現されていたと思う。
この映画はとてもデザイン性、アート性に優れていて、好きな人はとことんすきになる映画だと思う。私はまあまあ好き、でももう1回最初からは観たくない。
有識者に教えて欲しいのだが、人々がぞろぞろ丘に登るシーンはなにかのオマージュなのでしょうか、バビロンでも観たことがある構図だったので気になった。
もしかして一番最初らへんのゴジラ?
映画館で観る長尺映画が大好きです。 家とかスマホでは味わえない良さ...
余韻ブレイカー
真実の重みを感じたかった
ハンガリー出身のユダヤ人建築家、ラースロー・トートは大戦中のホロコーストを生き抜き、戦後アメリカに渡った。彼は生き別れた妻を苦労の末に呼び寄せ、困難と闘いながら米国で再び建築家として成功する―。
本作は、そう描いているがトートなる建築家は実在せず、まったくのフィクション、作り話である。しかし、その「事実=物語は事実あった話を基にしたものではない」を知らないまま映画を見ると、よくできた話に引き込まれ、なかなかによくできた映画だ、と思った。
鑑賞後、調べてみるとそんな建築家はいないということを知り、なんだか白けた感じ、だまされたような気分になった。
映画は「お話」でしかない、それを味わえばいいとうのであれば、これはこれでいいとも思えるのだが、事実を基にしたフィクション、登場人物は本当に存在した人であれば物語にもっと重みと手触りを感じたと思う。
つまり、監督、脚本家―作り手―の都合に合わせたホロコーストをサバイブしたユダヤ人というある意味で類型的なドラマになっただけ、という点にどうにも軽さを感じた。
オスカーを獲得した主演のブロディの芝居は過不足なく登場人物になりきった名演なのだろうが、それがきれいにはまりすぎている点に飽き足りなさを感じた。
オスカー3部門を獲得した作品だけに、それをチェックしたい人は見ればいい。だが、そういうこだわりを持たないのであればわざわざ休憩時間まで設定された長尺作品を見るほどではない。
東京都心のシネコン、平日昼間の入りは3割ほどか。あまり観客からも熱を感じなかったのは、ぼくと同様な印象を持ったからではないか、と勝手に思っている。
にしても、戦後80年の今年、日本映画でそれをテーマにしたようなものはないのだろうか。
昭和のはじめから戦中戦後をはさんだ30年くらいには、現代人には想像できない数多のドラマがあったはずだ。もちろん、昭和50年代以前にはそうした作品もあっただろうが、21世紀の今、再びそういうものを撮ろうとする映画人はいないのだろうか。
逆自由の女神は逆十字架
劇中にも出てくる建築ビエンナーレの展示作品のような映画だ。
映像や音、構成において、芸術的かつ実験的な手法を駆使しており、
IMAXで、
教会の建築シークエンスから、
【もっと光を】のシーンは観る者に一種の美的衝撃を与える。
ストーリーテリングは、
もちろん典型的なエンターテインメント映画とは一線を画している。
物語の中心には、主人公ラースロー(ラザロの復活とは無関係ではないだろう)のブルータルなパッションがひたすら描かれ、
彼の内面の葛藤や欲望がそのまま視覚的に表現されていく。
登場人物やストーリーの論理的な繋がりを可能な限り削ぎ落とし、
感情の爆発を直接的に伝えるスタイルが、
アート映画の枠組みを超えて、A24らしい独自の力強さを持つ。
映画の中盤で挿入されるインターミッションは、
この作品の特異な構成(ブルータルな建築のような)を象徴している。
100分が経過し、
急転直下でアメリカスティールの歴史が怒涛のように展開され、
観客は一瞬の休息を得ることになる。
劇場の照明がアップし15分の休憩、
効果音で観客の感覚をリセットさせた後、
再び映画は加速する。
この緊張と緩和のリズムは、
視覚的な印象を強烈に残し、
観客の感情を揺さぶり続ける。
色調においてもカメラは常に変化し続け、
シーンごとに色調やフレームが変化するのはA24作品ではおなじみだ。
特に60年代ハリウッド映画風の色調が際立っており、
4原色でいうとCMYKの「Y(イエロー)」を強調した映像が印象的だ、
しかし、A24らしい転調の連続でY好きな観客は消化不良化かも。
色のトーンが一瞬で変わることで、
観客はその予測不可能性に引き込まれるのも、
狙いなのかもしれない。
ガイ・ピアースが演じるキャラクターは、
作劇の観点ではあり得ない展開を見せるものの、
文学的な解釈の下では非常に魅力的である。
そのキャラクターの存在自体が、
映画全体のテーマにうまく溶け込んでおり、
観客にとってはその不条理さこそが魅力となり、
映画製作そのものをイメージする人もいるだろう。
逆自由の女神は、
ワイダの逆十字架、
山の端シルエットは、
ベルイマン、
巨大建築物を引いて、
小さな存在にみせるのは、
ダヴィアーニ兄弟のカメラと、
美術、
カメラは名機ARRI435を使用はスピルバーグか、
昨今流行りの、
プリントに白パラ(白いゴミ)。
本来は白は技術的なミス、
黒は何度も映写されている証し、
ビエンナーレの狙いであればよし・・か・・
そういうのは風化していくのだろう・・・
他もいろいろ。
天才建築家と傲慢なパトロンの確執…という「フォックスキャッチャー...
天才建築家と傲慢なパトロンの確執…という「フォックスキャッチャー」的なストーリーよりも、建築そのもの(とその建造過程)こそがこの本作の主役。それぞれに悩みや欠点を抱えてドロドロとした人間模様を遥かに見下ろし、大地に屹立する建築の、なんと荘重な姿!作中で建築家の理想、として掲げられる以上の偉容で、抜群に決まった劇伴も相まって、この3時間超のドラマを一瞬も弛緩させない迫力に満ちている。冒頭の移民船の狭苦しさから、外へ出て目にする逆さまの「自由の女神像」のシーンが示すように、緊張と解放、明暗のコントラストが凄まじい。冒頭は左から右へ、終幕ではななめに流れるスタッフロールも実に洒落ている。おそらく前述の理由で人間ドラマとしては敢えて描き切っていない部分もあるが、ガイ・ピアースの暴君ぶりは劇中随一の怪演として褒め称えられるべき。
な、ながすぎ…
私にはピンとこない映画やったなあ。前評判でアカデミーを狙いすぎとか言われていたが題材からして確かに意識しすぎなのかなとは思う。
上映時間脅威の215分。絶対にお手洗いいきたくなるやん!何考えてんねん!なんて思っていたが100分くらいで15分休憩が入るのでトイレ心配な人はご安心を!
3時間を超えるような長い映画はこの映画のように休みを入れてくれるとほんとにありがたい🙏
物語冒頭は収容所から無事脱出した後のシーンからスタート。アメリカンドリームに期待する主人公。収容所での困難はおそらく時間の問題で入れられなかったのかな?アメリカに渡った主人公に困難が…とか思いきや割と幸運が続き責任ある仕事を任せられることとなる。仕事の重圧とハリソンとの不和によりラースローと妻の間には歪みが生じていく。序章、第1章まで物語に入り込むことが全くできず関係ない仕事のことを考えていた。2章の妻エルジェベートの出演開始くらいからようやく集中。フェリシティジョーンズの夫思いで苦しみを抱えた妻役、熱演やったなあ。
ほぼ4時間という大作ではあるんやけど物語の緩急がほとんどないため眠気に負けそうに(1章あたりは負けました)
今回主演男優賞でノミネートされていたのは実在の人物を演じた人たちが多かった!
ボブディランに扮したティモシーシャラメ、トランプ大統領を演じたセバスチャンスタン…ラースロートートは実在の人物かと思っていたがフィクションだと知り驚き。皆さん熱演には違いない。
ただ、このラインナップみるとどうしても主観バリバリでセバスチャンスタン(トランプ政権化ではとれないよね)やティモシーシャラメよかったやん…ブロディ、戦場のピアニストで取ってるからええやんなんて思ってしもた🙄
ユダヤ人建築家ラースロー・トートの半生を通してアメリカの闇が見え隠れする秀作
初のIMAX鑑賞です。なぜ今まで見てこなかったかというと料金が高いからです。そしてなぜこの作品をIMAXで見たかというと都合の良い時間はIMAXしか上映がなかったからです(笑)
エイドリアン・ブロディのアカデミー主演男優賞受賞に納得の作品でした。215分の長尺に尻込みしてましたが、途中休憩が15分あり、内容的にも映画に没入でき上映時間は全然気にならなかったです。リアル・ペインもそうでしたがこの作品もホロコーストを内包した映画でした。なんだか最近多いように感じます。
1951年ホロコーストを生き延びたユダヤ人建築家ラースロー・トートはブダペストからアメリカに渡るが、そこは決して安住の地という訳ではなく苦難の連続で…というお話で、昔から建築に興味のあった私には興味深いお話でした。
入場時に「建築家ラ―スロー・トートの創造」というリーフレットをもらったので、てっきり実在する建築家かと思ってましたが上映後調べてみると創作だったことに驚かされました。ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展とか実際にある祭典まで登場するので、リアリティを追求する徹底ぶりがすごい。それに加え、エイドリアン・ブロディの迫真の演技。
映像美も随所に感じられました。画面構成など美術センスも良い映画だなあと感じました。
大理石の白い採石場のシーンも印象に残りました。
ラースローは結局実業家ハリソンに振り回され続ける訳ですが、この富と権力を振りかざす嫌な人物がまるでアメリカを象徴するかのような人物として描かれているのですが、昨今のアメリカとシンクロするようでそれはそれで恐ろしいと思いました。
ホロコーストの影響で骨粗しょう症になり歩けず痛みの発作に苦しめられる妻エルジェーベト。
話すことができなくなってしまった姪のジョーフィア。
そしてラースローはドラッグ中毒から抜け出せない。
しかし、ハリソンにとっては所詮他人事なんです。
彼にとっては富と権力と名声が大切なのであって、それ以外には関心がない。
逆に鉄道事故などでそれらが脅かされたときには平気で雇い人をクビにし、とにかく自己保身が最も重要といわんばかりの行動をみせる。
もっとも許せないのはラースローの才能に嫉妬し支配欲に駆られ〇〇〇するところです。
妻エルジェーベトがハリソンの屋敷に単身乗り込み告発する場面は見応えありました。
そして行方不明になったハリソンを捜索中にラースローの設計したコミュニティセンターの教会の天窓から月の光が差し込み十字架が映し出されるという見事なオチ。
大作だけあって中身の濃い映画でした。これはこれで一大叙事詩ですね。
しかし、実業家ハリソンという人物を通して現在のアメリカの闇が見え隠れしてしまうとは、結局のところそれが主題なのかもしれませんね。
今のアメリカは決して自由の女神に象徴されるような自由な国ではないのだと。
長い割に全く面白くない
暗い、長い、抑揚そんな無い、ノンフィクションじゃないらしい、内容濃くもないわで別に3時間半もかけて観るような内容じゃないな
という評価です。
感動も興奮も何もありません。
もっと時間削れるし、
もっとテンポ良くできるし、
もっと盛り上げれるんじゃないですか?と見ていて思いました。
そんな面白くありません。
「重厚」だが「浅い」のでは?
自分の人生を建築物に取込
完璧すぎて、少し息苦しいかも。
お尻がブルータル。
3時間20分あるから椅子の良い映画館を選ぶべし。
全く実在しない人間をよくここまで史実のように描けたなぁと驚愕する。たぶんそういう裏テーマで制作してだんだろう、脚本がすごいのか役者が凄いのか監督が凄いのか、、、全部か。
しかしぶっちゃけまいどのユダヤネタ映画なのでホロコーストや収容所の辺りはまだ分かるが、当時のアメリカでの風当たりや宗教的な異端視など不勉強な日本人にはピンとこない部分が多い。という訳で自分が完全にこの映画を楽しめてない事が残念である。
もう一つの軸は支配階級と下級市民、そして才能という物への羨望ってなかんじ。
話は大戦後生き残り才能あるユダヤ人の上がったり下がったり人生なんだけど、なんか後半の石切場のくだりが無理やりで唐突でイヤな感じがしたんだが、昔「パピオン」だったか「バーディ」だったか見た時に侮辱の仕方としてのレイプという存在が有ると知ったんだけど、それだったのかなぁ、、、。
あと最後の回顧展での説明は何だか設計思想が急に矮小化された感じがして残念に思ったなぁ。もっとスマートに中盤とかでやる事は出来なかったのかな?
音楽はその時代に合わせた作りになってるせいで最後がチャラい、、、と思ったら関心領域的後半無音、、、
どうしたいんじゃい!と思った。
あ、あとバウハウス出の主人公だからオープニングとエンドロールのタイトルデザインがカッコよい、マネしたい。
スクリーンから緊張感が伝わらない。
アカデミー主演男優賞おめでとうございます。
3月の寒い朝、映画館に入りインターミッションもある長尺の作品を観たら冷たい雨は雪混じりに変わっていた。ハンガリーに生まれホロコーストを生き抜いたユダヤ人のラースロー・トートの物語だったので、彼はもっと寒い思いをしてきたんだろうなぁ、。とか思い家に帰ってから、映画館で渡された小冊子を観たら、最後のページの下に小さく「本編の内容は一部を除きすべて架空の内容」とあった。色々検索したら実はフィクションでしたのオンパレード。
実話感たっぷりの映画だったので、戦禍の中のホロコーストの画像は無くてもユダヤ人の苦難が想像できたし、最初の図書館や丘の上のコミュニティセンターの建築の様子は実在するブルータリズムなんだな、。とか思ってました。
壮大な歴史物語で色んなものが詰まっているが、観客に突きつけたいものが何なのかが凡人の私にはわからない。もう一度、ちゃんと見直してみてから考えてみたい。
本日がオスカー発表日、作品賞は逃したがエイドリアン・ブロディは主演男優賞を獲得。歴史に名を刻んだ作品となった。
全163件中、41~60件目を表示