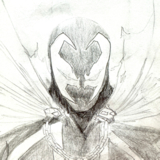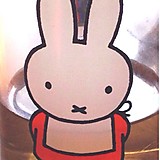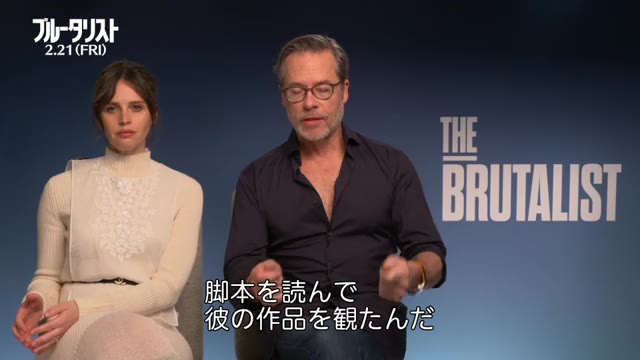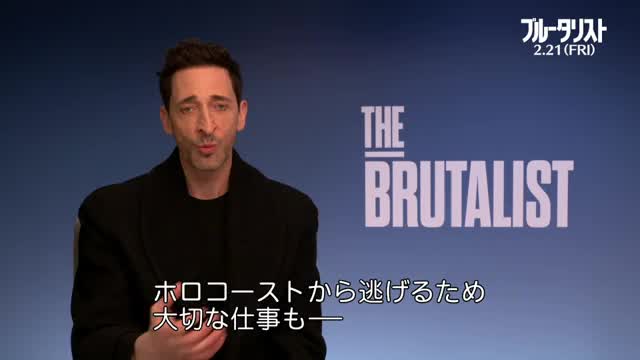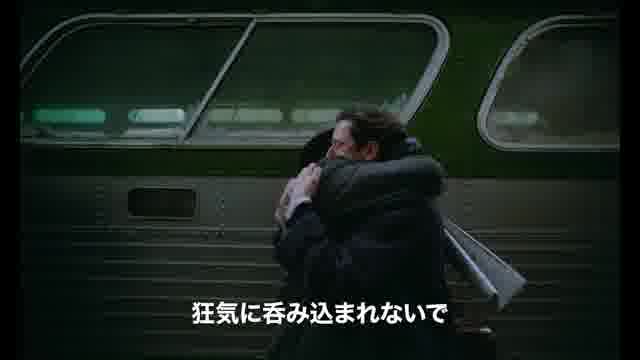ブルータリストのレビュー・感想・評価
全208件中、141~160件目を表示
クソクライアント二モマケズ
上映時間にビビってる人もいるかもですがインターミッション効果もあり、「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」や「ボーはおそれている」よりも全然ラクに観れました。
ただ正直、面白い映画ではありません。
ホロコーストを生き延びた主人公が新天地でも苦労の連続です。クライアントは親子でゲスいし、プロジェクトは度々頓挫します。当然、酒やドラッグに溺れます。
でもどんなに弱ってもプロジェクトに関しては絶対に信念を曲げないんですよね。彼はそこまでして何をつくろうとしているのか?というのがこの映画のキモだと思います。
自宅で食事中にちょっと険悪な雰囲気になるシーンがあるんですが、そこで「ごめん言い過ぎた」「いや私の方が悪かった」「僕もすまん」みたいなやりとりがあって、みんなちゃんとあやまっててえらい!という気持ちになりました。
腐った国
ダッハウ強制収容所で生き延びたハンガリー出身の建築家ラースロー・トートの渡米後の話。
ニューヨークに上陸し、フィラデルフィアでカスタムメイドの家具屋を営む従兄弟の世話になっていたラースローが、実業家ハリソン・ヴァン・ビューレンの息子に、父親の書斎の改装を頼まれて…まさかのそんな展開!?からの従兄弟とその嫁からのキツイ仕打ち。
そしてそこからまたもやまさかの流れでハリソンと再会となり展開して行く。
インターミッションを含んで計215分という長〜い作品だけれど、もったいつけたり無駄に引っ張ったりという感じがないから見応えありまくりで、冗長さは感じず。
エピローグ前のラストは結構衝撃的だし、寧ろ駆け足でそこからどうなったか端折られていて物足りなく感じるし。
その世界では有名なのかも知れないけれど、全然知らない人の伝記で、ホロコーストがなんちゃらをみせる訳でもないのになかなか面白かった。
建築家と差別する資本家
実話だと思ってみてきたのですが、皆さんのレビューを読んでびっくり。騙された感が膨らんだワタシです。想像か!!
トートさんの建築デザインは斬新でインパクト大。
凡人はつい経費を計算するし、デザインをイメージできない。建築家は施主を満足させる話術だったり、共に働く人と協調性がないと完成にこぎ着けない。
収容所から解放されてようやくアメリカに来たのに、ユダヤ人だからと差別されるのは、本当に苦労の日々だっただろうと思う。
トートが金融マンだったら、ここまで苦労することはないかったのではないか?
結局、アーティストである建築家は、人のお金で建物を建てるので、今も昔も変わらず雄弁でないと生き残れないのではないか?
ラストに収容所をイメージして建てた教会と説明してたけれど、脈々と負の連鎖を残しているのではないかと不安になった。反面教師と言う教えなのかなぁ?
何かありそうで何もない
本作で1番良かったのはインターミッションでした。
215分の大作。途中休憩のインターミッション15分付きという往年の格調高い映画のような風貌で、とてもワクワクしながら観賞。
デザイン性の高いオープニング、逆さまに画面に映り込む自由の女神("不自由"な国アメリカへようこそ!の意味か)、建築の力強さを体現するようなチェロとピアノのミニマルで極太の音楽、これまたデザイン性の高い斜めに進んでいくエンドロール。カッコいい!!
しかしそれだけの映画だった。
私も建築士として仕事をしており、この映画は色んな意味で楽しみにしていました。
主人公は架空の建築家だが、ナチスによって閉鎖された世界初の建築専門の学校「バウハウス」出身ということで、同じくワルター・グロピウス、ミース・ファン・デル・ローエの歴代校長2人がドイツからアメリカに亡命し、アメリカの建築史に多大な影響を及ぼしたことを思い出した。
そんな実在の建築家の半生を追っていく伝記映画風なのだが、実在の人物ではないのこの映画がどこに向かっているのか全くわからない。
移民問題の描き方にも新鮮味はない。イスラエル、パレスチナ問題に踏み込むなら名作になったかもしれないがそうではなかった。
また、肝心の建築や家具描写も薄味で残念だった。ラストのネタばらしも蛇足に感じた。言葉だけで説明するとは。
資材搬入中の事故で取り乱す実業家やそれが理由で計画自体がなくなってしまうというのもあまりリアリティがない。アメリカの超高層ビルの建設で一体幾つの事故があっただろうか。極めて現代的なコンプライアンスをもった実業家だった。
しかし、そこをエイドリアン・ブロディ、フェリシティ・ジョーンズ、ガイ・ピアーズの好演で中身のないキャラクターに何とか説得力を持たせていて流石だと思った。ここは素晴らしかった。70㎜フィルムで撮られた映像も綺麗だった。長回しの演技の見せ場もあり、こういった映画はやはり残っていって欲しいと思う。1.5倍速でなんて観られてたまるか!
監督のブラディ・コーベットさんは俳優でもあり人気ドラマシリーズ「24 -TWENTY FOUR-」のジャック・バウアーの娘キムの恋人役。
こんな立派な映画を撮るお方になってしまうとは。
名作なのか???
まず、観る前に驚いたのは上映時間の長さ。
「え、4時間近い!?」
最近は映画観ながらウトウトしてしまうことが珍しくなくなったので、それがまず心配に。半分ビビりながら、いざ観始めるとなんと最初に「INTERMISSIONが有ります」の案内画面。INTERMISSIONは俺的には「午前十時の映画祭」で観た“風と共に去りぬ”以来。最近ではほとんどないので驚いた。
結局100分+休憩15分+100分ということが分り、ちょっとホッとした。映画2本続けて観る感じ。これなら俺には珍しくない(笑)
【物語】
ハンガリー系ユダヤ人建築家ラースロー・トート(エイドリアン・ブロディ)と妻のエルジェーベト(フェリシティ・ジョーンズ)、姪のジョーフィア(ラフィー・キャシディ)は第2次世界大戦下にナチにより引き離され、別々の強制収容所に収容される。3人ともなんとか生き延び、ラースローは別れ際に妻に言われたとおり、アメリカに渡り、従妹を頼りにフィラデルフィアで生活を始める。
アメリカでも建築家としての才能を生かそうと、最初の仕事を独断で仕事を進めるが、オーナーである大実業家・ハリソン(ガイ・ピアース)に罵倒されクビになる。しかし、オースローの建築家としての実績、世間的評価に後になって気付いたハリソンはオースローを呼び戻し、彼の野心的プロジェクトである町の象徴となる巨大建造物の設計・建築をオースローに依頼する。
またとないチャンスとして全身全霊でその仕事に取り組むオースロー、またハリソンの人脈により難航していた妻と姪の渡米も実現する。オースローは人生が好転して来たと喜ぶが、価値観の異なるアメリカ人たちとの仕事や異国での生活は苦難が待ち受けていた。
【感想】
観賞後に知ったことだが、本作はヴェネチア映画祭やゴールデングローブ賞の受賞作品とのことで、映画のプロの間では高く評価されているらしい。が、残念ながら素人の俺には全然響かなかった。俺にはまだまだ映画観賞眼が無いことを突き付けられたようなものだが、良く思えなかったのだから仕方ない。
まず、とにかく重苦しい。特に音響効果が、重々しい曲が多い。また、作品展開的にも、ホロコーストの苦難から始まり、新天地アメリカでの苦労までは重くて仕方ないのだが、ハリソンに見出されて明るい未来が見えて来来たところでINTERMISSION。 なんか気が晴れた感じで休憩を過ごし、後半が楽しみになった。 なのに、後半またまた重苦しい展開に。
作品の長さも有り、最後はすっかり疲れてしまった。
作品の作りから(特にエンディング)、ラースローはてっきり実在の人物だと思ていたが、観賞後に調べたらフィクション。それにもビックリ。実在の人物と思って観ていたので、「最後にもっと作品紹介や偉業の紹介を入れればいいのに」と思ったが、その謎は解消。
しかしフィクションだとすると、終盤に展開されるラースローの妻がハリソン邸に乗り込むシーンも「実際に何かいざこざが有ったのか」と思って観ていたが、フィクションだとすると「あの展開必要だったのか?」と思うし、真相がどうだったのかハッキリさせないボンヤリした描写にも不満。
いずれにしても、万人が楽しめる作品ではないと思うし、3時間以上の長丁場なので、これから観る方は覚悟の上、ご鑑賞下さい!
ケガされた到達点
ブルータリスト
バウハウスと言えば、
カンディンスキー
パウル クレーなどの絵画を浮かべる。
絵画は大した費用を要しないし、
彼等の作品は室内絵画なので安価な費用で済む。
でも建築になるととんでもない費用が必要なので、どんな高名な建築家でも、施主やパトロンが必要となり、彼等から何度も設計変更、意匠変更や素材変更など幾らでもやり直しされ、更に枕営業もあるだろうな。
これは、人種や民族、宗教などの差別ではなく、費用が高額で、施工期間が長いための惨劇が生じるのは当然のこと。
映画程度でも同じような悲劇が常態として生じてそんな裏話をよく耳にする。
そんなことを今更、3時間半も、あることを元ネタにして見せるような話ではないように思う。
知らんけど…
何が言いたいのかわかるけど、
まあ、中東のリビエラ建設だけはやめて欲しい。
でも、ハリウッドはそんな所らしい。
この映画がアカデミー10部門ノミネートなんだから、それこそ怪しいわ。謎です。
(^ω^)
ブルータリスト
「戦場のピアニスト」のエイドリアン・ブロディが主演を務め、ホロコーストを生き延びてアメリカへ渡ったハンガリー系ユダヤ人建築家の数奇な半生を描いたヒューマンドラマ。
2024年・第81回ベネチア国際映画祭で銀獅子賞(最優秀監督賞)を受賞し、
第97回アカデミー賞でも作品賞ほか計10部門にノミネートされた。
ハンガリー系ユダヤ人の建築家ラースロー・トートは第2次世界大戦下のホロコーストを生き延びるが、妻エルジェーベトや姪ジョーフィアと強制的に引き離されてしまう。
家族と新しい生活を始めるためアメリカのペンシルベニアに移住した彼は、著名な実業家ハリソンと出会う。
建築家ラースローのハンガリーでの輝かしい実績を知ったハリソンは、彼の家族の早期アメリカ移住と引き換えに、あらゆる設備を備えた礼拝堂の設計と建築を依頼。
しかし母国とは文化もルールも異なるアメリカでの設計作業には、多くの困難が立ちはだかる。
「博士と彼女のセオリー」のフェリシティ・ジョーンズが妻エルジェーベト、
「メメント」のガイ・ピアースが実業家ハリソンを演じた。
「ポップスター」のブラディ・コーベット監督がメガホンをとった。
ブルータリスト
劇場公開日:2025年2月21日 215分
タイトルなし(ネタバレ)
215分の上映時間で前半100分インターミッション15分後半100分でちょうど間を空けて映画2本観る感じで思っていたよりは観やすいかなという感じでした。
前半の王道的な作りからとっ散らかった後半はホント違う映画みたいでしたが。
ラストの旅路より到達点が大事という姪のセリフは、ハンガリー訛りのアクセントの修正にAI使ったのが問題になってるけど出来たのが傑作ならいいんでしょ、というこの映画の関係者の今の本音を予言してるみたいで面白いですね。
新美の巨人たち?
建築とホロコーストの組合せはとても斬新
戦後なのにあの書斎はえっ、とてもオシャレですよ?と思ったけど当初は通じなかったようで
ペンシルバニア州の繁栄やその後のユダヤ人の生活なんかも意外だった 信心深いからやっぱり馴染めない人達もいたわけで
夫婦間のことは助長に感じたけど、長い割にはその後のあの人はあらら?
とはいえ丘の上のコミュニティセンターが無機質な理由は成る程と思ったし、建築関係のストーリーは結構好みなのでもうちょっといろいろ建物出てきて欲しかったけど結構興味を引かれて見ることが出来た
追記:かなり濃い、緻密なお話で実在のモデルはいるらしいですが壮大なフィクションですって!
凝ったデザイン
実在の人物を基にした作品かと思ったが、架空の人物なんですね。
最初のキャスト紹介が横にスクロールする。最後のエンドロールは斜めにスクロールする。
タイトルの文字も凝ったデザイン。主人公が素晴らしい才能の建築家だからでしょうか。
途中休憩を除くと200分の長尺だが、ストーリー面白いので長いと感じることはなかった。
最後は何かあっけなく終わった感じ。
とても長い映画でしたが、面白い構図のシーンが連続し、曲のセンスも良...
途中、15分の休憩が有り助かりました。 「シンドラーリフト」も長い...
エロシーン多し、カップルで見に行ったら気まずくなる
ユダヤ人のホロコーストを題材にした映画やドキュメンタリーはよく見ていて、この作品もその系列かと思ったら全く違っていた
(ホロコーストを生き延びた家族の再会までの、感動と涙のストーリーを期待していた)
冒頭、ニューヨークに向かう移民船の中の混乱から、船外に出て港の自由の女神像がアーティスティックに画面に映り込むシーンまでは、カメラアングルや、混乱の映像と台詞に主人公のバックグラウンドが盛り込まれていて斬新な映像でしたが、下船後?となった
新大陸での最初の夜、主人公はあどけない面差しの娼婦を買う。エイドリアン・ブロディの下半身がチラッと映り込む上、仕草もモロで際どいし、初めに身を寄せた従兄弟の家具店の妻も思わせぶり
インターミッション(15分)の映像がいいというレビューもあったし、別にトイレに行きたくもなかったので、そのまま座っていたが、主人公夫妻の結婚式の写真の真ん中に15分のタイマー表示があるだけ
【補足】満席に近いIMAXシアターで鑑賞、八割くらい席を外されたけど、皆さん再開までには戻って来てました。トイレタイム、是非取りましょう☆
後半主人公の妻を呼び寄せることに成功しますが、この二人の夜のシーンが生々しい。カップルで観に行っていたら、気まずいこと請け合い。他にも地上波放送するなら当然カットされそうなシーンがチラホラ、映倫はここはスルーなの…?ラスト間近にも夫婦でそういうシーンがまたあって、ホロコーストの経験者は性に障害が出るんだというテーマの映画なのかと、悶々とする
家族離合の話でもないし、現代建築を構築するアーティストの困難さを描く話でもないし、施主一家の話といってもバリューが割かれてないし、シオニズムがベースにあるけどあくまでもベースで、ストーリーにさほど影響は無し。画面の端をぬたぬた歩くエイドリアン・ブロディが立派な変態にしか見えない映画
ストーリー展開というほどのものも有るような無いようなで、前半ちょいちょい眠くなったことも付加します
「戦場のピアニスト」がとても好きな映画なだけに残念。戦火を生き延びたシュピルマンはボロボロの身なりで、飢えて痩せこけても、深夜ピアノの前でバラードを奏でる姿が誰も寄せつけないほど神々しかったのに…(泣)
補足:IMAXで鑑賞しましたが、「インターステラー」のような音や映像に特別のインパクトがある作品ではないので、追加料金払ってまでIMAXにこだわらなくても良いと思いました
【”大切なのは到達地。旅路ではない。”今作は架空のハンガリー系ユダヤ人の建築家、ラースロー・トートの激動の半生を彼が作ったコミュニティセンター建設過程を軸に、アーティスティックに描いた作品である。】
■今作品の構成を最初に敢えて記す。
1.序曲・・ラースロー・トート(エイドリアン・ブロディ)が妻を含めた家族と引き裂かれる様を描く。
2.第一部”到着の謎”・・ラースロー・トートがアメリカ・ペンシルベニアに単身渡り、富豪の実業家、ハリソン・ヴァン・ビューレン(ガイ・ピアース)と出会い、建築家としての才能を認められるまでを描く。
- ここまでで、キッチリ100分である。
そして、15分間のインターミッションが入る。
結構長いので、お客さんの半分くらいはゆっくりと席を立つ。
スクリーンでは15分から徐々に残り分数がカウントダウンされて行く。
そして、お客さんはゆっくりと自席に戻り、場内は徐々に暗くなるのである。-
3.第二部”美の核芯”・・ラースロー・トートの妻、エルジェーベト(フェシリティ・ジョーンズ)と姪ショーフィア(ラフィー・キャシディ)が漸くアメリカに辿り着き、ハリソン・ヴァン・ビューレンの依頼により、ラースロー・トートが彼の邸宅の近くの丘の上に、礼拝堂が併設されたコミュニティセンターを作る過程が描かれる。
4.エピローグ・・舞台は、1980年のヴェネツィア・ピエンナーレで開催された”第一回国際建築展”にイキナリ、移る。ラースロー・トートの数々の建築物が展示され、”過去の存在”と銘打たれている。シニカルだなあ・・。
で、ここまで再びキッチリ100分である。ストレスなく映画を堪能出来る構成である。今作では、構成自体も作品なのである。
◆感想
・今作では、ラースロー・トートが苦労して、アメリカに渡り、その後も様々な障壁に会いながらも、”マーガレット・ヴァン・ビューレン・コミュニティセンター”建設に挑む姿が描かれる。
・だが、そこでは観客が望むような気持のよい展開は、余りない。逆に1950年代のアメリカ社会における、人種や宗教の壁などが暗喩的に描かれる。ラースロー・トートも、資材搬送列車の度重なる事故により、一度はハリソン・ヴァン・ビューレンに理不尽に解雇されている。
・第二部の再後半は、会食するハリソン・ヴァン・ビューレン宅にエルジェーベトが乗り込み、激しく彼を罵倒するシーンまである。
ラースロー・トートが自分の夢を果たせなかったのかな、と勝手に解釈する。
今作は、作品に明快な解を求める人には戸惑う所が幾つかあると思う。だが、私はそれは気にならない。映画館で観る【力のある映画】は、大体面白いと思ってしまうからである。
<今作ではラスト、”マーガレット・ヴァン・ビューレン・コミュニティセンター”の円形の教会の天井の十字の形をした窓から、太陽光が差し込み十字架を映し出すのである。
そして、”ブルータリズム”の定義である”1950年代、”トートが設計したコンクリート打ちっぱなしの礼拝堂の様に、”素材を生かした建築様式”という言葉を思い出すのである。
今作は架空のハンガリー系ユダヤ人の建築家、ラースロー・トートの激動の半生を彼が作ったコミュニティセンター建設過程を軸に、アーティスティックに描いた作品なのである。>
羊頭狗肉じゃね?
傑作2本分の怪作!等身大の夫婦愛に浸る。
ナチスの迫害から自由の国アメリカへ逃げ延びた天才建築家が辿る数奇な運命の話。
ユダヤ人迫害、人種差別、立場や状況によって豹変(悪い意味です)する人の心、薬物含めた快楽依存などなど・・・私の嫌いなアカデミー賞(笑)にも複数部門エントリーされているだけはあり、社会派のお堅いイメージだったんですが、それらは「建築素材」として使われているだけでした。
描かれている・・・いや、いろんな効果を考えて設計され基礎からがっちり組み上げられて「建てられた」のは、「濃厚な人間ドラマ」であり、「夫婦愛」だった訳です。
特に、15分のインターミッションの後に始まった後編は、奥様と姪の登場シーンからして印象的で、感激というよりも互いの異変を気遣い心底心配するような・・・感情をセーブしながらの演技が本当に素晴らしかったです。
車椅子生活の自分より、外見はまともなようでも精神的にぶっ壊れつつある夫のケアに余念がない妻の発言、行動は努めて献身的でした。しかしそれは肉欲にもリンクし同時に自身の快楽にも忠実であることが示されており、等身大で互いに自身の奥まで曝け出す様な愛の形が美しかったです。
あと、敵役?の成金似非インテリオヤジ、その馬鹿息子の配置や演技も見事で、物語に効果的な起伏を与えておりました。
主人公の夫が似非インテリオヤジに、自分の妻の経歴などを一切伝えてなかったのは、彼が無口なの以上に防衛戦略的には最善手(笑)でした。つづくテーブルを挟んだやり取りも夫として最高で、夫婦愛が暗喩された大好きなシーンのひとつです。
長い時間の映画ですが、演出、描写の丁寧さと、しかけのうまさで終始退屈することなく鑑賞できました。
傑作2本分だから星は10個差し上げたいくらいです笑
ぜひぜひご鑑賞ください!
3時間半の没入体験が残した“違和感”
ある種の納得と、説明のつかないモヤモヤした感覚が残る映画だった。3時間半の長尺ながらも、十分に集中して観られる映画だった。
しかし、いざ振り返ってみると、登場人物たちの人間関係の変化や、繰り返されるトラブルの詳細が明確に語られることはなく、どこか霧の中を歩いているような印象が残る。
劇場で配られた「建築家ラースロー・トートの創造」というパンフレットをみると、あたかも実在の人物の伝記映画であるかのようである。
映画の最後には回顧展のシーンがあり、アーカイブ映像のような質感でもあり「この映画は実話を元にしている」と思い込んでしまう。しかし、調べてみるとトートは実在の建築家ではなくフィクションだった。この演出は意図的なものだろう。
『ブルータリスト』は、ホロコーストを生き延び、アメリカに渡ったユダヤ系建築家ラースロー・トートの半生を描く。しかし、映画の中で彼がどのようにブルータリズムの建築家になったのかは明確に語られない。さらに、彼の人生の中で起こる様々な問題——お金のトラブル、友人の妻との関係、浮気やセクハラの疑惑——これらは何度も繰り返されるが、すべてが曖昧なまま進んでいく。
通常の伝記映画であれば、「実際に何が起きたのか」という史実を説明する役割がある。しかし、この映画ではあえて「事実」を描かず、まるでトート本人の記憶の断片を追体験するような構成になっている。
彼の人生の出来事を、明確には理解できないまま眺めることになった。この手法は、実在の人物の伝記映画に見られる「すべてが説明されるわけではない」というリアリズムを再現しようとしたものなのかもしれない。
映画のラストシーン、回顧展の場でトートの姪が彼の言葉を代読する。「プロセスよりも、結果がすべて」というようなメッセージは、一見すると建築家としての合理的な哲学のようにも聞こえる。
しかし、彼の建築は個人的なメッセージ性の強い作品ばかりであり、むしろプロセスの中での思索こそが彼の作品を形作っているように見える。
この言葉は彼の本音なのか、それとも移民として「結果を出さなければ生き残れない」現実を受け入れた末の結論なのか。その答えは、映画の中では明示されない。映画の中で何度も描かれる「語られない出来事」と同じように、トートの哲学もまた、曖昧なまま提示されたように感じた。
本作は3時間35分という長尺だ。しかし、退屈する瞬間はほとんどなかった。視覚的にも魅力的なカメラワーク、テンポよく進む場面転換、そして何よりも「この人物の人生を追いたい」と思わせる不思議な吸引力がある。
この映画を、ストリーミングで観たら、多分、途中で集中力が切れてしまいそうだ。映画館という環境で一気に集中し、この世界に入り込むことこそが、本作を体験する上で最適な方法だと感じた。
こうして感想を書きながら、いろいろと思考を巡らせた。しかし、どうにも切れ味のある考察には至らない。それは、この映画自体が「明確な答えを出さない映画」だからなのか、それとも、僕がきちんと観れていなかったのか…。
実人生では、すべての出来事に明確な因果関係があるわけではなく、物事の真相が分からないまま終わることも多い。『ブルータリスト』は、まさにその「不可解さ」そのものを映画として体験させる作品だったのではないか。
全208件中、141~160件目を表示