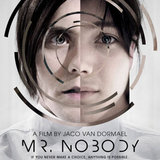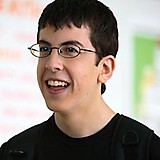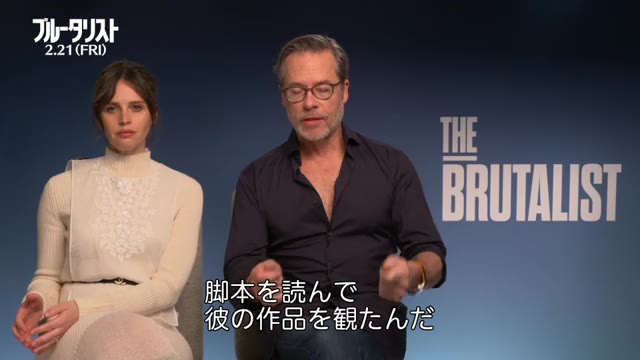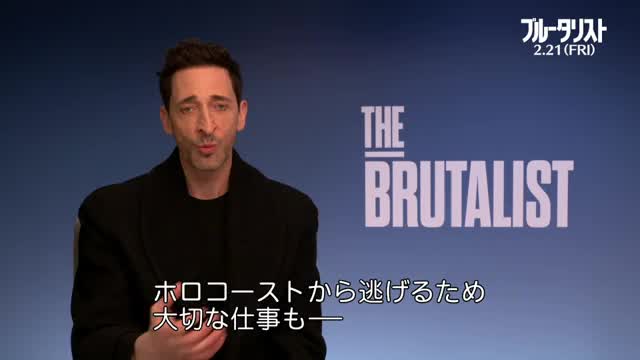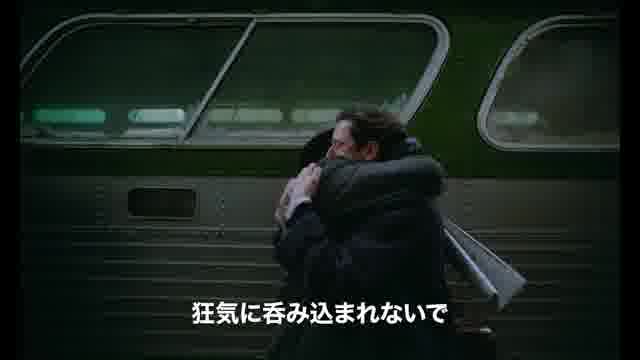ブルータリストのレビュー・感想・評価
全208件中、121~140件目を表示
新しい映画!長さを感じさせない!
面白かった!3時間超えの映画なのに、観終わった後に、すぐまた観たい!と思った映画は始めてです。
まず、映像・音楽が、ものすごく良かった。それぞれの役者も、ものすごく良かった。私は、美術館とか好きなんですが、好きな絵って、ぼーっと長い間見てても飽きないですよね。そんな感じの映画でした。
映画は、ラースロー・トートというヨーロッパで将来を期待されていた建築家が、ホロコーストを生き延び、アメリカに渡って建築家として再出発するという話しなのですが、これがこのあらすじからは想像出来ないような映画になってて、良い意味で裏切られました。
まずは、ラースロー・トートという建築家は、実在しない建築家ですが、『この映画は、実話を元に…』的な感じを観る者にイメージさせているところが、凄いなと思いました。まぁ、まず最近のこういうあらすじの映画って、観る前とか観た後に、『この映画は…』ってテロップ出がちなので、勝手にイメージしちゃいます。きっと主人公は、「ホロコーストを生き延び、何かのメッセージを込めた作品を創った偉大な建築家」なんだろうと。
劇中に出てくる、ラースローの作品は、どれも素晴しいし、良いやん!と思うのですが、これからアメリカで偉大な建築家になっていく人が、作ったと思うから、良いやん!と思うのか、本当に良いのか、分からなくなってきます。
序盤で、ハリソンが、自分の書斎を勝手に改装したのが、実はヨーロッパで名の売れていた建築家と知って、掌返しするシーンがありますが、最初は「こういう奴いるよな〜」と思って観てたのに、映画を観終わった後、「良いやん!」と思ってたラースロー作品も、ラースローを偉大な建築家やと勝手に思って観てたからなだけで、本当はそれっぽく似せて作られてるだけのものを良いと思ってたのか?それなら、ハリソンと変わらんやん、建築とか家具とか絵とか、そういう物の芸術的価値への評価って、結局なんなんやろ?と考えさせられました。
これがもし、本当に実在した偉大な建築家なら、「おー!凄い!」で、観る側は終われてたのに。でも、そう思ってしまうぐらい、ラースローの作ったものは良くて、それをちゃんと鑑賞させてくれる映像のつくりも、凄く良かったんですよね。
次に、『ホロコーストを生き延びたユダヤ人の描き方』。ラースローが、アメリカで直面するのは、ハンガリーでナチスから受けて来た、分かりやすい差別や迫害では無くて、なんか薄い膜に包まれたような差別。
黒人には、「出ていけ!ニグロ!」みたいな分かりやすい差別をするけど、ラースロー達には訛ってるから英語を習った方が良いとか、表面上は紳士的に振る舞って取り繕ってるけど、明らかに下に見ているみたいなところで、結局差別してるなと、感じます。
最たるシーンは、ラースローがハリソンにレイプされるところ。たぶん、天井の高さは、映画の中でラースローにとって自由を表していて、天井の高い洞窟?でパーティーを、自由に楽しむラースローを見て、なんでもコレクションしたいハリソンは、言葉もわからない異国で自分を放置して自由にしてるのが許せなかったのかな?と思いました。私は、その支配欲が、レイプに繋がったと解釈しています。
とにかく、ハリソンは性的に興奮してレイプしたのでは無いと思います。支配したくてレイプしてると感じさせるところに、WASPの表面的ではない、膜に包まれたような差別を感じ、これはむしろ今の世界に蔓延している差別なんだろなと思いました。
最後は、エピローグ。姪っ子のジョーフィアが式典で、ラースローの作品をシオニズムと絡めて語っています。
長い間に、ラースローの考えが変わったのならそうなのかもしれませんが、劇中でラースローはそんな事は一言も言ってません。締めのエピローグで、大団円風にしながら、スピーチがちぐはぐなところが非常に面白かったです。
それっぽく素晴しい作品を登場させ、ラースロー・トートという実在しない人間を描いたように、ジョーフィアの中で勝手に新しいラースローが出来上がっていたのかもしれません。もしかしたら、シオニストのアピールのために、そう語ったのかも。
長くなりましたが、ラースローを通して何かを学ばせるようで学ばせない。受け手にこの映画を含めた、全ての芸術的な美の解釈を放り投げたまま、放置してしまうという、めちゃくちゃ面白い映画だったと思います。
よく、圧倒的な没入感とか映画の予告で良いますが、そういう意味で、この映画の没入感は凄かった!
だから、癖になるというか、また観たいと思ったのかもしれません。
小冊子「建築家ラースロー・トートの創造」
第97回アカデミー賞において10部門にノミネートされている本作。以前はスカラ座だったTOHOシネマズ日比谷のSCREEN12(東京宝塚ビル地下)は同劇場最多座席数の大きな箱ながら、平日の割にそこそこの客入りで作品に対する注目度の高さが判ります。
本作の監督、ブラディ・コーベット。今作で初めて「アカデミー賞監督賞」にノミネートされたわけですが、彼のフィルモグラフィーでを過去の監督作品を確認すると『シークレット・オブ・モンスター(16)』『ポップスター(20)』となかなか個性を感じさせる2作品。そして本作でも裏切らず「いろいろと戸惑わせてくれる作品」に仕上がっています。
まず入場時に配られた小冊子「建築家ラースロー・トートの創造」。鑑賞前にあまり情報を入れないようにしている私は、それを見るともなしにサッと目を通してバッグに仕舞い込み、これから始まる長丁場に備えます。なんせ、本作の上映時間は215分。ただ、本作は大きく2部構成となっており、開始から1時間40分ほどで1部が終って15分のインターミッション(途中休憩)が入ります。その間は客電も点き、スクリーンにはカウントダウンも表示されるため落ち着いてトイレ休憩も可能。高揚感たっぷりで終わった1部のことを考えつつ、本作の主人公ラースロー・トート(エイドリアン・ブロディ)に興味が湧き始めた私。そういえばと思い出し、改めて例の小冊子に目を通します。そうこうしているうちにカウントダウンは1分を切り、再び小冊子を仕舞って2部に控えます。実は「劇場でのインターミッション初経験」の私、再開後の2部にすぐ集中できるか若干の不安もあったのですが、、2部の冒頭で早速、1部で出演のなかった「あの人」の登場シーンに、流石の存在感と演技力にすっかり涙腺を刺激された私。そこからは、1部以上に波乱万丈が続き「果たして、ラースロー・トートはこの偉業を成し遂げるのか?」心配がやまない展開。で、全て観終われば幾つか冗長に感じるシーンもなくはないのですが、215分の上映時間はインターミッションの効果もあって案外長くは感じませんでした。
そしてすっかりお昼のピークタイムが過ぎ、いつもは行列のできるラーメン屋に待ちなしで入店。この時点で本作を「建築家ラースロー・トートの伝記映画」と勘違いしている私、配膳を待つカウンター席にてWikipediaを検索、、ん?該当がない??。。何でだ?と思いながら改めて「小冊子」を出し、今度は注意深く目を通してようやく気付く小さな級数の注記に目を凝らすと…「本書の内容は一部を除き全て架空の内容です。」何と、全て創作だったとは。。。まぁそれを知ると、本作(特にエピローグ)に強く感じるシオニズムに対し、どうしても「今起きていること」が引っかからずにはいられないのですが、唯一無二の作品性と役者達の素晴らしい演技に対する高い評価は納得の一言。騙されたことも含め、すっかり楽しみました。いやはや参りました。
絶誘惑。
第二次世界大戦下のホロコーストを生き延びた建築家でヤクがやめられないラースロー・トートの話。
ハリソン家の息子に頼まれた1室、読書部屋(図書館)の改装を頼まれ…、改装当時は文句をつけられるが後に評価され、ハリソン家父から新たな依頼が…。
転機が訪れるも思った様に事は運ばず…、急なデザイン変更、事故、そこを経ての少し人に対してピリついちゃったり…。
唯一、主人公に共感出来たのは設計した天井を3メートル低くされ怒る、ここは色々計算されてのその高さでしょうしね。
上映時間215分ビビってましたがちゃんと15分休憩があるのは親切、…ごめんなさいどの作品でも賛否あるけど全然私には合いませんでした!時間の長さはそこまで感じないけどストーリーに全く面白さを感じず、始まって早々眠いし、数年ぶりに途中退席しようかなって思ったくらい…、ただこういった話も楽しめる様になれればとも思う。
商業映画としては実に含みをもたせた展開。安易な解釈を許さない。
世に難解な映画はたくさんあるがこの作品は別に難しくはない。観るのが苦痛になるといったところもない。でもこれほど異様な展開で進行する映画もあまりなくて全く先が読めなかったし観たあとでも腹落ちがなかなかしない。
入場時に「建築家ラースロー・トートの創造」と名打ったリーフレットをもらえる。映画のサービス品であるのだが美術展で配られるリーフレットと同じ体裁で、トートが設計したマーガレット・ヴァン・ビューレンコミュニティセンターの概要やその美術的位置づけを写真入りで解説してある。でもこれは全く架空のものなのである。そうこの作品は実在もしくはモデルがある人物の評伝ではなく完全なオリジナル脚本によるフィクションである。科学者なり芸術家の「業(ごう)」みたいなものを描いているという点では「オッペンハイマー」に似ているんだけどね。アイデアの素みたいなものはあったんだろうけどまさかこれがオリジナルだとは、と原作本、漫画があって当たり前の邦画を見慣れている日本人観客としては思うのです。
ところで、パンフレットには書いてあるかもしれないけど「Brutalist」の語源の話です。意味としては1950年代に英国のAlisonとPeterのSmithon夫妻が提唱したコンクリート打ち放しでそのテクスチャーを活用した建築家のことです。だからフランス語の「beton brut」〜生(き)のコンクリート〜からbrutを取り、同じような傾向の建築家をbrutalistと呼んだようです。建築様式としては割とすぐにモダン建築(ほらル・コルビジェや丹下健三なんかの)に吸収されたようだけどね。英語のbrutal(野蛮な)とは語源が一緒なのかもしれないけれど多分そちらではない。
ところでトートは自分は「Brutalist」だとは一言も言ってないし、まわりからそのように言われている場面もない。バウハウス出身だから流れとしてはそちらではあるんだけどね。ただこのbrutというのはトートの性格を表しているんだと理解することもできる。つまり純粋だとか、世間知らずだとかそういう意味で。
そうこの映画が予想できない展開になるのはトート自身の考え方や行動の傾向が全く予想できないから。周りのハリソン・フォンビューレンや妻のエルジューベトのような個性の強い人に引っ張られ右往左往しているだけのようにみえる。そして脚本上の仕掛けとしては、建築家だけに建築物に彼の思想は凝縮されているということで映画の最後にヴェネツィアで開かれる建築ビエンナーレでもはや身体がいうことのきかない彼に代わり姪のジョーフィアが種明かしをする。ここでホロコーストの記憶を残すこと、希望への足がかり、妻への愛などが建築の思想として披露されるが彼自身の発言でないから本当のところは分からない。私には彼が造ったたものは、彼自身を(そしてハリソンも妻も)永遠に閉じ込めておく牢獄に見えたけど。ホロコーストの傷跡というものは人の心の中で再生産されていくんだということなのかもしれないね。
最後に「Brutalism」のことだけど、建築様式としては過去のものにはなったがデザインの世界では生き残っているようです。例えばネットサイトのデザインなんかに。この場合は、非対称であるとか、文字だけ、写真だけといった素材の少なさ、バックを黒白一色にするとかが特徴になるようです。つまりこの映画のタイトルバックやエンドクレジットは「Brutalism」のデザインということです。凝ってるよね。
アカデミー賞大本命の理由が分からん
到達点を見据えた人生
壮絶な体験をかい潜り、生涯を通じて自身の信念を貫いた建築家の歴史。所々でみられた車両、列車、ゴンドラが突き進む様子を乗っている人の目線でみせた描写が、彼が邁進した生涯を象徴していたでしょうか。
途中、離れて暮らすことになる妻から「狂気に呑み込まれないで」と懇願された主人公が印象に残りました。そして、まんまと呑み込まれてしまったか…と落胆させられる後半。しかし、それは勘違いであったとエピローグで気付かされます。彼は、「なぜ建築家になったのか」という問いに明快に答えた、あのときの想いからブレることはなかったし、あのときの彼のままで生涯を奔走していたのでした。
エピローグの終わり方が爽やかで気持ちよく鑑賞を終えられました。30年ほど前に鑑賞した「ダンス・ウィズ・ウルブズ」の4時間バージョンを観て以来の長編でしたが、作品自体もスタイリッシュであったせいか、あっという間のエピローグでした。
そして、「決断の街」を舞台にしたこうした歴史が、「フィラデルフィア」につながってるのか等と感慨にふける、そんな作品でした。
ホロコーストを生き残り、アメリカへ渡った建築家
最近の映画では珍しく途中休憩あり。
インターミッションにもBGMと環境音があり独特な雰囲気。
【前半】
導入のスタッフロールで映されるシンプルながら美しい映像と洗練されたキャプション、将来への希望と不安を感じさせる音楽からセンスが溢れる。
心地よい間で進む会話のどれもがどこか品と情緒を兼ね備えている。
謙虚で脆く、芯があり不器用な人柄に危うさを感じつつ、この先を心待ちに前半を終える。
【後半】
建築や景色は特定の時代を表す普遍的な存在として語られる。数多くの定点映像が作品内に映されるが、その意味が後のスピーチに繋がる。
ラストシーンの演出には思わず拍手してしまいそうになる程感服させられた。
眠っていた感性を起こさせるような極めて鋭い刺激的な作品。
単調なようで企みたっぷりな知的好奇心を揺さぶられます
まあ冗長なのは確か、なにしろ3時間34分でたった一つの建築物の設計から完成までのみを描くのですから、波乱万丈の半生とは程遠い。ましてやユダヤ抹殺の激動の悲劇の感動作とは真逆ですらある。おまけに製作費節約のためか、やたらアップのシーンが多く、要するに背景セットを省けるからか。しかし、だからツマラナイとはならないのがミソ。役者上がりの監督ブラディ・コーベットはどう見てもユダヤ系には見えず、建築様式としてのプロセスにこそ興味があったのではないか。
ナチの迫害を受け収容所から命からがらにして脱出、渡米。数多の苦労を経て建築家として名を遺す、ってのがストーリー。ポイントはブルータリズムと称される装飾を排除した武骨なスタイル。コンクリート剥き出しの建築物って言えば日本の昭和の建物に多いですよね、市役所とかに。力強いけれど荒々しく洒落っ気なし、構造的デザインが命みたいな。この言葉から連想されるのが「ブルータス」ですね。マッチョであり男臭く残忍でもある。まさに二つの言葉は派生語の域で、タイトルの「Brutalist」はそんな野郎と解せばよろしいのではないか。
ならば本作におけるブルータスな野郎と言えば、助演男優賞にノミネートのベテラン役者ガイ・ピアースであり、助演ではなくタイトルロールと言っても差し支えない暴れん坊ぶりなんですね。大金持ちの気まぐれに留まらず、建築家を翻弄するハリソンを、彼(ガイ)史上最高のイケメン装いでタイクーンのように振る舞う。しかし、対するラースロー・トートとても相当なブルータスなのが本作の曲者ぶりでしょう。全面的被虐でもなく、頑固一徹なのが本作の縦軸として貫いています。
で、メインの男2人がマッチョイズムが強ければ強い程、却って浮かび上がるのがゲイ要素なんです。決して比喩でもなく、米国に到着早々に売春宿に出向くラースロー、帰りがけ女将から「肌の浅黒いハンサムボーイもいるよ」と誘惑するも、もちろん「その趣味はない」と言うシーンがわざわざ挿入され、咄嗟に?が私の頭を過る。やっと再開出来たとは言え、従弟とのハグの長すぎる異様、相棒然と面倒をみてやる黒人の親子、その大人ゴードンとはドラッグを共有する濃すぎる間柄。などなどの伏線の挙句のハリソンの暴走が描かれる。マッチョ信仰の裏返しが本作の横軸なんですね。
そうは言っても本作の異性とのラブシーンもかなり濃厚に描かれ、アカデミー賞女優のフェリシティーのヘア(本人かどうかは不明)まで映るわけで。当時の怪しげなブルーフィルム(多分本作のための撮影フィルムでしょう)の画面まで登場。なにより妻エルジェーベトが米国に到着した最初から、エルジェーベトはラースローにセックスを激しく要望する程に。生き様として性が積み重ねられるが、あくまでも前述のハリスンの支配欲に収斂させるためでしょう。
本作はタイトルから、肝心の建造物の連写、そしてエンドタイトルにいたるまで相当にスタイリッシュなのがポイントです。なにより劇伴奏が凝りに凝って、全編アグレッシブにオーケストラが鳴り響く。音楽が実に饒舌で、退屈な長廻しシーンに多用され効果を上げています。だからアカデミー賞に撮影も作曲も当然のノミネートですね。やっと辿り着いた自由の国、ニューヨークの自由の女神が何故か斜めの角度でしか描かれない作為が計算の上なのですね。
映画モギリで配られるリーフレット。ラースロー・トートの略歴が記載されてますが、なんと写真がエイドリアン・ブロディ。あれれ? ご本人ではないの? これがまた本作の仕掛けとは! 要するに実在の人物ではないのでした。ビエンナーレの表彰式まで描くものだから、てっきりですよ。もちろん近いモデルの著名人はいたようですが、エキセントリックなコンテンツゆえ、架空の人物に据えたのでしょうね。でも最後の種明かしである「収容所をイメージしてのデザイン」である事こそ本作の肝ですから。
「戦場のピアニスト」でオスカー獲って、再びユダヤを全面に押し出した役で二度目のオスカーも濃厚なエイドリアン・ブロディ。見事なユダヤ鼻が強烈な彼の名演によって、架空が真実に昇華されられた。対する妻役のフェリシティ・ジョーンズはなんと前半は全く登場せず、15分間の休憩のあとの後編にやっと登場ですが、流石の貫禄を見せつけます。
25-029
建築をちゃんと表現している秀作
かなりユニークなスタイルで引き込まれた。
●静物をちゃんと表現として捉えている絵が素晴らしい。
●物語も下手に急がず、独特のテンポがある。そのうえで行間や感情表現を微妙に抜いていて想像力を掻き立てる。
●とにかく音楽がいい。場面場面でスタイルを変え、ゴダールのソニマージュを意識したような感覚。
イイ映画だな。
自由と奴隷は紙一重の違い
昔の長尺モノは
インターミッションが設定されている作品も多かった。
そして、その途中休憩の間に趣向を凝らす場合も。
例えば〔レッズ (1981年)〕。上映時間は194分。
場内が明るくなると〔インターナショナル〕が流れる。
まさしく作品に合致した楽曲。
一方、直近で観た〔聖なるイチジクの種〕は
167分あっても設定はされていない。
そして、本作。
15分のインターミッションを入れて215分。
で、その間には、作品の一場面を象徴する
結婚式の家族写真がスクリーン上に投影され、
デジタルタイマーが時を刻む。
音楽や効果音は流されるものの、
もうちょっとの工夫は欲しかったところ。
タイトルの〔ブルータリスト〕は
「ブルータリズム」の建築家の意。
鉄筋コンクリートを多用した無骨で機能的な造形が特徴で、
1950年代に流行した。
主人公の『ラースロー・トート(エイドリアン・ブロディ)』は架空の人物も、
ハンガリー系ユダヤ人で
モダンなデザインを確立した「バウハウス」で学んだ建築家との設定。
「バウハウス」は勿論、ナチスにより閉校されている。
『ラースロー』はホロコーストを生き延び、
アメリカに渡る。
しかし、妻と姪は欧州に留め置かれたまま。
富豪の『ハリソン(ガイ・ピアース)』の知遇を得、
彼からの依頼で大規模なコミュニティーセンターの建設に挑むが
多難が次々と襲う。
嵩む建設費や資材を運搬している列車の事故。
施主の『ハリソン』に振り回され、
工事は度々の延期や中止の憂き目に。
しかし、『ラースロー』は自身の報酬を注ぎ込んでも、
憑かれように建物の完成を目指す。
酒と麻薬に溺れながらのその姿は、
鬼気迫るとの表現がピンと来るほど。
冒頭、移民船がエリス島に着き、
客室から甲板に出た主人公が目にするのは
何故か逆さまになった「自由の女神」像。
その意図するところは何か。
自由の国、誰もが成功者となれる可能性のある国は、
必ずしも万人に開かれているわけではなく、
社会的な差別や偏見が厳然と存在し
『ラースロー』はそうした悲哀も味わう。
とりわけパトロンとの関係性は
終生彼を苦しめる。
最後のシークエンスで
彼が心血を注いだ「マーガレット・ヴァン・ビューレン
コミュニティーセンター」の設計思想が明らかに。
小さい部屋を幾つも作った理由、
天井高の訳、
異様さを感じる四つの塔の背景、
地階の廊下で建物を繋げた思想、
何れもが、ナチスの迫害に起因していた。
一人の男の伝記ドラマと共に
反ホロコーストの意匠も潜めていたことが、
言葉を以ってして我々に伝わるのだ。
丁寧で美しい映像で半生を描写していくことは、上質な時間であり、上映時間の長さは苦にはならない。
これがオスカー大本命?、、、
面白くなくはなく、3時間最後まで見れましたがこれだけの尺は要らないな、と感じた薄口の作品でした。なんでこれがノミネートされたのか??
役者、音楽は悪くないけど、やはり脚本と演出がイマイチなのか。なんか全てのエピソードが中途半端な感じで3時間も見たのにほぼ心に響かなかった。渡米する前、ホロコースト、アメリカでの最初の生活の違和感、祖国での家族との生活、従兄弟夫婦との関係、姪ジョーフィアが殆ど喋らない事などなど全て中途半端にしか描かれないので、?と思いながら最後まで観て終了。
あの最後の明るい音楽と、静寂はなんだったのか?そして休憩15分は長い。
偽りの自由
第二次世界大戦下、ホロコーストを何とか生き延び渡米した、才能あるユダヤ人建築家ラースロー・トートをエイドリアン・ブロディが熱演。
妻エルジェーベトをフェシリティ・ジョーンズが、実業家ハリソンをガイ・ピアースが演じる。
辛い記憶、やり場のない怒り、理不尽な扱い … 。やむを得ず移民として生きる事の過酷さ、苦悩をリアルに描く。
映画館での鑑賞
ありそうで、あったら困るフィクション
※モデルとなった人物はいるようですが、完全にフィクションでした。
ホロコーストを生き延びた建築家が移民としてアメリカに渡り、丘の上に思想つよつよなコミュニティセンターを建てる話です。
移民としては、これ以上望めないぐらいのサクセスストーリーに思えるのですが、それでも破滅に近いところまで落ちます。特に、主人公が家族を連れてきてからは、酷いものでした。
そんな彼らの苦悩に三時間半付き合って思ったのは、『それをアメリカでやるから揉めるんじゃない?』という一点に尽きます。
アメリカに建てるコミュニティセンターは、アメリカ人が交流するためのものです。
仕事として請けた以上、そこに反映させる思想はあくまでクライアントのもので、光が差し込む設計にされた十字架の形を『ごめん、KKKも来たいって言ってるから、やっぱハーケンクロイツにして』と言われたら、その形のものを建てるしかないわけで。
主人公が完全に私財で建てたり、クライアントと思想面でがっつり手を組んだというのなら、分かりますが。
そういう深い交流はなく、クライアントが色々聞いても主人公がはぐらかすので、建築の真の目的が語られるのは1980年です。
本編で描かれるすったもんだから20年が経過して初めて、高さを削るところでやたら揉めた理由が分かるわけです。当時の現場にいた様々な立場の人達ですら、知らなかったことです。
理由を正直に伝えたら実現しない。そのことが分かっているから、思想を隠し通して、こっそりと押し込む。コミュニティセンターが完成した1973年から1980年まで、そこを訪れた人々は、知らない内にその思想に加担したことになるのです。
実は『わー綺麗』では済まない何かを、知らない内にくぐらされる。
この押しつけがましさと傲慢さが、高さ云々の下りで理由を説明しなかったり、揉める原因を作ってきたのではないかと。
ーー
あと、今のイスラエルの国際的な立ち位置を見ていると、彼らがどれだけ苦悩しようが体を張ったギャグにしか見えませんでした。
※私はどっち側のシンパでもなく、双方地球から消えてくれないかなと思っているタイプです。
光を当てる角度/悪魔のいけにえ的な
トートの建築同様、光を当てる角度によって見え方が全く変わる作品だと思った。最後、結局みなイスラエルを目指すというところを取れば、シオニズム翼賛みたいにも見えるが(それは設計に隠された意図が明かされる場面でピークに達する)、全員何かに怯え、征服したいと思っている、という意味ではもう少し普遍的なメッセージを読み取ることもできるように思う。フィラデルフィアという、“アメリカ”始まりの地が舞台になっている点もわかりやすく、見下していた“身体障害者”の“ユダヤ”“女”がオックスフォードで教育を受けていたりして、イギリスという抑圧者に対して腕一本の叩き上げでやってきた人(たち)がコンプレックスを刺激されるには十分だろう。/ところどころ、『悪魔のいけにえ』を想起する場面がちらほらあった(これは極めて個人的な連想のような気もするが)。腹に一物(という名のむき出しの欲望もしくは攻撃性・暴力性)を抱えながら生きることが象徴的に示されるという意味では晩餐・パーティというのはそうだろうし、なんだか薄暗く抑圧的な雰囲気のコミュニティセンターの内部のシーンもそうである。/イタリアが映画的仕掛けとして巻き込まれていくところにも意図が張り巡らされているような気がするし、とすると、日本はどう?/要は人間みな後ろ暗さとの戦いなのである。/知的に組み上げられた映画でエモーショナルなところはあまりないので、そこは賛否が分かれるところかもしれない。
重厚で壮大
作り込みはすごいが...
「我々は"無"だ。無ですらない」
ホロコーストを生き延び、アメリカで活動した「ブルータリズム」(1950年代に見られた建築様式で、文化的要素が低く無骨な意匠を建物の外観に多用する)の建築家ラースロー・トート(演:エイドリアン・ブロディ)の活動と、ユダヤ系としての苦悩を描く。製作は「ライトハウス」「関心領域」などのA24。
総上映時間3時間25分。現代作品には珍しく「序曲」と「インターミッション」があり、15分の休憩が挟まれる。総論からすると第一部「到達の謎」は素晴らしかったが、第二部「美の核芯」は冗長で、エピローグは及第点という感じ。
まず良かった点。主人公ラースロー・トートは1911年にハンガリーで生まれたユダヤ系の建築家で、若き日はワイマールのバウハウスで学び建築界の期待の星のひとりだった。しかしナチスの台頭によって迫害され、第二次大戦中はドイツ・ブーヘンヴァルト強制収容所で過ごした。1951年に渡米し実業家ハリソン・ヴァン・ビューレンの書斎を改築したことで脚光を浴びる。劇場に入る前にラースロー・トート本人や彼の代表作である「マーガレット・ヴァン・ビューレン・コミュニティセンター」について説明した小冊子が渡された。自分も建築学史には興味があり、著名な建築物の写真集を集めるくらいにはライトファンだったのだが、ラースローのことは全く知らなかった。我ながら自分の無学を恥じた...と思いきや、ここまで記載したことは全てフィクションで、ラースロー・トート自体が架空の人物とのこと。もちろんコミュニティセンターなるものも実在しない。すっかり騙されたし、ここまでの作り込みは大いに評価したい。IMAXで鑑賞したこともあり、時代を飾る名曲が沢山流れたのも心地良かった。
問題はインターミッションを挟んだ後半にある。第二次大戦で生き別れていた妻、そして姪とアメリカで再会したラースローだが、このあたりからやたらHなシーンが多くなり、まるで「エマニエル夫人」でも見せられているかのようだった。そして終盤になって妻エルジェーベト(演:フェリシティ・ジョーンズ)が突拍子もない告発を始め、それについて具体的な説明もないまま一気にエピローグに進んでしまう。あまりにも訳が分からず先に鑑賞した諸氏のレビューをいくつか漁り、どうやら「現代アメリカ社会におけるアングロサクソンとユダヤのメタファー」なるものらしいことがぼんやりと理解できてきたが、それにしてもあの描写は不親切極まりない。Hなシーンの連発で萎え気味だったところに浮いた展開を持ってこられて気持ちが醒めてしまった。アメリカ人(やアメリカナイズされた人)なら「ははぁ〜ん」となるのかもしれないが、側から観る限りあれでは説明不足とミスリードのリスクの方が高い。だからA24って苦手なんだよ!
あんなにHなシーンをダラダラ流して3時間半近い上映時間なら、他に描写するべき要素があったと思う。まあ重厚感は買いますが。
結局、ユダヤ教映画なのか?
休憩をいれ、3時間半の上映時間を飽きさせない力は凄い。波乱万丈の人生を体験させるかのような展開に、特に前半はあっとう間に時間が過ぎて行く。
それを支える役者たちの演技も素晴らしく、映画を観る喜びが味わえる。
途中の休憩はいいから、早く続きが観たい!
そして後半が開幕。
ブルータリズムの建築美とドラマの壮絶な交差を期待していたが、それは裏切られてしまった。
列車事故、突然のレイプ、死にそうなったと思ったら歩けたりと、伏線もなく、ゴシップ記事の様な展開にドラマから心が離れてしまった。
ヤク漬けの日々を送ってたのに長生きしてと、エピローグでは完全に気持ちは白けた。
結局、ユダヤ教イスラエル万歳の宗教映画なのか?反ブルータリズムで反移民を掲げるトランプ大統領批判を諷喩した骨太映画を期待したが(それはあるかもしれないが)、何を言いたいのか分からなかった。
ユダヤ人が多いハリウッドで特に評論家受けも納得だけど、映画を純粋に楽しみたかったので、いい所もたくさんあるだけに、鑑賞後は「えーっ!?」という気分です。
全208件中、121~140件目を表示