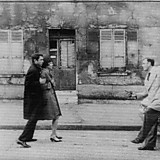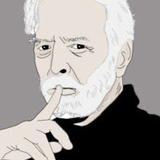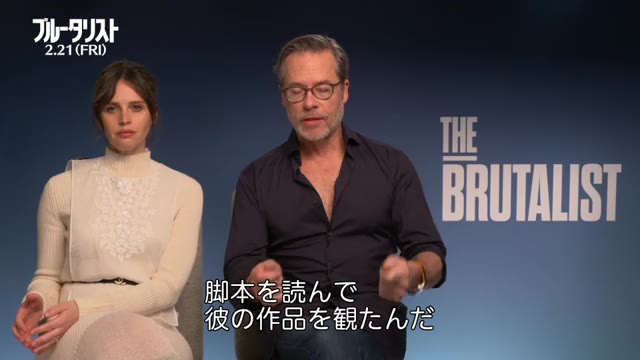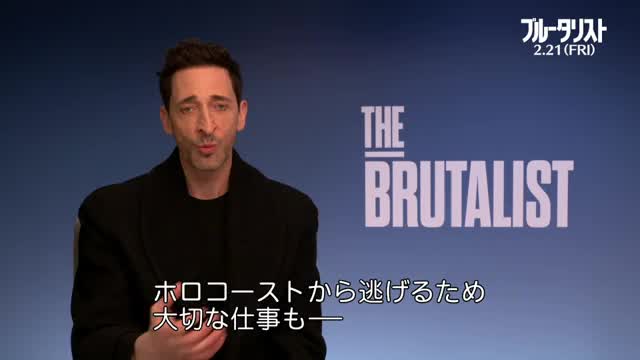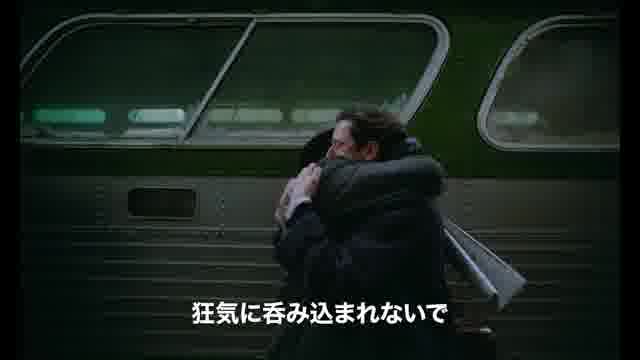ブルータリストのレビュー・感想・評価
全208件中、101~120件目を表示
ダチョウ倶楽部かよ
ブラディ・コーベット『ブルータリスト』をシネ・リーブル神戸にて。
『ブルータリスト』における「ブルータル」とはバウハウス様式から派生したコンクリートやガラスが剥き出しになった「ブルータリズム建築」の「ブルータル」さ(荒々しさ)であり、また剥き出しになったことから生まれる荒々しさは、アガンベン的な「剥き出しの生」を生き、まるで人権などないかのような、すなわち「ブルータル(獣のような)」な難民のあり方にも繋がるだろう。
ホロコーストを生き延びてアメリカに渡ったブダペスト出身ユダヤ人建築家の半生。
主演のエイドリアン・ブロディだけでなくフェリシティ・ジョーンズもガイ・ピアースも良かった。
バーでジャズ?の演奏に合わせて激しく踊るシーンは素晴しいとしか言いようがなく、バウハウス風のチェアを製作するために鉄パイプを加工するシーンで飛び散る火花(宣材写真に使われている)は美しいのひとことに尽きる。
ガイ・ピアースが邸宅に招いた客人たちを丘の上に連れていくロングショット、プレキャストコンクリートの建材を満載した列車が事故を起こす俯瞰ショット、イタリアで切り出される大理石を捉えたいくつかのショットなど、ともすれば審美的に過ぎると言われかねない映像が続く。
…いやはや、正直に申し上げれば退屈でした。
しかし、物語の重苦しさと緊張感に満ちた(しかし退屈な)この3時間35分の映画のなかで、ほとんど唯一笑ってしまったのは、絶対に落とすわけにはいかないと念には念を入れてクレーンで吊り上げた天井?屋根?の部材を、しっかりと地面に落としてしまうシーンだった。
ダチョウ倶楽部かよ、と。こういうの好き。
同じ回に観に来ていた知人と、少なくともあと1時間は削れたんじゃね?という意見で一致した。
215分の長尺ですが・・・
長さを全く感じさせない映画です。
途中15分のインターミッションが入りますが、これにも工夫が施されていて、プロローグ、第1部と第2部、エピローグの大事な繋ぎ目となっていて、あのカウントダウンも観客を飽きさせない要因のひとつとなっています。
肝心の映画の中身ですが、実在の人物ではなく、ハンガリー出身の別の建築家をベースにイメージした架空の人物だそうです。アメリカ映画は偉人を実名で映画化することが多いので、そこに拘る方も少なからずいらっしゃいますが、例えば、日本映画で言えば、山崎豊子さんの原作を映画化した場合は本作のような感じになるので、個人的違和感はありませんでした。
思ったよりも芸術映画って感じじゃなく、ゴッドファーザーのような、大河ドラマをイメージするとわかりやすいと思います。
215分観終えたときの満足感は最高です。
長いと思って敬遠してしまうと損します。
この逞しい演出力に引っ張られる
遥かなる、到達地へ
天才が故に、できたこと。
天才が故に、遺せたもの。
天才が故に、苦しんだこと。それは…
最近、気付いたんですけど、映画の主人公って、こういうキャラだよねっていう型に嵌めて、映画を観ている私がいます。(その型から大きく逸脱したのが「ジョーカー フォリアドゥ」。結果、ラジー賞にノミネート。私は、その勇気を讃えます。)
せっかく足を運んだのだから、何か得るものがある。映画館を出る頃の私は、どこまでレベルアップしているのかしら、なんて期待しちゃうわけです。でも、それは、考えようによっては、他者に期待しているだけで、自分に全く期待していない。挙げ句、期待ハズレだと、思いっきりコキおろす。そうでもしないと、存在の堪えられない自分に、気付いてしまう。他者を攻撃することで、自我を保とうとする。そんな過去の私が、フラッシュバックしそうです。
個人的に好きかどうかは、別として、濃い映画ですね。全く隙がない。張詰めた人間関係が続く。マーティン・スコセッシ並みに、観ているだけで、疲れます。ラースローが、そうであるように、この映画のプロデューサーと監督さんも、ある意味、天才かも。今時、こんな長い映画、よほどブレない意思がないと、出来ないよね。
ブレない何かを、持ち続けること自体、天才なのかな。何かを創ることで、何かを伝える。その何かが、よく分からない私です。(因みに私、大槻ケンヂの「人として軸がブレている」と云う曲が、大好物です。)
ところで、この映画のお金持ちおじさん、どう思います?。最初、ガチ切れしていた書斎、他者が褒め称えると、態度急変。あれはあざけ嗤うべきヒトなのか、あるいは、世間の価値観なんて、あの程度でしかないと云う皮肉なのか、どっちだと思います?。
何かを創ること。
何かを遺すこと。
他者に評価(及び、批判)されること。
その重圧を表現するには、やはりこれだけの時間とエネルギーが、要るようです。おかげで私の感想文も、インターミッションが要るレベルの長さになりました。
以上、映画には興味あるけど、建築にまるで興味のない私の感想文でした。
登場人物みんな業が深い、巨大建築の3時間35分
モダニズムとは何か
2024年。ブラディ・コーベット監督。ナチスドイツの迫害を逃れてアメリカに渡った著名なユダヤ人建築家が、不幸な境遇から這い上がっていく姿を丁寧に描く。一流の腕とセンスを持ちながら、親友に裏切られ、パトロンに振り回され、やっとアメリカに呼び寄せることができた妻は病に侵されていて、、、。
権力の塊のようなパトロンに見出され、次第に自らもその似姿になっていく主人公の姿には痛々しいものがあるが、主人公が構想する建築物と主人公の魂のあり方がいまいち説明不足な感じ。なぜあのような建築物を作ったのかの説明が、ユダヤ人の出自や妻の強制収容所体験といった「外面的でわかりやすい」説明のもとに回収されている。モダニズム建築を求める何か、もっと荒々しい心の叫びのようななにかが、あのコンクリート打ちっ放しの巨大建築物にはみなぎっているような気がする。そこはあえて不問にしたのかもしれないが。
才能ある「アーティスト」と「現実の権力」(金や生活)との相克、人生の不如意の話であり、具体的なモダニズム建築のありように迫っているわけではない。
タイトルなし(ネタバレ)
最近の映画でインターミッションがあるのは珍しい。建築やデザインに興味がある身としては、会話や展開が面白く、長さがあまり感じられなかった。バウハウス出身のユダヤ人エリート建築家が、祖国を追いやられ辿り着いたアメリカ。そこで直面する屈辱的な生活、実業家との出会い、妻への愛と苦悩、成功と挫折。ブルータリズムで有名なマルセル・ブロイヤーがモデルらしいが、途中から安藤忠雄の光の教会や、ダニエル・リベスキンドのユダヤ博物館が思い出されていたので、ラストの姪による建築の解説にはあまり驚かなかった。リベスキンドも本作を称賛したらしい。終盤の展開には驚いたというか、呆気にとられた。アカデミー賞作品賞、監督賞(ブラディ・コーベット)、主演男優賞(エイドリアン・ブロディ)、助演男優賞(ガイ・ピアース)、助演女優賞(フェリシティ・ジョーンズ)、脚本賞、撮影賞、編集賞、作曲賞、美術賞の10部門ノミネート。ブロディは2度目ありそう。個人的には『プリシラ』から好きなピアースにそろそろ獲ってもらいたいが『リアル・ペイン』のカルキンかなぁ…。さて、いかに。*追記:主演男優賞、撮影賞、作曲賞の3部門受賞!
1976年に建てられた改革派シナゴーグはサラッとしているけど意味は大きい
2025.2.26 字幕 イオンシネマ久御山
2024年のアメリカ&イギリス&ハンガリー合作の映画(215分、R15+)
ホロコーストを生き延びたユダヤ人建築家の半生を描いたヒューマンドラマ
監督はブラディ・コーベット
脚本はブラディ・コーベット&モナ・ファストヴォールド
原題の『The Brutalist』は「荒々しい建築を行う建築家」という意味
物語は、とある国境地帯にて、尋問を受けるユダヤ人女性ジョーフィア(ラフィー・キャシディ、成人期:Ariane Lebed)が描かれて始まる
彼女は叔父の建築家ラースロー(エイドリアン・ブロディ)についての質問をされていたが、訳がわからないまま精神的な圧迫を受けることになった
ラースローは強制収容所を生き延びたユダヤ人で、いとこのアティラ(アレッサンドロ・ニボラ)を頼って海を渡った
彼はアティラの経営する家具店で働くことになり、クライアントの要望に応えるために部屋の改築などを行なっていた
依頼主は資産家ハリソン(ガイ・ピアーズ)の息子ハリー(ジョー・アルウィン)で、ラースローは「ブルータリズム式の図書室」を完成させた
だが、そのことを知らされていないハリソンは激怒し、ラースローとアティラを追い出してしまう
さらにハリーは金を払えないと言い出し、この件にて、アティラはラースローを追い出してしまうのである
その後ラースローは路上生活を強いられ、炊き出しにてゴードン(イザック・ド・バンゴレ)と出会う
彼の息子ウィリアム(Charile Esoko、少年期:Zephan Hanson Amissah)らと過ごす日々が続き、期間労働として土木工事に従事するようになった
だが、そこにハリソンが訪れ、これまでの無礼を許してほしいと言う
彼は、ラースローが手がけた部屋の価値を知り、そして数々の功績を知った
そこでハリソンは、彼に自分のアイデアを話し、そのプロジェクトを引き受けてくれないかと打診するのである
映画は200分+インターバル15分の構成で、「序曲」「第1章:到達の謎」「第2章:美の核芯」「エピローグ:第1回 建築ビエンナーレ」という流れになっている
そして、「序曲」にてどこかの国境警備隊に尋問されるジョーフィアは、ラストでも登場するのだが、あのラストショットの意味は「ジョーフィアの到達点における出発点の想起」ということになるのだろう
ラースローとエルジェーベトから伝えられた「旅路ではなく到達点が大事」という言葉の意味を捉えると、叔父や叔母に感謝できる人生を歩んだことことがジョーフィアにとっての到達点だった、ということになるのだろう
映画は、前半でプロジェクトを任されるまで、後半でプロジェクトのトラブルを描き、ハリソンから強姦されるラースローが描かれていく
それに激怒した妻のエルジェーベト(フェリシティ・ジョーンズ)がハリソンに夫から聞いたことを突きつけるのだが、その後ハリソンがどうなったのかは描かれない
だが、この事件を機に、施設の存在意義がハリソンの母のためのものから、エルジェーベトやユダヤ人たちのためのものに変わっていて、それを告白するのが回顧展(1980年)となっている
俯瞰すれば、アメリカ人に金を出させて、ユダヤ人が考案して、奴隷が建設するという構図を暴露しているので、なかなか風刺が効いているように思える
ある意味、アメリカに来たユダヤ人のためのエルサレムをあの場所に建てたというようにも思える
行き場を失ったユダヤ人が権利を主張できるという文言が前半にあり、それによってイスラエルが建国されたという背景があるので、それをアメリカでも行なったとことになるのだろうか
劇中でも、エルサレムに帰ることが正義のように語るジョーフィアと対立するラースローがいるのだが、それに対するアンサーのようにも思えた
いずれにせよ、宗教に対する知識が必要な作品で、ユダヤ教徒のラースローやエルジェーベト、カトリックに改宗したアッテラ、プロテスタントであるハリソンなどの立ち位置というものがベースにある
ユダヤ人の迫害の歴史があり、アメリカに来るしかなかったという戦中戦後の状況があり、イスラエルの建国にまつわる話も登場する
このあたりに興味がないと苦痛の200分なので、観る人を選ぶ映画のように思えた
ちゃんとインターバルがあって、15分間用意されているので、生理的な苦痛は緩和できると思うが、精神的な部分はどうしようもないので、そのあたりの覚悟を持って臨んだ方が良い案件なのかな、と感じた
感動的な再会のその後
インターミッションがあって助かった。
もしなかったら座席が悲惨なことになっていたと思う。
「絨毯の方がまし」と怒られそう。
タイトルクレジットがオシャレ。
見たことない感じ。
芸術がテーマなだけある。
冒頭から「子供には見せられません」な場面から始まって、「この映画は大人向け」と宣言してくる作り。
重厚な人間ドラマで、大衆向けではないけど、こういうのが好きな映画ファンは多そう。
前半は「どんなに建築家としての才能があっても仕事がもらえなければホームレスと同じ」というシビアな話。
ただ、才能はあるので、一度才能を認めてもらえた後は順風満帆で、前半は可もなく不可もなく。
インターミッション後、数年が経過したところから再開。
ここから一気に面白みを感じた。
前半の会話中に出てきた人物が後半から登場するが、「なんか思ってた人と違う」感が凄い。
勝手に理想化していたこっちが悪い。
悲劇的な運命で引き裂かれた恋人が苦難の末に念願の再会、なんてしたらその後はハッピーエンドになるのが普通の映画だと思うが、この映画はその後がリアルに描かれていくのが興味深かった。
よくよく考えたら、ホロコーストを生き延びてアメリカへ渡ってまず最初に風俗に直行するような夫なわけで、年老いた妻と感動的な再会を果たしたとしても、恋愛感情が昔のままではない場合があっても不思議ではない。
人生がうまくいくかどうかは金持ちの機嫌次第という展開は、トランプ大統領再選後のアメリカと通じるものがあり、憂鬱な気分になった。
1950年代当時には早すぎたかも知れないブルータリズム建築様式の第...
1950年代当時には早すぎたかも知れないブルータリズム建築様式の第一人者のユダヤ人が、あたかもアメリカに実在してたかの様な不思議な映画。
「何んで こんなシーン入れたんだろう?」と何回か思った。バスタブに◯◯する、忍び足で後ろから近づくとか。後、不思議な音楽の使い方も特徴的。
そして奇抜なオープニング、奇抜なエンディング。
撮影も特徴的で上下逆さまの自由の女神像が直ぐに横向きに写される、歩く主人公の背中をひたすら追うカメラ、走る自動車や列車の目線、長い尺の映画なのに "省略" して観客に「どうして そうなった?」と想像させる。
私が観た回(12:10 - 15:50)は結構観客が多かった 珍しいビスタビジョンのフィルム撮影映画。
映画館で集中して見るべき作品。
※100分 → インターミッション15分 → 100分 (休憩中の15分の画面は撮影がOKで家族写真とカウントダウンがある)
※休憩中に読む冊子がもらえる
※ブルータリズム:コンクリートやレンガなどの素材をそのまま使用し、装飾を極力排除した建築様式
壮大などんでん返し
毎度お馴染みのナチス物。今年は「リアル・ペイン 心の旅」に続いて早くも2本目でした。
そんな本作の特徴は、何と言っても3時間35分というインド映画ばりの上映時間の長さ。近年劇場で観た映画の最長は「アイリッシュマン」の2時間29分、続いて「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」の2時間26分だったので、恐らく自己最長記録と思われます。ただそれら2作は休憩なしのぶっ通し上映だったのに対して、本作は途中15分の中入りがあり、トイレの心配もなく観られたのは幸いでした。
肝心の内容ですが、ハンガリー出身の実在のユダヤ人建築家であるラースロー・トート(エイドリアン・ブロディ)が、ナチスの迫害を逃れてアメリカに渡り、そこでも辛酸を舐めながら自分を貫き通して建築家として名を残すまでの半生を描いたものでした。
ペンシルバニアに辿り着いたトートは、最初従兄弟を頼って本職の建築の仕事を始めたものの、客からのクレームというか契約違反が原因で金を支払って貰えないという理不尽の結果、従兄弟とも決別。その後は日雇い仕事で糊口を凌いでいたところ、以前クレームを付けて来た大富豪ハリソン・ヴァン・ビューレン(ガイ・ピアース)に建築の才能を見出されてビッグプロジェクトを任される。でも芸術家気質の主人公は周りと調和が取れず、大富豪とも最終的に決裂。
また、後半になってヨーロッパに取り残されていた妻エルジェーベト・トート(フェリシティ・ジョーンズ)が姪っ子とともにようやく再会を果たすものの、夫婦仲はしっくりしなくなっていく悲劇。それでも妻は最後まで夫の側に立ち、寄り添っていたのがせめてもの救いでした。最終的に建築物が完成し、ラストは一応ハッピーエンドでした。
以上、祖国でもアメリカでもぶっ叩かれて半ば精神的におかしくなってしまった主人公・トートの物語でしたが、とにかく音楽や映像が特に素晴らしく、筋や役者の演技を際立たせていました。トートが作ったマーガレット・ヴァン・ビューレン・コミュニティーセンターの造形美は、画面を通してすら荘厳さが伝わってくるほどで、また大理石の採石場の場面なども、まるで異界に行ってしまったような浮遊感があって素敵でした。主演のエイドリアン・ブロディの演技も真に迫っていたし、彼を称賛し、嫉妬し、蹂躙した大富豪ハリソンを演じたガイ・ピアースの”アメリカらしさ”を地で行く演技も良かったです。
前述の通り、途中15分程の休憩を挟んでくれたことや、物語の展開が非常にテンポが良かったこともあり、3時間35分の長丁場も案外あっという間でした。
で、最後までトートが実在の人物だと信じて疑わなかった私ですが、鑑賞後に入場時に配られた「建築家ラースロー・トートの創造」という冊子を読んだら、なんと「本書の内容は一部を除きすべて架空の内容です」とのこと。まんまとブラディ・コーベット監督に騙されてしまうという壮大などんでん返しに、非常に驚いた次第です。
そんな訳で、本作の評価は★4.6とします。
215分は長く感じなかった
アメリカ映画は生きていた
空白の時間
ユダヤ人以外はどうみればいいのか?
数あるユダヤ人映画でも、これはホロコースト後の移民建築家を描くものであるが、架空の人物であるし長すぎる。観客にフレンドリーな語り手とはいえない。インターミッションを挟む映画体験は珍しいし、秀逸で斬新なカットや役に命を吹き込む俳優陣は讃えたいものの、脚本は頭が堅くて私の心にはなにも届かなかった。
移民の数々の苦難としてみてもどれも味があるようなないような演出で多くの場合であまり情も理も感じない。それどころかおそらく意図から離れるだろうが、それって民族差別だから、移民だからと言えるものなの?ってすら感じてしまうくらい描写が弱い。
が、ここは一旦折れて、彼らの苦しみを正面から受け止めてみる。彼らの希望までの苦難は狭く長い道のりなのだろう。建築物の哲学が自身の存在を物語るためには、あらゆる工程にこだわりを強くするのは理解できるし、妻や石工との衝突もわからなくない。しかし、ユダヤでないアメリカ人や日本人にとってその閉じた空想的構造物の物語から何を見出せばよいのか?我々の民族が同じ受難に見舞われることがあれば、きっと映画の外でも同じ気持ちになれるのかもしれないが。
詳しい解説はほかのレビューを参考にして気がつかないポイントを発見すれば評価も変わるかもしれない。しかし、この物語のいう「時代を定義した上で時を超えるもの」に普遍性を見出すまで縁もゆかりも感じない人々にとってはこの映画はどう扱えばいいのか戸惑いを隠せない。これが賞候補に上るのはなぜだろう。
そればかりか、多少厳しい言い方をするなら、この映画を体験してこの物語の構造を見抜いたり、思いを馳せたりしても畢竟、架空の人物物語で成り立っているのだし、下手に同情をするような観客にもユダヤ人は無だとしてるとメッセージを投げつけるようでは、非ユダヤ観客のユダヤについての映画を体験することを否定につながることにならないか。だったらこの映画を見ることもナンセンスになる。戦争や世界の悲劇を描いた作品が観客にそう言う映画ばかりならもうあまり関心を持つのも諦めたくなる。
さらに忌憚なく言うなら今のところアンチ反ユダヤの目線を多分に含んだスノビズムの民族高揚映画だと受け取っています。
全編に流れる薄明るい映像、彼の半生、彼の作品、タイトル、エンドロール・・・ 一貫したデザインが美しくも冷たい
第二次世界大戦後のアメリカを舞台に、ハンガリー系ユダヤ人の建築家ラースロー・トートの30年にわたる数奇な運命を描く。
来場者特典として配られたリーフレットから実在の人物かと思いきや架空の存在だったラースロー・トートは、同様の運命をたどったであろう人々の象徴として創造される。
15分のインターミッションを挟んだ前半・後半ともに100分という構成もまた建築の対称物のようだ。
さらにこの長さも、ラースローの半生を感じさせるために必要だった十分な長さである様に感じる。
彼がデザインしたとする家具から建造物、スタイリッシュなタイトルやエンドロールのタイポ・グラフィ、逆さまな自由の女神までもが彼の作品の美しさを表して、映画で描かれる、歓びが少なく常に苦悩に満ちて冷たい半生もまた彼の作品を思わせる。
統一された印象が薄明るく美しい。
大事なのは到達点であって旅路ではない
やっぱり長い
全208件中、101~120件目を表示