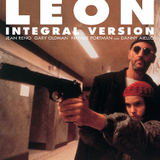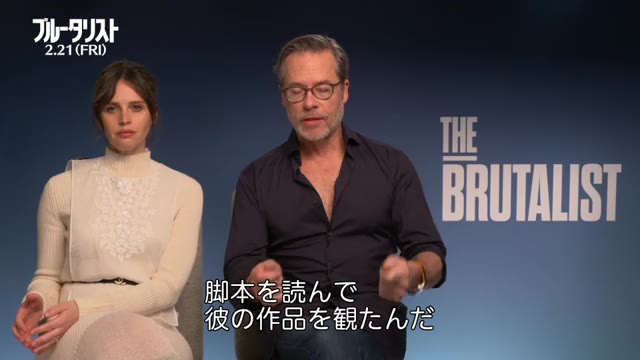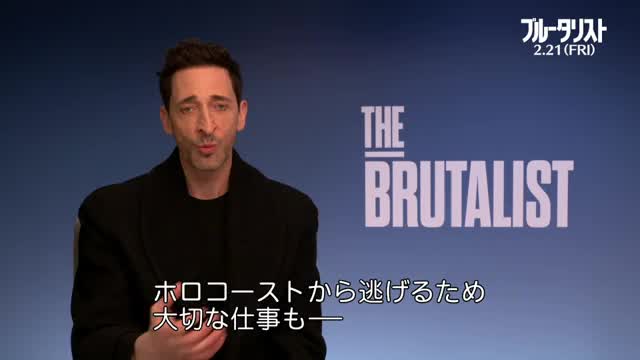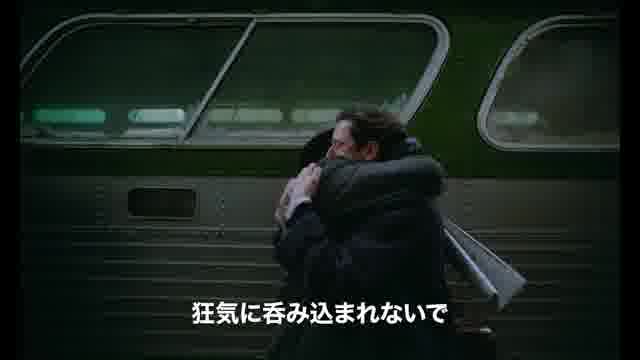ブルータリストのレビュー・感想・評価
全208件中、81~100件目を表示
A284 「2001年」以来のインターミッション
2025年公開
上映時間4時間弱!
絶対漏らすわ!
しかし注意書きで2時間弱で休憩に入ります、が
映し出され安堵。
で早朝上映だったので爆睡必至と思っていたのだが
結構見入れた。
ただ突き刺さる名作までは届かず。
ユダヤ人の話も欧米人程訴えられるわけではないので
インパクトにはならず。
ただ時間の濃さは凄い。出演者それぞれが物語に
浸りこんでいるなあ、と感心する。
それと最近は個人的に物語に外部ノイズが入るのが
嫌ではないんだがドキドキするもんで
しかし本作はこちらが想像できる線で抑えてくれているのも
ありがたい。
昨今のテレビ業界の正味1時間分しかないバラエティを
中身のないロゴ満載のうすーい4時間スペシャルとは
全然質が違う。比較するのも失礼なんだけどね。
クレジットがいわゆるパンフレット風になっていて
デザインの極致のような表し方も面白かった。
70点
鑑賞日 2025年3月2日 イオンシネマ草津
パンフ購入 ¥990
配給 PARCO/ユニバーサル映画
◇アメリカモザイク社会と建築物の構造
世紀のお騒がせ男-トランプ大統領は連邦政府が新設する建物は「人々の称賛を集める」古典主義建築が望ましいとする「美しい連邦公共建築(Beautiful Federal Civic Architecture)」と題された大統領令を発令しました。自らの趣味を押し通し、ブルータリズムやポストモダン建築のデザイン性を否定するような独断的大統領令に対して、米建築家協会は全面的反対を表明しています。
この映画の主たるモチーフである"ブルータリズム"は戦争と深い関係を持った建築様式でもあるようです。コンクリート打ちっ放しの幾何学的直線から成り立つデザイン。第2次世界大戦で荒廃した都市の復興の際、予算が不足していてもコンクリートは容易に安価に調達可能であり、大量に均一的に入手されたコンクリート建築には、短い工期で建設可能というメリットもありました。
主人公の建築家、ラースロー・トートは、明るい未来への希望を抱いてヨーロッパから渡米したユダヤ人です。しかし、理想やあるべき姿を明確に抱いた彼の設計姿勢は、アメリカの気まぐれな資本主義的妥協の産物社会の中で、大きく蛇行し取り止めもなく迷走を始めます。
多種多様な民族の寄せ集めであるアメリカ移民社会の特徴は、究極の相対主義なのかもしれません。多種多様な宗教や主義主張、民族的人種的な価値観の相違を越えて、資本(お金)こそが客観的な正義なのです。
215分という上映時間。100分(前半)+15分(休憩)+100分(後半)という建築物のように整然とした構成。建築家の天井高へのこだわりの種明かしを聞かされる結末に、この作品が独りよがりの建築家の伝記だけにとどまらずに、これからのアメリカ社会におけるそれぞれの生き様についての問題提起であると痛感しました。四角い部屋で分割されたコンクリートの教会は、人種や宗教、性別や貧富の差によって細かく分断されていくアメリカ社会を象徴するものでもあったのです。
とても上質で訴える力は強い映画だったが ぶっ刺さるところまでは至ら...
長さを感じさせない
インド映画顔負けの尺の長さ。
や、これは水分取らないでおこ、と。
でもインド映画にはないインターミッションがあった!
しかもたっぷり15分。
実話かと思ったが、創作?
渡された特典パンフを見てうっかり騙されそうになったわ。
実在の建築家かと。
しかしハンガリーからアメリカへ。
必死の思いで船に乗って来たユダヤ人は実在しただろうな。
アメリカ人には理解出来ない薬に頼ざるを得ない彼らの苦悩。
幸せになるかと思いきや…
ちょっとわからなかったのは最後の奥さん殴り?込み。
薬漬けなのは旦那さんだったのでは?
そしてキャラ変した姪っ子。
アメリカ映画の伝統とは
この作品、物語の筋はある意味移民にまつわる非常に伝統的なアメリカ映画である。正直何かすごい意外性があるタイプの映画ではない。ただ、作品のスケール感、音楽、映像、演技のクオリティが素晴らしく、映画を観ていることの充実感が非常に高い。
なぜ私がこの作品をアメリカの伝統的映画と言ったか。この話は呪いの物語だからだ。一つは権力の呪い。そしてもう一つは芸術の呪い。
権力についての物語は何度も何度もアメリカ映画史の中で語られてきた。市民ケーン、ゴッドファーザーパート2、ゼアウィルビーブラッドなどなど。権力を手に入れれば入れるほど、その人物は幸せになるのではなく、呪われていく。そのことをわかっていても止められない。権力のゆがみのようなものがこの映画でも何度も描写されている。なぜそのような物語が何度も何度もこの国では作られるのか?それはアメリカという国家の覇権国としての力と、そこからくる苦悩がいつも物語の根底に流れているからだ。アメリカ映画はキャラクター、物語というメタファーを通してアメリカという国家を映し出す。
富豪のハリソンと建築家ラースローはどちらも呪われているのだが、その呪いの種類が違う。ハリソンはまさにトランプ的なアメリカの権力志向のマッチョイムズだが、ラースローの場合は自分の究極のアイデアを形にすることに人生をかけていて、そのためにたくさんの物を犠牲にする。それは宮崎駿の風立ちぬで主人公がたくさんの人が不幸になっても自分の究極の飛行機を作るという夢をあきらめられないのと同じである。彼は「美」に仕えている。ただ、そのためにはハリソンという悪魔との取引が必要であり、それにより彼はむしばまれていく。それはもちろん、映画監督という仕事の狂気、この作品を作っているブラディ・コーベットの自分自身への言及でもある。
クレジットタイトルのグラフィックデザイン、映像と音楽のクオリティから感じる野心。わざわざ、ビスタビジョンのフィルムで撮った映像(現代の映画はカラーグレーディング処理により色とライティングをを演出のために統一させすぎて、逆に色の豊かさにかけているという事を今作では思い知らされる)で、超大作のような映像のスケールをこんな規模の作品でやってしまう度胸。
例えば一昨年のトッドフィールドのTARのような本当に表現自由度の高い作品は確かに今の時代にもある。ただ、そのトッド・フィールドにしても、アリ・アスターのようなA24関係の作家であっても、実はちゃんと観客にショックを与えるようなツイストやギミックは用意しているのだ。ある意味タランティーノ、ポール・トーマス・アンダーソン以降のアメリカインディペンデントの映画のあり方とでも言えるだろうか。私はPTAの大ファンだし、それが悪いと言いたいのではない。ただ、今の時代はそういう映画しかないのが問題だと思う。逆に映画表現の自由度がせばまっているような気がするのだ。
文学作品のように個人的な物語を積み上げて積み上げてゆっくり、しっかりと見せていくという、昔なら当然のようにあった映画のストーリーテリングをやるのが現代では逆に勇気がいることなのではないか。他人に刺さろうが刺さらまいが、巨費がかかろうが、自分が信じる物語を自分のために作る。そこに映画という芸術の素晴らしさと狂気を同時に感じる。私はここらへんで、やはりマイケル・チミノやテレンス・マリックの70年代の作品を思い出さずにはいられなかった。
あと、最後にもう一つ。この映画の最初の自由の女神のシーン。音楽とともに、本当ならとても開放感があるシーンとなるはずだ。ただ、私はこの映画を2025年の3月2日に見た。つまり、アメリカが自由の国では最早無いのではと、世界中が感じている中で見た。だから、あの逆さまに移された自由の女神のシーンには開放感よりもむしろ不穏さがあり、複雑な感情になった。そして、実際にこの映画は主人公と妻にとってアメリカは彼らが思っていた国ではなかったという結論へと向かっていく。ハリソン家の東欧移民への態度にもそれは見て取れる。私は見終わった直後、この映画は普遍的ではあるが、同じ「アーティストと権力」をテーマにしたTARと比較すると現代性が欠けているのではと思っていたが、実はそうではなかった。この映画はひょっとしたら時間が経つとともに、更に深い意味合いを帯びてくることになるのかもしれない。
シオニズムの映画、建築家の映画、芸術家とパトロンの映画、そして反トランプの映画……。
とても「豊かな」映画だと思う。
何が「豊か」かというと、
「時間」の使い方が。
すべてのシーンにおいて、ゆったりと構えて、
じっくり、手をかけて撮ってある。
時間の制約を気にせず。撮りたい間合いで。
きょうび伝記映画で、こんな「贅沢」な時間の使い方をする映画は本当に稀なので、そこはとても心地よかった。
「映画がいくら長くなっても全く気にしない」という前提で、無尽蔵に、時間というリソースを使って撮り上げる、おおらかなスタイル。
なんていうか、「源泉かけ流し」の温泉みたいな「豊かさ」を感じる。
あるいは「拾い放題」の果樹農園のような。
ふだん気にかけていることを、気にしないでいい豊かさ、とでもいうのか。
なぜか昔から、映画業界というのは「上映時間」を異様に気にする業界だ。
なるべく長くなりすぎないように。
客の飽きがこない程度の長さで。
コンパクトにまとめていくのがベター。
そう考える上層部と、長尺で撮りたい監督とのあいだで、今までにどれだけの激しい衝突と闘争が繰り返されてきたことか。
その「せちがらさ」から、
なぜか『ブルータリスト』は
完全に「解放」されている。
インディペンデント映画の、
インディペンデントたるゆえんである。
上映時間が何時間になろうが、まったくかまわない、
そんなことはどうでもいい、気にしない、考慮だにしない、
とにかくすべてのシーンを、撮りたいテンポでじっくり撮る。
そのことを優先して、結果長くなったところで、観てくれる人はちゃんと観てくれる。
その確かな理念に基づいて、本作は「自由」に撮られている。
凄いな、と思うのは、主人公であるラースローの人生を描くために「とりたてて必要のない」ようなシーンまで、じっくりと腰を据えて撮っている部分だ。
すなわち「主人公の人生を語る」ことだけに汲々としない。
3時間半の映画を、2時間半にするために、切り詰めない。
思えば、僕たちは、あまりに「説明的」で「せかせかした」映画に慣らされてきたのではないか。たとえば、マーティン・スコセッシのような。
本作の間合いは、たとえばベルイマンやヴィスコンティといった監督に代表されるような、欧州のテンポ感であり、語りの感覚だと思う。アメリカ人の撮った21世紀の映画としては、なかなかに得難いものだ。
結果として『ブルータリスト』は、
そこまで劇的でも、派手な話でもないのに、
観ると3時間半もかかる、不思議な映画となった(笑)。
収容所生活とか、脱出劇といった要素は敢えて、前段階の要素として捨象される。
物語は、無事に到着するところから始まり、そのまま主人公はさくっと従弟の家に迎えられる。
家具製作の手伝いを始めてからも、大きな波乱めいたものはない。
なんとなく、従弟の奥さんから嫌われるとか。
(この辺、ちょっとエミール・クストリッツァの『アンダーグラウンド』っぽいかも)
施工主と、リフォームで衝突するとか。
結果的に、家を追い出されることになるとはいえ、
「いかにも映画らしい波乱」があるわけではない。
そこからも、起きることはどれもちっぽけだし、世界観は常に狭い。
「復活劇」といっても、喧嘩した施工主が気を変えて雇い直してくれただけの話だし、結局映画のなかでは、ひとつの建物を延々ちまちまと作っているだけだ。
2時間くらい経って、ようやく奥さんと姪っ子がアメリカに渡航してくるが、ここにも劇的な要素は何もない。ふつうに電車で着いて、部屋も与えられ、基本よくしてもらえている。
終盤の展開も、切迫感があって濃密ではあるが、お話としてはむしろ広がりをもたず、「個」と「個」の精神的な闘争の話に終始している。
こういう、「大きな物語」をあえて志向しない映画を、3時間半の長尺で撮って、飽きさせず、満足感を与えて綺麗にまとめるというのは、想像以上に難しい作業だ。
若い監督にはなかなかできないことだが、それをブラディ・コーベット監督は成し遂げてみせた。
アカデミー賞候補に挙がるのも、むべなるかな、と思う。
― ― ― ―
●一義的に言えば、『ブルータリスト』は、シオニズムの映画であり、真正面からユダヤ人移民の苦悩を描いた映画である。
わざわざ主人公に『戦場のピアニスト』で一度亡命ユダヤ人役を演じたエイドリアン・ブロディをふたたび起用してまで、「これはそういう映画だ」と、これ見よがしに強調してきている。
エイドリアン・ブロディは、おそらくあの「巨大な鼻」のせいで、欧米人から見ると本当に「ユダヤ人らしいユダヤ人」なのだと思う。
ついこのあいだ、ブラッドリー・クーパーがユダヤ人のレナード・バーンスタインを演じるにあたって、「つけ鼻」を用いたという理由でバッシングされたことがあった。裏を返せば、それくらい「大きな鼻」はユダヤ人のアイコンとして欧米で深くしみついた共有イメージだということだ。そういえばフランス映画の『ふたりのマエストロ』でも、ユダヤ人親子役には巨大な鼻をもつユダヤ系俳優が起用されていた。
逃亡時にブロディの鼻が一度「折れて」、その痛みに耐えるためにヤク中になるという展開は、まさに「ユダヤ人であるがために人生をへし折られた」主人公の暗喩である。作中では、もう一回彼が「鼻を傷める」シーンが出てくるが、やはりこれも彼のキャリアの挫折と呼応している。
●それから、この映画は、「建築」の映画でもある。
丘の上に、ひたすら大型の建造物を建て続ける話という意味では、ケン・フォレットの『大聖堂』をどうしても思い出さざるを得ないが(あれは12世紀中葉を舞台に、イギリスの架空の町で一人の石工が大聖堂を建築するまでの群像劇だった)、本作で扱われているのは、「ブルータリズム」建築(コンクリートを用いた無骨な外観のモダニズム建築の一様式)だ。
なにせ、本作のタイトルは『ブルータリスト』。わざわざタイトルに付すくらいに、監督にとって主人公のこの属性は重要だということだ。
主人公のラースロー・トートは架空の人物だが、その経歴に関してはハンガリー出身でドイツからアメリカに渡ったブルータリズムの建築家、マルセル・ブロイヤーと共通する部分が多い。
ユダヤ人で、バウハウスでグロピウスのもと学び、戦争を機にアメリカに渡り、鉄パイプを曲げたモダンな椅子をデザインし、うちっぱなしのコンクリートを素材とした建築を得意とした著名な建築家。
おそらくなら、ラースローという人物は、ブロイヤーの人生を土台に、監督がさまざまな亡命ユダヤ人の物語を重ねて作り上げられたキャラクターということなのだろう。
50年代にブルータリズム建築が流行した背景には、戦後の経済的に厳しい時代にあって、資材であるコンクリートが著しく安価だったということがある。これは、50年代アメリカの変革を描こうとする本作でも、結構重要な要素だと思う。
華美で旧弊な上流社会が、モダンで大衆的なデザインと美学を獲得していく過程においてもまた、資本主義が密接にかかわっていることが如実に示唆されているからだ。
実は、これは舞台芸術においても同じことが言われていて、ワーグナー楽劇における新バイロイト様式の発端には、極度の資金難とコスト削減の必要性があったとされる。
ブルータリズムと新バイロイト様式。資本主義の「負」の要素が、芸術の新たな動きを加速させたというのは、興味深い現象だ。
なお、コンクリートの打ち放し建築といえば、日本人なら誰しもが安藤忠雄を思い出すはずだ。
独学で構築された彼の建築美学は、どちらかというとル・コルビュジェからの影響が強く、必ずしも50年代~70年代のブルータリズム建築の継承者とは考えられていないようだが、今回の映画できわめて重要な建築上のアイディアとして扱われる「光の十字架」は、まさに安藤忠雄のトレードマークのようなものだ。
茨木春日丘教会の壁に穿たれた「光の十字架」がつとに著名だが、淡路島にある「海の教会」では、十字架型の天井採光から差し込んだ光が壁に「光の十字架」を浮かび上がらせるという、まさに本作に出てくる大聖堂と同じ意匠が用いられている。
現在、アメリカでは安藤忠雄に建築を依頼するのが、大富豪にとっての最大のステータスともきく(カニエ・ウエストとか、ビヨンセとか)。コーベット監督がブルータリストを題材に映画を製作しようと思いついたときに、同じ打ち放しのコンクリート建築を得意とする安藤の仕事が脳裏をよぎったということは、十分に考えられるのではないか。
他にも、本作に「建築」にまつわる要素は多い。
たとえば、バウハウスといえば、本作に特徴的なデザイン化されたオープニングとエンディングのクレジットは、まさにバウハウス的な美学に彩られている。
オープニングの洒落た処理にも感銘を受けたが、斜行するエンドロールというのは人生で初めて観たので、おおいに驚いた。
あと、建築絡みでいうと、ラストで捜索隊が到達する市民センター兼大聖堂の「地下」空間は、明らかにオーソン・ウェルズの『オセロ』に出てくるアル・ジャディーダの地下貯水槽を意識してるよね……?? この監督さん、実はかなりのシネマフリークではないかと思う(なにせ、わざわざハンガリーでフィルム撮りして、ビスタビジョンを採用しているくらいのオタクぶりである)。
●それから、この映画は、芸術家とパトロンの関係性を描いた映画でもある。
本作における新興の大富豪ハリソンは、単なる「悪役」として描かれているわけではない。
資本家であるがゆえに、芸術にあこがれ、新奇な創造に焦がれ、天才に執着する、ある意味とても「人間味のある」パトロンとして描かれている。
一方で、主人公のラースローもまた、一筋縄ではいかない人物として描出される。彼があちこちで厄介者扱いされるのは、単なる出自の異質性のみに起因するものではない。自堕落で、傲岸で、短気で、恨みがましい。しかも重度のヤク中である。天才であるのは間違いないが、やりにくい人間であることに変わりはない。ハリソン一家からすれば、たしかに、「われわれは十分あなたに我慢させられている」と言いたくなるようなキャラクターだと思う。
そのなかで、監督はきわめて粘っこく、「才能はあるけど社会不適合者の天才」と「成功者だが芸術的センスをもたない俗物」の、数十年に渡る精神的闘争を描き込んでいく。
そこにあるのは、敬意と嫉妬、支配と被支配、援助と恩義、実際的な用途と芸術的な要請のせめぎあう、熾烈でインティメットなマウント合戦だ。
僕は意外とガイ・ピアースが熱演するハリソン氏を嫌いになれなかった。
大理石鉱山での「アレ」も、どうしても手の届かない天才を、なにがなんでも征服したいという妄念が劣情へとねじ曲がったとすれば、なんだか可哀そうな気すらしてくるくらいだ。
●で、最後に、本作は反トランプの映画でもある。
そもそも、ブルータリズム建築はトランプが前政権時に「醜い」とレッテルを張り、連邦政府の建物は「美しい建築」(=古典様式)にしなければならないとする大統領令を出したいわくつきの建築様式だ(翌年バイデンが取り消し)。監督はこの件に言及したうえで、「人々を苛つかせる」からこそテーマにしたかったと述べている。
共同脚本家のモナ・ファストヴォールドが、ハリーJr.役の若手俳優について「ジョー・アルウィンは初めて起用した俳優だけど、彼の演技を観てすぐに、まるでトランプ支持者のような姿を見ることができて安心した」と言っているくらいで(笑)、ハリソン一家とその仲間たちをトランピストに見立てて、ユダヤ人建築家との差異を際立たせ、やがて「愚弄」する「明快な意図」をもって作られた映画であることは間違いない。
本作のラストはまさに、「親トランプ的人物」に復讐したいという、リベラル寄りの制作者の「怨念」の発露でもあるだろう。
個人的に、そういう映画の作り方自体は気に食わないけれど、「だからこそ」この作品はアカデミー賞にもノミネートされている、というわけだ。
なお、今年のアカデミー賞の「傾向と対策」については、また別のところで書いてみたい。
知識が無くても色々感じることはできる
日本での公開前から数々の映画賞受賞やノミネートが報じられ、絶賛の声を多く目にしていた本作。215分という長尺で、インターミッションを挟むほど。
ホロコーストを生き延びたユダヤ人建築家の半生を描いた本作は、語られる台詞は詩のようでもあり、綴られるストーリーの構成は小説のようであり、いくつか登場する建築は絵画のようであり、総じて美しくて哀しく強い想いを感じる作品でした。
正直理解できていないことも多々あり、これから深掘りすることで捉え方が変わることもたくさんあると思います。また、やっぱり尺は長いと感じたし、物語として面白かったかというと、そうではなく。ただ、様々な想いを抱えながら口数の少ない主人公のトートを演じたエイドリアン・ブロディと、彼の恩人でもあり加害者でもあるハリソンを演じるガイ・ピアーズの演技は細かいところ抜きにして素晴らしく、強烈に印象に残っています。また、建築物をはじめ、構図やカットに監督の作家性が炸裂しており、ビジュアル面でも見応えがありました。
映画館で観て良かったです。
演出が凄くよかった
オープニングのクレジットがかっこよかった。文字のフォントを美しく同一にしつつ、人名など箇所によって字間をわざと広めにとってた。クレジットの中を建築の立方体なり直方体の柱みたいな黒い線(縦とか横とか)が走っている。章立てを表す文字は大き過ぎずかっこよかった。タランティーノとかファティ・アキンの映画の章立て構成は好きだけど文字でか過ぎ。斜めエンディングクレジットは初めて見た。オープニングと異なり字間のバラバラはなかった。映像は手持ち&固定カメラ、俯瞰、顔の大アップなど色々上手く使って光は自然光(的な)明かりが多く、話の場面転換に合わせてわかりやすく繋がっていた。一番いいと思ったのはサウンドデザインで、50年代にアメリカで流行った歌、本映画のテーマ曲変奏、ダンス音楽、効果音などよく考えられていて映画にテンポと雰囲気を与えていた。無駄なシーンがなくてポンポンと話を進ませているのがよかった。テーマの核がコミュニティー・センター建築に絞られていたからか、上映時間の長さは感じなかった。
1900年初頭や第一次世界大戦以後でなく、第二次世界大戦後にヨーロッパのハンガリーから、それもユダヤ人として移住したアメリカ合衆国はラースローにとっては醜悪に映ったろう。ラースローはブダペストの人だ。ブダペストの美しい町並みに比べたらアメリカ合衆国のどの町も建物も醜い。
アメリカ合衆国はマッチョだ。ジェンダーとしては「男」、レイプする側。ラースローの周囲の人間関係もそんな風に見ることができる。従兄弟のアティラとラースロー、顧客ハリーとアティラ、ハリーの父のハリソンと息子、ハリーとラースロー、ハリソンとラースロー;左はジェンダー的に男、右は女、別の言葉でいえば、支配者(強者)対被支配者(弱者)の関係性だ。(よく泣くラースロー、でも泣かなくなるとかなり支配的な言動になるが)ほぼ常に弱者側のラースローはハリソンもハリーも持っていない教養と美意識と譲らない頑固さを持った芸術家だ。ハリソンは雑誌でラースローが著名な建築家と知ったから態度を変えた。サプライズで息子が依頼した改装された図書室を自分で判断できない。同じ角度で開閉する木製のドアが各々の本棚につけられ、本が色褪せない為の厚ぼったい赤カーテンは取り外され、光を優しく通す白の薄物生地のカーテンが取りつけられている。天井窓からは外光が入りその真下に置かれた読書灯付きの一脚の長椅子は、ミース・ファン・デル・ローエとコルビジェとペリアンとアールトとマッソンとスタムの椅子を混ぜたようなデザイン。サプライズが嫌い、大好きな母親用の部屋にしたかったマザコンのハリソンは新しい書斎の美に気づけない。施主としてパトロンとして彼を雇い入れることでハリソンは辛うじてラースローの上位に立てる。ラースローの意見や提案を尊重する一方で、想像力が欠如していて思いつきだけ、辻褄が合わない、理不尽なアイデアしか出せない、金をいきなり出し渋るなどわがままで嫉妬深い暴君でもあった。
そのハリソンを徹底的にどん底まで突き落としたのはラースローの妻のエルジェベートだ。ラースローは妻との関係でもジェンダーは女、「男」はエルジェベートの方だ。オックスフォードで学び教養があり新聞社で記者として働いていたインテリ、英語も夫よりずっと流暢、何より自立した強い女性だ。それでも夫のためにエルジェベートがあそこまでやるとは思わなかったので驚愕した。
この映画の最後、ヴェネチア・ビエンナーレで開催された国際建築展でラースローの姪が述べる言葉「大事なのは到達地だ。旅路ではない」は、アメリカで差別されプロジェクトもなかなか進まず苦労したラースローのことだ。姪はイスラエルに行ったがラースローは行くとは絶対に言わなかった。ラースローはシオニストではない。でも姪の口を通すと「到達地」はイスラエルになってしまう。違う、極めて限られた文脈でのラースローの言葉だ。私は到達地がどこ・何であろうが到達できなかろうがどうでもいい。寄り道しながら色々なことをして人に出会って動いたり止まったりする旅路を歩めればいい。ある地を定めてそこに「安住」したいという気持ちは持ちすぎない位がちょうどいいと、サイード関連の映画で私は学んだ。
......................................................
(2025.03.03.)
アカデミー賞の主演男優賞、撮影賞、作曲賞の受賞、おめでとうございます❗️
思ったより混んでいた。インターミッションがある映画は久しぶり。なか...
劇部分とインターミッションの構造は天井から射す光のメタファーー?
覚悟してみてきましたが、215分という長さをほぼ感じさせない作品でした。
ユダヤ人建築家が戦後アメリカでどのように生き抜いたかを描く作品で、迫害から自由の国に渡り、新天地でも厳しい扱いを受けるものの、最後は目的をやり遂げた男の話としてとらえるのが正しいのでしょう。
家具屋の職人として再出発してから建築家としての資質を見込まれ、軋轢を生みながらも大きなプロジェクトを動かす。一癖二癖もあるキャラクターたちが織りなす濃厚な物語は、ひと時も飽きさせるものではありません。
また、大規模建造物や広大な石切り場など印象的な映像はその壮大さや美しさだけでなく、その制作過程を考えるとそれを作り上げたスタッフの苦労がしのばれ、観るものを圧倒します。
215分という上映ですが、前半100分・インターミッション15分・後半100分とキッチリ分けられているのは建築をテーマにした作品として意識されたものかもしれないなと感じております。インターミッションは、劇中の建造物の象徴的な部分である、コンクリとコンクリの間のガラス部分のようにも思えてきます。
期待度◎鑑賞後の満足度◎ 久しぶりに実に(正に)映画らしい映画を観た印象。一人の建築家の半生がスペクタクルとしてスクリーンに刻まれている。エイドリアン・プロディは好きな顔ではないが名演。
①210分という長尺だから覚悟して観に行ったけれども少しもだれるところがなく画面に引き込まれた。
昔の長い映画の様に「INTERMISSION 」を設けてくれたのも良かったのかもしれないが、それが逆効果になって冗長な映画はる可能性もあったのに、ならなかったのはやはり監督の演出の力量だろう。
②全編をユダヤ人であることの影が消えない雲の様に覆っている。
昨今の欧米や中近東の映画を観ていると、もはやユダヤ人問題に絡まないものが少数派になっているように思われる。
本作も冒頭のナチのホロコースト(完全なる自由の剥奪)から始まり、アメリカに来てもユダヤ人、ユダヤ教に対する白人(キリスト教徒)の声には出さない差別・偏見に陰に陽にさらされ道を塞がれそうになり、真の自由は得られない。
その生きづらさから姪は新しく出来た母国「イスラエル」の地へと旅立っていく。ロシアの捕虜収容所でもアメリカの大富豪の庇護のもとにあっても頑なに口を噤んでいた彼女がユダヤ人にとって自由の国である「イスラエル」に旅立つ時には(そしてラストも)饒舌になっているのが象徴的である。
③ハリソンに「何故、建築家になった?」と問われた時の返答、「時代がまたおかしな時代に戻っても建物はその美と思想を遺すものだから(だったかな?)」(またまたナチみたいな狂った連中が出てくる時代になったら壊されるんじゃない?という危惧が喉まででかかったけど)、ホロコースト時代の完全な自由の剥奪、自由の国アメリカなのに強いられる不自由さ、それがエピソードの姪のスピーチで一気に繋がる。
アメリカで最初に設計した「コミュニティーセンター」が強制収容所と同じスケールだったという事実、ホロコーストで完全に奪われた自由、アメリカでの鎖に繋がれた自由、ナチ収容所と同じスケールで作られた建物に設けられた“自由への窓”“太陽光で作られる十字架”…
新しい「コミュニティーセンター」は本当の自由への“希望・渇望”と、ナチに完全に破壊された美と思想とを未来に遺したいというトートの思想を体現するものだったということが最後の最後で分かる構成。だからあれほど建物の寸尺に拘泥したのも頷ける。
④フェリシティ・ジョーンズもいよいよ本格的な女優になってきた感じ。
⑤アレッサンドロ・ニボラも最近あちこちの作品に出てくるようになって若い頃から注目してた私としては嬉しい限り。そのうちアカデミー賞助演男優賞でも取ってくれないかな。
⑥エイドリアン・ブロディは、ダニエル・デイ=ルイスが引退した今では欧米の映画で最も演技力のある男優トップに立ったかも。
⑦ガイ・ピアースも好演だが、大好きな『プリシラ』のイメージをまだ引きずっているので(私がですよ)ちょっと変な感じ。
⑧個人的には、ああいった角角したデザインの建物は好みではないが、まあそれは映画の出来とは違うので。
鑑賞動機:賞レース10割
上映時間に恐れをなしていたが、インターミッションありということで、鑑賞に踏み切った。
美しい建築が必ずしも利用や管理がしやすいものではないというのを、毎日嫌というほど味合わされているので、光の十字以外は正直ピンとこない。
時間も長い上に余白も多い。その上、終盤やエピローグで明かされることを額面通りに受け取るのは危険に思えた。当然意図はあるのだろうが、単純に割り切れない部分も多いように感じた。
追記
主演男優/撮影/作曲
撮影は序盤の長回しからの自由の女神差し込んできたり、逆に建造物は短いカットで切り替えたり、編集含め色々やってるなとは思った。
作曲も合間合間で妙に耳に残る…耳につく曲が流れてて、意識させられたけど。
難解な事なく、意外と力作♪ が、後半に問題あり。 ★3.7
「TAR/ター」ほど難解でなく、「哀れなるものたち」ほどグロくなく、「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」ほど冗長ではない。 意外にじっくり見せる力作だった。
タイトルは、ブルータリズム建築と、
Brutal(粗野な、厳しい、冷酷な)ist(~な人)を掛けた意味かと。
さすがに長いと評している方もいるが、私はそう感じなかった。
迫害を感情のベースとした物語に、建築家としての腕の見せどころが相反する進展にオリジナリティーを感じ、ゆったりペースだがかなり引き込む。
ブロディーは喜怒哀楽全ての表情を見せた。 が「TAR/ター」のブランシェット同様で熱演には間違いないが、唸るような名演技に見てる方も同調した・・ほどには感じなかったのも事実。 (でもアカデミー主演男優は獲りそうな予感)
↓序盤展開含む
ただ冒頭のみ私には酷く感じた。
夢の国への船内は暗く、到着時になにがどう動いているか分からぬ描写で、いきなりマイナスポイントに。
そして明るく現れたニューヨークのシンボルは 逆さま?
何意味するのか思考中に、今度は横向き!(予告で流れるが私は初見)
「何だこの演出?」
このシーンは建築物を多方向からの観察、と評価している方もいるが、
私的にはビデオカメラを初めて購入した者が、遊んでいる様なとても稚拙な演出に感じた。
日中でも暗いシーンが続き、娼館でのリアル性描写もこの作品には不向きで、掴み映像としているなら、それは悪手。
ラジオナレーションがホロコースト状況を伝えながら映像も動き、両方の解釈に神経を使う為、作品そのものが入って来ない・・。
これは楽しめるというより、我慢する3時間になりそうだと、序盤からため息が出る・・。
が、その後家具店に赴くシーンからようやく物語が動き出し、引き込む。
一度は憤怒した資産家が、謝罪の為合うシーンは、前半一番の起伏ポイントで見所♪ 自身の過去建築写真を「もらってもいいか?」との台詞が、
グッと来て一番感情が傾いた。
それは自身の輝かしい履歴書であるから。
こういう描写が随所で存在すれば、文句なしの作品賞候補になっただろうと・・。
前半だけなら★3.9~に評価。
が、問題は後半でそれにより★減点
↓後半ネタバレ含む
「暗」に展開するのは致し方ないとしても、急転する様なシーンが増え始める。
談笑から、作業員に憤慨・・。
大理石断崖の美しく素晴らしい絶景をじっくり描写せず、作業所でのダンスパーティー?
採掘決定の祝宴にしては、娼婦の様な女性との唐突な絡み。
その後の暗シーンで、はっきり分からぬ描写が、LGBTとは!
序盤の家具店主との妙にベタベタした動作や、
娼館での性描写・ダンス女性を相手のしなかったのは、その伏線?!
にしては唐突過ぎるし、実業家ピアースにはそんな素振りが全くなかった様に思う。
そして結末は私が他作レビューでもよく批判している「逃げ脚本」・・。
(主要人物の死を持って作品に重厚感を増す、安易な脚本)
後半まで視聴者を引きつけるアイデアが持続せず、
アカデミー作品賞必須項目の "マイノリティ要素" を無理矢理挿入したイメージで、急に冷めてしまった。
エピローグでも建物実物の全体像を見せず、小さな大理石に十時が差すだけの描写。
実在の名建築家「安藤忠雄」設計 ”光の教会” を知っている者なら、
十時光サイズを小さくしたパクリじゃないかとすぐ分かる。
結局、圧倒する"物"は見せずに終わった後半に、★評価が下がるのも止むなしに。
ただ、この人物と物語は非情に独創性があり、
脚本を少し手直しして脇役にも魅力ある者を登場させ。
もっと年期の入った監督が撮れば、
映画史に残るような傑作になった予感もするので、非情に惜しい作品だとも感じた。 (コーベット監督はまだ若干36歳)
もしコーベットが作品賞の対象となる事を意識してこの脚本を書いたなら、もうアカデミー作品賞必須マイノリティ項目はハリウッドの為にも排除した方がいい。
トランプさんが米大統領に返り咲いて、この世に性は「男と女の2つしかない!」と明言して、
トランスジェンダーの女性競技参加を廃止したのを機に、
アカデミーも不要なLGBT推進の波が静まればよいのだが・・。
PS
劇伴がよいと評価している方も多数いて、
確かにそのシーンの雰囲気にインスト曲が合っている場合も多かったが、
音楽好きな私には違和感を感じた場面も複数。
まず家具店内。
高額品を売る店では、早いテンポの曲はほとんど流さない。
(会話の邪魔をしてノイジーに聞こえた)
落ち着いて品定めするには、スローな曲が必須。
丘の上からピアースが夢の提案を語っているのに、
不協和音の様な不安を醸し出すBGM。
ここは聞いてた者に拍手させ、メジャーコードの盛り上げる曲を流す方が、
見る者は感動するのでは?
後に出る資金面等の不安要素を暗示しているのかもしれないが、
初めて見る者には、まず違和感が湧き、使うのが早すぎたイメージが。
エピローグ開始時点での、シンセサイザー音の様なエレクトロポップはいくら何でも今作には不向き。
エンドロールがまだ終わらないうちに、曲がストップ。
その後もそこそこ長く文字は続く。
やはり違和感が。
斜めの文字列と共に、若い監督が安直に奇をてらってる様に感じた。
たしか「TAR」もエンドロールに凝っていた様な・・。
もし私がエンドロールに凝るなら、
文字列を全て、個別の "四角い長方形の塊" にして、文字で建造物を表すだろう♪
姪っ子はいつキャラ変したの?
ブルータリズム
全208件中、81~100件目を表示