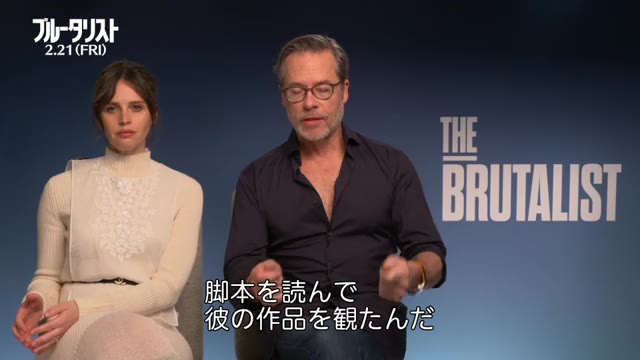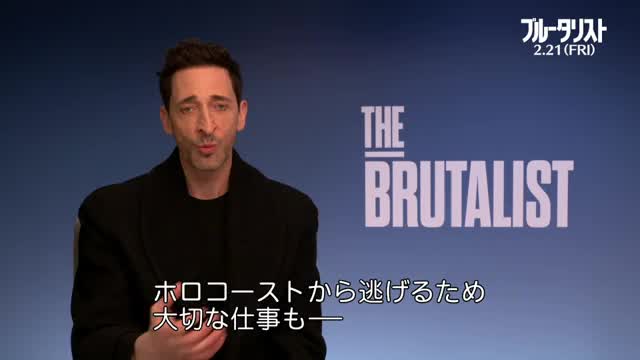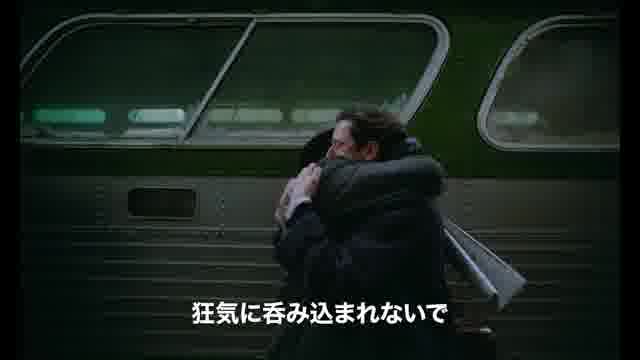「それは真の解放を求めた人間の切なる思いを反映した建物なのかあるいは忌まわしき資本主義の墓標なのか」ブルータリスト レントさんの映画レビュー(感想・評価)
それは真の解放を求めた人間の切なる思いを反映した建物なのかあるいは忌まわしき資本主義の墓標なのか
ブルータリズムを名指しで否定したトランプによる大統領令が一期目に続いて今回再び発令されることとなった。
連邦政府が建設する建物は伝統を重んじた古典主義的建築でなくてはならないという「美しい連邦公共建築」という名の大統領令。確かに公金が使われる建物が住民の感性で受け入れがたいようないわば芸術家たちにだけ称賛されるものであってはならないというのはエリート主義を叩いてのし上がってきたトランプにしてみれば必然的とも思える。
ブルータリズムが第二次大戦後台頭してきたのは安価な材料であるコンクリートにより工期も短く済むため戦後復興にとっても役立ったからだ。それと同時にその柔軟な工法が設計する者の作家性を反映させやすくもあった。このブルータリズム建築が美しいか美しくないか、それは確かに賛否が分かれるところではある。
その無骨で殺風景とも思えるシンプルな外観は実際に多くの住民に嫌悪感を抱かせるものもある。それを意図した設計でもあるのだが。
本作ではトートの設計による礼拝堂が景観にそぐわないという住民に対して住民説明を行う場面がある。彼の設計がいかに優れているかをプレゼンして住民に納得してもらうシーンだ。
美しいか美しくないかは見る者の感性にゆだねられる。それを判断するのはその人次第だが大統領令はそれを一概に美しくないとして一切を否定をしてしまう。これは価値観の押し付けでしかない。美的感覚は人によりさまざまで時代によっても移り変わるもの。そのような感性を画一的に一方的に否定する大統領令は彼の多様性否定の姿勢そのものでもある。
地域住民の納得の上でトートの建築は受け入れられる。これが大統領令に対するアンサーである。一見受け入れがたいデザインの建築物でもそのコンセプトを説明して理解してもらい地域住民に受け入れてもらえればなんら問題はない。一様に否定する大統領令がどれだけ愚かなのかを本作は訴えている。
自分とは異なる感性を否定する、他者を受け入れないという多様性の否定がかつてのホロコーストを生み出した。ホロコースト生存者を主人公にした本作がこの大統領令に端を発して製作されたのがよくわかる。
歴史は繰り返される。本作は他者を排斥し多くの異なる民族を悲劇に追いやった現代のホロコーストの再来を危惧して警告を発するための作品であると思える。
ホロコースト生存者の建築家トートはアメリカに渡りそこで大富豪のハリソンから支援を受け彼の依頼で礼拝堂を兼ねた複合公共施設の設計を手掛ける。
ハリソンはトートの才能にほれ込み、彼への支援を惜しまなかった。しかしトートは自分の思う通りの建設がなかなか進まないことに苛立ちを覚えていた。そんな時ハリソンが経営する運輸会社の列車事故により事業は中止されトートは一方的に解雇されてしまう。
事故処理が事なきを得ると途端にトートはハリソンに引き戻される。ハリソンによる気まぐれでトートが翻弄されるのはこの時だけではなかった。出会いのきっかけもトートが彼の書斎のリフォームを行なったことに対して激怒した彼がトートを追い出したことにあった。
ハリソンは一代で事業を成功させた富豪であるが、芸術的才能には恵まれなかった。トートの才能にほれ込んでいるようで実際彼の才能はもとより彼の人格についても理解などしてはいなかった。ただトートが有名芸術学校出身で業界で注目された建築家であることに目をつけたに過ぎない。彼を訪ねたのも書斎が雑誌に取り上げられたからだった。
彼にとってトートは彼の邸宅の数々の贅を尽くした装飾や調度品と同じくお飾りでしかなかった。トートは彼の権威をさらに箔づけするためのペットでしかなかったのだ。それは彼を糾弾するトートの妻に対して彼自身の口からも語られる。
かつて建築の分野で名声を手にしたトートはナチスの迫害によりすべてを奪われ、このアメリカではただの日雇い労働にしかつけなかった。ハリソンのような富豪のパトロンに頼るしか彼の才能を生かす道はなかった。たとえペットの身に甘んじても。
自由の国アメリカ。ホロコーストから逃れて自由を手に入れられると思っていた芸術家にとってそこはナチスの収容所と同様、囚われの身であることに変わりなかった。資本主義という名の牢獄の。
アメリカは彼に自由を与えてはくれず彼に与えたのはアヘンだけだった。薬物中毒になってしまった彼は妻の言う通り祖国イスラエルに渡る決心をする。
終始芸術家である主人公が実業家である大富豪に翻弄される姿はまさにトランプ政権下で翻弄される現在のアメリカの芸術家たちを見ているようだ。
今回の第二次トランプ政権によりアート界は危機感を抱いている。第一期でも文化芸術への支援が削減されたり、ムスリムの国々への渡航が禁じられたりと芸術家同士の交流が阻害される政策が次々とおこなわれた。
今回の政権でもさっそくトランスジェンダー否定をはじめとする多様性を尊重するDEI(多様性、公平性、包括性)事業の廃止を掲げている。
多様性こそがイノベーションを生む、それは芸術の分野に限らない。経済においてもアメリカの大手IT企業の創始者の六割が移民または移民二世だったりする。そもそもトランプの祖父自体がドイツからの移民であるし、イーロン・マスクも移民の子孫だ。
多くの移民を受け入れてきたからこその現在のアメリカの繁栄がある。それは多様性から生まれた。それを否定するトランプは自らのルーツを否定するようなものだ。
トートがアメリカで手掛けた礼拝堂はやがて完成する。建物の外観は収容所をモチーフにしながらも高い天窓から空を見上げる設計。それはトートの抱き続けた真の解放への思いが反映された建物であると同時に富豪が自ら命を絶った資本主義の墓標でもあったのかもしれない。
トランプの大統領令がいう古典主義的建築なるものは古代ローマやギリシア建築の要素を取り入れた建築様式を言うが、それは時の権力者たちが自分の権威を象徴するためにその多くが作られた。
外観に装飾を施した伝統的な建造物は歴代の為政者たちがその権威を表すために贅を尽くした装飾をまとわせた虚像でしかない。簡素で装飾をまとわないブルータリズム建築はそれとは真っ向対立する。まさに機能性だけを重視し、そこに権威が入り込む余地はないのだ。
権威主義に溺れるハリソンの下でトートがこだわり続けたのがまさにこれだった。反権威主義、彼は自分を支配しようとするハリソンの下で真の解放を目指していたのだろう。
資本主義の象徴ともいえるハリソンはトランプの姿と被る。そんな彼がトートを凌辱したことを糾弾されて建築途中の施設で自害をする。
トートの建物は資本主義の終焉を表した資本主義の墓標でもあり、権威と戦う芸術家たちの解放を象徴したものでもあったのかもしれない。
本作はまさにトランプ政権下で多様性や自由な思想がないがしろにされてることへのカウンター的な作品と言えるだろう。
ちなみにブルータリズムを否定するトランプだが、彼の成功者としての証でもあり象徴でもあるトランプタワーはまさにこのブルータリズム建築そのものであった。
トランプタワー設計に携わったバーバラ・レスによると当時建設を急いだために不完全な図面をもとに工事を始めたので、建築途中での変更にも柔軟に対応できるようにほとんど鉄骨を使わず大部分をコンクリートで建設した。
ブルータリズムを否定するトランプがブルータリズムの恩恵を受けていたという皮肉。また伝統を重んじた古典主義的建築などという彼だが、トランプタワーの敷地として購入した場所には歴史的価値ある装飾が外壁に施されたボンウィットテラーデパートの建物があり、外壁に施されたレリーフは当時の五番街の象徴でもあった。街のシンボルでもあるその装飾をメトロポリタン美術館に寄贈することを条件に取り壊し許可を得たにもかかわらず工事を急ぐあまりその約束を破り装飾ごと解体してしまったのだ。伝統的建造物を重んじるなどと聞いてあきれる。
ちなみにトランプの会社が当時この解体工事で雇い入れたのはすべて不法移民であり低賃金労働させて経費を削減したという。
レントさん
レントさんの情報満載のレビューとても読み応えがありました。
自由の女神が泣いていますよね 🗽
アメリカのイメージを変えてしまう大統領が誕生してしまいました 🇺🇸