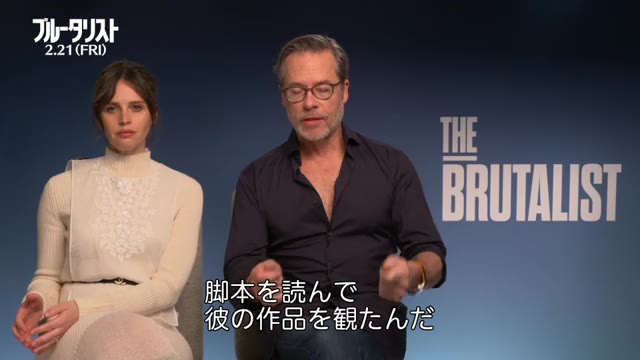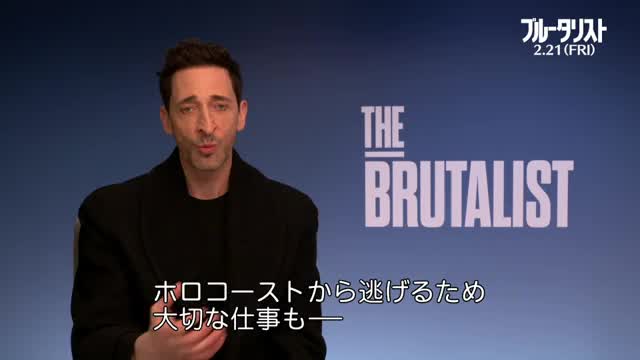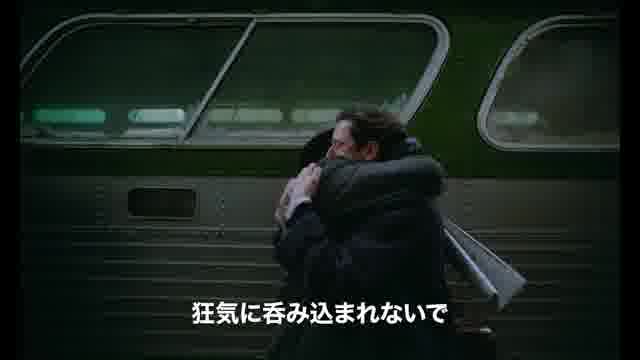「1976年に建てられた改革派シナゴーグはサラッとしているけど意味は大きい」ブルータリスト Dr.Hawkさんの映画レビュー(感想・評価)
1976年に建てられた改革派シナゴーグはサラッとしているけど意味は大きい
2025.2.26 字幕 イオンシネマ久御山
2024年のアメリカ&イギリス&ハンガリー合作の映画(215分、R15+)
ホロコーストを生き延びたユダヤ人建築家の半生を描いたヒューマンドラマ
監督はブラディ・コーベット
脚本はブラディ・コーベット&モナ・ファストヴォールド
原題の『The Brutalist』は「荒々しい建築を行う建築家」という意味
物語は、とある国境地帯にて、尋問を受けるユダヤ人女性ジョーフィア(ラフィー・キャシディ、成人期:Ariane Lebed)が描かれて始まる
彼女は叔父の建築家ラースロー(エイドリアン・ブロディ)についての質問をされていたが、訳がわからないまま精神的な圧迫を受けることになった
ラースローは強制収容所を生き延びたユダヤ人で、いとこのアティラ(アレッサンドロ・ニボラ)を頼って海を渡った
彼はアティラの経営する家具店で働くことになり、クライアントの要望に応えるために部屋の改築などを行なっていた
依頼主は資産家ハリソン(ガイ・ピアーズ)の息子ハリー(ジョー・アルウィン)で、ラースローは「ブルータリズム式の図書室」を完成させた
だが、そのことを知らされていないハリソンは激怒し、ラースローとアティラを追い出してしまう
さらにハリーは金を払えないと言い出し、この件にて、アティラはラースローを追い出してしまうのである
その後ラースローは路上生活を強いられ、炊き出しにてゴードン(イザック・ド・バンゴレ)と出会う
彼の息子ウィリアム(Charile Esoko、少年期:Zephan Hanson Amissah)らと過ごす日々が続き、期間労働として土木工事に従事するようになった
だが、そこにハリソンが訪れ、これまでの無礼を許してほしいと言う
彼は、ラースローが手がけた部屋の価値を知り、そして数々の功績を知った
そこでハリソンは、彼に自分のアイデアを話し、そのプロジェクトを引き受けてくれないかと打診するのである
映画は200分+インターバル15分の構成で、「序曲」「第1章:到達の謎」「第2章:美の核芯」「エピローグ:第1回 建築ビエンナーレ」という流れになっている
そして、「序曲」にてどこかの国境警備隊に尋問されるジョーフィアは、ラストでも登場するのだが、あのラストショットの意味は「ジョーフィアの到達点における出発点の想起」ということになるのだろう
ラースローとエルジェーベトから伝えられた「旅路ではなく到達点が大事」という言葉の意味を捉えると、叔父や叔母に感謝できる人生を歩んだことことがジョーフィアにとっての到達点だった、ということになるのだろう
映画は、前半でプロジェクトを任されるまで、後半でプロジェクトのトラブルを描き、ハリソンから強姦されるラースローが描かれていく
それに激怒した妻のエルジェーベト(フェリシティ・ジョーンズ)がハリソンに夫から聞いたことを突きつけるのだが、その後ハリソンがどうなったのかは描かれない
だが、この事件を機に、施設の存在意義がハリソンの母のためのものから、エルジェーベトやユダヤ人たちのためのものに変わっていて、それを告白するのが回顧展(1980年)となっている
俯瞰すれば、アメリカ人に金を出させて、ユダヤ人が考案して、奴隷が建設するという構図を暴露しているので、なかなか風刺が効いているように思える
ある意味、アメリカに来たユダヤ人のためのエルサレムをあの場所に建てたというようにも思える
行き場を失ったユダヤ人が権利を主張できるという文言が前半にあり、それによってイスラエルが建国されたという背景があるので、それをアメリカでも行なったとことになるのだろうか
劇中でも、エルサレムに帰ることが正義のように語るジョーフィアと対立するラースローがいるのだが、それに対するアンサーのようにも思えた
いずれにせよ、宗教に対する知識が必要な作品で、ユダヤ教徒のラースローやエルジェーベト、カトリックに改宗したアッテラ、プロテスタントであるハリソンなどの立ち位置というものがベースにある
ユダヤ人の迫害の歴史があり、アメリカに来るしかなかったという戦中戦後の状況があり、イスラエルの建国にまつわる話も登場する
このあたりに興味がないと苦痛の200分なので、観る人を選ぶ映画のように思えた
ちゃんとインターバルがあって、15分間用意されているので、生理的な苦痛は緩和できると思うが、精神的な部分はどうしようもないので、そのあたりの覚悟を持って臨んだ方が良い案件なのかな、と感じた