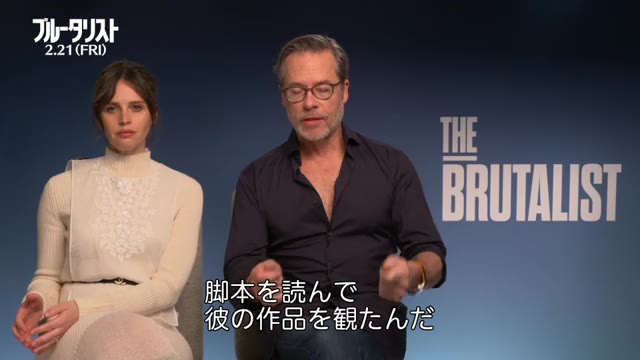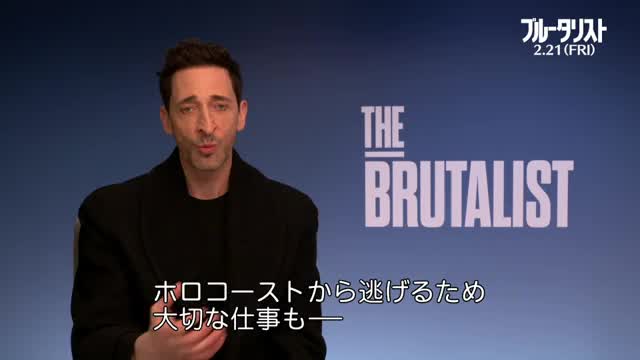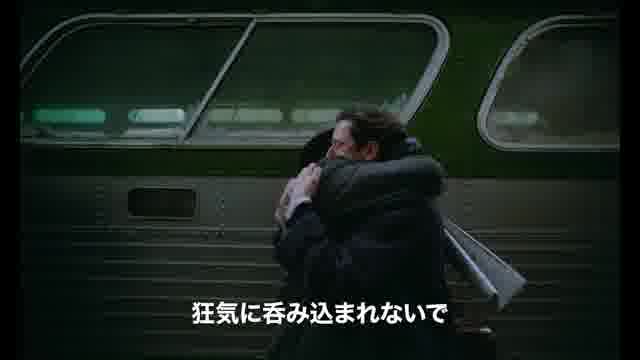「長尺の割には、描くべきものが描かれていないと思えてならない」ブルータリスト tomatoさんの映画レビュー(感想・評価)
長尺の割には、描くべきものが描かれていないと思えてならない
主人公が「ホロコーストを生き延びた」ということが主題になっていると思っていたのだが、そのことがまったく描かれないので、何だか肩透かしを食らった気分になる。
主人公が、ドラッグを常用しているのは、戦争のトラウマを忘れるためなのではないかと勝手に推察していたのだが、終盤で、「鼻の痛みを和らげるため」ということが分かり、「もしかしたら、主人公は、それほど過酷な経験をしていないのかも」とも思ってしまった。
あるいは、「戦場のピアニスト」の役柄がオーバーラップするエイドリアン・ブロディだけに、ユダヤ人に対する迫害の様子は、観客の脳内で補完しろということなのだろうか?
戦争のトラウマということであれば、何度も激しくうなされる妻の方が、よほど心身に深い傷を負っているように見えるのだが、その妻が、どうして夫と離れ離れになり、どんな経験をしてきたのかについても、最後までよく分からずじまいで、フラストレーションを感じてしまう。
主人公と妻との関係性にしても、せっかくアメリカで再会できたのに、どこかギクシャクとした雰囲気が続くばかりで、少なくとも、「互いに支え合っている」という印象はない。終盤で、ようやく愛を交わすことができるものの、それも、何だかドラッグのお陰のようで、夫婦愛の物語としても、物足りないとしか言いようがない。
それ以前に、冒頭に登場して、主人公の夢の中にも出てきた女性が、てっきり妻だと思っていたのだが、第2部になって、それが妻の姪だと明らかになり驚かされる。
そこで、この姪が、物語の鍵を握っているのに違いないと予想したのだが、大きな事件も起こらないまま、あっさり口がきけるようになった挙げ句に、夫とイスラエルに行ってしまい、ここでも、肩透かしを食らってしまった。
結局、これは、自らが追求する「理想」と、費用や人間関係等の「現実」の間で、「創造」のために苦闘する芸術家の話なのだろう。
ただ、彼が味わう「産みの苦しみ」は、故郷のハンガリーと移住先のアメリカの文化の違いによるものというよりは、彼自身の、妥協を許さない頑固な性格や、協調性のない傲慢な人間性に起因しているように思えてならない。
ここでも、ヨーロッパにおける主人公の経験が描かれず、アメリカでの出来事との比較ができないために、良く言えば「普遍的」だが、悪く言えば「どこにでもある」ような、単なる「偏屈な芸術家の話」になってしまったように思えてならない。
ガイ・ピアースが演じる主人公のパトロンも、「芸術の理解者」と「いけ好かない金持ち」という2つの個性のバランスが絶妙だっただけに、終盤のイタリアでのエピソードのせいで、後味の悪い印象しか残らなくなってしまったのは、残念としか言いようがない。
いずれにしても、主人公の人生そのものに、「数奇な」と形容できるような波乱万丈さが感じられず、それを描く物語も、平板で起伏に乏しいものになってしまったのは、やはり、ナチスによる迫害を逃れ、アメリカに来るまでの経緯が描かれなかったからだろう。
正味3時間20分の長尺だが、その割には、描くべきものが描かれていないと思わざるを得ず、逆に、これだけの内容の物語を、これだけの時間をかけて描く必要はあったのだろうかという疑問が残った。
同意
世間の評判の割に、自分的には何だかなぁという感じ。画面で語られる事象以外を、かなり想像を逞しくして、鑑賞しなければならない映画なのでしょうかね
「戦場のピアニスト」でアカデミー受賞した時のエイドリアン・ブロディの、プレゼンテーターの女優さんに激しいキスをして、半ばセクハラでないかと当時騒がれたことを思い出してしまうくらい、このトートという役が得体が知れない、穢らわしい者に見えてしまいました