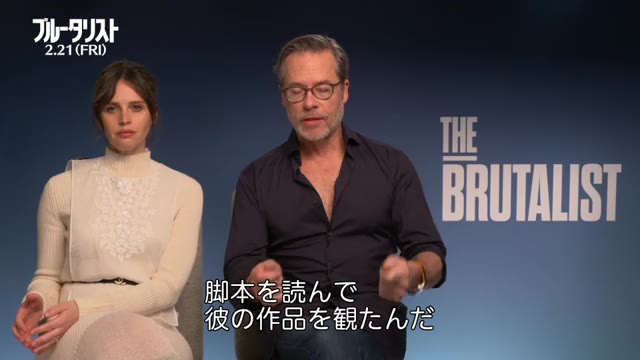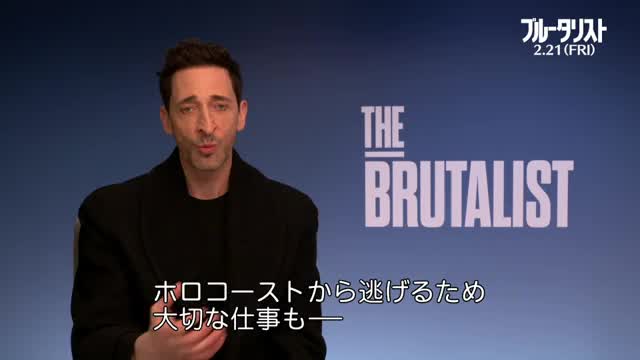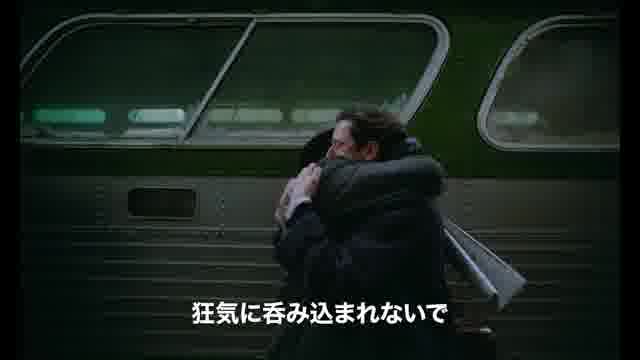「"アメリカン・ドリーム"の闇 = ありのままの美しさ(姿)で一つの時代(過去)を定義し、時を超える普遍性」ブルータリスト とぽとぽさんの映画レビュー(感想・評価)
"アメリカン・ドリーム"の闇 = ありのままの美しさ(姿)で一つの時代(過去)を定義し、時を超える普遍性
逆さの自由の女神像 = ポスタービジュアルにも使われているこの印象的なショットこそが、本作のテーマを端的に象徴するエスタブリッシュショット。移民が最初に目撃する希望の象徴の失墜。つまり、難民や売れない芸術家にとってそれぞれの夢や希望 -- 何より生そのもの -- への【道】を切り拓くような一筋の【光】であるアメリカもパトロンも、その出会い自体が「救われた!これで一生安泰だ」というゴールなのではなく、あくまでそこから別の苦労や挫折、人間の暗部・闇に迫る新たなスタートに過ぎないということ。観てわかった、建築様式のブルータリズムだけでなく、文字通りの「残酷主義者」でもあるタイトル。美の核芯、過去の存在。
"目玉"から鱗!釘付けになるファーストシーンから圧倒されては、オープニングクレジットが流れるところまでで完璧にやられた。そしてそこから展開される、何層にもなっては、あるがままの姿が剥き出しになっていくようなさまに引き込まれてしまう…。どのキャラクターにも影があって、闇を抱えており、その複雑さには魅了されてしまうものがある。彼らが体現しては暴くアメリカンドリームの疑問や醜さ(虚栄・嘘偽り)。"Miller & sons"アメリカ人はファミリービジネスが大好きだ!"我々"外国人はアメリカの人々に歓迎されていない…!! 改名・改宗してアメリカ人になることをえらんだ"従兄弟と、自身の原点エルサレムに行くことを選ぶ姪。そのどちらでもない(そして恐らくこれが一番多数派では?)主人公たち。その時代を生き残った生き証人であり、アーティスト = 表現者として語り継ぐこと。
怪我した鼻と車や列車が走ってゆく道。『戦場のピアニスト』エイドリアン・ブロディがまたもやホロコーストを生き延びたサバイバーを演じ、『博士と彼女のセオリー』フェリシティ・ジョーンズがまたもやそんな主人公に寄り添う妻役を演じた本作は、素晴らしい演技だけでなくフィルム撮影、音楽(サントラ最高すぎる!)、衣装、そして光を(時に意図的に窮屈かつ居心地悪くも)心ゆくまで堪能でき、本編尺は長いけどずっと観ていられるような映画としての強度・力強さには疑う余地がない。作中30年もの時が流れ主人公の半生を描き、大河ドラマと形容するに値する歴史巨編にふさわしい裏方スタッフの働きの充実っぷり(ex.『アラビアのロレンス』『ラスト・エンペラー』)!!
また、近年インディペンデント映画や中小規模な作品を中心に活躍するガイ・ピアースが、初登場シーンから強烈なインパクトを残す。キレやすい支配者(上流・特権)階級に、その一因にもなっていそうでありながら同時に母親思いな(屈折した)一面にもつながる生い立ちバックグラウンド。かたや図書室改装の1000ドル、かたや母を捨てた祖父母への手切れ金の1000ドルという同じ額の重さの違いと、そして政治的な力も働いた結果85万ドルもの巨額の予算をかけて建設される母の名前を冠したコミュニティセンター。夢を叶える = 思いを成し遂げるのに時間がかかる芸術家アーティストとパトロンの歪んだ・捻れた関係性(ドラッグ、性 etc.)など、鉄鋼のように社会の根幹から化けの皮を剥ぐ。若干36歳のブラディ・コーベット監督がここまで大胆に挑戦的・野心的かつ実験的な大作を生み出した意義。
勝手に関連作品『アンドレイ・ルブリョフ』『サウルの息子』『アラビアのロレンス』『ラスト・エンペラー』『オッペンハイマー』『戦場のピアニスト』『マエストロ』
P.S. 主人公が妻を想ってか性的に不能なのか判断しかねたけど、やはりそういうことなのだろうか?
↑↑↑↑↑
ウェス・アンダーソン組からジャンル映画まで信頼に足るメソッド俳優エイドリアン・ブロディが名作『戦場のピアニスト』以来、再びホロコーストから生き延びた人物を演じる注目の本作はぜひとも観たい作品。また、同じく伝記映画『博士と彼女のセオリー』でも妻役を演じ『ビリーブ』では女性解放と性差別撤廃に闘っていたフェリシティ・ジョーンズに、『ハート・ロッカー』など大作映画以外を主戦場に独自のキャリアを築いてきたガイ・ピアースと共演も気になゆ。最初は文字通りの残忍主義者ということかと思ったくらい建築のことは詳しくないけど、ブルータリズム建築という興味を惹かれるタイトル。弱冠36歳の脚本監督が放つ本作は、尺の長さ含め例えば現代の『アンドレイ・ルブリョフ』になるのではないかと期待。ゴールデン・グローブ賞より前から観たくてClipしていた本作、特報を見ていても引き込まれた。今年の『オッペンハイマー』になるか?