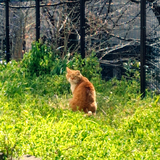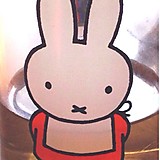ザ・ルーム・ネクスト・ドアのレビュー・感想・評価
全108件中、21~40件目を表示
深いようで深くもない
途中、退屈してしまった。
ファッションやインテリアは色彩豊かでセンスよく素敵ですが、ストーリーとしては淡々と進んでいき、死というテーマのわりには、重くはないけど、残るものもないです。
死ぬときに誰かそばにいてほしい、というのはだいたいの人が思うのかもしれないけど、相手の生活や時間を無駄に奪ってしまうのではないか、とか、そんな嫌なことに付き合わせたら悪い、とか例え家族であってもやっぱり普通は遠慮して言い出せないのだと思う。それを特に親しくしていたわけでもない人に頼むというのは、よくもわるくも我儘で自己愛の強い人、というかんじで共感したり同情したりっていう感情もなく見終わりました。
生と死をめぐる静謐な会話劇
これほどまでに「死」について濃密に描かれた映画があっただろうか。
しかもその死は暗くどんよりとしたものではなく、ポジティブで静謐に描かれる死だ。
2024年ベネチア国際映画祭のグランプリ受賞。名将ペドロ・アルモドバル監督初の英語劇でにして、円熟味を感じさせる研ぎ澄まされた作品だ。
ニューヨークが舞台、そしてアメリカの近代画家エドワード・ホッパーの「複製画」が大事な場面で使われていること、ジェイムズ・ジョイスの短編「死せる人々」が引用されることなどから英語を使ったのではないだろうか。
戦場記者だった末期がんを患うマーサ(ティルダ・スヴェンソン)は元同僚の小説家イングリッド(ジュリアン・ムーア)と再会すると、苦痛を伴う治療をやめて安楽死を選ぶと告げる。
そして、最後の数日を思い出がある自分の部屋ではなく郊外の別荘を借りて、イングリッドと過ごすことになる。
ただし、死の瞬間は隣の部屋(ルーム・ネクストドア)にいてほしいと言い、自分の部屋の扉が閉まっていたら旅立った合図だという。
ほぼ2人の会話劇でありながら、後半はサスペンス仕立てで展開し、画面に釘付けにするあたりはアルモドバルのストーリーテラーとしての真骨頂と言える。
また、映画はマーサの今までに至る人生がインサートされる。とりわけ娘との関係性の話はアルモドバルが過去作品でもテーマにする複雑な母性ともつながる。
ストーリーは劇的な展開やどんでん返しなどは無くシンプル。75歳の監督の引き算の美学だ。
ストーリーはシンプルだが、色合いは賑やか。マーサの洋服の色や病院や部屋の装飾はビビッドな色合いや現代アートで彩られている。死を前にしてもポジティブである象徴のように。
モネが晩年研ぎ澄まされた感覚でシンプルに「睡蓮」を描き続けたことを想起した。
会話劇を抑揚をもって演じ切ったティルダ・スウィントンとジュリアン・ムーアなくしてこの映画は存在しない。
唯一気になったのは、がんの先端医療も不法な安楽死の薬も高額で富裕層でなければ手に入らないということ。
お金がなければ自らの命の選択もできないと捉えられなくも無い。
死を受け止める名優ふたり
とにかくすべてが美しい。
どの場面をとっても絵画を観ているような気持になりました。
病室、ベランダの植物、キッチンの花や果物、壁・ソファ…美しくないものを見つける方が難しい。
主演のふたりも既に60歳を超えていると思いますがしわの一つ一つですら美しく、抑え目のトーンの鮮やかな色彩の景色にパチッとはまり、艶やかで鮮やか。
貴族のような大ぶりの重いトーンの花の終わりを迎える間際を観ているようでした。
ティルダ・スウィントンの瞳は淡いブルーですが、大きく黒々と静かにすべてを飲み込むようでマーサの寂寥感が瞳に現れているようでした。
彼女のみつめる先は何が映っていたのでしょう。
死に近い場所で生きてきたマーサが選んだ尊厳死。
考えれば考えるほど深みにはまって正しいとされることに疑問を感じてしまう。
そしてマーサの様な尊厳を選ぶことにも疑問がわいてしまう。
多分私には私に訪れる「その時」まで分からないのだろうと思う。
尊厳の内容は十人十色であるだろうから。
そしてイングリッドをはじめ、死に寄り添おうとする人々の言葉の一つ一つがとても真摯で響いた。心から生まれる言葉は穏やかで耳ではなく心に響く。
死にゆくマーサとたびたび会話や回想に出てくる生の象徴のセックスと言う言葉。
生を貪るように交わったであろう過去が色々な人の会話から想像できる。
背徳感などは本物の死を目の当たりしたらとてもちっぽけなことなのだと言う。
マーサの枯れゆく命との対比をこんなところからも感じ取れる。
そして尊厳など関係なく訪れるのが死であることもマーサの職業からちらつかせる。
望むと望まざると奪われ続ける死がすぐそこにある現状を垣間見せながら「死」そのものを重石に置いた作品なのだろうと「尊厳死」に気を奪われていた私はしばらくしてから気づくお粗末さ加減でした。
命のあるものと命が枯れてゆくもの。
雪はどちらにも同じように降り積もるのだと、繰り返されたセリフに頷きながら染み入りました。
この名優ふたりでなかったら、鑑賞後はざわつきがおさまらなかったかもしれない。
舞台「おやすみ、お母さん」が頭をよぎった〜だいぶ違うけど〜 マーサ...
安楽死を認めたい気持ちと認めたくない気持ち
むずい。
とても知的な作品。
全てのシーンや会話に何かしらの意味があるような気がするが、自分の読解力だといまいちはっきりせず、もやもやすることが多かった。
あと、ずっとミステリーな雰囲気を漂わせているのに、「実はそういうことだったのか!!」みたいな展開がなくて、それが逆に新鮮に感じた。
最後まで観ると、この映画は「ミステリー(最後に真相がわかるドラマ)」ではなく「「サスペンス(最初から真相がわかっているドラマ)」だったことがわかる。
自殺することを知っていて、それを止めなかったことを隠蔽しようとする人間の話。
だんだんと犯人視点で描かれるサスペンスになっていく。
後半、主人公が警察に盲点を突かれるところがサスペンスっぽい。
映画を観てると「ネクストドアじゃないじゃん」と思っていたが、警察との会話で「ネクストドア」が重要なキーワードだったことがわかる(「ネクストドア」にはもっと深い意味があるんだろうけど… )。
「安楽死」について考えさせられる内容だった。
主人公は癌で苦しむ友人を手助けするわけだが、自分も昔、同じような病気だったので、この友人の死にたがる気持ち、わかる気がしてしまった。
入院中に「あそこから飛び降りたら死ねそう」みたいなことを考えていたのを思い出した。
あの頃は精神がおかしくなっていたので…
後半、警察は主人公に「自殺は犯罪。許さない」と発言。
これが今の社会の考え方だと思うが、本人が強く望むなら好きにさせてあげても良いのでは?とチラッと思わないこともない。
一方で「尊厳死を認めることが本人の意思の尊重でもあるし、社会の負担を減らす意味にもなる」みたいな意見も出てきたと思うが、こちらについては反対したい気持ちがある(矛盾しているように見えるかもしれないが)。
この意見が出てきた時に、2022年公開の日本映画『PLAN 75』を思い出した。
個人が積極的に望むならともかく、国にとって負担になるからという理由で、それを本人に促そうとする動きは許容し難い。
ちょっと人工的だけど、とても品のいい映画
ちょっと人工的だけど、とても品のいい、いい映画を見たな、と思った。
自分自身も自分の死を受け入れる時が近い(まだ先だけど、若い時と比べて、という意味で)ので、とても切実さは感じられた。その意味では、先日見た「敵」を思い出す。
会話劇的なところもあり、会話のカットバックが印象的。
小津映画もそうだけど、小津映画に限らず、会話のカットバック(それぞれを交互に映す)って、映画手法の中でも、白眉の発明だったよな、と改めて思う。
で、それがとても論理的で倫理的で、でも過激的でもあり、面白く魅力的。ふと大島渚の映画を思い出す。
そんな会話劇がジュリアン・ムーアとティルダ・スウィントン(この人は初めて。すごくいい)の揺るぎない演技のなかで展開される。
何か結論があるわけでなく、終了は死、それも尊厳死。
映像が美しく、出てくる建物、服装、街並み、など洗練されている。特に終のすみかになる別荘は、美しい。
音楽もゆったりして全体に流れているけど、殊更盛り上げるものでなく、寄り添う感じで好感。
いい映画体験でした。
僕は、「死んだら全部終わり」と思っていたが
末期ガンで余命僅かとなった友達から「心が決まったら薬物を飲んで安楽死したいので、その日まで隣の部屋で一緒に過ごして欲しい」と依頼された女性の物語。ジュリアン・ムーア、ティルダ・スウィントンという二大女優の実質的には二人だけの会話劇です。
二人が語る過去の思い出・後悔、死への怯えの言葉は何気ない物までもが切実で、観る者の足許からゆっくりせり上がって来ます。僕は、死んだら全てはそこで終わりで、その後になど何もないと思っています。なのに、人間は死んだらどうなるのかなぁ等と、この映画と並走しながら
ぼんやり考えていました。死んだらどうなるかと言う事は、どの様に生きたかと言う事の裏返しなのでしょうか。この歳になると染みるなぁ。
地味だけれど深く素晴らしい作品でした。
死のイメージと対照的な鮮やかな色使い
静謐な気迫に見とれる
演技
稀有な親友
諸行無常?色即是空?否、人生は面白い
尊厳死、難しい問題です😱
不治の病に冒され安楽死を望む女性と、それに寄り添う事を決めた親友の最期の数日間。
扉を開けて寝るので、貴方に隣の部屋にいて欲しい、でも朝もし扉が閉まっていたら、私はこの世にはもう居ない…。
怖すぎるでしょ😱
アカデミー賞受賞女優2人の緊張感ある掛け合い。ピンクの雪が印象的。
もし、自分がどちらかの立場になったら、どうするんだろう。尊厳死、難しい問題です。
化学反応
アルモドバル監督初の英語作品で、ジュリアン・ムーアが初参加。彼女の存在で監督の世界観が少しマイルドになったような気がします。
ティルダ・スウィントンとは同い年で、バチバチの演技合戦になるのかと思ってたんですが、意外とかわされたというか淡々とした競演に感じました。
ジュリアン・ムーアはいつもながらの「寛容」と「誠実さ」がにじみ、一方ティルダ・スウィントンはこちらも彼女らしい泰然とした魅力で演じ切ってました(戦場ジャーナリストにはちょっと見えませんでしたが)。
お互いへの尊重は間違いなくある感じですね。
ティルダの覚悟の演技は、若い頃に重用されたデレクジャーマン監督の死(52才でHIVで死去)の影響があるとインタビューでコメントしています。
覚悟と感謝
アルモドバルの最近(と言っても10年くらい?)の作品、たんたんと、...
アルモドバルの最近(と言っても10年くらい?)の作品、たんたんと、アルモドバルの今思う気持ち、考えていることが、映し出されているように感じて、静かに共感できる。
相変わらず、インテリアもファッションも素敵過ぎなので、それだけでも満足度高いのだが、ちょうど最近日本で展覧会していたアーティストの作品が、主人公の部屋に飾られていたり、意外と日本ではまだよく知られてないようで驚く子宮頸がんが取りあげられていたのも感心した。
アルモドバルの作品は、昔っから、本人の関心、悩みごと、思ってることを美しく、印象深く伝えてくる。
映画と監督が一緒に歳とっていく感じがますますいい。
ジュリアン・ムーアに注目したことなかったが、それにしてもこの人この感じのまま長い(ある一定のところから老けない?)、演技もほんと自然でさすが。
あー、そうだろうな、って思うところは期待通りで、アルモドバル映画としては見やすい作品だと思った。
主人公が忘れ物、探し物する場面はどういうアクセントとしておかれたのか。
もう一回見て、気づくことがありそう。
見送るパターンとして、警察沙汰になるのも厭わない
友人を持てたラッキーなはなしの設定。
死という重めのテーマを和らげる、着ている服の色や家具の色が視覚的に美しい。
家で最期まで暮らし看取って家の座敷で通夜を行い、葬式も家で行っていた昭和の終わりまでは、わざわざ映画にするまでもなく日本人的には、死と隣り合わせに生活しどうやって生きるかは皆が学ぶことが出来た。生き残った人は、両親や親戚の死にいくさまを何度も見て、自分の生きる残りの毎日のことを考えて生きていく。そういう日本でした。
娘さん役が一人二役っていうのより、やはり、べつの人物が演じるほうが良かったのでは?そして、融通の効かない警察官が宗教的に許さないと強く言ったり、助けてくれるボーイフレンドが地球温暖化を作っているのは極右のせいだと、どことなくトランプの悪口をいれているところが、映画を作った時期と監督や脚本家の意見だろうか?
安楽死って、キリスト教的に許されない科学的なこと、超現実主義の頭の良い系の人がするという自負があるんだーと、再確認した。そういえば、祈りの言葉は一切なかった。
尊厳はダメなのか…
全108件中、21~40件目を表示