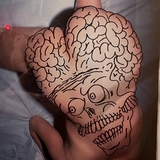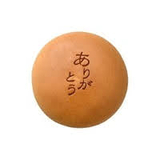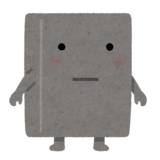野生の島のロズのレビュー・感想・評価
全265件中、21~40件目を表示
子育ての役割を担うのは
ロボットと動物の組み合わせのアニメというと近作ではロボット・ドリームズを想起するが、こっちはジブリ風味も入ったドリームのように美しいCG映像ワークス。
話は、ロボットがプログラムを逸脱して、そして母になる、というものなのだが、ロズが任務(どんな任務だったかわからんが)に忠実なロボットを逸脱して感情が表出すればするほど醒めてしまう感があった。野生の島での弱肉強食ルールも次第に緩んでぼんやりしていくし。大作少年の命令に忠実だったジャイアント・ロボは最後の最後に裏切るから泣けるわけで(古すぎ)。まあ、ウェルメイドなご家族向け作品といえばそれまでなので、人生に擦れたおっさんが文句つけるもんでもないけど。
ロボットをテーマにした作品だが、平凡
配信(アマゾンレンタル)で視聴。海外アニメだが、色々考えさせられる作品。
ロボットの視点で描くアニメはなるほどと思わせる。
ロボットと動物の関係からこの作品で学ばされっぱなし。色々考えさせられた。
ロボットをテーマにした作品はロボットドリームがある。ロボットドリームと比べると物足りなさを感じた。
ほっこりする
子育ての在り方。
親子の絆を最大のテーマに据えておきながらも、他者との共感をも内包した良質な作品でした。
アイザック・アシモフの小説「AL76失踪す」を皮切りに、スティーブン・スピルバーグが監督した「A.I.」など「ロボットが野良化する」作品は数あれど、野生の島に着眼している点は良い切り口だと思いました。
言葉か通じず、意思の疎通すらはかれない。
他国の人々に出会った時、「誰しもが感じ得る」であろう疎外感の中、子育てに奮闘する母親の姿を「野生の島」という突飛な場所で描き、「誰しもが共感できる」物語へと演出されておりました。
間違いなく万人に受け入れて貰える作品になっていたと思います。
余談ですが、CGとは思えない絵の具で書いたようなシーンが幾つも点在しておりました。
特に木々の描き方や葉の描き方が半端ないので気になる人は着目してみてください。
擬人化されるロボットと動物たち
絵柄がとてもセンスがあって美しく、動物たちもとてもかわいい。ロボットのロズもとても優しくて癒される。人間に奉仕するためのロボットだからその声も優しい女性の声に設定されてるのだろう。吹き替え版と両方鑑賞して綾瀬はるかさんの吹き替えは物凄くマッチしていた。さすがサイボーグ役もこなした俳優さんだけのことはある。
舞台は未来の地球で温暖化による気候変動で大都市が水没していることから同時期に公開されたやはり動物たちしか出てこない「Flow」とほぼ同じ。ただ、かの作品と違い本作は内容的にあまり深みはないように思われた。
何か深いメッセージが込められているかと鑑賞中考えたがそういう作品ではなくもともと児童向け絵本が原作なのでそこまで深く考える必要もないのかもしれない。
強いて言うなら自然(野生)と文明の共存をテーマにしていると考えられなくもない。しかし本作で描かれる動物たちは完全に擬人化された存在で本来の野生の姿ではない。
ロズが世話をする雁の雛キラリは本来兄弟の中では一番小さく生まれた個体で、捕食要員だった。彼が捕食されることで他の兄弟は生き延びることができて種の保存に役立つ。人間から見れば残酷な自然淘汰のシステムもちゃんとした理由があってのこと。肉食動物は自分の子供に食べさせるために狩りやすい小鹿を狙う。彼らも命がけの狩りをしている。間違えば大人の鹿の角に致命傷を負わされないとも限らない。
人間社会では子供を餌食にすることは残酷だと言われるが残酷などというのは人間の尺度でしかない。彼らは自然界でお互い狩り狩られる関係で共存関係を築いている。人間同士のように仲良く暮らすことを彼ら自然界で共存とは呼ばない。
本作は彼ら捕食する側される側を同じ場所に集めてお互い協力して苦難を乗り越えようなんて人間社会の話を無理くりに動物たちに投影させている。
児童向け絵本だから動物たちのそういう姿を通して子供に人間社会でそのように生きることの大切さを教えようという本作の意図が見えてくる。そういう意図で本作は作られたものなのだとしてようやく納得できた。
元来擬人化とはそのように子供が学びやすくするために使われてきた手法なんだから。大人だともっと深い意味があるのではないかと考えて見てしまうが本作はむしろ前述の「Flow」とは真逆な作品として楽しむのが正しんだろう。
ちなみにロボットの擬人化と書いたけどロボットが限りなく人間に近づいていくとこの言葉は意味をなさなくなる。人間と何ら変わらない感情や心を持つまでに至れば人間そのものなのだから擬人化の余地はなくなるんだろう。
キラリたちの群れが嵐を避けるために人間が作物栽培をしてるドームに潜り込む場面、あんなにたやすく潜り込めるのだから今までも他の鳥の群れが侵入することなんてあったはずなのにあの混乱ぶりが可笑しくて笑えた。侵入を許すどころか自分たちでドーム破壊してるわけだし。あれじゃあ森で動物たちに簡単に追い返されるわけだ。文明は所詮自然にはかなわないと言いたいのかな。温暖化で水没することも避けられなかったわけだから自然をなめるなと本作は言いたいのかも。
毎度毎度ドリームワークスさんは凄いっす。感動したっす。
噂通りの素晴らしい作品でした。とんでもなく優しい綺麗事だらけの物語でしたが、今の世界には特に必要なんじゃないでしょうか。綺麗事?結構じゃないの。この作品を通してその綺麗事を綺麗事に終わらせず、本当にやってやれる人が少しでも生まれると良いですね。私ですか?笑 ダメですね。全然変わってないです。いや、1か2くらいは親切にしようと思てるかな。それでも、そんな小さな親切が何万人、何十万人と増えれば少しはマシな世界になるんでしょうか。僕ら庶民にもだけど、特権階級で権力を行使出来る人達にも是非ご覧になって、少しでもハートを使って、親切を、優しさを胸に権力を行使して頂きたいものです。はい、コレも綺麗事ですね。物語の中でしかあり得ない事でしょうね。ロズ。この世界はたぶんほぼ詰んでるよ。それでも、生きます。今日も元気に生きてます。とりあえず、私の周りは平和で豊かです。本当に有難い事です。
児童映画の皮を被った大人映画(完成度は抜群)
映像、ストーリー、テンポ、音楽、全てにおいて本当に上手に出来ています。
基本「子育て」の話なので、子育てが終わった、もしくは一息つき始めた人にハマる作品です。
ま、ストーリー自体は単純ですし画もきれいなので、子供でも十分楽しめるとは思いますが…
各場面における作者の意図や思いに触れようと思うと、子育ての経験は必須と思います♪
最近の映画は興行成績を上げるために、統計学的、心理学的に色々計算されて作られている作品が多い印象です。
この作品も面白くなる方程式を存分に詰め込んだ感じは否めませんが…
そんな手法を導入しても大外しする作品が多々あるw中、この作品は本当に上手にまとめられています。
おヘソが曲がり気味の方や心が若年層に置いてけぼりになっている方以外は、純粋に楽しめると思います♪
もし子育てが終わっているのにこの作品を楽しめなかった場合、へそ曲がりかピータパン症候群を疑いましょうw
で、素直に泣いたし、笑ったし、良い作品だだったので~ ★5!
で終わりたいのですが、私は若干へそが曲がってまして…w
全てにおいて奇麗すぎるので★-1 して、合計 ★4 にします。
いや、でもホント、何の文句もない良い&巧い作品でした。
良いものを観せて頂き、クリエーターの方達に心から感謝!
DVD買っちゃいそう~(で、結局買わなかった的なオチになりそうw)
映像美!!
吹替え版の評価。ストーリーはちょっと。吹替えは駄目。映像は凄い。
恥ずかしながらおじさん泣きっぱなし💦
涙の洪水
素晴らしい映像と音楽、是非映画館で!
ここのところ大活躍の河合優実さんの作品を鑑賞してきて彼女の演技の素晴らしさを実感しながら、しかし作品のテーマの重さに気持ちを押し潰されてましたが、今日この作品の鑑賞でやわらかい気持ちになれました。
もともと綾瀬はるかさんのファンということもあるのですが、彼女が吹き替えたロズがだんだん感情を持ち始め、キラリとの心のつながりや動物たちが協力し合う姿には心洗われました。それにもまして非常に美しい映像と音楽に、それだけでも観てよかったと感じる作品でした。
それほど斬新なストーリー・展開ではないのですがゆったりと暖かい気持ちになれる素敵な映画だと思いました。正直綾瀬はるかさんが吹き替えたこと以外はあまり興味を持ってなくて割とノーマーク状態、今日も定時後自分の都合だけで時間のロスなく観られる作品という理由で選んだのですが、大正解でした。
心のデトックスになったいい時間でした!
飛行機で
王道にして、新鮮な切り口
この手の作品にハズレなし
全265件中、21~40件目を表示