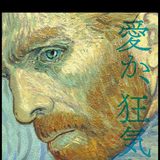ぼくとパパ、約束の週末のレビュー・感想・評価
全73件中、21~40件目を表示
よく練られた実話ベースの物語
本年、劇場鑑賞一本目。
自閉スペクトラム症の本人と、家族と、周囲の反応がとてもリアルで、よく練られているなぁと思ったら、エンディングで実話ベースの話だとわかり納得。本人の言葉の一つ一つになるほどと思わされ、父の関わり方、母の関わり方、それぞれから学ぶところが多かった。
劇的な変化は起きないのだが、ジェイソンが段々と自分のトリセツを周囲に伝えられるようになったり、こだわりを新たな考え方で置き換えられるようになったりしていくところがジーンとくるし、すれ違いながらも親子の絆を深めていく様子は素直に心温まる。また、祖父の関わり方も、その距離感を含めて、とてもよかった。
サッカーについては、スタジアム観戦の経験もなく詳しくないのだが、推しチーム探しの旅は、とても楽しそうで、ドイツの鉄道もとても魅力的だった。
<以下、この映画をきっかけに考えたこと>
*ちょっとだけネタバレ含みます。
本編から少し離れるかもしれないが、自分は、バス停での老婆に対する母のセリフが、一番考えさせられた。
何かしらの権威や立場を笠に着て、相手を屈服させようとする態度は、多くの人がNOと答えると思う。
そういう面で言うと、バス停での場面は、老婆が「年齢の差」からくる優位性を無言で笠に着てジェイソンや母に屈服を求めたと言える。
それに対して、見方によっては、母も、ジェイソンの「障害」を笠に着て、老婆をねじ伏せたようにも見える。
自分自身も、最初は、老婆に怒り続ける母の態度にちょっと引き、なぜそこまで強く主張できるのかという思いだった。
だが、母が老婆に投げかけた「そっちこそ何様?」の言葉にハッとさせられた。
自分も老婆同様に、譲れないジェイソンに対して「それはわがまま」と思っていなかったかと突きつけられた気がしたからだ。
母の言動に対する最初の違和感の原因は、自分が画面上から、自動的に「老婆=弱者」ととらえ、その立場から一連のやり取りをみていたためだろう。
ただ老婆は、身体の動く若い人たちに比べるとマイノリティだが、彼女自身は、こだわりなく席を譲ることが可能(自閉症的な特性はない)という点ではマジョリティでもある。
その点からすると、母の主張は、「その人自身にはどうにもならないことに関わるマイノリティの立場の者の訴え」であって、何ら非難を受けるいわれはない。
物事をみる側が、今回の自分のように「老人は大切にすべき」のようなわかりやすい一方的な見方のみに立っていると、母の言動のような非難を受けるいわれのない行為も、マジョリティ側が優位性を笠に着ている行為と同様に見えてしまう。
わかったつもりになっている自分も、よくよく気をつけないと、頭が硬くなってヤバいなということを感じさせられた。
まあ、母もあそこまで叫ばなくてもいいかもしれないが、自分もあの立場だったら、余裕を失って叫んでるかもしれないし…。
周りの人がみんな優しい
列車の食堂車で「躾しなさいよ」と
嫌味を言うおばさんが居たけど
口にしなくても
自分も思ってたりした。
自閉症と言うものが
こんなにも壮絶なものとは知らなかった。
理解ある職場の上司、祖父母の協力
両親の深い愛情の素晴らしさに感動する。
自分で作ったルールを少しづつ自分で
改変して行く事で、ジェイソンが成長していく姿も
微笑ましく、嬉しくなった。
推しチーム、見つけられたかなぁ⚽️
自閉症を個性と捉えれるか
幼い頃に自閉症と診断された10歳のジェイソンには、独自のルールがあり、それが守れなくなるとパニックを起こしていた。ある日、クラスメイトから好きなサッカーチームを聞かれたが、サッカーチームのことを知らず答えることができなかった。そこで、ドイツ国内のプロチーム1部から3部の計56チームを全て主催地で自分の目で見てから好きなチームを決めたいと言った。父ミルコは息子の願いをかなえようと、週末になると、ドイツ中のスタジアムを一緒に巡ることを約束し、多忙な仕事の合間を縫って列車の旅をしていく、という実話に基づく話。
自閉症は100人に1人の割合らしく、そう考えると、3クラスに1人くらいは居る計算になり、珍しい病気じゃ無いんだと改めて認識した。
これが実話に基づく話とは、そして現在19歳のジェイソンとまだサッカースタジアムを巡る旅を続けているとは、10年近くかけていくつのスタジアムを回ったのだろう?
ブンデスリーグの4部以下はアマチュアらしいので、プロ56チームを全て観た後は.4部103、5部245、6部599チーム全て行ったのだろうか?それともフランスやイタリアへも遠征してるのだろうか?興味ある。
お父さん役もお母さん役も素晴らしかったし、ジェイソン役の子も本当の自閉症かと思えるような熱演で素晴らしかった。
満員の劇場でなんとか観れて満足でした。
PKは自分で
自閉症の息子を持つ父親が、学校や夫婦間で様々な問題を抱えながらも、何かのキッカケになればと息子の推しチームを探すために旅に出る物語。
シリアスな雰囲気を見せながらも、コメディタッチな部分や明るいBGMが悲壮感を和らげてくれる。
ジェイソンの苦しみはよくわかる…なんて言葉で言うのは簡単だが、彼には彼にしか見えない世界があるのでしょう。席を簡単には譲らないお婆さんや注意してくる乗客達にも罪は無いわけで…。
改めて相互理解が大切だと、月並みな感想にはなってしまうが思わされた。
そんな中でも、スタジアムという自分の苦手がいっぱいな環境の中でも、やると決めたらとことん闘い続けるジェイソンの姿は逞しく見えたし、笑顔が増えていく様には見ていて嬉しくなった。
お父さん、よく頑張りました。そりゃあミルコだって人間だもの、悪態の1つも出るでしょう。それこそ、ミルコの置かれた世界も私達が中々に知り得ないものなのだから。
そして上司さん…あなた良い人過ぎだよ。。
俺もこんな上司の家族になりたいな…。
涙が出たり大きな笑いがあったりする作品でもなかったけど、色んなことがありつつも、ミルコ一家にしか見つけられない幸せを今後も手にしていって欲しいと思った作品だった。
親子両方の成長記
・父親は悪い奴ではないが不器用、接し方が下手で子供から逃げて、仕事に走っている。そんな父親が子供のために、動く、そして成長していく。常に正しい選択をできる人間ではないし、息子に酷いこともしてしまう時もあるが、それでも良い父親であることは間違いない。
・自閉症の方が感じ取っている世界が体験できる。音・光・接触をどのように感じ取っているのか分かりやすい。よく知らない人でも自閉症について簡単に理解できる。
・ところどころ笑いどころがあり、緩急がついていて良い。
・試合中はそれぞれのチームのファンの応援が主に映し出され、各応援の個性を楽しむことができる。サッカーをよく知らなくても、このスポーツ自体には詳しく触れないので大丈夫。
・最後に本人の写真や映像を見ることができる。いい笑顔でこちらにも幸せが伝わってくる。
ドイツのサッカースタジアムの臨場感にワクワク
ドイツのサッカーリーグにあんなにたくさんのチームがあるとは知りませんでした。
色んなサッカースタジアムの歓声や応援が映画館の大画面いっぱいで、なんだかワクワクしました。
にしても、毎週末スタジアムに同伴するパパの苦労は大変なもの。ゾッとするくらい汚いトイレで「解決して!」と言われても困ってしまう。パパ心身共にボロボロになって、それでも大事に息子を抱えて自宅のベッドにそっと戻すシーンには頭が下がります。
祖父の言葉も温かいし、ママもパパも深い愛情を持って息子を育てていることに感動しました。愛を感じられる映画は後味がいいですね。
ドイツでは錦鯉の人気が高いらしく、よく見ると、寝室の壁紙がブループリントの錦鯉!面白いなーと思いました。
親目線で見てしまう
アスペルガーの息子を育てる親の思いが痛いほど伝わってくる。
息子のこだわり、音や接触に敏感なところの表現がリアル。子役の演技が素晴らしい。小学生と接する仕事をしてきたので、ここまでではなくともこのような子は、クラスに1人はいる感覚だ。本人の苦しみも良く表現されていた。
周りの反応も無知からくるものが多く、どの国も似たり寄ったりなのだなと痛感。
観ていて涙がにじんだ。
それでも、ラストでは自分のことを客観的にみることができ、クラスの人たちに伝えることができた。
ドイツ中のスタジアムを巡るのだが、ちょっとした旅行気分を味わった。様々な列車、スタジアムの形状、ファンの応援の様子…圧巻だった。また、トイレについては、知ってはいたのだが、あんなに酷いとは!日本は、衛生的な国だとつくづく感じた。
ヨーロッパのサッカー熱の迫力
World
自閉症を持っている息子ジェイソンと父親ミルコが推しのサッカーチームを見つけるために各地を奔走するという触れ込みに惹かれての鑑賞。
中々にズッシリとくる作品でした。
自分が小学校や中学校の時までは自閉症を持っている友人と一緒に生活していましたが、高校生になってからはパッタリ触れることも出会う事も無くなったなと思っていたことを思い出しましたし、自閉症を持つ本人の気苦労、周りから理解されない苦しみと理解ができない周り、さらには親目線で映される自閉症の息子というのも本当に興味深くて、かつリアルだからこそ観ている途中の体は重かったです。
自分も接客がメインの仕事をやっているので自閉症らしき方と接客する事もありますし、その行動が理解できないという事も全然あるので、これを仕事として長くて5分ほどの触れ合うだけの自分と年中接する親となるとその苦労は計り知れないものがあるなと思いました。
ジェイソンの行動はやはり自分勝手かつ相手のことを考えていないようにしか見えず、自分のルーティンが崩されると激昂するし、同級生だろうと先生だろうと知らない人だろうとエゲツないくらい暴言を吐きまくるので初見の人からすると「なんやこのクソガキは」と見えるのは致し方ないですし、慣れた同級生からしたらからかいがいのある遊び道具に思われてしまいますし、先生からすると扱いにくくてしょうがない存在だと思うのでこの時点で誰も悪意がないのに雰囲気がよろしくないというのもリアルだなと思いました。
ふとしたきっかけでサッカーチーム探しに動き出したジェイソンとミルコですが、旅の始まりから大波乱起きまくりで本当に大変そうでした。
解決の糸口が全く見つからないジェイソンの行動に加えて、ジェイソンの症状を知らない他人から心無い言葉もあって挟まれたミルコの表情は辛そうでした。
いざサッカースタジアムに着いてからも大変そうで家族以外から触れられるのが苦手なジェイソンがサポーターが熱狂的な現場に行ったらそりゃ触れられまくり、歓声も大きいからびくりまくりでそれを守るミルコは試合を楽しめたもんじゃないですし、ジェイソンは細かい事が気になるのも拍車をかけて危険の連続ですがジェイソンはなんかスッキリしてるので気苦労の連発だと思います。
少しずつミルコが奥さんの苦労が分かってきてからは真摯にジェイソンと向き合って、2人だけの旅を楽しんでいる姿は親子の絆が感じられて素敵でした。
ミルコがジェイソンにぶっちゃけて怒ってしまうところも分かるけど、分かるけど言っちゃダメだよーとなったのと同時に、ミルコ自身のミスがあるとはいえジェイソンが意固地になってるからそりゃ頭に来るものもあるよ…とどちらかというとミルコ側に感情移入してしまいました。
終盤の展開も予想外の連発でミルコももう吹っ切れてジェイソンと共に駆け回っている姿は清々しかったですし、ただでは終わらないジェイソンもジェイソンで一貫してるわと感心してしまいました。
にしてもジェイソンの条件に見合うサッカーチームってこの世のどこかにいるんだろうか…。
レビューを書いてる途中で思い出したのですが、自分も昔は掃除機の音が極度に苦手で、とにかく嫌がっていたそうで母親が自閉症なんじゃ?と思っていた時期があったそうです。
徐々に慣れてきて掃除機にも反応しなくなったみたいなんですが、そういう兆候があるとやっぱり苦労したみたいでどうやって育てていこうと悩んだみたいです。
今では真っ暗な映画館で爆音上映を楽しむ子供に育ったので安心してくださいな。
今もまだ続いている推しサッカーチーム探し、どこかで運命のチームに出会えるといいなと願うことしかできませんが、父親とそうやって旅ができるっていうのも少し羨ましいところがあります。
この旅が成長にガンガン繋がっていってくれればなと遠い日本から願っています。
鑑賞日 11/28
鑑賞時間 18:05〜20:05
座席 D-7
上司が最高✨
素晴らしい作品です
既存の障がい児を巡る作品との共通性と独自性、そして疑問点
確かにテレビドラマ『ライオンの隠れ家』の自閉症者と同様に、自分のこだわりだけでなく、同伴者の言い分を受入れ、共に歩もうと成長する姿がみられるのが良いところであると感じた。『レインマン』にまつわる冗談や、ボディチェックでの係員の冗談も、少し可笑しみがあった。テンプル・グランディン氏も自分のルールをつくっていたが、本作の息子がつくったルールは窮屈な感じだった。
バス停や電車内で、親の躾がなっていないと非難する周囲の人々の姿は、日本ではそれほどみうけられなくなったような気がするけれども、ドイツではまだまだみられるのだろうか。それはそれで奇特である。
息子の相手をするために父親が勤務形態を変更することを上司に交渉したり、馘を覚悟で仕事を選ぼうとしたりしたところは、『どんぐりの家』に出てくる清の母親の姿勢とも通じる気がした。本作の父親は、妻も同じような苦労をしてきたことに思い到り、感謝しており、『クレーマー、クレーマー』等のように、妻から責任を丸投げされた夫とは違う。家族愛を尊重するような上司で良かったと思った。
家族や支援者が障がい者に対して堪忍袋の緒が切れ、怒鳴り散らし、やがて悔いる姿をみせる作品では、『ケニー』、『ギルバート・グレイプ』、『学校Ⅱ』も秀逸だった。
各競技場でのサポーターの熱狂的な応援や、鉄道旅の様子、オーロラの美しさもまたみどころであった。
疑問に感じたこととしては、生後1歳か2歳くらいの誕生日に電車模型をプレゼントに与え、興味を示さず、上体揺らしの常同行動を取ったことで、「アスペルガー症候群」の疑いをもたれたことが一つ。自閉症の判定基準の一つに、生後3歳くらいまでに発現するというのがあるが、「アスペルガー症候群」は、言語の遅れがないものが該当するはずなので、その年齢時点でのその判定はおかしいのではないか。また、発見者のアスペルガー氏はドイツ語圏のオーストリア人で、論文をドイツ語で発表したため、第2次大戦後もなかなか英米圏に広まることはなかったといわれるけれども、21世紀になったドイツ国内でさえ、その症状の子どもたちへの対応は、移民の子どもの受入れが進んでいたと思われる通常学校では行われず、分離制学校に委ねられることが多々あり、その学校に進学すると、大学教育への途は閉ざされているようである。恩師は、1990年代のドイツ国内の障がい児の学校インテグレーションが漸進的であると評していたが、本作を観た限りでは、日本の現状と比べても、かなり進展が遅れているように思えた。本作のパンフレットでもあれば、解説がなされていたかもしれない。最新の実態の詳細な研究成果が発表されることを期待したい。
心無い人と優しい人
今や自閉症の人が登場する映画は珍しくなくなった。まだまだ彼らに対する理解が深まっているとは言えないが、様々な描き方がされるようになった。本作では、ジェイソンが感じるもの(どう見えて、どう聞こえて、どう考えるのか)に焦点を当てている描写が印象的だった。マイルールが破られたときに取り乱す様も、そんなことを踏まえると受け入れやすくなりそうだ。本作でたびたび登場する、ジェイソンを拒絶する人たちの言動もわからないではない。自分たちが想像できる範囲内で物を言えばそうなってしまう。そんな現状をうまく表現したシーンだった。完全には理解できなくても、ジェイソンがそのままでいることを拒否しない、心優しい人たちがたくさんいたことも印象に残る。
ジェイソンが推しのサッカーチームを選ぶための基準が独特なのも面白いところ。変なキャラがいないチームなんて果たしてあるのだろうか。キャラもいて、鳴り物が大音量で響く日本のスタジアムは、ジェイソンにどこまで受け入れてもらえるのだろうか、なんてことを考えてしまった。
推しのサッカーチームを見つける週末旅行の話だが、ドイツサッカーのことを知っていても、まったく知らなくても問題ない。サッカーのことはほとんど関係ないから。彼ら親子の関係性が深まる過程をとても愛おしく感じられればそれでいい。ただ、クライマックスに泣けるような大きな出来事が起こるわけではない。穏やかに温かみを感じる終わり方だった。そんな映画もありだ。
自閉症の少年が父親とサッカー観戦する事で徐々に自分の殻を破って行く感じのドイツ映画。 本年度ベスト!!
自分が年間20試合程度サッカー観戦しているので興味があり鑑賞。
ドイツの色んなスタジアムが見られてテンションが上がっぱなしだった(笑)
自閉症のジェイソン。
日常生活で様々な障害がある中、自分が推せるサッカークラブを探す為、父親と2人でドイツの1部から3部リーグ全56クラブのホームスタジアムで試合を観戦するストーリー。
ラストで本作は実話ベースと言う事に驚くけどジェイソンの為に試合に連れて行く父親、ミルコの行動力が素晴らしかった。
ジェイソンとミルコが訪れるサッカースタジアムが全て美しい!
各クラブのサポーターが歌う歌も様々で迫力満点!
特にドルトムントのサポーターが歌う「You'll Never Walk Alone」の迫力が凄かった!
自分が推しているJリーグのクラブでもこの歌をサポーターが試合前に歌うけど迫力が全く違った!
ミルコが働くハンバーガーチェーンもミルコに対する優しい対応が素晴らしかった。
あんな会社で働きたい(笑)
深夜、サッカースタジアムのピッチで寝転びながら夜空に出現するオーロラの美しさが印象に残る。
あんな体験が出来るのが羨ましい。
親子や学校との衝突がある中、ミルコファミリーが諦める事無くジェイソンと共に成長する姿が素晴らしかった!
鑑賞後、近くの人が「サッカー生で見てみたい」って言った言葉が何故か嬉しくなった!
自閉症のジェイソンを演じたセシリオ・アンドレセン君が素晴らしい演技が印象に残る。
個人的には主演男優賞を差し上げたいです( ´∀`)
自分じゃあんなできない…
(時と場合により)ルーティンなんてぶち破れ!
原題: Wochenendrebellen
あー、うぉちぇーんどれべれ??
…失礼。
グーグル先生によると「週末の反逆者」ですか。
反逆者とはそうジェイソン君のこと。自らのルーティンや規則との闘い。心と心の闘い。愛情たっぷりの両親がサポーターとなったジェイジェイの反逆の勝利!でした。
権威的なオバチャンと衝突してしまうバス停での一幕にて「この子の苦労の何がわかるんですか?」と訴えるママの心境、見ているこちらも心が痛い。その他、登場し行き交う人々に悪人は少ないのは気休めとなった。(トイレで手を出してきたキッズは別ね)
至って普通の、むしろ優しさのある人しか出てこなかった物語であるが故に、一般的な社会通念とぶつかりまくってしまう主人公の障害の辛さ、切なさを際立たせていたように感じた。
物語のクライマックスは教室でのスピーチ。レビューで何度か触れている事だけど、やはり人と人の分かり合いは「言葉」なんだよな。にんげんだもの。
障害を持つ側も、社会側も、互いにすり寄る姿勢の「通念化」が必要というお話ですね。
実在モデルのジェイソン君は19歳。努力の末、自己と環境の分析は済んでそうな雰囲気でよかった。宇宙物理の学者さん、ぜひ実現して!本作のエンドクレジットにその後についての説明文を追補してくれたらいいですね。
***
The 欧州サッカーファンの私としては、実在テーマの「サッカーチーム全部見たい」については、ええ、ええ、いいじゃない!とお爺ちゃんと同じく無邪気に賛同してしまいたいところだ。が、しかし!例えば浦和レッズのゴール裏で想像してもですよ…。ハンディキャップの有無に関わらず子供連れでの観戦は、受け入れ体質はさておき、親としては…イヤーどうかなーっ(^_^;)て感じですよね。我が家はおとなしくメインスタンドから見てます。
そして毎週末はキツすぎる〜笑 あんな素晴らしい会社は滅多に無さそうですし。
私の好きなチームのひとつだけども、作品がドルト推しなのはなぁぜなぁぜ(言っててイラっ!)まぁいいけどね。
コマンやムシアラなど映って眼福、スーパースター軍団のバイエルンは、こう見るとやっぱりスゲ〜(*_*) アンチの気持ちも、わかるぞい。
接してみないと分からないもんだな
『僕が跳びはねる理由』でなんとなく自閉症について知ったけど、実際に接したことがないと分からないことも多い。
本人に悪気はないし、親も大変というのも理解できるのだけど序盤の、お前らが合わせろとでも言わんばかりのお母さんが若干モンスターっぽく感じてしまい、ちょっと辟易。
バス停でのコトも説明すれば分かるのに、あんな怒鳴らんでも。
音に敏感なのにサッカー観戦とは、と思ったら実話なのですね。
入場のボディチェックは、ジェイソンにとって大きな一歩でグッときた。
笑えるエピソードもあり、微笑ましい場面もありつつも、おぉい!ってのも度々あるから、相反する感情が行ったり来たり。
後半になって、お母さんも表情が柔らかくなり、ジェイソンも少し成長して良かった。
何よりお父さんの会社が理解ありすぎでドイツらしいというか、日本にはなさそうだなぁ。
自分の理解が追いつかない部分もあるけれど、良い映画だった。
残念なマスコット…確かにね…いやカワイイけどね。
アスペルガーの息子を持った夫婦。一人では支えきれなかった。選手交代しながら、祖父母という強力なサポーターに支えられながら、本人もゆっくりと変わっていく姿が描かれます。
アスペルガー症候群の少年が主人公の作品です。
ドイツ作品は余り鑑賞した事がないかも ということも
あって鑑賞することにしました。・_・
鑑賞開始。さて。
主人公の少年が誕生する時点から始まります。
素直に喜ぶ両親だったが、定期的な健診を受ける
うちに、医師から告げられる。
” この子の発達段階に正常ではない特性がみられます ”
突然の告知を、すぐには理解できない両親。 …分かる ・_・;
” それは治るものなのですか? ”
” いいえ この状態は治るコトはありません ”
納得しがたい現実に向き合いながらの生活が続く。
母親が仕事をやめ(翻訳?だったか)世話をする。
父親は… どうやら仕事に逃げているようだ。…うーん。
母方の祖父母が、何かと生活の面倒をみてくれている。
両方ともサッカーのTV観戦が大好きなようだ。
この少年=ジェイソン君は10才になった。
普通の小学校に通っている。 …のだが
小学校の同級生とは上手く行かない。
自分のルールやこだわりが強いのだ。 …分かる
宇宙のことに興味と才能がみられるようなのだが
それすら同級生のからかい対象になっている。
” 太陽系の惑星って何がある? ” と訊かれ
太陽に近い順番では 水星 金星…
大きさの順番では 木星 土星…
同級生たちは、同じことを何度も尋ねるのだ。
聞かれるたび、同じように応えるジェイソン君。
ある日、応援するサッカーチームも無いのかと言われ、
無いと答えると、普通はあるものだと言われる。
ゆりかごの中で推しチームは決まるのだ とも。
” 自分には推しチームが無い ”
そのことが妙に気になり、帰宅後両親に、それぞれの
推しチームがどこかを尋ねる。
サッカー好きの祖父母も話に混ざり、ああだこうだ。
話を聞いただけではぴんと来ない。それなら…
ジェイソン少年、推しチームを見つけるにはスタジアム
で実際の雰囲気や環境、サポーターの質などなど
自分の目で見て判断したい と主張する。
気軽にジェイソンとその約束をした父親。
どこにしようかと決めようとすると、ジェイソン君。
” 最初のチームはくじで決めるから ”
” 最初? ”
” 1部から3部、全部をみないと決められないよ ”
” … …” …気持ちは分かる
こうして、週末ごとのドイツ国内観戦の旅が始まる。
ブンデスリーガに所属するクラブのスタジアムを全て訪問
実際に観戦し、どのクラブが自分に合うかを決める。
そういうことの約束だ。
ブンデスリーガのチーム数は多い。
1部から3部までを数えると、チーム数は50を超える。
絶望的な困難を予想しながらも、実行に移す父。
仕事中心だった父の、息子との行動に安堵し、旅の成功を祈る母。
贔屓チームをTV観戦で応援する祖父母も、父と息子を後押しする。
一つ目の訪問から苦難が続く。
移動中の電車。パスタに付いたソースがガマンできない。
” 解決して! ”
食堂車から席に戻ろうとして、パスタの皿を落としてしまう父。
少年の頭と心が悲鳴をあげる。
” 食べるものをムダにしてはダメなのに!”
多難すぎる前途に、父親の心も悲鳴をあげる…
自分のルールに合わないモノを受け入れない息子と
解決してと言われても出来ないことの方が多い父。
そんな中での父と二人で国内を電車で移動。
スタジアムではサポーター席で試合観戦し周囲の様子を観察。
それに付き合う父と、ゆっくりと
自分のルールを変えることも覚えていく主人公。
そして観戦の旅を重ねていく内に…
◇
と、いう感じのお話でした。
決して悪い内容の話では無いのですが、
「解決して!」と騒ぐシーンの多さ。
観ていて頭が痛くなってきたのも正直な感想です。・_・;ハイ
そんな中でも
家族の理解が素晴らしかった。特に祖父母。
祖父は「自分の父親とジェイソンは似ている」といい
さらに「私は父親のことが大好きだった」とも口にする。
” 周りに自分の理解者がいる ”
そのことの大切さに改めて気付く作品でもありました。
観て良かった。
◇あれこれ
■アスペルガー症候群
作中で「最近流行りの病名」という言われ方をしてました…。
うーん。最近になって出現したわけではなく、昔からあった
病気・症状だろうとは思います。
・落ち着きの無い子
・夢中になると周りが見えなくなる子
・周囲の輪の中に入れない子
あれ? 自分も当てはまる… うーん。そうかも。
有名になっただけではなく、周囲の理解も進むといいなぁ と
そう切実に願います。
■タイトル
翻訳:週末の反逆者(…うーん 物騒)
自分のルールへの叛逆 だったり
周囲の価値観への叛逆 だったり
ゆっくりとでも、周囲を受け入れることも必要
自分を少しでも、周囲に分かってもらうことも大事
自閉症の人間も、少しずつゆっくりとでも
変化も成長もするのだということを改めて
認識できる作品です。・-・
◇最後に
地元にJリーグのチームがあって、スタジアム観戦が日常
生活になっていたり、そこまででなくともスタジアム観戦
の経験がある方のほうが、共感しやすい内容なのかも
そんな風には感じました。
静かな環境が好ましい方にはちょっと…かもしれません。
その点で、現実のジェイソン君も頑張ったなぁ…と。
※本人の画像がエンドテロップに出てますがイケメンです♡
☆映画の感想は人さまざまかとは思いますが、このように感じた映画ファンもいるということで。
全73件中、21~40件目を表示