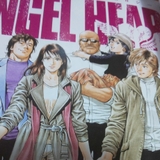十一人の賊軍のレビュー・感想・評価
全457件中、141~160件目を表示
有名無名絶妙なキャストに芸人さんが水をさす
auマンデー『十一人の賊軍』
予告から楽しみにして、山田孝之x仲野太賀W主演
時代劇版の仁義なき戦いと言われてますが・・・
私的には、時代劇版スーサイドスクワット
新政府と旧幕府軍の争いの中、砦を守れば無罪放免になる極悪人達の抗争劇
主演2人が、交わりそうで交わらない中・・・
個性豊かなキャラ達が裏切りに裏切られ助け合い討ち死にしていく描写は、白石組ならではの迫力!
今年三本目の時代劇ですが、殺陣シーンの迫力はこの作品が一番迫力ありました
特に爺(じ)っつぁんと呼ばれる老武者・本山力さんの鬼気迫る剣と槍捌きが観る価値あり!
キャストは、有名無名の組み合わせが最高でしたが、俳優実績ない芸人さんはいらない
この作品撮影中に大河主演が決まった仲野太賀の快進撃が始まるラストにスタオベ
素晴らしい殺陣と悪党の生き様
予告がかっこよすぎてずっと楽しみにしていた作品。
悪党の決死隊的な設定の作品は大抵ハチャメチャで面白いと思っていて、この作品も例に漏れずとても面白かった。
特に殺陣のシーンの迫力は、音も相まってすごいものだった。それぞれのキャラを活かした戦い方で、悪党ながら必死の形相で戦う彼らに感動すら覚えた。
意外とあっさり死んでいくキャラも多く、11人じゃなくなるのがだいぶ序盤ではあったが。。
大悪党のデカい男がわりとすぐ退場したのが、期待値高かっただけに少し寂しかった。
年寄りが強キャラというのもありがちな設定ではあるが単純に楽しめた。
しかし阿部サダヲには腹立たしい。
時代が時代だからとは思うし、城下を守るためなんだろうとは思うので、彼も彼なりに仕事をまっとうしただけで完全に悪者とは言えないが、なんとも容易に納得のいく決断ではない。
千原せいじらがあっけなく死にすぎだろ!
それによって阿部サダヲの外道さが引き立てられてたと思いました。
ずっとミギーの声にしか聞こえないし笑
しかし、簡単にはいかない戦争や政治、そのために死にゆく末端の人間たちを映画的な救済を与えずに描き、無情さをひしひしと感じる作品でした。
最後に、オープニングで題名が出るところ、もうちょっとかっこいい演出できなかったの?!と思ってしまった😓
ゴシック体じゃなくて普通に筆文字で良かったんじゃない?!とか思っていたのも束の間、作品自体には夢中になれたので良かったです。
歴史背景を知ると余計楽しめるかも
映画の冒頭とか、途中でナレーションと文字での背景説明があるので、なんとなく新潟港湾地域をもつ新発田藩が重要な意味を持っていたことは伝わるかなと思いますが
幕末の歴史の中で、近年役所さんが長岡藩の家老を演じた映画「峠 最後のサムライ」がありましたが、あちらは戦争を避けようとして避けきらなかった話ですね。逆に新発田藩は旧幕府側と官軍を手玉に取り、うまく切り抜けたという話ですが、結局のところ、その裏には賊軍として少人数で砦を守るために死地に赴かされた人たちがいたということですね。
罪人なので、選択肢はなかったわけですが、それにしてもかなり過酷だし、映画的には家老の阿部サダヲがかなりの嫌われ役ですね。街を救ってはいるのだけれど。武士として卑怯に映るというか、人情的にはかなり非道。途中でもかなりえぐいシーンがあります。
昔の東映的骨太時代的なところが話題になっていますが、実際殺戮というか戦いのシーン、首落としたり、爆殺したり、腕を斬り落としたり結構えぐい。
PG12だったけど、実際R15?Rー18くらいのイメージじゃないですかね、血とかドバドバです。
苦手な方はご注意ください、
演技的には仲野太賀よかったですけどね。
尾上右近がちょっとうざいくらい目立ってましたけども、作品内の活躍に比べ、とにかく存在感はすごい。
舞台映えっていうんですかね笑
吉本芸人を使う意味は正直よくわからなかった。。。抱き合わせ?ですかね。。。
11人は多すぎか?
感情移入できないせいか、全く泣けなかった。11人のうち女の子ぐらいしか印象に残ってないし、あと10人は汚い男ばっかりで見分けが付かない(イケメンが一人居た気はする。)名前も誰一人覚えていない。そもそも名前呼ぶ場面あったっけ?
なぜ11人もいるんだろうと思ったが、おそらく演出の都合で11人は必要で、人数合わせって所かな。11人のうち数人だけ主要人物にするという意図を感じたが、ただそれも失敗してるっぽくて、女の子しか覚えてないやという感じ。結局見ている人を混乱させるだけなので、最初から6人ぐらいにしておいたほうが良いのでは?
ストーリーも全体的によくわからんかったわ。戊辰戦争を勉強してから見たほうが良いかも。
大砲とか鉄砲とか音デカいので苦手な人注意ね。
仲野太賀の殺陣が良い
出演者さんたちが、それぞれの役を上手く演じきっていた作品だと感じた。特に鷲尾兵士郞役の仲野太賀の殺陣は、とても良かったし迫真の演技だ。映像も音も迫力が有り、家庭での鑑賞(DVD等)より映画館で観るべき作品だと思う。残念なのは、賊軍の10人の人物像が深掘りされていない。家老(阿部サダヲ)が、お白州で首を斬っていくシーンがあったが、このシーンをもっと短くして賊軍の深掘りをしてほしかった。
155分、生首多め。見応え十分。
この手の物語は、1人1人のスキルの披露であったり、緻密な計画での攻防などが見せ場となるものだけど、本作の魅せどころは別だった。
団結していない決死隊が、命が危険にさらされてから徐々に闘う意志が出てくる。
だが、決して団結しているわけではない。
裏切りや嘘もある……この感じが生々しい緊張感を醸し出して観ていて飽きない!
刀の達人も中にはいる(本山力がすんばらしい)
あと官軍の砲弾や、賊軍の爆弾の威力がちゃんと生々しいのがイイ!
砦での攻防とは別に、家老役の阿部サダヲがメインの同盟軍との駆け引きも見もの。
(しかしラストマイルといい本作といい、今年は阿部サダヲの悩める中間管理職っぷりが多い)
あと時代劇には声の良い人のほうが得している気がするのは自分だけだろうか?
尾上右近、松角洋平、そしてナダル(ナダルはセリフだいじょうぶなのか!?と別の緊張感を醸し出していた……意外に良かったですが(笑))
終盤、武士の矜持をみせた仲野大賀と覚悟を決めた山田孝之が本当に良かった。
ダブル主演にも納得。
ぜんぜん関係ないけど……『拾われた男』の原作者・松尾諭と主演・仲野大賀が決死隊として共演していたことに後から気づいた(笑)
何も考えずに楽しめる
戊辰戦争。同盟軍(旧幕府軍)と官軍(新政府軍)に挟まれた新発田藩の一計により戦いに駆り出されたならず者たちの死闘を描く面白さ満載の作品。
ならず者だけあってリアルにグダグダな所が面白くもあり怖くもある。ある意味やりたい放題。およそ結末は想像つきそうな話ではあるが、それを上回る脚本力と俳優陣の絶妙な演技によって最後まで飽きさせない。
主演の山田孝之も良いんだけど、それ以上に仲野太賀の演技が素晴らしかった。特にど迫力の殺陣シーン。口をポカ〜ンと開けて魅入ってしまった。カッコよすぎるぜ。
あとは爺っつぁん役の本山力の殺陣も凄い。見ている手足につい力が入ってしまう。さすが数々の時代劇に出演してるだけある本物の腕前。いい爺さんかと思いきやまだ55歳!驚きだ。
ほか罪人たちも曲者揃いで魅力たっぷり。ひとりでも釣り合わないのいるとぶち壊しだが、よくも揃えたものだ。
何も考えずに楽しめる痛快時代劇。満喫しました。
とてもよかった
新発田の囚人が、長岡藩のふりをして官軍と戦うというのがややこしい。その頃新発田城を訪れていた人たちが奥羽同盟で、それもあれ?官軍だっけどっちだっけ?と混乱する。それから新潟弁が泥くさくてちょっと恥ずかしい。実際、現存している新発田城は何度か子どもを連れて行ったことがあるけど天守閣がなくてすごく小さい。映画の中では立派なお城のようなスケール感がある。
11人対軍隊が丁寧に違和感なく丁寧に、壮絶な戦いが描かれている。合戦場面は素晴らしかった。山田孝之は何度も逃げたり、誰も信用していなかったのに最後、戻るところは泣ける。
面白いんだけどずっとモヤモヤ(主に阿部サダヲのせい)
映画館に行くほどじゃない
凄まじい でも見たくなる
間延び
東映制作陣の底力
白石和彌監督の前作に引き続いての時代劇。今回はお得意の生身の人間の痛さを味わわせるようなアクション劇で、2時間半の緩みない演出は、もはや巨匠の域に達したかのよう。
戊辰戦争を舞台にしていて、考えてみたら、日本刀での斬り合いと銃や大砲などの兵器が渾然一体となった戦いで、これは東映が最も得意とするところ。特に今作は新潟を舞台にしているので、黒い水(石油)を使った爆破シーンが凄まじい。密度の濃い画面に、リアルかつ美しい群像チャンバラ、銃・爆薬・炎の特殊効果と、東映制作陣の底力を見せつけられた感じ。
物語としては、もう少し賊軍たちにフォーカスしても良かったのでは。主人公二人の対決とか、ニセの弟が兄を慕う因縁話とか、あってもよかった。
役者陣では、特に仲野太賀に眼を見張った。ラストの壮絶な殺陣が本当に凄い。尾上右近もコメディリリーフ的でいい味。謎の侍、本山力の刀姿が美しい。鞘師里保はもう少し蓮っ葉さがほしかった。
シナリオを練り直して、いっそのこと3時間を超える大作にしていれば、七人の侍に匹敵するくらいの作品になっていたかも、と思うところもある。
時代を超える人間の生き方講座
ここに出て来る人たちは、基本的に罪人です。その配置が、個人的にはある種の裏テーマにも繋がっているのかな、とも思っています。
キャラクターは、とても個性的でともすればキャラ的な表層感が出そうだと思いましたが、それぞれが持つ「罪状」がある種の人間的厚みとなって、彼らがどういう人生を生きてきたのか、何となくでも最初から感じさせてくれたと思いました。また、山田孝之さん演じる主人公が一番狡くて生きることに貪欲なのも人間らしくて表面的ではない好印象を持ちました。恐らく、主人公は何があっても必ず妻のところに帰りたいという、単純だけど純粋な欲求を果たしたいだけなのだと思いますが、ならば何故罪を犯すようなことをしてしまったのか…そこにこの主人公の矛盾と葛藤が垣間見えた気がしました。
一方で、仲野太賀さんが演じるもう一人の主人公は、一途な武士という感じで、まったくブレることがありません。最後まで自分が信じるものを信じ切れるだけの強さがあります。そのためには討ち死にも怖くないという感じなのですが、いつもは清く正しく冷静な紳士然とした生き方をしているところも、朝の道場シーンで垣間見え、青い炎という印象です。だからこそ、主人公はダブルであるべきで、この対照的な二人だからこそ、思っていることが違っていても、起こる事象は同じになっていく楽しさがあるのだなと思いました。
影の主役とも言えるのは、阿部サダヲさんが演じる新発田藩を真に取り仕切る家老で、この人は単に自分の目に映る家族や新発田で生きる人々を生かすためにのみ奔走しているように感じました。長岡藩にも新政府にも詰められ、身内であるはずの殿様はお子ちゃまで我が儘言い放題。現代社会ならブラックオブブラックな環境ですが、懸命にすべてを綺麗に収めようとする姿勢には、美しさすら感じました。そんなこの人は、目的遂行のためには、味方にも嘘を吐くし、農民の首を自分の手を汚してまで斬っていくという惨さを見せつける一方、策略がバレるとびっくりするほど潔く切腹の命令にも応じようとします。加えて、当たり前のように自分の娘を愛し、その意も受け取ろうとするなど、随所にただの悪者ではないことが強調されていたように感じました。
その他にも、元長州藩剣術指南なのに強盗殺人しちゃったお爺ちゃんとか(滅茶苦茶に強い)、エロ坊主とか、一家心中の生き残りとか(普通に不憫すぎる)、詐欺師とか、不義密通とか密航とか辻斬りとか、罪状からでも想像力が掻き立てられますが、その人たちが短い時間の中でも見せてくれる考え方や行動理念が、この厳しすぎる時代を生きるからこそ強さの源流のようにも感じられ、力強くも見えるのでした。
何より良いのは、山田孝之さんのキャラだけでなく、全員が何かしらずる賢くて、愚かな面を持ち合わせているのがとても複層的というか、人間的にリアルで面白く思いました。
物語自体は、「最初は我欲のためだけに砦を守っていたが、やがて共通の敵(新政府軍)を倒すという目的のもとで情が芽生えて結束し、そのために死力を尽くす」という単純な構造だと思うのですが、キャラクターが生き生きと動くだけで、これだけ物語そのものや当時の世情にも厚みが増して、考えが深まるというのが、本当に面白い物語だと個人的には感じた次第です。上述した「死力を尽くす」を山田孝之演じる主人公が最後に自爆攻撃という壮絶な死にざまで見せてくれること、また、その直前に一ノ瀬颯さん演じる「ノロ」(この人だけ仇名とキャラが合致し過ぎて覚えていました)に生きるようにお願いすることで、より一層重みが積み上がったようにも思いました。
この映画に限らず、すべての物語のテーマは、その構成側も含めて各々だと思いますし、そもそも物語とは、それぞれの想いを受け止めるだけの器があればあるだけ良い作品だと思うのですが、個人的にこの作品のテーマは2つかあります。
一つ目は「白黒ハッキリつけることとはどういうことか」、二つ目は「受け容れるとはどういうことか」ということです。
一つ目に関しては、仲野太賀さんの主人公が大変白黒ハッキリしている方で、上記のとおり曲がったことが大嫌いな本物の武士然としたキャラクターでした。しかし、結果はこれも壮絶に刺されまくって(その分だけ殺しまくりますが)死にます。しかも、味方だったはずの阿部サダヲさん演じる家老が放った、拳銃によって(これもこのキャラクターらしいグレーな処世術が垣間見えて好きです)。これに代表するように、この作品は「白黒ハッキリさせようとした者=死」であり、「グレーな半端者=生」という暗黙のルールが存在しています。その証拠に、腹を刺されたものの一度は生き残った武士も、騙していたことを打ち明け一度主人公側に言った途端に状態が悪化、最後は言い名付けに見守られて死にます。それに、その言い名付けである家老の娘本人も、そもそも賊軍側に秘密裡に侵入して共闘しようとするほどの覚悟を付けていたのですが、父親が「賊軍を生かす」という自分との約束を反故にして行った殺戮を知った結果、自決しました。
一方、阿部サダヲさん演じる家老は言うまでもなく、新政府軍とてそもそもは江戸幕府お抱えの藩だった訳ですが、それが徳川慶喜という「ザ・徳川」を神輿に担いで「旧徳川軍」と戦争をしていること自体、新政府軍が如何にグレーな存在かを感じさせます。また、生き残ったノロや鞘師さん演じる紅一点なども、一緒に死んだり復讐することを選ばず、謂わばグレーでいることを選びました。結果、最後まで生き残ったのです。何より、山田孝之さん演じる主人公の妻が、女郎になっても生きており、理不尽に犯されても夫が罪人になっても、必死に生きようとした結果、ある種のグレーを選んでいるからだと感じました。その後に呆気なく死んでいたという結末にしようと良かったはずだと思うので。
ここまでで感じることは、現代に通用する「白黒ハッキリさせることの困難さと、グレーを選ぶことの代償」ということだと感じます。簡単にいうと、「白黒つけるのはカッコいいし悩まずに済みそうだが、結果的に容易に排除される」ということであり、「グレーは生き永らえることはできるけど、その分だけ背負うものも大きくなり、場合によっては大きな代償を支払うことになる」ということです。事実、家老は娘という大きな代償を支払って新発田の平穏を保ちましたし、ノロたち生き残りや女郎となった妻も、一生涯、死んでいった者たちのなにがしかを背負っていかねばなりません。現代にも同じことがいえると、私は思いました。細かいことを言いだすと、コンプライアンスに抵触して、それ以外の言葉も消されてしまうように思うので言いませんが、色々なことを踏まえて、本当にそう思いました。
次に、二つ目の「受け容れること」についてですが、これは割と簡単で、この作品に出て来るすべてキャラクターには、結局のところ本当の悪意は感じられません。敢えて上げるとすれば、玉木宏さん演じる山縣狂介(有朋)のようにも思いますが、それも山縣の生き方を考えると、グレーになりつつも愚直に日本が生き残ることに命を懸けていたようにも思えます。罪人も含め、みんなが精いっぱい生きている。だからこそ、仲野太賀さん演じる藩士であった主人公は、それぞれが悪事を働いていても一人の人間であることを認めて受け容れ、結果として藩を見限り自分を「十一人目の賊軍」と称して死ぬことを選んだと思う訳です。これは作品をメタ的に見ても思うことで、阿部サダヲさん案じる家老が、賊軍を裏切った後で、町民に親しまれ、誇らしげに日が照る新発田の街を眺めるというシーンがあります。つまり、実際のところ、この家老のおかげで生きられた人々がいるし街があることが示されたと感じるのですが、これは観客である私たちに、人間の複雑性を感じさせるための演出であるように感じました(結局、この後でどん底に叩き落とされる訳ですが)。
他にも書きたいことはたくさんありますが、取り敢えず、簡単に言葉にしてみました。一つ難点を言うのなら、確かに他作品と相対的に見て時間が長い(個人的にはまったく思わなかったですが)ことくらいです。
長文失礼しました。ご配慮いただきありがとうございます。
期待し過ぎたかな。山田孝之や鞘師里保の殺陣も楽しみにしていたけど、...
全457件中、141~160件目を表示