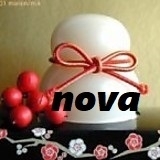十一人の賊軍のレビュー・感想・評価
全457件中、101~120件目を表示
みんな強すぎw
官軍に挑んだ多士済々の11人の激闘群像劇
幕末から明治維新にかけて、新政府軍(官軍)と旧幕府軍が繰り広げた戊辰戦争。この戦争で旧幕府軍側の奥羽越列藩同盟に加盟していた新発田藩が生き残るため官軍に寝返る奇策を実行した11人の壮絶な激闘を圧倒的な迫力で描いた群像劇である。
新発田藩・家老・溝口内匠(阿部サダヲ)は、官軍への寝返りを画策していた。折しも同盟軍は新発田城に赴き参戦を要求してきた。官軍も新発田城目前まで迫っていた。両軍の衝突を回避するため、溝口は官軍の進路にある砦に長岡藩を装った死罪が確定した多士済々の罪人達を送り込み赦免を成功報酬にして官軍と戦わせる。罪人達は奮闘するが、大砲を使った圧倒的な戦力の官軍に苦戦を強いられる・・・。
大砲の爆音が強烈。敢えて強烈にしたのは観客への意識付けでありラストへの布石だと推察できる。頭の弱い花火師の息子罪人ノロが黒い水を見つけるシーンも同様である。黒い水が何かは推察できる。罪人達が望遠鏡で見つける官軍布陣背後の山の中腹にある横穴も同様。布石を打つのは大切だが、布石なので観客にもっと考えさせて欲しかった。
序盤で煙幕を張り砦の門を利用して官軍勢を分断して倒す方法は七人の侍を彷彿とさせる。しかし大砲があるなら、門、物見櫓を真っ先に破壊するのが定石ではとの疑問が沸く。
戦力の優劣に関わらず理詰め、緻密さが戦いの必勝条件だろう。
溝口が同盟軍の疑いを払拭するため、罪なき市井の人々を次々と斬首していくシーンが出色である。画面に映るのは彼の血染めの顔と斬首された首のみ。彼の表情に喜怒哀楽はない。彼もまた戦争の被害者であることが画面から伝わって胸を打つ。名演技だった。
罪人達はそれぞれの事情を抱えているが、キーパーソンを絞って深堀すれば、もっと重厚な人間ドラマになっていただろう。罪人達を束ねる11人の賊軍リーダ鷲尾平士郎役の仲野太賀の殺陣が見事。剣捌き、姿勢が決まっている。とても時代劇初出演とは思えない。
観終わって“戦争の理不尽と不条理”という言葉が心に強く刻まれた。
和製スーサイドスクワッド
物語の構成とか面白かったなあ。
この砦を守る云々ってのは付属品みたいなもので、新発田藩的な大問題は、同盟軍を如何にして出立させるかって事である。
砦はどうでといいとまでは言わないが、目の前に大問題が居座っている状態なのである。
で、本来ならば忠義の徒とかが、砦を守り、家老連中が「今、しばらく!しばらく持ち堪えてくれっ」と、唇を噛み締め血の一つも流すもんなんだけど、砦を守ってるのは罪人なわけだ。
藩としては死んでくれても一向に構わず、なんならどうせ死ぬなら役に立てと言わんばかりだ。
で、まぁ、罪人達が奮闘するわけなんだけれど…どうにも感情移入しにくい。
なぜだかわからない。
10人もいるんだから、誰か1人くらいは居そうなもんなんだけれどそうならない。
なんか魅力的なキャラがいない。
中野氏は奮闘してた。体つきが侍のようであった。
そんなもんだから、決死隊が順次死んでいく時もあまり感情が動かない。
全員の腹が決まり反撃だって時もテンションはあがらない…真ん中にいる歌舞伎俳優が軽口を叩くからだ。
この人は抜群に上手いのだけど、なんか、上手すぎる。指先まで神経が行き届いているような芝居に見える。上手すぎて違和感ってちょっと珍しい感想だ。
まぁ、なんせ、やってる事やってんのにイマイチ盛り上がらないのだ!
なんでだ!?
結構好きなタイプの話だよ!
なぜ、俺のテンションは上がらんのだ!!
謎だ…。
俳優陣は山田氏筆頭に皆様、熱演でした。
難ありな人も居るにはいたけど…。
なんか分割されてんのが良くなかったのかなあ…。
砦と城内の繋がりが薄かったとか、砦の人間達と市井の人々との繋がりが少なかったのかな?
なんか原動力の源がピンと来なかったのかも。
中野氏が叫ぶ「城下を火の海にするわけにはいかない」って決意が刺さるような連中じゃないはずだし、中野氏の為に生命を賭けるような間柄でもない。
舐められてたまるか、死んだ方がマシだってタイプでもない…となると、キャラ立ちの方向性が違ってたのかなあと訝しむ。
老兵が言う「義によって助太刀いたす!」が全然響いてこないんだもの…お前、何に感化されたのさ?って問いかけてみたい。
あの砦って、最重要拠点なわけで…アレを通過されたら敵対する軍が城下で鉢合わせする事になり、町は戦場と化すは、両軍から卑怯者と罵られ武家の面目は潰れるわで、藩としては瀬戸際の分水嶺なわけで…。
あそこにダミー部隊を送り込んだ家老はかなりな切れ物で、起死回生の妙案でもあったと思う。
なのだが…あまりにおざなりというか、軽視しすぎというか。背負わなすぎというか…。まあ、城内は城内でそれどころではなかったのだけど。そう新発田藩としては内側と外側から絶大な圧力をかけられてる状態で、崖っ淵もいいとこなんだけれど…と状況は理解するも、イマイチ入り込めないもどかしさ。
白石和彌監督とは相性が良かったんだけど、今作だけはなんだかズレてた。
油田に火をつけたんだから、崖の一つも吹き飛ばせやって思う。
侍版「ワイルドバンチ」?
十一人目仲野太賀の殺陣が熱い
ポスターのビジュアルから伝わってくるのは「七人の侍」への熱烈なオマージュで話は和製「スーサイドスクワッド」。大好きな白石和彌監督が「仁義なき戦い」の脚本家・笠原和夫のプロットを映画化したと聞いて期待値が上がりすぎないように用心していた。前作の「碁盤斬り」がちょっと肩透かしだったのだけれど最後に無理やり殺陣シーンを設けたのもこの企画の前哨戦、時代劇予行演習なんだろうと納得していたのである。千葉県鋸南町に砦や吊り橋の大規模なロケセットを作って官軍との攻防を撮影したのだという、予告編を何度も見せられるにつけこのインディージョーンズ的な制作手法がハリウッドの真似事で終わることを危惧したが白石監督にとってはより大きな予算を掛けて思いっきり遊べる現場を手に入れたということなのだろう、子どもの頃切り崩した山の斜面でやっていた戦争ごっこをこれだけの兵隊をそろえて遠慮なく合法的にできるのだから楽しくってしょうがないに違いない。晩年の黒澤明巨編のごとく大味になることを恐れたがそこは白石監督の手腕はさすができっちり面白く及第点にまとめて見せた。NHK大河のイメージが残る山田孝之のキャスティングが残念で綾野剛ならばと思ってしまうのだ。
幕末スーサイドスクワッド
信念を貫くということ
凄え見応えあり!
中野太賀が頑張ってた!2026年大河ドラマ主演だけに〜
時は幕末!
徳川幕府に従う複数の藩に囲まれた東北の小さな藩では
周囲の藩との同盟を裏切り、
実は新政府軍に着きたいと密かに考えており
なんとか周辺の藩に悟られずに新政府軍に与する方法を
模索する中で、処刑が確定している罪人達に
無罪放免と引き換えにある任務を与えるところから始まる。
限られた空間で少数の人数で、多数の敵と戦うと言えば
「七人の侍」の系譜の映画で、
ちょっと前には「十三人の刺客」と言う、
これまた私の好きな傑作と同じような
シチュエーションの映画でした。
中野太賀が頑張ってた!2026年大河ドラマ主演だけに〜
それと今回紅一点として鞘師里保(サヤシ リホ)が
時代劇にありがちなか弱い女性ではなく
積極的に何かを守ったり、やり遂げようとする
現代的な女性を魅力的に演じていて
ああ、日本の俳優さん、本当にそうが厚いな〜〜と
実感した作品でした。
ダイナミックなシーンも多いですが
音響の凄さは映画館でしか味わえないので
是非是非、劇場で!!!!
で、月に8回くらい映画館で映画を観る中途半端な映画好きとしては
白石和彌監督の映画らしく、
血飛沫は普通、指はまるでフランクフルトの様に転がり
腕は蓮根の様な断面を残し、
生首はゴロゴロ転がり、なんなら時にスイカ割り状態!!
ゴア描写がかなり激しいので苦手な方は要注意です。
山田孝之とダブル主演の仲野太賀さんは殺陣も頑張ってました。
基本、罪人達なので、本気の殺陣が要求されるのは
仲野太賀さんと罪人の中にいた剣豪役の山本力さん。
山本さんの殺陣のシーンはここ最近
時代劇鑑賞が続いている中でもキレッキレ!!
藩と領民を守るため他藩を欺き大事な家族まで失う家老の
板挟み的苦悩を演じる阿部サダヲ。
こういう役が本当に上手いわ。
ただ、全部見終わった後、よく似たような作品として
「十三人の刺客」を思い出して
「ああ、『十三人の刺客』面白かったな〜〜」
そんな帰り道〜〜でした。
カラーだけど東映集団時代劇ってこともあり工藤栄一監督っぽい
2024年映画館鑑賞109作品目
11月17日(日)イオンシネマ石巻
6ミタ0円
監督は『凶悪』『日本で一番悪い奴ら』『彼女がその名を知らない鳥たち』『孤狼の血』『止められるか、俺たちを』
『凪待ち』『ひとよ』『孤狼の血 LEVEL2』『死刑にいたる病』『碁盤斬り』の白石和彌
脚本は『アンダルシア 女神の報復』『任侠ヘルパー』『日本で一番悪い奴ら』『孤狼の血』『孤狼の血 LEVEL2』の池上純哉
原案は『日本侠客伝 血斗神田祭り』『仁義なき戦い』『愛・旅立ち』『玄海つれづれ節』『肉体の門(1988)』の脚本家の笠原和夫
時代は慶應4年(1868年)戊辰戦争
江戸時代最後の年
この年の9月には明治に
舞台は新発田藩(現在の新発田市)
粗筋
新政府軍が官軍で旧幕府軍が賊軍
勝利目前の官軍側につきたい新発田藩ではあったが巻き返しに躍起な賊軍である奥羽越列藩同盟に加勢を求められ苦しい板挟み状態
そこで賊軍の長岡藩の旗を掲げ国境に砦を作り官軍に立ち向かうふりをして奥羽越列藩同盟に安心させ新発田藩から出てもらい狼煙をあげて決死隊を藩に戻し官軍を迎える計画を立てた
藩士だけでは足りず罪人の寄せ集めで結成された決死隊
砦を守り抜けば無罪放免になると聞かされた罪人たちは決死隊に参加したがそれは嘘だった
蜥蜴の尻尾切りで藩士はともかく罪人たちは口封じでやはり殺される運命
罪人たちと新発田藩剣術道場道場主鷲尾兵士郎は初めそれを知られされていなかった
それでも特別な配慮に期待し砦を守る決死隊
155分だが長くは感じなかった
それだけ自分好みで娯楽映画として楽しめたということだろう
長いからといっても例によってトイレに行きたくならなかった
設定としては大砲や花火による爆発の数々は迫力がある
特撮ヒーローものの爆発は間抜けな感じがするがこっちはなかなかスリリング
なぜだろう
元前頭豊山が引退し俳優に挑戦している
罪人になった経緯は辻斬りでなく相撲部屋寄りの大罪にした方がしっくりときたのだが
こういう内容だから男性俳優に比べ女性俳優は地味な役割
決死隊の中では紅一点の女郎なつを演じた鞘師里保がなんていうか大変失礼だけど顔が薄い
家老の娘・加奈を演じた木竜麻生がずば抜けて美人だと感じたが新発田出身
作品としては極悪人という位置づけであろう阿部サダヲ演じた策略家城代家老溝口内匠
しかし新発田を戦火から救った英雄の1人として民衆から高く評価されたことだろう
人間には良い面もあれば悪い面もある
政事となれば綺麗事ばかり言ってられない
倫理で国民の生活は改善しない
国民民主党玉木代表の件や斉藤兵庫県知事再選の件でますますそれを感じた
野口英世も美談ばかりの自分の伝記を読んで「あれは作り話だ」と不愉快になったエピソードは有名だし
こんなこと書いちゃ失礼だけど女とバカが長生きする理由が改めてわかるような気がする作品である
それぞれ理由は全く違うんだけど
新発田は「しばた」って読むんだよね
子供の頃は今より教養がなかったから「しんはつだ」と誤読していた
「しんはつだ」じゃまるで「ケンちゃんラーメンしんはつだ」
いかりや長介じゃなくても「ダメだこりゃ」と嘆かれそう
配役
妻さだを手篭めにした新発田藩士を殺害し罪人となるが砦を守り抜けば無罪放免と言われ決死隊と共に戦場に駆り出されるも度々逃げ出す駕籠かき人足の政に山田孝之
家老の命により砦を守る決死隊となる剣術道場の道場主で直心影流の使い手の鷲尾兵士郎に仲野太賀
政と共に死罪になる予定だったが砦を守り抜けば無罪放免になる条件で決死隊に参加したイカサマ博徒の赤丹に尾上右近
子を堕ろされた恨みで男の家に放火した罪で死罪になる予定だったが砦を守り抜けば無罪放免となると聞き決死隊に飯炊きとして雇われた新発田の女郎のなつに鞘師里保
捕えられた政を死んだ兄と思い込み逃がそうとした脱獄幇助の罪で捕えられたが兄と慕う政と共に決死隊に参加する新発田の花火師の息子で知恵遅れのノロに佐久本宝
檀家の女を手籠にした罪で死罪になる予定も砦を守り抜けば無罪放免になると聞き決死隊に参加した生臭坊主の引導に千原せいじ
医学を学ぶためロシアに密航しようとした罪で死罪になるはずだったが砦を守れば無罪放免になると聞き決死隊に参加した医師の倅の「おろしや」に岡山天音
一家心中をするが自分だけ死ねず死罪になるはずだったが砦を守り抜けば無罪放免になると聞き決死隊に参加する貧乏な百姓の三途に松浦祐也
侍の女房と姦通した罪で死罪になるはずだったが砦を守り抜けば無罪放免になると聞き決死隊に参加する新発田随一の二枚目に一ノ瀬颯
新発田の村で多くの村人を斬り殺し死罪になるはずだったが砦を守り抜けば無罪放免になると聞き決死隊に参加した相撲取りのような辻斬に小柳亮太
新発田で地主への強盗殺人で死罪になるはずだったが砦を守り抜けば無罪放免になると聞き決死隊に参加する長州出身の剣術家の爺っつぁんに本山力
家老の娘加奈の婚約者で決死隊隊長の入江数馬に野村周平
罪人と共に決死隊の一員となった新発田藩士となるも罪人との対立が深刻化し板挟みとなった入江に粛清される荒井万之助に田中俊介
罪人と共に決死隊の罪人と共に決死隊の一員となるも官軍による大砲の爆撃で瀕死の重傷を追う小暮総七に松尾諭
藩を守るため様々な画策を企てる新発田藩の城代家老の溝口内匠に阿部サダヲ
新発田藩御城使の寺田惣次郎に吉沢悠
新発田藩の御用人の里村官治に佐藤五郎
新発田藩の藩主でまだ10代半ばの溝口直正に柴崎楓雅
政の妻さだを手篭めにし政に刺し殺される新発田藩士の仙石善右エ門に音尾琢真
溝口内匠の妻の溝口みねに西田尚美
入江数馬の許嫁の溝口加奈に木竜麻生
耳が不自由な政の女房のさだに長井恵里
兵士たちにおにぎりを配る新発田の村娘にゆりやんレトリィバァ
柴田藩を官軍に取り込もうとする官軍先鋒総督府参謀の山縣狂介に玉木宏
官軍先鋒総督府軍監で山縣の右腕の岩村精一郎に浅香航大
岩村の側近の杉山荘一郎の佐野和真
官軍先遣隊隊長の世良荘一郎に安藤ヒロキオ
世良の腹心の水本正虎に佐野岳
世良の腹心で正虎の弟の水本正鷹にナダル
新発田藩に官軍との戦いを迫る奥羽越列藩同盟新潟総督米沢藩士の色部長門に松角洋平
新発田藩に官軍との戦いを迫る奥羽越列藩同盟新潟総督参謀米沢藩士の斉藤主計に駿河太郎
ナレーションに塚本誠浩
もったいない
おもしろかった。
けど中身は無かった。
役者も時間も、名作と云われる映画のための全てが揃っているのに役者さんが演じる役に個性がない。
魅力的な役者11人の無駄遣い。
湧き出す油について。仮に揮発性が高かったとしても密閉されてなかったら引火はしても爆発することはない。
星2.5かな?
武士道の素晴らしさ!
何故戦うのか
戊辰戦争(大きな戦)の戦禍を回避するために、局地戦(小さな戦)へ誘...
何のために戦う?
賊軍の戦う理由づけが緩い。なぜみな逃げない? 逃げようとするのが山田孝之一人。さっぱりわからない。
しかもお目付け役の武士がたった三人。みなで寝込みを襲って逃げるとか官軍に投降するとかなぜしない。彼らがまっとうな人たちならそんなことはしないよ、だけど罪人たちだからね。
一応あった動機づけが中盤で崩れたあと、それでも戦おうとするのかさらによくわからん。あんな死にかけの武士の言葉、あてにならないのに。
こういう動機づけの甘い映画はダメ。見ててずっとイライラした。
アクションシーンのゴア描写はよかったけど、ちょっとくどい。ラストで似たような強度の描写が続くとさすがに飽きる。官軍とのバトルをあっさり終わらせてラストの戦いをたっぷりやるとか緩急がないと。
できればそれぞれの罪人の得意技をもっと出して工夫して戦うようにしてほしかった。爆弾の少年だけそういう使い方をしてた。
ただ、繰り返すが最大の問題点は戦う動機づけの弱さ。
「この外道ども!」とか言ったって相手は官軍だからね。奥さんに絡んでないし、相手が違う。
オリジナルの笠原和夫の脚本を読んでみたい。さすがにこういうところはしっかり詰めてくれてたはずだ。
全457件中、101~120件目を表示