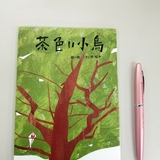「英雄が守りたかったもの」宝島 gladdesignさんの映画レビュー(感想・評価)
英雄が守りたかったもの
強い「怒り」を受け取った。
それは沖縄が感じた怒り。それはアメリカに不当に統治された歴史の怒り。それは、なぜ沖縄だけなのかという怒り。本土は「平和になった」と言うがどこが平和なのか、という怒り。信じてくれと言われ信じたのに裏切られた怒り。
ありとあらゆる怒りがマグマのように煮えたぎり、我慢の限界を迎え暴発してしまうコザ暴動の圧倒的描写は、観るものの脳裏に「もっと怒れ」と訴える。
本作は、1952年のサンフランシスコ講和条約から、1972年の沖縄日本復帰までの20年間を、単なるクロニクルではなく、若者たちの青春群像劇として描くことで、今まで見えなかった見えないようにされていた沖縄の真実の一端を、自分ごととして捉えることのできる映画だ。
沖縄の歴史を知ること
戦後80年が経った日本には、戦争は起きていないとされている。
だが、沖縄では、まだ戦争が終わっていないとも言える。
車で轢かれて死んでも文句が言えない、小学校に飛行機が墜落して子供たちが死んでも何も言えない、そんな状況が20年続いたら、それはもう戦争状態と何が違うのか。
沖縄の歴史を俯瞰してみると、沖縄はずっと脅威に晒され続けてきたことがわかる。
そういう意味では、パレスチナ・ガザと沖縄は似ている、と言えなくもないのではないか。
どちらも軍事的な支配や、土地の強制収用という、外的な介入や住民の抑圧の経験がある。
琉球王国からアメリカへ
沖縄はかつて琉球王国だった。
琉球王国は、江戸時代に日本の薩摩藩(現在の鹿児島県)と中国(清)に両属する状態であったという。
薩摩藩に事実上支配されつつも、中国皇帝からは独立した王国として認められていたのだ。
しかし、明治政府が近代的な中央集権国家を築く中で、このあいまいな状態は問題視され、明治政府は琉球を日本領に組み込むため、琉球処分と呼ばれる一連の政策を進めた。
その後、琉球藩となり、沖縄となり、戦後はアメリカ統治下に置かれた。
本土はGHQが統治していたが、沖縄はアメリカの統治下にあった。
通貨はドル、車は右側通行、本土へ行くにはパスポートを必要とした。
つまり、アメリカなのだ。
沖縄はかつてアメリカだったのだ。
こうした事実を、歴史を、学ぶ機会がこれまで無かった。
私は原作を読んで初めて知ったことがたくさんあった。
なぜ学ぶ機会がなかったのか。
なぜ学ぶ機会を与えられなかったのか。
知られると都合が悪いことなのだろうか。
都合が悪い? 誰にとって?
沖縄が日本である以上、国民は皆、知る必要があるのではないだろうか。
では、ドキュメンタリーでいいのではないか、という声もあるだろう。
しかし、ただ史実をドキュメンタリーで撮ることでは伝わらない何かがある、と思う。
それが、物語の力である。
沖縄が孕む「矛盾」と「葛藤」
どのシーンも印象的ではあるが、強いて言えば、まずひとつはラスト近くにグスクとレイが対峙するシーンは、役者の演技力に圧倒された。
暴力による革命を押し通そうとするレイ。
暴力では何も解決しない、後からツケが回ってくると説くグスク。
どちらも正しく、どちらも何も解決しそうにない。
単純な正義のぶつかり合い、と見ることもできなくはない。
だが、正論同士をぶつけ合っている二人は、どちらもそれを望んでいるわけではなく、「怒り」が溢れてしまうことを必死に押さえ込もうとしているようにも見えたのである。
次に印象に残るのは、史実をベースにした「コザ暴動」のシーン。
1970年12月20日、地元住民を米兵が車で轢き殺してしまったことで、火がつく。
その年の9月に、糸満市で同様に米兵による車の事故があり、住民女性が死亡。
しかも、事故を起こした米兵は無罪となった。
コザの住民は、この二の舞にならないよう、行動を起こしたのだった。
それは「暴動」でもあり「騒動」でもあると言われている。
それはひとえに沖縄人の気質によるものだと思う。
歴史の中でずっと隣国に主権を奪われ続けてきた沖縄人は、それでも誰にでも優しい。
様々な国の人を受け入れ、共に生きようとする。
その姿勢をつけ込まれて、都合のいい島になってしまっていたという見方もできてしまうだろう。
そのように耐え抜いた沖縄の人たちの「怒り」のマグマが暴発したシーンは、映画館にも関わらず声を上げてしまいそうだった。
それほどまでに、圧倒的なスケールと没入感があった。
3時間超えの没入感
上映時間3時間11分は、数字で見ると長いと感じるだろう。
そうした声もSNSでは多数上がっているようだ。
しかし、あの原作をよくぞ3時間に納めたと私はそこにも感動したくらいだ。
当然、原作から端折られたエピソードはいくつかあった。
だがそれも、破綻することなく、シームレスにつながっていたと思う。
ストーリーは原作同様、決して分かりやすいとは言えないが、原作よりは分かりやすくなっている。
それでいい。映画とはそういうものだ。
説明的過ぎる台詞はない方がいい。
この混沌とした猥雑さも含めて、沖縄の搾取された歴史なのだ。
方言が強くて、何と言っているかわからない、という声もあるようだ。
わからなくていい。考えるな、感じろ。
そのために役者が演じているのだ。
アメリカ統治下の20年の歴史的背景は、知っていた方がより面白くなるだろう。
なぜこんなにも理不尽を強いられるのか、と憤るには多少の知識も必要だ。
とにかく、まとめていうと、映画館で見るべきである、ということは言える。
そして、パンフレットもしっかりと作っており、情報量も十分である。
gladdesignさま、初めまして🙂
『宝島』の公開前に、「最近の戦争映画は、“悲しみ”はあっても“怒り”を描かない」という話を聞きました。
沖縄の方言・感情の熱量・映画の長尺は、ウチナンチュとヤマトンチュ=沖縄と私達の間にある、いつまでも超えられない“心のフェンス”を象徴しているのかな、と思いました。
これからもgladdesignさんのレビューの読者でいたいので、フォローさせていただきました🫡