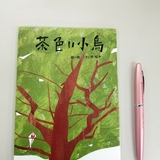「本土とは全く違う「戦後」の風景に脚光を当てる」宝島 ニコさんの映画レビュー(感想・評価)
本土とは全く違う「戦後」の風景に脚光を当てる
沖縄の歴史を知るという視点、映画としての娯楽性という視点、個人的にはそれぞれの尺度での評価にギャップが生じた作品だった。
1972年以前の、アメリカの施政下にあった頃の沖縄の姿をここまでクローズアップした作品には多分初めて触れた。本土復帰という出来事を知識として知ってはいても、何故沖縄の人々がそれを求め、どのようにしてそこに至ったのかをここまで踏み込んで想像したことはなかったと、本作を観た後振り返って思う。
今年を戦後80年とマスコミは呼ぶが、沖縄にとっての戦後は1972年5月15日以降、しかもそれ以降もアメリカ軍は駐留したままだから手放しで喜べない戦後なのかもしれない。
本作ではいくつかの史実(厳密にはそれを元にしたエピソード)が描写される。宮森小学校米軍機墜落事故、糸満轢殺事件、毒ガス漏洩事件。沖縄の人々の怒りの発露とも言えるコザ暴動に至るまで、どんな理不尽が積み上がってきたかがよくわかる。
一方、沖縄の人々の生活の経済面は軍人軍属相手の商売に支えられており、問題の根の深さや解決の難しさを思わせる。
少し調べればそういった出来事や当時の社会構造は知識としては知ることができるが、本当に理解する必要があるのはその時そこにいた人々、直接影響を受けた人々の感情だ。物語はそこに思いを馳せる手助けをしてくれる。そういう意味で有意義な作品だと思う。
それだけに、エンターテインメント性という観点で見ると若干空回り感というか、もやっとしたものが残る感じなのが惜しかった。
要所要所ではいいと思える部分もあった。まず、主要キャストの演技は素晴らしかった。個人的には窪田正孝の危なっかしさ、奥野瑛太の振り切った今際の際、チラ見せなのに存在感あるピエール瀧が特によかった。コザ暴動の映像には迫力があった。
原作の主要キャラにまつわるエピソードや登場人物が結構削られていたが、それは原作付き映画の宿命のようなものだし、悪いことばかりだとも思わない。特に今回の原作小説は、語り部(ユンター)の口述という体裁を取っているせいかもしれないが、話が右往左往して一直線に進まないので、映画の枠に合うよう削ることで話の筋を追いやすくなった気もする。
ただ細部については、説明が足りないのではと思う場面がぽつぽつとあった。原作の情報からいくつか補足する。
グスクが洞窟(ガマ)に入った時錯乱したのは自身が集団自決の生き残りなのでそのトラウマが蘇ったからだということ、よって彼は天涯孤独であるからカリスマのオンちゃんに絆を見出していたということも重要な要素のような気がするが、映画の描写で果たして伝わるのだろうか。
また、グスクがヤマコを諦めたのは、原作ではヤマコがレイに無理矢理犯されたショックで引きこもりグスクを遠ざけたからなのだがここも削られて、グスクとヤマコの関係が軽く感じられた。(家に侵入したレイとヤマコの緊張感に溢れたやり取りはとてもよかったのだが)
終盤、住民たちに「戦果」を配ったのはレイの仕業なのだが、その説明は映画ではなかった気がする(私が見落としたかな? ガスマスクで推測できることではあるが)。
ウタに関するエピソードをごっそり削った煽りで、ラストのオンちゃんの遺骨に辿り着くくだりが少々不自然になってしまった(吐血はしたけど、生きてるなら念のため病院に連れて行ってほしいとつい思った)。
また、この物語においてオンちゃんの行方というのは作品に娯楽性をもたらすミステリ要素にもなり得たと思うのだが、この謎の解明に至る道筋が断片的で中途半端な印象だった。そもそも原作自体にもその傾向があったが、映画化で色々削ったことで余計にそうなった気がする。
そんなわけで、おろそかにできない題材と頭で理解してはいても、エンタメ面での引力不足、人間ドラマの掘り下げ不足を感じた。
とはいえ、この時代の沖縄にスポットライトを当てたことの意義は大きい。私自身、そういえばあまり知らないなあと思って、ついネットでググったり新書を買ったりした。
「戦後」という言葉から浮かぶ風景が本土の人間と沖縄の人々とでは全く違うということ、かの時代を生きた沖縄の人々の感情を、本作から生々しく感じた。その違いを踏まえると、現在の沖縄の抱える問題の見え方もまた変わってくるのではないだろうか。
少し調べて、教公二法阻止闘争、毒ガス移送問題、コザ騒動、復帰措置建議書無視問題、等々、史実を知り、本当にあった事なんだと驚きました。(T . T)
そして、沖縄の英傑、瀬長亀次郎さんのドキュメンタリー映画が2本ある事を知りました。
今こそ、カメジローさん映画を再上映してほしいと思います! m(_ _)m
Freddie3vさんの意見にも同感です
こういう作品って、知られていない役者さんや新人、素人の方で
メインをやってもらった方が
リアル感があって作品世界に入り込める気がしますね〜
f^_^;
今回の役者陣は皆んな、本当に良かったのですが、なぜか共感しにくく感じてしまったのが、残念でした。
(><) m(_ _)m
あと、奥野瑛太ファンとしては、
顔もほぼ判別不可能なほどの熱演、最高でしたね!^ ^
三浦誠己と共に、主演よりも
この脇役みたいって思わせてくれる
昔気質の役者魂が最高です。
ピエール瀧さんも悪い奴をさせたら本当に最高です。 m(_ _)m
暴動シーンは良かったですね!
原作情報!ありがとうございました! m(_ _)m
「映画だけで理解できるだろうか?」と指摘があった箇所は、全て理解出来てませんでした。(T . T)
簡単でいいから、そこは補足してほしかったですね。なんなら、前編、後編の2作に分けても良かったかも。
f^_^;
コメントありがとうございます。オーディションをして新人を抜擢するとか、できないんでしょうか? 映画化すること自体、かなりの冒険なのにキャスティングとなると安全策。小器用に作ったそこそこの成功作より偉大な失敗作が観たい、今日この頃です
原作からの補足でとても理解が深まりました。
さっきuzさんの所にお邪魔したら私の思った疑問に触れておられ、
グスクの奥さんと子供どっから生えてきた?(原文のままw)
そうかヤマコはレイに。。
そういう事なんですね。。
その他の部分もレビュー全てにおいて作品の補完、勉強になるレビューでした。
無知な私でも中々に厳しい時間でしたが体験出来て良かったです。
共感ありがとうございました。
ガマの集団自決まで盛り込むと、映画の色合いが変わってしまいますね。(だからグスクの少しだけ)原作と違うのでしょうが、700ページは畏れ多くて……
全く同じ部分でモヤモヤしていたので、とても共感します。
その上で、ちょっとすり合わせですが、映画の中で、戦果を配ったのはレイだという場面はあったと思います。それに添えた手紙は、原作ではウタが書いたということだったと思いました。
ウタのエピソードが削られた煽りは大きかったですね。
ニコさま🙂
ここまで100件超えのレビューを読んできて、私の語彙力不足で表現できないことを伝えていただけるレビューに出会えました。
>少し調べればそういった出来事や当時の社会構造は知識としては知ることができるが、本当に理解する必要があるのはその時そこにいた人々、直接影響を受けた人々の感情だ。物語はそこに思いを馳せる手助けをしてくれる。そういう意味で有意義な作品だと思う。
>「戦後」という言葉から浮かぶ風景が本土の人間と沖縄の人々とでは全く違うということ、かの時代を生きた沖縄の人々の感情を、本作から生々しく感じた。その違いを踏まえると、現在の沖縄の抱える問題の見え方もまた変わってくるのではないだろうか。
沖縄の「戦後の空白」と、その空白に確かに存在した沖縄の人達の心を、伝えようとしてくれた映画だと思いました。
長尺も熱量も沖縄の方言も、ウチナンチュとヤマトンチュ=沖縄と私達の間にある、今だに超えられない壁や埋まらない溝なのではないか、と考えながら観ていました🤔
映画チケットがいつでも1,500円!
詳細は遷移先をご確認ください。