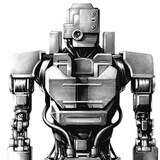シビル・ウォー アメリカ最後の日のレビュー・感想・評価
全867件中、1~20件目を表示
「真のアメリカ映画」
アメリカでは独立を試みるテキサスやカリフォルニアの西部勢力が首都を陥落させようと、内戦が起こっている。そんな状況の中で報道/戦場カメラマンのリーたちは大統領に取材をするためにワシントンに向かおうとする。リーの一向に若手カメラマンのジェシーが加わりたいとお願いする。彼女は戦場でリーに偶然助けられ、またリーを尊敬し憧れているのだ。そんなジェシーをリーは疎ましいと思いつつ、戦闘が繰り広げられるアメリカ横断の旅が始まるのだった。
画の全てが内戦状態だった。本当に報道/戦場カメラマンが現場をドキュメントしているようだったし、報道写真かにみえる構図はどうすれば撮れるのかーつまり登場人物はどう動き、カメラを置けばいいのかーが全く分からなかった。
戦闘シーンも見応えがある。緊張感が張り詰めているし、銃が乱射されている。たくさん爆撃が行われる。もちろんそれは映像イメージの卓越さでもあるが、音声イメージも素晴らしい。遠くで鳴っている銃撃の音など細部のリアリティが素晴らしいから世界観に浸れるのだと思った。
だから映画館で観たほうがいい。内戦状態の描写は娯楽性に富んでいるし、ポップコーンとか食べながらだとさらにいいと思う。きっと本作もそのようにみることを想定しているだろう。
しかしかなりグロテクスな構造だと思う。ポップコーンを食いながら、内戦状態を面白いなーと消費するのは。『虐殺器官』を書いた伊藤計劃なら『プライベート・ライアン』の冒頭15分映画と評していたはずだ。
ただこの構造こそアメリカ的だと思う。巨大な資本で素晴らしくも恐ろしい世界を映画にして、たっぷりな暴力で人をたくさん殺していく。そしてそれを娯楽として提供し、鑑賞者もまた娯楽として消費する。アメリカで内戦が起きたらヤバいけど、まあそんなことないし、というアメリカ/国民=つまり〈私〉の素晴らしさを再確認して劇場を後にする。本当は劇場の外に、内戦が起こる要因なんていくらでもあるのに。
もちろん本作はどちらかと言えば、インテリでリベラルな視点から描かれているとは思う。けれどインテリ層がこんな態度なんだから、アメリカの貧富の格差は拡大して、不法移民の労働力で収益をあげているくせに、国境を封鎖するとか言い出す実業家が大統領になるんですよ。
本作が最も欺瞞に満ちていると思うのは、リーの同僚であるアジア系の二人が射殺される場面である。アジア系の二人とは旅の途中で偶然再会し、車のかけっこ遊びをしていたのだが、一転、アジア系の男とジェシーを乗せた車が西部の人に捕まってしまう。そして死体の山を見てしまったのが原因か、それとも西部の男が単なる遊びでどうかは定かではないが二人を銃で処刑しようとするのだ。慌ててリーたちも救出のために駆け寄る。そして西部の男がある問い質しを行う。「お前は真のアメリカ人か」と。
ここで問題なのはアジア系の男のみを射殺する点であろう。アジア系の男は西部の男に「真のアメリカ人」の構成要件「白人」ではないと判定されて、問答無用で殺される。その構成要件と判定はさておき西部の男の中では理屈が通っている。しかし構成要件は「白人」だけではないだろう。「男性」や「労働者階級」ーというかブルカラーかホワイトカラーか、はたまたインテリかノンインテリか、つまり経済格差を生じさせる階級の要件ーもあるだろう。それなら西部の男に射殺される対象はアジア系の男だけではなく、全員なのである。しかしアジア系の男以外皆が殺されることを免れる。
それは今後の物語における展開の問題ではあるだろう。皆が殺されるべきとも思わない。だが、端役のアジア人なら雑に殺しても構わないという無神経さが透けているし、リーやジェシーが生かされることはいくら物語上で主体性を発揮しても「真のアメリカ人」の庇護の対象という家父長制やジェンダーの問題を隠蔽している。
こういった点から本作が決してアメリカが内戦状態になった原因について、SF的想像力を駆使して提示できているわけでも、オルタナティブな未来を創造しているわけでもない。もちろんSFには多種多様な描き方があり、本作がSF的世界観に埋没して思考実験をするのは構わない。しかしその態度こそ「真のアメリカ人」には決して殺されない語り手の傲慢な立場を明らかにしてしまっている。
そして何より本作の主題である「カメラのドキュメント性」までも毀損している。つまりいくらSF的に未来をドキュメントしようとも、現実さえドキュメントできていないし、カメラが出来事から必然的に遅れること(の反省)をいくら物語っても、何の訴求力も持ち得ないということである。
リーは判断を誤ってジェシーを連れ出し、庇って死んだ。けれどジェシーはもうリーと肩を並べるカメラマンに成長してしまったし、ドキュメントの「遅れ」を取り戻すためにリーの死を顧みることさえしない。そんな悲劇と大統領の死でもって物語は終わる。
残念ながらその切なさと大統領を殺害して撮る記念写真の果てに未来なんてない。待っているのは原因も解決も不明な混沌のみだ。この帰結は本作の判断の誤りと言っていいだろう。
「本作の判断の誤り」と記述できてしまうレビュー。レビューもまた映画から必然的に遅れてしまう行為ではある。だが、その「遅れ」が未来を訂正したり、再記述する可能性に開かれているのなら、悪くはない。
日常の、その先に
ふっと、倒れた兵士ではなく、草花にフォーカスが合わされる。陰惨な殺し合いが繰り広げられていても、草は風に心地よくそよぎ、花は可憐に咲く。戦場カメラマンの彼らは、銃弾を避けるため、よりリアルな画を撮るため、幾度となく身を潜める。そんな低い視線が捉えた、凡庸だが美しい光景が印象的だった。
衝撃的な予告編、大きなスクリーンでの上映で、派手なアクション映画を期待した観客は多かったと思う。(たまたまかもしれないが、私が観た回は中高年男性率が高かった。)同行者も「予想と違った…」とつぶやいていた。それでも、戸惑いながらも惹きつけられる、不思議な力が本作にはある。
舞台は、内戦で壊滅寸前のアメリカ。大統領のインタビューを取るため、主人公たちは戦線をくぐり抜け、ワシントンD.C.に向かう。容赦ない撃ち合い以上に不気味だったのは、「面倒ごとには関わりたくないの」と無関心を決め込む田舎町の人々。「今も世界のどこかで戦争をしています」という言葉を聞き飽きたと感じてしまう自分に重なり、どきりとした。そんな町であっても、銃口はごく当然に向けられる。無関心は、安全とはおそろしく無縁なのだ。
監督の過去作に「わたしを離さないで」の脚本•製作があり、なるほどと思った。東日本の震災後、おずおずと映画館が再開しても、ラインナップは明るく元気が出るものが主流だった。そんな中、ようやくあの作品に出逢えた。ためらいなく脱力し、悲しい、むなしいと感じていいんだと思えた安堵の記憶は、今も鮮やかだ。がむしゃらに進むだけでなく、こぼれ落ちるものを丁寧にすくい取る、そんな作風が、本作にも生きているように感じた。
非日常な戦争や災害の中にいても、笑い、はしゃぐのは当たり前。ただ、そのすぐ先に、何があるかわからない。だからこそ、なのか、それでも、なのか。彼らも私たちも、つかみきれない「今」に、感情を委ねずにはいられない。
予告では触れられていなかったので、主演がキルステン•ダンストだったのには少し驚いた。「スパイダーマン」のMJ、「マリー•アントワネット」のタイトルロールと、スクリーンを華やかに彩ってきた彼女。最後に観たのは、「メランコリア」だったと思う。ちょっと気難しく見える目元が、歳を重ねた熟練の戦場カメラマンという役どころにぴったりだった。ドレスもメイクもいらない!彼女を、これからも様々な映画で観てみたい。今後に期待だ。
こうならないための未来にするには
人によっては戦争映画と思うだろうし、ロードムービーだと思う人もいるだろうし、戦場カメラマンの成長譚と思う人もいるだろう。
それぐらい、見る人がどこに印象を感じたかで変わる映画だった。
「アメリカで19の州が離脱し、テキサスとカルフォルニアの西武勢力vs政府軍の内戦が起こっている」という、本当にそれだけしかわからない状態で物語は進んでいく。
内戦勃発のきっかけや、お互い何を正義として戦っているのかなどは一切わからない。
ただ、それも今のアメリカの状況を思えば致し方ないのかもしれない。
ファンタジーであればある程度理由付けもできるかもしれないけれど、今すでに存在しているアメリカの実際にある州での話となると、影響力の大きな映画は政治批判と受け取られるかもしれないし、プロパガンダと揶揄されるかもしれない。
作り手が見ている人にそう思われずに、今国内がひとつになっていない危機感だけをメッセージとして伝えたいと思ったのなら、こう描くのが一番なんだろう。
ウクライナやシリアのドキュメンタリー映画を見たことがあるので、内戦の描き方がすごくリアルだと感じた。銃社会のアメリカなので、市民が簡単に武装ができ、殺し合いができるという環境はとても恐ろしい。常にヒリヒリとした状況に、心休まる暇がない。
歴史物の戦争映画とは異なり、高層ビルや現代の風景(しかも都会)に、戦車や軍隊が進軍し、銃声が飛び交い、空には軍のヘリや戦闘機が飛び交う光景は恐ろしかった。こんな未来には絶対ならないでほしい。
あと、戦場カメラマンの人たちが、こんなに命懸けで戦場にいて撮影していることにも驚いた。
でも確かに、百聞は一見にしかずというし、聞いたことよりも実際見た光景が真実だと思うので、カメラでその瞬間の真実を記録することは、大切なことなのだと思った。
戦場カメラマンを通して見る、ifの世界線。
ひとつ間違ったら、こんな未来になってしまうかもしれないと、そうならないためにはどうしたら良いかを考えるきっかけになる映画だった。
大義名分から遠く離れた最前線で、戦争は容赦なく奪う
本作のメインビジュアルはいかにもハリウッドが作りそうな戦争映画という印象だが、やはりA24は切り口が少し違う。
開幕、既に内戦はたけなわだ。内戦が起こった理由については、最低限の説明しかない。内戦になるまでの政治的な経緯より、内戦になった結果無法地帯と化した最前線で何が起こったかが、大統領に取材するべくニューヨークからワシントンD.C.に向かう戦場カメラマンたちの目を通して生々しく描き出される。
原題に定冠詞を付け「the Civil War」とすると、南北戦争を意味する言葉になる。アメリカ合衆国で独立後に内戦があったのはこの一度だけだからだという。本作の世界線ではその呼び名も変わっているのだろうか。
アレックス・ガーランド監督は、この物語において抽象的な表現をする意図はなかったと語っている。確かに「3期目の大統領任期のために憲法改正をした」という設定からは、容易にトランプ元大統領が連想される。
米大統領の任期は2期8年までと憲法に定められているにも関わらず、トランプ氏は前回の在任中に3期目を目指すことを公言した。自らが立候補した大統領選挙を11月に控えた今も、「終身大統領になりたい」と発言しているという。
本作で大統領を演じたニック・オファーマンの雰囲気も、どことなくトランプ氏に寄せたもののように見える。
連邦議会占拠事件などを目の当たりにした(トランプ非支持層の)アメリカの人々の目に、この物語は日本の観客には計り知れないほどの不気味なリアリティがあるものに映るのかもしれない。
ただ私には、現在世界で既に起こっている紛争の舞台をアメリカに置き換え、彼の地での残酷で理不尽な犠牲を、自分ごととして考えるべきだという教訓めいたメッセージを、ダブルミーニング的に孕んでいるようにも見えた。
監督の意図からはズレるのかもしれないが、それだけ紛争がもたらす悲劇には普遍性があるということだろう。
いずれの勢力にどんな正当性があろうと、ひとたび武力での対立になれば前線の行き着くところは、大義名分の高潔さからかけ離れた破壊と非人道的殺戮だ。草原に伏せて銃を構えていた2人がジョエルに答えたように、自分が撃たれそうであれば、相手の正体が分からなかろうと撃つしかない。
殺すか殺されるかという状況は簡単に人間性を奪い、動物的なエゴをむきだしにさせる。ジェシー・プレモンスの演じた兵士が象徴的だ。ダンプから無造作に穴に放り込まれた遺体の山を背景に、彼は無抵抗なジョエルの友人を脈絡なく撃ち殺す。記者たちに出身地を問い、香港と答えた記者を殺す。もはや大義はなく、ただの人種差別だ。
洗車機に瀕死の男2人を吊るして、平然と写真を撮らせていた兵士もそうだ。彼らはリーたちが運悪く出会ったサイコパスではなく、紛争の極限状況が生んだ悪魔と言っていい。
(それにしてもプレモンスはああいう不気味な役が本当によく映える。妻のキルステン・ダンストのつてでカメオ出演することになったという。カメオ出演ってだいたいはもっとチョイ役で、というイメージなのだが、彼が演じたあの兵士は一般的なレベルのカメオを超えて作品に不可欠な存在になっている)
リーたちが道中で立ち寄る異様にのどかな街の、内戦に無関心な住民もこれまた象徴的だ。なるべく関わらないようにしている、と呑気に答える服屋の店員とリーたち一行の緊張感のコントラストに胸がちくりと痛んだ。私自身は、明らかに店員の側の人間だと思う。
記者たちの悲惨な道中記は、武力衝突の制御不能な一面を見せるためのサイドストーリーのようなものだが、兵士と違って戦闘行為の当事者ではなく、かといって無関心な傍観者でもない記者の目線で至近距離から描かれる内戦は、独特の緊張感があった。
当初の印象に反して、ジェシーはある意味リー以上に逞しくなっていく。ホワイトハウスの攻防の現場で「feel alive」とつぶやく彼女には、頼もしさとかすかな怖さを感じた。
だが、映画「マリウポリの20日間」が顕著に示したように、誰かが撮らないと私たちはそこで起こったことを真に知る由もない。銃弾に倒れるリーにもレンズを向ける彼女の姿は、あなたも戦争の現実に向き合ってと、こちらに訴えかけているようだった。
余談
パンフレットのバーコードのところに昔ながらの値札シールがあったのでつい爪で剥がそうとしたら、貼ってあるのではなくそういうデザインだった。電気供給が安定しない(バーコードが使えない)作品世界を表しているのだろうか。
理想と良識と常識はどこへいった?
内戦の背景などの説明がわずかであることから、さまざまな解釈を見かけた。もちろん受け手である観客自身が決めればいいとも思うのだが、自分の印象では、決して俯瞰などしておらず、非常に熱のある現代批判である。
というのも、カリフォルニアとテキサスという政治信条的には混ざり合わない二州が組んで大統領政府に立ち向かうという一見現実ではありえなさそうな設定も、「大統領が3期目」、つまり合衆国憲法(正確には修正第22条)に違反、もしくは強引な改憲をしたことが明らかであり、国の根幹を揺るがす非常事態であるとわかる。
民心が分断したというレベルでなはない。危機にさらされているのは、民主主義国家を成立させている大前提、つまり憲法であり、建国の理想であり、国をひとつに結びつける根源的な理念が壊れつつあるからこそ起きた内戦だと考えるのが打倒だろう。
ジャーナリストたちが追いかけているものも、ただのアドレナリンや興奮ではない。劇中のリーは、伝える価値があると信じていた仕事に疑いを持ったと述懐するが、リーの無力感は、信じていた前提が通用しない時代になったから生じたものだ。
現実の分断も、もはや政治的対立と呼べるようなものではない。この映画で描かれているような不条理な自体は、すべて現実の半歩先に想像できるものばかりであり、リーのように絶望する前に、常識と良識を取り戻そうと呼びかけている映画なのだと、自分は解釈しました。
武装権を認めている合衆国憲法
アメリカ合衆国の憲法修正第二条は、「武装する権利」を認めている。銃規制の議論などで度々引き合いに出されるこの条文には実際に何が書かれているかというと、「規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない」とある。この条文の解釈は歴史的に議論があって、民兵を組織する権利を認めたのであって個人が銃を持つことを許したのではないという解釈と、個人が武装する権利だという解釈があって、今は個人の武装する権利と解釈されているのが一般的だ。
ただ、これは最高裁の解釈であって、解釈はひっくり返ることもある。この映画は、テキサスとカリフォルニアが武力で中央政府に挑んだことで内戦が始まったことを背景にしているが、これは民兵が政府に戦いを挑んだという状態に近く、憲法解釈としては前者に近いかもしれない。
修正二条ができたのは、独立戦争の後。当時、イギリスから独立を勝ち取ったアメリカは、人民の自由を奪う時、国は武力を持ってやるに違いない、人民の自由を守るためには武器を手放すべきではないという論調があった。国が人の自由を奪う時は、民兵が立ち上がってこれに抵抗することを保障するための条文が修正第二条だ。
本作で大統領や政府が何をしたのかわからないが、これに対抗して武器を取ることを憲法が保障しているのがアメリカという国なのだ。
つまり、憲法解釈によっては、この映画のような事態が起きることを保障している国と言える。元々、イギリス相手に武力で独立と自由を勝ち取ってできた国なので、武力行使と自由が密接に結びついている国なのだ。
何がアメリカ人民の自由を脅かすのか、この映画はそれを直接描いていない。現実にその火種はたくさんあるので、見る人によってそれこそ「解釈」が変わるだろう。火種がたくさんあるから、このような内戦の勃発は決して絵空事ではないと思わせる。何せ憲法で保障されてるし。
ちなみに、テキサスとカリフォルニアは、全米の州兵で最も強いトップ2と言われている。この2州が手を組んだら、本当に政権転覆できるかもしれない。
状況と瞬間を濃密に焼き付けた一作
冒頭、スピーチ練習をする大統領の言い回しには、かの元大統領を思わせるものがあるし、この映画の挑発的設定がいくらかリアルに感じられるのも、我々の脳裏に議事堂襲撃事件が鮮烈に刻まれているからだろう。だが、結論から言うと本作は特定の人物や党を連想させることなく、あえて事の経緯は曖昧なまま、分断の果てにある状況そのものを描き出す。と同時に、これは世界各地の紛争を我が身に置き換え体感する映画でもあるのだと感じる。そのカオスを分け入るロードムービーの動線を担うのは銃の代わりにカメラを構えたジャーナリストたち。一つの車に同乗する性別、世代の異なる彼らは時おり疑似家族のように思えたりも。はたまた感情豊かな新米と冷静沈着なベテランの対比は一人の写真家の出発地と現在地を集約させているかのようだ。世にある歴史的瞬間を記録した一枚に写真家らの姿はない。その切り取られた世界の外側や背景を自ずと想像させる秀作である。
「お前はどの種類の日本人だ?」への正解を想像できるか
アレックス・ガーランド監督には「エクス・マキナ」や「アナイアレイション 全滅領域」などSFの印象が強かったので、新作が内戦を題材にしたアクションスリラーと聞いて意外に感じたものだ。だが実際に見ると、この「シビル・ウォー アメリカ最後の日」も米国の政治的社会的現状を客観的にふまえつつ、近い未来にもし内戦が勃発したらどんな戦闘や混乱が起こり得るか、それをジャーナリストが取材しようとしたらどんな行動をとるのかといったことを、出来る限りの科学的な正確さでフィクションとして描くという点で、広義のサイエンスフィクションと呼んでもよいのではと考えを改めた。
それにしても、ガーランド監督(脚本も担当)と製作会社A24の機動力には恐れ入る。2020年米大統領選の不正を訴えた当時現職トランプの過激な支持者らが米国議会議事堂を襲撃したのが2021年1月。それが映画の直接的な出発点ではないにせよ、インスピレーションの1つにはなったはず。ガーランドとA24は2022年1月までに契約を交わし、次の大統領選が行われる2024年の4月に米英での公開にこぎつけた。
映画では、連邦政府から19州が離脱し、テキサス・カリフォルニアの西部勢力が大統領側の政府軍と武力衝突を繰り広げていると説明される。赤い州(共和党支持)のテキサスと青い州(民主党支持)のカリフォルニアを組ませた点が脚本のしたたかさ。大統領選の年に公開されたことも考え合わせると、もし反政府勢力が赤い州か青い州のどちらに偏っていたら、本作が政治的プロパガンダだという非難をまず間違いなく浴びていただろう。そうしたリスクを回避するための戦略的な設定だと考えられる。
民間人の遺体を処理する武装集団のリーダー的存在、赤いサングラスの男を演じたジェシー・プレモンスは短い出演時間ながらも強烈な印象を残す。予告編にも使われている、ワシントンDCに向かうジャーナリストたちに向かって「お前はどの種類のアメリカ人だ?」と問う台詞が、米国の分断の根深さを象徴している。
昨年公開の「福田村事件」で描かれた、香川から関東を訪れていた行商の人々が、朝鮮出身者ではないかと村人たちから疑われる場面が思い出される。近い将来、日本でまた大規模な災害と大混乱が生じ、自警団とそれに追従する人々が似たような暴走を起こす可能性がまったくないとは言えない。そんな状況で、「お前はどの種類の日本人だ?」と問われたら、果たして何と答えるのが正解なのか。そんな想像をすることで、この「シビル・ウォー」がよりリアルに迫ってくるだろう。
戦場とカメラマンのジレンマ
本作は「第二次トランプ政権」を予言していた映画らしいので観てみた
基本的に戦場カメラマンのロードムービー要素が強いように思えた
アメリカで内戦が起きているらしいが
全体的な世界状況は映画ではわかりにくいようになっている
ホワイトハウスの大統領を取材するという目的で進んでいく
戦場などで緊迫した雰囲気が続く部分が多い
本作を象徴しているセリフである
「お前はどの種類のアメリカ人だ?」
という質問に対しては思った通りの答えでないと
躊躇なく撃つというシーンではあまりえげつないと感じた。
激しい戦闘のときに「いい写真」が撮影できるというジレンマが
話が進むにつれてよく表れているように思えた。
そして、戦場にいるときは
感覚をマヒさせていないとよい写真はとれないが
それはいいことなのかということも感じた
「What kind of American are you?」「Native」
GODZILLAだったら、ワシントンDCの「モニュメント」を派手に破壊して「クーデター成功」でハッピーエンドなんだろうが。やはり、建国のモニュメントを壊す勇気まではなかった様だ。
日本人にとっては
実に後味の良い❤痛快なお話である。
勿論、起こるわけがない。
こうなったらどうするって?って言うが、絶対にならない。
まァ、怖いのは世界ではこんな事が「日常茶飯事」だろうが。
テキサス軍の裏にはメキシコ軍がいるだろうし、中国軍辺りはカルフォルニア軍に付くだろし、カナダはイギリスやフランスの後押しで、必ずや利権を奪い返しに来る。
そして、ロシア❤インド❤
誰もアメリカ大統領を助けちゃくれない。挙句の果てに「グリーンランド、アラスカに亡命を願い出る」って!そんな寒い所しかないのか?
さて、ここで我が国が安保を理由に
「アメリカ大統領を亡命者として受け入れる」なんてね。そんな続篇作れそうだね❤
二度目のレビューなり。以前は外国で見たので、封切り前規定に違反して消された。
不謹慎だが
僕にとっては、最高に❤真っ白いワンちゃんの尾っぽ。
でも、あくまでも内政干渉のギャクだからね。
「What kind of American are you?」って聞かれたら、なんて言えば良いかなぁ。「ネイティブ!」って答えよう❤
終わりのない争いと記録
熟練の戦場カメラマンと、カメラマン志望のまだあどけなさの残る女性。DCへ向かう車に許可なく乗り込んだ事で、想像さえしていなかったほどの過酷な争いの場に巻き込まれていく。隣人を密告しリンチにかける。出身を聞きアジア人を射殺する。秩序がないということは、気分で人の生死が決められるということ、それはとてつもなく理不尽で恐ろしい。「理由は考えない。考えると撮れなくなる。ただ撮り、伝えるだけ」。考えたことで動けなくなる熟練カメラマン。一方で庇護されていた新人カメラマンは前のめりにカメラを構え始める。その彼女を助けるために弾丸の前に走りでる、それはこれまで死にゆく人を冷静に取り続けてきた、その心が「考えてしまった」からこそ。「死んでいくときも私を撮って」の言葉が現実となってなお、争いは終わりを知らず続いて行く。
新人が殻を破り成長するストーリーは普通なら感動を呼ぶが、この映画ではその成長はただただ虚しい。誰も得しない争いが終わりなく続くだけ。
巻き込まれないよう郊外に暮らす別世界の住人はとても奇異に映るが、実は世界の紛争に距離を置く自分たちのようだった。
恐怖。
戦争の酷さと命の尊さ
クローバーフィールドをアメリカの軍隊で著した作品
ゾンビがいないウォーキングデッド
内戦中のアメリカを舞台に
ホワイトハウスに向かうジャーナリストの話。
単なる戦争ものかと思いましたが
主人公が武器を持たないジャーナリストなので
自分が戦場の中に放り込まれたような
変な臨場感があってよかったです。
逆に激しさや迫力という意味では
少し物足りなかったかなと思います。
圧倒的な武力を持つアメリカの内戦は
世紀末に近いものがありました。
しばらくはアメリカに行きたくない笑
てか戦場カメラマンってほんとにすごい。
戦争映画かジャーナリズム映画かそれ以外の何かか
内戦に陥った米国で敗戦寸前の大統領にインタビューすべく旅するジャーナリストの話。
米国の内戦という舞台とジャーナリストの主人公でセンセーショナルな政治や戦争を期待してしまうと的外れかもしれません。
マクロな戦争に至る理由とか現在の状況とかは情報がかなり排除されていていて、決着は間近でジャーナリズムの付け入るスキがない(故に記者たちは焦り過激な取材に活路を見出す)。
戦争の描写は映像も音楽もコミカルで現実味がないのに、流血描写はなまなましく、シュールな感じはミッドサマーを想起した。
ストーリが進むうちに主人公たちからジャーナリズムという建前が剥がれ落ちていく、人間性も権力も、建前の大義すらなくなる。
中盤で検問で撃ちあう兵士が出てくる、相手が何者か敵かどうかもわからず狙撃銃でにらみ合い殺し合っている、主人公たちは状況を飲み込めず質問を繰り返すが、相手が撃ってくるから撃ち返すのだという蒙昧な返答。
しかし彼らこそがこの映画の本質だと感じた。
主人公たちがなぜ撮るのか、私たちがなぜ生きるのか、疑問が生まれてしまったらどうなるのか。
どんな映画か言葉にするのがすごく難しいけれど、実世界の自分にしみこんでくるような映画だった。
良作です。
ジャーナリズムとは?考えさせられる映画
米国は
全867件中、1~20件目を表示